9 / 10
■九 篤郎
しおりを挟む
カセットテープから流れる音楽を聞いた時、俺は遂に錬金術を閃いた。これで金を稼げるかもしれない。そう考えると、体が勝手に動いた。真相を確かめるため、夏鈴の母親の元に急いだ。店舗に実花の姿はなかった。靴を脱いで母屋にあがる。リビングでスマホを見つめている実花の姿を見つけると、余計な挨拶なんて抜きにして「あんた誰なんだ?」とやった。勝手についてきた夏鈴が「私のママだよ、知ってるだろ」と背中に蹴りを入れた。その後ろには夢乃の姿もあった。
「は? え? いきなりどうしたんですか?」
突然リビングに乗り込んできた三人の姿に、実花は驚いているようだった。腰を曲げ、尻を座面から中途半端に浮かせたどっちつかずの体勢を見せた。
「ママ、こいつに脅されてるんだよね?」
夏鈴が、どうかそうであって欲しいという期待を込めて言った。俺のことを押しのけて実花の隣に立つ。夢乃も同じように続く。無理矢理三対一の構図を作られた形だ。
「私が篤郎さんに脅されてる?」
「いいからママ。怖かったよね? でももう大丈夫、一緒に警察に行こ?」と夏鈴が、しっかりと棒立ちをしている実花の体をわざとらしく支えるような姿勢を取った。そして「それとも」と不安気に切り出す。
「それとも、マジでこいつと不倫関係にあるの?」
「不倫? 私が篤郎さんと? 違う違う。そんなことあるわけないじゃない」
そうだ。そんなことあるわけがない。大体俺は実花のことなんてあまり知らない。俺が知ってるのは社長の妻ってことと、馬鹿な娘を生んだってことだけだ。どうやら昔、写真を撮ったことがあるらしいがどんな関係だったかは覚えていない。覚えていないってことは大した関係じゃなかったってことだろう。それにどうやら皆、俺が実花を脅してバイトに受かったって勘違いしているようだけど、それってマジで失礼しちゃうんですけど。この結果は面接を担当した実花に、鋭い観察眼があっただけだし、それに俺には枯れた魅力もあった。惚れられただけで不倫裁判にかけられちゃ堪らねえよ。
「だからもう誤魔化さなくていいんだって。証拠ならあるんだから」
夏鈴が俺にも見せた写真とカセットテープをテーブルの上に並べる。実花はそれらを目にした途端「ああ」と言って頭を抱えた。
「それはちょっと昔を懐かしんでただけだから。大体勝手に部屋に入るなんて最低。いくら家族でも守るべき一線があるでしょ。私が夏鈴の部屋に入ったら烈火の如く怒りだすくせに自分は平気ってわけ?」
「ちょっとちょっと、昔を懐かしむってどういうこと? やっぱり二人は付き合ってたんでしょ? ねえ? このバンドのファン同士で意気投合なんかして」
「さっきからなにを言ってるのよあんた。いい加減にして。また興奮して自分でもわけ分からなくなってるじゃない」
「あたしの客観性に疑問を持ってるってわけね。そう、分かった。夢乃、言ってやりな」
夏鈴が夢乃の手のひらを無理矢理挙げさせて、そこにタッチをした。夢乃は明らかに準備不足だった。突然選手交代を告げられて、集中しきれていない。
「え、ああ、でも」とやると、夏鈴から背中にチョップの喝が入る。「そうですね。まず、私もおばさんの宝物を漁ってしまいました、すみません。写真とカセットテープをお借りしたのも私です。ちょっと興味があって。というか検証に必要で。それで思ったんです。やっぱりおばさんと彼になんの関係もないっていうのは無理があるなって。夏鈴の言ってることが全部正しいとは思えないですけど、ただの雇用主とアルバイトっていう関係は筋が通らないかと。あくまで客観的な意見です、はいすみません」
夢乃は言ってか数歩後退りをした。踵が部屋の壁に触れてからようやく動きを止める。
「ほらみろ」と夏鈴が勝ち誇ったように胸を張った。「ママとこいつは怒張ってバンドのファンだったんだ」
実花の言う通り、夏鈴は混乱していた。俺と実花がどんな関係にあれば納得するのか自分でも分かっていないんだ。ただ意見を押し通したいだけの子どもみたいになってしまっている。
「だから違うって。いや、私が怒張のファンだったっていうのは認めるよ。そこは否定しない。でもね、篤郎さんはバンドのファンなんかじゃない。だって怒張のボーカルだったんだもん」
三人の視線が俺に集まる。期待をされているみたいで緊張した。
「お恥ずかしい話ですが」
「え? 違いますよ。それは嘘ですね」
生唾を飲み込んでから思い切って真実を話したのに、夢乃がすぐに否定してきた。スマホをなにやらタッチして、画像を表示させたものを向けてくる。そこには怒張のメンバー全員が写った画像があった。
「おめえ誰にも相手にされないからって、小学生みたいな嘘つくなよ。こっちが悲しくなるだろ。あたし達は事前に調べてるんだよ。怒張のメンバーにお前はいない」
「そりゃそうだ。その画像に写ってるボーカルは二代目の奴だからな。さっきお前ら俺に聞いたよな。テープと音源じゃ全然印象が違うって。テープの方が俺で、デビューした時にいたボーカルがその糞ったれだよ。だから印象が違うんだよ。全く別物のバンドになっちまった」
夏鈴と夢乃は俺の発言の真偽を確かめるように実花のことを見た。実花は二人に頷く。
「嘘だ」夏鈴が助けを求めるように叫んだ。「このヘタレがテープの方のボーカルなの? 信じられない。だって格好良かったじゃんあのボーカル。それがこいつ? ちょっと待ってよ。嫌だ、違う違う」
「いやあ、別に誇れるようなことでもないから嘘でもいいんだけど」
「でも本当じゃないですか」実花が俺を慰めるようにして言う。「あの頃の篤郎さん、輝いてた。それをなかったことみたいにしないでくださいよ」
輝いてた? 俺が? そんな実感まるでない。確かに俺は夏鈴や夢乃が思うようなクズではない。だけど、憧れられるような人間では決してないはずだ。あの頃だって、今と変わらず世間と切り離された自分だけの人生を勝手に生きていただけだ。
高校の頃、友人達とバンドを組んだ。俺は別に音楽なんて興味がなかった。楽器だって弾けないしな。だけどそいつらとつるんでいるのは楽しかった。皆がバンドを始めるって勝手に盛り上がった時、頭の中で瞬時にそろばんを叩いた。俺も加わらなきゃ次第に疎遠になるだろうって。ここは自分に嘘をついてでも参加するべきだ。だから一緒に盛り上がった。みんなして音楽の字を解体して、音を楽しむことだなんてふざけたこと言い出す現象には辟易したけど、それすら顔に出さなかった。
最終的にバンドに参加したのは俺を入れて四人だった。皆ある程度楽器を演奏出来るようだった。その時始めて知ったよ、こいつら音楽好きだったんだなって。家とかスタジオとかで密かに練習していたらしい。唯一人楽器が弾けない俺は、ボーカルに立候補した。なにせ、今から楽器の練習なんてしたくなかったもんで。俺はただ、仲間たちと一緒に遊んでいたかっただけだから。きっと楽器の練習っていう制約が加わると、即座に投げ出してグループからも爪弾きにされるって分かっていたんだ。お前もギターくらいは練習した方がいんじゃねえか? って言ってた奴もいたけど、俺は譲らなかった。マイクスタンドを握って離さなかったってわけだ。他にボーカル希望の奴もいなかった。皆好みの楽器が弾けて、バンドという形態を取れればそれで良かったみたいだ。
俺の歌は大したことなかった。というかまあ、下手な部類だ。バンドでボーカルをしてたなんて言うと、じゃあカラオケでなんか歌ってって話に必ずなるだろ。別に歌ってやっても構わねえけど、お前らいつも微妙な空気になるじゃねえかってくらいに下手だった。俺には居場所が必要だった。楽器も弾けない、歌も下手なボーカルのままじゃバンドから追い出されるのは時間の問題だった。
ってことで、過激なパフォーマンスに走った。したり顔の音楽かぶれに「こいつのボーカルは歌じゃねえ、心の叫びだ」なんて寝ぼけたことを言わせれば勝ちだって思った。キャラクターも演じた。なにを考えているのか分からない凶暴で社会性のない男。ステージで血まみれになることも多かった。カミソリで肌を切り裂いたりして。地元のライブハウスに出始めの頃は、加減が分からずに苦労した。行き過ぎてしまうのは別に良かったけど、刃物まで出しておいて慎重に肌を切る男なんて誰も見たくはない。外科医が読むような専門書を取り寄せて勉強したもんだよ。最終的にはブラックジャックくらいのメスさばきを習得した。命に別状なく、派手に出血する血管を見つけたりしてな。俺も仲間外れになりたくなくて必死だったんだよ。
パフォーマンスは受けた。いつも貧血状態だったけど、客に盛り上がってもらえて安心した。でもバンド自体にファンがついたのは、結成して少し経ってから作り始めたオリジナルの楽曲が良かったからだと思う。俺だって身を削っているわけだし、自分の手柄にしたい気持ちはあったけど、結局のところ皆音楽を聞きにライブに来てるんだ。俺がピエロ役を買って出たからと言って、心を掴めるわけじゃない。ただ、メンバーにはそう思わせておきたかった。クビになりたくなかったからな。
俺はバンドをやってるのに音楽的なことになにも貢献できていなかった。自信なんて全然なかった。もちろんステージではそんな素振りは見せなかった。俺は怒張のボーカル篤郎だっていうアナーキーな姿勢を保ち続けた。俺にとってアナーキーっていうのは血だった。バンド内での劣等感を解消するために、多目の血飛沫を上げ続けた。やがて俺は、プレッシャーに耐えられなくなった。命の危険も感じていたし。その頃にはもう、二十代も半ばを過ぎていた。引き返すなら今しかないって思った。それに、バンドを組んで数年が経ち、俺も変わった。人間関係自体に変化もあった。もう、絶対にこのグループにいないといけないっていう幼い感情もなかった。で、バンドを抜けた。
その後で奴らは代わりのボーカルを迎え、念願だったデビューを果たした。図らずもメンバーの音楽的センスの良さが証明された形だ。やっぱり血でヌルヌルしたジョン・ゲイシーみたいなピエロなんてバンドには必要なかったってことだ。
俺にとってバンドとはそれくらいのものだった。間違いなく青春の一ページにはなっていたが、決して輝いていた過去ではない。それだけのこと。そう自分に言い聞かせてその後の人生を生きてきたから余計にそう思うのかもしれないけど。
だけどさ、どういうわけか俺のボーカルバージョンのカセットテープが出回っていることを知った。記憶にある限り、俺達は宣伝のためのテープなんて配布したことがなかった。封印されたはずの過去がしっかりと流通している証拠だ。さっきイヤホンから流れてきた、若かりし頃の自分の声を聞いて肝を冷やしたぜ。反対に、こりゃ一体どういうことだって体は熱くなった。このカッセットテープをキッズに売って稼いだ奴がいるって分かったからだ。販売元を探り当てることができれば、もしかしたら俺の権利を主張できるかもしれない。金の匂いがしたわけだ。大金にはならないだろう。だけど、拝島水道が潰れた場合の備えくらいにはなるかもしれない。大体よ、過去を暴かれて一番最初に思うことが権利の主張って奴に、輝いた過去なんてあるわけないだろうが。
「私は怒張のファンだった。それも大ファン。あの頃はよくライブハウスとか行ってて、色んなバンドを見たけど怒張くらい格好良いバンドは他になかった。私の青春の思い出。ちょうどその写真の頃。なによ? 私だってそういう過去はあるの。今はただのおばさんに見えるかもしれないけど、あんた達と同じように、私にだって若い頃はあったんだから」
実花が言うと、夏鈴は目を丸くした。誰にだって若い頃や青春時代はあるが、特に自分の親のこととなると、上手く想像できない気持ちは分かる。俺の母ちゃんだって、婆ちゃんの腹から出てきた瞬間にもうあのヨボヨボの姿だったって言われた方が納得出来る。それくらい親の若い頃っていうのは謎に包まれたものなんだ。
夏鈴は目を大きく見開いたまま「なんかキモい」と、辛辣な感想を述べた。
「あ、そんなこと言っていいの? 私、あの頃本当にめちゃくちゃだったんだから。人刺しミッキーとか呼ばれてたんだよ」
昔のあだ名がどうだったかは分からないが、おそらく実花がむちゃくちゃだったのは本当だろう。というのも、俺がいた頃の怒張にはめちゃくちゃなファンしかいなかったから。今の、普通のおばさんにしか見えない実花からは想像しにくいが、写真で見た若かりし頃の彼女みたいな女は、バンドの周りにはたくさんいた。実花自身があの場にいたと主張するなら、きっと本当にいたんだろう。
「ミッキー? なにそれダサ。信じらんない。でもそこはいいや。じゃあ、ママの方から交際を申し込んだってことね。この信じられないような話を全部信用するなら、だけど」
「だから違うって。当時の篤郎さんは孤高の存在だもん。ただの憧れ。そうやってライブ終わりに写真を撮ってもらうのが精一杯」
実花はテーブルに置いてある写真を指さした。そうか。俺、孤高の存在だったか。今の自分から完全に切り離された他人事のような過去だったけど、なんだかその言葉の響きは気に入った。流石にもっと言ってくれってねだるような気持ちはなかったけれど、言ってくれてもいいっていう許容の気持ちはあった。
「こいつと写真? いつでも何枚でも撮れるでしょ。ほら、何枚でも」
夏鈴は自分のスマホを取り出すと、俺に向けて雑にシャッターを切った。画面を覗いてもいなかった。ノールックで指だけを動かした盗撮スタイルだった。カシャ、カシャ、という無機質な音がしばらくリビングに響いた。
「分かってもらえないよね」
実花は「うーん」と考えた末に絞り出した。恨めしそうな目でちらりと俺の顔色を確認したのを見逃さなかった。今の俺がこんなだから信じてもらえないってことだと判断した。勝手に持ち上げられて、勝手に落胆されることほど悲しいことはない。
「分からないよ、全然分かんない」
夏鈴が大げさに手を振りながらアピールするものだから、右手が夢乃の頬を掠める。
「あ、ごめん」「いいよ、大丈夫」と、二人でクリトリスを舐め合っていた。
「でも彼は私に母親になる決心をさせてくれた人だから。やっぱり特別な存在なの」
母親になる? 俺は実花とやったのか? 玉袋の中にしまったデータベースにリクエストするが、四〇四エラーが返ってくるばかりだった。俺は控え目な方だった。あの頃同じくらい名が売れていたバンドマンの中では、だけど。皆派手に女遊びをしていたし、中にはモデルやアイドルと付き合っているような羨ましい奴もいた。でも俺は違う。所謂良い女には、はっきりと気後れしたからな。かと言って恥じらいもなくファンに手を出すようなこともなかった。そういう奴は仲間内でも馬鹿にされるような時代だったし。ってことで、俺がいったのはファンはファンでも口の固そうなファンばかりだった。
怒張目当てにライブハウスに来ているような奴らが相手なんだ。口の固そうなファンを見つけるのなんて、俺の中にアダムとイブのDNAを見つけるようなものだった。必然的に派手な遊びをしているような奴よりは控え目な行動を取らざるを得なくなった。だけど、年を重ねるだけ重ねた今となっては、ハーレムに住んでいるような暮らしだったのは間違いがない。実花がその口の固そうなファンの一人だったとしたら。考えると気不味かった。
「こいつがあたしのパパってこと? だとしたら私もう死ぬから」
「違う違う違う。言い方が悪かったわね。あなたの父親はパパ。篤郎さんとは関係がない。パパとはちゃんと大学時代に出会って恋愛結婚してるから」
「そこにどうやって篤郎の存在が割り込んでくるのさ。母親になる決意ってなにさ」
夏鈴はもう涙目だった。十代の女が見せる最高の拒絶だった。
「さっきも言ったけど、その頃の私はめちゃくちゃな生活をしてたの。パパは今と同じで真面目な人だったよ。でもそれでなんの問題もなかった。私はそんなパパのことを愛していたし、パパはほら、どんな私でも好きでいてくれるから。だからずっとそんなめちゃくちゃな生活が続くんだろうなって思ってた」
「そこ、そこが信じられないんだよね。だって今のママって普通のおばちゃんじゃん。怒張みたいに激しいバンドが好きだったなんて信じられないんだよね」
「母親になると人は変わるから」
実花は一言で娘を説き伏せた。夏鈴の疑問は行き場を失くしたようにその場を漂ってリビングの床に落ちた。そんなことで納得してしまう女同士のマウンティングが俺には信じられなかった。男からすれば、親になったからなんだっていうんだよってことだから。
「それでいつ篤郎が登場するのよ」
「大学卒業直前に妊娠していることが分かったの。同時にパパが大手の就職を蹴って、実家の水道屋を継ぐことも決まって。それでパニックった。だって、私は就職も決まってなかったから。ふらふらしてたから当然なんだけど。夢もなかったしね。しばらくフラフラして、遊ぶお金はバイトで稼げばいいやって考えてた。パパがキャリアを築いていってくれれば、いつかはそこに合流するんだからって甘い考えがあったんだと思う。でもそういう人生設計が一気に崩れたから。もちろん子どもが出来たのは嬉しかったけど、私自身が子ども過ぎたんだと思う。なんか色々と落ち込んじゃって。そんな時、篤郎さんと初めて話す機会があった。話を聞いてくれて、まだ当たり前の人生を生きることに抵抗があった馬鹿な私に言ってくれた。普通に生きられるチャンスがあるなら絶対にそうした方が良いって。死ぬ気で掴みにいけって。怒張の篤郎がそんなこと言うんだよ? 普通に生きてる奴の方が立派に決まってるだろって。大人になれば理解できる当たり前のことなんだけど、当時の私には妙にぐっときてね」
そんなこと言ったか? 全然記憶になかった。そもそも実花のことを覚えていないのだから、発言を記憶しているわけがなかった。
「それって、いつのことだ?」
「篤郎さんがバンドを抜ける前、ラストライブの数日後。病院の帰りに偶然会って」
閃くものがあった。最初はそれがなにかは分からなかった。だが、頭の中で光った物が周囲を照らし、記憶を呼び寄せている実感があった。ラストライブ。血。救急車。入院。その後で、確かに俺は誰かと話した。あれが誰で、何を話したかは覚えていない。前後関係を思い出す必要があった。思い出したくなくて、蓋をしたような過去も全部。その蓋はもうボロボロだった。気付くと集中してしまいそうになる神経に、ずっと晒されてきたんだから当然だ。思い出したくなかったんだ。あの頃のことは全部。だけど今、遂に蓋が外れてしまった。ステージ上で派手に出血した時みたいに、黒い液体が俺の脳を一気に侵食する。
ライブハウスではそれなりに有名になった。次なる目標はCDデビューだってことになった。オリジナル曲も溜まってきていたし、ライブでは概ね好評だった。俺達ならやれるんじゃねえのって機運がバンド内で高まっていた。レコード会社にコネなんてなかった。対バンなんかで、別のバンドが演っている時は客席にスーツを着たレコード会社関係者みたいな奴を見かけることならあったが、俺達の出番になると消えていた。一体あれはなんだったんだろうな。俺達にしか見えない妖怪かなんかだったのかも。
とにかく、毎回どこかを出血させるような、過激なパフォーマンスに従事するバンドは商売にならないって思ったんだろう。その頃の俺といったら、積年のパフォーマンスが祟り、腕には立派なためらい傷みたいなのが出来てて、まるでメンヘラみたいだったから扱いにくいって判断されたのかもしれない。
誰も協力してくれないなら、自分たちでやるしかないなって話になった。どこにも属さずインディーのまま食えてる先輩バンドを知っていたし、どっちかって言うとそっち側の方が格好良いよなって話になった。メジャーで金に魂を売ったような奴らのことも見てきたし。ま、俺達の場合相手にされなかっただけだけど。そうやって傷を舐め合って、最後には唾を吐きつけるみたいな思考に自ら飛び込まないとやっていられなかった。
レコーディングをするにしても、音源を流通させるにしてもまずは金が必要だった。バンド活動をしばらく休止させて、皆で金を稼ごうって話もあったけど、それは俺が反対した。今だ、って思った。バンドに貢献するなら今しかないって。必要な額の大半を、俺がバイトして貯めてやるって啖呵を切った。その間皆は曲作りに専念してくれって。
俺はコンプレックスの塊だった。音楽的な部分では、俺に価値はないって思ってた。だから金を稼ぐことで仲間に入れてもらおうとしたんだ。これじゃ、親の財布から一万円盗んで、駄菓子屋で大盤振る舞いをするガキと一緒だよな。でもなりふり構っていられなかった。もしかしたら、バンドで飯が食えるかもしれないって時だ。今更ふるいにかけられるわけにはいかなかった。
まだ体力があったし、モチベーションも高かったから昼は引っ越しバイト、夜は交通整理っていう、まるで自分に合っていない仕事を続けた。給料は良かったが、息を止めて生活するような苦しさを味わった。その代償に、ちょっと精神を病んだが、若いって素晴らしい。体の方は次第に慣れていった。ある程度金が溜まった。目標額にはまだ少し足りなかった。それでも苦しんだ分だけ一方で積み上がっていくものもあるのは充実感があった。俺にとって通帳に溜まっていく金額は、努力の結晶でもあったわけだ。
それで、突然惜しくなった。昼と夜にかく汗の量は、本望を洗い流すのに十分だった。別に欲しいものがあったわけではない。その頃から無駄遣いの悪癖もなかった。それでも自分だけの努力をバンド全体に横取りされるのは納得がいかなくなった。
ハイエナ共が俺の金を期待してそろそろレコーディングでも、という雰囲気になった頃だった。田舎のばあちゃんが病気になって入院費が必要になったって、正常な神経をしている者なら決して文句を言えない嘘をひねり出した。皆は快く騙されてくれた。基本的には良い奴らなんだ。俺はバンドのために金を出さなかった。これって着服って言うのかな。分からないけど、確かに強い罪悪感はあった。だけどそれよりも、貯金が一気になくなる方が惜しかった。
皆は皆で、勝手にレコーディングのスケジュールを切っていた。期待していた金額が足りないどころかゼロになったことで、相当焦ったみたいだ。ましてや、俺が死ぬ気で働いている間に、奴らも必死で曲をこさえてた。アーティストの創作意欲は後先を忘れさせる。俺が知らない内に、メンバーの一人が決して借りを作ってはいけない闇金で金を工面した。今すぐレコーディングを始めるにはそうするしかなかったみたいだ。
それで音源の制作を開始した。不思議だったのは、闇金の奴がレコーディングにまで同行して、口を出してきたことだ。聞けば金を借りる時にバンド活動をしていることを話し、お涙頂戴のストーリーで説き伏せたとのことだった。レコーディングに顔を出していたのは千葉って奴だった。闇金の責任者で、昔自身もバンドを組んでいたそうだ。口では若者を支援したいんだって言ってたけど、自分の叶わなかった夢でもって、更に金儲けしたかっただけだろうな。最低な奴だ。シンプルにヤクザだって言えば、こっちだってそれで納得するんだから。
金を貸せば自分もレコーディングごっこが出来るし、バンドが成功すればマルコム・マクラーレンみたいにバンドを支配出来る。なにより、あまりリスクがない。音楽で金を返せなくても、バンドをしているような奴らは元気な若者なんだ。闇金と関連のあるヤバい仕事で稼がせたり、健康な臓器を売りさばいたりすれば貸した金の回収は十分可能だ。多分、金が必要になったバンドマンが頼る有名な闇金だったんじゃないかな。被害者は俺等だけじゃなかったはずだ。
レコーディングした曲を聞いて、千葉は「こりゃいいぞ」って顔をしてた。俺達は「お前に何が分かる」って顔をしたはずだ。しばらくしてスタジオに顔を出した千葉があり得ない提案をした。「バンドでボーカルをやってる俺の息子を加入させろ」ってゴリ押ししてきたんだ。おいおい、ツインボーカルなんて勘弁してくれよって感じだった。あんたの息子に血は流せるのか? って聞きたくなったよ。だけど違った。俺を追放して新たに息子を迎え入れる提案だった。いや、あれは脅しみたいなものだったな。出資したからといって、そんな我儘が通るはずがない。当然メンバーは拒否した。このバンドのボーカルは篤郎だって言ってくれた。俺だって譲るつもりはなかった。千葉に反論するメンバーの後ろで、「そうだそうだ」って援護射撃を送った。
だけど金の力ってすごいよな。バンドのために貯めた金を着服した時にその力の偉大さは痛感しているつもりだった。それでも、あれは自分の弱さがなせる業だと思っていた。慣れない肉体労働で精神がやられ、弱っていた所に札束で頬をビンタされたような状況だったから心が折れたんだと納得していた。まさか他の奴らが金でなびくとは思っていなかった。中々首を縦に振らない怒張メンバーに痺れを切らした千葉は意固地になった。頭に血がのぼり一瞬損得勘定を忘れてしまったようだ。「息子を新ボーカルに抜擢するなら借金を帳消しにする」とまで言ってきた。「完成したCDのプレス代や流通費を負担してもいい」とか「お前らは俺の家族になるんだからな」って。
家族って言葉にはメンバー全員が恐れ慄いた。だってそれって広義では盃を交わすってことだろ? 逆効果だった。でも、今後しばらく金の心配はしなくてもよくなるっていうのは、現状では金を貯め込んでいる俺以外のメンバーの心を鷲掴みにした。皆が皮算用をし始めたことに気付いた。そもそもバンドなんてやっている奴らに労働意欲なんてあるわけがない。借りてしまった金は返さなくてはいけないけど、音源が上手いこと売れなければ労働で埋め合わせなければならないんだ。レコーディング中も皆少しずつではあるが、その重圧に怯えていた。だけど今、まさにくだらない金勘定から開放される提案を受けた。「少し考えさせてください」ってメンバーの一人が自身の中に眠る社会性を絞り出すようにして言ったのを聞いた。
実のある作戦会議の結果、取り敢えず新ボーカルを迎え入れようという話になった。金は返さなきゃならないし、俺バージョンのレコーディングは終わってた。千葉とその息子のお遊びに一旦付き合って、貸し借りなしの状態になったら追い出せばいいって話だった。
俺は滅茶苦茶不安だったね。相手はヤクザ者とその息子なんだ。そんな相手に付け焼き刃の心理戦が通用するとは思えなかった。それに、一時的でもバンドから追い出されるのは良い気がしなかった。千葉の息子は陸っていう少し年下の馬鹿だった。とんでもなく馬鹿だったが、ルックスだけは良かった。千葉が悪知恵を働かして、ルックスだけはいい水商売の女なんかに種付けした結果、この世に生を受けたのが容易に想像出来る外見をしていた。陸のボーカルは最悪だった。なよなよめそめそして、尻から声を出すような発声しか出来ないようなボーカルだった。それに馬鹿だから歌詞も覚えられない。バンドのグルーブに合わせることも出来ない。
俺は陸のボーカル指導としてレコーディングに立ち会った。どうせ追い出すにしても、千葉が目を光らせていたからな。一生懸命にやってるフリが必要だった。情けなかったよ。形式上ではあるが、首を切られたバンドのお手伝いをしている状況なんだから。それでも息を潜めて陸が辞めるのを待つより、少しでもバンドと接点を持っていたかった。存在感をアピールしなければ約束ごと忘れられてしまうんじゃないかって不安だったし。
陸バージョンのレコーディングが終わった頃、久しぶりにライブを行うことになった。ボーカルは俺。千葉の目が光っている時期だった。本来の怒張でライブを行うことに違和感を感じた。そんなことして大丈夫なのか? って感じだった。でも皆は「久しぶりに自由に演りたい。千葉も説得したから」と言ってくれた。ふーん、それならいっか。そんな風に軽く考えていた。
当日、ライブハウスに一番乗りして出番を待っていた。次第に緊張した様子のメンバーが楽屋に集まってくる。そして切り出された。 「悪いけど俺達は陸と一緒にやっていくことになった。お前は怒張から抜けてくれ」
これは俺達の悪巧みを見抜いていた千葉が先回りして通せんぼした結果だって散々言い訳していた気がする。千葉が悪い。俺達は全員悪くない。醜い言い訳が続いた。俺バージョンのマスターテープを退職金代わりに渡してきた。これをどう使おうが、お前の自由だからって。こんなもんもらっても、知恵もコネもない俺にはどうしようもなかった。要は一生使わないことになったから、代わりに処分しておいてくれってことだろ?
俺としては怒張完全体で復活前の、予習復習ライブのはずだったんだけど、いきなりラストライブになったもんだから自分を見失った。足元が崩れる感じがして、立っているのもやっとという状態だった。悔しさと寂しさと混乱に支配された。それでも最後に大きな花火を打ち上げることが出来たなら、皆の考えも変わるかもしれないっていう淡い期待が余計に心をかき乱した。
で、ライブの途中で粗相をした。感情だけが先走って、やったこともない特大パフォーマンスの切腹ショーに従事してしまった。いつもみたいな華麗なメスさばきとはいかず、用意して臨んだ果物ナイフをちょいと深く腹に突き刺し過ぎた。こりゃいかん、と思った時には遅かった。想定外の出血に目が眩んだ。客も引いた。メンバーも演奏を止めた。俺は死を覚悟した。ステージの上で死ねるなら本望だなんて思わなかった。実家の母ちゃんのことが頭に浮かんだ。そしてもし死ぬなら、メンバーが俺を追い詰めたことを一生悔いて、耐えられなくなるくらいの罪悪感を与えようと企んだ。そう企んだのが最後の記憶だ。俺は出血多量で気絶して、救急車で運ばれた。らしい。当然記憶にはなかったけど。
数日入院した。傷もそうだが、精神面を疑われちまってね。精神科医には正直にライブ中のパフォーマンスが行き過ぎたって話した。「三島由紀夫とか好きですか?」って真剣な顔で言われたのは笑ったよ。読んだことねえっつうの。入院中は暇だった。有り余る時間が憂鬱の波となって何度も俺を襲った。突然宙ぶらりんになってしまった。人生の目標も楽しみも、全部奪われたんだ。未来に希望がなくなった。何度も、なんでこんなことになっちまったのかな? って考えた。答えは分かっていた。俺がバンドに金を出さなかったあの瞬間、マルチバースが別の方向へ分岐し始めたんだ。そりゃ後悔はしてる。だけどもう一度人生をやり直しても、俺は絶対に同じことをするだろう。ケチってことなんだろうな。人生をやり直すチャンスがあっても、金を払ってそのチケットを買えないくらいの超ドケチ。ちっぽけな自分には相応しい称号だった。
それで。そうだ。退院した日に病院を出た所で声をかけられた。女だった。確か、妊娠して同じ総合病院の産婦人科に通ってるとか言っていた。でもダメだ。自分のことじゃないし、あの時の俺は自分の抜け殻みたいな感じだったからあまり覚えていない。
「最後のライブは最前列で見てた。まさか篤郎ボーカルの最後のライブにはなるとは思わなかったけど。突然篤郎さんがハラキリをして、虹みたいに血飛沫が飛んだ。客は騒然となった。いつものパフォーマンスとは様子が違ったから。演奏は止まって、救急車が呼ばれた。その後突然ボーカルが変わったから、あの頃のファンは全員、篤郎さんは死んだって噂してた。でも私だけは知っていた。ライブの後、突然体調が悪くなって病院に向かったの。そこで妊娠していることが分かった。ちょうどそのタイミングだったの。パニックになって病院を後にすると、そこに篤郎さんを見つけた。普段なら声を掛けたりしなかった。過去にライブハウスの近くで篤郎さんを見かけたこともあったし。その時はコンビニで成人雑誌を読んでいたからそっとしておいた。それくらい節度のあるファンだった。一緒に写真を撮って貰ったのも、ライブ終わりの一回だけだったし。それで精一杯。でもこの時はそうもいかなかった。お腹の中に子どもがいるっていう事実で混乱していたし」
「あの時妊娠してるって分かったのか?」
「そうです。だから失礼だと思ったけど自分を抑えられなくて」
「俺、ちゃんと対応してたか?」
「ええ、話しかけておいてなんですけど意外でした。ちゃんと相談に乗ってくれて。ライブ中は狂犬みたいに見えてたから。普通で良い。そっちの方が立派だって言ってくれた」
そりゃそうだ。あの時の俺は、中学生くらい人生に拗ねていたんだから。バンドなんてクソだって思ってたし。あまり覚えていないが、退院直後の俺はバンドを始めてからの人生全部を後悔していた。普通に生きられるものならそうするべきだって、したり顔で言っていても不思議じゃない。
「まあ、あの時ならそう言うだろうな。今だってそう思ってるし」
「普通に生きている人にそんなこと言われても響かなかったかもしれない。だけど、あの怒張の篤郎ですらそんなことを考えてるんだって思ったら、気が楽になった。当然まだ不安はあったけど、私ごときが破天荒に生きるなんて、所詮は無理があることなんだって自覚出来た。それで調子に乗って、経済的に不安があることも話した。話すつもりじゃなかったんだけど、偶然帰る方向が同じで、しかも二人共病み上がりって状態だったから歩く速度が遅くて。篤郎さんもあんまり饒舌な方じゃないし、なんと言っても私は憧れの人と一緒にいるわけだからさ。緊張して無言に耐えられなかったの。パパの就職のこととか、世間話のつもりでそういうことを話してたら、いつの間にか愚痴みたいになってた」
なんとなく思い出してきた。確かに気不味かった記憶がある。妊娠が明らかになったファンにかけてやる言葉なんて持ってなかったし。内心でテンパってた。妊婦が相手だ。無碍に突っぱねることも出来ず、ただ話を聞いていた。
「それで、俺はどうしたんだっけ?」
「マスターテープをくれました。DATって言うんですか? 少し小さなカセットで。普通のプレイヤーじゃ再生も出来ないやつ。怒張の最初で最後の音源が入ったマスターテープだって言ってました。金に困ったら、それを売るといいって言ってくれたんです」
退職金代わりのアレな。なんか悔しくて持っているのも嫌だった。俺の頭じゃ、それを金に変えるアイデアなんて思いつかなそうだった。それに、使い所としては最高だと思った。金に困った妊婦にプレゼントするんだ。これで格好もつくはずだって思った。
「まあ、困ってるみたいだったからな。当然のことをしたまでだよ」
「篤郎さんはその時、俺はバンドを抜けるつもりだって言ってた。バンドのメンバーにメジャー志向が芽生えて、もうやってられないって。音楽性の違いってやつなのかなって思った。寂しかったけど。でもその時くれた音源は最高の出来だからって。没になったけど、もし俺が抜けた後で怒張が腑抜けた音楽をやるようになったらそれを売れって。俺の怒張にも少しはファンだっているだろうから、幻の音源とか言ってさ、世界に広めてくれよって。そしたら少しは金になるだろって。なんか格好良かった」
なんかバンド抜けて、ロンドンかニューヨークに音楽修行をしに行くとか口走った気もする。どうかその部分は忘れていてほしいものだ。だって俺はずっと狭いアパートで暮らしていたから。引っ越しなら何度かした。でも狭いアパートから狭いアパートに移動しただけだ。ロンドンにもニューヨークにも行ったことがない。俺はあれから約二十年、どこにも行けていない。
「それでこのカセットテープか。少しは金になったのか?」
俺はテーブルのカセットテープを手に取って軽く振った。不意に今日の目的を思い出した。もし少しでも金になったのなら、俺は恥も外聞もなく権利を主張するつもりだ。まだ高校生の夏鈴と夢乃には軽蔑されるだろうし、実花の素敵な思い出に泥を塗ることにもなるだろう。だけど関係ない。俺はバンドのために金を払わなかった男だぜ。どうか売れていてくれ。
「全然売れなかったみたい」
「どういうことだよ」
がっかりして大声を出してしまった。俺の金はどこに消えた? って気分だった。「うるさいから」と夏鈴から蹴りを貰った。夢乃は俺から距離を置き、無言でため息をついた。
「その後、新しいボーカルを迎えた怒張はメジャーデビューを果たした。その頃にはもう夏鈴が生まれてて、子育てに必死の生活を送っていたからあんまり聞いてなかった。だからラジオで新しい怒張の音楽を聞いた時はびっくりした。全部篤郎さんの言った通りになったって思った。なにこの腑抜けた音楽はって愕然とした。子どもを生む前に感じたほど、経済的に困窮してなかった。パパが頑張ってくれたから。そんなこともあってマスターテープの存在はその時まで忘れていた。だけど、突然篤郎さんとの約束を守らないとって使命感が湧いた。本当の怒張を世界に広めるんだって気になったの。怒張のファン仲間に林蘭丸って子がいた。年下の子だったけど、高校には通わずアダルトビデオのダビング工場を運営してて、頭が切れるって有名だった。蘭丸君に事情を話して、マスターテープを渡した。でもやっぱりあんまり売れなかったみたい。そのカセットテープは売れ残りを記念に貰った一本」
「そうなんだ。今の篤郎のことを考えると複雑だけど、こんな格好良いバンドが売れなかったのって、なんだか残念だよね」
夏鈴が俺の手からカセットテープを取り上げた。残念なのは臨時収入のあてがなくなった俺も一緒だった。だけどショックではなかったな。格好良いのに売れないバンドなんて吐いて捨てるほどある。世の中はそう都合良く出来ていないってことだろうな。当たり前の結果でしかない。
「それが私と篤郎さんの関係。夏鈴が心配するような関係ではないの。別に隠してたわけじゃないけど、篤郎さんは私に気付いてなかったわけだし、わざわざ説明することでもないでしょ。だから黙ってただけ。アルバイトを雇うのは反対だった。そんな余裕うちにはないし。でも夏鈴は勝手だし、パパだって娘に甘いから頭に来ててさ。それで篤郎さんが面接にやって来て、たまたま体の傷を見た。体の傷と、それから切腹の傷跡も。それでピンときた。名前もまんま篤郎だったしね。反発のつもりで雇ったの。昔憧れてたバンドのボーカルと一緒に働けるんだよ? 普通そうするでしょ。なんかさ、懐かしくなって。タンスの奥から宝物が入った缶を引っ張り出して眺めていたのを娘に盗まれるとは思わなかったけどね」
実花は遠くを見つめるような仕草で目を細めた。実際にはリビングの壁を見つめていただけだ。でもその視線の先に、遠い昔の俺がいるのは明らかだった。
「は? え? いきなりどうしたんですか?」
突然リビングに乗り込んできた三人の姿に、実花は驚いているようだった。腰を曲げ、尻を座面から中途半端に浮かせたどっちつかずの体勢を見せた。
「ママ、こいつに脅されてるんだよね?」
夏鈴が、どうかそうであって欲しいという期待を込めて言った。俺のことを押しのけて実花の隣に立つ。夢乃も同じように続く。無理矢理三対一の構図を作られた形だ。
「私が篤郎さんに脅されてる?」
「いいからママ。怖かったよね? でももう大丈夫、一緒に警察に行こ?」と夏鈴が、しっかりと棒立ちをしている実花の体をわざとらしく支えるような姿勢を取った。そして「それとも」と不安気に切り出す。
「それとも、マジでこいつと不倫関係にあるの?」
「不倫? 私が篤郎さんと? 違う違う。そんなことあるわけないじゃない」
そうだ。そんなことあるわけがない。大体俺は実花のことなんてあまり知らない。俺が知ってるのは社長の妻ってことと、馬鹿な娘を生んだってことだけだ。どうやら昔、写真を撮ったことがあるらしいがどんな関係だったかは覚えていない。覚えていないってことは大した関係じゃなかったってことだろう。それにどうやら皆、俺が実花を脅してバイトに受かったって勘違いしているようだけど、それってマジで失礼しちゃうんですけど。この結果は面接を担当した実花に、鋭い観察眼があっただけだし、それに俺には枯れた魅力もあった。惚れられただけで不倫裁判にかけられちゃ堪らねえよ。
「だからもう誤魔化さなくていいんだって。証拠ならあるんだから」
夏鈴が俺にも見せた写真とカセットテープをテーブルの上に並べる。実花はそれらを目にした途端「ああ」と言って頭を抱えた。
「それはちょっと昔を懐かしんでただけだから。大体勝手に部屋に入るなんて最低。いくら家族でも守るべき一線があるでしょ。私が夏鈴の部屋に入ったら烈火の如く怒りだすくせに自分は平気ってわけ?」
「ちょっとちょっと、昔を懐かしむってどういうこと? やっぱり二人は付き合ってたんでしょ? ねえ? このバンドのファン同士で意気投合なんかして」
「さっきからなにを言ってるのよあんた。いい加減にして。また興奮して自分でもわけ分からなくなってるじゃない」
「あたしの客観性に疑問を持ってるってわけね。そう、分かった。夢乃、言ってやりな」
夏鈴が夢乃の手のひらを無理矢理挙げさせて、そこにタッチをした。夢乃は明らかに準備不足だった。突然選手交代を告げられて、集中しきれていない。
「え、ああ、でも」とやると、夏鈴から背中にチョップの喝が入る。「そうですね。まず、私もおばさんの宝物を漁ってしまいました、すみません。写真とカセットテープをお借りしたのも私です。ちょっと興味があって。というか検証に必要で。それで思ったんです。やっぱりおばさんと彼になんの関係もないっていうのは無理があるなって。夏鈴の言ってることが全部正しいとは思えないですけど、ただの雇用主とアルバイトっていう関係は筋が通らないかと。あくまで客観的な意見です、はいすみません」
夢乃は言ってか数歩後退りをした。踵が部屋の壁に触れてからようやく動きを止める。
「ほらみろ」と夏鈴が勝ち誇ったように胸を張った。「ママとこいつは怒張ってバンドのファンだったんだ」
実花の言う通り、夏鈴は混乱していた。俺と実花がどんな関係にあれば納得するのか自分でも分かっていないんだ。ただ意見を押し通したいだけの子どもみたいになってしまっている。
「だから違うって。いや、私が怒張のファンだったっていうのは認めるよ。そこは否定しない。でもね、篤郎さんはバンドのファンなんかじゃない。だって怒張のボーカルだったんだもん」
三人の視線が俺に集まる。期待をされているみたいで緊張した。
「お恥ずかしい話ですが」
「え? 違いますよ。それは嘘ですね」
生唾を飲み込んでから思い切って真実を話したのに、夢乃がすぐに否定してきた。スマホをなにやらタッチして、画像を表示させたものを向けてくる。そこには怒張のメンバー全員が写った画像があった。
「おめえ誰にも相手にされないからって、小学生みたいな嘘つくなよ。こっちが悲しくなるだろ。あたし達は事前に調べてるんだよ。怒張のメンバーにお前はいない」
「そりゃそうだ。その画像に写ってるボーカルは二代目の奴だからな。さっきお前ら俺に聞いたよな。テープと音源じゃ全然印象が違うって。テープの方が俺で、デビューした時にいたボーカルがその糞ったれだよ。だから印象が違うんだよ。全く別物のバンドになっちまった」
夏鈴と夢乃は俺の発言の真偽を確かめるように実花のことを見た。実花は二人に頷く。
「嘘だ」夏鈴が助けを求めるように叫んだ。「このヘタレがテープの方のボーカルなの? 信じられない。だって格好良かったじゃんあのボーカル。それがこいつ? ちょっと待ってよ。嫌だ、違う違う」
「いやあ、別に誇れるようなことでもないから嘘でもいいんだけど」
「でも本当じゃないですか」実花が俺を慰めるようにして言う。「あの頃の篤郎さん、輝いてた。それをなかったことみたいにしないでくださいよ」
輝いてた? 俺が? そんな実感まるでない。確かに俺は夏鈴や夢乃が思うようなクズではない。だけど、憧れられるような人間では決してないはずだ。あの頃だって、今と変わらず世間と切り離された自分だけの人生を勝手に生きていただけだ。
高校の頃、友人達とバンドを組んだ。俺は別に音楽なんて興味がなかった。楽器だって弾けないしな。だけどそいつらとつるんでいるのは楽しかった。皆がバンドを始めるって勝手に盛り上がった時、頭の中で瞬時にそろばんを叩いた。俺も加わらなきゃ次第に疎遠になるだろうって。ここは自分に嘘をついてでも参加するべきだ。だから一緒に盛り上がった。みんなして音楽の字を解体して、音を楽しむことだなんてふざけたこと言い出す現象には辟易したけど、それすら顔に出さなかった。
最終的にバンドに参加したのは俺を入れて四人だった。皆ある程度楽器を演奏出来るようだった。その時始めて知ったよ、こいつら音楽好きだったんだなって。家とかスタジオとかで密かに練習していたらしい。唯一人楽器が弾けない俺は、ボーカルに立候補した。なにせ、今から楽器の練習なんてしたくなかったもんで。俺はただ、仲間たちと一緒に遊んでいたかっただけだから。きっと楽器の練習っていう制約が加わると、即座に投げ出してグループからも爪弾きにされるって分かっていたんだ。お前もギターくらいは練習した方がいんじゃねえか? って言ってた奴もいたけど、俺は譲らなかった。マイクスタンドを握って離さなかったってわけだ。他にボーカル希望の奴もいなかった。皆好みの楽器が弾けて、バンドという形態を取れればそれで良かったみたいだ。
俺の歌は大したことなかった。というかまあ、下手な部類だ。バンドでボーカルをしてたなんて言うと、じゃあカラオケでなんか歌ってって話に必ずなるだろ。別に歌ってやっても構わねえけど、お前らいつも微妙な空気になるじゃねえかってくらいに下手だった。俺には居場所が必要だった。楽器も弾けない、歌も下手なボーカルのままじゃバンドから追い出されるのは時間の問題だった。
ってことで、過激なパフォーマンスに走った。したり顔の音楽かぶれに「こいつのボーカルは歌じゃねえ、心の叫びだ」なんて寝ぼけたことを言わせれば勝ちだって思った。キャラクターも演じた。なにを考えているのか分からない凶暴で社会性のない男。ステージで血まみれになることも多かった。カミソリで肌を切り裂いたりして。地元のライブハウスに出始めの頃は、加減が分からずに苦労した。行き過ぎてしまうのは別に良かったけど、刃物まで出しておいて慎重に肌を切る男なんて誰も見たくはない。外科医が読むような専門書を取り寄せて勉強したもんだよ。最終的にはブラックジャックくらいのメスさばきを習得した。命に別状なく、派手に出血する血管を見つけたりしてな。俺も仲間外れになりたくなくて必死だったんだよ。
パフォーマンスは受けた。いつも貧血状態だったけど、客に盛り上がってもらえて安心した。でもバンド自体にファンがついたのは、結成して少し経ってから作り始めたオリジナルの楽曲が良かったからだと思う。俺だって身を削っているわけだし、自分の手柄にしたい気持ちはあったけど、結局のところ皆音楽を聞きにライブに来てるんだ。俺がピエロ役を買って出たからと言って、心を掴めるわけじゃない。ただ、メンバーにはそう思わせておきたかった。クビになりたくなかったからな。
俺はバンドをやってるのに音楽的なことになにも貢献できていなかった。自信なんて全然なかった。もちろんステージではそんな素振りは見せなかった。俺は怒張のボーカル篤郎だっていうアナーキーな姿勢を保ち続けた。俺にとってアナーキーっていうのは血だった。バンド内での劣等感を解消するために、多目の血飛沫を上げ続けた。やがて俺は、プレッシャーに耐えられなくなった。命の危険も感じていたし。その頃にはもう、二十代も半ばを過ぎていた。引き返すなら今しかないって思った。それに、バンドを組んで数年が経ち、俺も変わった。人間関係自体に変化もあった。もう、絶対にこのグループにいないといけないっていう幼い感情もなかった。で、バンドを抜けた。
その後で奴らは代わりのボーカルを迎え、念願だったデビューを果たした。図らずもメンバーの音楽的センスの良さが証明された形だ。やっぱり血でヌルヌルしたジョン・ゲイシーみたいなピエロなんてバンドには必要なかったってことだ。
俺にとってバンドとはそれくらいのものだった。間違いなく青春の一ページにはなっていたが、決して輝いていた過去ではない。それだけのこと。そう自分に言い聞かせてその後の人生を生きてきたから余計にそう思うのかもしれないけど。
だけどさ、どういうわけか俺のボーカルバージョンのカセットテープが出回っていることを知った。記憶にある限り、俺達は宣伝のためのテープなんて配布したことがなかった。封印されたはずの過去がしっかりと流通している証拠だ。さっきイヤホンから流れてきた、若かりし頃の自分の声を聞いて肝を冷やしたぜ。反対に、こりゃ一体どういうことだって体は熱くなった。このカッセットテープをキッズに売って稼いだ奴がいるって分かったからだ。販売元を探り当てることができれば、もしかしたら俺の権利を主張できるかもしれない。金の匂いがしたわけだ。大金にはならないだろう。だけど、拝島水道が潰れた場合の備えくらいにはなるかもしれない。大体よ、過去を暴かれて一番最初に思うことが権利の主張って奴に、輝いた過去なんてあるわけないだろうが。
「私は怒張のファンだった。それも大ファン。あの頃はよくライブハウスとか行ってて、色んなバンドを見たけど怒張くらい格好良いバンドは他になかった。私の青春の思い出。ちょうどその写真の頃。なによ? 私だってそういう過去はあるの。今はただのおばさんに見えるかもしれないけど、あんた達と同じように、私にだって若い頃はあったんだから」
実花が言うと、夏鈴は目を丸くした。誰にだって若い頃や青春時代はあるが、特に自分の親のこととなると、上手く想像できない気持ちは分かる。俺の母ちゃんだって、婆ちゃんの腹から出てきた瞬間にもうあのヨボヨボの姿だったって言われた方が納得出来る。それくらい親の若い頃っていうのは謎に包まれたものなんだ。
夏鈴は目を大きく見開いたまま「なんかキモい」と、辛辣な感想を述べた。
「あ、そんなこと言っていいの? 私、あの頃本当にめちゃくちゃだったんだから。人刺しミッキーとか呼ばれてたんだよ」
昔のあだ名がどうだったかは分からないが、おそらく実花がむちゃくちゃだったのは本当だろう。というのも、俺がいた頃の怒張にはめちゃくちゃなファンしかいなかったから。今の、普通のおばさんにしか見えない実花からは想像しにくいが、写真で見た若かりし頃の彼女みたいな女は、バンドの周りにはたくさんいた。実花自身があの場にいたと主張するなら、きっと本当にいたんだろう。
「ミッキー? なにそれダサ。信じらんない。でもそこはいいや。じゃあ、ママの方から交際を申し込んだってことね。この信じられないような話を全部信用するなら、だけど」
「だから違うって。当時の篤郎さんは孤高の存在だもん。ただの憧れ。そうやってライブ終わりに写真を撮ってもらうのが精一杯」
実花はテーブルに置いてある写真を指さした。そうか。俺、孤高の存在だったか。今の自分から完全に切り離された他人事のような過去だったけど、なんだかその言葉の響きは気に入った。流石にもっと言ってくれってねだるような気持ちはなかったけれど、言ってくれてもいいっていう許容の気持ちはあった。
「こいつと写真? いつでも何枚でも撮れるでしょ。ほら、何枚でも」
夏鈴は自分のスマホを取り出すと、俺に向けて雑にシャッターを切った。画面を覗いてもいなかった。ノールックで指だけを動かした盗撮スタイルだった。カシャ、カシャ、という無機質な音がしばらくリビングに響いた。
「分かってもらえないよね」
実花は「うーん」と考えた末に絞り出した。恨めしそうな目でちらりと俺の顔色を確認したのを見逃さなかった。今の俺がこんなだから信じてもらえないってことだと判断した。勝手に持ち上げられて、勝手に落胆されることほど悲しいことはない。
「分からないよ、全然分かんない」
夏鈴が大げさに手を振りながらアピールするものだから、右手が夢乃の頬を掠める。
「あ、ごめん」「いいよ、大丈夫」と、二人でクリトリスを舐め合っていた。
「でも彼は私に母親になる決心をさせてくれた人だから。やっぱり特別な存在なの」
母親になる? 俺は実花とやったのか? 玉袋の中にしまったデータベースにリクエストするが、四〇四エラーが返ってくるばかりだった。俺は控え目な方だった。あの頃同じくらい名が売れていたバンドマンの中では、だけど。皆派手に女遊びをしていたし、中にはモデルやアイドルと付き合っているような羨ましい奴もいた。でも俺は違う。所謂良い女には、はっきりと気後れしたからな。かと言って恥じらいもなくファンに手を出すようなこともなかった。そういう奴は仲間内でも馬鹿にされるような時代だったし。ってことで、俺がいったのはファンはファンでも口の固そうなファンばかりだった。
怒張目当てにライブハウスに来ているような奴らが相手なんだ。口の固そうなファンを見つけるのなんて、俺の中にアダムとイブのDNAを見つけるようなものだった。必然的に派手な遊びをしているような奴よりは控え目な行動を取らざるを得なくなった。だけど、年を重ねるだけ重ねた今となっては、ハーレムに住んでいるような暮らしだったのは間違いがない。実花がその口の固そうなファンの一人だったとしたら。考えると気不味かった。
「こいつがあたしのパパってこと? だとしたら私もう死ぬから」
「違う違う違う。言い方が悪かったわね。あなたの父親はパパ。篤郎さんとは関係がない。パパとはちゃんと大学時代に出会って恋愛結婚してるから」
「そこにどうやって篤郎の存在が割り込んでくるのさ。母親になる決意ってなにさ」
夏鈴はもう涙目だった。十代の女が見せる最高の拒絶だった。
「さっきも言ったけど、その頃の私はめちゃくちゃな生活をしてたの。パパは今と同じで真面目な人だったよ。でもそれでなんの問題もなかった。私はそんなパパのことを愛していたし、パパはほら、どんな私でも好きでいてくれるから。だからずっとそんなめちゃくちゃな生活が続くんだろうなって思ってた」
「そこ、そこが信じられないんだよね。だって今のママって普通のおばちゃんじゃん。怒張みたいに激しいバンドが好きだったなんて信じられないんだよね」
「母親になると人は変わるから」
実花は一言で娘を説き伏せた。夏鈴の疑問は行き場を失くしたようにその場を漂ってリビングの床に落ちた。そんなことで納得してしまう女同士のマウンティングが俺には信じられなかった。男からすれば、親になったからなんだっていうんだよってことだから。
「それでいつ篤郎が登場するのよ」
「大学卒業直前に妊娠していることが分かったの。同時にパパが大手の就職を蹴って、実家の水道屋を継ぐことも決まって。それでパニックった。だって、私は就職も決まってなかったから。ふらふらしてたから当然なんだけど。夢もなかったしね。しばらくフラフラして、遊ぶお金はバイトで稼げばいいやって考えてた。パパがキャリアを築いていってくれれば、いつかはそこに合流するんだからって甘い考えがあったんだと思う。でもそういう人生設計が一気に崩れたから。もちろん子どもが出来たのは嬉しかったけど、私自身が子ども過ぎたんだと思う。なんか色々と落ち込んじゃって。そんな時、篤郎さんと初めて話す機会があった。話を聞いてくれて、まだ当たり前の人生を生きることに抵抗があった馬鹿な私に言ってくれた。普通に生きられるチャンスがあるなら絶対にそうした方が良いって。死ぬ気で掴みにいけって。怒張の篤郎がそんなこと言うんだよ? 普通に生きてる奴の方が立派に決まってるだろって。大人になれば理解できる当たり前のことなんだけど、当時の私には妙にぐっときてね」
そんなこと言ったか? 全然記憶になかった。そもそも実花のことを覚えていないのだから、発言を記憶しているわけがなかった。
「それって、いつのことだ?」
「篤郎さんがバンドを抜ける前、ラストライブの数日後。病院の帰りに偶然会って」
閃くものがあった。最初はそれがなにかは分からなかった。だが、頭の中で光った物が周囲を照らし、記憶を呼び寄せている実感があった。ラストライブ。血。救急車。入院。その後で、確かに俺は誰かと話した。あれが誰で、何を話したかは覚えていない。前後関係を思い出す必要があった。思い出したくなくて、蓋をしたような過去も全部。その蓋はもうボロボロだった。気付くと集中してしまいそうになる神経に、ずっと晒されてきたんだから当然だ。思い出したくなかったんだ。あの頃のことは全部。だけど今、遂に蓋が外れてしまった。ステージ上で派手に出血した時みたいに、黒い液体が俺の脳を一気に侵食する。
ライブハウスではそれなりに有名になった。次なる目標はCDデビューだってことになった。オリジナル曲も溜まってきていたし、ライブでは概ね好評だった。俺達ならやれるんじゃねえのって機運がバンド内で高まっていた。レコード会社にコネなんてなかった。対バンなんかで、別のバンドが演っている時は客席にスーツを着たレコード会社関係者みたいな奴を見かけることならあったが、俺達の出番になると消えていた。一体あれはなんだったんだろうな。俺達にしか見えない妖怪かなんかだったのかも。
とにかく、毎回どこかを出血させるような、過激なパフォーマンスに従事するバンドは商売にならないって思ったんだろう。その頃の俺といったら、積年のパフォーマンスが祟り、腕には立派なためらい傷みたいなのが出来てて、まるでメンヘラみたいだったから扱いにくいって判断されたのかもしれない。
誰も協力してくれないなら、自分たちでやるしかないなって話になった。どこにも属さずインディーのまま食えてる先輩バンドを知っていたし、どっちかって言うとそっち側の方が格好良いよなって話になった。メジャーで金に魂を売ったような奴らのことも見てきたし。ま、俺達の場合相手にされなかっただけだけど。そうやって傷を舐め合って、最後には唾を吐きつけるみたいな思考に自ら飛び込まないとやっていられなかった。
レコーディングをするにしても、音源を流通させるにしてもまずは金が必要だった。バンド活動をしばらく休止させて、皆で金を稼ごうって話もあったけど、それは俺が反対した。今だ、って思った。バンドに貢献するなら今しかないって。必要な額の大半を、俺がバイトして貯めてやるって啖呵を切った。その間皆は曲作りに専念してくれって。
俺はコンプレックスの塊だった。音楽的な部分では、俺に価値はないって思ってた。だから金を稼ぐことで仲間に入れてもらおうとしたんだ。これじゃ、親の財布から一万円盗んで、駄菓子屋で大盤振る舞いをするガキと一緒だよな。でもなりふり構っていられなかった。もしかしたら、バンドで飯が食えるかもしれないって時だ。今更ふるいにかけられるわけにはいかなかった。
まだ体力があったし、モチベーションも高かったから昼は引っ越しバイト、夜は交通整理っていう、まるで自分に合っていない仕事を続けた。給料は良かったが、息を止めて生活するような苦しさを味わった。その代償に、ちょっと精神を病んだが、若いって素晴らしい。体の方は次第に慣れていった。ある程度金が溜まった。目標額にはまだ少し足りなかった。それでも苦しんだ分だけ一方で積み上がっていくものもあるのは充実感があった。俺にとって通帳に溜まっていく金額は、努力の結晶でもあったわけだ。
それで、突然惜しくなった。昼と夜にかく汗の量は、本望を洗い流すのに十分だった。別に欲しいものがあったわけではない。その頃から無駄遣いの悪癖もなかった。それでも自分だけの努力をバンド全体に横取りされるのは納得がいかなくなった。
ハイエナ共が俺の金を期待してそろそろレコーディングでも、という雰囲気になった頃だった。田舎のばあちゃんが病気になって入院費が必要になったって、正常な神経をしている者なら決して文句を言えない嘘をひねり出した。皆は快く騙されてくれた。基本的には良い奴らなんだ。俺はバンドのために金を出さなかった。これって着服って言うのかな。分からないけど、確かに強い罪悪感はあった。だけどそれよりも、貯金が一気になくなる方が惜しかった。
皆は皆で、勝手にレコーディングのスケジュールを切っていた。期待していた金額が足りないどころかゼロになったことで、相当焦ったみたいだ。ましてや、俺が死ぬ気で働いている間に、奴らも必死で曲をこさえてた。アーティストの創作意欲は後先を忘れさせる。俺が知らない内に、メンバーの一人が決して借りを作ってはいけない闇金で金を工面した。今すぐレコーディングを始めるにはそうするしかなかったみたいだ。
それで音源の制作を開始した。不思議だったのは、闇金の奴がレコーディングにまで同行して、口を出してきたことだ。聞けば金を借りる時にバンド活動をしていることを話し、お涙頂戴のストーリーで説き伏せたとのことだった。レコーディングに顔を出していたのは千葉って奴だった。闇金の責任者で、昔自身もバンドを組んでいたそうだ。口では若者を支援したいんだって言ってたけど、自分の叶わなかった夢でもって、更に金儲けしたかっただけだろうな。最低な奴だ。シンプルにヤクザだって言えば、こっちだってそれで納得するんだから。
金を貸せば自分もレコーディングごっこが出来るし、バンドが成功すればマルコム・マクラーレンみたいにバンドを支配出来る。なにより、あまりリスクがない。音楽で金を返せなくても、バンドをしているような奴らは元気な若者なんだ。闇金と関連のあるヤバい仕事で稼がせたり、健康な臓器を売りさばいたりすれば貸した金の回収は十分可能だ。多分、金が必要になったバンドマンが頼る有名な闇金だったんじゃないかな。被害者は俺等だけじゃなかったはずだ。
レコーディングした曲を聞いて、千葉は「こりゃいいぞ」って顔をしてた。俺達は「お前に何が分かる」って顔をしたはずだ。しばらくしてスタジオに顔を出した千葉があり得ない提案をした。「バンドでボーカルをやってる俺の息子を加入させろ」ってゴリ押ししてきたんだ。おいおい、ツインボーカルなんて勘弁してくれよって感じだった。あんたの息子に血は流せるのか? って聞きたくなったよ。だけど違った。俺を追放して新たに息子を迎え入れる提案だった。いや、あれは脅しみたいなものだったな。出資したからといって、そんな我儘が通るはずがない。当然メンバーは拒否した。このバンドのボーカルは篤郎だって言ってくれた。俺だって譲るつもりはなかった。千葉に反論するメンバーの後ろで、「そうだそうだ」って援護射撃を送った。
だけど金の力ってすごいよな。バンドのために貯めた金を着服した時にその力の偉大さは痛感しているつもりだった。それでも、あれは自分の弱さがなせる業だと思っていた。慣れない肉体労働で精神がやられ、弱っていた所に札束で頬をビンタされたような状況だったから心が折れたんだと納得していた。まさか他の奴らが金でなびくとは思っていなかった。中々首を縦に振らない怒張メンバーに痺れを切らした千葉は意固地になった。頭に血がのぼり一瞬損得勘定を忘れてしまったようだ。「息子を新ボーカルに抜擢するなら借金を帳消しにする」とまで言ってきた。「完成したCDのプレス代や流通費を負担してもいい」とか「お前らは俺の家族になるんだからな」って。
家族って言葉にはメンバー全員が恐れ慄いた。だってそれって広義では盃を交わすってことだろ? 逆効果だった。でも、今後しばらく金の心配はしなくてもよくなるっていうのは、現状では金を貯め込んでいる俺以外のメンバーの心を鷲掴みにした。皆が皮算用をし始めたことに気付いた。そもそもバンドなんてやっている奴らに労働意欲なんてあるわけがない。借りてしまった金は返さなくてはいけないけど、音源が上手いこと売れなければ労働で埋め合わせなければならないんだ。レコーディング中も皆少しずつではあるが、その重圧に怯えていた。だけど今、まさにくだらない金勘定から開放される提案を受けた。「少し考えさせてください」ってメンバーの一人が自身の中に眠る社会性を絞り出すようにして言ったのを聞いた。
実のある作戦会議の結果、取り敢えず新ボーカルを迎え入れようという話になった。金は返さなきゃならないし、俺バージョンのレコーディングは終わってた。千葉とその息子のお遊びに一旦付き合って、貸し借りなしの状態になったら追い出せばいいって話だった。
俺は滅茶苦茶不安だったね。相手はヤクザ者とその息子なんだ。そんな相手に付け焼き刃の心理戦が通用するとは思えなかった。それに、一時的でもバンドから追い出されるのは良い気がしなかった。千葉の息子は陸っていう少し年下の馬鹿だった。とんでもなく馬鹿だったが、ルックスだけは良かった。千葉が悪知恵を働かして、ルックスだけはいい水商売の女なんかに種付けした結果、この世に生を受けたのが容易に想像出来る外見をしていた。陸のボーカルは最悪だった。なよなよめそめそして、尻から声を出すような発声しか出来ないようなボーカルだった。それに馬鹿だから歌詞も覚えられない。バンドのグルーブに合わせることも出来ない。
俺は陸のボーカル指導としてレコーディングに立ち会った。どうせ追い出すにしても、千葉が目を光らせていたからな。一生懸命にやってるフリが必要だった。情けなかったよ。形式上ではあるが、首を切られたバンドのお手伝いをしている状況なんだから。それでも息を潜めて陸が辞めるのを待つより、少しでもバンドと接点を持っていたかった。存在感をアピールしなければ約束ごと忘れられてしまうんじゃないかって不安だったし。
陸バージョンのレコーディングが終わった頃、久しぶりにライブを行うことになった。ボーカルは俺。千葉の目が光っている時期だった。本来の怒張でライブを行うことに違和感を感じた。そんなことして大丈夫なのか? って感じだった。でも皆は「久しぶりに自由に演りたい。千葉も説得したから」と言ってくれた。ふーん、それならいっか。そんな風に軽く考えていた。
当日、ライブハウスに一番乗りして出番を待っていた。次第に緊張した様子のメンバーが楽屋に集まってくる。そして切り出された。 「悪いけど俺達は陸と一緒にやっていくことになった。お前は怒張から抜けてくれ」
これは俺達の悪巧みを見抜いていた千葉が先回りして通せんぼした結果だって散々言い訳していた気がする。千葉が悪い。俺達は全員悪くない。醜い言い訳が続いた。俺バージョンのマスターテープを退職金代わりに渡してきた。これをどう使おうが、お前の自由だからって。こんなもんもらっても、知恵もコネもない俺にはどうしようもなかった。要は一生使わないことになったから、代わりに処分しておいてくれってことだろ?
俺としては怒張完全体で復活前の、予習復習ライブのはずだったんだけど、いきなりラストライブになったもんだから自分を見失った。足元が崩れる感じがして、立っているのもやっとという状態だった。悔しさと寂しさと混乱に支配された。それでも最後に大きな花火を打ち上げることが出来たなら、皆の考えも変わるかもしれないっていう淡い期待が余計に心をかき乱した。
で、ライブの途中で粗相をした。感情だけが先走って、やったこともない特大パフォーマンスの切腹ショーに従事してしまった。いつもみたいな華麗なメスさばきとはいかず、用意して臨んだ果物ナイフをちょいと深く腹に突き刺し過ぎた。こりゃいかん、と思った時には遅かった。想定外の出血に目が眩んだ。客も引いた。メンバーも演奏を止めた。俺は死を覚悟した。ステージの上で死ねるなら本望だなんて思わなかった。実家の母ちゃんのことが頭に浮かんだ。そしてもし死ぬなら、メンバーが俺を追い詰めたことを一生悔いて、耐えられなくなるくらいの罪悪感を与えようと企んだ。そう企んだのが最後の記憶だ。俺は出血多量で気絶して、救急車で運ばれた。らしい。当然記憶にはなかったけど。
数日入院した。傷もそうだが、精神面を疑われちまってね。精神科医には正直にライブ中のパフォーマンスが行き過ぎたって話した。「三島由紀夫とか好きですか?」って真剣な顔で言われたのは笑ったよ。読んだことねえっつうの。入院中は暇だった。有り余る時間が憂鬱の波となって何度も俺を襲った。突然宙ぶらりんになってしまった。人生の目標も楽しみも、全部奪われたんだ。未来に希望がなくなった。何度も、なんでこんなことになっちまったのかな? って考えた。答えは分かっていた。俺がバンドに金を出さなかったあの瞬間、マルチバースが別の方向へ分岐し始めたんだ。そりゃ後悔はしてる。だけどもう一度人生をやり直しても、俺は絶対に同じことをするだろう。ケチってことなんだろうな。人生をやり直すチャンスがあっても、金を払ってそのチケットを買えないくらいの超ドケチ。ちっぽけな自分には相応しい称号だった。
それで。そうだ。退院した日に病院を出た所で声をかけられた。女だった。確か、妊娠して同じ総合病院の産婦人科に通ってるとか言っていた。でもダメだ。自分のことじゃないし、あの時の俺は自分の抜け殻みたいな感じだったからあまり覚えていない。
「最後のライブは最前列で見てた。まさか篤郎ボーカルの最後のライブにはなるとは思わなかったけど。突然篤郎さんがハラキリをして、虹みたいに血飛沫が飛んだ。客は騒然となった。いつものパフォーマンスとは様子が違ったから。演奏は止まって、救急車が呼ばれた。その後突然ボーカルが変わったから、あの頃のファンは全員、篤郎さんは死んだって噂してた。でも私だけは知っていた。ライブの後、突然体調が悪くなって病院に向かったの。そこで妊娠していることが分かった。ちょうどそのタイミングだったの。パニックになって病院を後にすると、そこに篤郎さんを見つけた。普段なら声を掛けたりしなかった。過去にライブハウスの近くで篤郎さんを見かけたこともあったし。その時はコンビニで成人雑誌を読んでいたからそっとしておいた。それくらい節度のあるファンだった。一緒に写真を撮って貰ったのも、ライブ終わりの一回だけだったし。それで精一杯。でもこの時はそうもいかなかった。お腹の中に子どもがいるっていう事実で混乱していたし」
「あの時妊娠してるって分かったのか?」
「そうです。だから失礼だと思ったけど自分を抑えられなくて」
「俺、ちゃんと対応してたか?」
「ええ、話しかけておいてなんですけど意外でした。ちゃんと相談に乗ってくれて。ライブ中は狂犬みたいに見えてたから。普通で良い。そっちの方が立派だって言ってくれた」
そりゃそうだ。あの時の俺は、中学生くらい人生に拗ねていたんだから。バンドなんてクソだって思ってたし。あまり覚えていないが、退院直後の俺はバンドを始めてからの人生全部を後悔していた。普通に生きられるものならそうするべきだって、したり顔で言っていても不思議じゃない。
「まあ、あの時ならそう言うだろうな。今だってそう思ってるし」
「普通に生きている人にそんなこと言われても響かなかったかもしれない。だけど、あの怒張の篤郎ですらそんなことを考えてるんだって思ったら、気が楽になった。当然まだ不安はあったけど、私ごときが破天荒に生きるなんて、所詮は無理があることなんだって自覚出来た。それで調子に乗って、経済的に不安があることも話した。話すつもりじゃなかったんだけど、偶然帰る方向が同じで、しかも二人共病み上がりって状態だったから歩く速度が遅くて。篤郎さんもあんまり饒舌な方じゃないし、なんと言っても私は憧れの人と一緒にいるわけだからさ。緊張して無言に耐えられなかったの。パパの就職のこととか、世間話のつもりでそういうことを話してたら、いつの間にか愚痴みたいになってた」
なんとなく思い出してきた。確かに気不味かった記憶がある。妊娠が明らかになったファンにかけてやる言葉なんて持ってなかったし。内心でテンパってた。妊婦が相手だ。無碍に突っぱねることも出来ず、ただ話を聞いていた。
「それで、俺はどうしたんだっけ?」
「マスターテープをくれました。DATって言うんですか? 少し小さなカセットで。普通のプレイヤーじゃ再生も出来ないやつ。怒張の最初で最後の音源が入ったマスターテープだって言ってました。金に困ったら、それを売るといいって言ってくれたんです」
退職金代わりのアレな。なんか悔しくて持っているのも嫌だった。俺の頭じゃ、それを金に変えるアイデアなんて思いつかなそうだった。それに、使い所としては最高だと思った。金に困った妊婦にプレゼントするんだ。これで格好もつくはずだって思った。
「まあ、困ってるみたいだったからな。当然のことをしたまでだよ」
「篤郎さんはその時、俺はバンドを抜けるつもりだって言ってた。バンドのメンバーにメジャー志向が芽生えて、もうやってられないって。音楽性の違いってやつなのかなって思った。寂しかったけど。でもその時くれた音源は最高の出来だからって。没になったけど、もし俺が抜けた後で怒張が腑抜けた音楽をやるようになったらそれを売れって。俺の怒張にも少しはファンだっているだろうから、幻の音源とか言ってさ、世界に広めてくれよって。そしたら少しは金になるだろって。なんか格好良かった」
なんかバンド抜けて、ロンドンかニューヨークに音楽修行をしに行くとか口走った気もする。どうかその部分は忘れていてほしいものだ。だって俺はずっと狭いアパートで暮らしていたから。引っ越しなら何度かした。でも狭いアパートから狭いアパートに移動しただけだ。ロンドンにもニューヨークにも行ったことがない。俺はあれから約二十年、どこにも行けていない。
「それでこのカセットテープか。少しは金になったのか?」
俺はテーブルのカセットテープを手に取って軽く振った。不意に今日の目的を思い出した。もし少しでも金になったのなら、俺は恥も外聞もなく権利を主張するつもりだ。まだ高校生の夏鈴と夢乃には軽蔑されるだろうし、実花の素敵な思い出に泥を塗ることにもなるだろう。だけど関係ない。俺はバンドのために金を払わなかった男だぜ。どうか売れていてくれ。
「全然売れなかったみたい」
「どういうことだよ」
がっかりして大声を出してしまった。俺の金はどこに消えた? って気分だった。「うるさいから」と夏鈴から蹴りを貰った。夢乃は俺から距離を置き、無言でため息をついた。
「その後、新しいボーカルを迎えた怒張はメジャーデビューを果たした。その頃にはもう夏鈴が生まれてて、子育てに必死の生活を送っていたからあんまり聞いてなかった。だからラジオで新しい怒張の音楽を聞いた時はびっくりした。全部篤郎さんの言った通りになったって思った。なにこの腑抜けた音楽はって愕然とした。子どもを生む前に感じたほど、経済的に困窮してなかった。パパが頑張ってくれたから。そんなこともあってマスターテープの存在はその時まで忘れていた。だけど、突然篤郎さんとの約束を守らないとって使命感が湧いた。本当の怒張を世界に広めるんだって気になったの。怒張のファン仲間に林蘭丸って子がいた。年下の子だったけど、高校には通わずアダルトビデオのダビング工場を運営してて、頭が切れるって有名だった。蘭丸君に事情を話して、マスターテープを渡した。でもやっぱりあんまり売れなかったみたい。そのカセットテープは売れ残りを記念に貰った一本」
「そうなんだ。今の篤郎のことを考えると複雑だけど、こんな格好良いバンドが売れなかったのって、なんだか残念だよね」
夏鈴が俺の手からカセットテープを取り上げた。残念なのは臨時収入のあてがなくなった俺も一緒だった。だけどショックではなかったな。格好良いのに売れないバンドなんて吐いて捨てるほどある。世の中はそう都合良く出来ていないってことだろうな。当たり前の結果でしかない。
「それが私と篤郎さんの関係。夏鈴が心配するような関係ではないの。別に隠してたわけじゃないけど、篤郎さんは私に気付いてなかったわけだし、わざわざ説明することでもないでしょ。だから黙ってただけ。アルバイトを雇うのは反対だった。そんな余裕うちにはないし。でも夏鈴は勝手だし、パパだって娘に甘いから頭に来ててさ。それで篤郎さんが面接にやって来て、たまたま体の傷を見た。体の傷と、それから切腹の傷跡も。それでピンときた。名前もまんま篤郎だったしね。反発のつもりで雇ったの。昔憧れてたバンドのボーカルと一緒に働けるんだよ? 普通そうするでしょ。なんかさ、懐かしくなって。タンスの奥から宝物が入った缶を引っ張り出して眺めていたのを娘に盗まれるとは思わなかったけどね」
実花は遠くを見つめるような仕草で目を細めた。実際にはリビングの壁を見つめていただけだ。でもその視線の先に、遠い昔の俺がいるのは明らかだった。
0
あなたにおすすめの小説

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

クラスメイトの美少女と無人島に流された件
桜井正宗
青春
修学旅行で離島へ向かう最中――悪天候に見舞われ、台風が直撃。船が沈没した。
高校二年の早坂 啓(はやさか てつ)は、気づくと砂浜で寝ていた。周囲を見渡すとクラスメイトで美少女の天音 愛(あまね まな)が隣に倒れていた。
どうやら、漂流して流されていたようだった。
帰ろうにも島は『無人島』。
しばらくは島で生きていくしかなくなった。天音と共に無人島サバイバルをしていくのだが……クラスの女子が次々に見つかり、やがてハーレムに。
男一人と女子十五人で……取り合いに発展!?


Hand in Hand - 二人で進むフィギュアスケート青春小説
宮 都
青春
幼なじみへの気持ちの変化を自覚できずにいた中2の夏。ライバルとの出会いが、少年を未知のスポーツへと向わせた。
美少女と手に手をとって進むその競技の名は、アイスダンス!!
【2022/6/11完結】
その日僕たちの教室は、朝から転校生が来るという噂に落ち着きをなくしていた。帰国子女らしいという情報も入り、誰もがますます転校生への期待を募らせていた。
そんな中でただ一人、果歩(かほ)だけは違っていた。
「制覇、今日は五時からだから。来てね」
隣の席に座る彼女は大きな瞳を輝かせて、にっこりこちらを覗きこんだ。
担任が一人の生徒とともに教室に入ってきた。みんなの目が一斉にそちらに向かった。それでも果歩だけはずっと僕の方を見ていた。
◇
こんな二人の居場所に現れたアメリカ帰りの転校生。少年はアイスダンスをするという彼に強い焦りを感じ、彼と同じ道に飛び込んでいく……
――小説家になろう、カクヨム(別タイトル)にも掲載――

学園のアイドルに、俺の部屋のギャル地縛霊がちょっかいを出すから話がややこしくなる。
たかなしポン太
青春
【第1回ノベルピアWEB小説コンテスト中間選考通過作品】
『み、見えるの?』
「見えるかと言われると……ギリ見えない……」
『ふぇっ? ちょっ、ちょっと! どこ見てんのよ!』
◆◆◆
仏教系学園の高校に通う霊能者、尚也。
劣悪な環境での寮生活を1年間終えたあと、2年生から念願のアパート暮らしを始めることになった。
ところが入居予定のアパートの部屋に行ってみると……そこにはセーラー服を着たギャル地縛霊、りんが住み着いていた。
後悔の念が強すぎて、この世に魂が残ってしまったりん。
尚也はそんなりんを無事に成仏させるため、りんと共同生活をすることを決意する。
また新学期の学校では、尚也は学園のアイドルこと花宮琴葉と同じクラスで席も近くなった。
尚也は1年生の時、たまたま琴葉が困っていた時に助けてあげたことがあるのだが……
霊能者の尚也、ギャル地縛霊のりん、学園のアイドル琴葉。
3人とその仲間たちが繰り広げる、ちょっと不思議な日常。
愉快で甘くて、ちょっと切ない、ライトファンタジーなラブコメディー!
※本作品はフィクションであり、実在の人物や団体、製品とは一切関係ありません。
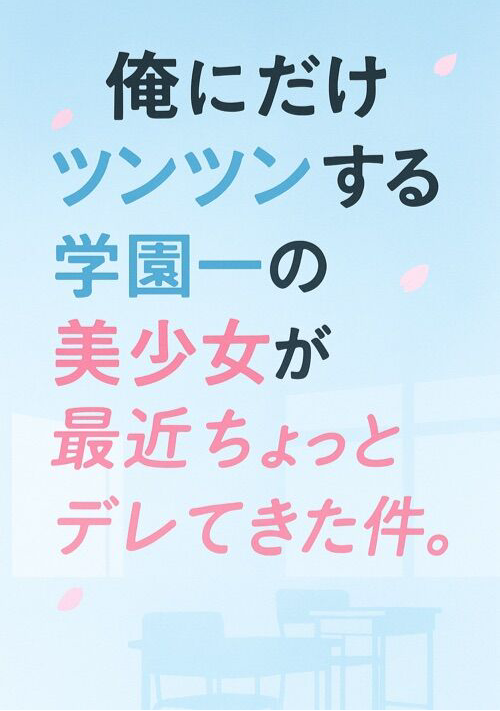
俺にだけツンツンする学園一の美少女が、最近ちょっとデレてきた件。
甘酢ニノ
恋愛
彼女いない歴=年齢の高校生・相沢蓮。
平凡な日々を送る彼の前に立ちはだかるのは──
学園一の美少女・黒瀬葵。
なぜか彼女は、俺にだけやたらとツンツンしてくる。
冷たくて、意地っ張りで、でも時々見せるその“素”が、どうしようもなく気になる。
最初はただの勘違いだったはずの関係。
けれど、小さな出来事の積み重ねが、少しずつ2人の距離を変えていく。
ツンデレな彼女と、不器用な俺がすれ違いながら少しずつ近づく、
焦れったくて甘酸っぱい、青春ラブコメディ。


『俺アレルギー』の抗体は、俺のことが好きな人にしか現れない?学園のアイドルから、幼馴染までノーマスク。その意味を俺は知らない
七星点灯
青春
雨宮優(あまみや ゆう)は、世界でたった一つしかない奇病、『俺アレルギー』の根源となってしまった。
彼の周りにいる人間は、花粉症の様な症状に見舞われ、マスク無しではまともに会話できない。
しかし、マスクをつけずに彼とラクラク会話ができる女の子達がいる。幼馴染、クラスメイトのギャル、先輩などなど……。
彼女達はそう、彼のことが好きすぎて、身体が勝手に『俺アレルギー』の抗体を作ってしまったのだ!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















