39 / 39
【39】
しおりを挟む
カサンドラは海を越え帝国にきていた――テシュロン学園が長期休暇に入ったので、王都や隣国の騒ぎなど我関せずとばかりに領地に戻ったつもりだったのだが、いつのまにかトリスタンに連れ出され、大型船に乗せられてフラグア海の対岸へ。
帝国へ行くとは言っていなかったが、行かないとも言っていなかったことを思い出し――領地にいる父親も、とくに何も言いはしなかった。
カサンドラが本気で拒めば、トリスタンが連れていかないことは、理解しているようだった。
カサンドラが乗せられた大型軍用船が停泊すると、
「姫さま、しっかりと捕まって」
「お前がしっかりと掴んでいればいいだけでしょう。わたくしを落とすなんて、もってのほかよ」
「台詞が言いたかっただけ。俺が姫さまを落とすわけないじゃないか」
「思いっきり落としそうな台詞ね」
「姫さまって、どこまでいっても姫さまだ」
トリスタンに抱きかかえられ、海の上で小型の船に乗りかえた。
小型の船といっても、船長や航海士や料理人に数名の雑用係。食糧はもちろん、生きた家畜も積み込まれている。
船室はさすがに広々とはいかないが、ベッドは大きさも寝具も整っていて寝心地は悪くない。
そんな小型船でフラグア海に流れ込む川を遡上し――
(帝国の首都へ向かうわけではないようね)
帝国の首都とは別方向――反対ではなく、首都から少しずれた方向に進んでいるこは分かった。
カサンドラはどこへ連れていかれるのか、もちろん聞かされていない。聞いたところでトリスタンが答えるとは思わなかった。
「目的地を聞かないの?」
「知らないほうが、楽しめそうだから、聞かないでおくわ。楽しませてくれるんでしょう? お前」
カサンドラは隣で横になっているトリスタンに背を向けて、目を閉じた。船底から海とは違った水音が、微かに聞こえてくる。
「もちろん。この穏やかで静かな水の音、共鳴によく似ているよね」
トリスタンに背を向けていたカサンドラは、体の向きを変えて文句を言う。
「お前の共鳴は、こんなに穏やかじゃないわ、とても煩いわよ。高い滝から落ちて来る水音もかき消すほどの轟音に似ているわ」
彼らがカサンドラの言うことを素直に聞くのは、カサンドラの血が彼らの凶暴性を、穏やかにできるからに他ならない。
「……え? そうなの」
心の底から驚いたと、トリスタンは目を大きくひらく。トリスタンの目は切れ長。肌は象牙色で、カサンドラたちが住む大陸の人間とは、随分と顔だちが違う。
海を挟んだ反対側だから……ということもあるが、どちらかと言えば、カサンドラたちが住む大陸から、神代の太陽の王家の血が根こそぎ奪われ、この顔だちが急激に減ったことが大きい。
かつては、カサンドラが生まれ育ったトラブゾン――神代の頃から闇の王家があった土地にも、太陽の王家の血を引く者はいた。
太陽の王家があった土地に、カサンドラと同じく闇の王家の血を色濃く引く者もいた。
それらが途絶えたのは、あの神兵を作り、世界を統一しようとした王が現れ――闇の王家の血は、安らぎを与えるので、攻撃性を求めた王にとっては必要なく、殺害、迫害され、カサンドラたちゼータ一族が住む、かつての領地に戻ってきた。
反対に太陽の王家の者たちは集められ、こちら側には、ほとんど太陽の王家の血を引くものはいなくなった。
その結果、花害が起こることになるのだが、ほんの僅かな歳月で人は忘れてしまった。
だが昔から、花の王家が神代を滅ぼした頃から続いている者たちは、そのことを知っていた。
繁栄しかできず滅ぶ。ならば繁栄の最中に滅ぼせば良い――強すぎる光は、すべての生き物を滅ぼすことができ、滅ぼしたという。
「わたくしは闇の血を引いているから、共鳴しても相手に安らぎを与えることができるのだけれど、お前の太陽の血はひときわ煩いのよ」
トリスタンはカサンドラに覆い被さる姿勢になる――色の違う髪が一房零れおちた。
「それはそれは。でも俺は姫さまに触れていると、安らぐんだよ」
「安らぐだけで満足なのかしら?」
カサンドラはトリスタンの一房の髪をつまんで軽く引っ張る。トリスタンはそれに応えるように顔を近づけてきて、そのまま口づけた――共鳴がトリスタンに安らぎを与えているなど、まったく信じられない二夜をカサンドラは過ごす。
川を遡ること三日目の朝、乗っていた小型船が停まる。
髪を緩やかな一本の三つ編みでまとめ、学園の作業服に似た、活動しやすい無地の黒いワンピースに着替え、テシュロン学園に持ち込んでいた、歩き慣れたレースアップブーツを履き替えたカサンドラが船室から出ると、陸地は見渡す限り青い花に覆われていた。
カサンドラが初めて見た花害――穀倉地帯を染め上げ、人々の糧を奪うそれ。
風に揺れる小さな青い花たちは、悪意など欠片もなく、ただそこに咲いている。青い花に悪意はない――花害に関しては、それは正しくはない。
一面に広がる青い花は、一人の男が咲かせている――トリスタンはカサンドラを抱き上げて船から下り、
「気を付けて、姫さま」
ゆっくりと地面に降ろした。久しぶりに地に足をつけたカサンドラは、慣れない感触に少しふらついたが、トリスタンに支えられて倒れることはなかった。
「もう、大丈夫よ」
「初めて会った日のことを、思い出して」
墓地で会った時のことを思い出したと言われて、カサンドラは笑い返す。
「お前、そんなこと思い出したりするの?」
「姫さま、俺のことをなんだと」
「ハンス・シュミット。それで、お前、ここはどこなの?」
「ああ、ここは――」
それは帝国の始まりの国。神兵を作り世界征服しようとした国の首都だった。
人の王の愚かな欲望の残骸が、青く青く広がっていた。
「似合わないわね」
「言うと思った」
腰に背骨を差し、片手にピクニックバスケットというちぐはぐな格好のトリスタンとともに、カサンドラは青い花に覆われた平地を少し歩き、同じく青い花に埋め尽くされた緩やかな傾斜の丘を登る。
歩いていると青い花に隠れているが、かつては規則正しく石畳が敷かれていたのがカサンドラにも分かった。
ところどころに、青い花が盛り上がり――折れた柱を覆い尽くしていた。柱の大きさから、この辺りに巨大な建物があったのが分かる。
(ということは、この先は――)
一歩一歩進むほどに、徐々に大きくなる、丘の上の建築物。
「かつての王宮。いまは眠れる墓と呼ばれている」
登りきったカサンドラの目の前にあったのは、ここに来るまでと同じく、青い花に浸食された赤みがかった大きな建物。
神兵たちに国を滅ぼされてから、ここはずっと放置されたままだと、トリスタンが言う。
「へえ、ここがねえ」
カサンドラは雨風に晒されざらついた大きな柱を撫でる――地面に生えていた青い花が、急激に伸びて、カサンドラの手を絡め取り、腕を覆い尽くす。
「今頃オルフロンデッタも、こうなっているはず」
「青い花に取り囲まれているということ?」
カサンドラは腕の青い花をそのままにして膝を折り、別の青い花の花弁を引きちぎり、風に乗せた。
「二十数年前、海の向こうの国に仕掛けた花害は、半分くらいしか成功しなかったが、あの失敗から学んだことも大きかった……と、カエターンが言っていた」
カサンドラは青い花に覆われた手をトリスタンの方へと伸ばし――青い花は見る間に萎れてゆく。
「そして今回は海の向こうの国に仕掛けて成功したわけね?」
トリスタンから答えはなく、運んだバスケットを開く。
「姫さま、散歩をして疲れたでしょう?」
「当たり前でしょう。早くクッションを用意なさい」
カサンドラは萎れた青い花を腕から剥がしながら、クッションに腰を降ろし、水筒の水で喉を潤し――風に揺れる青い花をを目を細めて眺める。
「これ、お前の仕業なのでしょう?」
見える全てを埋め尽くす青い花――大陸を征服しようなどと考えた始まりの国は、その国土のすべてをこの青い花によって埋め尽くされ、食糧を一切生産することができない、不毛の大地と化した。
「最初は俺じゃない。俺は引き継いだだけ。それでこれ、とても綺麗だと思うんだ。姫さまはどう思う?」
オフターディンゲンはこの青い花を、すべて枯らすこともできる。
「美しいと感じるわ。お前と同意見になるなんて、珍しいわね。嫌ではないけれど」
ゼータはこの青い花を、すべて枯らすことができる。
「じゃあ、このままでいいよね」
この青い花を、すべて枯らすことができるのはオフターディンゲンともう一人しかいない。
「勝手になさい。でも花を勝手に枯らすことは、許さないわ。クリームとジャムを塗ったビスケットが食べたいわ」
この青い花を、すべて枯らすことができるのは、ゼータともう一人しかいない。
「やったことないから、上手くできるかな」
「期待しているわ」
「俺も」
そして二人は青く染まった美しき永遠の不毛の大地で笑い合う――人がこの美しい不毛の地を踏むことは、もうしばらくない。終わりがどこにあるかは分からない
【終わり】
帝国へ行くとは言っていなかったが、行かないとも言っていなかったことを思い出し――領地にいる父親も、とくに何も言いはしなかった。
カサンドラが本気で拒めば、トリスタンが連れていかないことは、理解しているようだった。
カサンドラが乗せられた大型軍用船が停泊すると、
「姫さま、しっかりと捕まって」
「お前がしっかりと掴んでいればいいだけでしょう。わたくしを落とすなんて、もってのほかよ」
「台詞が言いたかっただけ。俺が姫さまを落とすわけないじゃないか」
「思いっきり落としそうな台詞ね」
「姫さまって、どこまでいっても姫さまだ」
トリスタンに抱きかかえられ、海の上で小型の船に乗りかえた。
小型の船といっても、船長や航海士や料理人に数名の雑用係。食糧はもちろん、生きた家畜も積み込まれている。
船室はさすがに広々とはいかないが、ベッドは大きさも寝具も整っていて寝心地は悪くない。
そんな小型船でフラグア海に流れ込む川を遡上し――
(帝国の首都へ向かうわけではないようね)
帝国の首都とは別方向――反対ではなく、首都から少しずれた方向に進んでいるこは分かった。
カサンドラはどこへ連れていかれるのか、もちろん聞かされていない。聞いたところでトリスタンが答えるとは思わなかった。
「目的地を聞かないの?」
「知らないほうが、楽しめそうだから、聞かないでおくわ。楽しませてくれるんでしょう? お前」
カサンドラは隣で横になっているトリスタンに背を向けて、目を閉じた。船底から海とは違った水音が、微かに聞こえてくる。
「もちろん。この穏やかで静かな水の音、共鳴によく似ているよね」
トリスタンに背を向けていたカサンドラは、体の向きを変えて文句を言う。
「お前の共鳴は、こんなに穏やかじゃないわ、とても煩いわよ。高い滝から落ちて来る水音もかき消すほどの轟音に似ているわ」
彼らがカサンドラの言うことを素直に聞くのは、カサンドラの血が彼らの凶暴性を、穏やかにできるからに他ならない。
「……え? そうなの」
心の底から驚いたと、トリスタンは目を大きくひらく。トリスタンの目は切れ長。肌は象牙色で、カサンドラたちが住む大陸の人間とは、随分と顔だちが違う。
海を挟んだ反対側だから……ということもあるが、どちらかと言えば、カサンドラたちが住む大陸から、神代の太陽の王家の血が根こそぎ奪われ、この顔だちが急激に減ったことが大きい。
かつては、カサンドラが生まれ育ったトラブゾン――神代の頃から闇の王家があった土地にも、太陽の王家の血を引く者はいた。
太陽の王家があった土地に、カサンドラと同じく闇の王家の血を色濃く引く者もいた。
それらが途絶えたのは、あの神兵を作り、世界を統一しようとした王が現れ――闇の王家の血は、安らぎを与えるので、攻撃性を求めた王にとっては必要なく、殺害、迫害され、カサンドラたちゼータ一族が住む、かつての領地に戻ってきた。
反対に太陽の王家の者たちは集められ、こちら側には、ほとんど太陽の王家の血を引くものはいなくなった。
その結果、花害が起こることになるのだが、ほんの僅かな歳月で人は忘れてしまった。
だが昔から、花の王家が神代を滅ぼした頃から続いている者たちは、そのことを知っていた。
繁栄しかできず滅ぶ。ならば繁栄の最中に滅ぼせば良い――強すぎる光は、すべての生き物を滅ぼすことができ、滅ぼしたという。
「わたくしは闇の血を引いているから、共鳴しても相手に安らぎを与えることができるのだけれど、お前の太陽の血はひときわ煩いのよ」
トリスタンはカサンドラに覆い被さる姿勢になる――色の違う髪が一房零れおちた。
「それはそれは。でも俺は姫さまに触れていると、安らぐんだよ」
「安らぐだけで満足なのかしら?」
カサンドラはトリスタンの一房の髪をつまんで軽く引っ張る。トリスタンはそれに応えるように顔を近づけてきて、そのまま口づけた――共鳴がトリスタンに安らぎを与えているなど、まったく信じられない二夜をカサンドラは過ごす。
川を遡ること三日目の朝、乗っていた小型船が停まる。
髪を緩やかな一本の三つ編みでまとめ、学園の作業服に似た、活動しやすい無地の黒いワンピースに着替え、テシュロン学園に持ち込んでいた、歩き慣れたレースアップブーツを履き替えたカサンドラが船室から出ると、陸地は見渡す限り青い花に覆われていた。
カサンドラが初めて見た花害――穀倉地帯を染め上げ、人々の糧を奪うそれ。
風に揺れる小さな青い花たちは、悪意など欠片もなく、ただそこに咲いている。青い花に悪意はない――花害に関しては、それは正しくはない。
一面に広がる青い花は、一人の男が咲かせている――トリスタンはカサンドラを抱き上げて船から下り、
「気を付けて、姫さま」
ゆっくりと地面に降ろした。久しぶりに地に足をつけたカサンドラは、慣れない感触に少しふらついたが、トリスタンに支えられて倒れることはなかった。
「もう、大丈夫よ」
「初めて会った日のことを、思い出して」
墓地で会った時のことを思い出したと言われて、カサンドラは笑い返す。
「お前、そんなこと思い出したりするの?」
「姫さま、俺のことをなんだと」
「ハンス・シュミット。それで、お前、ここはどこなの?」
「ああ、ここは――」
それは帝国の始まりの国。神兵を作り世界征服しようとした国の首都だった。
人の王の愚かな欲望の残骸が、青く青く広がっていた。
「似合わないわね」
「言うと思った」
腰に背骨を差し、片手にピクニックバスケットというちぐはぐな格好のトリスタンとともに、カサンドラは青い花に覆われた平地を少し歩き、同じく青い花に埋め尽くされた緩やかな傾斜の丘を登る。
歩いていると青い花に隠れているが、かつては規則正しく石畳が敷かれていたのがカサンドラにも分かった。
ところどころに、青い花が盛り上がり――折れた柱を覆い尽くしていた。柱の大きさから、この辺りに巨大な建物があったのが分かる。
(ということは、この先は――)
一歩一歩進むほどに、徐々に大きくなる、丘の上の建築物。
「かつての王宮。いまは眠れる墓と呼ばれている」
登りきったカサンドラの目の前にあったのは、ここに来るまでと同じく、青い花に浸食された赤みがかった大きな建物。
神兵たちに国を滅ぼされてから、ここはずっと放置されたままだと、トリスタンが言う。
「へえ、ここがねえ」
カサンドラは雨風に晒されざらついた大きな柱を撫でる――地面に生えていた青い花が、急激に伸びて、カサンドラの手を絡め取り、腕を覆い尽くす。
「今頃オルフロンデッタも、こうなっているはず」
「青い花に取り囲まれているということ?」
カサンドラは腕の青い花をそのままにして膝を折り、別の青い花の花弁を引きちぎり、風に乗せた。
「二十数年前、海の向こうの国に仕掛けた花害は、半分くらいしか成功しなかったが、あの失敗から学んだことも大きかった……と、カエターンが言っていた」
カサンドラは青い花に覆われた手をトリスタンの方へと伸ばし――青い花は見る間に萎れてゆく。
「そして今回は海の向こうの国に仕掛けて成功したわけね?」
トリスタンから答えはなく、運んだバスケットを開く。
「姫さま、散歩をして疲れたでしょう?」
「当たり前でしょう。早くクッションを用意なさい」
カサンドラは萎れた青い花を腕から剥がしながら、クッションに腰を降ろし、水筒の水で喉を潤し――風に揺れる青い花をを目を細めて眺める。
「これ、お前の仕業なのでしょう?」
見える全てを埋め尽くす青い花――大陸を征服しようなどと考えた始まりの国は、その国土のすべてをこの青い花によって埋め尽くされ、食糧を一切生産することができない、不毛の大地と化した。
「最初は俺じゃない。俺は引き継いだだけ。それでこれ、とても綺麗だと思うんだ。姫さまはどう思う?」
オフターディンゲンはこの青い花を、すべて枯らすこともできる。
「美しいと感じるわ。お前と同意見になるなんて、珍しいわね。嫌ではないけれど」
ゼータはこの青い花を、すべて枯らすことができる。
「じゃあ、このままでいいよね」
この青い花を、すべて枯らすことができるのはオフターディンゲンともう一人しかいない。
「勝手になさい。でも花を勝手に枯らすことは、許さないわ。クリームとジャムを塗ったビスケットが食べたいわ」
この青い花を、すべて枯らすことができるのは、ゼータともう一人しかいない。
「やったことないから、上手くできるかな」
「期待しているわ」
「俺も」
そして二人は青く染まった美しき永遠の不毛の大地で笑い合う――人がこの美しい不毛の地を踏むことは、もうしばらくない。終わりがどこにあるかは分からない
【終わり】
2
この作品は感想を受け付けておりません。
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

神のミスで転生したけど、幼児化しちゃった!〜もふもふと一緒に、異世界ライフを楽しもう!〜
一ノ蔵(いちのくら)
ファンタジー
※第18回ファンタジー小説大賞にて、奨励賞を受賞しました!投票して頂いた皆様には、感謝申し上げますm(_ _)m
✩物語は、ゆっくり進みます。冒険より、日常に重きありの異世界ライフです。
【あらすじ】
神のミスにより、異世界転生が決まったミオ。調子に乗って、スキルを欲張り過ぎた結果、幼児化してしまった!
そんなハプニングがありつつも、ミオは、大好きな異世界で送る第二の人生に、希望いっぱい!
事故のお詫びに遣わされた、守護獣神のジョウとともに、ミオは異世界ライフを楽しみます!
カクヨム(吉野 ひな)にて、先行投稿しています。

貧民街の元娼婦に育てられた孤児は前世の記憶が蘇り底辺から成り上がり世界の救世主になる。
黒ハット
ファンタジー
【完結しました】捨て子だった主人公は、元貴族の側室で騙せれて娼婦だった女性に拾われて最下層階級の貧民街で育てられるが、13歳の時に崖から川に突き落とされて意識が無くなり。気が付くと前世の日本で物理学の研究生だった記憶が蘇り、周りの人たちの善意で底辺から抜け出し成り上がって世界の救世主と呼ばれる様になる。
この作品は小説書き始めた初期の作品で内容と書き方をリメイクして再投稿を始めました。感想、応援よろしくお願いいたします。

王子を身籠りました
青の雀
恋愛
婚約者である王太子から、毒を盛って殺そうとした冤罪をかけられ収監されるが、その時すでに王太子の子供を身籠っていたセレンティー。
王太子に黙って、出産するも子供の容姿が王家特有の金髪金眼だった。
再び、王太子が毒を盛られ、死にかけた時、我が子と対面するが…というお話。

【完結・おまけ追加】期間限定の妻は夫にとろっとろに蕩けさせられて大変困惑しております
紬あおい
恋愛
病弱な妹リリスの代わりに嫁いだミルゼは、夫のラディアスと期間限定の夫婦となる。
二年後にはリリスと交代しなければならない。
そんなミルゼを閨で蕩かすラディアス。
普段も優しい良き夫に困惑を隠せないミルゼだった…
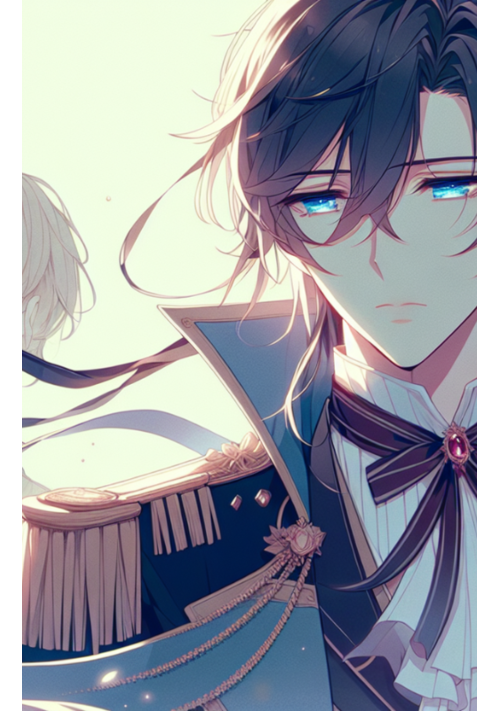
私たちの離婚幸福論
桔梗
ファンタジー
ヴェルディア帝国の皇后として、順風満帆な人生を歩んでいたルシェル。
しかし、彼女の平穏な日々は、ノアの突然の記憶喪失によって崩れ去る。
彼はルシェルとの記憶だけを失い、代わりに”愛する女性”としてイザベルを迎え入れたのだった。
信じていた愛が消え、冷たく突き放されるルシェル。
だがそこに、隣国アンダルシア王国の皇太子ゼノンが現れ、驚くべき提案を持ちかける。
それは救済か、あるいは——
真実を覆う闇の中、ルシェルの新たな運命が幕を開ける。

断る――――前にもそう言ったはずだ
鈴宮(すずみや)
恋愛
「寝室を分けませんか?」
結婚して三年。王太子エルネストと妃モニカの間にはまだ子供が居ない。
周囲からは『そろそろ側妃を』という声が上がっているものの、彼はモニカと寝室を分けることを拒んでいる。
けれど、エルネストはいつだって、モニカにだけ冷たかった。
他の人々に向けられる優しい言葉、笑顔が彼女に向けられることない。
(わたくし以外の女性が妃ならば、エルネスト様はもっと幸せだろうに……)
そんな時、侍女のコゼットが『エルネストから想いを寄せられている』ことをモニカに打ち明ける。
ようやく側妃を娶る気になったのか――――エルネストがコゼットと過ごせるよう、私室で休むことにしたモニカ。
そんな彼女の元に、護衛騎士であるヴィクトルがやってきて――――?

愛する夫が目の前で別の女性と恋に落ちました。
ましゅぺちーの
恋愛
伯爵令嬢のアンジェは公爵家の嫡男であるアランに嫁いだ。
子はなかなかできなかったが、それでも仲の良い夫婦だった。
――彼女が現れるまでは。
二人が結婚して五年を迎えた記念パーティーでアランは若く美しい令嬢と恋に落ちてしまう。
それからアランは変わり、何かと彼女のことを優先するようになり……
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















