6 / 55
第1章 とても古い屋敷のなかで
6
しおりを挟む
アヤだ、とミチは思った。
目は進一郎を見ていた。
そして進一郎もその目の絵を見つめていた。
「だめです進一郎さん、だめだ、見ちゃいけない!」
ミチは声をあげた。
声はのどに引っかかるようにしてつまった。口から出たときにはかすれていた。
ミチは叫んだつもりだったが、実際にはまるでささやくような頼りない声になってしまった。
だけどその場を囲んだ大きな切り石たちがミチの声を逃さなかった。
石に声が反響した。
そしてその声に反応したのは、進一郎ではなかった。
床に描かれた目玉がぎょろりと動いた。
ミチはゾッとした。一瞬で肌がフツフツフツと粟立った。
(目が動いた。絵なのに動いた。いやちがう、あれは絵じゃない――アヤだ。
あれが津江さんのいうアヤなんだ)
だれに教えられたわけでもないのに、ミチはそう思った。
目玉が左右にゆっくりと動いた。
まるで、なにかを探るようだった。
ミチは体をかたくし息をのんで目玉を見つめたが、目玉の視線はミチを素通りしていく。ミチは気づいた。
(ぼくが見えていないんだ。もしかして津江さんの『まじない』のせいかも)
だからといって安心する気持ちはまったくわいてこなかった。体が緊張ですっかり冷えきった。視線が赤い目玉にはりついて離れない。こわくて仕方がないのに、目を離すことができないのだ。
(動け、ぼくの体。動け、動いてくれ!)
ミチの額に汗がにじんだ。背中にもだ。でも暑いわけじゃない。その逆だ。
緊張で冷えた体が汗でいっそう冷たくなった。背中もおなかも指先も冷たい。
こわくてこわくてたまらない。冷えたミチの指先から力が抜けた。
そしてそのためにことが動いた。
懐中電灯がミチの指先からはなれた。
あ、と思う間に床に落ちてカツンと音が鳴った。
落ちたはずみにあかりがミチの目を照らした。
(まぶしい)
と思ったとたんにミチは体を動かした。赤い目玉から意識がはずれたのだ。
ミチはおおいそぎで進一郎に近づくと彼の手をひっぱった。
「進一郎さん、ここを出ましょうっ、いそいでもどりましょうっ」
だが遅かった。
ミチは進一郎の顔をのぞきこんだ。そしてハッとした。
一瞬ミチは気のせいかと思った。ここが暗いから、あの目玉のせいで気が動転しているから、自分の目がおかしくなったから、そんな考えが、一瞬でミチの頭のなかをかけめぐった。
進一郎の肌がおかしい。
その瞬間、ミチの目には進一郎の顔にいくつもの赤いアザが浮かびあがったように見えた。
ミチは自分の手でふれている進一郎の手を見た。
手もおなじだ。まだらに赤い。その赤みが消えたかと思うとまた浮かび上がった。赤くなったり肌色にもどったりと落ち着きなく色が変化している。
だめだ、とミチは思った。だめだもうだめだ――そう思ってさらに血の気が引いていく。
ミチの冷えた指先が何かのぬくもりを感じた。
進一郎の手だった。
そのぬくもりを感じたとたん、ミチはもう一方の手で自分の額を乱暴にぬぐった。
なにも考えなかった。どうしてそうしたのかミチ自身にもわからなかった。
ミチはどなった。
「こっちだ!」
そして床を見おろした。
赤い目玉が今度こそミチの姿をとらえたようだった。目玉とミチの視線がぶつかりあった。ミチは目玉の視線からおどろきを感じた。もしかしてそれはミチの気のせいかもしれない。
でもとにかくミチは目玉をにらみつけた。
自分が涙目になっているのをミチは感じた。それでもだ。
「君は、き、君なんかっ、ぼくはこ、こわく、なっ」
こわくない、と言おうとして、だけどその言葉はミチの口から出てこなかった。
嘘だからだ。ミチはこわかった。すごくこわかったのだ。はったりを口にすることにミチは慣れていなかった。(でも)とミチは思った。
ふるえる声がミチの口から出た。
「なんだよ、君は、ぼくは、君なんか、君はっ」
自分で自分がなにを言いたいのかミチにもさっぱりわからなかった。
このあとにどんな言葉をつづければいいのか見当がつかない。
それでもただ勢いだけにまかせて、ミチは無茶苦茶に言葉をしぼりだした。
「君は、ただのアヤのくせに!」
そのとたん、四方を岩に囲まれたその場の空気が変化した。
大きな赤い目玉がまるで火を吹くように熱を発した。
怒っている、とミチは感じた。
ただ単に怒っているという程度ではない、ミチがこれまで感じたことのないほど、たけり狂った怒りだった。どこかにあるかどうかもわからない、目玉の目玉じゃない部分、すごく奥のほうから火山のマグマのように怒りが噴き出てくるのを感じた。
ミチの足がふるえた。立っていられるのがふしぎなくらいだった。
(泣いちゃだめだ)とミチは自分にいいきかせた。なんといっても口から出た言葉をとりけすことなんかできないのだ。
ぼくはこの赤い目にケンカを売ったんだ、とミチは思った。
そんなことをしたのは生まれてはじめてだった。不慣れにもほどがあるがそれでもミチは(ケンカをするなら負けちゃだめだ)とさらに自分にいいきかせた。
とはいえミチはブルブルふるえている。だけどどうにかして手に力をこめた。
ふるえる手がにぎりこぶしを作った。
ミチはその手の甲がよごれていることに気づいた。
(まじないの跡だ。津江さんがつけたやつ)
額をぬぐって手にうつった赤い粉だ、そう気づいたとき――ミチはにぎりこぶしを赤い目玉に向かってつきだした。
そのとたんに空気が変化した。
おそろしいほどに噴き出ていた怒りがほんの少しだけゆらいだ。
わずかにだが、目玉はまるでとまどったような気配を出した。
それでミチは少しだけ楽になることができた。そして楽になったからこそ思った。
(もう無理、これ以上は無理、ぜったい無理!)
ミチはぐいっと進一郎の手を引いて走り出した。進一郎は逆らわなかった。
ランタンを置いたまま、懐中電灯も落としたまま、むしろそのあかりから逃れて身をかくすようにして、二人は走った。すぐにミチの息が切れた。心臓がドキドキと早いリズムで鳴った。のどのあたりが乾いた。胸ものども痛んだ。
床に描かれた赤い目玉も、壁の大牛や黄色い鳥の群れも、ぜんぶ放り出して二人は走った。
あかりから遠ざかるとすぐに辺り一帯が暗やみでおおわれたが、ミチはそのことをこわいとは思わなかった。さっきの噴出した怒りに比べたら、暗やみはこわいうちに入らなかった。
ミチの目から涙があふれた。
逃げ出せることができたと思ったとたんに目から涙が勝手にあふれたのだ。
でも、逃れることなんかできなかったのだ。
息を切らして走る時間がミチにはおそろしく長かった。
このまま暗やみが終わらないのかと感じたころ、行く手にあかりが見えた。
書庫のあかりだ。ミチはホッとした。安心が胸のあたりからせりあがってきた。
ミチは足の速度をゆるめた。
「よかった、あと少しです、進一郎さん」
ミチは横にならぶ進一郎の顔を見あげた。
でも進一郎はミチを見ていなかった。ミチの向こう、書庫のあかりを見ていた。
進一郎につられてミチも視線を移動した。
そして気づいた。
ちいさな人影があかりの一部をさえぎっていた。
声がした。
「にいさん」
ミチはドキッとした。ほんの少しだけ舌足らずな、子どもの声だった。
進一郎が声をあげた。
「聖」
ミチはその人影と進一郎の顔を交互に見比べた。
ミチの視線に気づいた進一郎が、ひとこと、
「弟だ」
と説明した。
目は進一郎を見ていた。
そして進一郎もその目の絵を見つめていた。
「だめです進一郎さん、だめだ、見ちゃいけない!」
ミチは声をあげた。
声はのどに引っかかるようにしてつまった。口から出たときにはかすれていた。
ミチは叫んだつもりだったが、実際にはまるでささやくような頼りない声になってしまった。
だけどその場を囲んだ大きな切り石たちがミチの声を逃さなかった。
石に声が反響した。
そしてその声に反応したのは、進一郎ではなかった。
床に描かれた目玉がぎょろりと動いた。
ミチはゾッとした。一瞬で肌がフツフツフツと粟立った。
(目が動いた。絵なのに動いた。いやちがう、あれは絵じゃない――アヤだ。
あれが津江さんのいうアヤなんだ)
だれに教えられたわけでもないのに、ミチはそう思った。
目玉が左右にゆっくりと動いた。
まるで、なにかを探るようだった。
ミチは体をかたくし息をのんで目玉を見つめたが、目玉の視線はミチを素通りしていく。ミチは気づいた。
(ぼくが見えていないんだ。もしかして津江さんの『まじない』のせいかも)
だからといって安心する気持ちはまったくわいてこなかった。体が緊張ですっかり冷えきった。視線が赤い目玉にはりついて離れない。こわくて仕方がないのに、目を離すことができないのだ。
(動け、ぼくの体。動け、動いてくれ!)
ミチの額に汗がにじんだ。背中にもだ。でも暑いわけじゃない。その逆だ。
緊張で冷えた体が汗でいっそう冷たくなった。背中もおなかも指先も冷たい。
こわくてこわくてたまらない。冷えたミチの指先から力が抜けた。
そしてそのためにことが動いた。
懐中電灯がミチの指先からはなれた。
あ、と思う間に床に落ちてカツンと音が鳴った。
落ちたはずみにあかりがミチの目を照らした。
(まぶしい)
と思ったとたんにミチは体を動かした。赤い目玉から意識がはずれたのだ。
ミチはおおいそぎで進一郎に近づくと彼の手をひっぱった。
「進一郎さん、ここを出ましょうっ、いそいでもどりましょうっ」
だが遅かった。
ミチは進一郎の顔をのぞきこんだ。そしてハッとした。
一瞬ミチは気のせいかと思った。ここが暗いから、あの目玉のせいで気が動転しているから、自分の目がおかしくなったから、そんな考えが、一瞬でミチの頭のなかをかけめぐった。
進一郎の肌がおかしい。
その瞬間、ミチの目には進一郎の顔にいくつもの赤いアザが浮かびあがったように見えた。
ミチは自分の手でふれている進一郎の手を見た。
手もおなじだ。まだらに赤い。その赤みが消えたかと思うとまた浮かび上がった。赤くなったり肌色にもどったりと落ち着きなく色が変化している。
だめだ、とミチは思った。だめだもうだめだ――そう思ってさらに血の気が引いていく。
ミチの冷えた指先が何かのぬくもりを感じた。
進一郎の手だった。
そのぬくもりを感じたとたん、ミチはもう一方の手で自分の額を乱暴にぬぐった。
なにも考えなかった。どうしてそうしたのかミチ自身にもわからなかった。
ミチはどなった。
「こっちだ!」
そして床を見おろした。
赤い目玉が今度こそミチの姿をとらえたようだった。目玉とミチの視線がぶつかりあった。ミチは目玉の視線からおどろきを感じた。もしかしてそれはミチの気のせいかもしれない。
でもとにかくミチは目玉をにらみつけた。
自分が涙目になっているのをミチは感じた。それでもだ。
「君は、き、君なんかっ、ぼくはこ、こわく、なっ」
こわくない、と言おうとして、だけどその言葉はミチの口から出てこなかった。
嘘だからだ。ミチはこわかった。すごくこわかったのだ。はったりを口にすることにミチは慣れていなかった。(でも)とミチは思った。
ふるえる声がミチの口から出た。
「なんだよ、君は、ぼくは、君なんか、君はっ」
自分で自分がなにを言いたいのかミチにもさっぱりわからなかった。
このあとにどんな言葉をつづければいいのか見当がつかない。
それでもただ勢いだけにまかせて、ミチは無茶苦茶に言葉をしぼりだした。
「君は、ただのアヤのくせに!」
そのとたん、四方を岩に囲まれたその場の空気が変化した。
大きな赤い目玉がまるで火を吹くように熱を発した。
怒っている、とミチは感じた。
ただ単に怒っているという程度ではない、ミチがこれまで感じたことのないほど、たけり狂った怒りだった。どこかにあるかどうかもわからない、目玉の目玉じゃない部分、すごく奥のほうから火山のマグマのように怒りが噴き出てくるのを感じた。
ミチの足がふるえた。立っていられるのがふしぎなくらいだった。
(泣いちゃだめだ)とミチは自分にいいきかせた。なんといっても口から出た言葉をとりけすことなんかできないのだ。
ぼくはこの赤い目にケンカを売ったんだ、とミチは思った。
そんなことをしたのは生まれてはじめてだった。不慣れにもほどがあるがそれでもミチは(ケンカをするなら負けちゃだめだ)とさらに自分にいいきかせた。
とはいえミチはブルブルふるえている。だけどどうにかして手に力をこめた。
ふるえる手がにぎりこぶしを作った。
ミチはその手の甲がよごれていることに気づいた。
(まじないの跡だ。津江さんがつけたやつ)
額をぬぐって手にうつった赤い粉だ、そう気づいたとき――ミチはにぎりこぶしを赤い目玉に向かってつきだした。
そのとたんに空気が変化した。
おそろしいほどに噴き出ていた怒りがほんの少しだけゆらいだ。
わずかにだが、目玉はまるでとまどったような気配を出した。
それでミチは少しだけ楽になることができた。そして楽になったからこそ思った。
(もう無理、これ以上は無理、ぜったい無理!)
ミチはぐいっと進一郎の手を引いて走り出した。進一郎は逆らわなかった。
ランタンを置いたまま、懐中電灯も落としたまま、むしろそのあかりから逃れて身をかくすようにして、二人は走った。すぐにミチの息が切れた。心臓がドキドキと早いリズムで鳴った。のどのあたりが乾いた。胸ものども痛んだ。
床に描かれた赤い目玉も、壁の大牛や黄色い鳥の群れも、ぜんぶ放り出して二人は走った。
あかりから遠ざかるとすぐに辺り一帯が暗やみでおおわれたが、ミチはそのことをこわいとは思わなかった。さっきの噴出した怒りに比べたら、暗やみはこわいうちに入らなかった。
ミチの目から涙があふれた。
逃げ出せることができたと思ったとたんに目から涙が勝手にあふれたのだ。
でも、逃れることなんかできなかったのだ。
息を切らして走る時間がミチにはおそろしく長かった。
このまま暗やみが終わらないのかと感じたころ、行く手にあかりが見えた。
書庫のあかりだ。ミチはホッとした。安心が胸のあたりからせりあがってきた。
ミチは足の速度をゆるめた。
「よかった、あと少しです、進一郎さん」
ミチは横にならぶ進一郎の顔を見あげた。
でも進一郎はミチを見ていなかった。ミチの向こう、書庫のあかりを見ていた。
進一郎につられてミチも視線を移動した。
そして気づいた。
ちいさな人影があかりの一部をさえぎっていた。
声がした。
「にいさん」
ミチはドキッとした。ほんの少しだけ舌足らずな、子どもの声だった。
進一郎が声をあげた。
「聖」
ミチはその人影と進一郎の顔を交互に見比べた。
ミチの視線に気づいた進一郎が、ひとこと、
「弟だ」
と説明した。
0
あなたにおすすめの小説

生贄姫の末路 【完結】
松林ナオ
児童書・童話
水の豊かな国の王様と魔物は、はるか昔にある契約を交わしました。
それは、姫を生贄に捧げる代わりに国へ繁栄をもたらすというものです。
水の豊かな国には双子のお姫様がいます。
ひとりは金色の髪をもつ、活発で愛らしい金のお姫様。
もうひとりは銀色の髪をもつ、表情が乏しく物静かな銀のお姫様。
王様が生贄に選んだのは、銀のお姫様でした。

星降る夜に落ちた子
千東風子
児童書・童話
あたしは、いらなかった?
ねえ、お父さん、お母さん。
ずっと心で泣いている女の子がいました。
名前は世羅。
いつもいつも弟ばかり。
何か買うのも出かけるのも、弟の言うことを聞いて。
ハイキングなんて、来たくなかった!
世羅が怒りながら歩いていると、急に体が浮きました。足を滑らせたのです。その先は、とても急な坂。
世羅は滑るように落ち、気を失いました。
そして、目が覚めたらそこは。
住んでいた所とはまるで違う、見知らぬ世界だったのです。
気が強いけれど寂しがり屋の女の子と、ワケ有りでいつも諦めることに慣れてしまった綺麗な男の子。
二人がお互いの心に寄り添い、成長するお話です。
全年齢ですが、けがをしたり、命を狙われたりする描写と「死」の表現があります。
苦手な方は回れ右をお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
私が子どもの頃から温めてきたお話のひとつで、小説家になろうの冬の童話際2022に参加した作品です。
石河 翠さまが開催されている個人アワード『石河翠プレゼンツ勝手に冬童話大賞2022』で大賞をいただきまして、イラストはその副賞に相内 充希さまよりいただいたファンアートです。ありがとうございます(^-^)!
こちらは他サイトにも掲載しています。


アリアさんの幽閉教室
柚月しずく
児童書・童話
この学校には、ある噂が広まっていた。
「黒い手紙が届いたら、それはアリアさんからの招待状」
招かれた人は、夜の学校に閉じ込められて「恐怖の時間」を過ごすことになる……と。
招待状を受け取った人は、アリアさんから絶対に逃れられないらしい。
『恋の以心伝心ゲーム』
私たちならこんなの楽勝!
夜の学校に閉じ込められた杏樹と星七くん。
アリアさんによって開催されたのは以心伝心ゲーム。
心が通じ合っていれば簡単なはずなのに、なぜかうまくいかなくて……??
『呪いの人形』
この人形、何度捨てても戻ってくる
体調が悪くなった陽菜は、原因が突然現れた人形のせいではないかと疑いはじめる。
人形の存在が恐ろしくなって捨てることにするが、ソレはまた家に現れた。
陽菜にずっと付き纏う理由とは――。
『恐怖の鬼ごっこ』
アリアさんに招待されたのは、美亜、梨々花、優斗。小さい頃から一緒にいる幼馴染の3人。
突如アリアさんに捕まってはいけない鬼ごっこがはじまるが、美亜が置いて行かれてしまう。
仲良し3人組の幼馴染に一体何があったのか。生き残るのは一体誰――?
『招かれざる人』
新聞部の七緒は、アリアさんの記事を書こうと自ら夜の学校に忍び込む。
アリアさんが見つからず意気消沈する中、代わりに現れたのは同じ新聞部の萌香だった。
強がっていたが、夜の学校に一人でいるのが怖かった七緒はホッと安心する。
しかしそこで待ち受けていたのは、予想しない出来事だった――。
ゾクッと怖くて、ハラハラドキドキ。
最後には、ゾッとするどんでん返しがあなたを待っている。

14歳で定年ってマジ!? 世界を変えた少年漫画家、再起のノート
谷川 雅
児童書・童話
この世界、子どもがエリート。
“スーパーチャイルド制度”によって、能力のピークは12歳。
そして14歳で、まさかの《定年》。
6歳の星野幸弘は、将来の夢「世界を笑顔にする漫画家」を目指して全力疾走する。
だけど、定年まで残された時間はわずか8年……!
――そして14歳。夢は叶わぬまま、制度に押し流されるように“退場”を迎える。
だが、そんな幸弘の前に現れたのは、
「まちがえた人間」のノートが集まる、不思議な図書室だった。
これは、間違えたままじゃ終われなかった少年たちの“再スタート”の物語。
描けなかった物語の“つづき”は、きっと君の手の中にある。
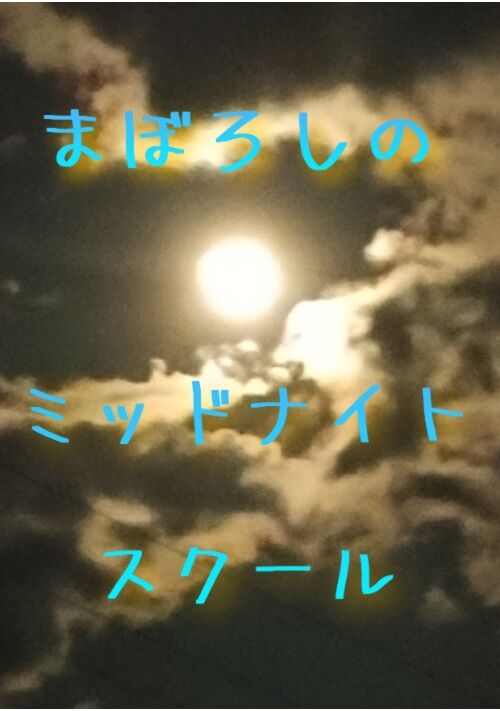
まぼろしのミッドナイトスクール
木野もくば
児童書・童話
深夜0時ちょうどに突然あらわれる不思議な学校。そこには、不思議な先生と生徒たちがいました。飼い猫との最後に後悔がある青年……。深い森の中で道に迷う少女……。人間に恋をした水の神さま……。それぞれの道に迷い、そして誰かと誰かの想いがつながったとき、暗闇の空に光る星くずの方から学校のチャイムが鳴り響いてくるのでした。

『異世界庭付き一戸建て』を相続した仲良し兄妹は今までの不幸にサヨナラしてスローライフを満喫できる、はず?
釈 余白(しやく)
児童書・童話
毒親の父が不慮の事故で死亡したことで最後の肉親を失い、残された高校生の小村雷人(こむら らいと)と小学生の真琴(まこと)の兄妹が聞かされたのは、父が家を担保に金を借りていたという絶望の事実だった。慣れ親しんだ自宅から早々の退去が必要となった二人は家の中で金目の物を探す。
その結果見つかったのは、僅かな現金に空の預金通帳といくつかの宝飾品、そして家の権利書と見知らぬ文字で書かれた書類くらいだった。謎の書類には祖父のサインが記されていたが内容は読めず、頼みの綱は挟まれていた弁護士の名刺だけだ。
最後の希望とも言える名刺の電話番号へ連絡した二人は、やってきた弁護士から契約書の内容を聞かされ唖然とする。それは祖父が遺産として残した『異世界トラス』にある土地と建物を孫へ渡すというものだった。もちろん現地へ行かなければ遺産は受け取れないが。兄妹には他に頼れるものがなく、思い切って異世界へと赴き新生活をスタートさせるのだった。
連載時、HOT 1位ありがとうございました!
その他、多数投稿しています。
こちらもよろしくお願いします!
https://www.alphapolis.co.jp/author/detail/398438394

ナナの初めてのお料理
いぬぬっこ
児童書・童話
ナナは七歳の女の子。
ある日、ナナはお母さんが仕事から帰ってくるのを待っていました。
けれど、お母さんが帰ってくる前に、ナナのお腹はペコペコになってしまいました。
もう我慢できそうにありません。
だというのに、冷蔵庫の中には、すぐ食べれるものがありません。
ーーそうだ、お母さんのマネをして、自分で作ろう!
ナナは、初めて自分一人で料理をすることを決めたのでした。
これは、ある日のナナのお留守番の様子です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















