4 / 9
- 肆 -
思いがけない寵
しおりを挟む
次の日の夜も、綉葩は寝所へと呼ばれた。
続けてなど、初めてのことだった。
「綉葩さまは近頃いっそう美しくなられましたから」
筆頭侍女の黄汐諾が誇らしそうに言う。
「皇上もお気づきになられたのでしょう」
後宮でもかなり古参の女官だが、この国の習慣に不慣れな綉葩の教育係兼お目付け役として、側仕えに抜擢された中年の女性だ。
つまりは、綉葩自身の望みや幸せを思って、喜んでいるわけではない。
辺境から来た田舎者を、皇帝が気に入るほどの女性に仕込めたとあれば、己の評判があがる。
それが嬉しいのだ。
「美しく……?」
誉め言葉にぴんとこない綉葩が鸚鵡返しに訊くと、頷いた。
「愛されることで、女性としての華がお開きになられたのでしょう。肌をよりお磨きになられるよう、新しい薬湯を調合させましょう」
あの爺のために肌を磨くなど……と言いかけ、やめた。
もしも薄衣で隔てていたとしても、皮膚の感触を煕佑が感じてくれているのなら。
心地よい肌触りを彼に与えるためなら、そうするのも悪くないように思えた。
それから一週間、寝所へと呼ばれ続けた。
つまり、煕佑とも毎日会うことができた。
「今日はずいぶん、お顔の色がいいようだ」
トン、トン。
「いつもこんな風に、お身体の調子が良ければいいのになあ」
トン、トン。
「皇上もさぞかしお喜びだろう」
スゥ。
そんな他愛もないやり取りが繰り返される時間が来ることを、いつしか綉葩は何時間も前から楽しみにするようになった。
しかしそうなってくると反面、続く後の時間がいよいよ苦痛になってきた。
長い夜のあいだ執拗に弄ばれ、くたくたになった身体で、迎えに来た煕佑に身体を預けるとこには、自分の汚れを彼に押しつけているような気にさえなった。
煕佑でさえ、疲れ切った様子の綉葩を気遣ってか、そのときには独り言さえ口にしないほどだ。
食はどんどん細くなり、椅子に座っているだけでも疲れるようになった。
結局、薄暗い寝室にこもりきりになり、ほとんどの時間を横になって過ごすようになった。
寝台の枕元のすぐ脇には、小さな透かし窓があった。
硝子の代わりに、精巧な葉の透かし彫りの木枠が全面に施された窓は、その隙間から庭が見えるようになっている。
それが手の込んだ物なのはわかるが、今の綉葩には、この狭まった世界の象徴であるようにしか思えない。
夢に見るのは故郷の広い空。満天の星。砂漠から吹く乾いた風。
せめてこの窓の向こう、庭を歩くことができたなら。
自分の動きがままならないことを、綉葩はますます気に病むようになっていた。
弱っていることが伝わったのか、皇帝からの夜伽の要請はぴたりと止んだ。
つまり煕佑にも、会えなくなった。
綉葩の心はいよいよ内に籠り、身体は骨が浮くようになった。侍女たちなど、死期が近いのではないかと囁き合う始末だ。
そんな折だった。
真夜中、誰もが寝静まった時間。
窓の向こうから、かすかな声が聞こえた。
「綉葩さま」
煕佑の声だった。
綉葩は飛び起きた。
隣の部屋に控えている女官たちに気づかれてはならないと、声は出さず、窓の木枠を指先で二度叩く。
トン、トン。
すると彫物の隙間から、小さな紙片が差し込まれた。
受け取り、月明かりを頼りに見てみると、そこには蝶の絵が筆で描かれている。
「特別な調合の墨で描かれた蝶です。それに一滴だけ血を垂らして染み込ませると、わずかのあいだではありますが、魂が蝶に化けます」
囁く声が、窓の外から聞こえる。
「蝶に……?」
「賢帝と誉れ高かった、古のとある皇帝が、ある日夢で蝶になったという伝承があります。それにちなんで、『翅の夢』と呼ばれている咒です」
「咒……」
思いがけない提案に、惹かれるよりも戸惑いのほうが先にきた。
「誰にも、言ってはなりません。私の出身地の一部の人々だけに伝わる、秘術ですので」
用心深く、そう言い添える声。
それほどまでのものを渡してくれることに戸惑い、思わず訊いてしまった。
「なぜ、私に……?」
「綉葩さまがご自分で動いて出歩きたがっていると、私にはわかります。もしもお心からくる病ならば、気晴らしがあれば、またお元気になられるかと」
「そう、ありがとう」
綉葩の目に、涙が滲む。
この宮では、誰も、自分の心を気遣ってくれる者はいなかった。
女官たちは一見、優しく礼儀正しく心配してくれているように見える。
しかしその本音といえば、ただ皇帝お気に入りの玩具が壊れないか、飽きられることで自分たちの立場が悪くはならないか、そういったことを気にしているだけだった。
だが、煕佑は違う。
それが今、はっきりとわかった。
「では私は、誰かに見つからないうちに戻ります」
綉葩の状態に気づいているのかいないのか、そっと声が呟き、窓のすぐ外にあった気配が遠ざかっていくのを感じる。
煕佑の言葉をそのまま信じるのは難しい。
ただ、声が聞けただけでも嬉しかった。
綉葩は乗り出していた身体をまた戻し、手にした紙を改めて広げてみた。
窓からはわずかな月の光が射しこんでいる。
それを頼りに、描かれている複雑な文様の翅をした蝶の絵を、じっくりと眺めた。
続けてなど、初めてのことだった。
「綉葩さまは近頃いっそう美しくなられましたから」
筆頭侍女の黄汐諾が誇らしそうに言う。
「皇上もお気づきになられたのでしょう」
後宮でもかなり古参の女官だが、この国の習慣に不慣れな綉葩の教育係兼お目付け役として、側仕えに抜擢された中年の女性だ。
つまりは、綉葩自身の望みや幸せを思って、喜んでいるわけではない。
辺境から来た田舎者を、皇帝が気に入るほどの女性に仕込めたとあれば、己の評判があがる。
それが嬉しいのだ。
「美しく……?」
誉め言葉にぴんとこない綉葩が鸚鵡返しに訊くと、頷いた。
「愛されることで、女性としての華がお開きになられたのでしょう。肌をよりお磨きになられるよう、新しい薬湯を調合させましょう」
あの爺のために肌を磨くなど……と言いかけ、やめた。
もしも薄衣で隔てていたとしても、皮膚の感触を煕佑が感じてくれているのなら。
心地よい肌触りを彼に与えるためなら、そうするのも悪くないように思えた。
それから一週間、寝所へと呼ばれ続けた。
つまり、煕佑とも毎日会うことができた。
「今日はずいぶん、お顔の色がいいようだ」
トン、トン。
「いつもこんな風に、お身体の調子が良ければいいのになあ」
トン、トン。
「皇上もさぞかしお喜びだろう」
スゥ。
そんな他愛もないやり取りが繰り返される時間が来ることを、いつしか綉葩は何時間も前から楽しみにするようになった。
しかしそうなってくると反面、続く後の時間がいよいよ苦痛になってきた。
長い夜のあいだ執拗に弄ばれ、くたくたになった身体で、迎えに来た煕佑に身体を預けるとこには、自分の汚れを彼に押しつけているような気にさえなった。
煕佑でさえ、疲れ切った様子の綉葩を気遣ってか、そのときには独り言さえ口にしないほどだ。
食はどんどん細くなり、椅子に座っているだけでも疲れるようになった。
結局、薄暗い寝室にこもりきりになり、ほとんどの時間を横になって過ごすようになった。
寝台の枕元のすぐ脇には、小さな透かし窓があった。
硝子の代わりに、精巧な葉の透かし彫りの木枠が全面に施された窓は、その隙間から庭が見えるようになっている。
それが手の込んだ物なのはわかるが、今の綉葩には、この狭まった世界の象徴であるようにしか思えない。
夢に見るのは故郷の広い空。満天の星。砂漠から吹く乾いた風。
せめてこの窓の向こう、庭を歩くことができたなら。
自分の動きがままならないことを、綉葩はますます気に病むようになっていた。
弱っていることが伝わったのか、皇帝からの夜伽の要請はぴたりと止んだ。
つまり煕佑にも、会えなくなった。
綉葩の心はいよいよ内に籠り、身体は骨が浮くようになった。侍女たちなど、死期が近いのではないかと囁き合う始末だ。
そんな折だった。
真夜中、誰もが寝静まった時間。
窓の向こうから、かすかな声が聞こえた。
「綉葩さま」
煕佑の声だった。
綉葩は飛び起きた。
隣の部屋に控えている女官たちに気づかれてはならないと、声は出さず、窓の木枠を指先で二度叩く。
トン、トン。
すると彫物の隙間から、小さな紙片が差し込まれた。
受け取り、月明かりを頼りに見てみると、そこには蝶の絵が筆で描かれている。
「特別な調合の墨で描かれた蝶です。それに一滴だけ血を垂らして染み込ませると、わずかのあいだではありますが、魂が蝶に化けます」
囁く声が、窓の外から聞こえる。
「蝶に……?」
「賢帝と誉れ高かった、古のとある皇帝が、ある日夢で蝶になったという伝承があります。それにちなんで、『翅の夢』と呼ばれている咒です」
「咒……」
思いがけない提案に、惹かれるよりも戸惑いのほうが先にきた。
「誰にも、言ってはなりません。私の出身地の一部の人々だけに伝わる、秘術ですので」
用心深く、そう言い添える声。
それほどまでのものを渡してくれることに戸惑い、思わず訊いてしまった。
「なぜ、私に……?」
「綉葩さまがご自分で動いて出歩きたがっていると、私にはわかります。もしもお心からくる病ならば、気晴らしがあれば、またお元気になられるかと」
「そう、ありがとう」
綉葩の目に、涙が滲む。
この宮では、誰も、自分の心を気遣ってくれる者はいなかった。
女官たちは一見、優しく礼儀正しく心配してくれているように見える。
しかしその本音といえば、ただ皇帝お気に入りの玩具が壊れないか、飽きられることで自分たちの立場が悪くはならないか、そういったことを気にしているだけだった。
だが、煕佑は違う。
それが今、はっきりとわかった。
「では私は、誰かに見つからないうちに戻ります」
綉葩の状態に気づいているのかいないのか、そっと声が呟き、窓のすぐ外にあった気配が遠ざかっていくのを感じる。
煕佑の言葉をそのまま信じるのは難しい。
ただ、声が聞けただけでも嬉しかった。
綉葩は乗り出していた身体をまた戻し、手にした紙を改めて広げてみた。
窓からはわずかな月の光が射しこんでいる。
それを頼りに、描かれている複雑な文様の翅をした蝶の絵を、じっくりと眺めた。
0
あなたにおすすめの小説

冤罪で辺境に幽閉された第4王子
satomi
ファンタジー
主人公・アンドリュート=ラルラは冤罪で辺境に幽閉されることになったわけだが…。
「辺境に幽閉とは、辺境で生きている人間を何だと思っているんだ!辺境は不要な人間を送る場所じゃない!」と、辺境伯は怒っているし当然のことだろう。元から辺境で暮している方々は決して不要な方ではないし、‘辺境に幽閉’というのはなんとも辺境に暮らしている方々にしてみれば、喧嘩売ってんの?となる。
辺境伯の娘さんと婚約という話だから辺境伯の主人公へのあたりも結構なものだけど、娘さんは美人だから万事OK。

愛人を選んだ夫を捨てたら、元婚約者の公爵に捕まりました
由香
恋愛
伯爵夫人リュシエンヌは、夫が公然と愛人を囲う結婚生活を送っていた。
尽くしても感謝されず、妻としての役割だけを求められる日々。
けれど彼女は、泣きわめくことも縋ることもなく、静かに離婚を選ぶ。
そうして“捨てられた妻”になったはずの彼女の前に現れたのは、かつて婚約していた元婚約者――冷静沈着で有能な公爵セドリックだった。
再会とともに始まるのは、彼女の価値を正しく理解し、決して手放さない男による溺愛の日々。
一方、彼女を失った元夫は、妻が担っていたすべてを失い、社会的にも転落していく。
“尽くすだけの妻”から、“選ばれ、守られる女性”へ。
静かに離婚しただけなのに、
なぜか元婚約者の公爵に捕まりました。

元公爵令嬢は年下騎士たちに「用済みのおばさん」と捨てられる 〜今更戻ってこいと泣きつかれても献身的な美少年に溺愛されているのでもう遅いです〜
日々埋没。
ファンタジー
「新しい従者を雇うことにした。おばさんはもう用済みだ。今すぐ消えてくれ」
かつて婚約破棄され、実家を追放された元公爵令嬢のレアーヌ。
その身分を隠し、年下の冒険者たちの身の回りを世話する『メイド』として献身的に尽くしてきた彼女に突きつけられたのは、あまりに非情な追放宣告だった。
レアーヌがこれまで教育し、支えてきた若い男たちは、新しく現れた他人の物を欲しがり子悪魔メイドに骨抜きにされ、彼女を「加齢臭のする汚いおばさん」と蔑み、笑いながら追い出したのだ。
地位も、居場所も、信じていた絆も……すべてを失い、絶望する彼女の前に現れたのは、一人の美少年だった。
「僕とパーティーを組んでくれませんか? 貴方が必要なんです」
新米ながら将来の可能性を感じさせる彼は、レアーヌを「おばさん」ではなく「一人の女性」として、甘く狂おしく溺愛し始める。
一方でレアーヌという『真の支柱』を失った元パーティーは、自分たちがどれほど愚かな選択をしたかを知る由もなかった。
やがて彼らが地獄の淵で「戻ってきてくれ」と泣きついてきても、もう遅い。
レアーヌの隣には、彼女を離さないと誓った執着愛の化身が微笑んでいるのだから。

人間嫌いの狐王に、契約妻として嫁いだら溺愛が止まりません
由香
ファンタジー
人間嫌いで知られる狐族の王・玄耀に、“契約上の妻”として嫁いだ少女・紗夜。
「感情は不要。契約が終われば離縁だ」
そう告げられたはずなのに、共に暮らすうち、冷酷な王は彼女だけに甘さを隠さなくなっていく。
やがて結ばれる“番”の契約、そして王妃宣言――。
契約結婚から始まる、人外王の溺愛が止まらない和風あやかし恋愛譚。


どうやらお前、死んだらしいぞ? ~変わり者令嬢は父親に報復する~
野菜ばたけ@既刊5冊📚好評発売中!
ファンタジー
「ビクティー・シークランドは、どうやら死んでしまったらしいぞ?」
「はぁ? 殿下、アンタついに頭沸いた?」
私は思わずそう言った。
だって仕方がないじゃない、普通にビックリしたんだから。
***
私、ビクティー・シークランドは少し変わった令嬢だ。
お世辞にも淑女然としているとは言えず、男が好む政治事に興味を持ってる。
だから父からも煙たがられているのは自覚があった。
しかしある日、殺されそうになった事で彼女は決める。
「必ず仕返ししてやろう」って。
そんな令嬢の人望と理性に支えられた大勝負をご覧あれ。

遡ったのは君だけじゃない。離縁状を置いて出ていった妻ーー始まりは、そこからだった。
沼野 花
恋愛
私は、夫にも子供にも選ばれなかった。
その事実だけを抱え、離縁を突きつけ、家を出た。
そこで待っていたのは、最悪の出来事――
けれど同時に、人生の扉がひらく瞬間でもあった。
夫は愛人と共に好きに生きればいい。
今さら「本当に愛していたのは君だ」と言われても、裏切ったあなたを許すことはできない。
でも、子供たちの心だけは、必ず取り戻す。
妻にも母にもなれなかった伯爵夫人イネス。
過去を悔いながらも、愛を手に入れることを決めた彼女が辿り着いた先には――
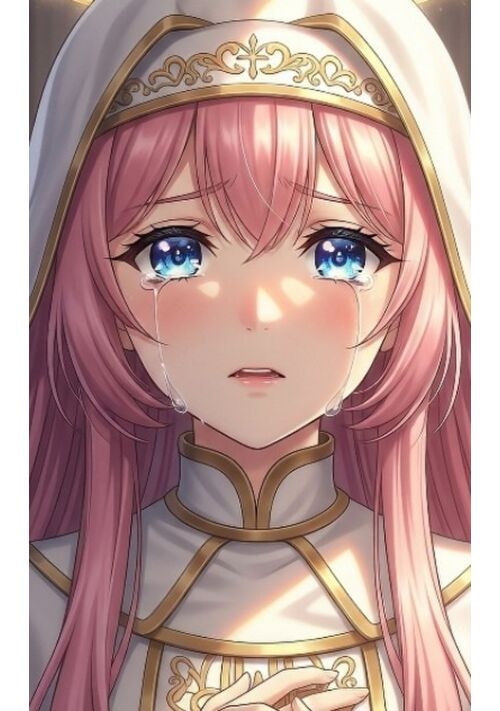
聖女は聞いてしまった
夕景あき
ファンタジー
「道具に心は不要だ」
父である国王に、そう言われて育った聖女。
彼女の周囲には、彼女を心を持つ人間として扱う人は、ほとんどいなくなっていた。
聖女自身も、自分の心の動きを無視して、聖女という治癒道具になりきり何も考えず、言われた事をただやり、ただ生きているだけの日々を過ごしていた。
そんな日々が10年過ぎた後、勇者と賢者と魔法使いと共に聖女は魔王討伐の旅に出ることになる。
旅の中で心をとり戻し、勇者に恋をする聖女。
しかし、勇者の本音を聞いてしまった聖女は絶望するのだった·····。
ネガティブ思考系聖女の恋愛ストーリー!
※ハッピーエンドなので、安心してお読みください!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















