10 / 22
<9>
しおりを挟む
変化と言うものは、一朝一夕に表れるものではない。
アルフォンス様と手合わせをしてから、私は一日に少なくとも一度は、アルフォンス様を強制的に私との『遊び』に付き合わせている。
一日のスケジュールは、学校のようにきちんと時間割が決められており、その通りに行動していれば休憩時間を取れる筈なのに、何故だか、アルフォンス様には自由時間が全くない。
朝食を食べながら予習をし、朝のお茶の時間は単なる水分補給、昼食も手づかみで食べられるようにサンドウィッチが中心で、昼のお茶の時間は午前同様。
晩餐だけは、ご家族と時間が合えば共に召し上がるので、比較的きちんと取っているけれど、毎日と言うわけにはいかない。
授業と授業の間に休憩時間を三十分から一時間取ってあるにも関わらず、これだ。
これはひとえに、アルフォンス様の真面目で熱心な授業態度に教師陣が過熱して、きちんと時間通りに授業を終えないせいである。
いや、彼等の中に、邪なものが全くない、とは言い切れないか。
自分の教える科目こそ最も得意として欲しい、優秀な教師と慕って欲しい、と言う欲があるのを感じられる。
「少しだけならいいだろう」、「他の教師もやっているのだから構わないだろう」。
アルフォンス様が全能だからこそ、教師同士の争いになってしまっているのだ。
その為、ずっと部屋の隅に控えている私は、タイミングを見計らって強制突入し、『遊び』と言う名の気分転換と休憩を取って頂いている。
一ヶ月が経過したものの、私の意図する所を理解してくれたらしい教師はまだ一人。
他の人間は、
「侍女風情が何故、アルフォンス殿下の学ばれたいと言う尊いお気持ちを蔑ろにするのか。不敬だぞ」
であるとか、
「アルフォンス殿下こそ、神が遣われし御子。百年に一度の天才の行く手を阻むとは、陛下に訴えるぞ」
であるとか、何とも姦しい。
アルフォンス様の前では、声高に私を非難出来ないので(何しろ、私はアラベラ様直属の特任侍女と言う扱いなわけで)、穴が開きそうな程、鋭い視線で睨まれているだけなのだけれど。
どちらにせよ、夫タカユキや元夫マイルズの嫌味に慣れている私には効きはしない。
他の問題もあると言えばあるけれど、私が無視すればいい話だ。
貴族令嬢として、貴族夫人としての規範を守らねば、と躍起になっていた時期ならば、気になっただろうけれど、貴族社会でどう思われようとどうでもいいと一度開き直ってしまった今は、本当にどうでもいい。
「あぁ、もう、ミカエラ。歴史学、あとちょっとでキリのいい所だったのに」
いつも話の長い歴史学の教師を追い出すと、アルフォンス様は口を僅かに尖らせて、でも、面白そうに、そう言った。
アルフォンス様が、あの教師の歴史豆知識と言う名の無駄話が好きではない事に、私は気づいている。
「そうでしたか。私は歴史が苦手なのですけど、過去は過去なんですから、今日学ぼうと明日学ぼうと、変わらないんじゃないですか?」
「でも、もしかしたら明日、『新事実発見!真実は百八十度違った!』なんて事があるかもしれないだろう?」
「まぁ、じゃあ、今日、お勉強しなくて良かったですね。二度手間になりますもの。私に感謝してくれてもいいんですよ?」
澄ました顔でそう言うと、アルフォンス様は、プッと小さく噴き出した。
最近では、このように声に出して笑ってくださる事が増えた。
いい傾向だ。
「今日は何をして遊びたいの?雨だから、中庭は使えないよ?」
アルフォンス様は飽くまで、私の遊びに付き合っている、と言う体を崩さない。
仕方なく遊んであげてるんだ、と思う事で、自分を許しているのだろう。
剣術の授業は毎日あるわけではないので、運動不足にならないように、私は出来る限り、アルフォンス様を中庭に連れ出していた。
成長期の子供には、適度な運動が必要なのだから。
けれど、昨夜から降り出した雨は、今も続いている。
「そうですねぇ。今日は、こちらのボードゲームはどうでしょう?」
自宅から持って来たボードゲームは、何しろ、私が子供の頃に遊んでいたものだから、古い。
もしも、アルフォンス様の食いつきが良ければ、新しく用意するつもりだ。
「へぇ?初めて見た」
「こちらはですね、戦術シミュレーションゲームです。ノーレイン公爵閣下がお得意だったんですよ」
ダリウス様に憧れているアルフォンス様は、『ノーレイン公爵閣下』の名に、ぐ、と身を乗り出した。
「叔父上が?」
「そうです」
「ミカエラのお父上が叔父上の師範だったとは聞いたけれど、ミカエラも叔父上の知り合いなの?」
「…えぇ、そうですよ」
返答に、一瞬間が空いてしまった事に、アルフォンス様は気づかなかったようだ。
王城で勤め口が見つかった事は、ユリシーズ様に働き口を問い合わせてくださった事へのお礼と共に報告してある。
ダリウス様からは、「王城ならば一先ず安心だが、王族の傍にいる事での危険もある故、くれぐれも気を抜くな」と言う旨のお返事が届いた。
最後にお顔を見てから、四ヶ月。
離婚が決まった事と就職が決まった事だけ連絡させて頂いたけれど、これは成り行き上、必要となった業務連絡であって、友達に送る近況報告とは、種類が違う。
「父がサディアス様には大変お世話になってましたし、剣術の指導についていく事もありましたから」
「あぁ、そうか。…ノーレイン公爵邸なら、友達も呼びやすいね。王城だと、なかなか…」
「呼びたいお友達がいるんですか?」
初耳だ。
アルフォンス様は、ノーレイン公爵家でも家庭教師について学ばれていたから、勝手に、友達はいないのだと思っていた。
「友達、と言うか…友達と言っていいのか判らないのだけれど…」
珍しく小さな声でぽそぽそと話すのを根気強く聞き出した所、ノーレイン公爵家に仕えている執事の子供と、仲良くしていたらしい。
ノーレイン公爵家には複数の執事と、バートと言う家令がいる。
バートは白髪口髭で、ミカの世界の人間なら「セバスチャン」と呼びたくなる人だけれど、彼の事は知っていても、家族構成は把握していない。
執事達も、私が幼い頃とは、代替わりをしているだろう。
執事と言っても、ウェインズ男爵家よりもずっとずっと上の爵位をお持ちの貴族だから、アルフォンス様の友達であっても何の不思議もない。
「ノーレイン公爵家にお勤めの方であれば、安心ですね。アラベラ様に相談してみては?」
ユリシーズ様もアラベラ様もご存知の方のご子息ならば、問題なく呼べる筈だ。
きっと、アラベラ様は、大喜びで手配する。
私のような似非友達ではなく、真の友達なのだろうから。
「…でも…」
だが、アルフォンス様は、暗い顔で押し黙ってしまった。
「でも?」
「…クレイグは、使用人の子だから…僕が仲良くしたら、いけないんだ」
「…なるほど?」
「そ、それに、僕が呼びつけたら、クレイグが僕の事をどう思っていても、仲良くしなくては、と思うだろう?」
そのまま、黙り込んで俯いたアルフォンス様を見て、遥か昔の思い出が蘇る。
ダリウス様も私に対して、
「俺に呼ばれたからって、無理して遊びに来てるわけじゃないよな?」
と、何度か確認していた。
当時は、何も考えずに、
「何で?あに様と遊ぶの楽しいよ?」
と答えていたけれど、爵位の差は、高位のダリウス様達にとっても、大きなものだったのだろう。
「そうですねぇ…私は、クレイグ様に会った事がないので、彼がアルフォンス様の事をどう思っているのか、勝手に推測する事は出来ませんけど。一つだけ、いいですか?」
「な、何?」
「使用人の子供と、アルフォンス様が仲良くしてはいけない理由って何です?」
「それは…僕は王子だから…王子に相応しい相手としか付き合ってはならないから…」
「相応しいかどうかは、何で判るんですか?つまり、アルフォンス様は付き合う友達を、身分で選ぶと言う事ですか?友達になる価値は、身分にあるんですか?」
「…ぅ…」
「サディアス様は、平民だった父と親しくしてくださいました。サディアス様は、間違っていたと言う事ですか?」
「ち、違う!おじい様は間違ってなんかない!おじい様にとって、ウェインズ男爵は英雄だったのだから!」
真っ赤な顔で叫んだアルフォンス様に、微笑みかける。
「ね?身分なんて、友達になるかどうかに関係ないんです。勿論、アルフォンス様は王子様ですから、身の安全を図る為にも、誰彼となく親しくするのは難しい。その判断基準の一つとして、身分を把握する事はいいでしょう。でもね、残念ですけど、貴族ならば皆が聖人なわけじゃありません。そして、平民ならば信用に値しないわけでもありません。最後は、自分の判断に委ねないといけません」
「自分の…判断…」
「例えば私が、『この人、いい人なんで、お友達になってあげてください』と誰かを連れて来たとします。アルフォンス様は、『確かにいい人そうだけど、何かイヤな感じがするんだよな』と思いながらも、私に紹介されたのだからいいだろう…と何がイヤな感じなのか調べる事なく、友達付き合いをします。ところが、その人はいい人の仮面を被った悪者で、アルフォンス様の名を借りて悪行三昧するんです。そんな事が起きたら、アルフォンス様はどうしますか?『紹介したミカエラが悪い!僕は悪くない!』と言いますか?」
アルフォンス様は、「え…」と小さく言うと、考え込んだ。
「何かイヤだ、と思いながらも付き合うと決めたなら…悪いのは、僕だ」
「勿論、悪者だと気づかずに、アルフォンス様に紹介した私が一番悪いんですけどね。誰かを紹介する、って、それ位に大事な事なので、私は『紹介する責任』を負わなくてはいけません。でも、受け入れる、付き合いを続ける、と選択した時点で、アルフォンス様も、責任を負う事になってしまいます」
「そうか…だから、最後は自分の判断、なのだね。自分の責任だと思えば、流されるだけじゃなくて、きちんと、相手が本当にいい人がどうかを考えるから」
「そう言う事です」
本当に、アルフォンス様は聡明だ。
今後、彼の周囲には、虎の威を借る狐達が侍ろうとするだろう。
だからこそ、アルフォンス様には、相手を身分や肩書で判断するのはなく、本質で見るようにして頂かなくては。
「一つ、昔話をしていいですか?」
「うん、何?」
「私はですね、二十三歳で叔母に紹介された男性と結婚しました」
「ミカエラ、結婚していたの?!独身だと言っていたのに」
「まぁまぁ、聞いてください。夫を紹介したのは叔母だし、両親も私の結婚相手を心配していたし、私も適齢期ぎりぎりだったし、これもご縁だろう、と結婚したんです。でも、夫と私は、とことん、性格が合わなかったんですね。だから、全然うまくいかなくて…結局、先日、離縁しました。結婚を決める前に、もっと深く考えるべきだったんです。自分の人生なのに、叔母の顔を立てなきゃ、とか、両親を安心させなきゃ、とか、言い訳をするって事は、人に責任を負わせようとしてるって事でしょう。自分の人生なら、自分で責任を負わないと。私が幸せだと思えないなら、意味がないんです」
アルフォンス様は、その透き通った青い目で、じっと私の顔を見つめた。
「…今、ミカエラは幸せ?」
「えぇ、幸せですよ。大好きなアルフォンス様と、毎日、遊べますから」
大好き、と聞いて、アルフォンス様が少し頬を染めて顔を上げる。
「大好き?ミカエラは、僕の事が大好きなの?」
「当たり前です。アルフォンス様と遊ぶ時間は、私にとって、とても楽しくて充実した時間です。それは、アルフォンス様が王子様だからじゃありません。頭が良くて、剣が強いからでもありません。アルフォンス様が、アルフォンス様だからですよ」
「僕が僕なのは、それこそ、当たり前でしょう?」
「そうですね。つまり、アルフォンス様は、そこにいるだけで私を幸せにしてくれる、って事ですよ」
アルフォンス様は、驚いたように目を大きく見開いた。
「…そこに、いるだけで?」
「はい」
「難しい勉強をしなくても?」
「はい」
「剣で勝てなくても?」
「はい」
「…っでも、僕は王子だから…」
「王子様だって、人間です。怒る時も泣く時もあるでしょう。悩む時だって疲れる時だってあります。愚痴りたい時もサボりたい時もあって当然です。そして、私は怒ろうと泣こうと悩もうと疲れようと愚痴ろうとサボろうと、アルフォンス様が好きですよ」
アルフォンス様は、唇を戦慄かせると、
「は、母上も、そうかな…?」
と尋ねた。
「アラベラ様ですか?勿論です」
「父上は…」
「ユリシーズ様も、ユージェニー様も、勿論ノーレイン公爵閣下も、皆、アルフォンス様が大好きですよ」
ぽろり、と。
アルフォンス様の目から、涙が零れ落ちる。
「臣下に取り乱さないお姿を見せる事は、安心に繋がります。ご立派な事です。けれど、ご家族の前では、いいじゃないですか」
「で、でも、おばあ様が…僕が、いつも王子らしくしていないと、母上が他の人に見くびられる、って…母上に甘えたり、父上に相談したり、そう言う、王子らしくない事をするな、って…」
…おばあ様、って、フェリシア様じゃなくて、エメライン先王妃殿下の事よね…。
フェリシア様が、そんな事を言う筈がない。
アラベラ様からも、確執があるような事は聞いていたけど、ご自分の孫に何て事を吹き込んでくれたのか。
ザラ、と、胸の中に飲み下せない嫌なものが残る。
「ほ、本当は僕、母上ともっと、お話がしたい。小さい頃みたいに、ギュッとして欲しい。でも、でも、おばあ様が、そんな事をすると、母上の迷惑になる、母上に嫌われる、って…。父上にも、頼りない王子じゃ呆れられる、って…」
「…そうですか。先王妃殿下が、そのように仰ったのですね?」
「うん…おばあ様が、ハーヴェイ叔父上は立派な王子様だった、お体が弱くなければ、歴史に残る賢王になった、って……叔父上にお子様がいらしたら、僕なんか足元にも及ばない、ずっとずっと優秀な王子になった、って…」
私は、ハーヴェイ殿下にお目通りが叶った事はない。
ウェインズ男爵家は殆ど社交を行っていないし、そもそも、ハーヴェイ殿下ご自身が、社交の場に出ていらしていない。
だから、実際の殿下がどのような方かは存じ上げない。
先王妃殿下が仰るように、賢王となる素質をお持ちだったのかもしれない。
けれど、それはアルフォンス様をご両親から遠ざけ、不要な罪悪感を植え付ける理由には成り得ない。
「だから、僕は、叔父上のお子様の代わりに、完璧な王子にならなくてはならないんだ…っ」
「アルフォンス様。先程の私の言葉を覚えていますか?最後は自分の判断です。『誰かが言ったから』とその言葉を鵜呑みにしてはいけません。自分の頭で考えなくてはいけません。例え、先王妃殿下であっても、です。…アルフォンス様は、大好きなご両親とハグして、楽しくお話する王子は、立派な王子ではないと思いますか?」
アルフォンス様は、逡巡するように視線を巡らせ、暫く沈黙すると、小さく答えた。
「……思わ、ない」
「ならば、それが答えです。私は王族ではありませんから、玉座に向き合うご両親のお考えは判りません。ですが、今のアルフォンス様のお気持ちを伝えると、お喜びになるだろうな、と言う事は判りますよ」
「そう、かな…嫌がられない…?呆れられたり、しないかな…?」
「アルフォンス様、今、私はアルフォンス様のお話を聞いて、嫌がったり呆れたりしていますか?」
「して、ない、と思う…」
「アルフォンス様が大好きなご両親なんです。褒めてくださりこそすれ、呆れるわけがないですよ。今まで、よく頑張って来ましたね」
そう言って微笑むと、アルフォンス様のお顔が、くしゃり、と歪んだ。
そのまま、声を上げて泣き出すのを、そっと抱き寄せる。
そして、涙が枯れて落ち着くまで、じっと黙って寄り添ったのだった。
アルフォンス様と手合わせをしてから、私は一日に少なくとも一度は、アルフォンス様を強制的に私との『遊び』に付き合わせている。
一日のスケジュールは、学校のようにきちんと時間割が決められており、その通りに行動していれば休憩時間を取れる筈なのに、何故だか、アルフォンス様には自由時間が全くない。
朝食を食べながら予習をし、朝のお茶の時間は単なる水分補給、昼食も手づかみで食べられるようにサンドウィッチが中心で、昼のお茶の時間は午前同様。
晩餐だけは、ご家族と時間が合えば共に召し上がるので、比較的きちんと取っているけれど、毎日と言うわけにはいかない。
授業と授業の間に休憩時間を三十分から一時間取ってあるにも関わらず、これだ。
これはひとえに、アルフォンス様の真面目で熱心な授業態度に教師陣が過熱して、きちんと時間通りに授業を終えないせいである。
いや、彼等の中に、邪なものが全くない、とは言い切れないか。
自分の教える科目こそ最も得意として欲しい、優秀な教師と慕って欲しい、と言う欲があるのを感じられる。
「少しだけならいいだろう」、「他の教師もやっているのだから構わないだろう」。
アルフォンス様が全能だからこそ、教師同士の争いになってしまっているのだ。
その為、ずっと部屋の隅に控えている私は、タイミングを見計らって強制突入し、『遊び』と言う名の気分転換と休憩を取って頂いている。
一ヶ月が経過したものの、私の意図する所を理解してくれたらしい教師はまだ一人。
他の人間は、
「侍女風情が何故、アルフォンス殿下の学ばれたいと言う尊いお気持ちを蔑ろにするのか。不敬だぞ」
であるとか、
「アルフォンス殿下こそ、神が遣われし御子。百年に一度の天才の行く手を阻むとは、陛下に訴えるぞ」
であるとか、何とも姦しい。
アルフォンス様の前では、声高に私を非難出来ないので(何しろ、私はアラベラ様直属の特任侍女と言う扱いなわけで)、穴が開きそうな程、鋭い視線で睨まれているだけなのだけれど。
どちらにせよ、夫タカユキや元夫マイルズの嫌味に慣れている私には効きはしない。
他の問題もあると言えばあるけれど、私が無視すればいい話だ。
貴族令嬢として、貴族夫人としての規範を守らねば、と躍起になっていた時期ならば、気になっただろうけれど、貴族社会でどう思われようとどうでもいいと一度開き直ってしまった今は、本当にどうでもいい。
「あぁ、もう、ミカエラ。歴史学、あとちょっとでキリのいい所だったのに」
いつも話の長い歴史学の教師を追い出すと、アルフォンス様は口を僅かに尖らせて、でも、面白そうに、そう言った。
アルフォンス様が、あの教師の歴史豆知識と言う名の無駄話が好きではない事に、私は気づいている。
「そうでしたか。私は歴史が苦手なのですけど、過去は過去なんですから、今日学ぼうと明日学ぼうと、変わらないんじゃないですか?」
「でも、もしかしたら明日、『新事実発見!真実は百八十度違った!』なんて事があるかもしれないだろう?」
「まぁ、じゃあ、今日、お勉強しなくて良かったですね。二度手間になりますもの。私に感謝してくれてもいいんですよ?」
澄ました顔でそう言うと、アルフォンス様は、プッと小さく噴き出した。
最近では、このように声に出して笑ってくださる事が増えた。
いい傾向だ。
「今日は何をして遊びたいの?雨だから、中庭は使えないよ?」
アルフォンス様は飽くまで、私の遊びに付き合っている、と言う体を崩さない。
仕方なく遊んであげてるんだ、と思う事で、自分を許しているのだろう。
剣術の授業は毎日あるわけではないので、運動不足にならないように、私は出来る限り、アルフォンス様を中庭に連れ出していた。
成長期の子供には、適度な運動が必要なのだから。
けれど、昨夜から降り出した雨は、今も続いている。
「そうですねぇ。今日は、こちらのボードゲームはどうでしょう?」
自宅から持って来たボードゲームは、何しろ、私が子供の頃に遊んでいたものだから、古い。
もしも、アルフォンス様の食いつきが良ければ、新しく用意するつもりだ。
「へぇ?初めて見た」
「こちらはですね、戦術シミュレーションゲームです。ノーレイン公爵閣下がお得意だったんですよ」
ダリウス様に憧れているアルフォンス様は、『ノーレイン公爵閣下』の名に、ぐ、と身を乗り出した。
「叔父上が?」
「そうです」
「ミカエラのお父上が叔父上の師範だったとは聞いたけれど、ミカエラも叔父上の知り合いなの?」
「…えぇ、そうですよ」
返答に、一瞬間が空いてしまった事に、アルフォンス様は気づかなかったようだ。
王城で勤め口が見つかった事は、ユリシーズ様に働き口を問い合わせてくださった事へのお礼と共に報告してある。
ダリウス様からは、「王城ならば一先ず安心だが、王族の傍にいる事での危険もある故、くれぐれも気を抜くな」と言う旨のお返事が届いた。
最後にお顔を見てから、四ヶ月。
離婚が決まった事と就職が決まった事だけ連絡させて頂いたけれど、これは成り行き上、必要となった業務連絡であって、友達に送る近況報告とは、種類が違う。
「父がサディアス様には大変お世話になってましたし、剣術の指導についていく事もありましたから」
「あぁ、そうか。…ノーレイン公爵邸なら、友達も呼びやすいね。王城だと、なかなか…」
「呼びたいお友達がいるんですか?」
初耳だ。
アルフォンス様は、ノーレイン公爵家でも家庭教師について学ばれていたから、勝手に、友達はいないのだと思っていた。
「友達、と言うか…友達と言っていいのか判らないのだけれど…」
珍しく小さな声でぽそぽそと話すのを根気強く聞き出した所、ノーレイン公爵家に仕えている執事の子供と、仲良くしていたらしい。
ノーレイン公爵家には複数の執事と、バートと言う家令がいる。
バートは白髪口髭で、ミカの世界の人間なら「セバスチャン」と呼びたくなる人だけれど、彼の事は知っていても、家族構成は把握していない。
執事達も、私が幼い頃とは、代替わりをしているだろう。
執事と言っても、ウェインズ男爵家よりもずっとずっと上の爵位をお持ちの貴族だから、アルフォンス様の友達であっても何の不思議もない。
「ノーレイン公爵家にお勤めの方であれば、安心ですね。アラベラ様に相談してみては?」
ユリシーズ様もアラベラ様もご存知の方のご子息ならば、問題なく呼べる筈だ。
きっと、アラベラ様は、大喜びで手配する。
私のような似非友達ではなく、真の友達なのだろうから。
「…でも…」
だが、アルフォンス様は、暗い顔で押し黙ってしまった。
「でも?」
「…クレイグは、使用人の子だから…僕が仲良くしたら、いけないんだ」
「…なるほど?」
「そ、それに、僕が呼びつけたら、クレイグが僕の事をどう思っていても、仲良くしなくては、と思うだろう?」
そのまま、黙り込んで俯いたアルフォンス様を見て、遥か昔の思い出が蘇る。
ダリウス様も私に対して、
「俺に呼ばれたからって、無理して遊びに来てるわけじゃないよな?」
と、何度か確認していた。
当時は、何も考えずに、
「何で?あに様と遊ぶの楽しいよ?」
と答えていたけれど、爵位の差は、高位のダリウス様達にとっても、大きなものだったのだろう。
「そうですねぇ…私は、クレイグ様に会った事がないので、彼がアルフォンス様の事をどう思っているのか、勝手に推測する事は出来ませんけど。一つだけ、いいですか?」
「な、何?」
「使用人の子供と、アルフォンス様が仲良くしてはいけない理由って何です?」
「それは…僕は王子だから…王子に相応しい相手としか付き合ってはならないから…」
「相応しいかどうかは、何で判るんですか?つまり、アルフォンス様は付き合う友達を、身分で選ぶと言う事ですか?友達になる価値は、身分にあるんですか?」
「…ぅ…」
「サディアス様は、平民だった父と親しくしてくださいました。サディアス様は、間違っていたと言う事ですか?」
「ち、違う!おじい様は間違ってなんかない!おじい様にとって、ウェインズ男爵は英雄だったのだから!」
真っ赤な顔で叫んだアルフォンス様に、微笑みかける。
「ね?身分なんて、友達になるかどうかに関係ないんです。勿論、アルフォンス様は王子様ですから、身の安全を図る為にも、誰彼となく親しくするのは難しい。その判断基準の一つとして、身分を把握する事はいいでしょう。でもね、残念ですけど、貴族ならば皆が聖人なわけじゃありません。そして、平民ならば信用に値しないわけでもありません。最後は、自分の判断に委ねないといけません」
「自分の…判断…」
「例えば私が、『この人、いい人なんで、お友達になってあげてください』と誰かを連れて来たとします。アルフォンス様は、『確かにいい人そうだけど、何かイヤな感じがするんだよな』と思いながらも、私に紹介されたのだからいいだろう…と何がイヤな感じなのか調べる事なく、友達付き合いをします。ところが、その人はいい人の仮面を被った悪者で、アルフォンス様の名を借りて悪行三昧するんです。そんな事が起きたら、アルフォンス様はどうしますか?『紹介したミカエラが悪い!僕は悪くない!』と言いますか?」
アルフォンス様は、「え…」と小さく言うと、考え込んだ。
「何かイヤだ、と思いながらも付き合うと決めたなら…悪いのは、僕だ」
「勿論、悪者だと気づかずに、アルフォンス様に紹介した私が一番悪いんですけどね。誰かを紹介する、って、それ位に大事な事なので、私は『紹介する責任』を負わなくてはいけません。でも、受け入れる、付き合いを続ける、と選択した時点で、アルフォンス様も、責任を負う事になってしまいます」
「そうか…だから、最後は自分の判断、なのだね。自分の責任だと思えば、流されるだけじゃなくて、きちんと、相手が本当にいい人がどうかを考えるから」
「そう言う事です」
本当に、アルフォンス様は聡明だ。
今後、彼の周囲には、虎の威を借る狐達が侍ろうとするだろう。
だからこそ、アルフォンス様には、相手を身分や肩書で判断するのはなく、本質で見るようにして頂かなくては。
「一つ、昔話をしていいですか?」
「うん、何?」
「私はですね、二十三歳で叔母に紹介された男性と結婚しました」
「ミカエラ、結婚していたの?!独身だと言っていたのに」
「まぁまぁ、聞いてください。夫を紹介したのは叔母だし、両親も私の結婚相手を心配していたし、私も適齢期ぎりぎりだったし、これもご縁だろう、と結婚したんです。でも、夫と私は、とことん、性格が合わなかったんですね。だから、全然うまくいかなくて…結局、先日、離縁しました。結婚を決める前に、もっと深く考えるべきだったんです。自分の人生なのに、叔母の顔を立てなきゃ、とか、両親を安心させなきゃ、とか、言い訳をするって事は、人に責任を負わせようとしてるって事でしょう。自分の人生なら、自分で責任を負わないと。私が幸せだと思えないなら、意味がないんです」
アルフォンス様は、その透き通った青い目で、じっと私の顔を見つめた。
「…今、ミカエラは幸せ?」
「えぇ、幸せですよ。大好きなアルフォンス様と、毎日、遊べますから」
大好き、と聞いて、アルフォンス様が少し頬を染めて顔を上げる。
「大好き?ミカエラは、僕の事が大好きなの?」
「当たり前です。アルフォンス様と遊ぶ時間は、私にとって、とても楽しくて充実した時間です。それは、アルフォンス様が王子様だからじゃありません。頭が良くて、剣が強いからでもありません。アルフォンス様が、アルフォンス様だからですよ」
「僕が僕なのは、それこそ、当たり前でしょう?」
「そうですね。つまり、アルフォンス様は、そこにいるだけで私を幸せにしてくれる、って事ですよ」
アルフォンス様は、驚いたように目を大きく見開いた。
「…そこに、いるだけで?」
「はい」
「難しい勉強をしなくても?」
「はい」
「剣で勝てなくても?」
「はい」
「…っでも、僕は王子だから…」
「王子様だって、人間です。怒る時も泣く時もあるでしょう。悩む時だって疲れる時だってあります。愚痴りたい時もサボりたい時もあって当然です。そして、私は怒ろうと泣こうと悩もうと疲れようと愚痴ろうとサボろうと、アルフォンス様が好きですよ」
アルフォンス様は、唇を戦慄かせると、
「は、母上も、そうかな…?」
と尋ねた。
「アラベラ様ですか?勿論です」
「父上は…」
「ユリシーズ様も、ユージェニー様も、勿論ノーレイン公爵閣下も、皆、アルフォンス様が大好きですよ」
ぽろり、と。
アルフォンス様の目から、涙が零れ落ちる。
「臣下に取り乱さないお姿を見せる事は、安心に繋がります。ご立派な事です。けれど、ご家族の前では、いいじゃないですか」
「で、でも、おばあ様が…僕が、いつも王子らしくしていないと、母上が他の人に見くびられる、って…母上に甘えたり、父上に相談したり、そう言う、王子らしくない事をするな、って…」
…おばあ様、って、フェリシア様じゃなくて、エメライン先王妃殿下の事よね…。
フェリシア様が、そんな事を言う筈がない。
アラベラ様からも、確執があるような事は聞いていたけど、ご自分の孫に何て事を吹き込んでくれたのか。
ザラ、と、胸の中に飲み下せない嫌なものが残る。
「ほ、本当は僕、母上ともっと、お話がしたい。小さい頃みたいに、ギュッとして欲しい。でも、でも、おばあ様が、そんな事をすると、母上の迷惑になる、母上に嫌われる、って…。父上にも、頼りない王子じゃ呆れられる、って…」
「…そうですか。先王妃殿下が、そのように仰ったのですね?」
「うん…おばあ様が、ハーヴェイ叔父上は立派な王子様だった、お体が弱くなければ、歴史に残る賢王になった、って……叔父上にお子様がいらしたら、僕なんか足元にも及ばない、ずっとずっと優秀な王子になった、って…」
私は、ハーヴェイ殿下にお目通りが叶った事はない。
ウェインズ男爵家は殆ど社交を行っていないし、そもそも、ハーヴェイ殿下ご自身が、社交の場に出ていらしていない。
だから、実際の殿下がどのような方かは存じ上げない。
先王妃殿下が仰るように、賢王となる素質をお持ちだったのかもしれない。
けれど、それはアルフォンス様をご両親から遠ざけ、不要な罪悪感を植え付ける理由には成り得ない。
「だから、僕は、叔父上のお子様の代わりに、完璧な王子にならなくてはならないんだ…っ」
「アルフォンス様。先程の私の言葉を覚えていますか?最後は自分の判断です。『誰かが言ったから』とその言葉を鵜呑みにしてはいけません。自分の頭で考えなくてはいけません。例え、先王妃殿下であっても、です。…アルフォンス様は、大好きなご両親とハグして、楽しくお話する王子は、立派な王子ではないと思いますか?」
アルフォンス様は、逡巡するように視線を巡らせ、暫く沈黙すると、小さく答えた。
「……思わ、ない」
「ならば、それが答えです。私は王族ではありませんから、玉座に向き合うご両親のお考えは判りません。ですが、今のアルフォンス様のお気持ちを伝えると、お喜びになるだろうな、と言う事は判りますよ」
「そう、かな…嫌がられない…?呆れられたり、しないかな…?」
「アルフォンス様、今、私はアルフォンス様のお話を聞いて、嫌がったり呆れたりしていますか?」
「して、ない、と思う…」
「アルフォンス様が大好きなご両親なんです。褒めてくださりこそすれ、呆れるわけがないですよ。今まで、よく頑張って来ましたね」
そう言って微笑むと、アルフォンス様のお顔が、くしゃり、と歪んだ。
そのまま、声を上げて泣き出すのを、そっと抱き寄せる。
そして、涙が枯れて落ち着くまで、じっと黙って寄り添ったのだった。
54
あなたにおすすめの小説

婚約者の命令により魔法で醜くなっていた私は、婚約破棄を言い渡されたので魔法を解きました
天宮有
恋愛
「貴様のような醜い者とは婚約を破棄する!」
婚約者バハムスにそんなことを言われて、侯爵令嬢の私ルーミエは唖然としていた。
婚約が決まった際に、バハムスは「お前の見た目は弱々しい。なんとかしろ」と私に言っていた。
私は独自に作成した魔法により太ることで解決したのに、その後バハムスは婚約破棄を言い渡してくる。
もう太る魔法を使い続ける必要はないと考えた私は――魔法を解くことにしていた。

君に何度でも恋をする
明日葉
恋愛
いろいろ訳ありの花音は、大好きな彼から別れを告げられる。別れを告げられた後でわかった現実に、花音は非常識とは思いつつ、かつて一度だけあったことのある翔に依頼をした。
「仕事の依頼です。個人的な依頼を受けるのかは分かりませんが、婚約者を演じてくれませんか」
「ふりなんて言わず、本当に婚約してもいいけど?」
そう答えた翔の真意が分からないまま、婚約者の演技が始まる。騙す相手は、花音の家族。期間は、残り少ない時間を生きている花音の祖父が生きている間。

俺の可愛い幼馴染
SHIN
恋愛
俺に微笑みかける少女の後ろで、泣きそうな顔でこちらを見ているのは、可愛い可愛い幼馴染。
ある日二人だけの秘密の場所で彼女に告げられたのは……。
連載の気分転換に執筆しているので鈍いです。おおらかな気分で読んでくれると嬉しいです。
感想もご自由にどうぞ。
ただし、作者は木綿豆腐メンタルです。

公爵令嬢は婚約破棄に微笑む〜かつて私を見下した人たちよ、後悔する準備はできてる?〜
sika
恋愛
婚約者に裏切られ、社交界で笑い者にされた公爵令嬢リリアナ。
しかし彼女には、誰も知らない“逆転の手札”があった。
婚約破棄を機に家を離れ、彼女は隣国の次期宰相に招かれる。
そこで出会った冷徹な青年公爵・アルヴェンが、彼女を本気で求めるようになり——?
誰もが後悔し、彼女だけが幸福を掴む“ざまぁ”と“溺愛”が交錯する、痛快な王道ラブロマンス!

婚約者はメイドに一目惚れしたようです~悪役になる決意をしたら幼馴染に異変アリ~
たんぽぽ
恋愛
両家の話し合いは円満に終わり、酒を交わし互いの家の繁栄を祈ろうとしていた矢先の出来事。
酒を運んできたメイドを見て小さく息を飲んだのは、たった今婚約が決まった男。
不運なことに、婚約者が一目惚れする瞬間を見てしまったカーテルチアはある日、幼馴染に「わたくし、立派な悪役になります」と宣言した。

わたくしが社交界を騒がす『毒女』です~旦那様、この結婚は離婚約だったはずですが?
澤谷弥(さわたに わたる)
恋愛
※完結しました。
離婚約――それは離婚を約束した結婚のこと。
王太子アルバートの婚約披露パーティーで目にあまる行動をした、社交界でも噂の毒女クラリスは、辺境伯ユージーンと結婚するようにと国王から命じられる。
アルバートの側にいたかったクラリスであるが、国王からの命令である以上、この結婚は断れない。
断れないのはユージーンも同じだったようで、二人は二年後の離婚を前提として結婚を受け入れた――はずなのだが。
毒女令嬢クラリスと女に縁のない辺境伯ユージーンの、離婚前提の結婚による空回り恋愛物語。
※以前、短編で書いたものを長編にしたものです。
※蛇が出てきますので、苦手な方はお気をつけください。

その断罪、三ヶ月後じゃダメですか?
荒瀬ヤヒロ
恋愛
ダメですか。
突然覚えのない罪をなすりつけられたアレクサンドルは兄と弟ともに深い溜め息を吐く。
「あと、三ヶ月だったのに…」
*「小説家になろう」にも掲載しています。
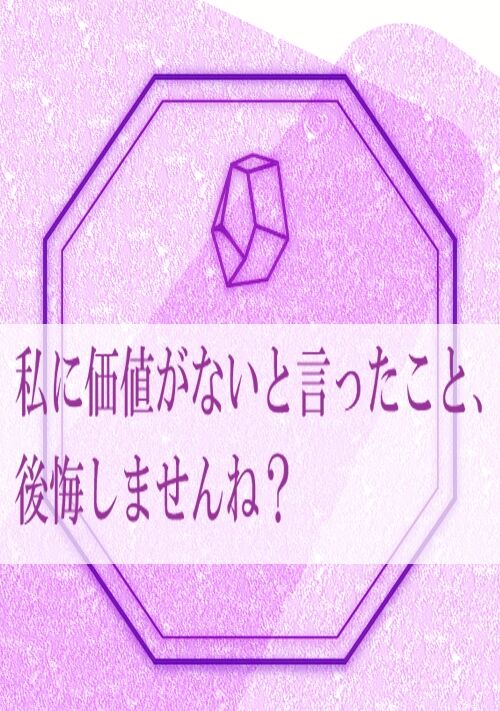
私に価値がないと言ったこと、後悔しませんね?
みこと。
恋愛
鉛色の髪と目を持つクローディアは"鉱石姫"と呼ばれ、婚約者ランバートからおざなりに扱われていた。
「俺には"宝石姫"であるタバサのほうが相応しい」そう言ってランバートは、新年祭のパートナーに、クローディアではなくタバサを伴う。
(あんなヤツ、こっちから婚約破棄してやりたいのに!)
現代日本にはなかった身分差のせいで、伯爵令嬢クローディアは、侯爵家のランバートに逆らえない。
そう、クローディアは転生者だった。現代知識で鉱石を扱い、カイロはじめ防寒具をドレス下に仕込む彼女は、冷えに苦しむ他国の王女リアナを助けるが──。
なんとリアナ王女の正体は、王子リアンで?
この出会いが、クローディアに新しい道を拓く!
※小説家になろう様でも「私に価値がないと言ったこと、後悔しませんね? 〜不実な婚約者を見限って。冷え性令嬢は、熱愛を希望します」というタイトルで掲載しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















