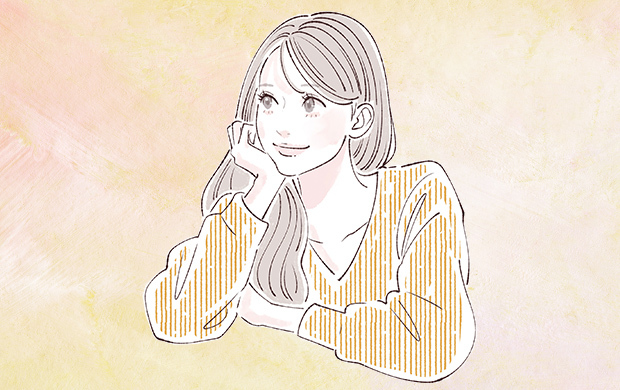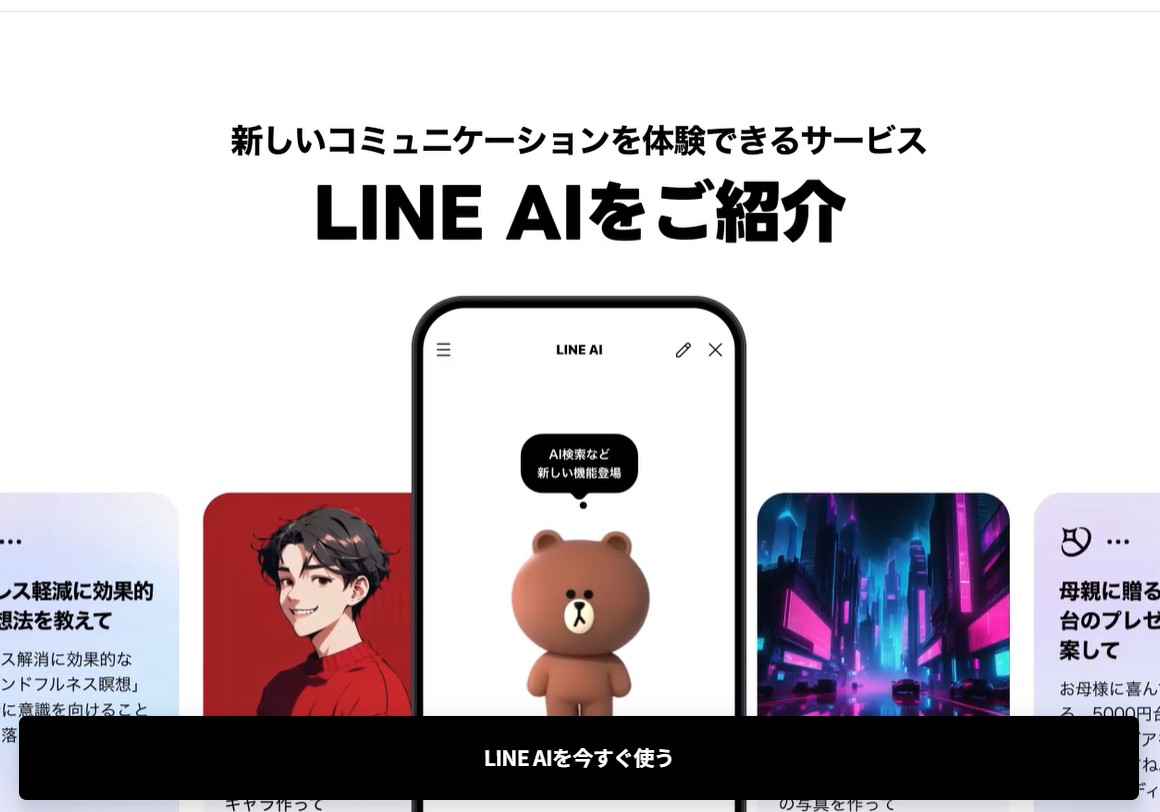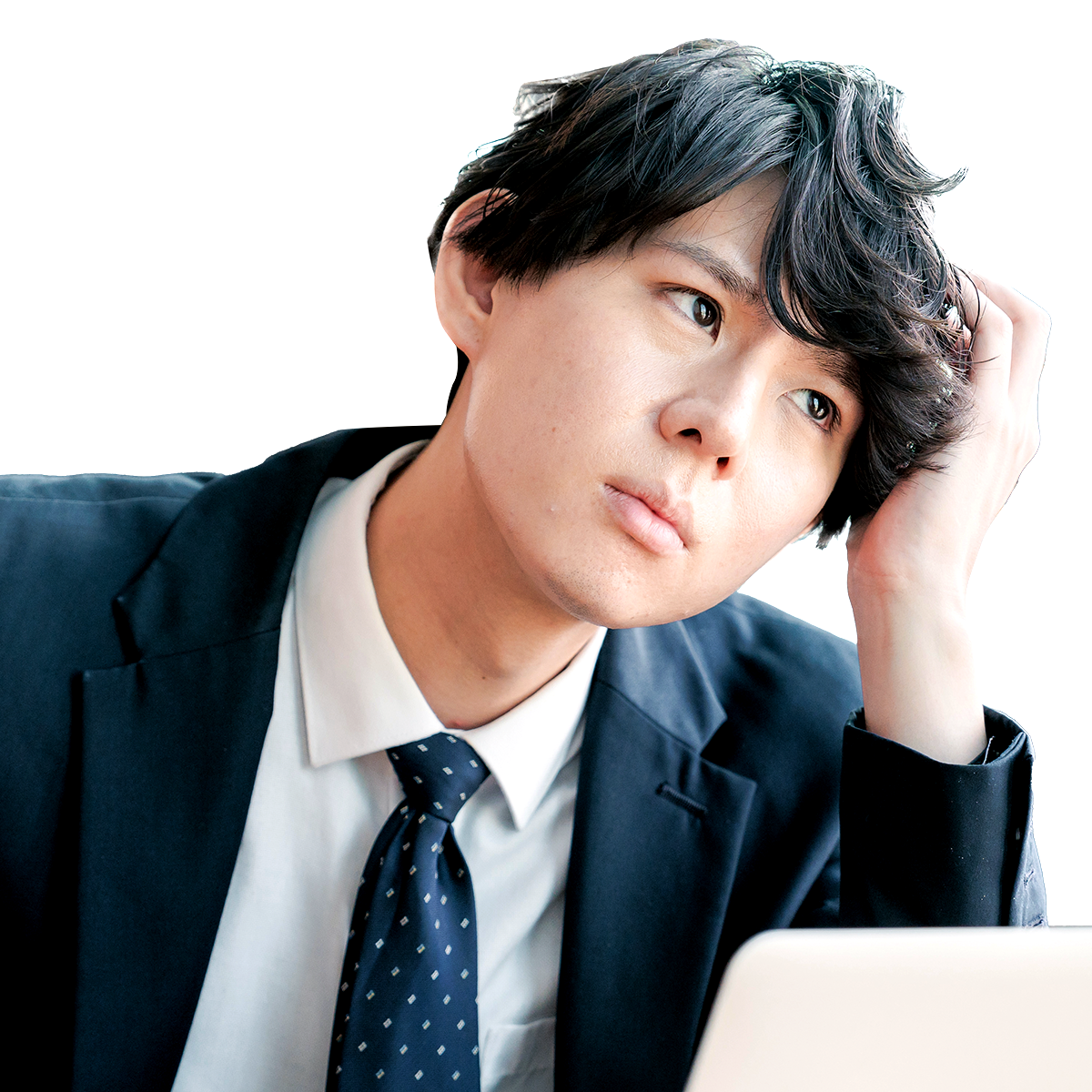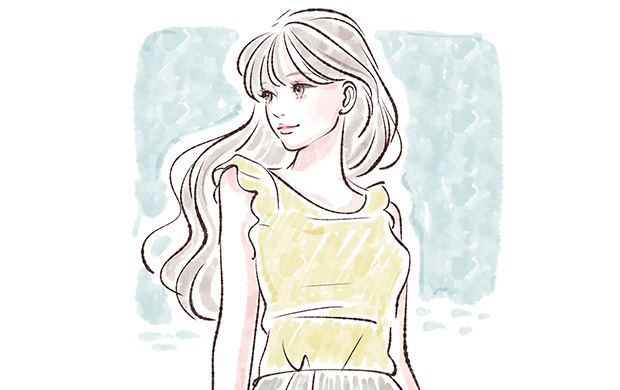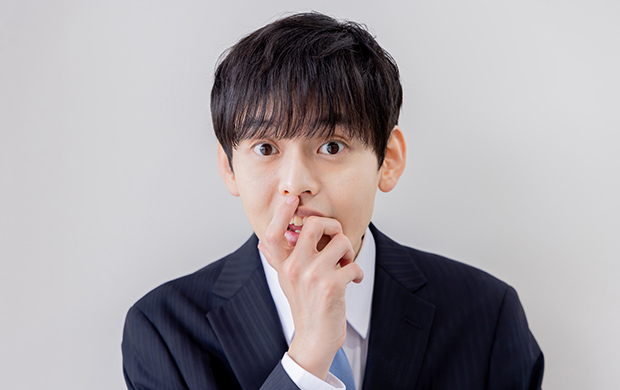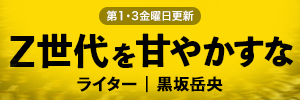大正製薬HD、なぜMBOで上場廃止?上場維持が成長の障害、経営の負担に
2024.01.11
ビジネスジャーナル
「継続的な情報開示に要する費用や株主総会の運営、株主名簿管理人への事務委託に要する費用など、株式の上場を維持するために必要な費用が増加しており、当該コストがグループの経営上のさらなる負担となる可能性がある」
このような経緯で大正製薬HDは、過去最大となるMBOを実施するに至った。
MBOが失敗する事例も
だがMBOはそう簡単ではない。なぜならば、PBR1倍割れのMBOについてはアクティビストの介入などによって非公開化が阻止されることもあるからだ。たとえば、光陽社、サカイオーベックス(1度目)、日本アジアグループは当初発表したMBOについてTOB価格が十分でない、あるいはPBR1倍よりも低いなどを理由にアクティビストなど株主から批判・介入され、MBOに失敗した。このようなMBOの失敗事例に共通するのは、アクティビストの介入や市場株価がTOB価格を上回ることで、非公開化に必要なTOBの下限まで応募が集まらないという点だ。
現に投資信託「マネックス・アクティビスト・ファンド」のマザーファンドなどに投資助言を行うカタリスト投資顧問は12月1日付ニュ―スリリースで、大正製薬HDのMBOについて「より強いリーダーシップを発揮して機動的な企業活動をするために、MBO は合理的な経営判断であると考えます」と一定の評価を示しながらも、TOB価格について「少数株主を軽視している」などと表明した。
これについて、大正製薬HDは「TOBにおいては、専門的な算定機関の算定に則していること及び市場株価に対してどれだけ株主様にとって適正なプレミアムが加味されているかという点が最も重要だと認識しております。当社のMBOへの賛同・応募推奨に至るプロセスにおいても、独立した特別委員会が機能し、交渉過程において価格の引き上げが実現するなど、少数株主保護の観点からも適正な対応を行っております」としている。
過去最大のMBOは成立するのか
果たして過去最大のMBOは成立するのか。市場株価は公表後の11月29日にはTOB価格を133円上回る年初来最高値8753円まで上昇したが、23年の大納会の終値ではTOB価格を25円上回る程度に落ち着き、TOB価格に収れんしつつある。これまでのところリリースを公表したカタリスト投資顧問も特段のアクションは行っておらず、それ以外に横やりを入れるアクティビストも出現していない。
大正製薬HDのTOBの成立の条件は、下限としている66.57%を超える応募を集めることだが、大正製薬HDでは上場の歴史の長い企業では珍しく創業家系の株主比率が40%を超え、メインバンクや株式持合い先など有価証券報告書で確認できる安定株主だけでも6割程度存在する。そうした安定株主のなかには、相互に株式の持ち合いを行っている企業も多くあり、その一つである養命酒製造は23年12月12日にはTOBに応募することを決議し、応募した場合には約4億5000万円の特別利益が生じるとの適時開示を行った。このように長年政策保有する上場企業からすると、TOBに応じることで一定のプレミアムで利益が出る上に、近年政策保有株式に対する自社株主からの視線が厳しくなるなかで持ち合い株式を売却できる機会でもあり、渡りに船という状況にもなっている。
加えて、大正製薬HDの沿革を見ると、1978年から株主特約店制度を設け、自社製品の取引先である小売店や薬局などに自社の株式保有を奨励するなど、数十年単位で安定株主を築いてきたことが見られる。このような株主特約店の存在も加わり、TOBの下限を超える応募が集まる確度は相当高いと見られる。
TOB成立後には上原氏が父の明氏に代わって大正製薬HDの社長に就任する。40年ぶりの世代交代となる。同社は新たな体制の下で、セルフメディケーション事業の営業体制の見直しとECサイトの強化、生産管理のてこ入れ、海外事業での有望なOTCブランドの買収、そして医薬事業における新薬開発など腰を据えた事業の抜本的強化に取り組むものと思われる。上場維持を選択する企業と上場廃止を選択する企業で今後成長力に差が生まれるのか注目される。
(文=松崎隆司/経済ジャーナリスト)