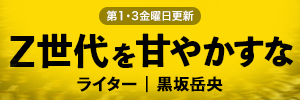資生堂、過去最大の赤字に…「マーケティングの巨人」に何が?V字回復の可能性は?
2025.11.12
ビジネスジャーナル
近年の資生堂は「ブランドポートフォリオの再編」という大命題に追われ、社内リソースの多くが構造改革に向けられた。その結果、現場の顧客接点から得られるデータや市場感覚をプロダクト戦略に反映するサイクルが弱まったとの指摘もある。
資生堂は2010年代後半から海外M&Aを積極化させた。米BareMineralsやNARSなどを傘下に収め、欧米の高級コスメ市場に足場を築こうとしたが、収益性は長く安定しなかった。特にコロナ禍では海外店舗の閉鎖や観光需要の消失が直撃し、巨額の減損を迫られた。これにより、成長ドライバーとしてのM&A戦略は転機を迎えている。
一方で、売却益を原資に財務体質は改善しており、手元資金の厚みは一定の安心材料となっている。資生堂は今後、買収依存ではなく、既存ブランドの磨き上げと研究開発への投資を軸に再成長を図るとみられる。
再生のカギは「中価格帯」と「ローカル適応」か
資生堂の再成長の方向性として有力視されるのが、「中価格帯」の再強化と「ローカル適応戦略」である。
「グローバル市場では、ラグジュアリーとマスの“二極化”が進む一方で、中間価格帯をうまく押さえた企業が安定的な収益を確保しています。韓国のアモーレパシフィック、フランスのロレアルなどはその代表例です。
また、近年はローカル発ブランドの価値が再評価されています。資生堂は世界中に研究拠点を持っているものの、各国市場に根ざしたプロダクト開発・広告展開を徹底できているとはいいがたいのが実情です。たとえば、タイやインドなど新興国市場では、美白やスキンケアよりも『肌の健康』や『自然志向』が重視されており、こうした文化的価値観への適応が鍵を握るでしょう」(戦略コンサルタント・高野輝氏)
さらに今後の資生堂が避けて通れないのが、AIとデータの活用だ。
「化粧品業界では、AIによるスキンケア分析やパーソナライズド提案が急速に普及しています。ロレアルはAI肌診断アプリ『ModiFace』でデータを蓄積し、顧客体験を深化させています。資生堂も同様にAIスキンケア診断を提供していますが、現状ではマーケティング活用が限定的です。
AIを顧客接点と商品開発の双方に統合すれば、従来型の『感性マーケティング』から『データ×感性』の新しいブランド戦略への転換が可能となります。研究開発・販売・広告をデジタルで一気通貫させる体制が整えば、収益構造の改善スピードは格段に上がるでしょう」(同)
復活への条件──「感性」と「構造」の再融合
競合他社の動きを見ても、資生堂の立て直し余地は小さくない。
「花王は『エスト』や『ソフィーナ』などの高価格帯を維持しつつ、生活領域全体でのブランド価値向上を進めています。コーセーは『雪肌精』を軸に海外展開を強化し、アジア市場での認知を拡大しています。いずれも高級ブランド一本足ではなく、複数の価格帯でリスク分散を図る構造となっています。
資生堂もその点で、再びミドルレンジに一部参入する柔軟なブランド設計を検討すべき段階にあるといえます」(同)
国内の消費構造が変化するなか、デジタル経由での販売・顧客接点の多様化も進んでおり、従来の百貨店モデルに依存しないチャネル戦略が不可欠となる。
「資生堂が再び輝きを取り戻すために必要なのは、マーケティングの再構築ではなく、感性と構造の融合です。同社の強みである『美意識』『ブランド物語』『クリエイティブな表現』は、いまも世界最高水準です。これに、経営構造の合理化、データ活用、人材のグローバル流動性を組み合わせることで、再成長の芽は十分にあると考えられます。
特に、デジタル世代の女性やZ世代男性を含む新市場に対して、資生堂が『自分らしさを表現するためのブランド』として再定義できれば、再浮上の可能性は高いでしょう。その際に重要なのは、過去の成功体験に依存せず、『顧客の変化を美しく取り込む企業』へと進化する意思です」(同)
今回の赤字は、単なる経営の失敗ではない。グローバル化と市場多様化が進む中で、従来型の成功モデルを一度リセットし、再構築を迫られた結果である。選択と集中の戦略が短期的には業績悪化をもたらしたとしても、その先に資生堂が「新しい美の定義」を再創造できるかどうか。
2020年代後半の資生堂に求められるのは、ブランド力とマーケティング力の再統合──「美とデータ」「伝統と変革」を両立させる経営力である。この難題を乗り越えたとき、資生堂は再び“世界で最も美しい企業”として市場に帰ってくるかもしれない。
(文=BUSINESS JOURNAL編集部)