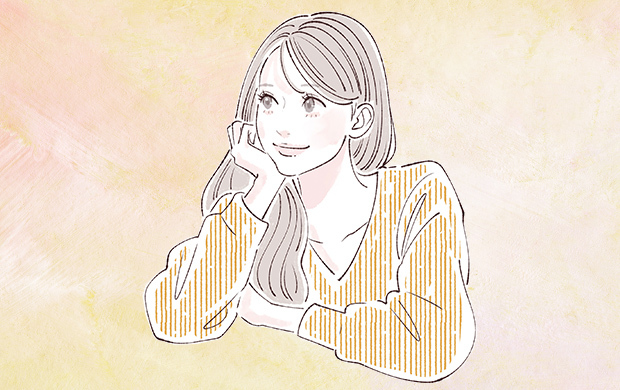創業2年のバイオスタートアップが「わきが」で勝負…4兆円市場に挑む
2025.11.06
ビジネスジャーナル
量産化のボトルネックは微生物の培養ではなく、プラスチックの剤型である。微生物を長期保存する方法自体が知的財産であり、セキュリティ上の観点からOEMは選択肢にない。需要予測が難しい中で、工場建設は初期投資が大きいため、慎重な意思決定を要する。
プロダクトのさらなる開発も続ける。9月には慶應義塾大学と、研究リソースの相互提供を通じ、アトピー性皮膚炎や蚊の誘因性を抑える微生物株の産出を目指すことを発表した。
販売チャネルはドラッグストアなどの小売と、D2C(Direct to Consumer)の両軸を検討している。今年6月にはAmazon Pharmacyの事業モデルを構築したTJ Parker氏が経営に参画し、D2Cのサプライチェーン構築を担う。
日本市場ももちろん視野に入っている。市場が大きいとはいえないが、日本には独自の可能性があると福永氏は話す。
「日本には“わきが”という言葉がありますが、私が調べた限り、わきの臭いに対して単語がある国は非常に限られます。一定数の日本人海外の方が、わきがに対して手術や注射など医療的な対応をしていると聞いたら、海外の方はまず驚かれます。日本ではわきがをコンプレックスであると捉えている人が多いということであり、デオドラントではなく長期的に効果がある製品へのニーズがあると考えています」
米国では自社サプライチェーンを構築する見込みだが、日本では事業提携も含め販路を広げることを視野に入れる。
「今後も、技術的なイノベーションを通じた社会課題の解決をして、一般的な消費者の手に届く形にしたい」と福永氏は語る。
創業わずか2年。合成生物学という先端技術を武器に、皮膚という“身近な生態系”から市場を変えようとしている若き起業家の挑戦は、ここからが本番だ。
(寄稿=相馬留美/ジャーナリスト)