あなたにおすすめの小説

敵に貞操を奪われて癒しの力を失うはずだった聖女ですが、なぜか前より漲っています
藤谷 要
恋愛
サルサン国の聖女たちは、隣国に征服される際に自国の王の命で殺されそうになった。ところが、侵略軍将帥のマトルヘル侯爵に助けられた。それから聖女たちは侵略国に仕えるようになったが、一か月後に筆頭聖女だったルミネラは命の恩人の侯爵へ嫁ぐように国王から命じられる。
結婚披露宴では、陛下に側妃として嫁いだ旧サルサン国王女が出席していたが、彼女は侯爵に腕を絡めて「陛下の手がつかなかったら一年後に妻にしてほしい」と頼んでいた。しかも、侯爵はその手を振り払いもしない。
聖女は愛のない交わりで神の加護を失うとされているので、当然白い結婚だと思っていたが、初夜に侯爵のメイアスから体の関係を迫られる。彼は命の恩人だったので、ルミネラはそのまま彼を受け入れた。
侯爵がかつての恋人に似ていたとはいえ、侯爵と孤児だった彼は全く別人。愛のない交わりだったので、当然力を失うと思っていたが、なぜか以前よりも力が漲っていた。
※全11話 2万字程度の話です。

迷子を助けたら生徒会長の婚約者兼女の子のパパになったけど別れたはずの彼女もなぜか近づいてくる
九戸政景
恋愛
新年に初詣に来た父川冬矢は、迷子になっていた頼母木茉莉を助け、従姉妹の田母神真夏と知り合う。その後、真夏と再会した冬矢は真夏の婚約者兼茉莉の父親になってほしいと頼まれる。
※こちらは、カクヨムやエブリスタでも公開している作品です。
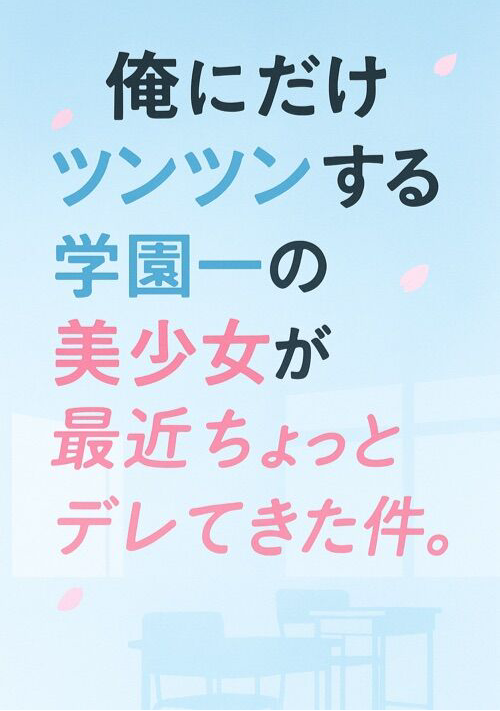
俺にだけツンツンする学園一の美少女が、最近ちょっとデレてきた件。
甘酢ニノ
恋愛
彼女いない歴=年齢の高校生・相沢蓮。
平凡な日々を送る彼の前に立ちはだかるのは──
学園一の美少女・黒瀬葵。
なぜか彼女は、俺にだけやたらとツンツンしてくる。
冷たくて、意地っ張りで、でも時々見せるその“素”が、どうしようもなく気になる。
最初はただの勘違いだったはずの関係。
けれど、小さな出来事の積み重ねが、少しずつ2人の距離を変えていく。
ツンデレな彼女と、不器用な俺がすれ違いながら少しずつ近づく、
焦れったくて甘酸っぱい、青春ラブコメディ。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

俺をフッた女子に拉致されて、逃げ場のない同棲生活が始まりました
ちくわ食べます
恋愛
大学のサークル飲み会。
意を決して想いを告げた相手は、学内でも有名な人気女子・一ノ瀬さくら。
しかし返ってきたのは――
「今はちょっと……」という、曖昧な言葉だった。
完全にフラれたと思い込んで落ち込む俺。
その3日後――なぜか自分のアパートに入れなくなっていた。

君と暮らす事になる365日
家具付
恋愛
いつでもぎりぎりまで疲れている主人公、環依里(たまき より)は、自宅である築28年のアパートの扉の前に立っている、驚くべきスタイルの良さのイケメンを発見する。このイケメンには見覚えがあった。
何故ならば、大学卒業後音信不通になった、無駄に料理がうまい、変人の幼馴染だったのだから。
しかし環依里は、ヤツの職業を知っていた。
ヤツはメディアにすら顔を出すほどの、世間に知られた天才料理人だったのだ!
取扱説明書が必要な変人(世間では天才料理人!?)×どこにでもいる一般人OL(通訳)の、ボケとツッコミがぶつかりあうラブコメディ!(予定)

英雄の番が名乗るまで
長野 雪
恋愛
突然発生した魔物の大侵攻。西の果てから始まったそれは、いくつもの集落どころか国すら飲みこみ、世界中の国々が人種・宗教を越えて協力し、とうとう終息を迎えた。魔物の駆逐・殲滅に目覚ましい活躍を見せた5人は吟遊詩人によって「五英傑」と謳われ、これから彼らの活躍は英雄譚として広く知られていくのであろう。
大侵攻の終息を祝う宴の最中、己の番《つがい》の気配を感じた五英傑の一人、竜人フィルは見つけ出した途端、気を失ってしまった彼女に対し、番の誓約を行おうとするが失敗に終わる。番と己の寿命を等しくするため、何より番を手元に置き続けるためにフィルにとっては重要な誓約がどうして失敗したのか分からないものの、とにかく庇護したいフィルと、ぐいぐい溺愛モードに入ろうとする彼に一歩距離を置いてしまう番の女性との一進一退のおはなし。
※小説家になろうにも投稿

【完結】退職を伝えたら、無愛想な上司に囲われました〜逃げられると思ったのが間違いでした〜
来栖れいな
恋愛
逃げたかったのは、
疲れきった日々と、叶うはずのない憧れ――のはずだった。
無愛想で冷静な上司・東條崇雅。
その背中に、ただ静かに憧れを抱きながら、
仕事の重圧と、自分の想いの行き場に限界を感じて、私は退職を申し出た。
けれど――
そこから、彼の態度は変わり始めた。
苦手な仕事から外され、
負担を減らされ、
静かに、けれど確実に囲い込まれていく私。
「辞めるのは認めない」
そんな言葉すらないのに、
無言の圧力と、不器用な優しさが、私を縛りつけていく。
これは愛?
それともただの執着?
じれじれと、甘く、不器用に。
二人の距離は、静かに、でも確かに近づいていく――。
無愛想な上司に、心ごと囲い込まれる、じれじれ溺愛・執着オフィスラブ。
※この物語はフィクションです。
登場する人物・団体・名称・出来事などはすべて架空であり、実在のものとは一切関係ありません。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















