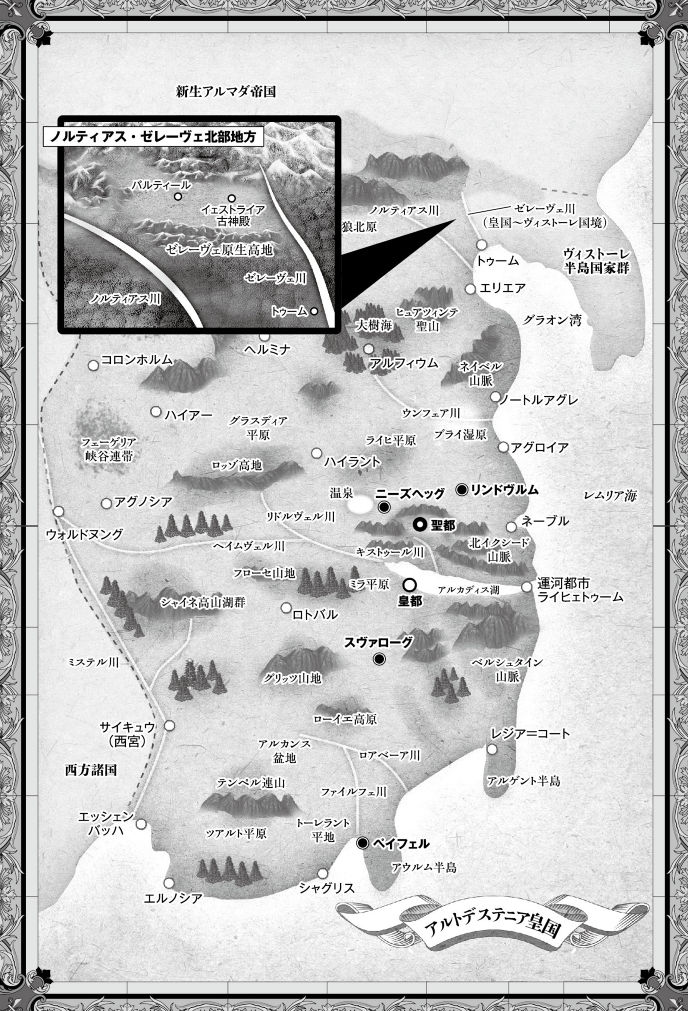81 / 526
6巻
6-1
しおりを挟むレクティファールという人物について一言頂きたい、と求められたら、私は『変な人』であったと答えるしかない。無学者のこの身には、それが限度だ。
私が彼の下で働いていたのはほんの数年のことであったが、その時期は我国にとって激動の期間であった。国土は劇的に広がり、人口は爆発的に増え、我々中央官僚は目が回るような忙しさの中で毎日を過ごしていたものだ。
〈アルストロメリア民主連邦〉の元官僚と私的に会う機会があったが、そのとき私は、皇国という国家が官僚に優しくない国なのだと知った。確かに我国の官僚は働き者だと以前から聞かされていたが、それは陛下の即断に引っ掻き回された我々に対する同情と、それでも諾々と従う我々への皮肉から出た言葉なのだと思っていた。
だが、それはまさに事実をそのまま表現していたに過ぎなかったのだ。
他国において高級官僚とは、人脈形成とちょっとした仕事をこなせば俸給を貰える存在だという。実に羨ましい。
嗚呼、しかしなんという悲劇であろう。
こうして筆を執っている私は今、皇国の官僚であって良かったと、機会があればまたあのような寝る間もない日々に戻りたいと思っている。
つまり皇王レクティファールとは、一線を退いた官僚にそう思わせる人物だったのだ。実に、実に嘆かわしいことである。
―――皇国暦二〇二五年刊行 元内務院三等勅任官の回顧録より抜粋
第一章 皇太子の帰還
皇都〈イクシード〉内、〈星天宮〉の皇城の一室に小さな影がある。
影は窓際の椅子に座り、分厚い、赤茶色の装丁の本を膝に載せていた。
「――――」
一枚、頁を捲る。そこに記されている文章を、目で追う。
「――――」
今この国には、勝利者と呼ばれる男がいる。
内乱を速やかに鎮め、外敵の侵攻を阻んだ上に返す刃で敵国に楔を打ち込んだ。
帝国圧倒的有利という前評判など、完全に覆った。
その手腕は諸外国に衝撃を与えた。
これまでこの国に対して、敵対とは言わないまでも否定的な方針をとっていた国々でさえ、こぞって大使や公使を凱旋式典に送り込んできた。
彼らは有形無形の供物を携え、公的には無位無官の自分にさえ遜った態度を見せている。
彼らが何を求めているのか、察するのは容易い。
あの電撃的な戦いを演じた男が、その矛先を自分に向けることが無いよう願っているのだ。そしてできるなら、それを自分と敵対する存在に向けて欲しいと思っている。
当たり前だ。強力な敵は厄介だが、それが味方であればこれほど心強いことはない。特に中小国にとっては、自分たちの味方であると喧伝するだけでも、それは万の軍勢を持ったに等しい。
強国との同盟や協力関係は、多少の危険を無視しても実現したい、身を守る鎧なのだ。
外務院総裁からそれとなく聞いた話によれば、レクティファールの帰還前にすでに我が国との安全保障条約の締結を望む国家が相当数現れている、ということだった。
小国であればあるほど必死で、外務院総裁から見ても悲痛なものであったという。
中には、応対した下級官吏に膝を突いて懇願した使者もいたと聞く。
レクティファールの行動により、大陸の勢力図は変化した。その変化に慌てた小国がそういった行動に出たのだ。
彼らは自国の安全保障を独力では購えない。大国と接した国境を持つ国は特にそうだ。彼らを守っているのは、単に手に入れる旨みが少なく攻める理由がないという事実のみ。
希少な鉱石を始めとした資源が国内で産出し、龍脈などの現在の魔法技術に欠かせない地理的要因を持つ小国が、難癖を付けられて主権を侵害された事実は、枚挙に暇がない。
逆に特筆するような産物や産業がない国は、その国を目的とした侵攻に晒されるようなことは稀なのだ。ただし、その国家のさらに先に本来の目的がある場合は、侵略を受ける。
大国の利己主義に翻弄され、絶えず命の危機に晒されてきた彼ら小国が、今回の戦いに時代の潮目を嗅ぎ取ったことは不思議ではない。
特に皇国の北や西に位置する国にとっては、まさに国家の存亡を懸けた一大事だろう。
かの男は、北の都市〈ウィルマグス〉とその周辺地域を奪取、後に停戦交渉により正式な皇国の国土として併合し、帝国との国境を北に押し上げた。
その結果、皇国と国境に接することとなった皇国北方の小国家は、これまでと同じように帝国側に付くか、その帝国を破って勢いに乗る皇国に付くかで真っ二つに分かれている。
皇国から連合軍が引き揚げたあとの西方も、皇国という共通の敵を失った諸国が再びお互いを潜在的敵国と見て牽制し合う状況に変わった。こちらでもまた、皇国に擦り寄る国家がちらほらと姿を見せている。
ほんの数カ国の大国と、多数の中小国で形成された連合。大国が互いにいがみ合えば、中小国は火の粉を恐れてどこかの傘の下に逃げ込もうとする。
そして幸運なことに、彼ら中小国の近くには、常に大きな傘を広げた大国がいる。
〈アルトデステニア皇国〉というその国は、彼らに対して大いに寛容であった。傘の下に入り込んだ国に対し、たとえ昨日の敵であっても古い友人のように温かく迎える。
それこそが、皇国の外交手法のひとつであった。
強い力を持った相手には警戒を怠らない皇国だが、庇護を求める中小国には相手が恐縮するほどの手厚い待遇を惜しまない。そのような待遇が、仮想敵国の懐柔や経済市場拡大を目的としていても、相手もまた多くのものを得る。
つい先日行われた北の小国との通商協定でも、相手側が過分と思うような条件で締結している。皇国としては新たに自国領土となった地域の安全を確保し、そこから生み出される諸々の商品を安全に流通させるためのものであった。
皇国は彼らから搾取はしない。その代わり、国家の安全と新たな市場を買う。
それは他国から見れば不思議なことかもしれない。巨万の富を持つ皇国といえども、その富は有限なのだ。分け与えてばかりでは、いつか金蔵の底が見えてしまうであろう、と。
しかし、話はそう単純なものではない。一方的に与えるだけと思っていると、思いもよらないところから与えられることもある。逆に与えられているつもりが、それ以上のものを与えてしまっている場合もある。
そんな『経済』という生き物の存在にいち早く気付いた者が、皇国にはいた。
それが、この部屋の主だ。彼女は、分かりやすい目先の利益ではなく、もっと遠くの大きいものを見つめることが、『経済』とうまく付き合う基本と考えているのだ。
「ふふん、今日もヴィストーレの連中は皇城参拝かな」
顔の横に浮かんだ表示窓をちらと横目で確認し、小さく笑みを浮かべる。
ヴィストーレ半島の国々の大使が皇城に日参するようになってもうひと月だ。
実際のところ相手が小国であれば、協力関係を結ぶことに大した手間はない。皇国はこれまで数多の国と協力関係を築き上げ、現在に至っている。
その間に行われた交渉は皇国に信用を与えており、これまでと同じように、ほぼ習慣となった遣り取りで諸々の条約を締結してしまえば良い。そうしないのは、相手に軽んじられていると思わせないためだ。
「まあ、貰うものは貰うけど――あっちもこれぐらい簡単に話が済めばな……でも無理だよねぇ」
現在外務院に持ち込まれている他国との協定案件の内、二つだけはこういった機械的な対応が適用できない。
なにせ、それを持ち込んできた国家は、片や皇国の六倍以上の国土面積と皇国を上回る国力、そして大陸最強の陸軍力を持った軍事大国。
片や純粋な国力こそ皇国に劣るものの、他国に『栄誉ある孤立』と称される非同盟半鎖国政策を行い、その上でアルマダ大陸最大規模の海軍を保有。その海軍力でもって広大な海上交易路を保持している海洋大国だった。
彼らはレクティファールとの個人的な繋がりを作り国家間の利益に結び付けようと、外務院の職員たちを不眠不休の超過労働に追い込んでいる。
前者とは正式な国交がない故に臨時の全権大使を派遣し、後者は相手国に駐在中の大使が交渉の任に当たっているが、共に中々侮れない敵手のようだ。
それも当然といえば当然だ。両国とも皇国に比肩しうる大国で、それぞれ多くの経験を持っている。一筋縄でいくはずもない。
外務院としては、できるならかの男の帰還までにある程度形にしておきたかったが、難しそうである。本人に色々確認すべきこともある。この国の外交権は、たったひとりに握られているのだから。
「――全く、面白いったら無いわね」
呟き、読んでいた本を閉じると、彼女はふわりと浮かび上がる。
窓から差し込んだ光が、彼女の姿を映し出す。
「どいつもこいつも、てんやわんやで余裕のないこと」
濃い緑の髪と、同じ色の瞳、そして、子どものように小さな体躯と薄紫の特徴的な翅脈を持つ三対六枚の透き通った翅。
〈妖精〉。
彼女はそう称される一族の者だった。
幼少の頃、彼女の一族と、交友のある人間種の一族との取り決めで〝取り替え子〟となり、以降ヒトの社会で暮らし続けてきた。
既に二〇〇〇年、この国を見詰め続けている。
昔はもっと気楽な、名前だけ同じ名誉職という立場であったが、いつの間にかその名の通りの要職に就けられてしまった。それでも暇を潰すには都合がいいということで、今の仕事はかれこれ四五〇年程度続けている。
これまで、かの男の前任者三人に仕え、内ひとりは早々に見限った。
これで四人目となるが、さて、どうなるだろうかと彼女は思う。
「あいつみたいな阿呆、もう二度と現れないのかなぁ……」
小さな手で窓に触れ、空を見上げながら彼女は呟いた。
人々が初代皇王と呼ぶ男。
彼女がヒトの社会に放り込まれた頃に出会った男。
初めて、自分の番として意識した男。
そして、自分を置いてさっさと逝ってしまった男だ。
半物質生命体の妖精族と違い、たとえ皇剣使いであってもヒトは死ぬ。それこそあっさりと、眠るように。
「まあ、いいか」
くるりと部屋の中を一周し、彼女は扉に向かう。
扉を開けて振り返ると、そこには、いつかこの部屋で自分を膝の上に乗せて物語を読み聞かせてくれた男の幻が見える。
太陽のような笑顔と、真っ直ぐな気性。
馬鹿だ馬鹿だと仲間に言われ続け、それでもこの国を創り上げた。
多くの男女が彼に惹かれた。それは友としてであり、想い人としてであり、そして連れ合いとしてであった。
彼女が、自分の内にあるもっとも大きなそれがどれであるのか気付いた頃には、もう彼は逝く直前であった。
自分の想いに気付き、少し大人になった彼女は、それでも出会った頃のままの少し馬鹿な妖精の振りをして彼を見送った。
彼を最後に笑顔にしたのは、彼女だった。
いつも通り馬鹿なことを言い、彼を笑顔で逝かせた。
そのことが、それからの彼女の誇りになった。
やがて、彼と共に戦った人々がひとり、またひとりと旅立った。
ある者は世界を見に、ある者は故郷に帰り、ある者は死出の旅に。
いつしか、この皇城には彼女以外に彼を直接知る者はいなくなった。
そんな彼女自身も、生まれたばかりの頃のことなど今は大して憶えていない。
ただ、彼の最後の笑顔だけが心に焼き付いて、色褪せずに残っている。
「じゃ、行ってくるよ――」
口の中だけで彼の名を呼び、彼女は扉を閉めた。
向かう先は〈星天宮〉の正門。
〈星天宮〉の新たな主を、皇王府総裁として出迎えるために。
◇ ◇ ◇
色とりどりの紙吹雪が舞い、国歌が斉唱される中、レクティファールは白い礼装姿で、鎧を纏った軍馬の上にいた。
彼を取り巻く近衛軍の将兵の内、数名が掲げる国旗と皇王の紋章旗、そして近衛軍の軍旗が、誇らしげに紙吹雪の空に翻っている。
晴れやかな空。清浄な空気。地面を揺らす歓声。
王橋を渡り、皇都外環線の線路を越え、城門を潜って皇都に入った時点で、すでに彼の耳は人々の歓呼の声と歌声に支配されており、自分でも正常な聴覚を維持しているのか分からない状況だった。
「万歳」
それは幾度も繰り返された言葉。
だが、どれだけ叫んでも彼らが満足することはない。
周囲が叫んでいるせいで、やめることができない者もいるだろうが、単に大声を上げる理由としてその言葉を選んでいるだけの者もいるだろう。
皇都が解放され、彼らもまた解放された。
大声で叫ぶという行為は、これまで閉じ込められていた自分たちの境遇から脱する手段でもあるのだ。
以前であれば大声を上げるだけでも生命の危険があった。だが、もうそんな危険はない。それを確かめるために、自分自身にそれを教えるために彼らは叫んだ。
「万歳」
大の男が涙を流しながら叫ぶ。
若い娘が太陽のような笑顔で叫ぶ。
年老いた翁が曲がった腰を伸ばして叫ぶ。
周囲の大人たちの真似をして子どもが叫ぶ。
「万歳」
その言葉は、彼らにとって過去からの解放を意味していた。
「随分、人も戻ってきたようで、結構なことです」
レクティファールは小さく口を動かし、自身の本音を零した。
彼に向けられる歓声は大きく、また多い。それはこの皇都が息を吹き返した証拠であった。
「このまま何ごともなく平穏な生活に戻れればいいのですが……」
レクティファールが進んでいるのは皇都の目抜き通りだ。
巨大な皇都正門から皇城へと向かう、皇都でもっとも幅員の広い大通りの沿道は、集まった市民によって埋め尽くされていた。
手作りの小さな国旗を力一杯振り、人々は口々にレクティファールの名を呼んだ。
それに応えるようにレクティファールは視線を巡らせ、手を掲げた。
彼の姿を目にしたことで、さらに人々の間で連鎖する万歳の声。
五〇〇万の市民が彼を讃え、狂ったように叫んでいる。
生き残った。死んでいない。まだ、生きている。
それだけで彼らは喜ぶのだと、レクティファールは身をもって理解した。
叫び、喉の痛みを感じる。その痛みさえ嬉しい。
死にたくない。だから、生きていることが嬉しい。
生命として当たり前のことだが、人々は死を目の当たりにしないとそれに気付けない。
生きていることが当たり前になってしまったから、突然の死に鈍感になっていた。
そんな彼らに生きることの喜びを教えたのは、当代と次代の皇王。
今では名前を出すことさえ憚られるようになってしまった今上皇王と、民に「万歳」と讃えられる次期皇王レクティファールのふたりだった。
両者の扱いはまさに天と地。
今上皇王と同じ名である者は神殿に乞うて聖名を授けて貰い、それを名乗るようになった。
逆にレクティファールという名は、ここひと月で産まれた新生児の男子に付けられる名として最も多い。名前総てを頂くなど恐れ多いという理由で、一部だけを貰うという親も合わせれば、その数は何倍にも膨れ上がるだろう。
同じ国主という立場でありながら、片や名前さえ葬り去られ、片やまだ代理の立場でありながら歴代の皇と同じだけ敬われ、慕われている。
その理由は何か。
簡単なことだ。疎んじられたか、認められたか。それだけの違いに過ぎない。
才気に溢れ、人々に認められようとした男と、ただ流され、必要なとき必要なだけ必要なことをやったに過ぎない男。
皇という立場に掛ける想いと、この国に対する気持ちは、間違いなく前者の方が大きかったはずだ。
しかし、認められたのは後者。誰かに認められようとは一度も考えなかった男だった。
単に自分にできる範囲で求められることをした。それだけだった。
「それが運だとは、思いたくないが」
万感の想いを込めたその呟きは、人々の歓声の中であっさりと掻き消される。
ほんの少ししか道はずれていなかった。だがその先は天国と地獄ほどの隔たりがあった。
個人の想いではなく、状況こそが人の生き死にを決めるということなのだろうか。
皇都に入る前、ミラ平原を通過している時、すでに皇都に続く街道は人々に埋め尽くされていた。
比較するのも馬鹿らしい戦力差をひっくり返し、帝国領に逆侵攻した英雄を一目見ようと、国中から国民が集まっているのだと、ミラ平原に入る前に近衛軍中隊の中隊長がレクティファールに教えてくれた。
君主と共に凱旋することがどれ程軍人にとって名誉なことなのか、彼はレクティファールが困った顔をしていることにも気付かず延々と語り続け、副官に窘められてようやく正気に返った。
自分の行動を振り返って恐縮する中隊長を宥め、レクティファールは馬上の人となったのだ。
そうして馬に揺られて幾時間、彼は大歓声の中をゆっくりと進んでいる。隣に陸軍の第一種礼装を纏った女性参謀を伴い、胸を張り、努めて威厳を保とうとしていた。
「リーデ、まだ慣れませんか」
「は、はい。流石にこうも人の目が多いと……」
彼女は要塞を離れられないガラハの名代として、そしてレクティファールと共に戦った勇気ある側妃候補として、この式典に参加している。
同じ妃候補であるメリエラが、傷に負担をかけないよう馬車での移動となったため、急遽リーデがレクティファールの随伴者となったのだ。
本来なら式典後に側妃となることを正式に発表する予定だったのだが、すでに陸軍の女性参謀が側妃入りするという噂が流れていることもあり、改めて発表する必要はないのかもしれない。
時折、「妃殿下万歳」の声が聞こえてくることもあり、リーデの顔は先程から真っ赤に染まったまま元に戻らない。
あっちにふらふら、こっちにふらふらと視線を彷徨わせ、全力で羞恥心を抑え込んで小さく手を振っている。
もう少し大きく振らないと遠くの人には見えないのではなかろうかと、レクティファールは思ったが、年上の女性が必死になっている最中に言うことではないだろうと自重した。
それでも微妙に生暖かい視線になってしまうのは、まあ、仕方の無いことなのだと思うようにする。
「殿下……その……馬車に入っても……」
「駄目でしょうね。ガラハ中将の名代でもありますし」
「あうぅ……」
実のところ、先の戦争の英雄ガリアン・アーデンの娘が皇太子の寵を受けたことも、民の熱狂の一因となっていた。
英雄を父に持ってはいるものの一介の士族であり、立場としては平民とさほど変わらないリーデ。
そんな彼女が新たな英雄であるレクティファールと想いを交わし、こうして側妃として〈星天宮〉に上がることは、ごく普通の市井の女性にとって、舞台で演じられる物語のようにも思えるらしい。従って彼女たちがリーデに憧憬と嫉妬の入り交じった視線を向けるのも、ある意味では仕方の無いことだった。
11
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

娼館で元夫と再会しました
無味無臭(不定期更新)
恋愛
公爵家に嫁いですぐ、寡黙な夫と厳格な義父母との関係に悩みホームシックにもなった私は、ついに耐えきれず離縁状を机に置いて嫁ぎ先から逃げ出した。
しかし実家に帰っても、そこに私の居場所はない。
連れ戻されてしまうと危惧した私は、自らの体を売って生計を立てることにした。
「シーク様…」
どうして貴方がここに?
元夫と娼館で再会してしまうなんて、なんという不運なの!

私が死んで満足ですか?
マチバリ
恋愛
王太子に婚約破棄を告げられた伯爵令嬢ロロナが死んだ。
ある者は面倒な婚約破棄の手続きをせずに済んだと安堵し、ある者はずっと欲しかった物が手に入ると喜んだ。
全てが上手くおさまると思っていた彼らだったが、ロロナの死が与えた影響はあまりに大きかった。
書籍化にともない本編を引き下げいたしました

魔王を倒した手柄を横取りされたけど、俺を処刑するのは無理じゃないかな
七辻ゆゆ
ファンタジー
「では罪人よ。おまえはあくまで自分が勇者であり、魔王を倒したと言うのだな?」
「そうそう」
茶番にも飽きてきた。処刑できるというのなら、ぜひやってみてほしい。
無理だと思うけど。

もう無理して私に笑いかけなくてもいいですよ?
冬馬亮
恋愛
公爵令嬢のエリーゼは、遅れて出席した夜会で、婚約者のオズワルドがエリーゼへの不満を口にするのを偶然耳にする。
オズワルドを愛していたエリーゼはひどくショックを受けるが、悩んだ末に婚約解消を決意する。
だが、喜んで受け入れると思っていたオズワルドが、なぜか婚約解消を拒否。関係の再構築を提案する。
その後、プレゼント攻撃や突撃訪問の日々が始まるが、オズワルドは別の令嬢をそばに置くようになり・・・
「彼女は友人の妹で、なんとも思ってない。オレが好きなのはエリーゼだ」
「私みたいな女に無理して笑いかけるのも限界だって夜会で愚痴をこぼしてたじゃないですか。よかったですね、これでもう、無理して私に笑いかけなくてよくなりましたよ」

本物の夫は愛人に夢中なので、影武者とだけ愛し合います
こじまき
恋愛
幼い頃から許嫁だった王太子ヴァレリアンと結婚した公爵令嬢ディアーヌ。しかしヴァレリアンは身分の低い男爵令嬢に夢中で、初夜をすっぽかしてしまう。代わりに寝室にいたのは、彼そっくりの影武者…生まれたときに存在を消された双子の弟ルイだった。
※「小説家になろう」にも投稿しています

魔王を倒した勇者を迫害した人間様方の末路はなかなか悲惨なようです。
カモミール
ファンタジー
勇者ロキは長い冒険の末魔王を討伐する。
だが、人間の王エスカダルはそんな英雄であるロキをなぜか認めず、
ロキに身の覚えのない罪をなすりつけて投獄してしまう。
国民たちもその罪を信じ勇者を迫害した。
そして、処刑場される間際、勇者は驚きの発言をするのだった。

王子を身籠りました
青の雀
恋愛
婚約者である王太子から、毒を盛って殺そうとした冤罪をかけられ収監されるが、その時すでに王太子の子供を身籠っていたセレンティー。
王太子に黙って、出産するも子供の容姿が王家特有の金髪金眼だった。
再び、王太子が毒を盛られ、死にかけた時、我が子と対面するが…というお話。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる
本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。
このユーザをミュートしますか?
※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。
※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。
※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。