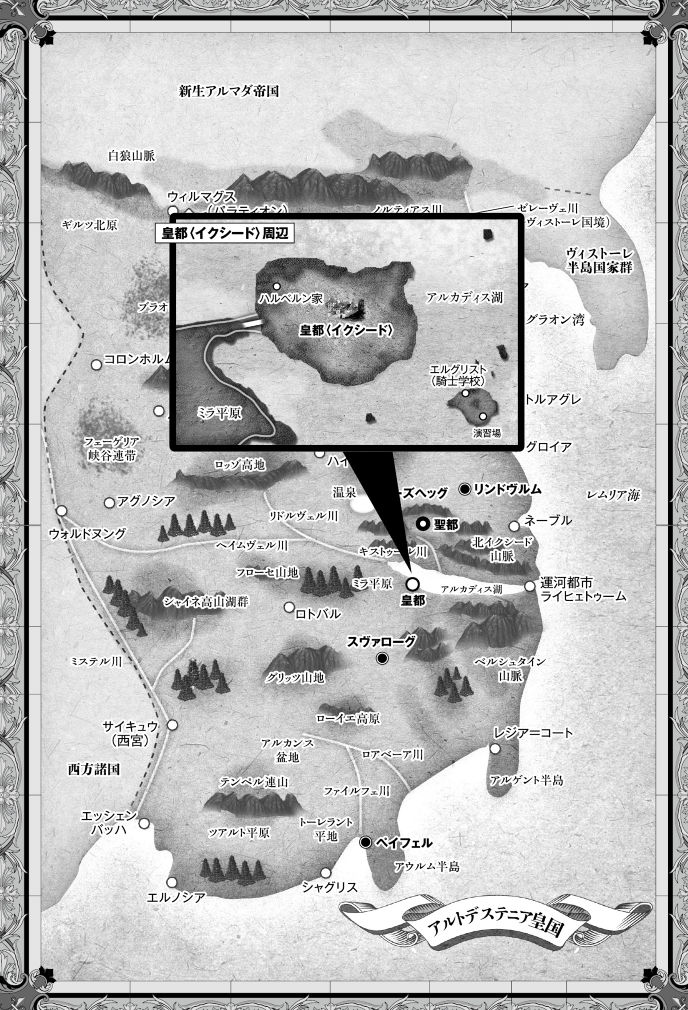177 / 526
12巻
12-1
しおりを挟む歴史も、文化も、精神さえも、国家の振るう暴力の前に潰えていく。
権力とは本来本能的であり、理性によってのみこれを制御することができる。
その理性による制御の術こそが、政治である。
ならば、正しい政治とは何か。
それを追い求める姿勢だけが、現状でもっとも正しい政治だと言えよう。
我らが己を呼び習わす名、『知恵ある者ども』。
来るべき危機に備え、その名の通りに知恵を出し、周囲と協調し、そして決断せよ。
かの世界は、既に我らが故郷と互いに引き寄せ合う距離にまで近付いている。
逃げ道などありはしない。
総ての指導者たちは、己の本当の使命を果たせ。
血統によって選ばれたとしても、選挙によって選ばれたとしても、等しく与えられたとしても、その手にある権力はただひとつの使命、『生き残る』ためにある。
――年代不明 皇国北部第一次文明ミルアルダ遺跡群の壁画文より抜粋
第一章 勝者なき戦い
アルマダ大陸西域ミリストレア国マルトハ沖。
そこに、皇国海軍遣西艦隊とは別の目的を持って派遣された艦がいた。
彼女の名は汎用観測艦〈ランドリッサー〉。
表向きは海底地形や潮流、沿岸地形の調査などを行う艦だ。複数種の探測儀を並べ、そこを半円筒の屋根で蔽った上甲板と、艦首と両舷側に据えられた観測用の海底伝纜敷設装置のせいで、軍艦としてはかなり特異な形状を持っている。
非武装のこの艦は、皇国海軍艦艇の西域派遣に伴う様々な環境調査任務を課せられていた。だがその実、西域周辺の雑多な通信情報や軍事情報の収集を行う密偵艦でもあった。
もちろん、周辺国もこの艦の正体には勘付いている。ただ、自国の領海外で行われる調査行動を掣肘することはできず、時折沿岸警備船などを近付けては様子を窺うのみだ。
皇国側も、それらの艦船に対して高圧的な行動に出ることはなく、無力な観測艦のふりを続けている。艦を取り巻く状況は、西域にある国々の皇国に対する、等しい信頼と不信を象徴しているとも言える。
この艦は決して自分たちに攻撃を仕掛けないだろうという信頼と、この艦の国は決して自分たちを信頼しないだろうという不信。
ただ、信頼と不信の共存は、何処の国同士でも変わらない。
信頼と不信は硬貨の裏表のごとくであり、くるくるとどちらの面を相手に見せるかによって、両者の関係は変化する。どちらかに偏っている事例は、あまりない。たとえ、戦争が始まったとしても。
〈ランドリッサー〉の乗員たちは、時折下される戦闘配置のときにそのことを思い出し、配置が解除されると忘れてしまう。それを繰り返しながら、彼らは任務を遂行していた。
「ふあぁ……」
〈ランドリッサー〉の艦内奥深く、重防護区画に指定された一角にある薄暗い情報分析室で、海軍曹長の階級章を付けた分析官のひとりが、口を押さえて欠伸をした。
隣で海底潮流探測伝纜の管制をしている同僚が、ちらりと彼を見た。
「茶を入れてくるよ」
そう言ったのは、欠伸をした分析官だった。ライフェール・カカリアといい、今年で勤続五年目。ようやく威張れる相手が現れ始め、最近はそれなりに余裕のある態度を取ることができるようになった。
「お前もいるか?」
取り繕うようにそう問えば、同僚は「砂糖ひと匙」とだけ言って、管制用表示窓に視線を戻した。ライフェールは肩を竦め、分析器からの警報音を聞くための無線式遮音付発音器を被ったまま席を立つ。
分析室の責任者である海軍大尉がちらりとライフェールを見たが、これは服務規程で禁止された行動ではない――そもそも生理的に何時間も椅子には座っていられない――ため、声を掛けてくることはなかった。
ライフェールは、分析室の奥まったところにある給湯室に入ると、自動給仕器の釦を押して、軽量磁器製の磁碗に自分と同僚の黒豆茶を入れた。
以前はお湯を沸かしていたというが、いくら巨大とはいえ艦船は揺れるものである。
最初は精密装置のある区画に軽食や飲料の自動給仕器が設置されるようになり、やがてほとんどの区画から発熱器と薬缶が消えた。
今では、来客を迎えることのある士官居住区と、食堂区画に残るばかりだ。
ライフェールは、同僚の磁碗に砂糖をひと匙入れて、溢れ防止の蓋を閉めた後、ふたつの磁碗を持って給湯室を出た。
「ほら」
「ああ、ありがとう」
同僚は磁碗を受け取ると、蓋の一部を開いて黒豆茶を啜った。自動給仕器の黒豆茶の味は、その給仕器を管理する艦の給養員の腕次第だ。〈ランドリッサー〉の給養員は、少なくとも自動給仕器を操る分には、それなりの腕前であった。
(異常なし、と)
ライフェールは自分が担当する次元干渉計の表示画面を見詰め、常と変わらない細波が映っているだけだと確認して大きく息を吐いた。
季節や時間毎に変化する次元波動だが、一日の間に急激な変化を見せることは少ない。だからこそ、異常を検知するために有用とされているのだ。
もっとも、それを監視する側にとっては、退屈極まりない仕事である。海底潮流や海温測定、音響観測ならばと思うことも度々あった。
今日もこのままろくな変化を見ることなく、交代することになるのだろう。
ライフェールはそう思い、ふと時計を見た。
交代まであと二時間だった。
そして、交代まであと一時間と迫った頃、ライフェールが被っていた発音器に警報音が交じった。
「――!?」
最初は艦全体に発せられているのかと思った。だが、隣にいる同僚は、びくりと身体を震わせたライフェールを訝しげに見るだけで、焦った様子はない。
ならば自分だけかと観測画面を見たライフェールは、次元干渉計の表示画面に異常を見付けていた。
自然状態であれば、表示された波形は小さく揺れるだけだが、今は波紋が広がっている。それは、波紋の発生源で強い次元干渉力が発生したことを示している。大抵の場合は大規模な魔法や大型の魔導生物の活動に起因するものだった。
「訓練計画も魔導実験の兆候もなし。とすると、なんだぁこりゃあ」
制御盤を打鍵し、画面を次々と切り替えていく。
同時に、艦上の大半を占める半円筒形の蔽いの中で、気象探測儀に擬装されている次元探測儀が、次々と波紋の発生源と見た東を指向した。
その頃になると、彼の背後に当番士官である大尉が現れ、同じように画面を見詰めている。
「方位は?」
「〇―八―九。ほぼ真東です」
ふたりが言葉を交わしている間にも、波紋は次々と現れては〈ランドリッサー〉の上を通過していく。もし、次元波動に敏感な種族がここにいたら、自分の身体を通過する波にも気付いたかもしれない。
「通信班!」
大尉は首に引っ掛けていた集音器にそう叫び、二階構造となっている分析室の下段にいる通信分析班を呼んだ。
『はい』
階下からの声は、ライフェールの耳を蔽う発音器にも入ってくる。
「そっちに異常は?」
何らかの軍事行動であれば、周辺の国々の政府や軍の間で通信が活発化する。内容までは分からなくとも、何かが起きたということは分かるのだ。
『先刻の帝国西部での一時的な通信増大以外には何も――いえ、これは……』
「どうした?」
『民間通信が活発化しています』
「民間?」
大尉は顎に手を当て、現状にもっとも即した予想を立てようとした。しかし彼が答えを出すよりも早く、分析室の水密扉が開く。
大尉は、そこから姿を見せた人物に少し驚いた。
「艦長」
「室長、何があった」
略帽を脇に抱えて鉄鼠色の髪を纏めながら入ってきた女性は、この艦の責任者だ。前職は給兵艦の艦長を務めていたというが、その声は良く通って力強く、大尉の背筋は自然と伸びた。
畳まれていた略帽を広げて被り、艦内服の襟を整えている艦長に、大尉が報告する。
「正体不明の次元波動を検知。同時に、西域各地で民間の通信量が増大しています」
「――次元波動、なるほど」
略帽を被った艦長は頷くと、妙に納得した様子を見せた。
「わたしが見たものと同じものを、他にも大勢の人々が見たということだな」
「は、あの、それは……」
「全員が全員ではないだろうが、子を持つ母なら飛び起きるさ」
我が子が死んでいく様を見せ付けられて、黙っていられる母などいるものか――艦長はそう小さく呟き、胸元の物入れを押さえた。
そこには、彼女がふたりの子供とともに撮った写真が入っている。
「あの……艦長?」
「ん? ああ、そうだな、次元波動の記録を取りつつ、通信分析を行え。波動そのものは我々には手に余る。それよりも、この事態に各国政府がどう対処するか見ておきたい」
民間通信の異常増大は、戦時でも災害時でもあり得ることだが、その対処に関する行政通信や軍事通信を分析すれば、周辺国の政府機構の練度をかなり正確に測ることができる。
艦長の軍人としての意識は、既にそちらに移っていた。彼女の本質的な任務は、西域諸国の情報収集なのだ。
「はい」
大尉が通信班のもとに走っていく姿を見送り、艦長は分析室の正面壁にある大型表示板を見た。
東方から広がる次元波動は、少しずつ弱まっているようだった。
(波は情報を持つ。そして、波動を受けた者たちの脳は情報を再生し、夢を見せる)
それは、夢魔族などが行っている精神感応系魔法の基礎理論だ。
他者の精神に直接侵入するよりも簡単に、相手に望む夢を見せることができる。ただ通常は、間違っても一地方を丸ごと覆い尽くすような規模ではない。
それだけの純粋熱量を持つのは、国家というものに与しない上位の魔族や天族、あるいは神族、そして龍族といった上位種だけだ。
「何が起きている」
そう呟きながら、彼女は胸を満たす悲しみの根源を探した。
この波動の中心には、我が身を引き裂かれるよりも辛く悲しい感情に支配された存在がいる。その存在は悲しみを撒き散らし、それでもなお自分の抱く苦痛から逃げ出せずにもがいているのだ。
「分かるさ、分かるとも」
艦長は部下たちが忙しなく動き回る様子を眺めながら、そう呟いた。
しかし、他者から理解されても、当人が救われるとは限らない。
救いとは、誰かを救おうという意志と、自ら救われようという決意がなければ成立しないのだ。
この日の深夜。西域全体を覆い尽くした正体不明の次元波動について、その正体を解き明かした者はいなかった。
ただし、各地で発生した通信量の増加については、原因が判明している。
膨大な通信の中心には女性たちがいた。彼女らの証言によると、個人差はあるものの、我が子を失う苦痛を感じたという。とりわけ強く感じた者たちは、同居していれば我が子を見て涙を流し、離れて暮らしていれば声が聞きたくて通信を送った――ということだった。
これらの混乱について、西域各国は思念兵器の存在を疑う声明を発したが、そのようなことを実現できる国家は現時点で存在しておらず、単なる疑惑のひとつとして扱われた。
真相は明らかになることがなく、この夜の一件は人々の記憶の中から消えていく。
人々の内に残ったものは、疎遠になっていた親子が取り戻したいくらかの関わりのみであった。
◇ ◇ ◇
既に高度は五〇〇を超えている。眼下には総てを呑み込みそうな真っ黒い森林が広がり、少し離れた盆地にぽつりぽつりと街の灯りが見えた。
そこには、多くの人々の暮らしがある。
そして、目の前には理性をなくした一匹の龍――シヴェイラがいる。
街に住むのは、レクティファールとは無関係の――彼が権利の代償としての責任を負っていない人々だ。彼自身、彼らを巻き込んだとしても必要な犠牲として割り切ることはできる。しかし、かつて皇国の民であったシヴェイラに同じことはさせられない。彼女にはその権利がない。
レクティファールは、いずれ義母になるであろう女性に対し、個人としてだけではなく、君主としても責任を背負っているのだ。
彼には国民を戦いに差し向ける権限がある。しかし、その戦いは皇国の利益のためにのみ行われるべきもので、決して私闘であってはならない。
シヴェイラに他国の人命や財産を損なわせるのは、自らの責任に背くことになる。彼女が追放された存在だとしても、それが皇王の手で下された処分である以上は、レクティファールは責任から逃れられないのだ。
「これ以上、あなたに何かを奪わせるわけにはいきません」
レクティファールはもう、シヴェイラが何かを奪う事態を許容することはできなかった。
だが彼は、遠目に見える他国に住む人々の暮らしを守ろうとしているわけではない。それを傲慢と取るか、冷徹と取るかは、人によって異なるだろうが、人々を守ることはレクティファールにとって自国を守る手段でしかない。
奪えば、いずれ奪われる。だから、奪われないために、相手からその意志を消失させる。奪うことが自分たちの損失を招くと教える。それだけのことである。
なぜなら、彼の責任は、彼を皇王と仰ぐ人々の信認の上に成り立つものであったからだ。周辺友好国との安定した関わりは、国民の生活に影響するからこそ維持されているもので、決して周辺国そのものに対する責任を果たしているわけではない。
皇国から遠く離れたこの地の場合、「周囲に配慮する」ということは、すなわち事態を可能な限り隠蔽することで諸国に介入を躊躇させる手段にすぎない。そこにあるのは、やはり皇国の民への責任のみであった。
「死して祖国の礎となるか、生きて娘の礎となるか、あなたはどちらですか」
剣の鋒を向け、その先に幾重もの魔法陣を掲げた。
彼の身長よりも遥かに大きな魔法陣に、周囲の魔力が収束していく。皇国に較べて周囲の魔素は薄かったが、魔法の行使に影響が出るほどではない。
シヴェイラはここにきて、ようやくレクティファールの存在に気が付いたようだった。
大きく口を開き、吼え、空気を揺るがせながら、彼に向かって突っ込んできた。
「フェリスにも、オリガにも、フェリエルにも、ファリエルにも、他の誰にも討たせない」
討てば悲しみを背負う。
失った悲しみに加え、討った悲しみも背負う。
それを、レクティファールは許容できなかった。
我侭だと理解してなお、許容できなかった。
「だから、私に討たれてください」
その宣言通り、極太の光条が幾つもシヴェイラに向かって放たれた。
「――ッ!」
空気を震わせる爆光。
光条は互いに干渉して絡み合い、一本の巨大な光軸となった。白の魔力光が夜空を裂き、巻き込まれた空気中の魔素とともにシヴェイラに殺到した。
最も相対速度の速い方向からの一撃。回避行動を取る暇もなく、光はシヴェイラを直撃する。
「――!!」
シヴェイラは甲高い鳴き声を上げ、煙を曳いて落ちていく。
レクティファールはそれを追った。
「――さすがに、これでは落ちませんか」
確かに煙を曳いて落下していたシヴェイラだが、空中の一点で大きく翼を広げて、体勢を立て直した。そのまま風に乗ってレクティファールと相対する。
焼かれ、削り取られた表皮の損壊は、白い煙とともに癒され、しかし完全には治りきらずに爛れている。身体を構成するための種々の情報が壊れつつあるのだ。
先ほどよりもなお醜い姿となったシヴェイラは、大きく開いた口腔に光を集めていた。
「〈龍の吐息〉か!」
レクティファールは忌々しげに叫び、大きく腕を振って〈皇剣〉に纏わりつく魔素の残滓を振り払った。光の粒が舞い散り、レクティファールの横顔を照らし出す。
「来るか」
シヴェイラの口腔に集まった紅の魔力、それは集束を終えて一拍を置き、正確にレクティファールへ向けて放たれた。
先ほどのレクティファールの魔法よりも巨大な光の濁流が、彼に向かってくる。制御の甘い魔素の流れは、周囲の空気の流れを乱し、轟音を発していた。
「龍族の本気、そういうことですかね!」
剣を縦に構え、そこに魔力を集中させることで、レクティファールは光の濁流を斬り裂いた。
斬り裂かれた光が夜空に飛び散り、輝く。
〈紅空の朔〉の表面が、残留魔力で灼かれる。それ以外にも各箇所が異常を起こして、警報がレクティファールの視界を飛び交い、彼の神経を逆撫でした。
「うるさいッ!」
警報を総て切断し、レクティファールは〈龍の吐息〉の最大発射によって敵を見失っているシヴェイラに迫った。
刺突の構えで剣を持ち、そのままシヴェイラへと向かっていく。
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

娼館で元夫と再会しました
無味無臭(不定期更新)
恋愛
公爵家に嫁いですぐ、寡黙な夫と厳格な義父母との関係に悩みホームシックにもなった私は、ついに耐えきれず離縁状を机に置いて嫁ぎ先から逃げ出した。
しかし実家に帰っても、そこに私の居場所はない。
連れ戻されてしまうと危惧した私は、自らの体を売って生計を立てることにした。
「シーク様…」
どうして貴方がここに?
元夫と娼館で再会してしまうなんて、なんという不運なの!

私が死んで満足ですか?
マチバリ
恋愛
王太子に婚約破棄を告げられた伯爵令嬢ロロナが死んだ。
ある者は面倒な婚約破棄の手続きをせずに済んだと安堵し、ある者はずっと欲しかった物が手に入ると喜んだ。
全てが上手くおさまると思っていた彼らだったが、ロロナの死が与えた影響はあまりに大きかった。
書籍化にともない本編を引き下げいたしました

もう無理して私に笑いかけなくてもいいですよ?
冬馬亮
恋愛
公爵令嬢のエリーゼは、遅れて出席した夜会で、婚約者のオズワルドがエリーゼへの不満を口にするのを偶然耳にする。
オズワルドを愛していたエリーゼはひどくショックを受けるが、悩んだ末に婚約解消を決意する。
だが、喜んで受け入れると思っていたオズワルドが、なぜか婚約解消を拒否。関係の再構築を提案する。
その後、プレゼント攻撃や突撃訪問の日々が始まるが、オズワルドは別の令嬢をそばに置くようになり・・・
「彼女は友人の妹で、なんとも思ってない。オレが好きなのはエリーゼだ」
「私みたいな女に無理して笑いかけるのも限界だって夜会で愚痴をこぼしてたじゃないですか。よかったですね、これでもう、無理して私に笑いかけなくてよくなりましたよ」

王子を身籠りました
青の雀
恋愛
婚約者である王太子から、毒を盛って殺そうとした冤罪をかけられ収監されるが、その時すでに王太子の子供を身籠っていたセレンティー。
王太子に黙って、出産するも子供の容姿が王家特有の金髪金眼だった。
再び、王太子が毒を盛られ、死にかけた時、我が子と対面するが…というお話。

最難関ダンジョンをクリアした成功報酬は勇者パーティーの裏切りでした
新緑あらた
ファンタジー
最難関であるS級ダンジョン最深部の隠し部屋。金銀財宝を前に告げられた言葉は労いでも喜びでもなく、解雇通告だった。
「もうオマエはいらん」
勇者アレクサンダー、癒し手エリーゼ、赤魔道士フェルノに、自身の黒髪黒目を忌避しないことから期待していた俺は大きなショックを受ける。
ヤツらは俺の外見を受け入れていたわけじゃない。ただ仲間と思っていなかっただけ、眼中になかっただけなのだ。
転生者は曾祖父だけどチートは隔世遺伝した「俺」にも受け継がれています。
勇者達は大富豪スタートで貧民窟の住人がゴールです(笑)

魔王を倒した手柄を横取りされたけど、俺を処刑するのは無理じゃないかな
七辻ゆゆ
ファンタジー
「では罪人よ。おまえはあくまで自分が勇者であり、魔王を倒したと言うのだな?」
「そうそう」
茶番にも飽きてきた。処刑できるというのなら、ぜひやってみてほしい。
無理だと思うけど。

愛された側妃と、愛されなかった正妃
編端みどり
恋愛
隣国から嫁いだ正妃は、夫に全く相手にされない。
夫が愛しているのは、美人で妖艶な側妃だけ。
連れて来た使用人はいつの間にか入れ替えられ、味方がいなくなり、全てを諦めていた正妃は、ある日側妃に子が産まれたと知った。自分の子として育てろと無茶振りをした国王と違い、産まれたばかりの赤ん坊は可愛らしかった。
正妃は、子育てを通じて強く逞しくなり、夫を切り捨てると決めた。
※カクヨムさんにも掲載中
※ 『※』があるところは、血の流れるシーンがあります
※センシティブな表現があります。血縁を重視している世界観のためです。このような考え方を肯定するものではありません。不快な表現があればご指摘下さい。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる
本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。
このユーザをミュートしますか?
※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。
※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。
※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。