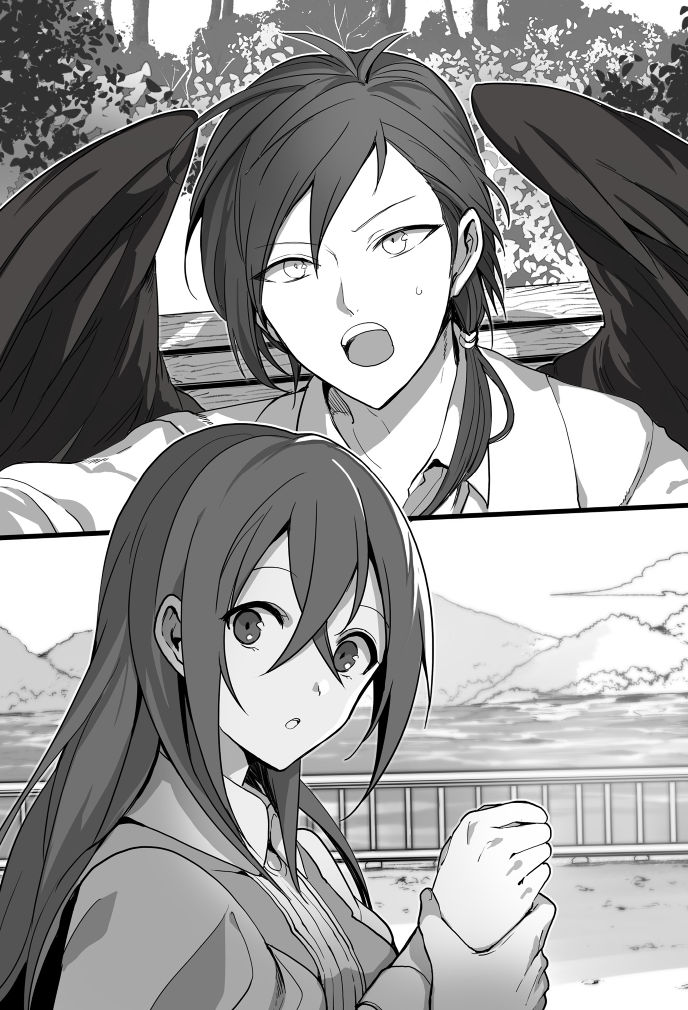209 / 526
14巻
14-1
しおりを挟む多くの苦難を乗り越え、彼らは父祖の地へ帰ってきた。
それが望まれた帰還ではないことに気付きながらも。
世界は変わってしまっていた。
周囲に彼らが記録していた星座はすでになく、見慣れた蒼い星はまったく別の形に変化していた。
四つの強固な次元障壁に阻まれ、多くの犠牲を払いながら辿り着いた故郷は、かつての故郷ではなくなっていた。さらには、星を守るようにして幾体もの守護者が配置されており、地上に降りることは困難だった。
守護者との戦いに敗れた彼らは、宇宙の彼方に新天地を求めて旅立った同胞たちの元へ帰るしかなかった。
だが、彼らは自分たちの故郷に自分たちの記憶を残したいと願った。そして、比較的損傷が軽微だった十六隻の艦に自らの記録を残し、惑星へと送り込んだ。
半数以上が、守護者によって撃沈されるか、推進力を失って衛星へと落ちた。
そして片手で教えられるほどになった彼らの艦は、やはり大半が惑星へと落ちる途中で砕けた。
地上まで辿り着いたのは、僅か二隻のみだった。
――銀河暦五二〇年 銀河移民船〈出雲〉『遙かなる故郷への追憶』より抜粋
第一章 新星
公都〈リンドヴルム〉の街並みは、想像していたよりも遥かに整っていた。
首都である〈イクシード〉に較べれば、いささか古風でこぢんまりとした印象を感じさせるものの、傍らにある名勝水精湖との組み合わせは、この地が皇国有数の観光地であることを納得させた。
「あれが白龍宮か」
街の片隅にある湖畔の公園。その長椅子に座っている有翼人の少年は、街からすこし離れた場所にある白亜の城を見詰めて呟いた。
四つの公都のうち、構造的に見てもっとも軍事色が薄いのが〈リンドヴルム〉だ。
都市としての規模も決して大きくなく、人口のみで考えれば皇国の上位十都市に辛うじて数えられるに過ぎない。
だが、ここを治める人物が皇国でもっとも権威ある貴族であることを、少年は知っていた。
白龍公カール・フォン・リンドヴルム。貴族の中の貴族と呼ばれる龍の貴顕。
(少なくとも、母上を王都から追い遣った者たちとは較べものにならないだろうな)
顔を顰め、じっと城を見据える。
リンドヴルム公爵領は決して、裕福な土地とは言えない。面積も、少なくとも他の三人の公爵の所領に較べれば小さなものだ。大身で知られる幾人かの侯爵と較べても、見劣りするかもしれない。
しかし俯瞰して見れば、この地が皇都に向かうための街道の要衝にあり、周囲を山々に囲まれている天然の要塞であることに気付く。
リンドヴルム公爵家は、率先して皇都の盾になる場所を所領として求め、それを認められた。より正確に言うならば、縄張りであった場所を皇王家に譲り、生まれ故郷の片隅を所領としたのだ。
その事実ひとつをとっても、リンドヴルム公爵家が貴族としての気質を備えていることが分かる。
また、他の大都市と違って巨大な城壁を築かなかったのは、皇王家に対する謀叛の意思を否定するためだとされている。とはいえそこには、そんなものがなくてもこの地形自体が要害であるため、いたずらに軍都化する必要はなく、なにより民に負担を掛けるような真似はしないという意図もあった。
「あやつは、まだ戻らんか」
師であると同時に唯一の家臣である男が、公都にある商会のひとつに入ってからだいぶ時間が経っている。
この都市の治安は、少年をひとり公園で待たせていてもまったく問題が生じない程度には良かったし、本人もそうした心配はしていない。ただ、胸中に言いようのない寂寥感が溢れてくるのだ。
「何を莫迦な」
あの男は自分を裏切らない。裏切るはずがない。
もしも裏切るならば、もっと前にそうしていたはずだ。自分というお荷物を抱えるには、あの男は優秀すぎる。たとえ祖国に戻ることができないとしても、いくらでも仕官先を見付けることができるはずだった。
「くそっ」
彼は小さく毒づき、木製の長椅子を殴る。
――彼に何者かが近付いてきたのは、そのときだった。
「もし、そこの人」
彼は身体を緊張させ、飛び立つ準備をしながら振り返った。
果たして、そこにいたのは少年と同年代の少女がひとり。
蒼い髪を背中まで伸ばした彼女は、鳶色の瞳で少年を見詰めた。
「体調が悪いのですか? 顔色があまり良くないように見えますが……」
少女の言葉遣いは、大人のそれと何ら違いがなかった。ところどころ舌っ足らずな発音が見られるが、子どもっぽさは感じられない。
そのため、少年は警戒を緩めることができなかった。
(誰だ? 地元の子どもというにはいささか……)
自分を追ってきた誰かかと思ったが、言葉の訛りは皇国のそれである。まったく別の言語を第二言語として用いる〈イズモ神州連合〉が隣にあるせいか、幾つか特徴的な訛りがあるのだ。
もっとも、この世界に独自の言語を持っている国は少ない。少年は少女の言葉を申し分なく理解していた。
「大丈夫だ。何も問題はない」
彼は突き放すような冷たい声音で答えた。これで少女が怯えて立ち去るならば儲けもの、と思っていた。
しかし、彼の予想に反し、少女は全く怯えた様子を見せずに、かえって近付いてきた。
それには少年の方が驚いてしまった。
「でも、あなたはこの街の方ではありませんよね? もしかしたら、旅の疲れが溜まっているのかもしれません」
少女は少年の前に立つと、そっと手を伸ばして彼の額に触れた。
「やめ……っ」
彼女の手を振り払おうと手を上げたが、しかし少年はそれを実行することができなかった。
自分の額に触れる少女の手のひらが、母と同じ温もりを持っていたからだ。
武門の娘なのか、臣下の老将と同じように硬くなった手のひら。だがそこから感じる温かさは、彼が遥か昔に忘れてしまったものだった。
「熱はないようですけど、旅の疲れは本人が気付かないうちに溜まっていくものと聞きます。今日は宿に戻って休まれた方が良いのではありませんか?」
少女は彼の内心など気にすることなく、ただ体調だけを心配している。
彼女生来の気質がそうさせるのか、初対面の少年に対しても全く遠慮がなかった。
(くそ、何だというのだ)
少年は、自分の瞳をじっとまっすぐ見詰めてくる少女に戸惑った。
母が死んで以来、こうして少年と目を合わせる者などいなかったのだ。一瞬視線を交わしたとしても、すぐにその目に宿る狂気に触れて顔を逸らした。
もしも少年が少女の出自を知っていたら、自分の弱さに気付いたかも知れない。
彼が抱く狂おしいまでの復讐心も、千年万年を費やして形成された力ある種族の意識には到底及ばない。そうした者たちの意識に日常的に触れている彼女だからこそ、たとえ幼子であっても少年の眼差しに耐えられたのだろう。
しかし、彼は何も知らなかった。
故に、ただ顔を伏せて言った。
「大丈夫と言いたいところだが、お前の顔を立てておく」
「そうしてください」
少女はそう言って立ち上がった。
「お、おい」
その仕草に慌てた少年が、少女の手を取る。突然手を握られた少女は驚いた様子だったが、彼は一気にまくし立てた。
「俺はまだしばらくこの街にいる。いつもこの公園にいる」
それは年相応の少年らしい、何よりも自らの矜持が先に立つ物言いだった。
会いたい。
たった一言が、素直に口から出せない。
「だから……」
そこまで口にして、少年は自分の言動に強い羞恥を抱いたらしい。
彼は握っていた手を離し、ぷいと顔を逸らした。
「何でもない」
ちょうどそのとき、どこか遠くから人の声が聞こえてきた。
甲高い声は幼い子どものものだろう。少年は声が聞こえてきた方向に目を向ける。すると、少女も同じようにそちらを向いていることに気付いた。
「どうやら、わたしを呼んでいるようです」
「そうか……」
友人が少女を探しているのだろう。少年はそう当たりを付けた。
「さっさと行ってやったらどうだ?」
彼は少女に言い放ち、足を組んで湖に向き直る。
少女は一瞬躊躇ったようだったが、一礼して声の主がいる方向に向けて歩き出した。
そして、しばらく進んで立ち止まり、言った。
「それでは、また」
「――!」
驚き、振り向いた少年は、背筋を伸ばして歩く少女の後ろ姿しか見ることができなかった。
しかしその姿は彼の心に焼き付き、自らの生涯を大きく変化させることになる。
それは同時に、ふたつの国の運命をも左右することになるのだった――
◇ ◇ ◇
皇国議会議事堂は、皇国暦一八九九年に七代目の建物が完成した。レクティファールが摂政としてはじめて議会観覧を行うことになったのは、この建物である。
皇城の添え物扱いされることの多い建物だが、初等学校の研修旅行などでは見学順路に含まれることが多く、国民の認知度は高い。
議事堂にはふたつの議場があり、ひとつは貴族議会議場、もうひとつは国民議会議場と呼ばれている。これらはあくまで俗称であり、公的にはどちらの議会がどちらの議場を使うべしという規定はない。ただ、皇城に近い方の議場を貴族議会が使用し、皇都に近い方を国民議会が使用している。
その国民議会議場で、定例本会議と呼ばれる会議が行われていた。
「軍務院と内務院の人材交流に関しましては、内務院としては有事の際に軍の指揮下に入る衛視隊への実戦に即した訓練。軍務院としては市井を知っている主計士官の育成など、互いに多くの利点がございまして……」
「どうせいつも同じ奴が行ったり来たりしてるだけだろぉ!!」
「交流した結果の報告書が上がってないぞぉ!!」
「将来の幹部候補だけ優遇してるんじゃないのか!!」
扇状に広がる議場の一角を占める少数派閥からの質問に答えた軍務院副総裁に野次が飛ぶ。
官庁間の人材交流には毎年それなりの予算が投じられているが、それが形骸化しているのではないかという指摘は以前からあった。
確かに、そうした部分もある。
いつも同じ人員が交流しているのは、何も知らない者を送り込まれても教育に時間を取られてしまうから。
提出される報告書が少ないのは、出向先の官庁で知り得た情報を元の職場で明かせない場合が多いから。
そして、将来が有望視されている官僚が優先的に交流人員に選ばれるのは、単純に優秀な人材にこそ他の官庁の実情を知っておいて欲しいからだ。
それぞれ理由があり、何度も説明されているのだが、議員たちは納得しない。いや、あえて納得していない。
議員の存在意義のひとつは、皇王から権限を貸し与えられている行政府の運営が、その権限に相応しい形で行われているかを監視することにある。
各官庁を秘密裏に調査するために、皇王直轄の国事監察院という組織も存在するが、誰の目にも明らかな形で官庁の存在意義を糺すこともまた必要なのだ。
少なくとも議員たちはそのように自分たちの行動を正当化していたし、政府としてもそうした姿勢を批判することはない。
ただ国民議会では、議員としての評価が後の人生をも大きく左右してしまうため、自然と議員たちの追及は苛烈なものとなるのだ。そして、追及の対象となった様々な人々は憔悴するか、怒りを堪える。
ちなみに、今壇上に立っている軍務院副総裁は、議会担当副総裁という立場でもあった。仕事は、皇国議会の小会議や定例本会議で軍務院としての意見を述べ、諸処との交渉を行うことだ。
軍務院の中でも激務として知られており、健康を損なうことの多い立場だとも言われている。これまで健康そのもので精気に満ちていた官僚が、僅か一ヶ月で生ける屍と化することも珍しくない。
だがごく稀に、この立場になってから輝きを見せる者もいる。
現在の軍務院副総裁は、そういった人物だった。彼は勢い込んで責め立ててくる議員に対し、軍の現役時代に培った低く響く声で答える。
「我々は、誓って、必要な、報告は、す、べ、て、摂政殿下に献じております」
「だからどうしたと――」
さらに野次を飛ばそうとした議員が、隣に座っている同僚から体当たりを食らう。何をするのかと文句を言おうとするも、周囲に座る、これまで一緒に声を上げていた議員たちが自分を睨み付けていることを察し、口を噤んだ。
そこで彼は、自分がうっかり皇王家を軽んじる発言をしようとしていたことに気付く。摂政が見ているからと張り切っていたが、張り切り過ぎて摂政を貶める言葉を発してしまうところだった。
顔を真っ青にした彼が自らの手で自らの口を塞ぐのを見て、同僚たちは緊張を解いた。彼ら議員の名誉を保証しているのは皇王家である。その皇王家を正当な理由なく貶めてしまえば、それは自分たちの名誉を否定することにも繋がる。
「――あー、質問はないようなので、この件に関する軍務院からの報告と、それに対する質疑応答を終了します」
議長が傍聴席の一角にちらちらと視線を向け、議題の終了を告げる。
それに対し、誰も文句を付ける者はいなかった。
「あの莫迦者め」
レクティファールは、隣から聞こえてきた低く震える声でそちらを見遣り、声の主である宰相ハイデルの額にはっきりと青筋が浮かんでいるのを確認した。
三院――外務院・内務院・軍務院――を統括する立場の彼にとって、副総裁は当然部下になる。その部下が、摂政の名を用いて議員たちの質問を押し潰したことに、彼は深い怒りを抱いていた。
「まあ、いいじゃないか。私の名で収まる程度の疑問だったということだ」
「そうであったとしても、殿下の権威を笠に着て己を押し通すことは、公僕たる三院幹部がするべきことではありませぬ」
レクティファールは、老人らしい節くれ立った手が青瑪瑙でできた杖の握りの上で震えているのを見て、この老人の死因は憤死になるかもしれないなと思った。
しかし、ハイデルは宰相位に就いてから体調が劇的に改善しており、健康診断でも軽く一〇歳は若い数値を叩き出している。実際、ここ最近は毎日皇城正面城門から宰相府までを歩いて出仕し、昇降機も用いずに過ごしているという。
(食事もそこらの若い官僚より摂っていると聞くし、やはり何か仕事をしていた方が人生に張りが出るのかもしれないな)
そうレクティファールは考えているが、本当のところハイデル自身にもよく分からない。
ただハイデルの細君は、夫が以前よりも生き生きとしていることを喜んでおり、夫を変えてくれたレクティファールに感謝していた。
「とにかく、あやつには一度言って聞かせねばなりません」
「そうか、まあ、良きに計らえ」
「ははっ」
レクティファールは、ハイデルやそれ以外の誰であっても、その仕事に横から口を挟むようなことはしない。レクティファールは事業に対し、自らが最善と思う臣下を配置するのが仕事だ。
自分が最善と思うことと、臣下が最善と考えることは違う。別の意識を持っているのだから、辿り着く結論が異なるのは当たり前だ。
レクティファールがすべきは、そのふたつの最善の差異をどのような形で許容するか考えることで、差異を悪として是正することではない。もしもそれがどうしても悪だとするならば、それは結局レクティファール自身の責任なのだ。
「さて、貴族議会の方も見てみようか」
「は」
レクティファールが傍聴席から立ち上がると、議長が目敏く気付いて、議員たちに起立を促そうとする。しかし、レクティファールは手を挙げてそれを制し、ハイデルと護衛の衛兵を伴って議場をあとにした。
他人の仕事の邪魔をするのが摂政の趣味だと思われるのは、やや愉快だが外聞はよろしくない。彼は国民議会名物である取っ組み合いを始めた議員たちの怒声を聞きながら、分厚く巨大な議場の扉を潜った。
「ああ、お帰りになったようだ」
傍聴席に目を向けた隣の議員が、どこかほっとしたように呟いた。
国民議会議員キャベンディッシュは、そんな同輩の姿に苦笑いし、どこかから自らの眉間目掛けて飛んできた鋼筆を避けた。
鋼筆はそのまま飛んでいって背後の壁に当たり、文墨を撒き散らす。係員が慌てて掃除を始めるが、この調子ではまだまだ汚れるだろう。
「パートン卿は、殿下が苦手でいらっしゃるか?」
キャベンディッシュは、分厚い下敷きを盾にしている同僚にそう訊ねる。
「まさか! しかしこう、初等学校の時分の参観日を思い出しましてな。どうしても緊張してしまうのです」
「なるほど」
キャベンディッシュは何度も深く頷いた。
議員たち――否、皇国の民にとって、皇王や摂政は親のようなものだ。それは自分を庇護してくれると同時に、生殺与奪の全権を握っているという意味も含まれる。
子の将来をある程度決めてしまえる点では、まさに『親』と言える。
「おお、商会派の連中、あの野人まで持ち出しましたぞ」
そう言われ、乱闘の中心を見る。
そこには、巨大な腕を振るう巨人族の姿があった。国民議会の一会派である商人たちの一派、その中に属する坑夫から身を立てた鉱山商会の会頭だ。名をザルグという。
「議長が逃げ出しましたな」
「そのようで……」
いつの間にか、議長席に座っていた男の姿が消えている。確かに戦場は議長席に近い位置で、何が飛んでくるか分かったものではない。
議長席の背後には国旗と皇王家紋章旗が掲げられているから、そちらに向かって何かを投げつける者はいないだろうが、流れ弾が飛んでこないとも限らない。
実際に、議長にお茶入りの断熱瓶が直撃し、そのまま医務室に担ぎ込まれた事態もかつてあった。
おそらく今頃は、議長席の下から移動できる隠し通路で控え室に避難していることだろう。
「やはり、金が絡むとやる気が違うものですな」
キャベンディッシュが言うと、先ほどまで喋っていた議員とは逆隣にいた老年の女性が、静かに笑い声を上げた。
扇子を振るって飛んできた杯を撥ね飛ばし、ころころと笑っている。
「税の話題ですから、皆さん真剣になってしまうものですよ」
新たな議題は、来年から施行する新しい税率だった。皇国ではほとんど毎年のように税率の再計算が行われ、対象になる品目も多い。
官僚出身で現在も各官庁と関係の深い官僚派と、商人出身の商会派による争いは枚挙に遑がないが、こと税に関することとなると加熱するのも仕方がない。
一方は如何にして多くの税を取るかを考え、もう一方は如何にしてそれを防ぐかを考えているのだ。激しい争いになるのも当然と言える。
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

娼館で元夫と再会しました
無味無臭(不定期更新)
恋愛
公爵家に嫁いですぐ、寡黙な夫と厳格な義父母との関係に悩みホームシックにもなった私は、ついに耐えきれず離縁状を机に置いて嫁ぎ先から逃げ出した。
しかし実家に帰っても、そこに私の居場所はない。
連れ戻されてしまうと危惧した私は、自らの体を売って生計を立てることにした。
「シーク様…」
どうして貴方がここに?
元夫と娼館で再会してしまうなんて、なんという不運なの!

私が死んで満足ですか?
マチバリ
恋愛
王太子に婚約破棄を告げられた伯爵令嬢ロロナが死んだ。
ある者は面倒な婚約破棄の手続きをせずに済んだと安堵し、ある者はずっと欲しかった物が手に入ると喜んだ。
全てが上手くおさまると思っていた彼らだったが、ロロナの死が与えた影響はあまりに大きかった。
書籍化にともない本編を引き下げいたしました

魔王を倒した手柄を横取りされたけど、俺を処刑するのは無理じゃないかな
七辻ゆゆ
ファンタジー
「では罪人よ。おまえはあくまで自分が勇者であり、魔王を倒したと言うのだな?」
「そうそう」
茶番にも飽きてきた。処刑できるというのなら、ぜひやってみてほしい。
無理だと思うけど。

もう無理して私に笑いかけなくてもいいですよ?
冬馬亮
恋愛
公爵令嬢のエリーゼは、遅れて出席した夜会で、婚約者のオズワルドがエリーゼへの不満を口にするのを偶然耳にする。
オズワルドを愛していたエリーゼはひどくショックを受けるが、悩んだ末に婚約解消を決意する。
だが、喜んで受け入れると思っていたオズワルドが、なぜか婚約解消を拒否。関係の再構築を提案する。
その後、プレゼント攻撃や突撃訪問の日々が始まるが、オズワルドは別の令嬢をそばに置くようになり・・・
「彼女は友人の妹で、なんとも思ってない。オレが好きなのはエリーゼだ」
「私みたいな女に無理して笑いかけるのも限界だって夜会で愚痴をこぼしてたじゃないですか。よかったですね、これでもう、無理して私に笑いかけなくてよくなりましたよ」

本物の夫は愛人に夢中なので、影武者とだけ愛し合います
こじまき
恋愛
幼い頃から許嫁だった王太子ヴァレリアンと結婚した公爵令嬢ディアーヌ。しかしヴァレリアンは身分の低い男爵令嬢に夢中で、初夜をすっぽかしてしまう。代わりに寝室にいたのは、彼そっくりの影武者…生まれたときに存在を消された双子の弟ルイだった。
※「小説家になろう」にも投稿しています

魔王を倒した勇者を迫害した人間様方の末路はなかなか悲惨なようです。
カモミール
ファンタジー
勇者ロキは長い冒険の末魔王を討伐する。
だが、人間の王エスカダルはそんな英雄であるロキをなぜか認めず、
ロキに身の覚えのない罪をなすりつけて投獄してしまう。
国民たちもその罪を信じ勇者を迫害した。
そして、処刑場される間際、勇者は驚きの発言をするのだった。

王子を身籠りました
青の雀
恋愛
婚約者である王太子から、毒を盛って殺そうとした冤罪をかけられ収監されるが、その時すでに王太子の子供を身籠っていたセレンティー。
王太子に黙って、出産するも子供の容姿が王家特有の金髪金眼だった。
再び、王太子が毒を盛られ、死にかけた時、我が子と対面するが…というお話。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる
本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。
このユーザをミュートしますか?
※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。
※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。
※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。