35 / 119
父・田沼意次が帰邸するまで、その息・意知が松平定邦の接遇に努める ~意知は定邦を将軍のように敬い、定邦を恐縮させる~
しおりを挟む
松平越中守定邦は江戸留守居の日下部武大夫と共に、田沼家取次頭取の各務源吾の案内により奥座敷へと通された。
ちなみに外の家来、例えば定邦の駕籠を担いで来た六尺や、或いは駕籠を護る警衛の士である供侍については台所へと通され、そこで田沼家よりの饗応を受けた。つまりは飲食を振舞われた。
さて、奥座敷へと通された定邦はここでも、
「育ちの良さ…」
それを遺憾なく発揮し、案内役の各務源吾を慌てさせた。
即ち、定邦は下座に着座したのであった。
「越中様、御席が…」
下座ではなく、上座へと、各務源吾は定邦にそう勧めたものの、しかし定邦は頭を振った。
「されば主殿頭殿は従四位下、それにひきかえこの定邦は朝散太夫なれば…」
確かに定邦の言う通り、定邦当人は如何に家門、親藩大名とは言え、その身はあくまで、朝散太夫、即ち、従五位下諸太夫に過ぎず、老中として従四位下侍従の官位にある「主殿頭殿」こと意次よりも格下であった。
そうであれば定邦が意次と向かい合うに当たっては、成程、下座に着座するのが礼には適う。
だがそれはあくまで「建前」に過ぎない。
意次は家門や、或いは譜代衆、それも新興譜代である雁間詰衆ではなく、
「古代御譜代…」
そう称される帝鑑間詰の諸侯から良く思われてはいなかった。要は、
「何処ぞの馬の骨とも分からぬ、盗賊も同然の下賤なる成上がり者めが…」
彼等からそう蔑まれており、意次もそのことは承知していた。
否、それは実力のある、その為に成程、確かに誇るべき家柄こそないものの、それでも己の実力によって老中へと昇り詰めた意次に対する嫉妬心の「裏返し」であった。
それ故、誇るべき家柄と共に、実力をも兼備えている老中首座の松平右近将監武元などは、
「この手の…」
嫉妬心とは無縁であり、意次を蔑むところが全くなかった。
そしてそれはこの松平定邦にも当て嵌まることであった。
定邦もまた、家格の向上を願うといった、
「数多の…」
意次を蔑む家門や譜代衆と同様、家柄に囚われている面もあった。
だがその為に、意次を蔑むというところは全くなかった。
無論、そこには打算もあったであろう。
「白河松平家の家格を向上させるにあたり、上様の寵愛を得ている意次を取込むのが大事…」
定邦にはその様な打算があったのも事実である。
しかし、だからと言って、それで意次のことを肚の中では蔑んでいるかと言うと、決してそんなことはなかった。
定邦は意次のことをあくまで、一人の老中、一人の大名として認めており、のみならず、その実力を素直に認め、評価していたのだ。
それこそが、「育ちの良さ」の所以であった。
定邦と同じく、家柄こそ確かだが、しかし意次が嫉ましく、それ故、意次を素直に認められずに蔑むことしか能がない、
「数多の…」
家門や譜代衆との大きな違いと言えよう。
さて、今日、平日の25日は将軍・家治が参府、この江戸へとやって来た大名より挨拶を、所謂、参観の挨拶を受けるべく、そこで月次御礼に准ずる、
「臨時の朝會」
その形式を取ることにより、平日登城が許されていない、例えば定邦の様な帝鑑間詰の諸侯にも参観の挨拶の為の登城を可能とした。
そしてこの「臨時の朝會」は月次御礼に准ずる為に外の、つまりは参観の挨拶とは無縁にして、平日登城が許されていない大廊下詰や大広間詰、或いは帝鑑間詰や柳間詰、そして菊間詰といった諸侯らも登城に及んでは、
「将軍・家治との主従の絆を再確認…」
家治に拝謁を果たした。
帝鑑間詰にして、参観の挨拶とは無縁の本多肥後守忠可が今日、御城の殿中にて、
「偶然にも…」
定邦と出くわしたのも、否、出くわすことが出来たのもその為である。
そして平日登城が許されている溜間詰の諸侯や、或いは雁間詰衆にしてもまた、
「将軍・家治との主従の絆の再確認…」
家治に拝謁を許されており、その為、雁間詰衆の一人、意知も勿論、登城に及んだ。
その意知だが、定邦が奥座敷へと通されてから暫くしてから帰邸へと及んだ。
今日の「臨時の朝會」はあくまで、
「将軍・家治が参府した大名から参観の挨拶を受ける…」
その為に催されたものであり、それ故、まずは彼等、つまりは定邦たちから最初に将軍・家治に拝謁をし、その後は、
「参観の挨拶とは無縁の…」
大廊下詰、溜間詰、大広間詰、帝鑑間詰、柳間詰、雁間詰、菊間詰の順番で家治に拝謁した。
雁間詰衆の一人、意知が家治に拝謁出来たのは昼の九つ半(午後1時頃)であり、それから半刻(約1時間)程が経った昼八つ(午後2時頃)の今時分になってこの神田橋御門内にある屋敷へと帰って来たのはその為である。
但し、父・意次はまだ老中としての仕事が残っていた為に、本来ならば下城の刻限である筈の昼八つ(午後2時頃)の今時分、まだ御城に居残っていた。
そこで意次の息、意知が父、意次が帰邸に及ぶまで定邦の相手をすることにした。
意知が昼八つ(午後2時頃)に帰邸に及ぶや、意知の附人である倉見金大夫が意知を出迎え、すると意知は倉見金大夫より定邦の来訪を告げられたのであった。
そこで意知は瞬時に、
「これは…、父に代わりて、定邦様の接遇に努めねば…」
そう判断して、奥座敷へと急ぎ、足を向けた次第である。
その奥座敷の廊下には定邦の家臣である日下部武大夫が控えており、そこで意知もその日下部武大夫と向かい合う格好で廊下に控えた。
これに驚いたのは日下部武大夫であった。日下部武大夫は意知の顔を知っていたので、意知が向かい合って控えたので、まずは意知に対して慌てて叩頭した上で、
「殿…」
主・定邦の背中に向かって声をかけた。
定邦は下座、つまりは廊下を背にして着座していたので、家臣の日下部武大夫のその声により廊下へと振向いた。
結果、定邦は家臣の日下部武大夫と共に、その武大夫と向かい合う意知の姿をも捉えた。
定邦も当然、意知の顔は知っていたので、
「おお、これは大和守殿…、ささっ、中へ入られよ…」
意知に声をかけるや、奥座敷へと入る様、勧めた。
だが意知はそれを拝辞した。
「この意知が座るべき場所がござりませぬ故…」
それが拝辞の理由であった。
つまりは定邦に下座に陣取られては、意知が座るべき場所は畢竟、上座しかなく、しかし定邦と意知とは同格の従五位下諸大夫、しかもその任官は定邦の方が意知よりも早く、定邦と意知が向かい合う場合、上座には定邦が座らなければならない。
その定邦が下座に陣取る以上、意知としては廊下にて控えるより外にはない。
否、それ故に定邦の家臣、陪臣である日下部武大夫もまた、廊下にて控えていたのだ。
ともあれその日下部武大夫からも主君・定邦へと、
「大和守様も斯様に申されておりますれば…」
このままでは意知が奥座敷の中へと入れないので上座へと、そう進言が為されたことから、それで定邦も遂に折れ、
「渋々…」
ではあったものの、上座へと移動した。
実を言えば以前にも同じ「やり取り」が繰広げられたことがあった。
それは定邦が意次に「アポ」を取った上での面会の折、定邦がやはり下座から中々、動かずに意次を大いに困らせたことがあり、その場には意知もいた。
さて、定邦が上座へと移るや、意知も漸くに奥座敷へと入った。
但し、一人ではない。日下部武大夫も誘って、である。
意知は奥座敷へと入るにあたり、日下部武大夫をも誘った。
日下部武大夫は当然、拝辞した。
日下部武大夫の立場からすれば拝辞は当然のことであり、意知もまずはそれを当然のことと受止め、しかしそれを、
「サラリと…」
受流しては、
「御家門、それも由緒ある久松松平の御血筋にあらせらるる白河松平家が御重役をこのまま廊下にて控えさせましては申訳なく…」
日下部武大夫にそう告げ、あまつさえ、武大夫の手を取ったのだ。
これには日下部武大夫も大いに恐縮し、それは上座に陣取る定邦にしてもそうであった。
「大和守殿…、それは余りに鄭重に過ぎると申すもの…」
定邦は意知を諫めた。
成程、白河松平家の当主たる定邦に対してならば、意知が鄭重な態度を取るのも当然と言えよう。
だがその陪臣に過ぎぬ日下部武大夫にまで意知が鄭重な態度を取る必要はなかった。
それどころか尊大に振舞っても何ら問題はなかった。
否、むしろそれが当然と言えよう。
何しろ意知は、
「今を時めく…」
老中、田沼意次の息なのである。
だが意知は日下部武大夫に対して尊大に振舞うどころか、定邦に対するのと同様、実に鄭重に接し、それは見苦しい程であった。
定邦が意知を諫めたのも当然と言えよう。
だが意知は微笑を浮かべると、
「この意知、今はまだ、一介の厄介者に過ぎませぬ故、江戸御留守居役様の日下部殿と立場は同じく…、いえ、それ以下やも知れませぬ…」
定邦に静かにだが、そう反駁した。
確かに意知は厄介者、つまりはこの田沼家の部屋住の身ではあるものの、それでも雁間詰衆として「半役人」の立場にあった。
そうであれば決して江戸留守居役以下ということはあり得ず、
「大和守殿…、そは余りに謙遜が過ぎると申すもの…」
定邦はやはりそう意知を諫めた。
「畏れ入りまする…、なれど日下部殿もまた、当家へと態々、お運びになられました御方なれば、粗略には出来ませぬ故…」
意知は定邦にやはりそう反駁し、結果、
「押切る格好で…」
日下部武大夫と共に奥座敷へと入り、下座にて並んで着座した。
日下部武大夫は元より、定邦も居心地が悪そうであったが、それでも意知と向かい合ったが為に、
「一別以来でござるな」
意知にそう声をかけた。
「越中様におかせられましては御機嫌麗しく…」
定邦に対して両手を突きつつ、そう応じた。
それはまるで将軍に対するかの様な態度であり、
「大和守殿、左様に畏まるには及ばぬによって…」
定邦は半ば、懇願する様な口調で意知を諫めた。
「いえ、左様な訳には参りませぬ。越中様は何しろ、古来御譜代、帝鑑間詰の諸侯にあらせられれば…」
意知は叩頭しつつ、そう応えた。
叩頭、それは一見、相手を敬う様にも見えるが、この場合はそれだけではない。
定邦は意知に頭を下げられてしまったが為に、意知の顔を見ることが出来ず、これでは意知に意見しようにも不可能であった。
つまりは意知はあくまで、
「我を通すべく…」
この場合は定邦の固辞にもかかわらず、定邦を将軍の如く敬おうとすることを押通すべく、そこで定邦の意見は受付けぬとばかり、頭を下げたのだ。
定邦も意知の様子からそうと察するや、
「やれやれ…」
意知の依怙地さに心底、そう思わずにはいられなかった。
「相分かった…、されば大和守殿が気儘にされるが宜しかろう…」
定邦は苦笑しつつ、そう応えたので、それで意知も漸くに頭を上げ、
「御認め下さり、有難き幸せ…」
やはり将軍に対するかの様にそう応じた。
ちなみに外の家来、例えば定邦の駕籠を担いで来た六尺や、或いは駕籠を護る警衛の士である供侍については台所へと通され、そこで田沼家よりの饗応を受けた。つまりは飲食を振舞われた。
さて、奥座敷へと通された定邦はここでも、
「育ちの良さ…」
それを遺憾なく発揮し、案内役の各務源吾を慌てさせた。
即ち、定邦は下座に着座したのであった。
「越中様、御席が…」
下座ではなく、上座へと、各務源吾は定邦にそう勧めたものの、しかし定邦は頭を振った。
「されば主殿頭殿は従四位下、それにひきかえこの定邦は朝散太夫なれば…」
確かに定邦の言う通り、定邦当人は如何に家門、親藩大名とは言え、その身はあくまで、朝散太夫、即ち、従五位下諸太夫に過ぎず、老中として従四位下侍従の官位にある「主殿頭殿」こと意次よりも格下であった。
そうであれば定邦が意次と向かい合うに当たっては、成程、下座に着座するのが礼には適う。
だがそれはあくまで「建前」に過ぎない。
意次は家門や、或いは譜代衆、それも新興譜代である雁間詰衆ではなく、
「古代御譜代…」
そう称される帝鑑間詰の諸侯から良く思われてはいなかった。要は、
「何処ぞの馬の骨とも分からぬ、盗賊も同然の下賤なる成上がり者めが…」
彼等からそう蔑まれており、意次もそのことは承知していた。
否、それは実力のある、その為に成程、確かに誇るべき家柄こそないものの、それでも己の実力によって老中へと昇り詰めた意次に対する嫉妬心の「裏返し」であった。
それ故、誇るべき家柄と共に、実力をも兼備えている老中首座の松平右近将監武元などは、
「この手の…」
嫉妬心とは無縁であり、意次を蔑むところが全くなかった。
そしてそれはこの松平定邦にも当て嵌まることであった。
定邦もまた、家格の向上を願うといった、
「数多の…」
意次を蔑む家門や譜代衆と同様、家柄に囚われている面もあった。
だがその為に、意次を蔑むというところは全くなかった。
無論、そこには打算もあったであろう。
「白河松平家の家格を向上させるにあたり、上様の寵愛を得ている意次を取込むのが大事…」
定邦にはその様な打算があったのも事実である。
しかし、だからと言って、それで意次のことを肚の中では蔑んでいるかと言うと、決してそんなことはなかった。
定邦は意次のことをあくまで、一人の老中、一人の大名として認めており、のみならず、その実力を素直に認め、評価していたのだ。
それこそが、「育ちの良さ」の所以であった。
定邦と同じく、家柄こそ確かだが、しかし意次が嫉ましく、それ故、意次を素直に認められずに蔑むことしか能がない、
「数多の…」
家門や譜代衆との大きな違いと言えよう。
さて、今日、平日の25日は将軍・家治が参府、この江戸へとやって来た大名より挨拶を、所謂、参観の挨拶を受けるべく、そこで月次御礼に准ずる、
「臨時の朝會」
その形式を取ることにより、平日登城が許されていない、例えば定邦の様な帝鑑間詰の諸侯にも参観の挨拶の為の登城を可能とした。
そしてこの「臨時の朝會」は月次御礼に准ずる為に外の、つまりは参観の挨拶とは無縁にして、平日登城が許されていない大廊下詰や大広間詰、或いは帝鑑間詰や柳間詰、そして菊間詰といった諸侯らも登城に及んでは、
「将軍・家治との主従の絆を再確認…」
家治に拝謁を果たした。
帝鑑間詰にして、参観の挨拶とは無縁の本多肥後守忠可が今日、御城の殿中にて、
「偶然にも…」
定邦と出くわしたのも、否、出くわすことが出来たのもその為である。
そして平日登城が許されている溜間詰の諸侯や、或いは雁間詰衆にしてもまた、
「将軍・家治との主従の絆の再確認…」
家治に拝謁を許されており、その為、雁間詰衆の一人、意知も勿論、登城に及んだ。
その意知だが、定邦が奥座敷へと通されてから暫くしてから帰邸へと及んだ。
今日の「臨時の朝會」はあくまで、
「将軍・家治が参府した大名から参観の挨拶を受ける…」
その為に催されたものであり、それ故、まずは彼等、つまりは定邦たちから最初に将軍・家治に拝謁をし、その後は、
「参観の挨拶とは無縁の…」
大廊下詰、溜間詰、大広間詰、帝鑑間詰、柳間詰、雁間詰、菊間詰の順番で家治に拝謁した。
雁間詰衆の一人、意知が家治に拝謁出来たのは昼の九つ半(午後1時頃)であり、それから半刻(約1時間)程が経った昼八つ(午後2時頃)の今時分になってこの神田橋御門内にある屋敷へと帰って来たのはその為である。
但し、父・意次はまだ老中としての仕事が残っていた為に、本来ならば下城の刻限である筈の昼八つ(午後2時頃)の今時分、まだ御城に居残っていた。
そこで意次の息、意知が父、意次が帰邸に及ぶまで定邦の相手をすることにした。
意知が昼八つ(午後2時頃)に帰邸に及ぶや、意知の附人である倉見金大夫が意知を出迎え、すると意知は倉見金大夫より定邦の来訪を告げられたのであった。
そこで意知は瞬時に、
「これは…、父に代わりて、定邦様の接遇に努めねば…」
そう判断して、奥座敷へと急ぎ、足を向けた次第である。
その奥座敷の廊下には定邦の家臣である日下部武大夫が控えており、そこで意知もその日下部武大夫と向かい合う格好で廊下に控えた。
これに驚いたのは日下部武大夫であった。日下部武大夫は意知の顔を知っていたので、意知が向かい合って控えたので、まずは意知に対して慌てて叩頭した上で、
「殿…」
主・定邦の背中に向かって声をかけた。
定邦は下座、つまりは廊下を背にして着座していたので、家臣の日下部武大夫のその声により廊下へと振向いた。
結果、定邦は家臣の日下部武大夫と共に、その武大夫と向かい合う意知の姿をも捉えた。
定邦も当然、意知の顔は知っていたので、
「おお、これは大和守殿…、ささっ、中へ入られよ…」
意知に声をかけるや、奥座敷へと入る様、勧めた。
だが意知はそれを拝辞した。
「この意知が座るべき場所がござりませぬ故…」
それが拝辞の理由であった。
つまりは定邦に下座に陣取られては、意知が座るべき場所は畢竟、上座しかなく、しかし定邦と意知とは同格の従五位下諸大夫、しかもその任官は定邦の方が意知よりも早く、定邦と意知が向かい合う場合、上座には定邦が座らなければならない。
その定邦が下座に陣取る以上、意知としては廊下にて控えるより外にはない。
否、それ故に定邦の家臣、陪臣である日下部武大夫もまた、廊下にて控えていたのだ。
ともあれその日下部武大夫からも主君・定邦へと、
「大和守様も斯様に申されておりますれば…」
このままでは意知が奥座敷の中へと入れないので上座へと、そう進言が為されたことから、それで定邦も遂に折れ、
「渋々…」
ではあったものの、上座へと移動した。
実を言えば以前にも同じ「やり取り」が繰広げられたことがあった。
それは定邦が意次に「アポ」を取った上での面会の折、定邦がやはり下座から中々、動かずに意次を大いに困らせたことがあり、その場には意知もいた。
さて、定邦が上座へと移るや、意知も漸くに奥座敷へと入った。
但し、一人ではない。日下部武大夫も誘って、である。
意知は奥座敷へと入るにあたり、日下部武大夫をも誘った。
日下部武大夫は当然、拝辞した。
日下部武大夫の立場からすれば拝辞は当然のことであり、意知もまずはそれを当然のことと受止め、しかしそれを、
「サラリと…」
受流しては、
「御家門、それも由緒ある久松松平の御血筋にあらせらるる白河松平家が御重役をこのまま廊下にて控えさせましては申訳なく…」
日下部武大夫にそう告げ、あまつさえ、武大夫の手を取ったのだ。
これには日下部武大夫も大いに恐縮し、それは上座に陣取る定邦にしてもそうであった。
「大和守殿…、それは余りに鄭重に過ぎると申すもの…」
定邦は意知を諫めた。
成程、白河松平家の当主たる定邦に対してならば、意知が鄭重な態度を取るのも当然と言えよう。
だがその陪臣に過ぎぬ日下部武大夫にまで意知が鄭重な態度を取る必要はなかった。
それどころか尊大に振舞っても何ら問題はなかった。
否、むしろそれが当然と言えよう。
何しろ意知は、
「今を時めく…」
老中、田沼意次の息なのである。
だが意知は日下部武大夫に対して尊大に振舞うどころか、定邦に対するのと同様、実に鄭重に接し、それは見苦しい程であった。
定邦が意知を諫めたのも当然と言えよう。
だが意知は微笑を浮かべると、
「この意知、今はまだ、一介の厄介者に過ぎませぬ故、江戸御留守居役様の日下部殿と立場は同じく…、いえ、それ以下やも知れませぬ…」
定邦に静かにだが、そう反駁した。
確かに意知は厄介者、つまりはこの田沼家の部屋住の身ではあるものの、それでも雁間詰衆として「半役人」の立場にあった。
そうであれば決して江戸留守居役以下ということはあり得ず、
「大和守殿…、そは余りに謙遜が過ぎると申すもの…」
定邦はやはりそう意知を諫めた。
「畏れ入りまする…、なれど日下部殿もまた、当家へと態々、お運びになられました御方なれば、粗略には出来ませぬ故…」
意知は定邦にやはりそう反駁し、結果、
「押切る格好で…」
日下部武大夫と共に奥座敷へと入り、下座にて並んで着座した。
日下部武大夫は元より、定邦も居心地が悪そうであったが、それでも意知と向かい合ったが為に、
「一別以来でござるな」
意知にそう声をかけた。
「越中様におかせられましては御機嫌麗しく…」
定邦に対して両手を突きつつ、そう応じた。
それはまるで将軍に対するかの様な態度であり、
「大和守殿、左様に畏まるには及ばぬによって…」
定邦は半ば、懇願する様な口調で意知を諫めた。
「いえ、左様な訳には参りませぬ。越中様は何しろ、古来御譜代、帝鑑間詰の諸侯にあらせられれば…」
意知は叩頭しつつ、そう応えた。
叩頭、それは一見、相手を敬う様にも見えるが、この場合はそれだけではない。
定邦は意知に頭を下げられてしまったが為に、意知の顔を見ることが出来ず、これでは意知に意見しようにも不可能であった。
つまりは意知はあくまで、
「我を通すべく…」
この場合は定邦の固辞にもかかわらず、定邦を将軍の如く敬おうとすることを押通すべく、そこで定邦の意見は受付けぬとばかり、頭を下げたのだ。
定邦も意知の様子からそうと察するや、
「やれやれ…」
意知の依怙地さに心底、そう思わずにはいられなかった。
「相分かった…、されば大和守殿が気儘にされるが宜しかろう…」
定邦は苦笑しつつ、そう応えたので、それで意知も漸くに頭を上げ、
「御認め下さり、有難き幸せ…」
やはり将軍に対するかの様にそう応じた。
1
あなたにおすすめの小説

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

あるフィギュアスケーターの性事情
蔵屋
恋愛
この小説はフィクションです。
しかし、そのようなことが現実にあったかもしれません。
何故ならどんな人間も、悪魔や邪神や悪神に憑依された偽善者なのですから。
この物語は浅岡結衣(16才)とそのコーチ(25才)の恋の物語。
そのコーチの名前は高木文哉(25才)という。
この物語はフィクションです。
実在の人物、団体等とは、一切関係がありません。

四代目 豊臣秀勝
克全
歴史・時代
アルファポリス第5回歴史時代小説大賞参加作です。
読者賞を狙っていますので、アルファポリスで投票とお気に入り登録してくださると助かります。
史実で三木城合戦前後で夭折した木下与一郎が生き延びた。
秀吉の最年長の甥であり、秀長の嫡男・与一郎が生き延びた豊臣家が辿る歴史はどう言うモノになるのか。
小牧長久手で秀吉は勝てるのか?
朝日姫は徳川家康の嫁ぐのか?
朝鮮征伐は行われるのか?
秀頼は生まれるのか。
秀次が後継者に指名され切腹させられるのか?
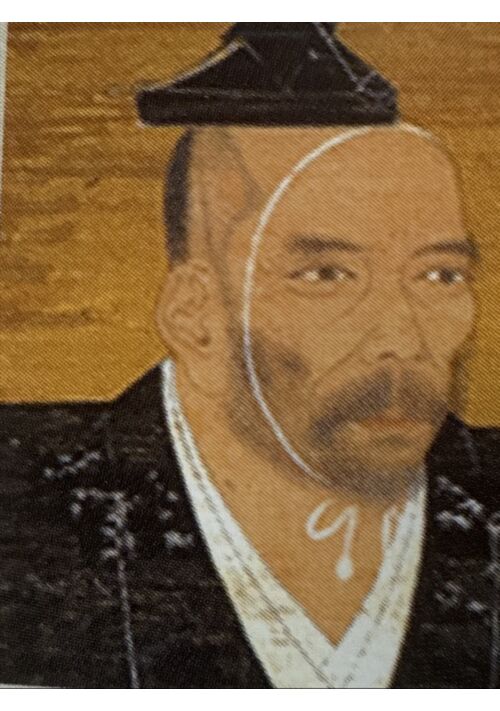
【歴史小説】 秀吉と家康 信長亡き後、秀吉の天下統一への道
蔵屋
歴史・時代
この小説は、読者の皆様もよくご存知の『秀吉』と『家康』に焦点を当て、信長亡き後の秀吉と家康、二人の天下統一の為の確執と家康の秀吉に対する思いやりをテーマとして、執筆しました。一部、私の脚色を加えていることをご承知おき下さい。
信長が本能寺の変で討たれた後、秀吉が家康に先んじて、光秀を討ち破ります。
家康は秀吉に対して大きく出遅れます。
家康は考えました。「このままでは、天下を狙うどころか、秀吉に攻め滅ぼされるかもしれない。織田信雄(のぶかつ)からの呼びかけに応じよう。
これ以上秀吉に我が物顔をさせて、なるものか。
今こそ、信雄と一緒に立ち上がるぞ。」
天正一二年(一五八四)三月。
秀吉は家康は、ともに進軍を開始し、
三月二八日、愛知県小牧市の付近で、相対することになります。
秀吉と家康、最初で、最後の直接対決が、今、まさに始まろうとしています。
歴史上の小牧・長久手の戦いです。
【歴史小説】
「秀吉と家康 信長亡き後、天下統一への道」
どうぞお楽しみ下さい。

本能寺からの決死の脱出 ~尾張の大うつけ 織田信長 天下を統一す~
bekichi
歴史・時代
戦国時代の日本を背景に、織田信長の若き日の物語を語る。荒れ狂う風が尾張の大地を駆け巡る中、夜空の星々はこれから繰り広げられる壮絶な戦いの予兆のように輝いている。この混沌とした時代において、信長はまだ無名であったが、彼の野望はやがて天下を揺るがすことになる。信長は、父・信秀の治世に疑問を持ちながらも、独自の力を蓄え、異なる理想を追求し、反逆者とみなされることもあれば期待の星と讃えられることもあった。彼の目標は、乱世を統一し平和な時代を創ることにあった。物語は信長の足跡を追い、若き日の友情、父との確執、大名との駆け引きを描く。信長の人生は、斎藤道三、明智光秀、羽柴秀吉、徳川家康、伊達政宗といった時代の英傑たちとの交流とともに、一つの大きな物語を形成する。この物語は、信長の未知なる野望の軌跡を描くものである。

小日本帝国
ypaaaaaaa
歴史・時代
日露戦争で判定勝ちを得た日本は韓国などを併合することなく独立させ経済的な植民地とした。これは直接的な併合を主張した大日本主義の対局であるから小日本主義と呼称された。
大日本帝国ならぬ小日本帝国はこうして経済を盤石としてさらなる高みを目指していく…
戦線拡大が甚だしいですが、何卒!

天竜川で逢いましょう 〜日本史教師が石田三成とか無理なので平和な世界を目指します〜
岩 大志
歴史・時代
ごくありふれた高校教師津久見裕太は、ひょんなことから頭を打ち、気を失う。
けたたましい轟音に気付き目を覚ますと多数の軍旗。
髭もじゃの男に「いよいよですな。」と、言われ混乱する津久見。
戦国時代の大きな分かれ道のド真ん中に転生した津久見はどうするのか!!???
そもそも現代人が生首とか無理なので、平和な世の中を目指そうと思います。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















