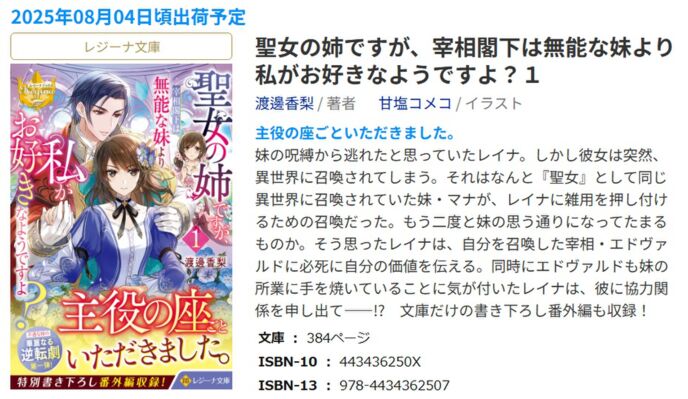778 / 785
第三部 宰相閣下の婚約者
810 嘆きの草
しおりを挟む
「どーもー」
軽い。
どこのアヤシイ外国人か、と言わんばかりの胡散臭さ全開。
元から細い目を更に細めて手を振る男――王宮が抱える諜報組織〝草〟のリーシン。
アンディション侯爵邸のベランダで、ひらひらと片手を振っていた。
「……やっぱり返品か?」
窓の近くで警戒するように佇むゲルトナーのこめかみが、思いきり痙攣っている。
「ひどいなー。話くらい聞いてくれても良くないー?」
「……よく手打ちにされないわね」
ぽつりと呟くシャルリーヌさん。ええ、私もそう思います。
エドヴァルドもそうだけど、直属上司のロイヴァス・ヘルマン長官も、こういったノリは好まない気がするのだけれど。
「ええっと……ここに来ることは、王宮関係者の方々はご存知で……?」
はい、ここ重要。
司法・公安セクションをすっとばして来たとなれば、三国会談中のこの時期、問題でしかない。
本人が「サレステーデ、バリエンダールの情報」と口にしたのだから、尚更に。
「どうだろうねー?」
私の問いかけに一瞬、ぎょっとするようなことをリーシンは口にしたものの、私の顔色を読んだのか「ああ」と、宥めるようにこちらを向いた。
「知らないわけじゃないんだよ。情報を伝えろとは言われたけど、口頭でとは言ってなかったから、手紙が届く――くらいに思ってるかも?」
「……なるほど」
「けどさ、色々と込み入った話もあるから、それなら直接伝えた方が早いじゃん?」
「…………」
手紙の方が、言った言わないにならずにいいのでは――と思うものの、そこは人それぞれ考え方があるだろうから、私は賛成も反対も出来ない。
「そうか。では、さっさと話してさっさとお引き取り願おう」
そして私以上に、ゲルトナーがケンカ腰だった。
落ち着いたら〝鷹の眼〟と〝草〟は、かつての特殊部隊並みに相性が悪いのか、聞いてみようと思ったくらいだ。
「えーそんな威嚇しなくても、こっちの上司はヘルマン長官なんだから、領域侵犯はしないって」
ゲルトナーの威嚇にまったく怯んだ様子はなく、リーシンは軽く肩を竦めている。
「長官からも〝鷹の眼〟とはムダにぶつかるなと言われてるワケだし?」
確かにヘルマン侯爵家の三男というよりは、エドヴァルドの同級生フェリクス・ヘルマンの兄という立場の方が前に出ているのが現長官だ。
ムダにぶつかるなと言われているのは恐らく事実だろう。
それ以前に、まともに〝鷹の眼〟とぶつかったところで、無傷で済むはずがない。
私なんかよりも、同業者である〝草〟あるいはリーシンの方が、それはよく分かっているはずだった。
「で、本題入っていい?」
リーシンの視線が、一瞬だけシャルリーヌを捕らえた。
もちろん「誰」かは知っているだろうけど、この場にいていいのかと思ったんだろう。
私としては出ていかれる方が後々マズそうなので「どうぞどうぞ」と、場の空気を柔らかくするように微笑んだ。
本当に? と、ここにいる私以外の皆が思っていそうだ。が、あえて無視を通しておく。
「ふーん……?」
リーシンも話が進まないと思ったのか、それ以上は食い下がってこなかった。
「じゃあ、まあ、まずはサレステーデのバレス宰相が入国してきたってところからかな」
リーシンはサレステーデを中心に情報を収集している〝草〟だ。その延長で、バリエンダールの情報も入手することがある。
今回は三国会談を不利にしないため、バレス宰相周辺の情報を探って、帰国するはずだった。
「上は軽く下は緩い第三王子のことはさてお――痛っ⁉」
「下品だ、言葉を選べ」
どうやらゲルトナーが足元のゴミか何かをリーシンに投げつけたようだ。
リーシンは額をさすっているものの、本気でケガをしたわけでもないようなので、私もシャルリーヌも乾いた笑いを浮かべることしかできない。
「ま、まあ、第三王子のことは臣籍降下先が外に出さないようにするって話だったから、その話はいいよね。長官にも伝えてあるし」
放蕩の限りを尽くして、臣籍降下とは名ばかりの王宮追放予定らしい、サレステーデの第三王子。
そこまで知らなくても「上は軽い(頭が軽い)」「下は緩い(下半身は緩い)」でその為人が概ね予測出来たらしいシャルリーヌも、私と同様に深くツッコむことはしなかった。
「存外、臣籍降下先がまともなのね?」
むしろ私の方が、神輿がそんなに軽いなら、いっそ担いでやれと思っても不思議じゃない――と思ったくらいだ。
うっかりそう口に出してしまった私を見て、リーシンは「あはは」と、軽く笑い飛ばした。
「その辺はね、バレス宰相がね、手を回したみたいだよ。そりゃ本気で担がれたら、会談通り越して滅亡の道まっしぐらじゃん?」
「へえ……」
どうやら非常識揃いの王族を、これまで宰相が押さえてきたというのは本当らしい。
「それにさ、レイフ殿下が乗り込むとあっちゃ誰も動けないでしょ? しかも宰相と入れ違いくらいのタイミングで。こっちに来てしまえば宰相もすぐさま『戻る』とは言えないし、自国で他国の王族相手に何かしようなんていう愚か者もいないだろうから、会談中に国が荒れる心配も減る。さあオハナシしましょうか――が、今の状況」
「わあ……」
まだ本格的な赴任ではないにせよ、牽制役としてレイフ殿下が動いたのだ。
さすが「フィルバートが絡まなければ有能」な王族である。
政争に敗れたにせよ、サレステーデの王族よりは格が上なのだ。
「あれ、でも、その話のどこに問題が? リーシンがここに来る要素ある?」
「まあまあ、話にはまだ続きがあるんだって」
思わず首を傾げた私に、リーシンが軽く片手を上げる。
そう言われてしまえば、黙って続きを促すしかない。
「いや、そこまではバレス宰相も有能だったんだけどさ。どうも娘さんが絡んだ途端に、ポンコツ親父に成り下がったらしくて」
「は?」
――娘さん。
私の頭を、バリエンダールで知り合った女商人こと、サラチェーニ・バレス宰相令嬢の姿がよぎる。
今回の騒動に巻き込まれて、狙われることを恐れた父親に、サレステーデに戻るよう言われていた。
バリエンダール側で身を隠すか、一度サレステーデの実家に顔を出すかという話をしていて、ベッカリーア公爵家にラディスが狙われる危険と、サラがサレステーデで王家のゴタゴタに巻き込まれる危険とを、ギリギリまで天秤にかけて悩んでいた。
いったんは北部地域の村で留まる方向に話は着地していたはずだけど、何か身の危険があったのか、宰相の方が何か策を巡らせたか……恋人であるラディズ・ロサーナ公爵令息と共にサレステーデに向かう方向に傾いてしまった……?
それはそれで誰が非難できるはずもない話だ。だけど。
「え、何、もしかして戻った途端に邸宅に監禁されちゃったとか?」
「ちょっとレイナ、物騒!」
多分シャルリーヌは冗談のつもりで聞いていたし、私も「まさか」くらいの気持ちで言っただけである。
だけど。
「…………」
リーシンはただ、無言で微笑んだ。
それが正解とばかりに。
「嘘でしょ……」
それが本当なら確かに「ポンコツ親父」である。
私は思わず口を開けたまま固まってしまった。
「家に閉じ込めることが必ずしもその身を守れるとは限らないのに……」
「ねー、身内に裏切り者がいたり、弱い護衛ばっかりだったりとか、可能性は色々あるよねー?」
リーシンの軽口を咎める気にはならない。まさしくその通りなのだから。
どこか安心出来る預け先を確保していての、一時的な措置ならまだいい。だけどリーシンの口調からするに「ただ閉じ込めただけ」と見るのが正しいはずだ。
「サラ……」
恋人であるラディズ・ロサーナ公爵令息は見た目通りの非武闘派。大暴れして、共に宰相宅から脱出出来るような性格でもなければ、腕っぷしもない。
事態が鎮静化するのをじっと待つか……あるいは頭を使って、自分ではなく他人を動かすか……?
「そのバレス宰相の娘さんと知り合いなのね?」
サラ、と略称を呟いたところで気付いたのだろう。
シャルリーヌが、眉根を寄せて唸る私の顔を覗き込んでくる。
その仕種で、私もハッと我に返った。
「ああ、うん、そう。商業ギルドの登録証を持っていて、自立心も旺盛だし、恋人もいるから……ユングベリ商会の支店を向こうで持ってくれないかなと思ってたところなのよ」
「へえ……なんだか話が合いそう」
「かもね。宰相家の令嬢って感じはあまりしないから」
「そう。じゃあ、いつかの楽しみにとっておくことにするわ……で、本題は、そのお嬢様が自宅で恋人と閉じ込められちゃってるってことなのね?」
「そうなのよね……本人が宰相家の令嬢だってこともあるんだけど、その恋人の方もバリエンダールの公爵家の令息で、しかも今回やり玉に上がっている公爵家の悪事の生き証人みたいなものなのよね……」
「え」
もちろん、エモニエ先代侯爵夫人も証人の一人ではある。
だけどロサーナ公爵とその息子であるラディズも、騙されて恐喝されたという点では同じくらい重要な立ち位置にいるのだ。
バレス宰相家でうっかり巻き添えを喰いました、で済む人物ではなかった。
宰相はそのことを知っているのだろうか……?
「あー……なるほど、そういうこと……なるほど」
私とシャルリーヌの会話を聞いていたリーシンが、不意に「納得した」と言わんばかりの呟きを発したため、いったん会話を中断する。
「リーシン?」
「いや、なんで自分がこの情報を得たかと言えば」
そう言って、リーシンは驚きの情報入手ルートを口にしたのである。
「バレス宰相邸から密かに出された手紙が、サレステーデの王都商業ギルド前で奪われそうになっているところに遭遇して」
「手紙」
「あ、これは本当にたまたま。誓って。日銭を稼ぐのがやっと、みたいな子だったからさ、つい助けたくなっちゃったんだよね……って、まぁそれはそれとして、その拍子に手紙が地面に落ちて中身が見えちゃって」
なんてご都合主義――と思ったものの、事実は小説より奇なりということはいくらでもある。
私は大人しくリーシンの言葉の続きを待った。
「物凄く焦った、殴り書きみたいな文字でさ。書いてあったわけ。この手紙を、アンジェス国のユングベリ商会・商会長へ……って」
「……え」
「今すぐ身の危険はないと思うが、いつまでとも言えない。貴女の采配で、これと思う人に、状況の打破を依頼しては貰えないか――要は『助けて!』ってコトだよね?」
「えぇ……」
「で、まあ、見ちゃったら無視も出来ないし?」
「…………」
「それでざっと状況を確かめてから、宰相御一行様に紛れて戻ってきました、と」
「それは……」
それはリーシンの上司と言い、エドヴァルドといい、私にも話を回すよう言うはずである。
「明日、再度会談する時までに、この情報をどう活かすべきなのかを知らせるように――ってさ」
会談が終わるまで、サラとラディズを閉じ込めておくのは、良策のようで悪手だ。ましてバリエンダール側にとっては、ベッカリーア公爵家断罪のための生き証人をサレステーデに押さえられているようなものだ。
そのことをバレス宰相が知ってしまえば、会談の行方が違ってくる可能性がある。
「娘可愛さか知らないけど、何てコトしてくれたのよ……」
想定外の情報に、私は思わず頭を抱えていた。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
祝・文庫化……!!
いつも読んでいただき、応援やいいねをありがとうございます!m(_ _)m
聖女の姉ですが、宰相閣下は無能な妹より私がお好きなようですよ?
文庫化決定です!!
レジーナ文庫から8月4日(月)出荷、5-6日頃から店頭に並ぶ予定です。
文庫だけの書き下ろし番外編も収録されています。
人物紹介欄の誤字もちゃんと修正されています(;^_^A
主要サイトでの予約も始まっています。
単行本版ともども、文庫版もどうぞよろしくお願いします……!!
軽い。
どこのアヤシイ外国人か、と言わんばかりの胡散臭さ全開。
元から細い目を更に細めて手を振る男――王宮が抱える諜報組織〝草〟のリーシン。
アンディション侯爵邸のベランダで、ひらひらと片手を振っていた。
「……やっぱり返品か?」
窓の近くで警戒するように佇むゲルトナーのこめかみが、思いきり痙攣っている。
「ひどいなー。話くらい聞いてくれても良くないー?」
「……よく手打ちにされないわね」
ぽつりと呟くシャルリーヌさん。ええ、私もそう思います。
エドヴァルドもそうだけど、直属上司のロイヴァス・ヘルマン長官も、こういったノリは好まない気がするのだけれど。
「ええっと……ここに来ることは、王宮関係者の方々はご存知で……?」
はい、ここ重要。
司法・公安セクションをすっとばして来たとなれば、三国会談中のこの時期、問題でしかない。
本人が「サレステーデ、バリエンダールの情報」と口にしたのだから、尚更に。
「どうだろうねー?」
私の問いかけに一瞬、ぎょっとするようなことをリーシンは口にしたものの、私の顔色を読んだのか「ああ」と、宥めるようにこちらを向いた。
「知らないわけじゃないんだよ。情報を伝えろとは言われたけど、口頭でとは言ってなかったから、手紙が届く――くらいに思ってるかも?」
「……なるほど」
「けどさ、色々と込み入った話もあるから、それなら直接伝えた方が早いじゃん?」
「…………」
手紙の方が、言った言わないにならずにいいのでは――と思うものの、そこは人それぞれ考え方があるだろうから、私は賛成も反対も出来ない。
「そうか。では、さっさと話してさっさとお引き取り願おう」
そして私以上に、ゲルトナーがケンカ腰だった。
落ち着いたら〝鷹の眼〟と〝草〟は、かつての特殊部隊並みに相性が悪いのか、聞いてみようと思ったくらいだ。
「えーそんな威嚇しなくても、こっちの上司はヘルマン長官なんだから、領域侵犯はしないって」
ゲルトナーの威嚇にまったく怯んだ様子はなく、リーシンは軽く肩を竦めている。
「長官からも〝鷹の眼〟とはムダにぶつかるなと言われてるワケだし?」
確かにヘルマン侯爵家の三男というよりは、エドヴァルドの同級生フェリクス・ヘルマンの兄という立場の方が前に出ているのが現長官だ。
ムダにぶつかるなと言われているのは恐らく事実だろう。
それ以前に、まともに〝鷹の眼〟とぶつかったところで、無傷で済むはずがない。
私なんかよりも、同業者である〝草〟あるいはリーシンの方が、それはよく分かっているはずだった。
「で、本題入っていい?」
リーシンの視線が、一瞬だけシャルリーヌを捕らえた。
もちろん「誰」かは知っているだろうけど、この場にいていいのかと思ったんだろう。
私としては出ていかれる方が後々マズそうなので「どうぞどうぞ」と、場の空気を柔らかくするように微笑んだ。
本当に? と、ここにいる私以外の皆が思っていそうだ。が、あえて無視を通しておく。
「ふーん……?」
リーシンも話が進まないと思ったのか、それ以上は食い下がってこなかった。
「じゃあ、まあ、まずはサレステーデのバレス宰相が入国してきたってところからかな」
リーシンはサレステーデを中心に情報を収集している〝草〟だ。その延長で、バリエンダールの情報も入手することがある。
今回は三国会談を不利にしないため、バレス宰相周辺の情報を探って、帰国するはずだった。
「上は軽く下は緩い第三王子のことはさてお――痛っ⁉」
「下品だ、言葉を選べ」
どうやらゲルトナーが足元のゴミか何かをリーシンに投げつけたようだ。
リーシンは額をさすっているものの、本気でケガをしたわけでもないようなので、私もシャルリーヌも乾いた笑いを浮かべることしかできない。
「ま、まあ、第三王子のことは臣籍降下先が外に出さないようにするって話だったから、その話はいいよね。長官にも伝えてあるし」
放蕩の限りを尽くして、臣籍降下とは名ばかりの王宮追放予定らしい、サレステーデの第三王子。
そこまで知らなくても「上は軽い(頭が軽い)」「下は緩い(下半身は緩い)」でその為人が概ね予測出来たらしいシャルリーヌも、私と同様に深くツッコむことはしなかった。
「存外、臣籍降下先がまともなのね?」
むしろ私の方が、神輿がそんなに軽いなら、いっそ担いでやれと思っても不思議じゃない――と思ったくらいだ。
うっかりそう口に出してしまった私を見て、リーシンは「あはは」と、軽く笑い飛ばした。
「その辺はね、バレス宰相がね、手を回したみたいだよ。そりゃ本気で担がれたら、会談通り越して滅亡の道まっしぐらじゃん?」
「へえ……」
どうやら非常識揃いの王族を、これまで宰相が押さえてきたというのは本当らしい。
「それにさ、レイフ殿下が乗り込むとあっちゃ誰も動けないでしょ? しかも宰相と入れ違いくらいのタイミングで。こっちに来てしまえば宰相もすぐさま『戻る』とは言えないし、自国で他国の王族相手に何かしようなんていう愚か者もいないだろうから、会談中に国が荒れる心配も減る。さあオハナシしましょうか――が、今の状況」
「わあ……」
まだ本格的な赴任ではないにせよ、牽制役としてレイフ殿下が動いたのだ。
さすが「フィルバートが絡まなければ有能」な王族である。
政争に敗れたにせよ、サレステーデの王族よりは格が上なのだ。
「あれ、でも、その話のどこに問題が? リーシンがここに来る要素ある?」
「まあまあ、話にはまだ続きがあるんだって」
思わず首を傾げた私に、リーシンが軽く片手を上げる。
そう言われてしまえば、黙って続きを促すしかない。
「いや、そこまではバレス宰相も有能だったんだけどさ。どうも娘さんが絡んだ途端に、ポンコツ親父に成り下がったらしくて」
「は?」
――娘さん。
私の頭を、バリエンダールで知り合った女商人こと、サラチェーニ・バレス宰相令嬢の姿がよぎる。
今回の騒動に巻き込まれて、狙われることを恐れた父親に、サレステーデに戻るよう言われていた。
バリエンダール側で身を隠すか、一度サレステーデの実家に顔を出すかという話をしていて、ベッカリーア公爵家にラディスが狙われる危険と、サラがサレステーデで王家のゴタゴタに巻き込まれる危険とを、ギリギリまで天秤にかけて悩んでいた。
いったんは北部地域の村で留まる方向に話は着地していたはずだけど、何か身の危険があったのか、宰相の方が何か策を巡らせたか……恋人であるラディズ・ロサーナ公爵令息と共にサレステーデに向かう方向に傾いてしまった……?
それはそれで誰が非難できるはずもない話だ。だけど。
「え、何、もしかして戻った途端に邸宅に監禁されちゃったとか?」
「ちょっとレイナ、物騒!」
多分シャルリーヌは冗談のつもりで聞いていたし、私も「まさか」くらいの気持ちで言っただけである。
だけど。
「…………」
リーシンはただ、無言で微笑んだ。
それが正解とばかりに。
「嘘でしょ……」
それが本当なら確かに「ポンコツ親父」である。
私は思わず口を開けたまま固まってしまった。
「家に閉じ込めることが必ずしもその身を守れるとは限らないのに……」
「ねー、身内に裏切り者がいたり、弱い護衛ばっかりだったりとか、可能性は色々あるよねー?」
リーシンの軽口を咎める気にはならない。まさしくその通りなのだから。
どこか安心出来る預け先を確保していての、一時的な措置ならまだいい。だけどリーシンの口調からするに「ただ閉じ込めただけ」と見るのが正しいはずだ。
「サラ……」
恋人であるラディズ・ロサーナ公爵令息は見た目通りの非武闘派。大暴れして、共に宰相宅から脱出出来るような性格でもなければ、腕っぷしもない。
事態が鎮静化するのをじっと待つか……あるいは頭を使って、自分ではなく他人を動かすか……?
「そのバレス宰相の娘さんと知り合いなのね?」
サラ、と略称を呟いたところで気付いたのだろう。
シャルリーヌが、眉根を寄せて唸る私の顔を覗き込んでくる。
その仕種で、私もハッと我に返った。
「ああ、うん、そう。商業ギルドの登録証を持っていて、自立心も旺盛だし、恋人もいるから……ユングベリ商会の支店を向こうで持ってくれないかなと思ってたところなのよ」
「へえ……なんだか話が合いそう」
「かもね。宰相家の令嬢って感じはあまりしないから」
「そう。じゃあ、いつかの楽しみにとっておくことにするわ……で、本題は、そのお嬢様が自宅で恋人と閉じ込められちゃってるってことなのね?」
「そうなのよね……本人が宰相家の令嬢だってこともあるんだけど、その恋人の方もバリエンダールの公爵家の令息で、しかも今回やり玉に上がっている公爵家の悪事の生き証人みたいなものなのよね……」
「え」
もちろん、エモニエ先代侯爵夫人も証人の一人ではある。
だけどロサーナ公爵とその息子であるラディズも、騙されて恐喝されたという点では同じくらい重要な立ち位置にいるのだ。
バレス宰相家でうっかり巻き添えを喰いました、で済む人物ではなかった。
宰相はそのことを知っているのだろうか……?
「あー……なるほど、そういうこと……なるほど」
私とシャルリーヌの会話を聞いていたリーシンが、不意に「納得した」と言わんばかりの呟きを発したため、いったん会話を中断する。
「リーシン?」
「いや、なんで自分がこの情報を得たかと言えば」
そう言って、リーシンは驚きの情報入手ルートを口にしたのである。
「バレス宰相邸から密かに出された手紙が、サレステーデの王都商業ギルド前で奪われそうになっているところに遭遇して」
「手紙」
「あ、これは本当にたまたま。誓って。日銭を稼ぐのがやっと、みたいな子だったからさ、つい助けたくなっちゃったんだよね……って、まぁそれはそれとして、その拍子に手紙が地面に落ちて中身が見えちゃって」
なんてご都合主義――と思ったものの、事実は小説より奇なりということはいくらでもある。
私は大人しくリーシンの言葉の続きを待った。
「物凄く焦った、殴り書きみたいな文字でさ。書いてあったわけ。この手紙を、アンジェス国のユングベリ商会・商会長へ……って」
「……え」
「今すぐ身の危険はないと思うが、いつまでとも言えない。貴女の采配で、これと思う人に、状況の打破を依頼しては貰えないか――要は『助けて!』ってコトだよね?」
「えぇ……」
「で、まあ、見ちゃったら無視も出来ないし?」
「…………」
「それでざっと状況を確かめてから、宰相御一行様に紛れて戻ってきました、と」
「それは……」
それはリーシンの上司と言い、エドヴァルドといい、私にも話を回すよう言うはずである。
「明日、再度会談する時までに、この情報をどう活かすべきなのかを知らせるように――ってさ」
会談が終わるまで、サラとラディズを閉じ込めておくのは、良策のようで悪手だ。ましてバリエンダール側にとっては、ベッカリーア公爵家断罪のための生き証人をサレステーデに押さえられているようなものだ。
そのことをバレス宰相が知ってしまえば、会談の行方が違ってくる可能性がある。
「娘可愛さか知らないけど、何てコトしてくれたのよ……」
想定外の情報に、私は思わず頭を抱えていた。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
祝・文庫化……!!
いつも読んでいただき、応援やいいねをありがとうございます!m(_ _)m
聖女の姉ですが、宰相閣下は無能な妹より私がお好きなようですよ?
文庫化決定です!!
レジーナ文庫から8月4日(月)出荷、5-6日頃から店頭に並ぶ予定です。
文庫だけの書き下ろし番外編も収録されています。
人物紹介欄の誤字もちゃんと修正されています(;^_^A
主要サイトでの予約も始まっています。
単行本版ともども、文庫版もどうぞよろしくお願いします……!!
1,996
あなたにおすすめの小説

『白い結婚だったので、勝手に離婚しました。何か問題あります?』
夢窓(ゆめまど)
恋愛
「――離婚届、受理されました。お疲れさまでした」
教会の事務官がそう言ったとき、私は心の底からこう思った。
ああ、これでようやく三年分の無視に終止符を打てるわ。
王命による“形式結婚”。
夫の顔も知らず、手紙もなし、戦地から帰ってきたという噂すらない。
だから、はい、離婚。勝手に。
白い結婚だったので、勝手に離婚しました。
何か問題あります?

処刑前夜に逃亡した悪役令嬢、五年後に氷の公爵様に捕まる〜冷徹旦那様が溺愛パパに豹変しましたが私の抱いている赤ちゃん実は人生2周目です〜
放浪人
恋愛
「処刑されるなんて真っ平ごめんです!」 無実の罪で投獄された悪役令嬢レティシア(中身は元社畜のアラサー日本人)は、処刑前夜、お腹の子供と共に脱獄し、辺境の田舎村へ逃亡した。 それから五年。薬師として穏やかに暮らしていた彼女のもとに、かつて自分を冷遇し、処刑を命じた夫――「氷の公爵」アレクセイが現れる。 殺される!と震えるレティシアだったが、再会した彼は地面に頭を擦り付け、まさかの溺愛キャラに豹変していて!?
「愛しているレティシア! 二度と離さない!」 「(顔が怖いです公爵様……!)」
不器用すぎて顔が怖い旦那様の暴走する溺愛。 そして、二人の息子であるシオン(1歳)は、実は前世で魔王を倒した「英雄」の生まれ変わりだった! 「パパとママは僕が守る(物理)」 最強の赤ちゃんが裏で暗躍し、聖女(自称)の陰謀も、帝国の侵略も、古代兵器も、ガラガラ一振りで粉砕していく。

愛人を選んだ夫を捨てたら、元婚約者の公爵に捕まりました
由香
恋愛
伯爵夫人リュシエンヌは、夫が公然と愛人を囲う結婚生活を送っていた。
尽くしても感謝されず、妻としての役割だけを求められる日々。
けれど彼女は、泣きわめくことも縋ることもなく、静かに離婚を選ぶ。
そうして“捨てられた妻”になったはずの彼女の前に現れたのは、かつて婚約していた元婚約者――冷静沈着で有能な公爵セドリックだった。
再会とともに始まるのは、彼女の価値を正しく理解し、決して手放さない男による溺愛の日々。
一方、彼女を失った元夫は、妻が担っていたすべてを失い、社会的にも転落していく。
“尽くすだけの妻”から、“選ばれ、守られる女性”へ。
静かに離婚しただけなのに、
なぜか元婚約者の公爵に捕まりました。

事情があってメイドとして働いていますが、実は公爵家の令嬢です。
木山楽斗
恋愛
ラナリアが仕えるバルドリュー伯爵家では、子爵家の令嬢であるメイドが幅を利かせていた。
彼女は貴族の地位を誇示して、平民のメイドを虐げていた。その毒牙は、平民のメイドを庇ったラナリアにも及んだ。
しかし彼女は知らなかった。ラナリアは事情があって伯爵家に仕えている公爵令嬢だったのである。

お前は家から追放する?構いませんが、この家の全権力を持っているのは私ですよ?
水垣するめ
恋愛
「アリス、お前をこのアトキンソン伯爵家から追放する」
「はぁ?」
静かな食堂の間。
主人公アリス・アトキンソンの父アランはアリスに向かって突然追放すると告げた。
同じく席に座っている母や兄、そして妹も父に同意したように頷いている。
いきなり食堂に集められたかと思えば、思いも寄らない追放宣言にアリスは戸惑いよりも心底呆れた。
「はぁ、何を言っているんですか、この領地を経営しているのは私ですよ?」
「ああ、その経営も最近軌道に乗ってきたのでな、お前はもう用済みになったから追放する」
父のあまりに無茶苦茶な言い分にアリスは辟易する。
「いいでしょう。そんなに出ていって欲しいなら出ていってあげます」
アリスは家から一度出る決心をする。
それを聞いて両親や兄弟は大喜びした。
アリスはそれを哀れみの目で見ながら家を出る。
彼らがこれから地獄を見ることを知っていたからだ。
「大方、私が今まで稼いだお金や開発した資源を全て自分のものにしたかったんでしょうね。……でもそんなことがまかり通るわけないじゃないですか」
アリスはため息をつく。
「──だって、この家の全権力を持っているのは私なのに」
後悔したところでもう遅い。

離婚する両親のどちらと暮らすか……娘が選んだのは夫の方だった。
しゃーりん
恋愛
夫の愛人に子供ができた。夫は私と離婚して愛人と再婚したいという。
私たち夫婦には娘が1人。
愛人との再婚に娘は邪魔になるかもしれないと思い、自分と一緒に連れ出すつもりだった。
だけど娘が選んだのは夫の方だった。
失意のまま実家に戻り、再婚した私が数年後に耳にしたのは、娘が冷遇されているのではないかという話。
事実ならば娘を引き取りたいと思い、元夫の家を訪れた。
再び娘が選ぶのは父か母か?というお話です。

【完結】冷酷伯爵ディートリヒは、去った妻を取り戻せない
くろねこ
恋愛
名門伯爵家に政略結婚で嫁いだ、正妻エレノア・リーヴェルト。夫である伯爵ディートリヒ・フォン・アイゼンヴァルトは、
軍務と義務を最優先し、彼女に関心を向けることはなかった。
言葉も、視線も、愛情も与えられない日々。それでも伯爵夫人として尽くし続けたエレノアは、ある一言をきっかけに、静かに伯爵家を去る決意をする。
――そして初めて、夫は気づく。
自分がどれほど多くのものを、彼女から与えられていたのかを。
一方、エレノアは新たな地でその才覚と人柄を評価され、
「必要とされる存在」として歩き始めていた。
去った妻を想い、今さら後悔する冷酷伯爵。前を向いて生きる正妻令嬢。
これは、失ってから愛に気づいた男と、
二度と戻らないかもしれない夫婦の物語。
――今さら、遅いのです。

継子いじめで糾弾されたけれど、義娘本人は離婚したら私についてくると言っています〜出戻り夫人の商売繁盛記〜
野生のイエネコ
恋愛
後妻として男爵家に嫁いだヴィオラは、継子いじめで糾弾され離婚を申し立てられた。
しかし当の義娘であるシャーロットは、親としてどうしようもない父よりも必要な教育を与えたヴィオラの味方。
義娘を連れて実家の商会に出戻ったヴィオラは、貴族での生活を通じて身につけた知恵で新しい服の開発をし、美形の義娘と息子は服飾モデルとして王都に流行の大旋風を引き起こす。
度々襲来してくる元夫の、借金の申込みやヨリを戻そうなどの言葉を躱しながら、事業に成功していくヴィオラ。
そんな中、伯爵家嫡男が、継子いじめの疑惑でヴィオラに近づいてきて?
※小説家になろうで「離婚したので幸せになります!〜出戻り夫人の商売繁盛記〜」として掲載しています。
過去1ヶ月以内にレジーナの小説・漫画を1話以上レンタルしている
と、レジーナのすべての番外編を読むことができます。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる
本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。
番外編を閲覧することが出来ません。
過去1ヶ月以内にレジーナの小説・漫画を1話以上レンタルしている
と、レジーナのすべての番外編を読むことができます。
このユーザをミュートしますか?
※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。
※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。
※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。