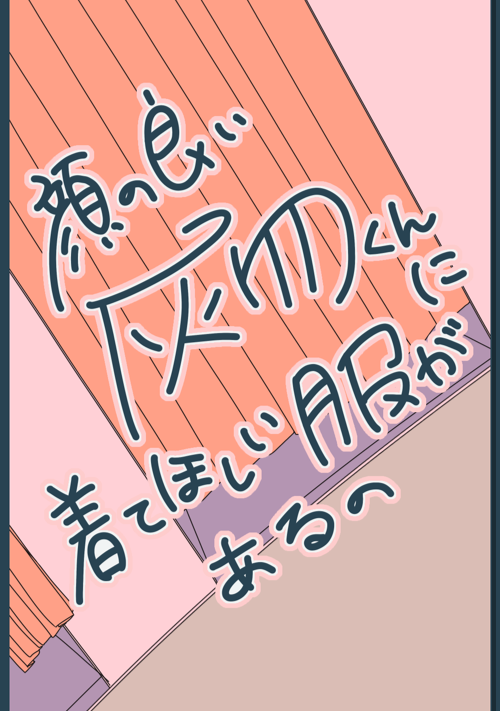2 / 50
みなしごと百貨の王2
しおりを挟むしまった。寝そべった。
うつらうつらと眠りが浅瀬に浮かび上がったとき、しおんが最初に考えたのはそれだった。地面に直接寝ると体温を奪われすぎるから、いつもどこかに背中を預けて眠ることにしているのに。
しまったと思ったあとに気がついた。心なしか地面がいつもより柔らかい。
もしかして俺、死んだのか。
ずっとそれを望んでいたというのに、いざそのときを迎えてみるとなんともあっけないというのがしおん感想だった。
なんかだかふわふわ浮いているみたいだ。
なんだ。死ぬほうが生きてるよりよっぽどいいな。
ぐっすり眠ってる間にあの世とやらにきてしまったのなら、悪くはない最後だった。孤児院でくり返された天国と、浅草寺の坊主がいう極楽や地獄、自分はその中のどこに行くんだろう。
そこには俺みたいなのにも居場所があるんだろうか。
ふわふわと心地良い浮遊感に身を任せて再び意識を手放そうとしたとき、誰かの気配がした。ユウだろうか。寒がりなユウは冷える夜には避けても避けてもくっついてくることが多かった。その甘っちょろさで今日まで生きているのが不思議なくらいだ。
鬱陶しいと思いながら、しおんはその体を抱き寄せた。どうせあと少しで死ぬなら、そのわずかな間だ体温をわけてやっても罰は当たらないかと思ったのだ。
ユウは身じろいだようだったが、構わずにぽんぽんと頭を撫でてやる。自分はこんなこと、誰にもされたことがないけど、と思いながら。
「どういうつもりなんですか、社長」
誰かの話し声であの世から呼び戻された。というか、あの世に着いたと思ったさっきの目覚めはまだ眠りの中だったらしい。
――なんだ、俺、生きてる。
安堵より落胆の気持ちが大きかった。最後の眠りは温かく心地が良かったから、あのまま魂を運ばれてしまっても構わなかったのに。
あの世でないなら、ここはいったいどこだ。
しおんは注意深く辺りを見回した。
天井が高い。高めの腰壁の上には薄い青色に銀鼠でなにか植物のような文様が刷り出されている。腰壁そのものも、孤児院の簡素なものと違って上下に植物の彫刻が入っていた。それがぐるりと張られているのだから、職人に払う手間賃は大変なものだろう。カーテンも壁紙と合わせた色合いで、外から差し込む光が、しっとりとした生地をうす青にも銀鼠にも輝かせていた。
光の柔らかさからいって朝だろうか。となると自分は一晩眠りこけていたことになる。
部屋の一角に暖炉が埋め込まれていた。大理石をさらに彫刻で取り囲んで、上部には大きな鏡が取り付けられている。部屋が快適に温かいのはそこで火を焚いているからだろうと思ったが、炎も見えなければ薪のはぜる音もしない。よく見るとストーブのようなものが置かれていた。部屋の意匠に合った装飾が施された小造りの本体から、配管がどこかに繋がっているようだ。
瓦斯(ガス)ストーブ……?
そういうものがあると噂には聞いたことがあったが、この目で見るのは初めてだ。いったいどんな仕組みなのか、部屋の中は良く晴れた昼下がりのように温められている。
ふかふかしていると思ったのは雲ではなく寝台で、体を支配していた痛みも、鉛のような重苦しさもいつの間にか消えていた。着ているものもいつの間にか足首まで丈のある寝間着に着替えさせられている。今頃気づいたのは、それがふんわりと柔らかく、まるでなにも着ていないかのように軽くて素肌に馴染むからだ。
今まで寝台といえば孤児院の固いものしか知らなかったしおんには、文字通り雲泥の差だった。眠りから覚めてみれば、その柔らかさは逆に落ち着かない。
取り敢えず、状況を把握しよう。
獣のように伏せたまま、しおんは耳をそばだたせた。声は扉で繋がった隣の部屋から聞こえている。書斎だろうか。話しているのは昨夜劇場で見た男たちのようだ。
あの、射貫くようにまっすぐこちらを見据えていた黒い瞳をしおんは思い出した。
「同じような背格好の、楽器も出来る子で揃えるという話でしたよね?」
「当初の予定では、な。あれを一目見たとき、もっと面白い売り出し方を思いついた」
「面白いって……」
ため息は昨夜彼の横でなにごとか耳打ちしていたほうの男だろう。その様子から、黒い瞳の男―龍郷が、いつもこうして彼を困らせているのが想像できる。
「それにしたって、いきなり邸にまで連れてくるなんて」
「身元がわからないからな。逃がしたくなかった。―ただの音楽隊ならよそもやってる。先手を打たないと」
提案ではない。「もう決まり切ったことにおまえはなにを言ってるんだ?」という響き。しおんは相手が何者かもわからないまま龍郷の話し相手に同情する。と同時に、昨夜の眼差しを思い出した。
『どうした。歌わないのか』
あれも提案や質問ではなかった。
歌うだろう? 歌えるだろう?
言外ににおわせる、なんて生やさしいものではない。それ以外の選択肢がおまえにあるのか? とでも言いたげな。
その一方的な態度に反発を覚えながら従ってしまったのは、熱のせいだろうか。すっかり体の痛みもひいた今あらためて考えてみるが、よくはわからなかった。
今龍郷と話している相手も、結局は気圧されたように諦めのため息をつく。
「……まあ、おまえがそう言うなら仕方ない」
さっきは社長って呼んでたのに。
思えばふたりは年格好が近いようだった。仕事は関係なしに古くからの知り合いなのかもしれない。
「午後からは予定通りで?」
「二時間ずつずらしてくれ」
「またそんな簡単に」
「おまえならできるだろう? 野々宮」
命じるときと同じくらいに「なにを言っているんだ?」という響きで言われ、男が言葉を失うのがわかった。続いた今度のため息には、さっきとは別の諦めが含まれている。
「わかりましたよ。では、後ほど、寮で」
野々宮と呼ばれた男は、再び主人と仕える者という距離感の言葉遣いに戻ると、部屋を出て行った。
見聞きした情報を繋ぎ合わせてみるに、ここは昨夜出会ったあの男、龍郷の邸なのだろう。
百貨店の社長なんてものは、あの興行師と同じ、でっぷりと太ったおやじだとばかり思っていたが、龍郷はまだ二十代後半、三十も手前のように見えた。龍郷百貨店の前身となった店自体は江戸の頃からあるはずだから、龍郷は先祖が作った財産をただ生まれ落ちただけで受け継いだ、幸福なぼんぼんということになる。
とはいえ百貨店は今や龍郷に止まらず、白木屋、大丸と林立しているから、ここは宣伝のため結成した音楽隊に毛色の変わった自分を入れて、よそより目立とうという腹なのだろう。
――見世物かよ。
この髪と目の色のせいで捨てられた。孤児院でも他の子供に蔑まれた。同じ親なし子だというのに、大多数と違う特徴を持っているというだけで奴らは俺を自分たちより格下扱いにしてもいいのだと判断する。
そんな理不尽にうんざりして街に逃げ出してからだって、一目で覚えられてしまうこの容姿がどんなに邪魔だったか。隠したら隠したで、あの銘酒屋の女たちのように鬱陶しくからんでくる。
しおんは自分のこの容姿にも、それを理由に自分を蔑む連中にも――要するにこの世のすべてにすでに倦いていた。十代半ばにして。
金儲けのために晒し者になれって?
まだ心地良い眠りの余韻のなかにあった体が、かっと熱を帯びる。冗談じゃない。こんなとこ、一刻も早く逃げ出すに限る。しおんはがばっと布団をはぎ(それは拍子抜けするほど軽かった)、勢いよく起き上がった。
でも、どこへ行く?
ここがどこかさえわからないのに? うまいこと逃げられたとして、また十二階下に戻るのか―?
その一瞬の逡巡が失敗の元だった。
書斎らしき隣室のドアが開き、龍郷がこちらの部屋に入ってくる。あとは上着を羽織ればすぐにでも外に出られそうなシャツにベスト姿。それも遠目で見ていいものだとわかる生地だった。目利きなどできるわけもないが、自然と目にそう訴えてくるのだ。金のかかっているものにはそういう力があると、しおんは初めて知った。
龍郷は起き上がっているしおんの姿に気がつくと、たいして驚いた様子もなく口を開いた。
「目が覚めたか。あのまま死ぬかと思ったが」
「……そのほうが百倍ましだったけどな。どけよ、俺は帰る」
「帰るって、どこに?」
いらだちに任せてぶつけた言葉じりを思いがけず愉快そうに拾い上げられ、それははっきりと怒りに変わった。
「……っ!」
ここがふかふかの寝台の上だということをすっかり忘れていた。寝間着がずるずると長いのもよくない。詰め寄ろうとして裾を踏んづける。顔から床に落ちそうになった体を支えたのは、龍郷だった。
「おっと。威勢がいいのはけっこうだが、気をつけろよ」
しおんの体を抱いたまま、龍郷はしおんの額に己の額をこつんとつける。
「熱は下がったようだな」
「――、は、なせ! 俺は見世物になんかならねえ!」
無様なところを見せてしまった気まずさも手伝って、しおんは龍郷をきつく睨み返した。だが龍郷が怯む様子は微塵もない。
「そうだな。そのままじゃとてもじゃないが見られたもんじゃない」
悪びれる様子もなくそう言うと、しおんの膝裏に手を入れて、軽々と抱き上げた。
「な……ッ!」
自分が薄汚れている、というか、もの凄く汚れているという自覚はあった。それでもこの男からあらためて言われると、なんだかとてつもなく腹が立つ。
龍郷はしおんを抱えたまま部屋を出た。連れ出された廊下も室内と同様に温かい。よく見れば廊下の要所要所にも暖炉が設けられている。そこから暖気が送られてきているのだ。
窓からは中庭を挟んでもう一棟建物が見える。この広い邸のどこもかしこもこんなふうに暖炉が整えられているのだろうか。いったいいくらかければそんな贅沢ができるのか、しおんには想像もつかない。
――って、感心してる場合か。
「おろせ、俺は――」
帰る、という言葉は先ほど奪われたばかりだ。口惜しさを噛み締めながらとにかく大暴れして、どうにかその腕を逃れる。駆け出そうとしたところで大きくつんのめった。
「――ッ!」
振り返れば、着せられていた寝巻きの裾を龍郷が踏んでいる。勝ち誇ったような笑みの形に口の端を持ち上げるのが腹が立つ。
だがしおんは、このずるずるとした寝巻きの前が釦で止められていることに気がつくと、手早くそれをすべて外した。
「――おまえ、」
するりと脱ぎ捨てた抜け殻を手にあっけにとられている龍郷を残し、廊下を駆ける。どこかにあるはずの階段を目指すが、長身の龍郷はすぐ背後に迫ってきていた。
こうなりゃ、どこかの部屋の窓から――
内側から鍵をかければ時間も稼げるだろう。素早く作戦を立て直したしおんは、目についた部屋に滑り込んだ。
爽やかなうす青に塗られた木枠に曇り硝子(がらす)がはめられたその部屋のドアは、明らかに道中の他の部屋と造りが違う。所々配された青い硝子部分が日の光を透かして宝石のように輝いていた。
壁と床には、ドアの木枠と同じ色のうす青と白のタイルが市松に施されている。水の気配がして、どうやら風呂のようだと悟ったときにはもう、龍郷に追いつかれていた。入ってきたドアの前を塞がれて、引き返すことも出来ない。
「その汚れたなりじゃ連れ歩けもしないから風呂にと思ったんだが、自分から進んで飛び込むとは、手間が省けた」
己の迂闊さを悔いたがもう遅い。龍郷は再びしおんの体をひょいと持ち上げると、滑らかな曲線を描く浴槽の中に下ろした。飛び出す間もなく、何かを頭に振りかけられる。
「な、に、すんだ……!」
「暴れるな。ただのシャンプーだ」
「しゃ……?」
「髪を洗う粉だ。うちでは仏蘭西(フランス)から輸入したものを使っているが、そのうちに国産も出回るだろう」
龍郷が言うが早いか、今度は頭上から突然湯の雨が降ってきて、思わず飛びずさった。
「な、なんだ」
見上げれば、壁から瓢箪池で秋枯れの時期見かける蓮の台座のようなものがにょっきり生えている。その無数の穴から、勝手にお湯が降り注いでいるのだった。
龍郷はシャツの袖をまくり、湯で濡れたしおんの髪を洗い始める。シャンプーとやらは見る間に泡立って、汚れが落ちていくのがわかった。
孤児院で暮らしていたときも、こんな風呂には入ったことがない。全員を銭湯に行かせるような金があるわけもなく、風呂といえば盥で行水をすることだった。
「目を閉じていろ」
龍郷が言い、念入りに湯ですすがれる。「いいぞ」と言われて目を開けると、すぐ近くに龍郷の満足げな顔があった。まっすぐに見据えられるとなにか恐ろしさすら感じる龍郷の瞳だが、今は無邪気なものさえ感じる。嫌悪以外の感情で顔を覗き込まれるのも、久しくないことだった。
シャンプーとやらの香りは、女たちのまとう脂粉のにおいよりずっと柔らかい。甘くはあるが清潔なにおいだった。湯は適温で温かい。
「だいぶ見られるようになったじゃないか」
龍郷の言葉でしおんは我に返った。そうだ。こいつは俺を見世物にしようとしてるんだった。危ない。うっかりこの心地よさにほだされてしまうところだった。
「今度は背中を――」
「触んな!」
伸ばされた腕を払いのける。
「こら、じっとしていろ。人がせっかく綺麗にしてやろうと―」
「う、るさい」
それだって人を見世物にしようという下心故だろう。恩に着せられる義理はない。しつこく伸びてくる龍郷の腕をかわしているうちに、しおんの腕は龍郷のネクタイを引っ掴んでいた。
「――」
龍郷がつんのめり、浴槽の中に転がり込む。しおんはすかさずシャワーのコックをひねる。やり方はさっき龍郷を盗み見て覚えた。
「うわ、」
湯の雨が強く降り注ぎ、龍郷が短く悲鳴を上げる。濡れ髪をかき上げながら面を上げるその顔は、苦虫を数匹まとめて噛みつぶしたような表情をしていた。その顔のまま、壁の白いボタンを押す。
なんだ? と訝しむ間もないほどすぐにドアの向こうから「お呼びでしょうか」と声がした。
入れ、という龍郷の招きに応じて室内へ入ってきたのは、初老の女性だった。灰色の生地に白い襟と袖がついた洋装に身を包んでいる。ワンピースというやつなのだろうが、たまに六区で見かける女たちよりずいぶん地味、そして生地は上等だった。髪は襟足の辺りで一つにまとめている。少なくともしおんはその年齢で日本髪でもなく洋装をしている女というものを初めて間近に見た。
いやそれよりなにより。
――さっき、あれで呼んだんだよな。
壁に備え付けられたボタンはおそらく使用人の控え室につながっていて、押せば主の求めに応じて誰かがやってくるのだろう。そんな暮らしぶりを初めて見た。
「俺が着替えている間に、こいつがちゃんと風呂に入るように見張っててくれ」
「かしこまりました」
「ふざけんな、俺は―」
「あまり聞き分けがないようでしたら、若い女中を呼んで手足を押さえつけた上でわたくしが念入りに」
「――自分で入る!」
主人が主人なら、使用人も使用人だ。しおんはふたりを浴室から追い出すと、諦めて湯船につかった。
風呂から出ると、浴室の続きの部屋には「一真(かずま)様のお小さい頃のお召し物ですが、ひとまずこちらをお召しくださいとのことです」と女中が用意していった着替えが置かれていた。
あいつの?
心底嫌な気分で眉間に皺が寄ってしまったが、素っ裸は逃げ出すのにも不都合だ。仕方なく袖を通すと、肌が触れただけで上等とわかった。濃紺の生地の袖の先は手首にぴったり沿うようにすぼまっていて、白いラインが入っている。首の後ろには同じく白いラインの入った大きな襟がついていた。セーラー服というやつだ。下は膝下までのズボン。こんな小綺麗な格好をした子供はもちろん浅草では見たことがない。
ともかく風呂に入って体はすっかり軽くなったし、着る物も得て、逃げる算段は整った。
そっと浴室のドアを開け、辺りを伺う。長い廊下の左右どちらにも、人影はなかった。
――いいぞ、今のうちに。
「お部屋でお待ちいただくようにとのことです」
廊下に足を踏み出した瞬間背後で声がして、危うく飛び上がりそうになる。恐る恐る振り返れば、声の主はあの使用人だった。今確かに廊下に誰もいないことを確かめたはずだったのに。
裕福層の邸では、使用人の姿が目につくのは主人や来客に失礼になる、と専用の隠し通路が設けられていることが多いなどということをしおんが知ることになるのは、もう少し先のことだ。
ともかく今はひたすらに「忍者かよ」と肝を冷やしているしおんだが、肝を冷やしつつも龍郷の言葉を思い出していた。
『その汚れたなりじゃ連れ歩けもしない』―ということは、これから龍郷は自分を伴って出かけるつもりなのだろう。そのときを待ったほうが賢いかもしれない。
――ババアをわざわざ蹴倒していくのも寝覚めが悪いしな。
小さな頭の中で策を練りながら案内されるまま部屋に戻ると、龍郷の姿はなかった。すでに出かけるばかりに整えていた服から髪まで濡れたから、手間取っているのかもしれない。
――となれば、だ。
しおんは目をすがめて部屋の中を見渡した。数々の失礼な扱いを思えば、逃げ出す前に少しばかり金目のものを頂戴したって罰は当たらないだろう。
寝台の周りをざっと見てみて、小さな丸い銀の器を見つけた。手のひらに収まる、失敬するにはおあつらえ向きの大きさだ。表には目立つ細工はないが、開けてみると蓋の裏側に龍の文様が刻まれていた。表から見ただけでは出自がわからなさそうなのも売りさばくのに都合がいい。
幸先がいいぞ。
いい獲物に気を良くし、中に入っていた小さな金平糖をかじりながらしおんはさらに部屋を見渡した。
目覚めに龍郷と野々宮と呼ばれた男が話をしていた書斎のドアが目に留まる。続きの扉を細く開けて体を滑り込ませると、壁一面が書棚になっていた。そのすべてにみっしり本が収まっている。ひとつひとつ革や布で張られているようで、多くは背表紙に金色の文字が刷り出されている。もちろんなにやら虫の這ったようなその字を見てもしおんにはなにが書いてあるのかはさっぱりだ。おそらくこれらも高価なものなのだろうが、持って逃げるには嵩張りすぎる。
持ち運べて売りさばけそうなもの……腕時計とか。
わざわざ髪の毛を洗う粉とやらも舶来品を使うくらいなのだから、時計だって当然いい舶来品を使っているだろう。外して置いておくとしたら机の上か。そう考えて飴色に磨かれた机に回り込んだ拍子、床の敷物に足を取られる。とっさに机につかまって体を支えると、その衝撃でなにかが床に落ちた。
――やべ、
しゃがみ込んで、見つけた〈なにか〉は、弧を描いた本体に紙を挟んである、奇妙な代物だった。この形状が揺れやすかったのだろう。拾い上げてみると、紙の面に青黒いインクのあとがぽつぽつとにじんでいた。そういえば孤児院でも、宣教師が本国への金の無心を万年筆で書いて、インクをこういうもので押さえていた気がする。孤児院で見た物とは違って木製部分に凝った彫りが施してあるが、これはそんなに金になるものでもなさそうだ。
舌打ちして拾い上げたとき、机に半ば隠された棚の一番下できらりと鋭い目が光った。
「ひ……っ」
――なんか、いる……! ……る?
きゅっと喉元を締め上げられたように驚いたのは束の間で、気を落ち着けてみれば、光る目を持つそいつは、生き物ではなかった。
くまの形をした人形だ。
といっても、しおんが目にしたことのある、もっと簡素な布でできたものとはまったく別物で、本物の生き物のようなふわふわした毛を持っている。耳のところに縫い付けられた小さな布には、棚に並ぶ本と同じようなうねうねとした字のような模様のようなものが織り出してある。おそらくはこれも舶来物だろう。
人形って、だいたいは親が買ってくれるもんだ。
しおんの眉間に、無意識のうち皺が刻まれる。
立ったりしゃがんだりしたせいで、風呂上がりに着た服の生地が上等であることはあらためてよくわかっていた。
上等な服。上等で本物のような人形。龍郷が子供だった頃を思い描くことができなくとも、ひとつだけはっきりとわかっている。
なにもかも俺とは正反対だ。
すべてを持っていて、好きに人を動かせる側の男。
「この部屋に金目の物はないぞ」
張本人の声に腹を決めて机の下から這い出すと、着替えを終えた龍郷が戸口に体を預けて立っていた。乱れた髪も元通り整えられて、相変わらず咎めるというより楽しんでいるような風情だ。
「音楽隊に入れば食事と住む場所の世話はしてやると言っているだろう」
昨日の今日で他人の生き方を変えられるとでも思っているのだろうか。行きたいところもやりたいこともないしおんだが、物のような扱いには腹が立つ。
「俺はそんなものに入りたくない」
あらためてはっきり告げても、龍郷には少しも堪えた様子がなかった。
「そうはいかない。支配人に払った金の分くらいは働いてもらわないと」
「は? ……あいつ」
昨日たまたま紛れ込んだだけで、自分と支配人は無関係だ。そもそも水をぶっかけて追い立てたのはあいつだったのに、ちゃっかり金を受け取っているなんて。
所詮この世はそんなものだ。最初から恵まれた奴と、狡く図太い奴が得をする。いまさらそんなことをまくしたてる気にもならず、しおんは頑強にくり返した。
「とにかく、俺は人前に出るのなんて、いやだ」
この髪と瞳のせいで、どこへ言っても奇異の目で見られた。ただでさえ隠れるように生きてきたのだ。百貨店の音楽隊だなんてとんでもない。
百貨店に買い物に来られるような奴らはどのみち恵まれている層だ。そんな奴らをなにも持たない俺が楽しませてやらなきゃいけない理屈がどこに―ふつふつと憤りがわき出して止まらないというのに、龍郷はまったくどこ吹く風で、面白そうに訊ねてくる。
「なら、払った金の分はどうする。返すあてがあるのか?」
「俺が受け取ったわけじゃ……!」
叫んではみるが、義賊でもない限り金を払っておいてはいそうですかと放免する者もいないだろう。金さえあれば路上で凍えなくとも済む。翻ってみれば、払った側が相応のものを要求するのも当然のことだとしおんは身に染みていた。あの団長が金を返すとも思えない。だったら一番自分にとって被害が少ないのは――
「……ここの下働きとか」
「ここで暮らすのも今は俺ひとりだからな。手は足りてる」
最も現実的だと思われる提案を無碍にされ、しおんは言葉に詰まった。そうなるともう、なにも持たない自分に支払えるものなどない。
――いや。
なくはない。あと、ひとつだけなら。
しおんは龍郷には見えない机の影で、ぎゅと拳を握った。
「……じゃあ〈そういう〉ので払う」
「そういう?」
龍郷は怪訝そうに眉を顰める。しおんは問いには答えず、ただ唇を噛んで押し黙った。そういうつもりがある奴になら、これで通じる。
しばらくして「なるほど」と呟いた男の声には、明らかに棘があった。
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
180
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる