5 / 10
第5話「友達、という距離」
しおりを挟む
第5話「友達、という距離」
「律子さん、また会いましたね」
洋一は、再び開かれた“シングルナイト・交流編”の会場で、赤いカーディガンを羽織った女性に声をかけた。
律子は驚いたように目を丸くし、それから柔らかく笑った。
「あら、洋一さん。こんな偶然もあるんですね」
「いえ、ちょっと期待してました。律子さん、もう一度来るような気がして」
「そうですか?私は、前回で最後にしようと思ってたんですよ」
「どうして?」
「……自分が何を求めてるのか、わからなくなったから」
律子はそう言って、テーブルのティーカップに視線を落とした。
「恋愛か、友達か、それとも、ただ寂しさを紛らわせたいだけなのか……自分でも、まだ答えが出ていないんです」
「でも、来た。きっと、それでいいと思います」
洋一の声は、やさしく、力強かった。
彼は60歳を過ぎて、定年を迎えた元高校教師。
いまは趣味のカメラを片手に、自由気ままな生活を送っている。
律子は58歳。元看護師で、数年前に早期退職。
一人暮らしを選んだが、時間ができるほど、空白が心に染みるようになった。
二人は、最初のイベントで偶然同じグループになり、他愛のない会話を交わしただけだった。
でも、それが妙に心に残っていた。
「洋一さんは、何か見つかりましたか?ここで」
「……まだ。でも、何かを探してる仲間がいるってだけで、少し気持ちが救われる気がします」
律子は、小さくうなずいた。
「……私ね、昔から、友達って苦手なんです。話を聞くのは得意なんですけど、自分のことを話すのが怖くて」
「それは、誰かに否定された経験があるから?」
律子は、少しだけ驚いた表情を浮かべた。
「……そうですね。若い頃、親友だと思っていた人に、いちばん大事なことを打ち明けたら、次の日には他の人に広まっていて。何かが壊れた気がしました」
「それ以来、壁をつくるようになった」
「はい。でも、そのせいで、本当に寂しくなったのは、自分だったのかもしれません」
洋一は、しばらく黙ってから言った。
「俺も、教師という仕事柄、ずっと“人に頼られる”側にいた。でも、定年を迎えてふと気づいたんです。自分は、誰に頼ってきただろうって」
律子の目が、そっと洋一に向けられる。
「今なら、頼ってもいいんじゃないですか?お互いに」
その言葉に、洋一は照れたように笑った。
「じゃあ……今日は、散歩でもしませんか?このあと、駅前の公園に桜が咲いてるらしいんです」
「桜?まだ早いんじゃ……」
「いえ、早咲きの種類らしくて。人も少ないし、静かに歩けます」
律子は、一瞬迷ったような表情を見せたが、やがて頷いた。
「はい。行きましょうか」
駅前の小さな公園には、確かに数本の桜が咲き始めていた。
ピンク色の花びらが、夕方の空に淡く滲んでいた。
「きれいですね……」
律子がぽつりとつぶやくと、洋一は軽く笑った。
「律子さん、なんだか学生みたいですよ」
「失礼ね。もうすぐ還暦なのに」
「還暦でも、笑う姿が素敵なら、それでいいじゃないですか」
ふと、二人の距離が近づく。
言葉にするにはまだ早い。
でも、心の奥にあった“孤独”が、そっと溶けていくようだった。
「洋一さん、私……友達、になれるかもしれません。今度こそ」
「ええ。俺も、そんな気がしています」
春は、始まりの季節。
誰かと並んで歩く、その一歩が、少しずつ未来を変えていく。
「律子さん、また会いましたね」
洋一は、再び開かれた“シングルナイト・交流編”の会場で、赤いカーディガンを羽織った女性に声をかけた。
律子は驚いたように目を丸くし、それから柔らかく笑った。
「あら、洋一さん。こんな偶然もあるんですね」
「いえ、ちょっと期待してました。律子さん、もう一度来るような気がして」
「そうですか?私は、前回で最後にしようと思ってたんですよ」
「どうして?」
「……自分が何を求めてるのか、わからなくなったから」
律子はそう言って、テーブルのティーカップに視線を落とした。
「恋愛か、友達か、それとも、ただ寂しさを紛らわせたいだけなのか……自分でも、まだ答えが出ていないんです」
「でも、来た。きっと、それでいいと思います」
洋一の声は、やさしく、力強かった。
彼は60歳を過ぎて、定年を迎えた元高校教師。
いまは趣味のカメラを片手に、自由気ままな生活を送っている。
律子は58歳。元看護師で、数年前に早期退職。
一人暮らしを選んだが、時間ができるほど、空白が心に染みるようになった。
二人は、最初のイベントで偶然同じグループになり、他愛のない会話を交わしただけだった。
でも、それが妙に心に残っていた。
「洋一さんは、何か見つかりましたか?ここで」
「……まだ。でも、何かを探してる仲間がいるってだけで、少し気持ちが救われる気がします」
律子は、小さくうなずいた。
「……私ね、昔から、友達って苦手なんです。話を聞くのは得意なんですけど、自分のことを話すのが怖くて」
「それは、誰かに否定された経験があるから?」
律子は、少しだけ驚いた表情を浮かべた。
「……そうですね。若い頃、親友だと思っていた人に、いちばん大事なことを打ち明けたら、次の日には他の人に広まっていて。何かが壊れた気がしました」
「それ以来、壁をつくるようになった」
「はい。でも、そのせいで、本当に寂しくなったのは、自分だったのかもしれません」
洋一は、しばらく黙ってから言った。
「俺も、教師という仕事柄、ずっと“人に頼られる”側にいた。でも、定年を迎えてふと気づいたんです。自分は、誰に頼ってきただろうって」
律子の目が、そっと洋一に向けられる。
「今なら、頼ってもいいんじゃないですか?お互いに」
その言葉に、洋一は照れたように笑った。
「じゃあ……今日は、散歩でもしませんか?このあと、駅前の公園に桜が咲いてるらしいんです」
「桜?まだ早いんじゃ……」
「いえ、早咲きの種類らしくて。人も少ないし、静かに歩けます」
律子は、一瞬迷ったような表情を見せたが、やがて頷いた。
「はい。行きましょうか」
駅前の小さな公園には、確かに数本の桜が咲き始めていた。
ピンク色の花びらが、夕方の空に淡く滲んでいた。
「きれいですね……」
律子がぽつりとつぶやくと、洋一は軽く笑った。
「律子さん、なんだか学生みたいですよ」
「失礼ね。もうすぐ還暦なのに」
「還暦でも、笑う姿が素敵なら、それでいいじゃないですか」
ふと、二人の距離が近づく。
言葉にするにはまだ早い。
でも、心の奥にあった“孤独”が、そっと溶けていくようだった。
「洋一さん、私……友達、になれるかもしれません。今度こそ」
「ええ。俺も、そんな気がしています」
春は、始まりの季節。
誰かと並んで歩く、その一歩が、少しずつ未来を変えていく。
0
あなたにおすすめの小説
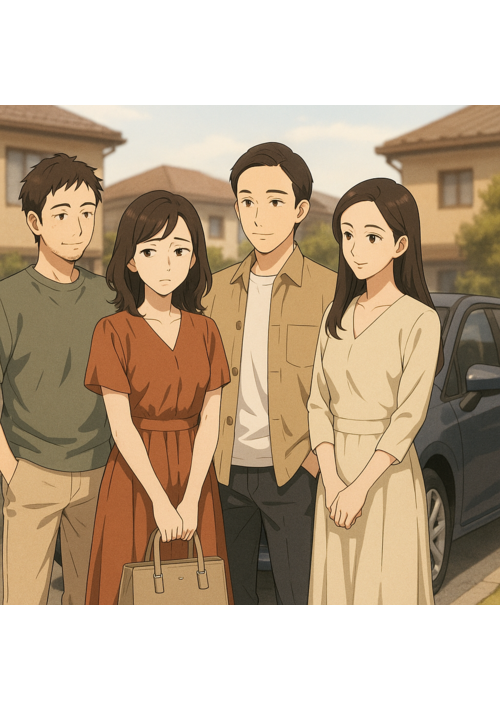

心のすきまに【社会人恋愛短編集】
山田森湖
恋愛
仕事に追われる毎日、でも心のすきまに、あの人の存在が忍び込む――。
偶然の出会い、初めての感情、すれ違いのもどかしさ。
大人の社会人恋愛を描いた短編集です。


【完結】泡になった約束
山田森湖
恋愛
三十九歳、専業主婦。
夫と娘を送り出し、静まり返ったキッチンで食器を洗う朝。
洗剤の泡が立っては消えるその繰り返しに、自分の人生を重ねながら、彼女は「ごく普通」の日常を受け入れている。
愛がないわけではない。けれど、満たされているとも言い切れない。
そんな午前中、何気なく出かけたスーパーで、背後から名前を呼ばれる。
振り返った先にいたのは、かつて確かに愛した男――元恋人・佐々木拓也。
平穏だったはずの毎日に、静かな波紋が広がり始める。

極上イケメン先生が秘密の溺愛教育に熱心です
朝陽七彩
恋愛
私は。
「夕鶴、こっちにおいで」
現役の高校生だけど。
「ずっと夕鶴とこうしていたい」
担任の先生と。
「夕鶴を誰にも渡したくない」
付き合っています。
♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡
神城夕鶴(かみしろ ゆづる)
軽音楽部の絶対的エース
飛鷹隼理(ひだか しゅんり)
アイドル的存在の超イケメン先生
♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡
彼の名前は飛鷹隼理くん。
隼理くんは。
「夕鶴にこうしていいのは俺だけ」
そう言って……。
「そんなにも可愛い声を出されたら……俺、止められないよ」
そして隼理くんは……。
……‼
しゅっ……隼理くん……っ。
そんなことをされたら……。
隼理くんと過ごす日々はドキドキとわくわくの連続。
……だけど……。
え……。
誰……?
誰なの……?
その人はいったい誰なの、隼理くん。
ドキドキとわくわくの連続だった私に突如現れた隼理くんへの疑惑。
その疑惑は次第に大きくなり、私の心の中を不安でいっぱいにさせる。
でも。
でも訊けない。
隼理くんに直接訊くことなんて。
私にはできない。
私は。
私は、これから先、一体どうすればいいの……?



こじらせ女子の恋愛事情
あさの紅茶
恋愛
過去の恋愛の失敗を未だに引きずるこじらせアラサー女子の私、仁科真知(26)
そんな私のことをずっと好きだったと言う同期の宗田優くん(26)
いやいや、宗田くんには私なんかより、若くて可愛い可憐ちゃん(女子力高め)の方がお似合いだよ。
なんて自らまたこじらせる残念な私。
「俺はずっと好きだけど?」
「仁科の返事を待ってるんだよね」
宗田くんのまっすぐな瞳に耐えきれなくて逃げ出してしまった。
これ以上こじらせたくないから、神様どうか私に勇気をください。
*******************
この作品は、他のサイトにも掲載しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















