4 / 8
第4章
しおりを挟む
第4章-1 懐かしい再会
峠への街道をおおう夜霧は、月明かりを吸い込み銀灰に揺れていた。
アイリーンは白銀の走竜〈セレーネ〉を林道へ滑り込ませ、馬蹄音を抑えるように手綱を絞る。木々の隙間から灯火が瞬いた。山腹をくり抜いて造られた前線補給所――“アストラ第七洞営”だ。
ここは十年前、魔王戦役時に彼女がたびたび出入りした隠密拠点でもある。当時の仲間は各地へ散ったが、補給所を束ねるのは変わらずあの人――
耳に届く低い口笛。
アイリーンはマントを翻し、岩壁の影へ降り立った。暗がりで待っていた男が兜を外し、灰銀の短髪をくしゃりと掻く。
「やれやれ。白銀の姫が直々に来るとは、月に兎が降るよりびっくりだ」
低くしわがれた声。その主、ガウェイン・ザカリアス。かつて王国第一騎士団を率いた猛将であり、今は補給路を裏から支える“影の大隊長”だ。銀縁の眼帯が夜光を弾き、片目がなお鋭さを失わない。
「お久しぶりです、ガウェイン隊長」
アイリーンは兜に見立てた革帽を取る。銀髪が月光に瞬き、ガウェインは片眉を上げた。
「その呼び方はやめろと十年言ったろうに。――で? 今日はただの懐古談か、それとも」
「峠が危ないわ。“血濡れのベルゼ”が動く。夫の本隊は罠に気づいていない」
囁きは風より低く、それでいて戦鼓のように強い。
ガウェインは短く息を呑んだ。
「ベルゼだと……魔王直轄のあの狂犬が、囮を捨てて表へ? 情報筋は確かか」
「確かよ。魔族刻印の封蝋と、眠り砂を積んだ補給車両。全部、王都を出る前に抑えたわ。裏で操るのはアクノ公爵。王命を偽造して私を屋敷から排除し、夫を“名誉の戦死”に追い込む筋書き」
ガウェインは渋面をつくり、岩壁を拳で叩いた。
「相変わらず王都貴族の陰謀は嗅ぎたくもねえ匂いだ。だがお前さん一人でベルゼを抑えるのは骨が折れる」
「だから来たの。あなたの“竜牙隊”に力を借りたい」
アイリーンは短杖を引き抜き、紋章を露わにした。七芒星の中央に凍る聖獣――かつて勇者一党だけが帯びた証。「白銀の剣姫」の真標。
眼帯の奥でガウェインの片眼が燃える。
「……あの頃の俺たちは“国の狗”じゃなく“人の盾”だった。いいだろう。峠前線に先回りし、補給隘路に伏兵を置く。お前は本隊へ潜り込み、レイフォード公爵を動かせ」
アイリーンの唇が淡く弧を描く。
「感謝を」
「感謝など要らん。――ただ、無理はするな」
巨大な手が彼女の肩をぽんと叩く。その重みは友情の鎧のように温かい。
◆ ◆ ◆
洞営深部。火槌を打つ音と乾いた号令が交差する。竜牙隊の兵たちは影の補給を担う熟練揃いだ。アイリーンが姿を現すと、はっと直立した若兵が声を漏らす。
「あ、あの方が噂の……!」
「静かに。今は“白銀”の名を伏せる時だ」
ガウェインの一喝に空気が引き締まる。
アイリーンは食料木箱の間を縫うように歩き、鉄製の長箱を見つけた。蓋を開ける。中には深藍の鏡鱗甲冑――十年前、彼女が魔王の心臓を貫いた時の装備が眠っていた。刃を弾き、炎を透す希少金属“ミスリオル”製。
指で触れると鎧は小さく歌い、主を懐かしむようにブルーグレーの光を散らす。
「覚えていてくれたのね」
「縁起物は捨てられなくてな」
ガウェインははにかむ。獅子が仔猫に頭を撫でられたような不器用な照れ笑い。
闇を裂く遠雷が轟いた。峠方面。
アイリーンは鎧を抱え、決然と振り向く。
「時が来たわ。竜牙隊を動かして」
「応っ!」
号令が洞営にこだまし、兵たちが一斉に立ち上がる。箱に蓋が戻され、荷駄に括りつけられた。
アイリーンは愛馬セレーネの鞍に鎧をくくり、鞭打つように舌を鳴らす。馬の瞳が星光を映し、力強く嘶いた。
見送りに立つガウェインが片手を挙げる。
「十年前と同じ合図でいいか、白銀!」
「もちろん。月が雲を裂く時――蒼光三度」
「了解! 必ず峠を死地にさせてやる!」
アイリーンは頷き、セレーネの背に軽やかに跳び乗った。
洞窟を抜け出た瞬間、山風が銀髪を大きく逸らす。
夜空の月がちょうど雲間から姿を覗かせ、剣姫の笑みを照らした。
――懐かしい絆はまだ折れていない。
その確信が胸を満たし、少女の頃のように心が澄む。
そして次の瞬間、彼女は戦乙女としての自分へ鋼と化した。
丘陵を駆け降りる足音が雪面に火花を刻む。
峠まで残り三リーグ。
魔王軍の牙と人の奸計が交差する前に、白銀の刃は再び歴史に灼光を刻むだろう。
第4章-2 夫の誤解(約2,300字)
峠の臨時本営は黄昏とともに沈黙した。
裂けた雲のあいだから覗く夕陽が、剥き出しの岩肌を血のように染め上げる。
レイフォード公爵フェルディナンドは帷幕の外で甲冑を解き、薄い湯煙に紛れるように肩を回した。昼の一斉突撃――敵の牙城を退けたとはいえ、兵の損耗は重い。周囲では衛生兵が黙々と止血や縫合に当たり、重い呻き声が風に流れていく。
その凄惨な光景を前にしてなお、公爵の胸には燠火のような奇妙な高揚が燻っていた。
昼の激戦で、彼らを救った銀閃。あの“女勇者”の姿が網膜に焼き付いて離れないのだ。
――銀の髪が翻り、剣に纏った蒼雷が魔物の群れを一刀両断。
――まるで天上の星が落ち、地を灼き払うような威容。
彼女が駆け抜けた後には血の臭いすら残らず、ただ冷たい風だけが澄んでいた。
「公爵閣下」
副官トラヴィスがそっと声を掛けた。目の下の隈が深く、疲労を隠せない。
「負傷者の整理が終わりました。死傷総計、今朝の報告より一割減です」
「……うむ。女勇者のおかげだな」
「はい。あの方がいなければ、我らは峠の麓で壊走していたでしょう」
公爵は頷きつつテント裏の高台へ歩き、夕焼けに浸る峡谷を見下ろした。
胸に去来するのは感謝、畏敬、そして――嫉妬にも似た感情だ。
己の軍を救った英雄に抱くべきは純粋な敬意のはず。だが心の底で何かがざらつく。
(もし、妻があのような力を持っていたなら……)
唐突に浮かんだ想像を、彼は苦い笑みで打ち消した。
「公爵、あの方にお礼の使いを出しましょうか?」
トラヴィスの提案に、公爵は逡巡の末、首を横に振った。
「名乗りを拒む者に過度な探索は無礼だ。それに……いつ現れるかわからぬ。礼は次に会った時で構わん」
内心では“ぜひ対面したい”という思いが募る。しかしあれほどの戦功を示す人物に比肩し得るものを、平凡な妻は持たない――そう悟ると同時に、どこかで安堵している自分がいた。妻の無力を嘆いてきたはずなのに、強すぎる女は手に余ると恐れている。そんな矛盾が胃を突き上げる。
「……閣下?」
副官の呼びかけに我に返り、公爵は声を潜めた。
「おまえは、あの女勇者の顔をはっきり見たか?」
「一瞬だけですが。蒼い瞳でした。吸い込まれそうなほどに……美しかった」
「……そうか」
目の前に、紅茶を淹れるたびに手元を震わせる妻のぼんやり顔が浮かぶ。
公爵は拳を固めた。“謎の英雄”と“無能な妻”――両極端の女性像が頭の中でせめぎ合い、やがて奇妙な妄念を生む。もし自分の伴侶が英雄であったなら、家も領民も、もっと輝いていたのではないか、と。
そのとき遠方で狼煙が上がり、警鐘が連打された。
斥候の合図――敵の再襲来だ。
公爵はすべての雑念を剣とともに鞘へ収め、兜を被り直した。
「副官! 全隊に配置を!」
脳裏に残った女勇者の残像だけが、闇を裂く灯のように彼を奮い立たせた。
◆ ◆ ◆
一方その頃。
峠裏手の斜面を駆け下りる白い影があった。アイリーンだ。
月影を焼くような剣勢で魔物の斥候を屠り、岩陰に身を滑り込ませる。遠方には夫の指揮幕営。その帳の中で彼が悩みを滲ませることなど知る由もない。
彼女の耳に届くのは兵たちの苦悶と剣戟の金属音、そして自らの心臓の鼓動だけ。
(お館様……いまも私を“頼りない妻”と思っているでしょう。でもいいの)
剣を杖に持ち替え、霧を裂く雷光をふた筋走らせる。敵の後衛が沈黙し、本陣へ迫る脅威が一つ減った。
息を整えながら、彼女は遠い帷幕を見やり口の中でだけ呟く。
(あなたが前だけを見ること。そのために私は背を斬る。
いつか、あなたが真実に辿りつく日まで)
夜風が髪を揺らす。蒼い瞳に宿る光は、決して届かぬ場所へ投げた静かな祈りだった。
第4章-3 名もなき忠義
雪煙をかき分けて峠に吹き込む夜風は、常よりも生暖かく感じられた。
魔王軍が放つ〈瘴気〉が空気を濁し、雪の結晶を鈍い灰色へ変えているのだ。
アイリーンは岩陰にしゃがみ込み、指先でその灰の粒をそっと弾いた。じゅっ、と焦げる音。微量の魔力が篭っている証拠だった。
(……瘴気濃度が上がっている。ベルゼが近い)
遠く、本営の方角を示す狼煙が再び上がる。
しかし今夜は救援など望めない。竜牙隊は峠裏の補給道を封鎖するため分散し、公爵本軍も再襲に備え張り付いた。
夫の背に届く矢を折るのは、今は自分ただ一人――そう言い聞かせ、銀の髪を結い直す。
「……さて」
短杖を拾い上げると、杖先の蒼石が月光に呼応して淡く脈動した。
アイリーンはそっと瞳を閉じ、意識を戦場の地脈へ沈める。
――土中に潜む魔族歩兵三十七、樹上の猿狼八頭、後衛の呪術師が二。
そして谷底を進軍中の重装騎兵。嗤うような血臭が風に混じる。
(まず阻むべきは後衛。呪術師を残せば瘴気は濃くなる)
口に出さず計算を終えると、身をひるがえし雪面を蹴った。
滑るような斜行で魔族の警戒網を抜け、樹上の猿狼へ跳躍。
瞬間、剣を振り抜く。凍気の刃が三体の首を刈り、残りの群れが悲鳴とともに散開した。
地表に降りるより速く、アイリーンは杖を逆手に掲げ、三重の魔法陣を展開する。
「──《雷牙穿》」
閃光が夜空を引き裂き、呪術師の詠唱陣を直撃した。
凄まじい爆風が巻き起こり、瘴気を帯びた霧が一息に浄化される。
だが雷鳴が収まる間もなく、谷底から金属の咆哮が返った。重装騎兵が一直線に駆け上がって来る。
アイリーンは剣を深く構え直した。
──だが次の瞬間、奇妙なことが起こる。重装兵たちがいきなり馬を止め、一斉に視線を別の方向へ向けたのだ。
夜闇にかすかに揺らめく蒼光。峠裏の補給道から、巨弩の矢が雨のように降り注いで来た。
竜牙隊が伏兵を完了させた合図――蒼光三度。
ガウェインとの取り決めが、寸分違わず実行された証だった。
(……頼もしいわ)
アイリーンは胸の奥で礼を言い、剣先を返す。動揺した魔族兵を瞬時に切り崩し、谷底へ追い落とす。
やがて瘴気がほとんど消えたと判断すると、剣を腰へ収め、再び本営を振り返った。
◆ ◆ ◆
本営では、負傷兵を寝かせた衛生幕の中が慌ただしかった。
レイフォード公爵は鎧を脱ぐ間もなく、次の配陣を決めるため地図の前に立っている。
しかし兵が持ち込む最新戦況は、不思議とこちらに有利なものばかりだった。
「猿狼斥候部隊、全滅を確認!」
「敵呪術師の魔力反応、消失!」
「谷底からの騎兵は補給道で殲滅!」
副官トラヴィスが驚愕を隠せない。
「閣下、これは……いったい誰が」
「……“彼女”だろう」
そう呟きながらも、公爵の心は複雑だった。
自軍が苦戦しているあいだ、妻は屋敷でぼんやりと紅茶を啜っているはず――その光景を打ち消すかのように、銀の英雄の姿が輝く。
「くそ……戦場ではかくも役立たずな自分に苛立つのか」
思わずつぶやき、拳を握り締める。その指先が白くなるほど力がこもっていた。
◆ ◆ ◆
月が天頂を越える頃。
アイリーンは峠の背後に取り付いた最後の猿狼を斬り伏せ、剣を収めた。
鎧に跳ねた魔血を拭いながら、深い息をつく。
これで夫の帷幕を急襲できる敵はいない。奴らが再編する前に、公爵軍は態勢を立て直せるはずだ。
(……もう少しだけ近くで様子を)
そう考え、本営の灯火を遠目に見守っていたとき。
陣の外れで、ふいに人影が倒れ込むのを視界の端が捉えた。
斥候兵。肩から流れる血が雪を黒く染めている。
アイリーンは遮蔽物の陰に剣と杖を置き、“妻”の顔に戻るため髪と頬を魔法でぼんやり整えた。
そのまま走り寄り、兵の背を支える。
「大丈夫、しっかり」
声色を限界まで柔らかく落とす。兵は虚ろな目で彼女を見た。
「……ど、どちら様……?」
「ただの旅の療術師ですわ。ほら、痛み止め」
サッシュから小瓶を取り出し、複合鎮痛薬を飲ませる。
兵の呼吸がやや整ったのを確認すると、彼女は軽く微笑んだ。
「隊へ戻って。あなたの上官が待っているでしょう?」
「は……はい……!」
兵が歩き去る後ろ姿を見届けるまで、アイリーンは立ち尽くしていた。
自分が戦場へ現れたことを悟らせぬよう、救護ですら影に徹する――それが名もなき忠義の条件だ。
◆ ◆ ◆
深夜。
本営の高台で、公爵は遠くの闇に向けて無意識に頭を垂れた。
誰に、と問われれば答えに窮する。それでも礼を言わずにはいられない。
その姿は、闇に潜むアイリーンの眼に映り、胸をじんと温めた。
(お館様……あなたが“ありがとう”と呟いた声、ちゃんと届きましたわ)
涙ではなく、静かな笑みがこぼれる。
彼女は剣を背に回し、踵を返した。
名を告げる必要などない。ただ守る。それこそが、自分にとって何より甘美な報酬だから。
薄雲に月が隠れ、夜はさらに深くなる。
星の瞬きの下、ぼんやりした公爵夫人の忠義は、今日も光より速く夫の背へ届いていた。
第4章-4 すれ違う想い
峠を包んだ深夜の静寂は、何より雄弁だった。
雪の反射光が消え、雲間に沈んだ月が闇の色を濃くする。残ったのは焚き火のかすかな煌めきと、折れた矢柄が時折ぱきりと弾ける音──それだけだ。
帷幕の内側で、レイフォード公爵フェルディナンドは粗末な折り畳み椅子に腰掛けていた。鎧の継ぎ目には乾ききらぬ血がこびりつき、剣帯は幾度も締め直した跡で裂けそうになっている。
提灯の灯は弱く、紙障子に投げた影はやつれた己を誇張していた。副官トラヴィスが昼の戦果を読み上げたが、公爵はほとんど耳に入っていない。
──いま、峠の外に立っているであろう銀の女勇者は、どんな面持ちで夜を切り抜けているのか。
想像は夜気のように胸を冷やし、同時に熱した鉄のように心を焦がす。
「……閣下、ご休息を。まだ仮眠を一刻しか取られておりません」
「構わん。うたた寝などしていられる状況ではない」
副官が下がると、帷幕は再び静けさに閉ざされた。
公爵は顎に手を当て、視線を俯く。脳裏に浮かぶのは、屋敷で紅茶をこぼしながら慌ててハンカチで拭く妻アイリーンの姿。長年連れ添ってなお、彼女は剣どころか包丁の扱いすら覚束ない。
──いや、覚束ない“ふり”をしているのかもしれない。
その刹那、昼間見た女勇者の蒼い瞳が重なった。あの深さ、あの情熱。何かをひたむきに守ろうとする者だけが持つ光。
「……ばかな」
否定の声が漏れる。それでも思考は勝手に巡る。
もしあの女勇者がアイリーンと同一人物だったなら──。頭のどこかで囁く甘い妄想。しかし現実を思い返せば、屋敷での彼女に剣技も魔術も見たことはない。鼻緒を踏み外して転ぶ彼女の姿しか、記憶にないのだ。
「嗚呼、私の妻があのような力を……」
言いかけて、言葉を噛み殺した。
“力”を望む心と、“変わらぬ平凡さ”を願う心。その矛盾が胸を刺し続ける。もし妻が強すぎる者だったなら、畏れと距離が生まれ、自分は彼女を守る側でなくなるのではないか──それもまた、武骨な男の小さな臆病だった。
◆ ◆ ◆
そして同時刻。
本営を見下ろす断崖の途中に、風と同化した影があった。
アイリーンは岩肌に膝をつき、帷幕を照らす灯火を静かに見守っている。
瘴気が払われた後も小競り合いは続き、彼女は何度も本営へ迫る敵影を斬り伏せた。それでも夫が無事だと確信できるまでは、近寄ることも正体を明かすことも出来ない。
(お館様……あなたの背中はまだ一点の翳りもないわ)
思わず微笑みが漏れた。
だが次の瞬間、夫のテントから洩れた独白が耳に届く。風に乗った微かな声。
──私の妻があのような力を。
アイリーンの胸が小さく震えた。夫の苦悩も羨望も、その全てが痛いほど伝わる。だが彼の中に芽生える“英雄に対する憧れ”は、まだ自分へ向いていない。
遠い距離を埋めるには、真実を告げることが最も速い。しかし今その行為は、夫から“自分で戦う機会”を奪うかもしれない。彼は一人の武人として、峠の戦いを勝ち抜かねばならないのだ。
(知っているの。あなたは表も裏も強くあってほしい)
アイリーンは胸元のペンダントを握りしめる。
それは夫が結婚祝いに贈った瑠璃石の首飾り。ぼんやり顔の彼女が落とさないよう丈夫な革紐を通した、質素なものだ。それでもアイリーンにとっては世界の宝冠より重い。
(私はあなたを信じている。だからあなたも、いつかなにも疑わず私を信じて)
◆ ◆ ◆
帷幕の中。
公爵は立ち上がり、剣を抜いた。刃に映る己の目は躊躇と決意の狭間で揺れている。
「私は剣で道を切り開く。それが、己の妻を守る唯一の証明だ」
そう呟いた時、テント入口の布が捲れ、副官が飛び込んだ。
「緊急報告! 南東尾根で敵重装部隊の動き。斥候によると“血濡れのベルゼ”が自ら指揮を──」
「来たか……! 全軍、迎撃陣形へ移行。私が前に出る!」
公爵は兜を深く被り、剣を掲げた。胸のざらつきは、戦場の熱量へ押し流す。
──英雄の背中を追う自分ではない。自分が英雄になるのだ、と。
◆ ◆ ◆
崖上で見送るアイリーンの頬を、冷たい風が撫でた。
茸雲のように立ちのぼる狼煙。遠雷のような鬨の声。
彼女は瞳を閉じ、静かに剣に手を添える。
(さあ、行ってらっしゃいませ。お館様。あなたが輝く舞台を、私が影から守ります)
月が再び雲を割き、銀光が剣の峰を照らす。
ぼんやり夫人の面影は欠片もなく、そこに立つのはただ一人の“護りの戦乙女”。
夫の誤解はまだ解けない。けれど、すれ違いの軌道は必ず交差する。
──その瞬間を信じて、今はまだ名を告げず、ただ剣を研ぐ。
峠の闇が、一段と深く沈んだ。
峠への街道をおおう夜霧は、月明かりを吸い込み銀灰に揺れていた。
アイリーンは白銀の走竜〈セレーネ〉を林道へ滑り込ませ、馬蹄音を抑えるように手綱を絞る。木々の隙間から灯火が瞬いた。山腹をくり抜いて造られた前線補給所――“アストラ第七洞営”だ。
ここは十年前、魔王戦役時に彼女がたびたび出入りした隠密拠点でもある。当時の仲間は各地へ散ったが、補給所を束ねるのは変わらずあの人――
耳に届く低い口笛。
アイリーンはマントを翻し、岩壁の影へ降り立った。暗がりで待っていた男が兜を外し、灰銀の短髪をくしゃりと掻く。
「やれやれ。白銀の姫が直々に来るとは、月に兎が降るよりびっくりだ」
低くしわがれた声。その主、ガウェイン・ザカリアス。かつて王国第一騎士団を率いた猛将であり、今は補給路を裏から支える“影の大隊長”だ。銀縁の眼帯が夜光を弾き、片目がなお鋭さを失わない。
「お久しぶりです、ガウェイン隊長」
アイリーンは兜に見立てた革帽を取る。銀髪が月光に瞬き、ガウェインは片眉を上げた。
「その呼び方はやめろと十年言ったろうに。――で? 今日はただの懐古談か、それとも」
「峠が危ないわ。“血濡れのベルゼ”が動く。夫の本隊は罠に気づいていない」
囁きは風より低く、それでいて戦鼓のように強い。
ガウェインは短く息を呑んだ。
「ベルゼだと……魔王直轄のあの狂犬が、囮を捨てて表へ? 情報筋は確かか」
「確かよ。魔族刻印の封蝋と、眠り砂を積んだ補給車両。全部、王都を出る前に抑えたわ。裏で操るのはアクノ公爵。王命を偽造して私を屋敷から排除し、夫を“名誉の戦死”に追い込む筋書き」
ガウェインは渋面をつくり、岩壁を拳で叩いた。
「相変わらず王都貴族の陰謀は嗅ぎたくもねえ匂いだ。だがお前さん一人でベルゼを抑えるのは骨が折れる」
「だから来たの。あなたの“竜牙隊”に力を借りたい」
アイリーンは短杖を引き抜き、紋章を露わにした。七芒星の中央に凍る聖獣――かつて勇者一党だけが帯びた証。「白銀の剣姫」の真標。
眼帯の奥でガウェインの片眼が燃える。
「……あの頃の俺たちは“国の狗”じゃなく“人の盾”だった。いいだろう。峠前線に先回りし、補給隘路に伏兵を置く。お前は本隊へ潜り込み、レイフォード公爵を動かせ」
アイリーンの唇が淡く弧を描く。
「感謝を」
「感謝など要らん。――ただ、無理はするな」
巨大な手が彼女の肩をぽんと叩く。その重みは友情の鎧のように温かい。
◆ ◆ ◆
洞営深部。火槌を打つ音と乾いた号令が交差する。竜牙隊の兵たちは影の補給を担う熟練揃いだ。アイリーンが姿を現すと、はっと直立した若兵が声を漏らす。
「あ、あの方が噂の……!」
「静かに。今は“白銀”の名を伏せる時だ」
ガウェインの一喝に空気が引き締まる。
アイリーンは食料木箱の間を縫うように歩き、鉄製の長箱を見つけた。蓋を開ける。中には深藍の鏡鱗甲冑――十年前、彼女が魔王の心臓を貫いた時の装備が眠っていた。刃を弾き、炎を透す希少金属“ミスリオル”製。
指で触れると鎧は小さく歌い、主を懐かしむようにブルーグレーの光を散らす。
「覚えていてくれたのね」
「縁起物は捨てられなくてな」
ガウェインははにかむ。獅子が仔猫に頭を撫でられたような不器用な照れ笑い。
闇を裂く遠雷が轟いた。峠方面。
アイリーンは鎧を抱え、決然と振り向く。
「時が来たわ。竜牙隊を動かして」
「応っ!」
号令が洞営にこだまし、兵たちが一斉に立ち上がる。箱に蓋が戻され、荷駄に括りつけられた。
アイリーンは愛馬セレーネの鞍に鎧をくくり、鞭打つように舌を鳴らす。馬の瞳が星光を映し、力強く嘶いた。
見送りに立つガウェインが片手を挙げる。
「十年前と同じ合図でいいか、白銀!」
「もちろん。月が雲を裂く時――蒼光三度」
「了解! 必ず峠を死地にさせてやる!」
アイリーンは頷き、セレーネの背に軽やかに跳び乗った。
洞窟を抜け出た瞬間、山風が銀髪を大きく逸らす。
夜空の月がちょうど雲間から姿を覗かせ、剣姫の笑みを照らした。
――懐かしい絆はまだ折れていない。
その確信が胸を満たし、少女の頃のように心が澄む。
そして次の瞬間、彼女は戦乙女としての自分へ鋼と化した。
丘陵を駆け降りる足音が雪面に火花を刻む。
峠まで残り三リーグ。
魔王軍の牙と人の奸計が交差する前に、白銀の刃は再び歴史に灼光を刻むだろう。
第4章-2 夫の誤解(約2,300字)
峠の臨時本営は黄昏とともに沈黙した。
裂けた雲のあいだから覗く夕陽が、剥き出しの岩肌を血のように染め上げる。
レイフォード公爵フェルディナンドは帷幕の外で甲冑を解き、薄い湯煙に紛れるように肩を回した。昼の一斉突撃――敵の牙城を退けたとはいえ、兵の損耗は重い。周囲では衛生兵が黙々と止血や縫合に当たり、重い呻き声が風に流れていく。
その凄惨な光景を前にしてなお、公爵の胸には燠火のような奇妙な高揚が燻っていた。
昼の激戦で、彼らを救った銀閃。あの“女勇者”の姿が網膜に焼き付いて離れないのだ。
――銀の髪が翻り、剣に纏った蒼雷が魔物の群れを一刀両断。
――まるで天上の星が落ち、地を灼き払うような威容。
彼女が駆け抜けた後には血の臭いすら残らず、ただ冷たい風だけが澄んでいた。
「公爵閣下」
副官トラヴィスがそっと声を掛けた。目の下の隈が深く、疲労を隠せない。
「負傷者の整理が終わりました。死傷総計、今朝の報告より一割減です」
「……うむ。女勇者のおかげだな」
「はい。あの方がいなければ、我らは峠の麓で壊走していたでしょう」
公爵は頷きつつテント裏の高台へ歩き、夕焼けに浸る峡谷を見下ろした。
胸に去来するのは感謝、畏敬、そして――嫉妬にも似た感情だ。
己の軍を救った英雄に抱くべきは純粋な敬意のはず。だが心の底で何かがざらつく。
(もし、妻があのような力を持っていたなら……)
唐突に浮かんだ想像を、彼は苦い笑みで打ち消した。
「公爵、あの方にお礼の使いを出しましょうか?」
トラヴィスの提案に、公爵は逡巡の末、首を横に振った。
「名乗りを拒む者に過度な探索は無礼だ。それに……いつ現れるかわからぬ。礼は次に会った時で構わん」
内心では“ぜひ対面したい”という思いが募る。しかしあれほどの戦功を示す人物に比肩し得るものを、平凡な妻は持たない――そう悟ると同時に、どこかで安堵している自分がいた。妻の無力を嘆いてきたはずなのに、強すぎる女は手に余ると恐れている。そんな矛盾が胃を突き上げる。
「……閣下?」
副官の呼びかけに我に返り、公爵は声を潜めた。
「おまえは、あの女勇者の顔をはっきり見たか?」
「一瞬だけですが。蒼い瞳でした。吸い込まれそうなほどに……美しかった」
「……そうか」
目の前に、紅茶を淹れるたびに手元を震わせる妻のぼんやり顔が浮かぶ。
公爵は拳を固めた。“謎の英雄”と“無能な妻”――両極端の女性像が頭の中でせめぎ合い、やがて奇妙な妄念を生む。もし自分の伴侶が英雄であったなら、家も領民も、もっと輝いていたのではないか、と。
そのとき遠方で狼煙が上がり、警鐘が連打された。
斥候の合図――敵の再襲来だ。
公爵はすべての雑念を剣とともに鞘へ収め、兜を被り直した。
「副官! 全隊に配置を!」
脳裏に残った女勇者の残像だけが、闇を裂く灯のように彼を奮い立たせた。
◆ ◆ ◆
一方その頃。
峠裏手の斜面を駆け下りる白い影があった。アイリーンだ。
月影を焼くような剣勢で魔物の斥候を屠り、岩陰に身を滑り込ませる。遠方には夫の指揮幕営。その帳の中で彼が悩みを滲ませることなど知る由もない。
彼女の耳に届くのは兵たちの苦悶と剣戟の金属音、そして自らの心臓の鼓動だけ。
(お館様……いまも私を“頼りない妻”と思っているでしょう。でもいいの)
剣を杖に持ち替え、霧を裂く雷光をふた筋走らせる。敵の後衛が沈黙し、本陣へ迫る脅威が一つ減った。
息を整えながら、彼女は遠い帷幕を見やり口の中でだけ呟く。
(あなたが前だけを見ること。そのために私は背を斬る。
いつか、あなたが真実に辿りつく日まで)
夜風が髪を揺らす。蒼い瞳に宿る光は、決して届かぬ場所へ投げた静かな祈りだった。
第4章-3 名もなき忠義
雪煙をかき分けて峠に吹き込む夜風は、常よりも生暖かく感じられた。
魔王軍が放つ〈瘴気〉が空気を濁し、雪の結晶を鈍い灰色へ変えているのだ。
アイリーンは岩陰にしゃがみ込み、指先でその灰の粒をそっと弾いた。じゅっ、と焦げる音。微量の魔力が篭っている証拠だった。
(……瘴気濃度が上がっている。ベルゼが近い)
遠く、本営の方角を示す狼煙が再び上がる。
しかし今夜は救援など望めない。竜牙隊は峠裏の補給道を封鎖するため分散し、公爵本軍も再襲に備え張り付いた。
夫の背に届く矢を折るのは、今は自分ただ一人――そう言い聞かせ、銀の髪を結い直す。
「……さて」
短杖を拾い上げると、杖先の蒼石が月光に呼応して淡く脈動した。
アイリーンはそっと瞳を閉じ、意識を戦場の地脈へ沈める。
――土中に潜む魔族歩兵三十七、樹上の猿狼八頭、後衛の呪術師が二。
そして谷底を進軍中の重装騎兵。嗤うような血臭が風に混じる。
(まず阻むべきは後衛。呪術師を残せば瘴気は濃くなる)
口に出さず計算を終えると、身をひるがえし雪面を蹴った。
滑るような斜行で魔族の警戒網を抜け、樹上の猿狼へ跳躍。
瞬間、剣を振り抜く。凍気の刃が三体の首を刈り、残りの群れが悲鳴とともに散開した。
地表に降りるより速く、アイリーンは杖を逆手に掲げ、三重の魔法陣を展開する。
「──《雷牙穿》」
閃光が夜空を引き裂き、呪術師の詠唱陣を直撃した。
凄まじい爆風が巻き起こり、瘴気を帯びた霧が一息に浄化される。
だが雷鳴が収まる間もなく、谷底から金属の咆哮が返った。重装騎兵が一直線に駆け上がって来る。
アイリーンは剣を深く構え直した。
──だが次の瞬間、奇妙なことが起こる。重装兵たちがいきなり馬を止め、一斉に視線を別の方向へ向けたのだ。
夜闇にかすかに揺らめく蒼光。峠裏の補給道から、巨弩の矢が雨のように降り注いで来た。
竜牙隊が伏兵を完了させた合図――蒼光三度。
ガウェインとの取り決めが、寸分違わず実行された証だった。
(……頼もしいわ)
アイリーンは胸の奥で礼を言い、剣先を返す。動揺した魔族兵を瞬時に切り崩し、谷底へ追い落とす。
やがて瘴気がほとんど消えたと判断すると、剣を腰へ収め、再び本営を振り返った。
◆ ◆ ◆
本営では、負傷兵を寝かせた衛生幕の中が慌ただしかった。
レイフォード公爵は鎧を脱ぐ間もなく、次の配陣を決めるため地図の前に立っている。
しかし兵が持ち込む最新戦況は、不思議とこちらに有利なものばかりだった。
「猿狼斥候部隊、全滅を確認!」
「敵呪術師の魔力反応、消失!」
「谷底からの騎兵は補給道で殲滅!」
副官トラヴィスが驚愕を隠せない。
「閣下、これは……いったい誰が」
「……“彼女”だろう」
そう呟きながらも、公爵の心は複雑だった。
自軍が苦戦しているあいだ、妻は屋敷でぼんやりと紅茶を啜っているはず――その光景を打ち消すかのように、銀の英雄の姿が輝く。
「くそ……戦場ではかくも役立たずな自分に苛立つのか」
思わずつぶやき、拳を握り締める。その指先が白くなるほど力がこもっていた。
◆ ◆ ◆
月が天頂を越える頃。
アイリーンは峠の背後に取り付いた最後の猿狼を斬り伏せ、剣を収めた。
鎧に跳ねた魔血を拭いながら、深い息をつく。
これで夫の帷幕を急襲できる敵はいない。奴らが再編する前に、公爵軍は態勢を立て直せるはずだ。
(……もう少しだけ近くで様子を)
そう考え、本営の灯火を遠目に見守っていたとき。
陣の外れで、ふいに人影が倒れ込むのを視界の端が捉えた。
斥候兵。肩から流れる血が雪を黒く染めている。
アイリーンは遮蔽物の陰に剣と杖を置き、“妻”の顔に戻るため髪と頬を魔法でぼんやり整えた。
そのまま走り寄り、兵の背を支える。
「大丈夫、しっかり」
声色を限界まで柔らかく落とす。兵は虚ろな目で彼女を見た。
「……ど、どちら様……?」
「ただの旅の療術師ですわ。ほら、痛み止め」
サッシュから小瓶を取り出し、複合鎮痛薬を飲ませる。
兵の呼吸がやや整ったのを確認すると、彼女は軽く微笑んだ。
「隊へ戻って。あなたの上官が待っているでしょう?」
「は……はい……!」
兵が歩き去る後ろ姿を見届けるまで、アイリーンは立ち尽くしていた。
自分が戦場へ現れたことを悟らせぬよう、救護ですら影に徹する――それが名もなき忠義の条件だ。
◆ ◆ ◆
深夜。
本営の高台で、公爵は遠くの闇に向けて無意識に頭を垂れた。
誰に、と問われれば答えに窮する。それでも礼を言わずにはいられない。
その姿は、闇に潜むアイリーンの眼に映り、胸をじんと温めた。
(お館様……あなたが“ありがとう”と呟いた声、ちゃんと届きましたわ)
涙ではなく、静かな笑みがこぼれる。
彼女は剣を背に回し、踵を返した。
名を告げる必要などない。ただ守る。それこそが、自分にとって何より甘美な報酬だから。
薄雲に月が隠れ、夜はさらに深くなる。
星の瞬きの下、ぼんやりした公爵夫人の忠義は、今日も光より速く夫の背へ届いていた。
第4章-4 すれ違う想い
峠を包んだ深夜の静寂は、何より雄弁だった。
雪の反射光が消え、雲間に沈んだ月が闇の色を濃くする。残ったのは焚き火のかすかな煌めきと、折れた矢柄が時折ぱきりと弾ける音──それだけだ。
帷幕の内側で、レイフォード公爵フェルディナンドは粗末な折り畳み椅子に腰掛けていた。鎧の継ぎ目には乾ききらぬ血がこびりつき、剣帯は幾度も締め直した跡で裂けそうになっている。
提灯の灯は弱く、紙障子に投げた影はやつれた己を誇張していた。副官トラヴィスが昼の戦果を読み上げたが、公爵はほとんど耳に入っていない。
──いま、峠の外に立っているであろう銀の女勇者は、どんな面持ちで夜を切り抜けているのか。
想像は夜気のように胸を冷やし、同時に熱した鉄のように心を焦がす。
「……閣下、ご休息を。まだ仮眠を一刻しか取られておりません」
「構わん。うたた寝などしていられる状況ではない」
副官が下がると、帷幕は再び静けさに閉ざされた。
公爵は顎に手を当て、視線を俯く。脳裏に浮かぶのは、屋敷で紅茶をこぼしながら慌ててハンカチで拭く妻アイリーンの姿。長年連れ添ってなお、彼女は剣どころか包丁の扱いすら覚束ない。
──いや、覚束ない“ふり”をしているのかもしれない。
その刹那、昼間見た女勇者の蒼い瞳が重なった。あの深さ、あの情熱。何かをひたむきに守ろうとする者だけが持つ光。
「……ばかな」
否定の声が漏れる。それでも思考は勝手に巡る。
もしあの女勇者がアイリーンと同一人物だったなら──。頭のどこかで囁く甘い妄想。しかし現実を思い返せば、屋敷での彼女に剣技も魔術も見たことはない。鼻緒を踏み外して転ぶ彼女の姿しか、記憶にないのだ。
「嗚呼、私の妻があのような力を……」
言いかけて、言葉を噛み殺した。
“力”を望む心と、“変わらぬ平凡さ”を願う心。その矛盾が胸を刺し続ける。もし妻が強すぎる者だったなら、畏れと距離が生まれ、自分は彼女を守る側でなくなるのではないか──それもまた、武骨な男の小さな臆病だった。
◆ ◆ ◆
そして同時刻。
本営を見下ろす断崖の途中に、風と同化した影があった。
アイリーンは岩肌に膝をつき、帷幕を照らす灯火を静かに見守っている。
瘴気が払われた後も小競り合いは続き、彼女は何度も本営へ迫る敵影を斬り伏せた。それでも夫が無事だと確信できるまでは、近寄ることも正体を明かすことも出来ない。
(お館様……あなたの背中はまだ一点の翳りもないわ)
思わず微笑みが漏れた。
だが次の瞬間、夫のテントから洩れた独白が耳に届く。風に乗った微かな声。
──私の妻があのような力を。
アイリーンの胸が小さく震えた。夫の苦悩も羨望も、その全てが痛いほど伝わる。だが彼の中に芽生える“英雄に対する憧れ”は、まだ自分へ向いていない。
遠い距離を埋めるには、真実を告げることが最も速い。しかし今その行為は、夫から“自分で戦う機会”を奪うかもしれない。彼は一人の武人として、峠の戦いを勝ち抜かねばならないのだ。
(知っているの。あなたは表も裏も強くあってほしい)
アイリーンは胸元のペンダントを握りしめる。
それは夫が結婚祝いに贈った瑠璃石の首飾り。ぼんやり顔の彼女が落とさないよう丈夫な革紐を通した、質素なものだ。それでもアイリーンにとっては世界の宝冠より重い。
(私はあなたを信じている。だからあなたも、いつかなにも疑わず私を信じて)
◆ ◆ ◆
帷幕の中。
公爵は立ち上がり、剣を抜いた。刃に映る己の目は躊躇と決意の狭間で揺れている。
「私は剣で道を切り開く。それが、己の妻を守る唯一の証明だ」
そう呟いた時、テント入口の布が捲れ、副官が飛び込んだ。
「緊急報告! 南東尾根で敵重装部隊の動き。斥候によると“血濡れのベルゼ”が自ら指揮を──」
「来たか……! 全軍、迎撃陣形へ移行。私が前に出る!」
公爵は兜を深く被り、剣を掲げた。胸のざらつきは、戦場の熱量へ押し流す。
──英雄の背中を追う自分ではない。自分が英雄になるのだ、と。
◆ ◆ ◆
崖上で見送るアイリーンの頬を、冷たい風が撫でた。
茸雲のように立ちのぼる狼煙。遠雷のような鬨の声。
彼女は瞳を閉じ、静かに剣に手を添える。
(さあ、行ってらっしゃいませ。お館様。あなたが輝く舞台を、私が影から守ります)
月が再び雲を割き、銀光が剣の峰を照らす。
ぼんやり夫人の面影は欠片もなく、そこに立つのはただ一人の“護りの戦乙女”。
夫の誤解はまだ解けない。けれど、すれ違いの軌道は必ず交差する。
──その瞬間を信じて、今はまだ名を告げず、ただ剣を研ぐ。
峠の闇が、一段と深く沈んだ。
86
あなたにおすすめの小説

奪う人たちは放っておいて私はお菓子を焼きます
タマ マコト
ファンタジー
伯爵家の次女クラリス・フォン・ブランディエは、姉ヴィオレッタと常に比較され、「控えめでいなさい」と言われ続けて育った。やがて姉の縁談を機に、母ベアトリスの価値観の中では自分が永遠に“引き立て役”でしかないと悟ったクラリスは、父が遺した領都の家を頼りに自ら家を出る。
領都の端でひとり焼き菓子を焼き始めた彼女は、午後の光が差す小さな店『午後の窓』を開く。そこへ、紅茶の香りに異様に敏感な謎の青年が現れる。名も素性も明かさぬまま、ただ菓子の味を静かに言い当てる彼との出会いが、クラリスの新しい人生をゆっくりと動かし始める。
奪い合う世界から離れ、比較されない場所で生きると決めた少女の、静かな再出発の物語。

このわたくしが、婚約者になるはずでしょう!?
碧井 汐桜香
恋愛
先々代の王女が降嫁したほどの筆頭公爵家に産まれた、ルティアヌール公爵家の唯一の姫、メリアッセンヌ。
産まれた時から当然に王子と結婚すると本人も思っていたし、周囲も期待していた。
それは、身内のみと言っても、王宮で行われる王妃主催のお茶会で、本人が公言しても不敬とされないほどの。
そのためにメリアッセンヌ自身も大変努力し、勉学に励み、健康と美容のために毎日屋敷の敷地内をランニングし、外国語も複数扱えるようになった。
ただし、実際の内定発表は王子が成年を迎えた時に行うのが慣習だった。
第一王子を“ルーおにいさま”と慕う彼女に、第一王子は婚約内定発表の数日前、呼び出しをかける。
別の女性を隣に立たせ、「君とは結婚できない」と告げる王子の真意とは?
7話完結です

五年後、元夫の後悔が遅すぎる。~娘が「パパ」と呼びそうで困ってます~
放浪人
恋愛
「君との婚姻は無効だ。実家へ帰るがいい」
大聖堂の冷たい石畳の上で、辺境伯ロルフから突然「婚姻は最初から無かった」と宣告された子爵家次女のエリシア。実家にも見放され、身重の体で王都の旧市街へ追放された彼女は、絶望のどん底で愛娘クララを出産する。
生き抜くために針と糸を握ったエリシアは、持ち前の技術で不思議な力を持つ「祝布(しゅくふ)」を織り上げる職人として立ち上がる。施しではなく「仕事」として正当な対価を払い、決して土足で踏み込んでこない救恤院の監督官リュシアンの温かい優しさに触れエリシアは少しずつ人間らしい心と笑顔を取り戻していった。
しかし五年後。辺境を襲った疫病を救うための緊急要請を通じ、エリシアは冷酷だった元夫ロルフと再会してしまう。しかも隣にいる娘の青い瞳は彼と瓜二つだった。
「すまない。私は父としての責任を果たす」
かつての合理主義の塊だった元夫は、自らの過ちを深く悔い、家の権益を捨ててでも母子を守る「強固な盾」になろうとする。娘のクララもまた、危機から救ってくれた彼を「パパ」と呼び始めてしまい……。
だが、どんなに後悔されても、どんなに身を挺して守られても、一度完全に壊された関係が元に戻ることは絶対にない。エリシアが真の伴侶として選ぶのは、凍えた心を溶かし、温かい日常を共に歩んでくれたリュシアンただ一人だった。
これは、全てを奪われた一人の女性が母として力強く成長し誰にも脅かされることのない「本物の家族」と「静かで確かな幸福」を自分の手で選び取るまでの物語。

婚約破棄は構いませんが、私が管理していたものは全て引き上げます 〜成金伯爵家令嬢は、もう都合のいい婚約者ではありません〜
藤原遊
ファンタジー
成金と揶揄される伯爵家の令嬢である私は、
名門だが実情はジリ貧な公爵家の令息と婚約していた。
公爵家の財政管理、契約、商会との折衝――
そのすべてを私が担っていたにもかかわらず、
彼は隣国の王女と結ばれることになったと言い出す。
「まあ素敵。では、私たちは円満に婚約解消ですね」
そう思っていたのに、返ってきたのは
「婚約破棄だ。君の不出来が原因だ」という言葉だった。
……はぁ?
有責で婚約破棄されるのなら、
私が“善意で管理していたもの”を引き上げるのは当然でしょう。
資金も、契約も、人脈も――すべて。
成金伯爵家令嬢は、
もう都合のいい婚約者ではありません。

ずっとヤモリだと思ってた俺の相棒は実は最強の竜らしい
空色蜻蛉
ファンタジー
選ばれし竜の痣(竜紋)を持つ竜騎士が国の威信を掛けて戦う世界。
孤児の少年アサヒは、同じ孤児の仲間を集めて窃盗を繰り返して貧しい生活をしていた。
竜騎士なんて貧民の自分には関係の無いことだと思っていたアサヒに、ある日、転機が訪れる。
火傷の跡だと思っていたものが竜紋で、壁に住んでたヤモリが俺の竜?
いやいや、ないでしょ……。
【お知らせ】2018/2/27 完結しました。
◇空色蜻蛉の作品一覧はhttps://kakuyomu.jp/users/25tonbo/news/1177354054882823862をご覧ください。

婚約破棄された竜好き令嬢は黒竜様に溺愛される。残念ですが、守護竜を捨てたこの国は滅亡するようですよ
水無瀬
ファンタジー
竜が好きで、三度のご飯より竜研究に没頭していた侯爵令嬢の私は、婚約者の王太子から婚約破棄を突きつけられる。
それだけでなく、この国をずっと守護してきた黒竜様を捨てると言うの。
黒竜様のことをずっと研究してきた私も、見せしめとして処刑されてしまうらしいです。
叶うなら、死ぬ前に一度でいいから黒竜様に会ってみたかったな。
ですが、私は知らなかった。
黒竜様はずっと私のそばで、私を見守ってくれていたのだ。
残念ですが、守護竜を捨てたこの国は滅亡するようですよ?

妹だけを可愛がるなら私はいらないでしょう。だから消えます……。何でもねだる妹と溺愛する両親に私は見切りをつける。
しげむろ ゆうき
ファンタジー
誕生日に買ってもらったドレスを欲しがる妹
そんな妹を溺愛する両親は、笑顔であげなさいと言ってくる
もう限界がきた私はあることを決心するのだった
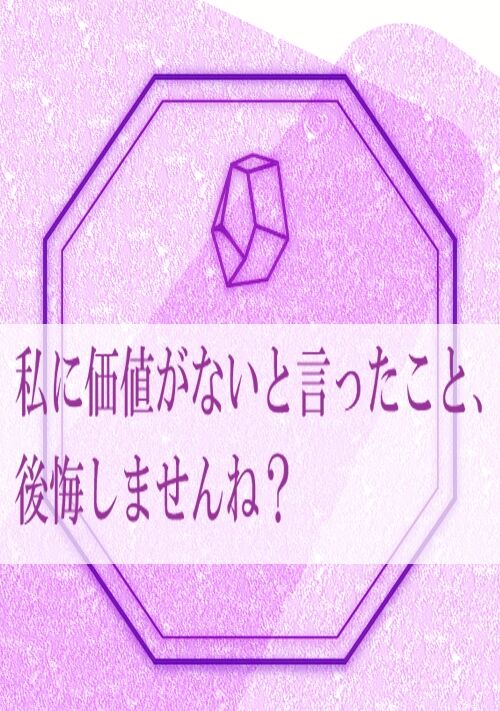
私に価値がないと言ったこと、後悔しませんね?
みこと。
恋愛
鉛色の髪と目を持つクローディアは"鉱石姫"と呼ばれ、婚約者ランバートからおざなりに扱われていた。
「俺には"宝石姫"であるタバサのほうが相応しい」そう言ってランバートは、新年祭のパートナーに、クローディアではなくタバサを伴う。
(あんなヤツ、こっちから婚約破棄してやりたいのに!)
現代日本にはなかった身分差のせいで、伯爵令嬢クローディアは、侯爵家のランバートに逆らえない。
そう、クローディアは転生者だった。現代知識で鉱石を扱い、カイロはじめ防寒具をドレス下に仕込む彼女は、冷えに苦しむ他国の王女リアナを助けるが──。
なんとリアナ王女の正体は、王子リアンで?
この出会いが、クローディアに新しい道を拓く!
※小説家になろう様でも「私に価値がないと言ったこと、後悔しませんね? 〜不実な婚約者を見限って。冷え性令嬢は、熱愛を希望します」というタイトルで掲載しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















