18 / 91
2巻
2-2
しおりを挟む
「私は父上から、誰のことも信用するなと教わったが……。私は、お前が白家に害をなさぬ限りは、お前を害することはない。その点は信用するといい」
碧玉はたとえ身を許した相手でも、白家のためにならないなら手を下すだろう。
「俺は兄上の期待に応えられるように励みます。そもそも、俺が道を踏み外している時は兄上が注意してくださればよいのです。兄上の望みこそ、俺の望みですから。まあ、兄上に殺されるのならば、俺も本望ですが」
「おかしな奴だな」
天祐が碧玉へ向ける盲目的な慕いぶりに、碧玉はときどき薄ら寒いものを感じる。だが、深く考えたところで、今更この関係から抜け出すのは容易ではないのを分かっている。気づかなかったことにした。
「お話が変わりますが、兄上、しばらく黒家の者が滞在しますので、不用意に離れを出ないようにお願いいたします」
「分かった。私とて、幽霊騒ぎは面倒だからな」
紫曜の枕元に立って、からかってみたら面白いかもしれない。ふとそんなことを思ったが、黒家の異能である直感により、碧玉が生きているとばれては厄介だ。
(天治帝とその一派はもうこの世におらぬし、人の好い紫曜のことだから、私の生存を知ったところで、内密にするだろうが……。賜死を受けた身ゆえ、大人しくしておくか)
紫曜は「親切で優しい皆の兄貴」と自称している。実際、黒家での評判はその通りだ。つまり、あの男は親切で優しいと言われている分だけ、周りの問題事を解決してやっているというわけだ。それでいて問題事の具体的な内容は噂にならないのだから、あの男の口の堅さがよく分かる。
それから紫曜が持ちこんだ依頼へと考えを巡らせ、碧玉は顎に指を当てる。
「しかし、敵に怪しまれずに黒家に入りこむためとはいえ、お前が見合いをするとはな。しかも、黒雪花殿と」
黒雪花とは、黒家の長女であり、紫曜の一歳下の妹だ。
「父上がご存命の折に、いつかは雪花殿と婚約してはどうかと言われていたのを思い出した」
「え……っ」
天祐の顔色があからさまに悪くなる。
「で、では、兄上はまさか……雪花殿に何かしらの感情を……?」
「美しい人だとは思ったが、それくらいだな。政略結婚の相手など、家を管理できれば、誰でも良かった」
「美しいですって? 兄上が女性に対して、そんなことを思うことがおありに?」
動揺のあまり、天祐はふらついた。碧玉は眉をひそめる。
「お前は私をなんだと思っている? 人間の美醜くらい、判別はつく。お前も、会ってみれば分かる。雪花の名がよく合う婦人だ。しかし、私は彼女に嫌われていたようだから、どちらにせよ婚約はしなかっただろう」
「えっ、嫌われるなんて……どうしてですか?」
「私といると自信を失うとか、隣に立つなんてごめんだとか、侍女にこぼしていたのを聞いた覚えがある。どうも私の容姿を好まぬようだったぞ」
「それは……兄上はその辺の女性よりもよほど美人ですから……なるほど……」
天祐はしみじみとつぶやいて、深く納得したようだ。
碧玉はその感想を聞き流し、厄介事へと再び意識を傾ける。
「それにしても、なかなか面白いことになっているようだな」
紫曜の依頼は、封印の塚から逃げ出した九尾の狐を退治することだ。
それでどうして、紫曜の妹と天祐が見合いをするかというと、九尾の狐が化けているのではないかと紫曜が怪しんでいるのが、黒家の中にいるせいだ。よりによって、黒宗主が側室に迎えた平民の女がそれだという。
紫曜の直感ではその女がクロだが、証拠がないのではっきり言えない。父親の側室が相手では、正室の子がいじめているように見える。父親や周囲の反感を買うのは困るので、大っぴらに指摘もできない。そもそも、宗主を筆頭に、黒家の人間の直感ではっきりと判別できていない状況だから困っているそうだ。
「もし冤罪だった場合、その方がかわいそうです。見合いは嫌ですが、俺は助けてやりたいですね」
善良さを発揮して、天祐は黒紫曜の依頼を引き受けたのだ。
「しっかり解決して、報酬をもらってくればよい。ああ、そうそう、私も同行するゆえ、そのつもりでいるように」
「……は?」
ぽかんとし、数秒黙りこんだ天祐は、意味を呑みこむやのけぞった。
「兄上、白領を出るつもりなのですか? あのクソ帝はもういないとはいえ、兄上の怨霊で殺されたと思っている者達に、兄上の生存がばれたら危険です!」
「お前を一人で行かせては、気づいた時には実際に婚約しているかもしれぬ。紫曜は口が達者なのだ。お前程度、丸めこむのはたやすいだろう。――天祐、私を情人としたからには、私を最優先にしないなどあり得ぬ。浮気をするなら、お前とその相手を殺すからな」
つまり、好奇心が半分で、残り半分は監視目的だ。
(こやつは知らぬが、『白天祐の凱旋』では、黒雪花がメインヒロインだった。油断ならぬ)
前世で読んだあの書物では、たくさんの魅力的なヒロインが登場する。しかし、ハーレムものではなく、大本命のメインヒロインがいて、主人公に片思いをしているサブヒロインが複数いるという形だった。天祐はメインヒロインである黒雪花に一途な愛を捧げており、それが男らしくて格好いいと、読者人気を博していたというわけだ。十二歳で妖邪退治の戦へと放りこまれた天祐は、怪我をして黒家の領地に入りこむ。そこで雪花と出会い、彼女の手厚い看護を受ける。恩とともに恋心を抱いた天祐は、それから何かと雪花を訪ね、地道に愛を重ねていく。
しかし、結局、雪花は碧玉との結婚が決まる。雪花を救うために天祐は立ち上がり、悪役を排除して、白家を手に入れる。そして、雪花と結婚して大団円という、苦労を乗り越えてのハッピーエンドだった。
(ヒロインの存在など忘れていたが、他の者はともかく、黒雪花との見合いだけは見過ごせぬ)
自分を一番にしない恋人など許せないという、自分勝手な理由である。やたらと碧玉に甘い天祐でも、碧玉に嫌悪を抱くだろうかと様子見をしたが、碧玉の予想に反し、天祐は感動に浸って頬を紅潮させている。
「兄上が嫉妬してくれるなんて、ありがとうございます!」
しかも、お礼まで言われた。
「兄上が俺を想ってくださるならば、どんなことでもうれしいです! 分かりました、一緒に行きましょう!」
「……ああ」
拍子抜けしたものの、天祐が喜んでいるようなのでこれでいいのだろうと、碧玉は深く考えずに返事をしたのだった。
それから、碧玉が黒家への遠征に付き添うことを、碧玉の生存を知る古参の配下に伝えたところ、配下の間で、自分こそが二人についていくと、熾烈な戦いが繰り広げられた。
武官は武術で、道士は術で、使用人は家事勝負をして、十五人の精鋭が残った。
出発の日の早朝。
黒家よりも先に、碧玉は玄関前に出た。旅の同行者はすでに勢ぞろいしていて、見送りの門弟や使用人も集まっている。そこで、碧玉は奇妙なことに気がついた。
「灰炎、気のせいかこやつら、まだ出発してもいないのに疲れてはおらぬか?」
碧玉は傍らの灰炎にひそりと問う。今回、碧玉は白家に招かれている遠縁のふりをすることにしたが、幼馴染が相手なので、顔を見られるのはまずい。そこで紗のついた笠をかぶって周りから見えにくいようにして、天祐と灰炎の傍にいる。
灰炎は我慢できずに噴き出した。
「ふ、ふふっ。それはですね、主君に同行したい者達が、競い合いをしていたせいですよ」
「そんなに旅がしたいのなら、遠征任務を与えてはどうだ?」
「そういう意味ではございませんよ、主君」
やれやれとため息をついて、灰炎は首を横に振る。
碧玉としては、天祐の侍女・青鈴がいるのは分かるが、道士として崔白蓮がまじっていることに驚いた。白蓮は碧玉と天祐が道術の基礎を教わった師父でもある。門弟を束ねる立場にいる男なので、てっきり留守番をするのだと思っていた。
「崔師父まで同行されるとは」
「上の者はたまには外出をして、子弟に成長の機会を与えねば。私に頼ればどうにかなるという甘えた根性を、この機会に叩き直そうかと」
白蓮は三十代後半で、糸目でひょうひょうとした男だ。常に冷静沈着で、師として適切な指導をする。むやみに厳しいわけではないが、優しいわけでもない。匙加減が絶妙だ。
「崔師父にお考えがあるのでしたら構いません」
白蓮の言うことももっともだが、碧玉には家の守りが薄れることが気にかかる。
灰炎にどうなっているのか確認すると、青炎の側近だった者達の名をあげたので、碧玉は胸をなで下ろした。彼らならば、突発的事態にも問題なく対応できるし、忠誠心が熱いので、主の留守中に悪さをすることもない。
白蓮は真面目な顔をして話を続ける。
「こたびの件には、九尾の狐が関わっているとか。よき君主の到来を示す瑞獣とはいえ、長らく封印されていたのでは、黒家に恨みもあるでしょう。天祐様は道士としての実力はございますが、経験が足りておりませぬ。私にも何かお手伝いできることがあるやもと、愚考いたしました」
「ああ。崔師父が付き添ってくれるならば、私も安心だ。頼りにしているぞ」
「お任せください」
九尾の狐が相手なのだから、精鋭をそろえ、道具を余分に持っていっても、まだ準備が足りないかもしれない。九尾の狐が吉祥をもたらすか破滅をもたらすか、現時点ではどちらか分からないのだ。神獣に近い妖怪でもあるので、事は簡単ではない。
「ところで、我らは先代をどうお呼びすればよろしいでしょうか。宗主が遠縁を食客として丁重に招き、灰炎殿を仕えさせているのでしたら、主君と呼んでも差しつかえないでしょうが。我らは白家に仕える身。食客の配下ではございませんので」
「師父のおっしゃる通りですね。では、偽名を使うか。天祐、適当に考えよ」
碧玉が天祐に振ると、天祐は少し考えてから提案する。
「兄上と分からないあだ名ですよね。銀嶺はどうでしょうか」
「雪が積もって、銀に輝く山のことか。気に入った。お前達は銀嶺と呼ぶがいい」
とっさに思いついたにしては良い名だ。見事な銀髪を持つ碧玉にぴったりである。皆もそう思ったようで、素晴らしい名だと天祐を褒める声があちらこちらで上がる。
「では、銀嶺殿とお呼びしましょう。銀嶺殿も黒家の中まで入りこむ予定でしょうか」
白蓮の問いに、碧玉は首を横に振って示す。
「あとで合流するつもりだ。さすがに黒家直系が大勢いる場に入っては、彼らの異能である直感で、私の正体がばれるだろう。最初の歓迎が終わり、白家への注目が収まるまでは、城街の宿にいるつもりだ。見合いのことは、灰炎がいれば問題ない」
碧玉が灰炎をちらと見ると、灰炎は拱手をした。
「は。お任せください」
天祐は彼らを見回して、命令する。
「お前達は兄……銀嶺のことをかぎつけられぬように、道中は特に気を付けよ。黒家の連中をできるだけ遠ざけるように」
「は!」
家臣らが声をそろえる。
「そろそろ連中が来る頃か。私は馬車にいるとしよう」
「では兄上、後ほど」
天祐に一つ頷いて、碧玉は馬車に乗りこんだ。
五日の旅程を経て、黒家の領地に入った。
急げば四日で着くものの、天祐が碧玉の体調を気遣って、普通の速度で進ませたのだ。黒家の者達は一刻も早く帰りたいようだったが、焦りを見せては敵が変に思うだろうと、天祐が紫曜を説き伏せた。
領境の川にかかる木橋を越えると、黒領だ。白領と違い、黒領の山は低いものが多く、石切り場や鉱山をいくつか所有している。山のふもとには森があり、それ以外は水田や村がほとんどだ。
「天祐、黒家は資源の宝庫だ。発明の材料は、この地だけでほとんどまかなっている」
馬車の窓から外を示し、碧玉は天祐に教える。
大昔、この辺りは手つかずの山野に過ぎなかった。それを黒家の異能である直感により、水脈や鉱脈を当てて切り拓いた結果だ。
「あの服装といい、豊かなわけですね。それにしても、黒領には祠や堂が多いですね」
「黒家の異能は直感だが、ほとんど神通力と変わらない、領民は、彼らの能力により利益を得ている。白家と同じく、黒家も元々は神官の家系だ。白家は天帝からさずけられた火を大事に受け継ぎ、妖邪から人々を守っていた功績から浄火の異能を与えられた。一方で、黒家は巫女として天帝にお仕えしていた。神への信心が深く、神降ろしの儀式をして、人々に預言をしていたのだ。そのうち、直感という異能を与えられた。それで自然と信仰があつくなっているというわけだ」
白家と黒家は生業が似ているので、歴史を辿れば仲が良いこともあれば悪いこともある。断言できるのは、占いの能力が上なのは黒家で、祓魔の能力に優れるのは白家ということだ。
「兄上、大丈夫ですか?」
隣に座っている天祐が、碧玉の横顔を心配そうに覗きこんだ。碧玉は眉をひそめる。
「まったく、毒をあおって以来、体が弱くなり過ぎだ。まさか、馬車酔いするようになるとは……」
これまでも馬車の乗り心地が良かった試しはないが、以前はもう少し平気だった。
「黒家の客が一緒でなければ、式神の飛行で道のりを短縮したのですが……」
薄らぼんやりした前世の知識も、たまには役に立つ。前世の物語は、想像力豊かなものばかりだった。式神作りは霊力と想像力がものをいう。碧玉は妖怪退治をする時、前世の創作物を参考に、巨大な鳥の式神を作り出して利用していた。妖怪でもない限り、巨大な鳥は存在しない。この世界の人間にとって、巨大な鳥は倒すべきもので、背に乗ろうなどと考えないのだ。碧玉は前世の記憶の影響で、そんな常識をあっさりと打ち壊した。
天祐は宗主になってから、碧玉が思いえがいた式神の造作を取り入れて、移動手段の短縮に使っているのだ。
「あれは余所者に気安く見せるべきではない」
「そうですね。霊力が低い者が真似をしては、落下事故を起こして大惨事になります」
碧玉としては、空を自由に飛べるようになると、領の防衛に影響が出るから余所者には見せるべきではないという意味で言ったのだが、根が善良な天祐は、見知らぬ誰かが怪我をしないかと案じている。
(こういうところを見ると、本当にこやつが天治帝らを策略にはめて皆殺しにしたのかと疑わしくなるな)
普段の天祐は、温厚で快活な好青年だ。冷酷な碧玉と比べれば、ずっと性格が良い。だというのに、彼を怒らせると性格が豹変するのだから油断ならない。
(否、普段が優しい者ほど、怒らせると恐ろしいと聞く。むしろその典型例なのか?)
碧玉がじーっと見つめると、天祐はわずかに首を傾げ、ふいに碧玉に口づけをした。
「……おい」
思わずにらむと、天祐はにこりと微笑む。
「口づけをしたいのかと思いました」
「それはお前だろう?」
「俺はいつでも口づけをしたいですよ」
「聞いた私が馬鹿だった」
「兄上は分かっておりません」
天祐がじとりとした目を、碧玉に向ける。
「お疲れの兄上に無茶をさせるわけには参りませんから、これでも触れるのを我慢しているのですよ?」
碧玉はぎくりとした。天祐は普段は碧玉第一で、素直に言うことを聞くが、閨に入ると一切の遠慮がなくなるのだ。旅の間は添い寝する程度で何もしてこないのは、碧玉の体調のためだったらしい。
「しかし、兄上が留守番でしたら、会うこともかないませんでしたから、こうしてお傍にいられるだけで幸せです」
「……そうか」
碧玉はふいっと目をそらす。
恥ずかしいことを平然と言ってのける天祐には、どんな態度をとっていいか分からなくなることがある。胸の奥がむずがゆいのに、悪い気はしないのが厄介だ。
水田の間にある広い道を進んでいくと、黒領で最も高い山――天声山のふもとに着いた。
黒領の本拠地・龍拠だ。早朝は山の裾野にまとわりつくようにして霧が出ることが多く、龍に守られているように見える場所だった。実際に龍脈が通っており、霊気が強い土地でもある。
龍拠の町の奥にあるのが、黒家の屋敷だ。
宿の多い界隈で馬車を停め、碧玉は車を降りることにした。配下の数名は町の宿に泊まるので、彼らにまぎれこむ予定だった。車を降りる間際に、天祐に注意する。
「天祐、上手くやるのだぞ。判断に困ったら、灰炎か崔師父を頼りなさい」
「ええ。兄上、くれぐれも気軽にお顔をお見せになりませんように。灰炎殿」
天祐は心配そうに、灰炎の名を呼ぶ。
「お任せください、白宗主」
馬車の入り口から顔を覗かせ、灰炎は天祐に拱手をする。町の宿に泊まる使用人と門弟も、碧玉にならい、いっせいに拱手した。
黒家の者達が焦れったそうにしているのに気づいているので、碧玉は灰炎と共に、あっさりと馬車から離れる。一台の荷車と数名が列を離れ、近くの宿に向かう。
中級の宿を貸し切りにして、その中の一番良い部屋を碧玉が使うことにしたのだが、碧玉は早々に庭の木陰に追いやられてしまった。宿の掃除がなっていないと使用人らが憤慨し、支度が済むまで待っていてほしいと言い出したせいだ。
「あやつら、いつからあんなに仕事熱心になったのだ?」
庭に追いやられるなど滅多とない。彼らの言い分は理解できるので、碧玉は無礼だと怒るよりも呆れている。
「はは。こたびは精鋭がそろっておりますからねえ」
笑いながら返す灰炎ですら、宿の下女の支度を断り、自分で茶と菓子を用意している。
「旅先でくらい、宿の者に仕事を任せればよいだろうに」
「得体の知れぬ者の淹れた茶など、主君に出すわけに参りません。それに、ほとんどの場合、私のほうが上手にできます」
「それはそうだな」
大男という見た目に反し、灰炎は繊細な男だ。祓魔業のことになると大雑把なのに、何故か身の回りの仕事では丁寧さを発揮する。軽食程度ならば、灰炎でも作ることができ、不思議と美味い。灰炎を一人連れていけば、旅には困らないだろう。
「灰炎、馬車酔いも落ち着いたゆえ、暇つぶしに周りを冷やかしにいかぬか」
「しかし、宗主様が心配なされますよ。それに黒家の方々にばれるかもしれません」
「白家の新宗主が、わざわざ黒領まで足を運んだのだぞ。今は準備に気を取られて、出かける余裕もあるまい。だからむしろ、出歩くなら今がちょうどいい」
「確かにそうですね」
灰炎は納得を見せた。
「とはいえ、昔、父上と共に、黒領には何度か来たことがある。覚えのある者もいるだろうから、おおっぴらに顔をさらすのはまずいな。身なりを隠すなら笠でも充分だが、散歩には邪魔だ。何かよいものはないか」
「そうですね。仮面はいかがです?」
「祭りでもないのに、不審ではないか?」
碧玉の問いに、灰炎は少し考えてから答える。
「怪しいことは怪しいですが、いないこともありません。普段ならば芸人が芸を披露する時につけることが多いでしょうが、それ以外では、病気や怪我の痕を隠すのに使っていることもありますから」
「怪我か。例えば、やけど痕とかか?」
「ええ。そうですね、細かい設定を考えましょう。幼い頃、焚火の傍で転んで顔にやけどをしたので隠している……というのはいかがですか?」
「そうだな。幼少期はそういうやけどをしがちだ。それでいこう」
碧玉自身も幼い頃、火の美しさに魅了されて手を伸ばし、指先に軽いやけどをしたことがある。
「もし仮面が外れた時に備えて、目の下にほくろを書いておきましょう。もし碧玉様ではないかと詰められたら、先代にそっくりな白家の遠縁ですと押し通します」
「そうだな。宗主が兄にそっくりな者を役人にしているのは、白家としては外聞が悪い。能力ではなく外見で選んだことになるからな。それで身なりを隠していると言えば、深く追及もしないだろう」
礼儀正しい者なら、見ないふりをするはずだ。そうでない者が好奇心に駆られても、後ろ盾が白家の宗主ならば、身分を恐れて引き下がる案件でもある。
灰炎との話し合いを終えると、碧玉は門弟に命じて木製の仮面を手に入れさせた。顔の上半分だけを隠す仮面を目元につけ、碧玉は灰炎と共に宿を抜け出す。
黒家の者が妖狐騒動に慌てているのに反して、町の雰囲気はのどかだ。
ぶらぶらと歩きながら、出店や商店を覗いて回る。庶民向けの菓子や食べ物を売る店、玩具屋や小間物屋がある中、占い師の店を多く見かけるのが黒領らしい。
「何か問題が起きているようには見えぬな」
「民を不安がらせないように、気を付けておられるのでしょう」
詳しいことは、あとで天祐に聞かなくてはならないようだ。
「灰炎、黒領の茶菓子はなんだろうか」
「分かりません。私も黒領には滅多に来ないので気になりますね。主君、あちらに茶楼がございますから、休憩にいたしましょう」
二階建ての茶楼に入ると、一階は四人掛けの丸几が整然と並んでおり、昼時を過ぎた午後にもかかわらず、多くの人で賑わっている。前のほうには鶴と松がえがかれた衝立が置かれ、その前に立つ三十代ほどの講談師が、折よく黒領の昔話を始めたところだった。
「これはまだ黒領が切り拓かれるよりも前の、古い時代のこと。この世は魑魅魍魎が跋扈し、人々は夜の闇に怯えておりました」
碧玉達は目立たない壁際の席に落ち着き、すぐさま近づいてきた店員に茶菓子を頼んで、講談師の話に耳を傾ける。
「黒家の宗主の前に、天女のごとき美しい女人が現れました。その名は梅花。紅梅のような小さな唇、白梅のような肌をした絶世の美女でございました。その声は迦陵頻伽のごとく、彼女の弾く琵琶は天上の楽のようでした」
碧玉はたとえ身を許した相手でも、白家のためにならないなら手を下すだろう。
「俺は兄上の期待に応えられるように励みます。そもそも、俺が道を踏み外している時は兄上が注意してくださればよいのです。兄上の望みこそ、俺の望みですから。まあ、兄上に殺されるのならば、俺も本望ですが」
「おかしな奴だな」
天祐が碧玉へ向ける盲目的な慕いぶりに、碧玉はときどき薄ら寒いものを感じる。だが、深く考えたところで、今更この関係から抜け出すのは容易ではないのを分かっている。気づかなかったことにした。
「お話が変わりますが、兄上、しばらく黒家の者が滞在しますので、不用意に離れを出ないようにお願いいたします」
「分かった。私とて、幽霊騒ぎは面倒だからな」
紫曜の枕元に立って、からかってみたら面白いかもしれない。ふとそんなことを思ったが、黒家の異能である直感により、碧玉が生きているとばれては厄介だ。
(天治帝とその一派はもうこの世におらぬし、人の好い紫曜のことだから、私の生存を知ったところで、内密にするだろうが……。賜死を受けた身ゆえ、大人しくしておくか)
紫曜は「親切で優しい皆の兄貴」と自称している。実際、黒家での評判はその通りだ。つまり、あの男は親切で優しいと言われている分だけ、周りの問題事を解決してやっているというわけだ。それでいて問題事の具体的な内容は噂にならないのだから、あの男の口の堅さがよく分かる。
それから紫曜が持ちこんだ依頼へと考えを巡らせ、碧玉は顎に指を当てる。
「しかし、敵に怪しまれずに黒家に入りこむためとはいえ、お前が見合いをするとはな。しかも、黒雪花殿と」
黒雪花とは、黒家の長女であり、紫曜の一歳下の妹だ。
「父上がご存命の折に、いつかは雪花殿と婚約してはどうかと言われていたのを思い出した」
「え……っ」
天祐の顔色があからさまに悪くなる。
「で、では、兄上はまさか……雪花殿に何かしらの感情を……?」
「美しい人だとは思ったが、それくらいだな。政略結婚の相手など、家を管理できれば、誰でも良かった」
「美しいですって? 兄上が女性に対して、そんなことを思うことがおありに?」
動揺のあまり、天祐はふらついた。碧玉は眉をひそめる。
「お前は私をなんだと思っている? 人間の美醜くらい、判別はつく。お前も、会ってみれば分かる。雪花の名がよく合う婦人だ。しかし、私は彼女に嫌われていたようだから、どちらにせよ婚約はしなかっただろう」
「えっ、嫌われるなんて……どうしてですか?」
「私といると自信を失うとか、隣に立つなんてごめんだとか、侍女にこぼしていたのを聞いた覚えがある。どうも私の容姿を好まぬようだったぞ」
「それは……兄上はその辺の女性よりもよほど美人ですから……なるほど……」
天祐はしみじみとつぶやいて、深く納得したようだ。
碧玉はその感想を聞き流し、厄介事へと再び意識を傾ける。
「それにしても、なかなか面白いことになっているようだな」
紫曜の依頼は、封印の塚から逃げ出した九尾の狐を退治することだ。
それでどうして、紫曜の妹と天祐が見合いをするかというと、九尾の狐が化けているのではないかと紫曜が怪しんでいるのが、黒家の中にいるせいだ。よりによって、黒宗主が側室に迎えた平民の女がそれだという。
紫曜の直感ではその女がクロだが、証拠がないのではっきり言えない。父親の側室が相手では、正室の子がいじめているように見える。父親や周囲の反感を買うのは困るので、大っぴらに指摘もできない。そもそも、宗主を筆頭に、黒家の人間の直感ではっきりと判別できていない状況だから困っているそうだ。
「もし冤罪だった場合、その方がかわいそうです。見合いは嫌ですが、俺は助けてやりたいですね」
善良さを発揮して、天祐は黒紫曜の依頼を引き受けたのだ。
「しっかり解決して、報酬をもらってくればよい。ああ、そうそう、私も同行するゆえ、そのつもりでいるように」
「……は?」
ぽかんとし、数秒黙りこんだ天祐は、意味を呑みこむやのけぞった。
「兄上、白領を出るつもりなのですか? あのクソ帝はもういないとはいえ、兄上の怨霊で殺されたと思っている者達に、兄上の生存がばれたら危険です!」
「お前を一人で行かせては、気づいた時には実際に婚約しているかもしれぬ。紫曜は口が達者なのだ。お前程度、丸めこむのはたやすいだろう。――天祐、私を情人としたからには、私を最優先にしないなどあり得ぬ。浮気をするなら、お前とその相手を殺すからな」
つまり、好奇心が半分で、残り半分は監視目的だ。
(こやつは知らぬが、『白天祐の凱旋』では、黒雪花がメインヒロインだった。油断ならぬ)
前世で読んだあの書物では、たくさんの魅力的なヒロインが登場する。しかし、ハーレムものではなく、大本命のメインヒロインがいて、主人公に片思いをしているサブヒロインが複数いるという形だった。天祐はメインヒロインである黒雪花に一途な愛を捧げており、それが男らしくて格好いいと、読者人気を博していたというわけだ。十二歳で妖邪退治の戦へと放りこまれた天祐は、怪我をして黒家の領地に入りこむ。そこで雪花と出会い、彼女の手厚い看護を受ける。恩とともに恋心を抱いた天祐は、それから何かと雪花を訪ね、地道に愛を重ねていく。
しかし、結局、雪花は碧玉との結婚が決まる。雪花を救うために天祐は立ち上がり、悪役を排除して、白家を手に入れる。そして、雪花と結婚して大団円という、苦労を乗り越えてのハッピーエンドだった。
(ヒロインの存在など忘れていたが、他の者はともかく、黒雪花との見合いだけは見過ごせぬ)
自分を一番にしない恋人など許せないという、自分勝手な理由である。やたらと碧玉に甘い天祐でも、碧玉に嫌悪を抱くだろうかと様子見をしたが、碧玉の予想に反し、天祐は感動に浸って頬を紅潮させている。
「兄上が嫉妬してくれるなんて、ありがとうございます!」
しかも、お礼まで言われた。
「兄上が俺を想ってくださるならば、どんなことでもうれしいです! 分かりました、一緒に行きましょう!」
「……ああ」
拍子抜けしたものの、天祐が喜んでいるようなのでこれでいいのだろうと、碧玉は深く考えずに返事をしたのだった。
それから、碧玉が黒家への遠征に付き添うことを、碧玉の生存を知る古参の配下に伝えたところ、配下の間で、自分こそが二人についていくと、熾烈な戦いが繰り広げられた。
武官は武術で、道士は術で、使用人は家事勝負をして、十五人の精鋭が残った。
出発の日の早朝。
黒家よりも先に、碧玉は玄関前に出た。旅の同行者はすでに勢ぞろいしていて、見送りの門弟や使用人も集まっている。そこで、碧玉は奇妙なことに気がついた。
「灰炎、気のせいかこやつら、まだ出発してもいないのに疲れてはおらぬか?」
碧玉は傍らの灰炎にひそりと問う。今回、碧玉は白家に招かれている遠縁のふりをすることにしたが、幼馴染が相手なので、顔を見られるのはまずい。そこで紗のついた笠をかぶって周りから見えにくいようにして、天祐と灰炎の傍にいる。
灰炎は我慢できずに噴き出した。
「ふ、ふふっ。それはですね、主君に同行したい者達が、競い合いをしていたせいですよ」
「そんなに旅がしたいのなら、遠征任務を与えてはどうだ?」
「そういう意味ではございませんよ、主君」
やれやれとため息をついて、灰炎は首を横に振る。
碧玉としては、天祐の侍女・青鈴がいるのは分かるが、道士として崔白蓮がまじっていることに驚いた。白蓮は碧玉と天祐が道術の基礎を教わった師父でもある。門弟を束ねる立場にいる男なので、てっきり留守番をするのだと思っていた。
「崔師父まで同行されるとは」
「上の者はたまには外出をして、子弟に成長の機会を与えねば。私に頼ればどうにかなるという甘えた根性を、この機会に叩き直そうかと」
白蓮は三十代後半で、糸目でひょうひょうとした男だ。常に冷静沈着で、師として適切な指導をする。むやみに厳しいわけではないが、優しいわけでもない。匙加減が絶妙だ。
「崔師父にお考えがあるのでしたら構いません」
白蓮の言うことももっともだが、碧玉には家の守りが薄れることが気にかかる。
灰炎にどうなっているのか確認すると、青炎の側近だった者達の名をあげたので、碧玉は胸をなで下ろした。彼らならば、突発的事態にも問題なく対応できるし、忠誠心が熱いので、主の留守中に悪さをすることもない。
白蓮は真面目な顔をして話を続ける。
「こたびの件には、九尾の狐が関わっているとか。よき君主の到来を示す瑞獣とはいえ、長らく封印されていたのでは、黒家に恨みもあるでしょう。天祐様は道士としての実力はございますが、経験が足りておりませぬ。私にも何かお手伝いできることがあるやもと、愚考いたしました」
「ああ。崔師父が付き添ってくれるならば、私も安心だ。頼りにしているぞ」
「お任せください」
九尾の狐が相手なのだから、精鋭をそろえ、道具を余分に持っていっても、まだ準備が足りないかもしれない。九尾の狐が吉祥をもたらすか破滅をもたらすか、現時点ではどちらか分からないのだ。神獣に近い妖怪でもあるので、事は簡単ではない。
「ところで、我らは先代をどうお呼びすればよろしいでしょうか。宗主が遠縁を食客として丁重に招き、灰炎殿を仕えさせているのでしたら、主君と呼んでも差しつかえないでしょうが。我らは白家に仕える身。食客の配下ではございませんので」
「師父のおっしゃる通りですね。では、偽名を使うか。天祐、適当に考えよ」
碧玉が天祐に振ると、天祐は少し考えてから提案する。
「兄上と分からないあだ名ですよね。銀嶺はどうでしょうか」
「雪が積もって、銀に輝く山のことか。気に入った。お前達は銀嶺と呼ぶがいい」
とっさに思いついたにしては良い名だ。見事な銀髪を持つ碧玉にぴったりである。皆もそう思ったようで、素晴らしい名だと天祐を褒める声があちらこちらで上がる。
「では、銀嶺殿とお呼びしましょう。銀嶺殿も黒家の中まで入りこむ予定でしょうか」
白蓮の問いに、碧玉は首を横に振って示す。
「あとで合流するつもりだ。さすがに黒家直系が大勢いる場に入っては、彼らの異能である直感で、私の正体がばれるだろう。最初の歓迎が終わり、白家への注目が収まるまでは、城街の宿にいるつもりだ。見合いのことは、灰炎がいれば問題ない」
碧玉が灰炎をちらと見ると、灰炎は拱手をした。
「は。お任せください」
天祐は彼らを見回して、命令する。
「お前達は兄……銀嶺のことをかぎつけられぬように、道中は特に気を付けよ。黒家の連中をできるだけ遠ざけるように」
「は!」
家臣らが声をそろえる。
「そろそろ連中が来る頃か。私は馬車にいるとしよう」
「では兄上、後ほど」
天祐に一つ頷いて、碧玉は馬車に乗りこんだ。
五日の旅程を経て、黒家の領地に入った。
急げば四日で着くものの、天祐が碧玉の体調を気遣って、普通の速度で進ませたのだ。黒家の者達は一刻も早く帰りたいようだったが、焦りを見せては敵が変に思うだろうと、天祐が紫曜を説き伏せた。
領境の川にかかる木橋を越えると、黒領だ。白領と違い、黒領の山は低いものが多く、石切り場や鉱山をいくつか所有している。山のふもとには森があり、それ以外は水田や村がほとんどだ。
「天祐、黒家は資源の宝庫だ。発明の材料は、この地だけでほとんどまかなっている」
馬車の窓から外を示し、碧玉は天祐に教える。
大昔、この辺りは手つかずの山野に過ぎなかった。それを黒家の異能である直感により、水脈や鉱脈を当てて切り拓いた結果だ。
「あの服装といい、豊かなわけですね。それにしても、黒領には祠や堂が多いですね」
「黒家の異能は直感だが、ほとんど神通力と変わらない、領民は、彼らの能力により利益を得ている。白家と同じく、黒家も元々は神官の家系だ。白家は天帝からさずけられた火を大事に受け継ぎ、妖邪から人々を守っていた功績から浄火の異能を与えられた。一方で、黒家は巫女として天帝にお仕えしていた。神への信心が深く、神降ろしの儀式をして、人々に預言をしていたのだ。そのうち、直感という異能を与えられた。それで自然と信仰があつくなっているというわけだ」
白家と黒家は生業が似ているので、歴史を辿れば仲が良いこともあれば悪いこともある。断言できるのは、占いの能力が上なのは黒家で、祓魔の能力に優れるのは白家ということだ。
「兄上、大丈夫ですか?」
隣に座っている天祐が、碧玉の横顔を心配そうに覗きこんだ。碧玉は眉をひそめる。
「まったく、毒をあおって以来、体が弱くなり過ぎだ。まさか、馬車酔いするようになるとは……」
これまでも馬車の乗り心地が良かった試しはないが、以前はもう少し平気だった。
「黒家の客が一緒でなければ、式神の飛行で道のりを短縮したのですが……」
薄らぼんやりした前世の知識も、たまには役に立つ。前世の物語は、想像力豊かなものばかりだった。式神作りは霊力と想像力がものをいう。碧玉は妖怪退治をする時、前世の創作物を参考に、巨大な鳥の式神を作り出して利用していた。妖怪でもない限り、巨大な鳥は存在しない。この世界の人間にとって、巨大な鳥は倒すべきもので、背に乗ろうなどと考えないのだ。碧玉は前世の記憶の影響で、そんな常識をあっさりと打ち壊した。
天祐は宗主になってから、碧玉が思いえがいた式神の造作を取り入れて、移動手段の短縮に使っているのだ。
「あれは余所者に気安く見せるべきではない」
「そうですね。霊力が低い者が真似をしては、落下事故を起こして大惨事になります」
碧玉としては、空を自由に飛べるようになると、領の防衛に影響が出るから余所者には見せるべきではないという意味で言ったのだが、根が善良な天祐は、見知らぬ誰かが怪我をしないかと案じている。
(こういうところを見ると、本当にこやつが天治帝らを策略にはめて皆殺しにしたのかと疑わしくなるな)
普段の天祐は、温厚で快活な好青年だ。冷酷な碧玉と比べれば、ずっと性格が良い。だというのに、彼を怒らせると性格が豹変するのだから油断ならない。
(否、普段が優しい者ほど、怒らせると恐ろしいと聞く。むしろその典型例なのか?)
碧玉がじーっと見つめると、天祐はわずかに首を傾げ、ふいに碧玉に口づけをした。
「……おい」
思わずにらむと、天祐はにこりと微笑む。
「口づけをしたいのかと思いました」
「それはお前だろう?」
「俺はいつでも口づけをしたいですよ」
「聞いた私が馬鹿だった」
「兄上は分かっておりません」
天祐がじとりとした目を、碧玉に向ける。
「お疲れの兄上に無茶をさせるわけには参りませんから、これでも触れるのを我慢しているのですよ?」
碧玉はぎくりとした。天祐は普段は碧玉第一で、素直に言うことを聞くが、閨に入ると一切の遠慮がなくなるのだ。旅の間は添い寝する程度で何もしてこないのは、碧玉の体調のためだったらしい。
「しかし、兄上が留守番でしたら、会うこともかないませんでしたから、こうしてお傍にいられるだけで幸せです」
「……そうか」
碧玉はふいっと目をそらす。
恥ずかしいことを平然と言ってのける天祐には、どんな態度をとっていいか分からなくなることがある。胸の奥がむずがゆいのに、悪い気はしないのが厄介だ。
水田の間にある広い道を進んでいくと、黒領で最も高い山――天声山のふもとに着いた。
黒領の本拠地・龍拠だ。早朝は山の裾野にまとわりつくようにして霧が出ることが多く、龍に守られているように見える場所だった。実際に龍脈が通っており、霊気が強い土地でもある。
龍拠の町の奥にあるのが、黒家の屋敷だ。
宿の多い界隈で馬車を停め、碧玉は車を降りることにした。配下の数名は町の宿に泊まるので、彼らにまぎれこむ予定だった。車を降りる間際に、天祐に注意する。
「天祐、上手くやるのだぞ。判断に困ったら、灰炎か崔師父を頼りなさい」
「ええ。兄上、くれぐれも気軽にお顔をお見せになりませんように。灰炎殿」
天祐は心配そうに、灰炎の名を呼ぶ。
「お任せください、白宗主」
馬車の入り口から顔を覗かせ、灰炎は天祐に拱手をする。町の宿に泊まる使用人と門弟も、碧玉にならい、いっせいに拱手した。
黒家の者達が焦れったそうにしているのに気づいているので、碧玉は灰炎と共に、あっさりと馬車から離れる。一台の荷車と数名が列を離れ、近くの宿に向かう。
中級の宿を貸し切りにして、その中の一番良い部屋を碧玉が使うことにしたのだが、碧玉は早々に庭の木陰に追いやられてしまった。宿の掃除がなっていないと使用人らが憤慨し、支度が済むまで待っていてほしいと言い出したせいだ。
「あやつら、いつからあんなに仕事熱心になったのだ?」
庭に追いやられるなど滅多とない。彼らの言い分は理解できるので、碧玉は無礼だと怒るよりも呆れている。
「はは。こたびは精鋭がそろっておりますからねえ」
笑いながら返す灰炎ですら、宿の下女の支度を断り、自分で茶と菓子を用意している。
「旅先でくらい、宿の者に仕事を任せればよいだろうに」
「得体の知れぬ者の淹れた茶など、主君に出すわけに参りません。それに、ほとんどの場合、私のほうが上手にできます」
「それはそうだな」
大男という見た目に反し、灰炎は繊細な男だ。祓魔業のことになると大雑把なのに、何故か身の回りの仕事では丁寧さを発揮する。軽食程度ならば、灰炎でも作ることができ、不思議と美味い。灰炎を一人連れていけば、旅には困らないだろう。
「灰炎、馬車酔いも落ち着いたゆえ、暇つぶしに周りを冷やかしにいかぬか」
「しかし、宗主様が心配なされますよ。それに黒家の方々にばれるかもしれません」
「白家の新宗主が、わざわざ黒領まで足を運んだのだぞ。今は準備に気を取られて、出かける余裕もあるまい。だからむしろ、出歩くなら今がちょうどいい」
「確かにそうですね」
灰炎は納得を見せた。
「とはいえ、昔、父上と共に、黒領には何度か来たことがある。覚えのある者もいるだろうから、おおっぴらに顔をさらすのはまずいな。身なりを隠すなら笠でも充分だが、散歩には邪魔だ。何かよいものはないか」
「そうですね。仮面はいかがです?」
「祭りでもないのに、不審ではないか?」
碧玉の問いに、灰炎は少し考えてから答える。
「怪しいことは怪しいですが、いないこともありません。普段ならば芸人が芸を披露する時につけることが多いでしょうが、それ以外では、病気や怪我の痕を隠すのに使っていることもありますから」
「怪我か。例えば、やけど痕とかか?」
「ええ。そうですね、細かい設定を考えましょう。幼い頃、焚火の傍で転んで顔にやけどをしたので隠している……というのはいかがですか?」
「そうだな。幼少期はそういうやけどをしがちだ。それでいこう」
碧玉自身も幼い頃、火の美しさに魅了されて手を伸ばし、指先に軽いやけどをしたことがある。
「もし仮面が外れた時に備えて、目の下にほくろを書いておきましょう。もし碧玉様ではないかと詰められたら、先代にそっくりな白家の遠縁ですと押し通します」
「そうだな。宗主が兄にそっくりな者を役人にしているのは、白家としては外聞が悪い。能力ではなく外見で選んだことになるからな。それで身なりを隠していると言えば、深く追及もしないだろう」
礼儀正しい者なら、見ないふりをするはずだ。そうでない者が好奇心に駆られても、後ろ盾が白家の宗主ならば、身分を恐れて引き下がる案件でもある。
灰炎との話し合いを終えると、碧玉は門弟に命じて木製の仮面を手に入れさせた。顔の上半分だけを隠す仮面を目元につけ、碧玉は灰炎と共に宿を抜け出す。
黒家の者が妖狐騒動に慌てているのに反して、町の雰囲気はのどかだ。
ぶらぶらと歩きながら、出店や商店を覗いて回る。庶民向けの菓子や食べ物を売る店、玩具屋や小間物屋がある中、占い師の店を多く見かけるのが黒領らしい。
「何か問題が起きているようには見えぬな」
「民を不安がらせないように、気を付けておられるのでしょう」
詳しいことは、あとで天祐に聞かなくてはならないようだ。
「灰炎、黒領の茶菓子はなんだろうか」
「分かりません。私も黒領には滅多に来ないので気になりますね。主君、あちらに茶楼がございますから、休憩にいたしましょう」
二階建ての茶楼に入ると、一階は四人掛けの丸几が整然と並んでおり、昼時を過ぎた午後にもかかわらず、多くの人で賑わっている。前のほうには鶴と松がえがかれた衝立が置かれ、その前に立つ三十代ほどの講談師が、折よく黒領の昔話を始めたところだった。
「これはまだ黒領が切り拓かれるよりも前の、古い時代のこと。この世は魑魅魍魎が跋扈し、人々は夜の闇に怯えておりました」
碧玉達は目立たない壁際の席に落ち着き、すぐさま近づいてきた店員に茶菓子を頼んで、講談師の話に耳を傾ける。
「黒家の宗主の前に、天女のごとき美しい女人が現れました。その名は梅花。紅梅のような小さな唇、白梅のような肌をした絶世の美女でございました。その声は迦陵頻伽のごとく、彼女の弾く琵琶は天上の楽のようでした」
57
あなたにおすすめの小説

愛された側妃と、愛されなかった正妃
編端みどり
恋愛
隣国から嫁いだ正妃は、夫に全く相手にされない。
夫が愛しているのは、美人で妖艶な側妃だけ。
連れて来た使用人はいつの間にか入れ替えられ、味方がいなくなり、全てを諦めていた正妃は、ある日側妃に子が産まれたと知った。自分の子として育てろと無茶振りをした国王と違い、産まれたばかりの赤ん坊は可愛らしかった。
正妃は、子育てを通じて強く逞しくなり、夫を切り捨てると決めた。
※カクヨムさんにも掲載中
※ 『※』があるところは、血の流れるシーンがあります
※センシティブな表現があります。血縁を重視している世界観のためです。このような考え方を肯定するものではありません。不快な表現があればご指摘下さい。

愛してやまなかった婚約者は俺に興味がない
了承
BL
卒業パーティー。
皇子は婚約者に破棄を告げ、左腕には新しい恋人を抱いていた。
青年はただ微笑み、一枚の紙を手渡す。
皇子が目を向けた、その瞬間——。
「この瞬間だと思った。」
すべてを愛で終わらせた、沈黙の恋の物語。
IFストーリーあり
誤字あれば報告お願いします!
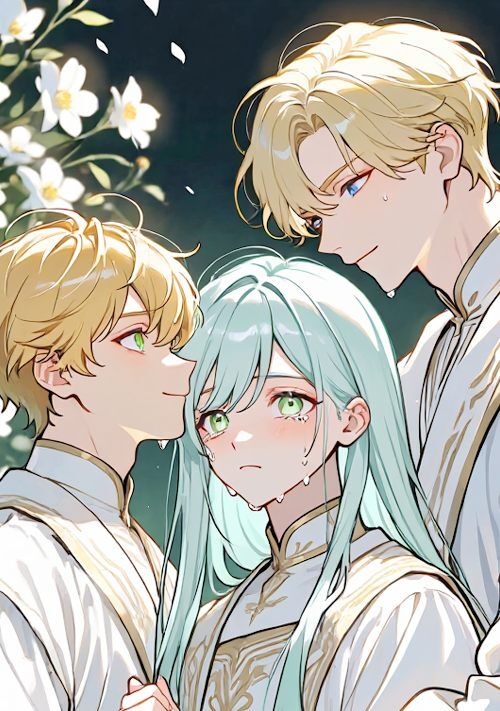
悪役令息を改めたら皆の様子がおかしいです?
* ゆるゆ
BL
王太子から伴侶(予定)契約を破棄された瞬間、前世の記憶がよみがえって、悪役令息だと気づいたよ! しかし気づいたのが終了した後な件について。
悪役令息で断罪なんて絶対だめだ! 泣いちゃう!
せっかく前世を思い出したんだから、これからは心を入れ替えて、真面目にがんばっていこう! と思ったんだけど……あれ? 皆やさしい? 主人公はあっちだよー?
ユィリと皆の動画をつくりました!
インスタ @yuruyu0 絵も動画もあがります。ほぼ毎日更新!
Youtube @BL小説動画 アカウントがなくても、どなたでもご覧になれます。動画を作ったときに更新!
プロフのWebサイトから、両方に飛べるので、もしよかったら!
名前が * ゆるゆ になりましたー!
中身はいっしょなので(笑)これからもどうぞよろしくお願い致しますー!
ご感想欄 、うれしくてすぐ承認を押してしまい(笑)ネタバレ 配慮できないので、ご覧になる時は、お気をつけください!

やっと退場できるはずだったβの悪役令息。ワンナイトしたらΩになりました。
毒島醜女
BL
目が覚めると、妻であるヒロインを虐げた挙句に彼女の運命の番である皇帝に断罪される最低最低なモラハラDV常習犯の悪役夫、イライ・ロザリンドに転生した。
そんな最期は絶対に避けたいイライはヒーローとヒロインの仲を結ばせつつ、ヒロインと円満に別れる為に策を練った。
彼の努力は実り、主人公たちは結ばれ、イライはお役御免となった。
「これでやっと安心して退場できる」
これまでの自分の努力を労うように酒場で飲んでいたイライは、いい薫りを漂わせる男と意気投合し、彼と一夜を共にしてしまう。
目が覚めると罪悪感に襲われ、すぐさま宿を去っていく。
「これじゃあ原作のイライと変わらないじゃん!」
その後体調不良を訴え、医師に診てもらうととんでもない事を言われたのだった。
「あなた……Ωになっていますよ」
「へ?」
そしてワンナイトをした男がまさかの国の英雄で、まさかまさか求愛し公開プロポーズまでして来て――
オメガバースの世界で運命に導かれる、強引な俺様α×頑張り屋な元悪役令息の元βのΩのラブストーリー。

【完結】これをもちまして、終了とさせていただきます
楽歩
恋愛
異世界から王宮に現れたという“女神の使徒”サラ。公爵令嬢のルシアーナの婚約者である王太子は、簡単に心奪われた。
伝承に語られる“女神の使徒”は時代ごとに現れ、国に奇跡をもたらす存在と言われている。婚約解消を告げる王、口々にルシアーナの処遇を言い合う重臣。
そんな混乱の中、ルシアーナは冷静に状況を見据えていた。
「王妃教育には、国の内部機密が含まれている。君がそれを知ったまま他家に嫁ぐことは……困難だ。女神アウレリア様を祀る神殿にて、王家の監視のもと、一生を女神に仕えて過ごすことになる」
神殿に閉じ込められて一生を過ごす? 冗談じゃないわ。
「お話はもうよろしいかしら?」
王族や重臣たち、誰もが自分の思惑通りに動くと考えている中で、ルシアーナは静かに、己の存在感を突きつける。
※39話、約9万字で完結予定です。最後までお付き合いいただけると嬉しいですm(__)m

冷遇王妃はときめかない
あんど もあ
ファンタジー
幼いころから婚約していた彼と結婚して王妃になった私。
だが、陛下は側妃だけを溺愛し、私は白い結婚のまま離宮へ追いやられる…って何てラッキー! 国の事は陛下と側妃様に任せて、私はこのまま離宮で何の責任も無い楽な生活を!…と思っていたのに…。

王子を身籠りました
青の雀
恋愛
婚約者である王太子から、毒を盛って殺そうとした冤罪をかけられ収監されるが、その時すでに王太子の子供を身籠っていたセレンティー。
王太子に黙って、出産するも子供の容姿が王家特有の金髪金眼だった。
再び、王太子が毒を盛られ、死にかけた時、我が子と対面するが…というお話。

夫が妹を第二夫人に迎えたので、英雄の妻の座を捨てます。
Nao*
恋愛
夫が英雄の称号を授かり、私は英雄の妻となった。
そして英雄は、何でも一つ願いを叶える事が出来る。
そんな夫が願ったのは、私の妹を第二夫人に迎えると言う信じられないものだった。
これまで夫の為に祈りを捧げて来たと言うのに、私は彼に手酷く裏切られたのだ──。
(1万字以上と少し長いので、短編集とは別にしてあります。)
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる
本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。
このユーザをミュートしますか?
※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。
※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。
※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。




















