3 / 15
第1話 「ソウル・ドラキュラ」
しおりを挟む
第1話 「ソウル・ドラキュラ」
「ソウル・ドラキュラ!」
おばあちゃんの声が玄関まで響いた。
リビングのテレビでは、YouTubeの懐メロチャンネルが再生されている。
画面の中、70年代のステージ。黒いマントにサングラスの男が、指をパチンと鳴らして踊っていた。
――Hot Blood「Soul Dracula」。
おばあちゃんは、ステップを踏みながら嬉しそうに体を揺らしている。
「ほら、ルイ! この曲、昔めっちゃ流行ったのよ!」
「おばあちゃん、朝からテンション高すぎ」
「ハロウィンでしょ? 血が騒ぐのよ」
「……それ、洒落になってないから」
類は笑いながらリュックを背負う。
カーテン越しの光が、ほこりを金色に照らしていた。
台所からは柚子味噌の香り。
甘じょっぱくて、ちょっと焦げた匂い。
おばあちゃんは鍋を火からおろしながら、ステップを止めずに言った。
「今夜は渋谷行くの?」
「うん。友達と、ちょっと見に行くだけ」
「人多いでしょ。気をつけてよ」
「わかってる」
「……あんた、仮装しないの?」
「うーん、今日はパス。見る側でいいかな」
「つまんないわねぇ。じゃあ代わりに、私が仮装する!」
「え、するの!?」
おばあちゃんは笑いながら、赤いマントを羽織って見せた。
「どう? “グランマ・ドラキュラ”」
「最高。てか、似合いすぎ」
類は腹を抱えて笑った。
そのとき、曲がちょうどサビに入った。
――♪Soul Dracula~ Ha ha ha ha~
おばあちゃんは腕を伸ばし、軽やかにターンした。
「おばあちゃん、めっちゃノリノリだね」
「だって、ハロウィンは年に一度よ。ルイ、笑って行きなさい。
笑ってる人には、いい出会いがあるの」
「ふふ……ありがとう」
「今日は素敵な夜になるかも。いってらっしゃい」
その言葉に、類は軽く手を振って家を出た。
まさか、あんな夜になるなんて――思ってもいなかった。
*
夕方の渋谷は、もう熱を帯びていた。
駅前からスクランブル交差点にかけて、仮装した若者たちが溢れている。
魔女、警官、アニメキャラ、ゾンビ、そして吸血鬼。
スピーカーからは低音のビートが響き、街全体が心臓のように脈打っていた。
「人、多っ……」
類は汗ばんだ手でスマホを握りしめた。
「カズ、どこー?」
電話しても、通じない。
人の波に押されて、まるで漂流しているみたいだ。
鼻をかすめる甘い香水、汗、アルコール、綿菓子の匂い。
目の前ではゾンビが叫び、背後では誰かが笑っている。
その混沌が、息苦しいほど眩しかった。
「……写真でも撮るか」
類はスマホを構えた。
画面の中で、仮装した群衆がカメラ目線で笑う。
けれど、その隙間に――一瞬、赤い影が見えた。
黒い外套、背の高いシルエット。
人混みの中で、ただ一人だけ静止している男。
「……あれ?」
ズームしても、ピントが合わない。
赤い瞳のようなものが、カメラ越しに光った気がした。
「気のせいか」
類は笑って、スマホを下ろす。
でも、背中の奥がざわめいた。
まるで――見られている。
「……誰か、見てる?」
振り向く。
だが、視界は仮装した人々で埋まっていた。
ドラキュラも、デビルも、骸骨も、みんな笑っている。
“仮面の街”とは、こういうことかもしれない。
「はは……雰囲気に飲まれてるだけだ」
類は笑いながら、群衆に溶け込んだ。
*
夜十時。
渋谷の空気はさらに熱くなり、道玄坂のあたりは人でぎっしり詰まっていた。
路上ライブの音が混ざり、クラブの低音が響き、
焼きとうもろこしの煙が、秋の夜気をくすぐった。
「……やっぱ帰るかな」
類は信号待ちの列に並んだ。
青に変わる。
渡ろうとした瞬間、目の前に――黒いマント。
「……!」
ぶつかる寸前、男の腕が類の肩を押さえた。
「危ないよ」
低い声。
驚いて顔を上げた瞬間、息が止まった。
血のように紅い瞳。
整いすぎた顔立ち。
肌は雪のように白い。
「……あ、すみません」
「謝らなくていい。君の方が、少し迷ってるだけだ」
「え?」
「渋谷は広い。迷子になる者ほど、美味しそうに見える」
「……え、今なんて?」
男は軽く笑った。
「冗談だよ。僕はヴァン。君は?」
「……類です」
「ルイ」
その名を呼ぶ声が、妙に心地よかった。
「友達とはぐれたの?」
「はい。ていうか、なんでそんなに……」
「目が?」
「……はい」
「夜目が利くんだ。生まれつき、暗闇に慣れてる」
言葉が、どこか違う響きを持っていた。
口調は丁寧なのに、まるで心を覗かれているようで、落ち着かない。
それでも、目が離せなかった。
「ヴァンさん……仮装、すごいリアルですね」
「仮装?」
「ドラキュラでしょ?」
「君は、そう見えるのか」
「え?」
「なら、そういうことにしておこう」
笑ったとき、月明かりに白い牙がのぞいた。
「じゃあ、どこまで送ろうか。夜は危ない」
「え、いいです! 全然、大丈夫なんで」
「そう言う人ほど、帰ってこない」
「は……?」
「君も感じているだろう、この夜の熱。
渋谷の血管を流れる音。
誰もが何かを失くして、何かを得ようとしてる」
男の声が、鼓膜の奥を撫でるように響く。
人の声じゃない。
音そのものが甘く、危険な香りをしていた。
「君は、選ばれたんだよ」
「……選ばれた?」
「そう。僕に、見つけられたんだ」
類は一歩、後ずさる。
でも、逃げられない。
足が地面に縫いつけられたみたいに動かない。
ヴァンの瞳が、闇を引きずり込む。
「怖い?」
「……少し」
「いい顔だ」
男は微笑み、指先で類の頬をなぞった。
冷たいのに、熱を帯びている。
心臓がドクンと鳴るたび、その音がヴァンに伝わっている気がした。
「君の血の音、よく聞こえる」
「な……に言って」
「怖がらなくていい。痛みよりも、先に快楽が来る」
「やめ――」
「目を閉じて。すぐ終わる」
ヴァンの唇が、首筋に触れた。
冷たい。
でも次の瞬間、熱が走る。
呼吸が止まり、世界が遠のく。
鉄の味。
甘く、苦い。
涙がこぼれた。
――そのとき、頭の奥で“ソウル・ドラキュラ”のサビが鳴った。
おばあちゃんの笑顔。
「今日は素敵な夜になるかも。いってらっしゃい」
その言葉が、血のように胸に滲んだ。
「……おばあちゃん」
呟いた声は、もう彼の指の中で溶けていた。
ヴァンの囁きが、遠くで響く。
「そうさ。これは“素敵な夜”のはじまりだよ、ルイ」
(つづく)
「ソウル・ドラキュラ!」
おばあちゃんの声が玄関まで響いた。
リビングのテレビでは、YouTubeの懐メロチャンネルが再生されている。
画面の中、70年代のステージ。黒いマントにサングラスの男が、指をパチンと鳴らして踊っていた。
――Hot Blood「Soul Dracula」。
おばあちゃんは、ステップを踏みながら嬉しそうに体を揺らしている。
「ほら、ルイ! この曲、昔めっちゃ流行ったのよ!」
「おばあちゃん、朝からテンション高すぎ」
「ハロウィンでしょ? 血が騒ぐのよ」
「……それ、洒落になってないから」
類は笑いながらリュックを背負う。
カーテン越しの光が、ほこりを金色に照らしていた。
台所からは柚子味噌の香り。
甘じょっぱくて、ちょっと焦げた匂い。
おばあちゃんは鍋を火からおろしながら、ステップを止めずに言った。
「今夜は渋谷行くの?」
「うん。友達と、ちょっと見に行くだけ」
「人多いでしょ。気をつけてよ」
「わかってる」
「……あんた、仮装しないの?」
「うーん、今日はパス。見る側でいいかな」
「つまんないわねぇ。じゃあ代わりに、私が仮装する!」
「え、するの!?」
おばあちゃんは笑いながら、赤いマントを羽織って見せた。
「どう? “グランマ・ドラキュラ”」
「最高。てか、似合いすぎ」
類は腹を抱えて笑った。
そのとき、曲がちょうどサビに入った。
――♪Soul Dracula~ Ha ha ha ha~
おばあちゃんは腕を伸ばし、軽やかにターンした。
「おばあちゃん、めっちゃノリノリだね」
「だって、ハロウィンは年に一度よ。ルイ、笑って行きなさい。
笑ってる人には、いい出会いがあるの」
「ふふ……ありがとう」
「今日は素敵な夜になるかも。いってらっしゃい」
その言葉に、類は軽く手を振って家を出た。
まさか、あんな夜になるなんて――思ってもいなかった。
*
夕方の渋谷は、もう熱を帯びていた。
駅前からスクランブル交差点にかけて、仮装した若者たちが溢れている。
魔女、警官、アニメキャラ、ゾンビ、そして吸血鬼。
スピーカーからは低音のビートが響き、街全体が心臓のように脈打っていた。
「人、多っ……」
類は汗ばんだ手でスマホを握りしめた。
「カズ、どこー?」
電話しても、通じない。
人の波に押されて、まるで漂流しているみたいだ。
鼻をかすめる甘い香水、汗、アルコール、綿菓子の匂い。
目の前ではゾンビが叫び、背後では誰かが笑っている。
その混沌が、息苦しいほど眩しかった。
「……写真でも撮るか」
類はスマホを構えた。
画面の中で、仮装した群衆がカメラ目線で笑う。
けれど、その隙間に――一瞬、赤い影が見えた。
黒い外套、背の高いシルエット。
人混みの中で、ただ一人だけ静止している男。
「……あれ?」
ズームしても、ピントが合わない。
赤い瞳のようなものが、カメラ越しに光った気がした。
「気のせいか」
類は笑って、スマホを下ろす。
でも、背中の奥がざわめいた。
まるで――見られている。
「……誰か、見てる?」
振り向く。
だが、視界は仮装した人々で埋まっていた。
ドラキュラも、デビルも、骸骨も、みんな笑っている。
“仮面の街”とは、こういうことかもしれない。
「はは……雰囲気に飲まれてるだけだ」
類は笑いながら、群衆に溶け込んだ。
*
夜十時。
渋谷の空気はさらに熱くなり、道玄坂のあたりは人でぎっしり詰まっていた。
路上ライブの音が混ざり、クラブの低音が響き、
焼きとうもろこしの煙が、秋の夜気をくすぐった。
「……やっぱ帰るかな」
類は信号待ちの列に並んだ。
青に変わる。
渡ろうとした瞬間、目の前に――黒いマント。
「……!」
ぶつかる寸前、男の腕が類の肩を押さえた。
「危ないよ」
低い声。
驚いて顔を上げた瞬間、息が止まった。
血のように紅い瞳。
整いすぎた顔立ち。
肌は雪のように白い。
「……あ、すみません」
「謝らなくていい。君の方が、少し迷ってるだけだ」
「え?」
「渋谷は広い。迷子になる者ほど、美味しそうに見える」
「……え、今なんて?」
男は軽く笑った。
「冗談だよ。僕はヴァン。君は?」
「……類です」
「ルイ」
その名を呼ぶ声が、妙に心地よかった。
「友達とはぐれたの?」
「はい。ていうか、なんでそんなに……」
「目が?」
「……はい」
「夜目が利くんだ。生まれつき、暗闇に慣れてる」
言葉が、どこか違う響きを持っていた。
口調は丁寧なのに、まるで心を覗かれているようで、落ち着かない。
それでも、目が離せなかった。
「ヴァンさん……仮装、すごいリアルですね」
「仮装?」
「ドラキュラでしょ?」
「君は、そう見えるのか」
「え?」
「なら、そういうことにしておこう」
笑ったとき、月明かりに白い牙がのぞいた。
「じゃあ、どこまで送ろうか。夜は危ない」
「え、いいです! 全然、大丈夫なんで」
「そう言う人ほど、帰ってこない」
「は……?」
「君も感じているだろう、この夜の熱。
渋谷の血管を流れる音。
誰もが何かを失くして、何かを得ようとしてる」
男の声が、鼓膜の奥を撫でるように響く。
人の声じゃない。
音そのものが甘く、危険な香りをしていた。
「君は、選ばれたんだよ」
「……選ばれた?」
「そう。僕に、見つけられたんだ」
類は一歩、後ずさる。
でも、逃げられない。
足が地面に縫いつけられたみたいに動かない。
ヴァンの瞳が、闇を引きずり込む。
「怖い?」
「……少し」
「いい顔だ」
男は微笑み、指先で類の頬をなぞった。
冷たいのに、熱を帯びている。
心臓がドクンと鳴るたび、その音がヴァンに伝わっている気がした。
「君の血の音、よく聞こえる」
「な……に言って」
「怖がらなくていい。痛みよりも、先に快楽が来る」
「やめ――」
「目を閉じて。すぐ終わる」
ヴァンの唇が、首筋に触れた。
冷たい。
でも次の瞬間、熱が走る。
呼吸が止まり、世界が遠のく。
鉄の味。
甘く、苦い。
涙がこぼれた。
――そのとき、頭の奥で“ソウル・ドラキュラ”のサビが鳴った。
おばあちゃんの笑顔。
「今日は素敵な夜になるかも。いってらっしゃい」
その言葉が、血のように胸に滲んだ。
「……おばあちゃん」
呟いた声は、もう彼の指の中で溶けていた。
ヴァンの囁きが、遠くで響く。
「そうさ。これは“素敵な夜”のはじまりだよ、ルイ」
(つづく)
0
あなたにおすすめの小説

サラリーマン二人、酔いどれ同伴
風
BL
久しぶりの飲み会!
楽しむ佐万里(さまり)は後輩の迅蛇(じんだ)と翌朝ベッドの上で出会う。
「……え、やった?」
「やりましたね」
「あれ、俺は受け?攻め?」
「受けでしたね」
絶望する佐万里!
しかし今週末も仕事終わりには飲み会だ!
こうして佐万里は同じ過ちを繰り返すのだった……。

僕たち、結婚することになりました
リリーブルー
BL
俺は、なぜか知らないが、会社の後輩(♂)と結婚することになった!
後輩はモテモテな25歳。
俺は37歳。
笑えるBL。ラブコメディ💛
fujossyの結婚テーマコンテスト応募作です。

優しい檻に囚われて ―俺のことを好きすぎる彼らから逃げられません―
無玄々
BL
「俺たちから、逃げられると思う?」
卑屈な少年・織理は、三人の男から同時に告白されてしまう。
一人は必死で熱く重い男、一人は常に包んでくれる優しい先輩、一人は「嫌い」と言いながら離れない奇妙な奴。
選べない織理に押し付けられる彼らの恋情――それは優しくも逃げられない檻のようで。
本作は織理と三人の関係性を描いた短編集です。
愛か、束縛か――その境界線の上で揺れる、執着ハーレムBL。
※この作品は『記憶を失うほどに【https://www.alphapolis.co.jp/novel/364672311/155993505】』のハーレムパロディです。本編未読でも雰囲気は伝わりますが、キャラクターの背景は本編を読むとさらに楽しめます。
※本作は織理受けのハーレム形式です。
※一部描写にてそれ以外のカプとも取れるような関係性・心理描写がありますが、明確なカップリング意図はありません。が、ご注意ください
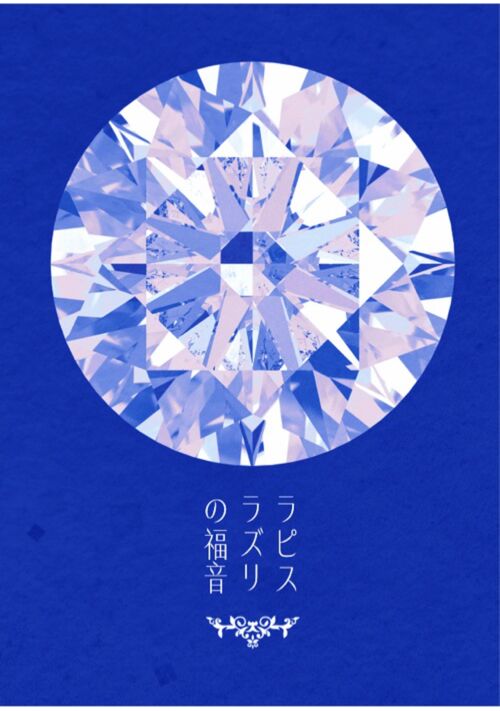
ラピスラズリの福音
東雲
BL
*異世界ファンタジーBL*
特別な世界観も特殊な設定もありません。壮大な何かもありません。
幼馴染みの二人が遠回りをしながら、相思相愛の果てに結ばれるお話です。
金髪碧眼美形攻め×純朴一途筋肉受け
息をするように体の大きい子受けです。
珍しく年齢制限のないお話ですが、いつもの如く己の『好き』と性癖をたんと詰め込みました!

青龍将軍の新婚生活
蒼井あざらし
BL
犬猿の仲だった青辰国と涼白国は長年の争いに終止符を打ち、友好を結ぶこととなった。その友好の証として、それぞれの国を代表する二人の将軍――青龍将軍と白虎将軍の婚姻話が持ち上がる。
武勇名高い二人の将軍の婚姻は政略結婚であることが火を見るより明らかで、国民の誰もが「国境沿いで睨み合いをしていた将軍同士の結婚など上手くいくはずがない」と心の中では思っていた。
そんな国民たちの心配と期待を背負い、青辰の青龍将軍・星燐は家族に高らかに宣言し母国を旅立った。
「私は……良き伴侶となり幸せな家庭を築いて参ります!」
幼少期から伴侶となる人に尽くしたいという願望を持っていた星燐の願いは叶うのか。
中華風政略結婚ラブコメ。
※他のサイトにも投稿しています。

龍の無垢、狼の執心~跡取り美少年は侠客の愛を知らない〜
中岡 始
BL
「辰巳会の次期跡取りは、俺の息子――辰巳悠真や」
大阪を拠点とする巨大極道組織・辰巳会。その跡取りとして名を告げられたのは、一見するとただの天然ボンボンにしか見えない、超絶美貌の若き御曹司だった。
しかも、現役大学生である。
「え、あの子で大丈夫なんか……?」
幹部たちの不安をよそに、悠真は「ふわふわ天然」な言動を繰り返しながらも、確実に辰巳会を掌握していく。
――誰もが気づかないうちに。
専属護衛として選ばれたのは、寡黙な武闘派No.1・久我陣。
「命に代えても、お守りします」
そう誓った陣だったが、悠真の"ただの跡取り"とは思えない鋭さに次第に気づき始める。
そして辰巳会の跡目争いが激化する中、敵対組織・六波羅会が悠真の命を狙い、抗争の火種が燻り始める――
「僕、舐められるの得意やねん」
敵の思惑をすべて見透かし、逆に追い詰める悠真の冷徹な手腕。
その圧倒的な"跡取り"としての覚醒を、誰よりも近くで見届けた陣は、次第に自分の心が揺れ動くのを感じていた。
それは忠誠か、それとも――
そして、悠真自身もまた「陣の存在が自分にとって何なのか」を考え始める。
「僕、陣さんおらんと困る。それって、好きってことちゃう?」
最強の天然跡取り × 一途な忠誠心を貫く武闘派護衛。
極道の世界で交差する、戦いと策謀、そして"特別"な感情。
これは、跡取りが"覚醒"し、そして"恋を知る"物語。


聖者の愛はお前だけのもの
いちみりヒビキ
BL
スパダリ聖者とツンデレ王子の王道イチャラブファンタジー。
<あらすじ>
ツンデレ王子”ユリウス”の元に、希少な男性聖者”レオンハルト”がやってきた。
ユリウスは、魔法が使えないレオンハルトを偽聖者と罵るが、心の中ではレオンハルトのことが気になって仕方ない。
意地悪なのにとても優しいレオンハルト。そして、圧倒的な拳の破壊力で、数々の難題を解決していく姿に、ユリウスは惹かれ、次第に心を許していく……。
全年齢対象。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















