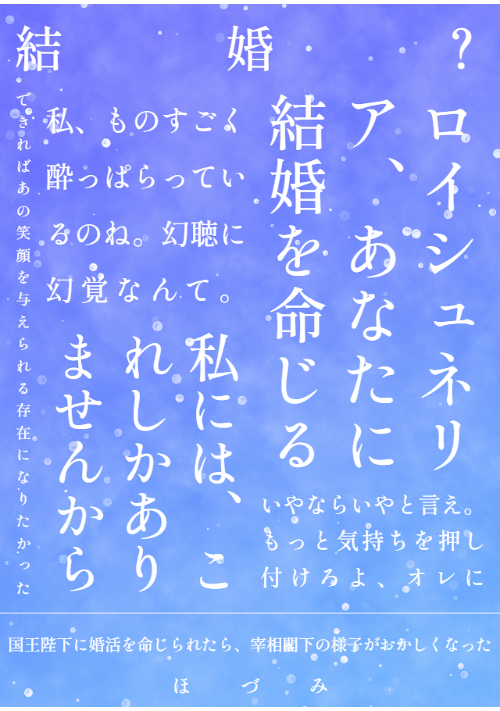1 / 16
1巻
1-1
しおりを挟む1
今日は、王宮で半年に一度だけ催される特別な夜会の日だ。豪奢な大広間には美しく着飾った貴族たちがひしめき合い、話に花を咲かせている。
王宮で働くメイドであるアレット・ダンピエールは、給仕に片付けにと忙しく働く合間に、その中心にいる人物をちらちらと目で追っていた。
彼はこのバラディア王国の王太子、リオネル・バラデュール。まだ二十六歳だが、経験豊富な重臣たちに引けを取らず、行動力があり的確な判断を下すので、すでに国政に与える影響力は少なくない。
そのうえ、誰にでも等しく接する人格者で、老若男女問わず国民に愛されている。特に、その見目の麗しさから女性人気は絶大で、アレットもリオネルに憧れる女性の一人だった。
リオネルはメイドや下男といった下々の者にも礼や挨拶を欠かさない。アレットの同僚のエミリーなど、先日、床に落としてしまった雑巾を彼に拾ってもらったのだと自慢していた。
(リオネル殿下、今日も素敵だわ……)
アレットは一応男爵令嬢ということになっているが、実のところダンピエール男爵が平民の女に産ませた庶子にすぎない。末端貴族の中でも、さらに下層にいるのがアレットだ。
その証拠に、アレットは魔法が使えない。ほとんどの貴族が魔法を使えるこの国において、魔法が使えない人間はもはや貴族とはいえなかった。
だからアレットは、多くの貴族令嬢が行儀見習いとして働く中、純粋にお給金を稼ぐために下働きをしている。
アレットは、そんな自分がリオネルとどうにかなれるとは思っていない。ただ心の癒やしとして、憧れのリオネルを眺めているのだった。
真夜中を過ぎた頃に夜会が終わり、それからようやく後片付けが始まる。仕事が終わるのはかなり遅い時間になってしまうが、その分明日は丸一日お休みだ。
アレットは夜会が終わったあとの、この独特の雰囲気が好きだった。
参加者たちの熱気の名残が、そこかしこにたゆたっているような気がするからだ。
大きなイベントが無事に終わった安心感からか、働く者みんなになんとなく連帯感のようなものも生まれる。
雑然とした大きな広間からテーブルなどが片付けられ、もと通り美しく磨き上げられていく様は、なんとも言えない達成感を与えてくれた。
「アレット、こっちは終わったけど、もう帰れる?」
床の清掃をしていたアレットに声をかけてきたのは、同僚のエミリーだ。その後ろには、仕事が終わったのであろう他のメイドたちが数人見えた。みんなで一緒に王宮の別棟にある宿舎に戻るのだろう。
「床に料理のソースをこぼした人がいたみたいで、綺麗になるまでもう少しかかりそうなの。先に帰っててくれる?」
「一人で大丈夫? 手伝おうか?」
「ありがとう。でも、本当にあと少しだから大丈夫よ」
「じゃあ先に戻ってるから。気を付けて帰ってきてね」
アレットはエミリーたちに「わかったわ」と返事をすると、また床掃除に戻った。
ついつい他の汚れも気になってかたっぱしから綺麗にしていくと、あっという間に時間が過ぎてしまう。
仕事が終わったのは、午前二時も過ぎようかという頃だった。
広間から宿舎まではそれなりに離れているが、同じ王宮内。あちこちに寝ずの番兵たちもいる。夜中に女一人で歩いたところで危険なこともない。
アレットは心地よい疲労感を覚えつつ、欠伸を噛み殺しながら宿舎へ向かって廊下を歩いていた。
すると、前のほうに人影が現れた。
それは、遠目に見ても身なりがいいとわかる男性だった。ここからは客室も近いし、きっと夜会のあと王宮に宿泊することになった貴族だろう。
(もう少し近付いたら、脇に控えてやり過ごそうっと)
アレットはそれ以上のことは考えずに歩みを進める。だんだんと距離が狭まっていくうちに、相手の姿形がはっきりしてきた。
すらりとした細身で背が高く、薄茶色の髪に整った目鼻立ち。歳は二十代半ばといったところだろうか。
そこでアレットは、はっと気付く。
(あれはリオネル殿下……!?)
こんな夜更けに、お供も連れずに一体何をしているのだろう。
アレットは疑問を覚えるとともに、思わぬところで憧れのリオネルに出会えたことを嬉しく思った。
このまま歩いていけば彼とすれ違うだろう。こんなに接近できるチャンスはなかなかない。彼が近付くにつれて、心臓がドキドキと高鳴っていく。
普通であれば立ち止まって頭を下げ、リオネルが通り過ぎるのを待つのが礼儀だ。
しかし、よくよく見るとどうにも彼の様子がおかしい。ふらふらと蛇行しており、目も虚ろだ。
どうしようか悩んでいると、リオネルが足を縺れさせてよろめいたので、アレットは慌てて駆け寄った。
「殿下! 大丈夫ですか!?」
ぷうんと酒の匂いが鼻をつく。相当に酒を飲んでいるようだ。
リオネルの顔は上気しており、吐く息も荒い。
しかし、ただ酔っぱらっているだけではないような気がする。もしかしたら熱でもあるのかもしれない。
「恐れながら殿下、お加減が悪いのでは? 侍従を呼んで参りましょうか?」
アレットが手を差し伸べると、リオネルはいきなり彼女の細い手首を掴んで自身に引き寄せた。
「きゃっ!」
アレットの短い悲鳴を完全に無視して、リオネルは彼女を荷物のように持ち上げる。
「身体が熱い……。熱を鎮めてくれ」
「で、殿下!? 熱があるのならば、安静にしていたほうが……!」
アレットは突然の出来事に混乱するが、相手は王太子殿下。自分のような一介のメイドが怪我でもさせてしまったら大事だ。
アレットが抵抗できずにいると、リオネルは彼女をかかえたまま近くの客室の扉を開き、中をずんずんと進む。そしてベッドの前で立ち止まり、そこにアレットを放った。
乱暴に落とされたので、アレットは思わず身を硬くする。しかし、そこはさすがに王宮のベッド。大きく弾んだだけでまったく痛くはなかった。
(ふかふかだわ……。よく眠れそうなベッドね)
妙なところでアレットが感心していると、リオネルが夜会用のジャケットをもどかしそうに脱ぎ捨て、アレットに覆いかぶさってくる。
太ももに押し付けられたリオネルの下半身は熱を持っており、瞳は情欲に濡れている。ここでアレットは、先ほどのリオネルの言葉の意味をようやく理解して、背筋が冷たくなった。
(え、まさか、そんなことって……!)
薄暗かった部屋には、いつの間にかほのかに明かりが灯っていた。リオネルが魔法を使ったのだろう。
メイドに支給されるシンプルな黒いワンピースをリオネルによって乱暴にはだけさせられ、ボタンが弾け飛ぶ。ピリリと生地が裂けたような音もした。
飾り気のない下着が露わになると、リオネルはアレットの首筋に舌を這わせ、控えめな胸を布越しに強く揉みしだく。
「で、殿下……お願いです! おやめください!」
アレットは最初、憧れのリオネルに会うことができて嬉しく思っていた。けれど、彼がまとったいつもと違う雰囲気に、気が付けばカタカタと手足が震え出していた。
かろうじて絞り出した制止の言葉も、彼の耳にはまるで届かない。それどころか、ワンピースの裾をあられもなく捲り上げられ、下穿きにも手をかけられる。
勇気を振り絞り、震える手でリオネルの胸をなんとか押し返そうと試みるものの、びくともしない。
(どうしよう。どうすれば。このままじゃ……)
「やだ! やめて!」
必死になったアレットは、敬語を使うのも忘れて無我夢中で叫んだ。
運よく誰かが近くを通りかかってくれないだろうかと。
しかし、その希望は儚くもすぐに消え去った。
「静かにしていろ」
アレットの目を捉えたリオネルの瞳には、強い情欲が滲んでいた。
今自分を襲っているのは、この国で国王陛下の次に偉い王太子殿下だ。誰かが通りかかったとしても、果たして彼を止めることができるのだろうか。それこそ、止められるのは国王陛下ぐらいだろう。
きっともう、どうしようもない。逃げられない。
脳裏が悲しみに塗りつぶされていき、アレットは抵抗するのを諦めた。同時に、次から次へと涙が溢れてくる。
「ふ……うぅ……」
「それでいい。おとなしくしていればすぐに終わる」
秘裂を乱暴に嬲り、リオネルが強引に入ってくる。今までの人生で経験したことのないほどの痛みがアレットを襲ったが、それでも懸命に指を噛んで耐えた。
「……っ……つっ……」
リオネルの動きが止まり、アレットが息をついたのも束の間。破瓜の痛みがおさまらないうちに、リオネルは激しく腰を打ち付けてくる。
「っ……う……ああ!」
どれほど必死に耐えても、リオネルの腰が動くたびに、強く噛んだ指の隙間から呻き声がこぼれ出た。
ほんのわずかな……けれどアレットにとっては永遠とも思える時間が経った頃、リオネルがひと際荒々しく息を吐き、それと同時にアレットの中に熱いものが広がった。
とっさに思ったのは、リオネルは避妊をしているのかということだった。もしくは魔法でどうにかできるものなのだろうか。
性行為にも魔法にも疎いアレットにはわからず、不安な気持ちが押し寄せてくる。
そんなアレットの顔色を読み取ったのだろう。リオネルは彼女の中から出ていくと、自嘲気味に呟いた。
「心配は無用だ。どうせ子供はできない」
どういう意味か気になるけれど、アレットにそれを問う余裕はなかった。
恐怖で声が出なかったせいもあるが、そのあとすぐにリオネルが口付けてきたためだ。
舌を入れた激しい口付け。
何もかも初めてのアレットは呼吸の仕方もわからず、リオネルの唇が離れた頃には肩で息をしていた。
リオネルの呼吸も荒くなっていて、逞しい胸板が大きく上下している。
……やっと終わった。
そう思ったアレットに、リオネルは残酷な言葉を突き付ける。
「まだ足りない……。熱が鎮まらない」
そしてアレットは意識が遠のくまで、リオネルにその身を貪られた。
(……ここ、は……? 私……?)
アレットが気付くと、そこは見慣れないベッドの上だった。そして隣には穏やかな寝顔で横たわるリオネルがいる。
眉目秀麗とは、彼のためにある言葉なのだろう。
けれど、いかに端麗であろうと身体を汚されたアレットにとってはなんの慰めにもならなかった。
(リオネル殿下が、まさかあんなことをなさるなんて……)
呆然としたまま、なんとか首を動かして窓のほうに目を向ける。そこから見える空は白み始めており、自分はしばらくの間気を失っていたのだと気付いた。
アレットはなるべくベッドを揺らさないように、そろそろと身体を起こす。
「っ!」
その瞬間、身体のあちこちが痛み、股の間からどろりと何かが出ていく感触がした。
まさか月のものがきたのだろうか。
一瞬ひやりとしたアレットだったが、すぐにリオネルが放ったものだと思い当たる。
改めて昨夜の恐怖が蘇り、胸が苦しくなった。
今にも泣き出してしまいそうな自分を叱咤して、深呼吸をする。それを何度か繰り返すうちに、アレットは少しずつ落ち着きを取り戻していった。
身体は痛むが、早くここから出たい。リオネルのそばにいるのは恐ろしいし、自分にはボタンが弾け飛んだお仕着せしかないのだから、夜が明けて人が多くなる前に部屋に戻らなければ。
震える手足を動かして、なんとかお仕着せを身にまとうと、アレットは部屋をあとにした。
身体のあちこちがきしんで思うように歩くことができず、苦労しながら自室へ向かう。途中、何人かの番兵を見かけたが、なんとかその目をかいくぐりつつ、部屋にたどり着くことができた。
アレットはべたついた身体を念入りに清め、部屋着に着替えてベッドに倒れ込む。
すると気が緩んだのか、涙がじわりと目に滲んできた。
リオネルはなぜあんなことをしたのだろう。
見目麗しく、未来の統治者として優れた能力を持ち、国民に愛されている王太子。彼が即位すれば必ずや賢君になるだろうと噂されている。
そんな彼が、メイドを無理矢理手篭めにするなどと誰が思うだろうか。
それに、彼には五人もの美しい側妃がいたはずだ。彼女たちと違って、ただの平凡なメイドであるアレットには男性を誘惑するような魅力はないと言っていい。
きっとアレットが昨夜のことを誰かに話したところで、信じてはもらえないだろう。むしろ、虚言と決めつけられて牢に入れられてしまうかもしれない。
やり場のない悲しみと恐怖で、アレットの心の中はぐちゃぐちゃだった。
……でも、それも仕方のないことだ。
相手は王族で、自分は一介のメイドにすぎない。その身分には天と地ほどの差がある。自分は運が悪かったのだ。天災にでもあったと思って諦めるしかないのだろう。
幸いにして、命は無事だ。
アレットは目が覚めたら全て忘れると決め、眠りにつこうと試みる。
身体は疲れ切っているはずなのになかなか眠ることができず、アレットはしばらくの間、ベッドの上で悶々と過ごした。
2
「うぅ……」
リオネルはひどい頭痛とともに目を覚まし、思わず呻き声を上げた。
(ここはどこだ……?)
酒を飲みすぎたせいだろうか。昨夜の記憶は、靄がかかったように曖昧だった。
寝ぼけた頭で辺りを見回す。見慣れない客室に、乱れたベッド、散らばった自分の服。
そして何も身につけていない自身の身体を見て、唐突に全てを思い出す。
(そうだ昨日は……)
リオネルは信じられない気持ちで、昨夜の行いを思い返した。
王宮で半年に一度催される夜会。リオネルは次々と話しかけてくる出席者の相手をしながら、内心でため息をついていた。
彼はこの夜会に心底嫌気がさしている。
まずは社交界デビューする若き貴族令嬢たちとのダンス。これは王太子としての務めであるが、要は体のいいお見合いのようなものだ。
そしてここぞとばかりに自分の娘を売り込んでくる貴族たちの相手。古狸があの手この手を使って自分の娘を後宮に送り込もうとしてくるので、令嬢たち本人よりもタチが悪い。
さらには、近頃ではあまり会うこともなくなった五人の側妃との会話も辛かった。
これら全ての面倒事の原因は、まだ自分に世継ぎがいないことにある。
リオネルは十八歳になって成人するとともに、三人の側妃を娶った。そして二十六歳になる現在までにさらに二人が加わり、計五人の側妃がいる。けれどその八年もの間、誰一人として懐妊していない。
一般的に位が高い貴族ほど強大な魔力を持ち、それに反比例して妊娠する確率は低くなる。その最たる王族は、さらに子供ができにくい。とはいえ、五年以上経っても世継ぎができないのは珍しく、由々しき問題でもあった。
リオネルも最初は嫁いできた妃たちを大切にし、周囲の期待に応えようと頻繁に後宮に通っていた。
しかし四年、五年経っても子は一向にできず、リオネルは焦りを覚えるようになった。
自分には子種がないのではないか。
このまま後宮に通い続け、子ができなければ、それが証明されてしまう。
――その恐怖は次第に大きくなり、リオネルの足は後宮から遠のいていった。
すると側妃たちは競うように己を飾り立て、なんとかリオネルをその気にさせようと露骨に媚を売るようになってきた。
しかしリオネルは、どうしても彼女たちを抱くことができなかった。
一方、リオネルが後宮へ通っていないと知った貴族たちは、新しい女を召し上げさせようと、躍起になり始めた。
こうして、ここ一年余りの間は悪循環に陥っていたのだ。
出席者たちの列が途切れ、近くに誰もいなくなった隙に、リオネルはこっそりとため息をつく。
ふと、くるくるとよく働く一人のメイドが目に留まった。黒い髪をひとつに括ってネットでまとめ、お仕着せを着ているなんの変哲もないメイド。
だが、彼女はにこにこしながら給仕をしている。派手な化粧をしているわけでもないのに、リオネルはそのメイドから目が離せなくなっていた。
(ああいう娘と、普通の恋愛をしてみたかった……)
派手な側妃たちとは正反対とも言える地味な娘だ。しかしリオネルには、彼女がひどく眩しく映った。
(……馬鹿なことを考えてしまったな)
リオネルは自嘲の笑みを浮かべ、そのメイドから無理矢理視線をそらす。
そうして長々と続いた夜会もようやくお開きになるかという頃。
引きとめる貴族たちに別れを告げて広間を抜け出したリオネルは、幼馴染で側近でもあるエルネストと、別室で酒を酌み交わしていた。
「おい、リオネル。飲みすぎだぞ」
「放っておけ。飲まずにやっていられるか」
リオネルはイライラとした気持ちに蓋をするように、強い酒を飲んでいた。
夜会のたびに側妃を、世継ぎをと言われると、自分が種馬にでもなったような気分だ。
――そもそも、自分には子種がないかもしれないというのに。リオネルは世継ぎ作りを半ば諦め、いざというときは従兄弟の子供にでも王位を継がせればいいと、投げやりになっていた。
「そう荒れるなよ。いつものことだろ?」
「……ユリウスの妻が懐妊したのはお前も知っているだろ? そのせいで一層風当たりが強くなった」
ユリウスはリオネルの三つ年下の従兄弟だ。直系の自分ほどではないとはいえ、ユリウスも同じく世継ぎを求められ、プレッシャーをかけられていた。そして先日、ついに彼の妻が妊娠したのだ。
「なるほどね。王族というのは大変だなあ。僕はただの貴族で本当によかった。何より何人もいる妃をそれぞれ抱くなんて、僕にはできないよ」
ブローニュ公爵の子息であるエルネストは金髪碧眼の中性的な美男子で、いかにも軽そうな外見をしている。だがそれに反して大層な愛妻家だ。そんな彼には、妻以外の女を抱くなどということは考えられないのだろう。
口に出したことこそないが、そんなふうに想える相手を見つけることができたエルネストを、リオネルは羨ましく思っていた。
ふと頭によぎるのは、先ほど夜会で見たメイドの姿。自分も王族でさえなかったら……とどうしようもない妄想が頭に浮かぶ。
「俺も好きで王族に生まれたわけではない。ったく他人事だと思って……」
そう言うとリオネルは自分で杯に酒を注ぎ、一気にあおった。
酒に溺れるのはよくないことだとわかってはいるが、一時の憂さを晴らすのにこれほど適したものはない。
明らかに飲みすぎているという自覚はありつつも、半ば自棄になっていて止められない。エルネストもリオネルの心中を察しているのか、心配そうに見守るものの、強いて止めようとはしなかった。
そろそろ自室に戻ろうかという頃、扉の向こうから男女が言い合う声が聞こえてきた。男性の声は護衛をしている近衛兵のものだが、女性のほうは……
リオネルが嫌な予感を覚えたと同時に扉が開かれ、一人の女性がずかずかと部屋の中に踏み込んでくる。
「こんなところにいらっしゃいましたのね、リオネル殿下」
「リュシエンヌ……」
部屋に入ってきたのはリオネルの側妃の一人、リュシエンヌだった。
リオネルはこの部屋に入る際、近衛兵に誰も入室させないようにと命じていた。職務を全うしようとした兵に止められたであろうに、リュシエンヌはまったく悪びれることなくリオネルの前までやってくる。
「今日の夜会であまりお話しできなかったので、探しておりましたの。もしよろしければこのあと、わたくしのお部屋で過ごしませんこと?」
リュシエンヌは妖艶な微笑を湛え、傷ひとつない白魚のような指でリオネルの腕をつーっと撫で上げる。
リオネルはもちろんのこと、エルネストまでもが険のある表情を向けているが、彼女はものともしない。
「申し訳ないが、今日はそんな気分ではない。下がってくれないか?」
「そんな、あまりにも冷たいですわ。……では、せめてここでお酒の一杯だけでも付き合ってくださいませ」
リュシエンヌは大げさに悲しそうな顔をすると、次の瞬間には媚びた瞳でリオネルを見つめてくる。
すでにリオネルの気持ちは冷め切っているが、相手は仮にも側妃だ。あまり強く拒むのも問題だろうと、リオネルはややあってから頷いた。
「……酒はもういい。茶の一杯でよければ付き合おう」
「まあ、ありがとうございます! わたくしがお淹れいたしますわ」
リュシエンヌは大輪の薔薇が咲いたような美しい笑みを浮かべて喜びを表すと、そのままエルネストのほうを向く。
「エルネスト様。申し訳ありませんが、席を外していただけるかしら? 久しぶりにリオネル様と二人きりでお話がしたいの」
エルネストはリオネルのためにこの場に残ろうとしていたが、側妃にそう言われては退室せざるをえない。
「わかりました。では、殿下、リュシエンヌ様、失礼いたします」
親友であるリオネルに頑張れよと目くばせをして、エルネストは部屋を出ていった。
リュシエンヌは宣言通り自らお茶を淹れ、リオネルにそれを振る舞う。
リオネルはさっさとこれを飲んでこの場を去ろうと、熱いお茶の温度を魔法で下げ、失礼にならないよう数回にわけて飲み干した。
もしリオネルが素面だったのなら、リュシエンヌの行動やこのお茶の味に違和感を覚えたかもしれない。
応援ありがとうございます!
10
お気に入りに追加
4,393
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる
本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。
このユーザをミュートしますか?
※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。
※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。
※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。