15 / 26
ランプの魔人Ⅱ
しおりを挟む
訥々と雨が降るように。
一言一言が一粒の水滴となって、聞くものの鼓膜を、その先の心を打つような――そんな話し方で、魔人はずっと、話し続けた。
時折、唇を舌で湿らす。
それ以外に、他の音は一切しない。
淀むことも詰まることもなく、そうして最後まで語り終えた。
伏し目がちであった茶混じりの紅は、いま、静かな色を湛えて真っ直ぐと俺を映し出す。
俺の反応を、ただ待ち続けている。
目を閉じ、与えられた情報を反復する。
なぜ、今になってこのような話をしたのか。
気が向いたからか、俺だから良いと思ったのか。
わからないこともあれど、たった一つ。
わかるものがある。
これが最初で最後なのだと。
ここを逃せばおそらく、もう二度と、この扉は開かれないのだと。
故に、踏み込む。
「お前は。
……寂しく、なかったのか」
紺墨の眉根がきゅっと寄り、反して眉尻は深く下がる。
茶混じりの二つの紅は細められ、目頭はくぅと上がる。
口角は両端ともわななきながら下を向き、口蓋を細かに揺らしながら。
そうして叫びあげるように。
――どこまでも、真摯な慟哭を吐き出した。
「そんなのっ。
さみしいにっ、決まってるっ……じゃないかっ!」
先までが降りしきる雨粒であったなら。
これは、怒濤のごとく巌を貫く一筋の水針。
どこまでも深く、聞くものの胸を刺し貫く悲痛な叫び。
なぜこれで泣いていないのか、不思議になるほど、それは水気を孕んでいた。
けれど、その瞳が。
燃え上がる焔のように、茶混じりの紅が強く瞬く。
「それでも、これが。
これが、僕の選んだ道だ。
死にたくないからといえど。
これが、僕が選んだ道なんだ」
あぁ、その煌めきのなんと眩いことか。
夜空駆けゆく流星のごとく、闇夜切り裂く彗星のごとく、見るものの網膜を、その奥の脳髄すら焼き尽くす。
逸れず、ぶれず、揺らぐことなく真っ直ぐに、意思を貫くことの――なんと難しいことか。
それをこの男は、何千年と前から燻ることなくやってきた。
肌がさざめく。
肌だけでなく、身体が震える。
芯の芯まで震えているのは身体だけではなく、心の奥からこの男に感嘆しているから。
揺らめく陽炎すら幻視できるほどに、眼前は燃え上がっている。
それを目に焼きつけることができた。
その喜びが、誇らしさが、心身の隅から隅まで走り抜ける。
あぁ、なんとしたたかなことか。
再度、同じように思う。
孤独の夜は確かに、この男を、その魂を強く苛んだのだろう。
だがそれを毒とせず。
毒だけにせず、自身を磨き上げる研磨剤とした。
より鋭く、細く、折れることのない、針のように鋭敏な一つの刃と成したのだ。
それが今、垣間見えている。
故に、下手な同情ではなく、安易な慰めでもなく。
口にするのは、これこそが相応しい。
「お前は、強い。
誰よりもなによりも、不自由なのに。
それをものともせず、揺らぐことなく立ち続ける」
俺は、それが誇らしい。
それを目にできたことに歓喜している。
それでもなお。
いや、だからこそ。
そんなお前にどうしようもなく惹かれてしまう。
その身を縛る不自由さを、少しでも緩ませることができたなら。
そんなどうしようもなく、栓のないことを考えてしまうぐらいに、盲目になっている。
あぁ、ならば、ここは一つ。
賭けでもしてみようじゃないか。
それはこれ以上ないほどの大博打。
下手をすれば俺自身もただでは済まない、けれど得るものは大きな賭けを。
「なぁ。
もし、永遠の生に膿んでいるなら。
一つ、賭けに乗ってみないか」
成功するか、失敗するか。
正直にいえば上手いこといく自信はないし、これが正しいのだと盲目にもなれない。
けれど――試してみる価値はある。
俺のそんな心情を察したのか。
男は一つ頷くと、視線のみで先を促してきた。
「お前の、終わりなき真円の運命。
これを帯状にして、俺のものに巻きつければ。
運命とやらを、誤認させることができるんじゃないか?」
そうすべてを吐き出してみて、魔人を見れば。
この人、なにを言ってるのだろう。
まさしくそう言いたげな顔、片眉だけを跳ね上げた表情のまま、魔人は小首を傾げた。
あぁ、唐突に過ぎたか。
今までこの男から見聞きしたものや、俺の価値観というのだろうか。
そこから導き出したのだが、口に出したのはこれがはじめてなのだから、面食らうのもよくわかる。
それを反省し、改めての確認を言葉にする。
「少し、焦りすぎた。
確認というか、認識のすりあわせをしたいんだが」
そこで再度、魔人の目を見て尋ねれば、小さく頷いてみせる。
それに、ならばと持論を展開する。
「運命って、その人物……人間というのか、生き物というのか。
その存在の一から十まで、始まりから終わりまでを記した、一つの帯みたいなもの。
その認識であってるか?」
俺の問いに、魔人は再度、こくりと一つ頷いた。
それならばと更なる推測を確信に変えるべく、言葉を紡ぐ。
「普通は帯であるのなら、お前の運命は真円、輪になってるんじゃないか?
端と端が繋がって、終わりがないから、不死になっている。
だったら、端と端とをつかんで伸ばしてみれば。
折り重なる帯に見立てることができるんじゃないか?」
俺の推論に、紅の相貌が大きく見開かれる。
直径がどの程度あるかはわからないが、それでも理論上は可能なはずだ。
「それでいくと、さ。
君の運命をフランクフルトに、僕の運命をそれに巻きついてるパンに見立ててたりする?」
あぁ、それは確かに近い例えかもしれない。
パン部分がものすごく厚みがありそうだが、これなら。
頭頂から最後の切れ端部分まで、しっかりと重ね合わせれば。
俺が永遠の眠りへと旅立つとき。
お前もともに、眠りにつくことができるんじゃないかと、俺はそう思うのだ。
そのつもりで頷いてみれば、魔人は。
勢いよく息を吹き出して、大きく笑い声を上げた。
「それはなんとも罰当たりな。
けれど、君にしかできない発想だ!」
そうして再度、茶混じりの紅が強く瞬く。
内からあふれ出す激情のままに強く強く煌めいた。
「その話、ノった!
いい加減、長々とこの世に残り続けるのも飽いていたんだ。
だったらここらで一度、試してみるのも悪くない」
けれど一転して、勢いを落とし。
俺に視線をあわせ、静かに問いかけた。
「だけど、もし。
上手くいかなかった、そのときは。
――君も、ランプの魔人となり囚われる」
それでも、いいの?
そう、茶混じりの紅は問いかける。
あぁ、そんなこと。
そんなもので、俺が止まると。
そんな風に見くびられるのは、冗談ではない。
「そんなこと、起こらないって信じてる。
それに、もし仮に、そうなったとして」
そこで区切り、睨みつけるような鋭い眼光で以て、魔人を。
愛しい男を射抜き、言う。
「お前となら。
永劫をともにしたって、後悔しない」
だから、怖じることなくやってみろ。
そのつもりで手を差し伸べた。
骨張って太い俺の手を、細長い褐色の指先が握り締める。
魔人はそのまま立ち上がり、前を見据えた。
俺たちは背の高さが違う。
故に、目線の位置は違えど。
――見つめる先は、同じであると確信する。
「なら、遠慮なく。
やらせてもらおうか!」
そうして魔人は一歩、テーブルを背にして立ち、瞑目のち、俯いた。
小さく開いた口から、細く鋭く呼気を吐く。
開眼すると、見えない某か――。
二つの運命を、睨み据えた。
「これから、君の運命を軸に、僕の運命を薄く引き延ばして巻きつける。
過去にも干渉する難事だ。
正直、いままで一度もやったことがないから、成功するかもわからない」
けれど。
そこで、く、と顎を引き、一度だけ振り向いた。
ほんの少し子どもっぽく、悪戯げな顔で。
でもそこに揺るぎない自信を感じさせる、そんな笑みで以てこちらを見た。
「絶対、成功させる。
だから君は、そこで。
――見てて」
元からそのつもりだ。
俺はただ、ここで。
お前の最初で最後の勇姿を見届ける。
前に向き直った魔人は、肩幅程度に足を開き、両手を緩く開いて持ち上げた。
そうしてまず、鉤爪のように丸めた右手で以て、何かを掴みあげた。
そこに、“熱”を幻視する。
魔人の眉根が傷みで強く寄せられ、唇に歯が立てられる。
実際に――物理的な意味では、右手は何も掴んでいない。
けれど、見えない何かが確かにそこに在り、その高温で以て魔人の触れる指を焼いているのだと、そう理解する。
激痛が走っているのだろう。
魔人は時折、息を詰まらせながら、それでも一切怯むことなく両手で以て何かを引き延ばした。
ぐうと胸を開くようにして両手で広く空間を引き裂いて、それを何かに巻きつける。
その仕草に、いつもの軽やかさがない。
酷く重いものを、本来であれば両手で持たねばならないほどの重量があるものを、片手で扱っている。
だから時折、その重さに振り回されて身体が傾ぐ。
けれど一切、足裏が床を離れず、大きく屈伸をしたり、反転、背伸びをするように伸ばしたりして、ぐるぐると全身を使って何かを巻きつけている。
そのたびに、肌を焦がす熱量が上がっているような気がする。
いや、気のせいじゃない。
喉が焼けるかのように渇き上がり、滴る汗が米神を伝う。
その渦中にある魔人の額にはいくつもの大粒の汗が貼りつき、長いまつげに重そうな雫を作っている。
ばららららっと床に転がる雑誌が行きつ戻りつして中身を晒す。
髪が舞い上がり、服の裾から入り込んだ風が火照った身体を撫ぜていく。
魔人の細く長い三つ編みが風に煽られ、肩ほどまで舞い上がる。
音のない嘶きがわんわんと幾度も鼓膜を叩き、揺すりあげる。
再度、伸び上がる身体が肩で息をしているのに気付き、もどかしさに唇を噛む。
そうして見つめる傍ら、神様、と譫言のように魔人の唇が、音もなく呟いた。
「どうか、どうか。
この願いを、聞き届けて下さい」
そうして、一度、息を飲んで。
「この男と共に歩み、眠りにつける。
ただそれだけで、いいんです。
永遠の命なんて、いらない。
だから、どうか。
――この願いを、聞き届けて下さい」
この男の前身を象った神へ、祈るように願いを捧げる魔人を目に焼きつける。
そうして、最後。
ぎちりと音を立てるかのように、魔人はそれを巻き終えた。
魔人が瞑目したまましばし、時が流れる。
かたっ。
どこからか、硬いものが何かを叩く音が響き、瞬く間に連続した破砕音へと変わっていく。
音の鳴る方へと視線を向ければ、小棚の上で鈍金のランプが踊り狂うようにして、独りでにかたかたと揺れている。
次第に震えは大きく激しくなって、奏でられる悲鳴のような金属音もそれに合わせて絶叫のように響き渡る。
これ以上大きくなったら、鼓膜が破れるかもしれないほどの轟音となった瞬間、ぴたりと動きが止まると。
――きらきらと輝く粒子となって、端から解けるようにして崩れて消えた。
あ、と思わず零れた魔人の声で、硬直が解ける。
これは、もしかするともしかするんじゃないか。
「――消えた。
僕を取り巻いてた、運命の糸が、消えたっ!
違う、見えなくなったんだっ。
もう、もうっ。
僕を縛るものは、なにもない……っ!」
それは歓喜だった。
だけど、どこか寂しさも孕んでいた。
それもそうだ。
この男の長い長い道のりと共に歩んだ、あらゆるしがらみは。
たった一言で、言い表せるものではない。
どれほど疎んだとしても、それは男の一部だったのだから、欠片も残さず消えてしまえば、喪失感を覚えて然るべきなのだ。
柔らかな曲線を描く眦から、ぽろりと一粒の雫が転がり落ちて頬を濡らす。
後から後から流れ出るそれは、滂沱の涙となって男の顔を彩った。
「僕はっ……おかしいっ!
こんなにも、嬉しくてたまらないのに。
疎ましくて、仕方なかったのにっ!
なんで、こんなに遣る瀬ない気持ちになるのっ?
立ってられないくらいに寂しくて、苦しくてっ。
気が、狂いそうなの……!?」
くしゃりと髪を掻きむしり、涙で濡れた顔を歪めに歪めて放たれた慟哭は。
自らを構築していたもの、その支柱たるものを永劫に失ったことによる――魂を裂かれる叫びとなって迸った。
疎ましく感じていた。
けれど、自身を構築する柱でもあった、運命を視る目と、因果を紡ぎ手繰る手。
それにより支えられていた、ランプの魔人であるという自負。
叶えてきた願いと、託されてきた思い。
自分を置いて通り過ぎる数多の人々との記憶、幾多の出会いと別れ。
それらがない交ぜになり、作り上げられた自我は。
自ら望んで手放したにもかかわらず、削り取られた半身を求めてすすり泣いていた。
自由になったことを歓喜する心と、不自由ではあれど人の手に余る力を行使してきたという自尊心が、男の中で対立し混乱を呼び起こしている。
喉が枯れるほどの絶叫を放ち、紺墨の髪を振り乱して泣き喘ぐ男の姿を見ていられなくて、その身体をかき抱いた。
見る間に胸の辺りが熱い雫で濡れていく。
胸に押しつけるようにして頭を抱き寄せれば、ひぐひぐと喉を鳴らし溺れるようにして呼吸の苦しみに喘いでいる。
本当の意味で、この男の抱える苦悩を理解してやることはできない。
それでも、一人ではないのだと伝わるように、強く強く抱きしめた。
ごめんなさいと譫言のように繰り返す男の頭を、何度も撫でその額に口づける。
なぜ謝るのか、きっと男は理解してはいないだろう。
自由になれたことを素直に喜べなくて、申し訳ないと思う気持ち。
万能の権能を以て願いを叶える愉悦、その甘やかさを惜しんでしまった後ろめたさ。
もう残されることはないという、安堵。
素直によかったよかったと喜ぶには、それらは重く心を苛み傷つける。
それに涙する男には悪いが、俺にとってはそんな男の姿が喜ばしい。
己を道具と言い放ち、人を遠ざけ、一歩引いたところに立っていた男が、身も世もなく泣きじゃくる。
それだけの心を、未だ大事に有していたことが、嬉しくて仕方がなかった。
「泣けるだけ、泣け。
お前を責め苛むものは、もうどこにもないんだから」
わぁとまた大声をあげて泣きつかれ、あふれ出た涙を胸に擦りつけられる。
男の流したそれが、一人の人間がこぼすにはあまりにも多すぎて、布地の吸収力を超えて腹まで滴り落ちているのがわかる。
このままでは枯れ果ててしまうのではなかろうかと危惧するも、おそらく数百年。
下手をすれば、数千年分のたまりにたまったものだろうと思えば、好きなだけ泣かせてやりたかった。
男の秀でた額に、優しく思いを込めた口づけを落とす。
早く泣き止めばいい。
そうして、笑いかけてほしい。
世界は――こんなにも、優しい色をしている。
それをこの男と。
他でもないお前と、隣に並んで見ることのできる喜びを分かち合いたい。
ともに肩を並べて歩んでいきたい。
そう願いながら、またもう一度、その額へと唇を落とし。
――ただ、その時が来るのを待ち続けた。
一言一言が一粒の水滴となって、聞くものの鼓膜を、その先の心を打つような――そんな話し方で、魔人はずっと、話し続けた。
時折、唇を舌で湿らす。
それ以外に、他の音は一切しない。
淀むことも詰まることもなく、そうして最後まで語り終えた。
伏し目がちであった茶混じりの紅は、いま、静かな色を湛えて真っ直ぐと俺を映し出す。
俺の反応を、ただ待ち続けている。
目を閉じ、与えられた情報を反復する。
なぜ、今になってこのような話をしたのか。
気が向いたからか、俺だから良いと思ったのか。
わからないこともあれど、たった一つ。
わかるものがある。
これが最初で最後なのだと。
ここを逃せばおそらく、もう二度と、この扉は開かれないのだと。
故に、踏み込む。
「お前は。
……寂しく、なかったのか」
紺墨の眉根がきゅっと寄り、反して眉尻は深く下がる。
茶混じりの二つの紅は細められ、目頭はくぅと上がる。
口角は両端ともわななきながら下を向き、口蓋を細かに揺らしながら。
そうして叫びあげるように。
――どこまでも、真摯な慟哭を吐き出した。
「そんなのっ。
さみしいにっ、決まってるっ……じゃないかっ!」
先までが降りしきる雨粒であったなら。
これは、怒濤のごとく巌を貫く一筋の水針。
どこまでも深く、聞くものの胸を刺し貫く悲痛な叫び。
なぜこれで泣いていないのか、不思議になるほど、それは水気を孕んでいた。
けれど、その瞳が。
燃え上がる焔のように、茶混じりの紅が強く瞬く。
「それでも、これが。
これが、僕の選んだ道だ。
死にたくないからといえど。
これが、僕が選んだ道なんだ」
あぁ、その煌めきのなんと眩いことか。
夜空駆けゆく流星のごとく、闇夜切り裂く彗星のごとく、見るものの網膜を、その奥の脳髄すら焼き尽くす。
逸れず、ぶれず、揺らぐことなく真っ直ぐに、意思を貫くことの――なんと難しいことか。
それをこの男は、何千年と前から燻ることなくやってきた。
肌がさざめく。
肌だけでなく、身体が震える。
芯の芯まで震えているのは身体だけではなく、心の奥からこの男に感嘆しているから。
揺らめく陽炎すら幻視できるほどに、眼前は燃え上がっている。
それを目に焼きつけることができた。
その喜びが、誇らしさが、心身の隅から隅まで走り抜ける。
あぁ、なんとしたたかなことか。
再度、同じように思う。
孤独の夜は確かに、この男を、その魂を強く苛んだのだろう。
だがそれを毒とせず。
毒だけにせず、自身を磨き上げる研磨剤とした。
より鋭く、細く、折れることのない、針のように鋭敏な一つの刃と成したのだ。
それが今、垣間見えている。
故に、下手な同情ではなく、安易な慰めでもなく。
口にするのは、これこそが相応しい。
「お前は、強い。
誰よりもなによりも、不自由なのに。
それをものともせず、揺らぐことなく立ち続ける」
俺は、それが誇らしい。
それを目にできたことに歓喜している。
それでもなお。
いや、だからこそ。
そんなお前にどうしようもなく惹かれてしまう。
その身を縛る不自由さを、少しでも緩ませることができたなら。
そんなどうしようもなく、栓のないことを考えてしまうぐらいに、盲目になっている。
あぁ、ならば、ここは一つ。
賭けでもしてみようじゃないか。
それはこれ以上ないほどの大博打。
下手をすれば俺自身もただでは済まない、けれど得るものは大きな賭けを。
「なぁ。
もし、永遠の生に膿んでいるなら。
一つ、賭けに乗ってみないか」
成功するか、失敗するか。
正直にいえば上手いこといく自信はないし、これが正しいのだと盲目にもなれない。
けれど――試してみる価値はある。
俺のそんな心情を察したのか。
男は一つ頷くと、視線のみで先を促してきた。
「お前の、終わりなき真円の運命。
これを帯状にして、俺のものに巻きつければ。
運命とやらを、誤認させることができるんじゃないか?」
そうすべてを吐き出してみて、魔人を見れば。
この人、なにを言ってるのだろう。
まさしくそう言いたげな顔、片眉だけを跳ね上げた表情のまま、魔人は小首を傾げた。
あぁ、唐突に過ぎたか。
今までこの男から見聞きしたものや、俺の価値観というのだろうか。
そこから導き出したのだが、口に出したのはこれがはじめてなのだから、面食らうのもよくわかる。
それを反省し、改めての確認を言葉にする。
「少し、焦りすぎた。
確認というか、認識のすりあわせをしたいんだが」
そこで再度、魔人の目を見て尋ねれば、小さく頷いてみせる。
それに、ならばと持論を展開する。
「運命って、その人物……人間というのか、生き物というのか。
その存在の一から十まで、始まりから終わりまでを記した、一つの帯みたいなもの。
その認識であってるか?」
俺の問いに、魔人は再度、こくりと一つ頷いた。
それならばと更なる推測を確信に変えるべく、言葉を紡ぐ。
「普通は帯であるのなら、お前の運命は真円、輪になってるんじゃないか?
端と端が繋がって、終わりがないから、不死になっている。
だったら、端と端とをつかんで伸ばしてみれば。
折り重なる帯に見立てることができるんじゃないか?」
俺の推論に、紅の相貌が大きく見開かれる。
直径がどの程度あるかはわからないが、それでも理論上は可能なはずだ。
「それでいくと、さ。
君の運命をフランクフルトに、僕の運命をそれに巻きついてるパンに見立ててたりする?」
あぁ、それは確かに近い例えかもしれない。
パン部分がものすごく厚みがありそうだが、これなら。
頭頂から最後の切れ端部分まで、しっかりと重ね合わせれば。
俺が永遠の眠りへと旅立つとき。
お前もともに、眠りにつくことができるんじゃないかと、俺はそう思うのだ。
そのつもりで頷いてみれば、魔人は。
勢いよく息を吹き出して、大きく笑い声を上げた。
「それはなんとも罰当たりな。
けれど、君にしかできない発想だ!」
そうして再度、茶混じりの紅が強く瞬く。
内からあふれ出す激情のままに強く強く煌めいた。
「その話、ノった!
いい加減、長々とこの世に残り続けるのも飽いていたんだ。
だったらここらで一度、試してみるのも悪くない」
けれど一転して、勢いを落とし。
俺に視線をあわせ、静かに問いかけた。
「だけど、もし。
上手くいかなかった、そのときは。
――君も、ランプの魔人となり囚われる」
それでも、いいの?
そう、茶混じりの紅は問いかける。
あぁ、そんなこと。
そんなもので、俺が止まると。
そんな風に見くびられるのは、冗談ではない。
「そんなこと、起こらないって信じてる。
それに、もし仮に、そうなったとして」
そこで区切り、睨みつけるような鋭い眼光で以て、魔人を。
愛しい男を射抜き、言う。
「お前となら。
永劫をともにしたって、後悔しない」
だから、怖じることなくやってみろ。
そのつもりで手を差し伸べた。
骨張って太い俺の手を、細長い褐色の指先が握り締める。
魔人はそのまま立ち上がり、前を見据えた。
俺たちは背の高さが違う。
故に、目線の位置は違えど。
――見つめる先は、同じであると確信する。
「なら、遠慮なく。
やらせてもらおうか!」
そうして魔人は一歩、テーブルを背にして立ち、瞑目のち、俯いた。
小さく開いた口から、細く鋭く呼気を吐く。
開眼すると、見えない某か――。
二つの運命を、睨み据えた。
「これから、君の運命を軸に、僕の運命を薄く引き延ばして巻きつける。
過去にも干渉する難事だ。
正直、いままで一度もやったことがないから、成功するかもわからない」
けれど。
そこで、く、と顎を引き、一度だけ振り向いた。
ほんの少し子どもっぽく、悪戯げな顔で。
でもそこに揺るぎない自信を感じさせる、そんな笑みで以てこちらを見た。
「絶対、成功させる。
だから君は、そこで。
――見てて」
元からそのつもりだ。
俺はただ、ここで。
お前の最初で最後の勇姿を見届ける。
前に向き直った魔人は、肩幅程度に足を開き、両手を緩く開いて持ち上げた。
そうしてまず、鉤爪のように丸めた右手で以て、何かを掴みあげた。
そこに、“熱”を幻視する。
魔人の眉根が傷みで強く寄せられ、唇に歯が立てられる。
実際に――物理的な意味では、右手は何も掴んでいない。
けれど、見えない何かが確かにそこに在り、その高温で以て魔人の触れる指を焼いているのだと、そう理解する。
激痛が走っているのだろう。
魔人は時折、息を詰まらせながら、それでも一切怯むことなく両手で以て何かを引き延ばした。
ぐうと胸を開くようにして両手で広く空間を引き裂いて、それを何かに巻きつける。
その仕草に、いつもの軽やかさがない。
酷く重いものを、本来であれば両手で持たねばならないほどの重量があるものを、片手で扱っている。
だから時折、その重さに振り回されて身体が傾ぐ。
けれど一切、足裏が床を離れず、大きく屈伸をしたり、反転、背伸びをするように伸ばしたりして、ぐるぐると全身を使って何かを巻きつけている。
そのたびに、肌を焦がす熱量が上がっているような気がする。
いや、気のせいじゃない。
喉が焼けるかのように渇き上がり、滴る汗が米神を伝う。
その渦中にある魔人の額にはいくつもの大粒の汗が貼りつき、長いまつげに重そうな雫を作っている。
ばららららっと床に転がる雑誌が行きつ戻りつして中身を晒す。
髪が舞い上がり、服の裾から入り込んだ風が火照った身体を撫ぜていく。
魔人の細く長い三つ編みが風に煽られ、肩ほどまで舞い上がる。
音のない嘶きがわんわんと幾度も鼓膜を叩き、揺すりあげる。
再度、伸び上がる身体が肩で息をしているのに気付き、もどかしさに唇を噛む。
そうして見つめる傍ら、神様、と譫言のように魔人の唇が、音もなく呟いた。
「どうか、どうか。
この願いを、聞き届けて下さい」
そうして、一度、息を飲んで。
「この男と共に歩み、眠りにつける。
ただそれだけで、いいんです。
永遠の命なんて、いらない。
だから、どうか。
――この願いを、聞き届けて下さい」
この男の前身を象った神へ、祈るように願いを捧げる魔人を目に焼きつける。
そうして、最後。
ぎちりと音を立てるかのように、魔人はそれを巻き終えた。
魔人が瞑目したまましばし、時が流れる。
かたっ。
どこからか、硬いものが何かを叩く音が響き、瞬く間に連続した破砕音へと変わっていく。
音の鳴る方へと視線を向ければ、小棚の上で鈍金のランプが踊り狂うようにして、独りでにかたかたと揺れている。
次第に震えは大きく激しくなって、奏でられる悲鳴のような金属音もそれに合わせて絶叫のように響き渡る。
これ以上大きくなったら、鼓膜が破れるかもしれないほどの轟音となった瞬間、ぴたりと動きが止まると。
――きらきらと輝く粒子となって、端から解けるようにして崩れて消えた。
あ、と思わず零れた魔人の声で、硬直が解ける。
これは、もしかするともしかするんじゃないか。
「――消えた。
僕を取り巻いてた、運命の糸が、消えたっ!
違う、見えなくなったんだっ。
もう、もうっ。
僕を縛るものは、なにもない……っ!」
それは歓喜だった。
だけど、どこか寂しさも孕んでいた。
それもそうだ。
この男の長い長い道のりと共に歩んだ、あらゆるしがらみは。
たった一言で、言い表せるものではない。
どれほど疎んだとしても、それは男の一部だったのだから、欠片も残さず消えてしまえば、喪失感を覚えて然るべきなのだ。
柔らかな曲線を描く眦から、ぽろりと一粒の雫が転がり落ちて頬を濡らす。
後から後から流れ出るそれは、滂沱の涙となって男の顔を彩った。
「僕はっ……おかしいっ!
こんなにも、嬉しくてたまらないのに。
疎ましくて、仕方なかったのにっ!
なんで、こんなに遣る瀬ない気持ちになるのっ?
立ってられないくらいに寂しくて、苦しくてっ。
気が、狂いそうなの……!?」
くしゃりと髪を掻きむしり、涙で濡れた顔を歪めに歪めて放たれた慟哭は。
自らを構築していたもの、その支柱たるものを永劫に失ったことによる――魂を裂かれる叫びとなって迸った。
疎ましく感じていた。
けれど、自身を構築する柱でもあった、運命を視る目と、因果を紡ぎ手繰る手。
それにより支えられていた、ランプの魔人であるという自負。
叶えてきた願いと、託されてきた思い。
自分を置いて通り過ぎる数多の人々との記憶、幾多の出会いと別れ。
それらがない交ぜになり、作り上げられた自我は。
自ら望んで手放したにもかかわらず、削り取られた半身を求めてすすり泣いていた。
自由になったことを歓喜する心と、不自由ではあれど人の手に余る力を行使してきたという自尊心が、男の中で対立し混乱を呼び起こしている。
喉が枯れるほどの絶叫を放ち、紺墨の髪を振り乱して泣き喘ぐ男の姿を見ていられなくて、その身体をかき抱いた。
見る間に胸の辺りが熱い雫で濡れていく。
胸に押しつけるようにして頭を抱き寄せれば、ひぐひぐと喉を鳴らし溺れるようにして呼吸の苦しみに喘いでいる。
本当の意味で、この男の抱える苦悩を理解してやることはできない。
それでも、一人ではないのだと伝わるように、強く強く抱きしめた。
ごめんなさいと譫言のように繰り返す男の頭を、何度も撫でその額に口づける。
なぜ謝るのか、きっと男は理解してはいないだろう。
自由になれたことを素直に喜べなくて、申し訳ないと思う気持ち。
万能の権能を以て願いを叶える愉悦、その甘やかさを惜しんでしまった後ろめたさ。
もう残されることはないという、安堵。
素直によかったよかったと喜ぶには、それらは重く心を苛み傷つける。
それに涙する男には悪いが、俺にとってはそんな男の姿が喜ばしい。
己を道具と言い放ち、人を遠ざけ、一歩引いたところに立っていた男が、身も世もなく泣きじゃくる。
それだけの心を、未だ大事に有していたことが、嬉しくて仕方がなかった。
「泣けるだけ、泣け。
お前を責め苛むものは、もうどこにもないんだから」
わぁとまた大声をあげて泣きつかれ、あふれ出た涙を胸に擦りつけられる。
男の流したそれが、一人の人間がこぼすにはあまりにも多すぎて、布地の吸収力を超えて腹まで滴り落ちているのがわかる。
このままでは枯れ果ててしまうのではなかろうかと危惧するも、おそらく数百年。
下手をすれば、数千年分のたまりにたまったものだろうと思えば、好きなだけ泣かせてやりたかった。
男の秀でた額に、優しく思いを込めた口づけを落とす。
早く泣き止めばいい。
そうして、笑いかけてほしい。
世界は――こんなにも、優しい色をしている。
それをこの男と。
他でもないお前と、隣に並んで見ることのできる喜びを分かち合いたい。
ともに肩を並べて歩んでいきたい。
そう願いながら、またもう一度、その額へと唇を落とし。
――ただ、その時が来るのを待ち続けた。
0
あなたにおすすめの小説


執着
紅林
BL
聖緋帝国の華族、瀬川凛は引っ込み思案で特に目立つこともない平凡な伯爵家の三男坊。だが、彼の婚約者は違った。帝室の血を引く高貴な公爵家の生まれであり帝国陸軍の将校として目覚しい活躍をしている男だった。

夫と息子に邪険にされたので王太子妃の座を譲ります~死に戻ってから溺愛されても今更遅い
青の雀
恋愛
夫婦喧嘩の末に置き去りにされた妻は、旦那が若い愛人とイチャついている間に盗賊に襲われ、命を落とした。
神様の温情により、10日間だけこの世に戻った妻と護衛の騎士は、その10日間の間に心残りを処分する。それは、娘の行く末と……もし、来世があるならば、今度は政略といえども夫以外の人の妻になるということ。
もう二度と夫と出会いたくない彼女は、彼女を蔑ろにしてきた息子とも縁を切ることを決意する。
生まれかわった妻は、新しい人生を強く生きることを決意。
過去世と同じ轍を踏みたくない……


王様の恋
うりぼう
BL
「惚れ薬は手に入るか?」
突然王に言われた一言。
王は惚れ薬を使ってでも手に入れたい人間がいるらしい。
ずっと王を見つめてきた幼馴染の側近と王の話。
※エセ王国
※エセファンタジー
※惚れ薬
※異世界トリップ表現が少しあります

鎖に繋がれた騎士は、敵国で皇帝の愛に囚われる
結衣可
BL
戦場で捕らえられた若き騎士エリアスは、牢に繋がれながらも誇りを折らず、帝国の皇帝オルフェンの瞳を惹きつける。
冷酷と畏怖で人を遠ざけてきた皇帝は、彼を望み、夜ごと逢瀬を重ねていく。
憎しみと抗いのはずが、いつしか芽生える心の揺らぎ。
誇り高き騎士が囚われたのは、冷徹な皇帝の愛。
鎖に繋がれた誇りと、独占欲に満ちた溺愛の行方は――。

声なき王子は素性不明の猟師に恋をする
石月煤子
BL
第一王子である腹違いの兄から命を狙われた、妾の子である庶子のロスティア。
毒薬によって声を失った彼は城から逃げ延び、雪原に倒れていたところを、猟師と狼によって助けられた。
「王冠はあんたに相応しい。王子」
貴方のそばで生きられたら。
それ以上の幸福なんて、きっと、ない。
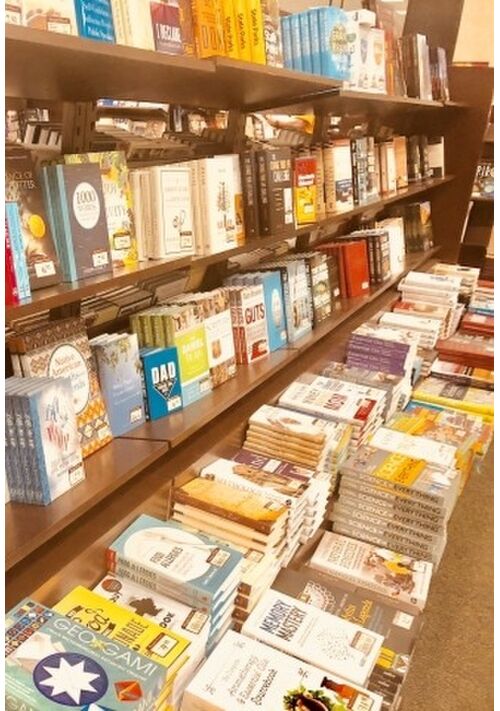
【完結】言えない言葉
未希かずは(Miki)
BL
双子の弟・水瀬碧依は、明るい兄・翼と比べられ、自信がない引っ込み思案な大学生。
同じゼミの気さくで眩しい如月大和に密かに恋するが、話しかける勇気はない。
ある日、碧依は兄になりすまし、本屋のバイトで大和に近づく大胆な計画を立てる。
兄の笑顔で大和と心を通わせる碧依だが、嘘の自分に葛藤し……。
すれ違いを経て本当の想いを伝える、切なく甘い青春BLストーリー。
第1回青春BLカップ参加作品です。
1章 「出会い」が長くなってしまったので、前後編に分けました。
2章、3章も長くなってしまって、分けました。碧依の恋心を丁寧に書き直しました。(2025/9/2 18:40)
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















