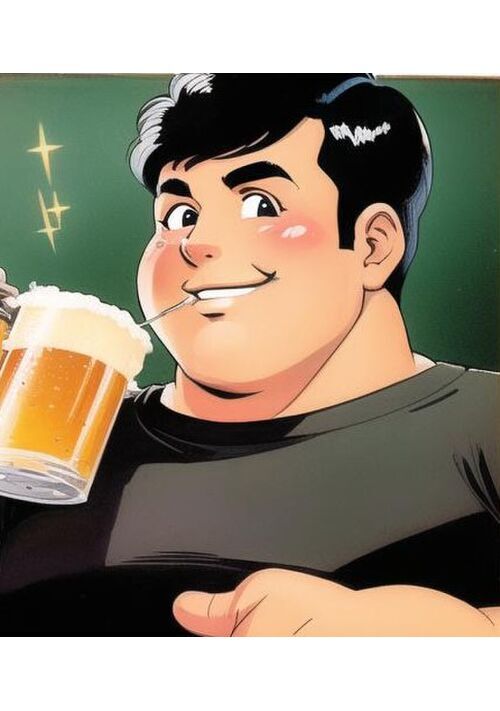2 / 9
特別じゃない贈り物
1
しおりを挟む
年明けの寒さが一層厳しくなってきた今日この頃。俺の職場である城下町の食堂は、いつもに増して混雑していた。
「セディ、ぼやぼやしてるな! これ7番テーブル!」
「はいっ、ただ今!」
厨房に続くカウンターから無造作に手渡されたのは、湯気の立つオニオンスープが入った深皿と、焼きたての骨付き肉が乗った鉄板の皿だ。
(くっそ重てぇ……)
料理を乗せたトレーの両端をしっかり握りしめ、慎重な足取りで指定のテーブルを目指す。もうかれこれ何往復しただろうか……運んでも運んでもきりが無いほど注文が殺到するのは、店のオーナーにとっては売上が伸びてさぞ喜ばしいことだろう。
(まあだからって俺たち下働きの給料が上がるわけじゃないけど)
さいきん厨房の手伝いだけでなく、フロアに出るようになった。日が暮れた一番混雑する時間帯になると、出来上がった料理をせっせとテーブルまで運ぶ。
運んでいる料理は見るからにうまそうで、存分に目を楽しませてくれるが、テーブルへ運ぶ作業は正直きつくてげんなりする。オーブンから出したての鉄板に乗ったステーキは、うっかり皿の端に触れると火傷するし、熱々のスープをなみなみ注いだ深皿は、ステーキと併せてかなりの重さだ。
(くそっ、半分食って軽くしちゃえたらなぁ)
そんなことを心の中でぼやきながら運んでいたら、奥のテーブルに着く見知った顔に気づいた。
(あれ、店に来るなんてめずらしいな……)
四人がけのテーブル席に着いたのは、バルテレミー第五部隊の隊長ベルンハルト・アーベルだった。第五部隊は市井の警備や治安を担当し、不法労働にも目を光らせている。
俺は去年の秋ごろからアーベルに目をつけられていて、ことあるごとにつかまっては説教を受けていた。要するに俺にとっては面倒でやかましい、非常に厄介な存在だ……。
アーベルは、同じ制服姿の同僚らしき男たちと一緒に料理を囲み、いつもよりリラックスした様子で、相手の話に相槌を打ちながら食事をしていた。銀色の髪に端正な横顔は、俺の前ではいつも気難しそうなしかめ面なのに、今は仲間と食事しているせいか表情はやわらかく、ときおり笑顔すら浮かべている。
(一応あいさつぐらい、しといたほうがいいのかな?)
とは思いつつも、注文が次から次へと入るから、運ぶ手を止めることができない。途中一度だけ、アーベルと目が合った気がしたが、そのとき三つの料理を同時に運んでいた為、自分の手元から目を離すわけにはいかなかった。
実は年末の仕事帰り、アパートまで送ってくれたアーベルからマフラーを渡されのだ。自分としては、成り行き上借りただけで、あとから返すつもりだったのだが、次に会った時には、彼はすでに新しいマフラーを身につけていて『それはもういらないから、使うも捨てるも好きにするがいい』と素っ気なく言われた。
もちろん、捨てるなんてもったいないことはせず、ありがたく使わせてもらっている。
(それに、泊まらせてもらったお礼もまだだったな)
その上、年末から新年にかけて、第五部隊の事務所に泊まらせてもらった。
本当は事務所ではなく、アーベルの屋敷に連れてかれるはずだった。しかし繁華街で酔っ払いによる傷害事件が発生し、年末年始で人手が足りない中、隊長であるアーベルも現場へ向かうことになった為、当初の予定を変更せざるを得なかった。
事情を知った俺は、そういう事ならと自宅へ引き返そうとしたが、アーベルに『こちらの方が近い』からと、半ば強引に第五部隊の事務所へ連れていかれ、けっきょくそこに一晩泊まらせてもらった。
後日アーベルからは、なぜか謝罪の手紙が届いた。あの夜の件を気にしているようだったが、俺にしてみればタダで事務所に泊まらせてもらったので、感謝こそすれ不満はない。しかも夜食だと振舞われたコーヒーとサンドウィッチはうまかった上、案内された宿直用の仮眠室は温かく、厚手の毛布に包まって、久しぶりにぐっすりと眠ることができた。
(そういやマフラー返し損ねた時から、ずっと会ってないな……いや、今そこのテーブルにいるけどさ)
年明けは、城下町ではイベントも多いし、きっと忙しいに違いない。
しかも来週は新年を祝う、大規模なパレードが催される予定だ。城下町はお祭り騒ぎになるから、第五部隊は警備などで、さぞや忙しいだろう。ちなみにうちの店も例年通り祭りに出店する予定で、俺も少しだけ手伝いをすることになってる。
「セディ、このスープは二番、こっちのデザートを八番テーブル!」
「はいっ……あ、そうだ。あとデザート四つお願いします」
「追加注文か?」
「いえ、俺からです。知り合いが来てるんで。給料から引いといてください」
従業員は、家族や知り合いが来店した時、ツケで追加注文して、後日給料から天引きしてもらうことができる。金額も従業員価格で割安となるから利用者が多いが、俺が利用するのは初めてだ。
「ほらよ、サービスしといたぞ」
「ありがとうございます!」
俺はほくほくしながら、心持ち多めに盛られたデザート四人前をトレーにのせ、アーベルたちの席へ向かった。
「セディウス・ゾルガー……!」
いち早く気づいたアーベルは席から立ち上がると、俺の抱えているトレーに手を伸ばした。
「すいません、お客さんなのに手伝ってもらっちゃって」
「いや、それはかまわないが……これは注文していないぞ?」
テーブルに並べたプディングに、アーベルは眉をひそめた。
「俺からのサービスです! ここのチョコレートプディングは人気なんで、ぜひ食べてみてください」
「えっ、おい……」
「あと改めて、年末はお世話になりました。夜食を振舞ってくれた事務所の人たちにも、よろしくお伝えください。じゃ、俺まだ仕事ありますんで!」
まだ何か言いたそうなアーベルをその場に残し、俺はテーブルから逃げるように厨房へ戻った。そろそろ皿洗いの手伝いをする時間だから、奥へ引っ込むにはちょうどいい。
(ふふ、驚いてたな)
泡のついたスポンジで皿を洗いながら、俺はいたずらが成功した子どもみたいにクスクスと笑った。
深夜になって日付の変わる頃。
厨房の裏口から外に出ると、久しぶりにアーベルの姿があった。
「……またかよ」
「それはこちらの台詞だ、セディウス・ゾルガー」
いつものように『まだこんな遅くまで仕事してるのか』とひと通り説教され、有無を言わさず家まで送ってもらう事になった。
アーベルは、これまたいつものように、半歩後ろから追うようについてくる。道すがら話すことは途切れ途切れで、とりとめもなく、はずむ話題もなく、面白くもないが気まずくもない、なんとも言えない空気が漂っていた。
「……ところで、あのプディングだが」
その言葉に振り返ったが、なぜかアーベルは視線を合わせようとしない。
「人気があるって、本当か?」
「本当かって?」
何を言いたいのか分からず、ただ言われた言葉を繰り返したら、次に耳を疑うような事を言われた。
「プディングなら、もっとうまいのを食べたことがある」
「は?」
アーベルは相変わらず視線を合わせようとせず、まっすぐ前を向いている。俺は困惑しながらも、恐る恐る口を開いた。
「俺はうちの店の味、けっこう好きなんだけど……」
「お前が、好きなだけか?」
「いや、俺だけじゃなくってさ、ホントあのプディングは人気なんだよ。毎日いっぱい注文入るから、閉店前には完売しちゃうこともしょっちゅうだぜ?」
「……そうか」
(なんだよ、その嫌味な言い方……気分わりぃ)
それきり俺は口を閉ざすと、心持ち歩調を早めた。とっとと家に帰ってふて寝したい。
しばらくお互い無言で歩いていたが、あとひとつ角を曲がれば家に着く、というタイミングでアーベルが沈黙を破った。
「では、他の物と比べたことあるのか」
最初、何の事を言われたのか分からなかった。だがアーベルはしつこく、今度ははっきりと別の言い方で質問を繰り返した。
「他のプディングと比べたことがあるのか」
俺は仕方なく、ない、と正直にこたえた。
「では、比較のしようがないだろう」
「……」
一体何を言いたいのだろう。話の着地点が見えず、無言のまま早足で歩き続け、ようやく自宅アパートが見えた時はホッとした。
扉の前で、ポケットの中にあるはずの鍵を探っていると、なぜか後ろに立って待っているアーベルが唐突に話題を変えた。
「次の休みはいつだ」
「……なんであんたに、そんなこと教えなきゃいけないんだよ」
また労働時間がどうのとか同じ説教を繰り返すのかと、うんざりして言い返すと、アーベルは腕を組んだまま気難しい表情を浮かべた。
「……労働基準に従って、きちんと休日を取っているのか確認したいからだ」
「あっそ。あさってだよ」
俺は口ごたえする気も失せ、そっけなくそう答えると、玄関の扉をやや乱暴に開けた。そのまま振り返らずに中へ入ろうとしたところ、背中から大きな声が響いて、文字通り飛び上がった。
「では、あさっての正午に迎えに来るからな」
「急に大声出すなよ、びっくりするだろ! それに迎えに来るって、どういうつもりだよ」
「比較してもらう。もっとうまいプディングを食べてもらう」
ここでどうしてプディングが出て来るのだろう。困惑する俺に対し、アーベルはいつもの冷たい事務的な口調で淡々と続けた。
「明後日の正午、馬車で迎えに来る。時間になったら玄関まで降りてくるように。二時間程度で帰宅できるよう、帰りの馬車も手配しておく」
「ちょっと待て、なに勝手に話を進めてんだよ」
「二時間では不満か。では一時間半、いや一時間以内に終わるようにする」
「そういう問題じゃなくって……ああ、もう! わかったよ、正午だな?」
半分やけになって怒鳴るように承諾すると、アーベルは少し驚いたように瞬きをし、それからフワリと微笑んだので、俺は腰を抜かしそうになった。
「……アーベルさんってさ……」
「なんだ」
「いや、やっぱいい」
「そうか?」
何となく気まずいまま、手袋の指先を弄んでいると、黒い手袋の指先が伸びてきたので、あわてて両手を背中に隠した。
「な、なんだよ?」
「いや……寒いのか」
「別に。ちょっとあかぎれが、かゆくなっただけだよ」
「あかぎれ?」
毎日長時間皿洗いすれば、両手があかぎれだらけになって当然で、いわば職業病みたいなもんだ。特に冬場は水が冷たく、空気が乾燥しているから、一年でもっともひどい有様となる。夜シャワーを浴びる時など、ぬるま湯すら染みて地味につらい。
「手を見せてみろ」
「な、なんでだよ……やだよ」
「いいから見せろ」
強引に手を取られ、穴のあいた手袋を外されてしまった。冷たい外気がひび割れた皮膚に突き刺さり、俺は痛みを堪える為、ぐっと奥歯を噛みしめる。
「こんなになるまで、なぜ放っておいてたんだ……」
アーベルの息を飲む様子に、なんともばつの悪い思いでそっぽを向いた。
「こんなの普通だって。水仕事してんだから当たり前だよ」
「だが、ここまで悪化する前に、医者に見せるべきだ」
「医者って……あかぎれ程度で何言ってんの?」
俺はわり本気だったが、アーベルはえらい剣幕で怒り出した。
「ふざけるな! これは普通のあかぎれではない、とうに怪我の域に達してる!」
「お、おい、夜中なのに、近所迷惑だろ」
アーベルは俺の手首をつかんだまま、何か堪えるような表情でうつむいた。
「アーベルさん……そんな心配すんなよ」
「……」
「これ、見た目ほどひどくないんだ」
「駄目だ。耐えられるはずがない……絶対に」
「いや、慣れちゃえばたいして痛くも……うわっ」
アーベルは俺の手をつかんだまま、引きずるようにして玄関から通りへと逆戻りし始めた。
「ちょ、どこ行くんだよ!? もう夜中だってば……俺、早く帰って寝たいんだよ、明日も仕事なんだからさ」
強引に歩かされ、足をもつれさせながらも必死に抗議をした。するとアーベルはとんでもないことを言い出した。
「今夜はこのままうちの屋敷へ連れていく。間に合わせでも、なにか薬があるはずだ。明日は朝一番で医者にみせる」
「はあ!? だから明日も仕事あるんだってば! 勝手に休めないし、休むと給料から差っ引かれるし、困るよ!」
「店には、私から連絡を入れておく。明日の分の給金は、私が支払えば文句ないだろう?」
その勝手で傲慢な物言いに、俺はついカッとなって乱暴に手を振りほどいた。
「なんだよそれ、ふざけんじゃねーよ!」
対峙するアーベルの強い視線が、容赦なく突き刺さる。だが俺も負けてはいなかった。
「なんでも自分の思い通りになると思うなよ!」
そんな捨て台詞を残して踵を返すと、俺は振り返らずに玄関に飛び込むと、一気に階段を駆け上がった。
「セディ、ぼやぼやしてるな! これ7番テーブル!」
「はいっ、ただ今!」
厨房に続くカウンターから無造作に手渡されたのは、湯気の立つオニオンスープが入った深皿と、焼きたての骨付き肉が乗った鉄板の皿だ。
(くっそ重てぇ……)
料理を乗せたトレーの両端をしっかり握りしめ、慎重な足取りで指定のテーブルを目指す。もうかれこれ何往復しただろうか……運んでも運んでもきりが無いほど注文が殺到するのは、店のオーナーにとっては売上が伸びてさぞ喜ばしいことだろう。
(まあだからって俺たち下働きの給料が上がるわけじゃないけど)
さいきん厨房の手伝いだけでなく、フロアに出るようになった。日が暮れた一番混雑する時間帯になると、出来上がった料理をせっせとテーブルまで運ぶ。
運んでいる料理は見るからにうまそうで、存分に目を楽しませてくれるが、テーブルへ運ぶ作業は正直きつくてげんなりする。オーブンから出したての鉄板に乗ったステーキは、うっかり皿の端に触れると火傷するし、熱々のスープをなみなみ注いだ深皿は、ステーキと併せてかなりの重さだ。
(くそっ、半分食って軽くしちゃえたらなぁ)
そんなことを心の中でぼやきながら運んでいたら、奥のテーブルに着く見知った顔に気づいた。
(あれ、店に来るなんてめずらしいな……)
四人がけのテーブル席に着いたのは、バルテレミー第五部隊の隊長ベルンハルト・アーベルだった。第五部隊は市井の警備や治安を担当し、不法労働にも目を光らせている。
俺は去年の秋ごろからアーベルに目をつけられていて、ことあるごとにつかまっては説教を受けていた。要するに俺にとっては面倒でやかましい、非常に厄介な存在だ……。
アーベルは、同じ制服姿の同僚らしき男たちと一緒に料理を囲み、いつもよりリラックスした様子で、相手の話に相槌を打ちながら食事をしていた。銀色の髪に端正な横顔は、俺の前ではいつも気難しそうなしかめ面なのに、今は仲間と食事しているせいか表情はやわらかく、ときおり笑顔すら浮かべている。
(一応あいさつぐらい、しといたほうがいいのかな?)
とは思いつつも、注文が次から次へと入るから、運ぶ手を止めることができない。途中一度だけ、アーベルと目が合った気がしたが、そのとき三つの料理を同時に運んでいた為、自分の手元から目を離すわけにはいかなかった。
実は年末の仕事帰り、アパートまで送ってくれたアーベルからマフラーを渡されのだ。自分としては、成り行き上借りただけで、あとから返すつもりだったのだが、次に会った時には、彼はすでに新しいマフラーを身につけていて『それはもういらないから、使うも捨てるも好きにするがいい』と素っ気なく言われた。
もちろん、捨てるなんてもったいないことはせず、ありがたく使わせてもらっている。
(それに、泊まらせてもらったお礼もまだだったな)
その上、年末から新年にかけて、第五部隊の事務所に泊まらせてもらった。
本当は事務所ではなく、アーベルの屋敷に連れてかれるはずだった。しかし繁華街で酔っ払いによる傷害事件が発生し、年末年始で人手が足りない中、隊長であるアーベルも現場へ向かうことになった為、当初の予定を変更せざるを得なかった。
事情を知った俺は、そういう事ならと自宅へ引き返そうとしたが、アーベルに『こちらの方が近い』からと、半ば強引に第五部隊の事務所へ連れていかれ、けっきょくそこに一晩泊まらせてもらった。
後日アーベルからは、なぜか謝罪の手紙が届いた。あの夜の件を気にしているようだったが、俺にしてみればタダで事務所に泊まらせてもらったので、感謝こそすれ不満はない。しかも夜食だと振舞われたコーヒーとサンドウィッチはうまかった上、案内された宿直用の仮眠室は温かく、厚手の毛布に包まって、久しぶりにぐっすりと眠ることができた。
(そういやマフラー返し損ねた時から、ずっと会ってないな……いや、今そこのテーブルにいるけどさ)
年明けは、城下町ではイベントも多いし、きっと忙しいに違いない。
しかも来週は新年を祝う、大規模なパレードが催される予定だ。城下町はお祭り騒ぎになるから、第五部隊は警備などで、さぞや忙しいだろう。ちなみにうちの店も例年通り祭りに出店する予定で、俺も少しだけ手伝いをすることになってる。
「セディ、このスープは二番、こっちのデザートを八番テーブル!」
「はいっ……あ、そうだ。あとデザート四つお願いします」
「追加注文か?」
「いえ、俺からです。知り合いが来てるんで。給料から引いといてください」
従業員は、家族や知り合いが来店した時、ツケで追加注文して、後日給料から天引きしてもらうことができる。金額も従業員価格で割安となるから利用者が多いが、俺が利用するのは初めてだ。
「ほらよ、サービスしといたぞ」
「ありがとうございます!」
俺はほくほくしながら、心持ち多めに盛られたデザート四人前をトレーにのせ、アーベルたちの席へ向かった。
「セディウス・ゾルガー……!」
いち早く気づいたアーベルは席から立ち上がると、俺の抱えているトレーに手を伸ばした。
「すいません、お客さんなのに手伝ってもらっちゃって」
「いや、それはかまわないが……これは注文していないぞ?」
テーブルに並べたプディングに、アーベルは眉をひそめた。
「俺からのサービスです! ここのチョコレートプディングは人気なんで、ぜひ食べてみてください」
「えっ、おい……」
「あと改めて、年末はお世話になりました。夜食を振舞ってくれた事務所の人たちにも、よろしくお伝えください。じゃ、俺まだ仕事ありますんで!」
まだ何か言いたそうなアーベルをその場に残し、俺はテーブルから逃げるように厨房へ戻った。そろそろ皿洗いの手伝いをする時間だから、奥へ引っ込むにはちょうどいい。
(ふふ、驚いてたな)
泡のついたスポンジで皿を洗いながら、俺はいたずらが成功した子どもみたいにクスクスと笑った。
深夜になって日付の変わる頃。
厨房の裏口から外に出ると、久しぶりにアーベルの姿があった。
「……またかよ」
「それはこちらの台詞だ、セディウス・ゾルガー」
いつものように『まだこんな遅くまで仕事してるのか』とひと通り説教され、有無を言わさず家まで送ってもらう事になった。
アーベルは、これまたいつものように、半歩後ろから追うようについてくる。道すがら話すことは途切れ途切れで、とりとめもなく、はずむ話題もなく、面白くもないが気まずくもない、なんとも言えない空気が漂っていた。
「……ところで、あのプディングだが」
その言葉に振り返ったが、なぜかアーベルは視線を合わせようとしない。
「人気があるって、本当か?」
「本当かって?」
何を言いたいのか分からず、ただ言われた言葉を繰り返したら、次に耳を疑うような事を言われた。
「プディングなら、もっとうまいのを食べたことがある」
「は?」
アーベルは相変わらず視線を合わせようとせず、まっすぐ前を向いている。俺は困惑しながらも、恐る恐る口を開いた。
「俺はうちの店の味、けっこう好きなんだけど……」
「お前が、好きなだけか?」
「いや、俺だけじゃなくってさ、ホントあのプディングは人気なんだよ。毎日いっぱい注文入るから、閉店前には完売しちゃうこともしょっちゅうだぜ?」
「……そうか」
(なんだよ、その嫌味な言い方……気分わりぃ)
それきり俺は口を閉ざすと、心持ち歩調を早めた。とっとと家に帰ってふて寝したい。
しばらくお互い無言で歩いていたが、あとひとつ角を曲がれば家に着く、というタイミングでアーベルが沈黙を破った。
「では、他の物と比べたことあるのか」
最初、何の事を言われたのか分からなかった。だがアーベルはしつこく、今度ははっきりと別の言い方で質問を繰り返した。
「他のプディングと比べたことがあるのか」
俺は仕方なく、ない、と正直にこたえた。
「では、比較のしようがないだろう」
「……」
一体何を言いたいのだろう。話の着地点が見えず、無言のまま早足で歩き続け、ようやく自宅アパートが見えた時はホッとした。
扉の前で、ポケットの中にあるはずの鍵を探っていると、なぜか後ろに立って待っているアーベルが唐突に話題を変えた。
「次の休みはいつだ」
「……なんであんたに、そんなこと教えなきゃいけないんだよ」
また労働時間がどうのとか同じ説教を繰り返すのかと、うんざりして言い返すと、アーベルは腕を組んだまま気難しい表情を浮かべた。
「……労働基準に従って、きちんと休日を取っているのか確認したいからだ」
「あっそ。あさってだよ」
俺は口ごたえする気も失せ、そっけなくそう答えると、玄関の扉をやや乱暴に開けた。そのまま振り返らずに中へ入ろうとしたところ、背中から大きな声が響いて、文字通り飛び上がった。
「では、あさっての正午に迎えに来るからな」
「急に大声出すなよ、びっくりするだろ! それに迎えに来るって、どういうつもりだよ」
「比較してもらう。もっとうまいプディングを食べてもらう」
ここでどうしてプディングが出て来るのだろう。困惑する俺に対し、アーベルはいつもの冷たい事務的な口調で淡々と続けた。
「明後日の正午、馬車で迎えに来る。時間になったら玄関まで降りてくるように。二時間程度で帰宅できるよう、帰りの馬車も手配しておく」
「ちょっと待て、なに勝手に話を進めてんだよ」
「二時間では不満か。では一時間半、いや一時間以内に終わるようにする」
「そういう問題じゃなくって……ああ、もう! わかったよ、正午だな?」
半分やけになって怒鳴るように承諾すると、アーベルは少し驚いたように瞬きをし、それからフワリと微笑んだので、俺は腰を抜かしそうになった。
「……アーベルさんってさ……」
「なんだ」
「いや、やっぱいい」
「そうか?」
何となく気まずいまま、手袋の指先を弄んでいると、黒い手袋の指先が伸びてきたので、あわてて両手を背中に隠した。
「な、なんだよ?」
「いや……寒いのか」
「別に。ちょっとあかぎれが、かゆくなっただけだよ」
「あかぎれ?」
毎日長時間皿洗いすれば、両手があかぎれだらけになって当然で、いわば職業病みたいなもんだ。特に冬場は水が冷たく、空気が乾燥しているから、一年でもっともひどい有様となる。夜シャワーを浴びる時など、ぬるま湯すら染みて地味につらい。
「手を見せてみろ」
「な、なんでだよ……やだよ」
「いいから見せろ」
強引に手を取られ、穴のあいた手袋を外されてしまった。冷たい外気がひび割れた皮膚に突き刺さり、俺は痛みを堪える為、ぐっと奥歯を噛みしめる。
「こんなになるまで、なぜ放っておいてたんだ……」
アーベルの息を飲む様子に、なんともばつの悪い思いでそっぽを向いた。
「こんなの普通だって。水仕事してんだから当たり前だよ」
「だが、ここまで悪化する前に、医者に見せるべきだ」
「医者って……あかぎれ程度で何言ってんの?」
俺はわり本気だったが、アーベルはえらい剣幕で怒り出した。
「ふざけるな! これは普通のあかぎれではない、とうに怪我の域に達してる!」
「お、おい、夜中なのに、近所迷惑だろ」
アーベルは俺の手首をつかんだまま、何か堪えるような表情でうつむいた。
「アーベルさん……そんな心配すんなよ」
「……」
「これ、見た目ほどひどくないんだ」
「駄目だ。耐えられるはずがない……絶対に」
「いや、慣れちゃえばたいして痛くも……うわっ」
アーベルは俺の手をつかんだまま、引きずるようにして玄関から通りへと逆戻りし始めた。
「ちょ、どこ行くんだよ!? もう夜中だってば……俺、早く帰って寝たいんだよ、明日も仕事なんだからさ」
強引に歩かされ、足をもつれさせながらも必死に抗議をした。するとアーベルはとんでもないことを言い出した。
「今夜はこのままうちの屋敷へ連れていく。間に合わせでも、なにか薬があるはずだ。明日は朝一番で医者にみせる」
「はあ!? だから明日も仕事あるんだってば! 勝手に休めないし、休むと給料から差っ引かれるし、困るよ!」
「店には、私から連絡を入れておく。明日の分の給金は、私が支払えば文句ないだろう?」
その勝手で傲慢な物言いに、俺はついカッとなって乱暴に手を振りほどいた。
「なんだよそれ、ふざけんじゃねーよ!」
対峙するアーベルの強い視線が、容赦なく突き刺さる。だが俺も負けてはいなかった。
「なんでも自分の思い通りになると思うなよ!」
そんな捨て台詞を残して踵を返すと、俺は振り返らずに玄関に飛び込むと、一気に階段を駆け上がった。
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
121
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる