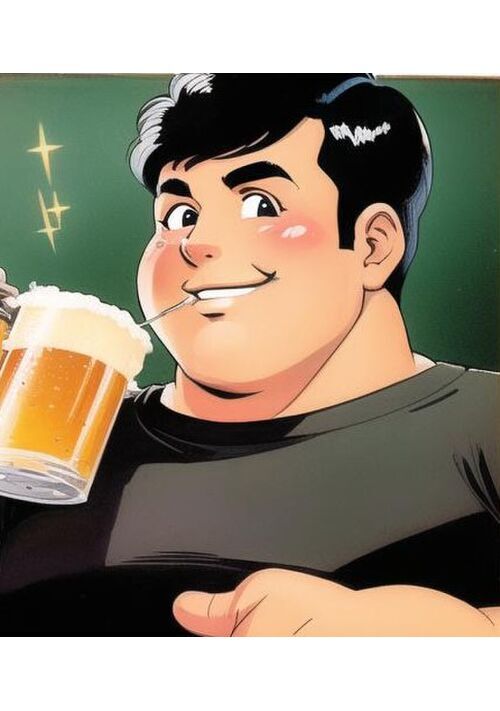4 / 9
特別じゃない贈り物
3
しおりを挟む
馬車に揺られて到着した先は『要塞城』の異名を持つ、バルテレミー城の西門に面した大通りだった。
貴族の邸宅が並ぶ南門付近とは違い、この辺りは噴水広場を中心に、高級ブティックやレストランが軒を連ねる、王都で最も華やかな観光スポットだ。だが高級店に縁がない俺にとって、この辺りはあまり馴染みがない。
俺たちを乗せた馬車は、広場の前で停まった。先に降りたアーベルの後を追って、常緑樹が立ち並ぶ遊歩道をサクサク進む。
周囲は家族連れよりも、恋人同士が寄り添って歩く姿が目につく。ふと、この公園が有名なデートスポットだったことを思い出し、若干居心地が悪くなった。
「寒くないか」
少し前を歩いていたアーベルが、突然立ち止まって振り返った。
「え、いや別に……」
「そうか」
アーベルは俺が追いつくのを待って、再び歩き出す。目を合わそうともせず、硬い表情で前を向いたままだ。かなり緊張してるのが分かる。
(なんで、こんなとこ歩いてんだ俺たち?)
会話もなく、しばらくただひたすら黙々と歩いていたが、やがてアーベルが重い口を開いた。
「……悪かった」
一瞬なんのことかと思ったが、ふと先日の別れ際にした口喧嘩に思い至った。
「いや、俺も態度悪かったよ」
俺が苦々しい気持ちで首をさすりながら謝ると、アーベルはキッパリと首を振った。
(この人って、基本いい人なんだよな)
お互い謝ったことで、少しだけ緊張感が薄らいだ。俺は肩の力を抜くと、ようやく歩きながら周囲を見回す余裕ができた。
すっかり葉を落とした木々が立ち並び、その細い枝の隙間から、澄んだ透明感のある冬の空がのぞく。明るくて、少し物悲しいが、とてもきれいだ。
(ん……? なんか甘い匂いがする……)
鼻をひくつかせて辺りを見回すと、道の先にカラフルな色に塗られた屋台があった。小さなカウンターからは、焼いたナッツに飴を絡めた、香ばしい匂いが漂ってくる。店先には暖かそうなコートを着た親子連れや、デート中らしき若い男女が五、六人列を作っていた。
俺が物珍しげに眺めてきると、隣から小さな咳払いが聞こえた。
「……君が食べたいのなら買ってくるが、どうする?」
「えっ、いいよ」
突然のアーベルの申し出に、俺はびっくりして首を振った。
「ところで昼はもう食べたのか」
「やっ、昼は……」
つい『普段は食べない』と言いかけ、寸前で言葉を飲みこんだ。職場の仲間内では、朝晩一日二食なんてちっとも珍しくないけど、おそらくアーベル達は昼飯を食べるのが当たり前なはずだ。
ここでうっかり正直に答えたら『だからそんなに痩せてしまうんだ』と、いつもの説教が始まるに違いない。
(説教だけならいいけど、この人なんだかんだ心配するからな……)
俺は少し躊躇って、喉を小さく鳴らした。
「今日はその、時間なくて……」
「ならば私もまだだから、悪いが食事に付き合って欲しい。なにか食べ物の好みはあるか」
「ええと、食べれないものってこと?」
「君の、好きな食べ物を聞いている」
好きな食べ物なんていっぱいある。でも普段から食べられる物が限られていて、好き嫌いなんて贅沢言えないから、急に聞かれてもすぐに思いつかない。
俺が黙っていると、アーベルは少し困ったように「では、あの辺りの店に行こう」と、噴水の先に見える小綺麗なカフェを指し示した。俺は特に反対する理由もないので、黙ってついて行くことにする。どうせ俺は食べないし、アーベルの腹が満たされればそれで構わなかった。
だがカフェのテラス席に着くなり、メニューを渡されたので首を傾げる。
「俺、食べないよ?」
「は? 昼はまだ食べてないのだろう?」
「食べてないけど、だからって食べないよ?」
「……もし支払いを気にしてるのなら、私が払うから心配しなくていい。その、食事に付き合ってもらうのだから、そのくらい当然だろう?」
またアーベルに気を使わせてしまった。俺はいたたまれない気持ちで視線を落とす。
「では、私が適当に注文してもいいか?」
「いいけど……」
アーベルは近くの給仕を呼び止めると、あれこれ注文した。あきらかに一人前には多い量で、きっと俺の分ぶんも入ってるのかと思うと、あらためて気恥ずかしい。誰かに食事をご馳走になるなんて、この街に移り住んでから初めてかもしれない。
木目調のテーブルには、季節の生花が飾られ、薄く繊細なグラスに注がれた炭酸水が、シャワシャワと陽気な音を立てている。向かいに座るアーベルは、この風景にしっくり馴染むけど、俺はどうだろう……考えるまでもないか。
(まあ、ここまで来ちゃったんだし、せっかくだから楽しむか)
冬でも温かい日差しのせいか、特に寒さは感じなかった。周囲を見回すと、あちらこちらに銀色のストーブが設置されていて、むしろ少し暑いくらいだ。俺はコートを脱いで椅子の背もたれに掛けると、手袋を外しかけて、ふと正面に座るアーベルの視線を感じた。
「何?」
「……その、君にこれを」
そっとテーブルに置かれたのは、手のひらに収まるほどの、小さな丸い容器だった。
「軍で支給される軟膏だ。傷やあかぎれにもよく効く」
「えっ、でも悪いよ」
「だから、軍で無料で支給されるものだから、気にしなくていいと言ってる」
でも俺は軍に勤めているわけじゃない。やっぱり断ろうとすると、アーベルの視線が不安そうに揺れていた。ここで意地を張って断るのも悪い気がして、おずおずと手を伸ばす。
(ん……? これは……)
手に取った容器に貼られたラベルは、有名メーカーのロゴ入りだった。軍がまとめて薬局から仕入れるのかもしれないけど、たぶん俺のために店で購入してきたに違いない。
(きっと、わざわざ買ってきたって言ったら、俺が断ると思ったんだろうな)
こういう器用だか不器用だか分からないやさしさが、本当に困ってしまう。
「ありがとう、アーベルさん」
「……ああ」
アーベルはホッとした表情を浮かべた。俺もなんだかホッとしてしまう。
「えーと、じゃあさっそくためしてみよっかなぁ……」
「ああ」
顔を赤らめて視線をそらしたアーベルに、俺も急に恥ずかしくなってしまい、間を持たせるために、いそいそと容器のフタを開けた。
(少し薄荷の香りがするな)
薄緑色のクリームを、人さし指でタップリすくい、手の甲に塗りつけてみた。すると途端に塗布した箇所がじくじくと痛み出す。
「いっ……たあ、イタタタ、な、コレすっげ、しみる……」
急激な痛みに堪えきれず、自然に涙がボロボロとこぼれ落ちた。俺はうめくのも辛くて、前のめりに体を折り曲げたまま椅子から転げ落ちてしまった。
朦朧とする意識の中で、アーベルの慌てた声が聞こえたけど、何を言ってるのかよく分からない。
(そういや店で洗い物してたとき、包丁で手をちょっと深めに切っちゃったんだ……あんまり痛くなかったけど、なかなか血が止まんなかったっけ……)
いつの間にか、アーベルが俺を抱きかかえ、なにか言葉を発する前に店を飛び出し、あっという間に馬車に押しこまれた。俺は痛みに震えながらも、背中に寄り添うあたたかい感触に、グッタリと身を任せて目を閉じた。
それから……意識が飛んでしまった。
子どもの頃、冬の寒い夜は母親によく手をさすってもらった。
母親は、いつも体の弱い弟につきっきりで、あまり構ってもらった記憶がないけど、これだけは鮮明に覚えている。
「あっ……つ……」
「もう少しで楽になるから、こらえてくれ……」
こめかみに柔らかい物が押し付けられる感触に、薄っすらと目を開いた。
「気がついたか」
「アーベルさん? ここは……」
涙の膜の向こう側に、アーベルの心配そうな顔があった。
視線を落とすと、両手は膝の上に乗せられた洗面器の、熱すぎずぬるすぎない湯に浸されていた。そして俺の赤く腫れた手を、ひとまわり大きな手がゆっくりと撫でていた。
少しずつ薄らいでいく痛みに、だんだんと思考がクリアになっていく。そしてようやく、自分がどこか立派な部屋にいて、椅子に座るアーベルに、背中からすっぽり抱き込まれていることに気づいた。
「わっ、どうしてこんな……は、はなして」
「こら、急に動くと危ない。薬を洗い落とすまで大人しくしてろ」
有無を言わさぬ態度に、俺はあきらめて強張る体から力を抜いた。ぬるま湯の中の手はふにゃふにゃにふやけて、だんだんむず痒くなってきた。
「……痛みはどうだ」
「うん、もう平気」
湯の中でアーベルの手をそっと外し、洗面器から両手を恐る恐る取り出した。指先から水を滴らせる両手は、すぐにアーベルの手で真っ白な柔らかいタオルで包まれた。
「血が、出ている……」
「あ、うん。この間ちょっとヘマして切っちゃったんだ」
アーベルはまるで自分が痛むように、眉をギュッと寄せた。俺はそれに気づかない振りをして、黙って拭かれるまま両手を差し出す。
服の袖が視界に入り、俺はようやく自分が見慣れない服を着ていることに気づいた。やたら肌触りが良くて柔らかい、寝巻のような前ボタンの上下を身に纏っている。
(い、いつの間に着替えたんだ?)
なんでも俺が意識を失っている間に、お医者さんを呼んで診察してもらったらしい。しきりに『誓って、診察中に部屋には入ってない』と繰り返すアーベルに、何が問題なのかよく理解できなかった。
知らない内に、医者に体を診られていたことには驚いたけど、それ以上にアーベルの心配性の方が気になった。
「……勝手に悪いが、君の店に連絡して仕事はしばらく休みにしてもらった」
「はあ!?」
「手のあかぎれも酷い状態だが、それ以上に君の体はだいぶ衰弱しているそうだ。医師の見立てでは、少なくとも十日は安静する必要があるらしい」
俺は呆けたまま、タオルに包まれた自分の両手を見下ろす。
(えっ、なに、手だけじゃないの?)
ようやくタオルを外された両手は、両脇から伸びたアーベルの両手によって、今度は濡れた布で慎重に包まれた。少ししみるのは、おそらく布に薬が浸してあるせいだろう。その上から手際よく包帯を巻かれると、次に後ろからギュッと抱きしめられた。
「も、もう終わっただろ……離せよ」
「……もう少しだけ、このまま」
肩に埋められた銀色の頭が震えてるから、どうしても突き放せない。
「アーベルさん、こ、困るよ」
「悪い……」
ようやく緩んだ腕にホッとするも、今度は膝の上から離してもらえない。よくみると両足は、靴も靴下も履いてない素足のままだ。
「あの、俺の靴は……」
「後で用意させるから、しばらくここで横になるといい」
アーベルさんは俺を一瞬抱き上げると、傍らの長椅子に下ろしてくれた。そしてテキパキと毛布を掛けられてしまう。急な病人扱いに、すっかり面食らうと同時に気分が滅入ってくる。
「……ゴメン、いろいろ迷惑掛けちゃて」
「いや、もとはと言えば私のせいだから、気にしなくていい」
たしかにアーベルのくれた薬が引き金だが、あかぎれは元から酷かったから、そこまで気にする事ないのに。
「ところで……ここ、どこ?」
「私の部屋だ」
「えっ、アーベルさんの屋敷なんだ」
「いや、バルテレミー城の西棟にある私の部屋だ」
どうやら俺は、現在お城の中にいるらしい。
「ちょっ、大丈夫なのかよ!? 一般市民は門の中に入れないはずだろ!」
「一般市民でも、城の関係者の付き添いがあれば入っても問題ない」
「そ、そっか……じゃあ、手当もしてもらったことだし、俺そろそろ帰るよ」
俺は長椅子から降りようとして、ふと靴が無い事を思い出した。
「えーと、俺の靴どこ? あと出口はどっちか教えてもらえる? 俺、帰って明日の支度をしないと……」
そこまで言いかけて、明日からしばらく仕事が休みになった事を思い出した。包帯を巻かれた両手を見下ろす。
(たしかに、これじゃあ水仕事は無理だな。給仕も包帯だらけの手だと、接客させてくれないだろうし……弱ったな)
何か、別の仕事を見つけないと。俺は顔を上げて、アーベルさんを見つめる。
「あのさ、食堂の仕事が休みの間、なにか簡単な仕事とかしたいんだけど……労働局の相談窓口だっけ? あれって、俺みたいな国外からの移民者も利用できたりするの?」
「……簡単な仕事、か」
アーベルは俺の座る長椅子の前に跪いた。視線が同じ高さになって、その真剣な視線にドキリとする。
「ならば……うちの屋敷に来ないか」
貴族の邸宅が並ぶ南門付近とは違い、この辺りは噴水広場を中心に、高級ブティックやレストランが軒を連ねる、王都で最も華やかな観光スポットだ。だが高級店に縁がない俺にとって、この辺りはあまり馴染みがない。
俺たちを乗せた馬車は、広場の前で停まった。先に降りたアーベルの後を追って、常緑樹が立ち並ぶ遊歩道をサクサク進む。
周囲は家族連れよりも、恋人同士が寄り添って歩く姿が目につく。ふと、この公園が有名なデートスポットだったことを思い出し、若干居心地が悪くなった。
「寒くないか」
少し前を歩いていたアーベルが、突然立ち止まって振り返った。
「え、いや別に……」
「そうか」
アーベルは俺が追いつくのを待って、再び歩き出す。目を合わそうともせず、硬い表情で前を向いたままだ。かなり緊張してるのが分かる。
(なんで、こんなとこ歩いてんだ俺たち?)
会話もなく、しばらくただひたすら黙々と歩いていたが、やがてアーベルが重い口を開いた。
「……悪かった」
一瞬なんのことかと思ったが、ふと先日の別れ際にした口喧嘩に思い至った。
「いや、俺も態度悪かったよ」
俺が苦々しい気持ちで首をさすりながら謝ると、アーベルはキッパリと首を振った。
(この人って、基本いい人なんだよな)
お互い謝ったことで、少しだけ緊張感が薄らいだ。俺は肩の力を抜くと、ようやく歩きながら周囲を見回す余裕ができた。
すっかり葉を落とした木々が立ち並び、その細い枝の隙間から、澄んだ透明感のある冬の空がのぞく。明るくて、少し物悲しいが、とてもきれいだ。
(ん……? なんか甘い匂いがする……)
鼻をひくつかせて辺りを見回すと、道の先にカラフルな色に塗られた屋台があった。小さなカウンターからは、焼いたナッツに飴を絡めた、香ばしい匂いが漂ってくる。店先には暖かそうなコートを着た親子連れや、デート中らしき若い男女が五、六人列を作っていた。
俺が物珍しげに眺めてきると、隣から小さな咳払いが聞こえた。
「……君が食べたいのなら買ってくるが、どうする?」
「えっ、いいよ」
突然のアーベルの申し出に、俺はびっくりして首を振った。
「ところで昼はもう食べたのか」
「やっ、昼は……」
つい『普段は食べない』と言いかけ、寸前で言葉を飲みこんだ。職場の仲間内では、朝晩一日二食なんてちっとも珍しくないけど、おそらくアーベル達は昼飯を食べるのが当たり前なはずだ。
ここでうっかり正直に答えたら『だからそんなに痩せてしまうんだ』と、いつもの説教が始まるに違いない。
(説教だけならいいけど、この人なんだかんだ心配するからな……)
俺は少し躊躇って、喉を小さく鳴らした。
「今日はその、時間なくて……」
「ならば私もまだだから、悪いが食事に付き合って欲しい。なにか食べ物の好みはあるか」
「ええと、食べれないものってこと?」
「君の、好きな食べ物を聞いている」
好きな食べ物なんていっぱいある。でも普段から食べられる物が限られていて、好き嫌いなんて贅沢言えないから、急に聞かれてもすぐに思いつかない。
俺が黙っていると、アーベルは少し困ったように「では、あの辺りの店に行こう」と、噴水の先に見える小綺麗なカフェを指し示した。俺は特に反対する理由もないので、黙ってついて行くことにする。どうせ俺は食べないし、アーベルの腹が満たされればそれで構わなかった。
だがカフェのテラス席に着くなり、メニューを渡されたので首を傾げる。
「俺、食べないよ?」
「は? 昼はまだ食べてないのだろう?」
「食べてないけど、だからって食べないよ?」
「……もし支払いを気にしてるのなら、私が払うから心配しなくていい。その、食事に付き合ってもらうのだから、そのくらい当然だろう?」
またアーベルに気を使わせてしまった。俺はいたたまれない気持ちで視線を落とす。
「では、私が適当に注文してもいいか?」
「いいけど……」
アーベルは近くの給仕を呼び止めると、あれこれ注文した。あきらかに一人前には多い量で、きっと俺の分ぶんも入ってるのかと思うと、あらためて気恥ずかしい。誰かに食事をご馳走になるなんて、この街に移り住んでから初めてかもしれない。
木目調のテーブルには、季節の生花が飾られ、薄く繊細なグラスに注がれた炭酸水が、シャワシャワと陽気な音を立てている。向かいに座るアーベルは、この風景にしっくり馴染むけど、俺はどうだろう……考えるまでもないか。
(まあ、ここまで来ちゃったんだし、せっかくだから楽しむか)
冬でも温かい日差しのせいか、特に寒さは感じなかった。周囲を見回すと、あちらこちらに銀色のストーブが設置されていて、むしろ少し暑いくらいだ。俺はコートを脱いで椅子の背もたれに掛けると、手袋を外しかけて、ふと正面に座るアーベルの視線を感じた。
「何?」
「……その、君にこれを」
そっとテーブルに置かれたのは、手のひらに収まるほどの、小さな丸い容器だった。
「軍で支給される軟膏だ。傷やあかぎれにもよく効く」
「えっ、でも悪いよ」
「だから、軍で無料で支給されるものだから、気にしなくていいと言ってる」
でも俺は軍に勤めているわけじゃない。やっぱり断ろうとすると、アーベルの視線が不安そうに揺れていた。ここで意地を張って断るのも悪い気がして、おずおずと手を伸ばす。
(ん……? これは……)
手に取った容器に貼られたラベルは、有名メーカーのロゴ入りだった。軍がまとめて薬局から仕入れるのかもしれないけど、たぶん俺のために店で購入してきたに違いない。
(きっと、わざわざ買ってきたって言ったら、俺が断ると思ったんだろうな)
こういう器用だか不器用だか分からないやさしさが、本当に困ってしまう。
「ありがとう、アーベルさん」
「……ああ」
アーベルはホッとした表情を浮かべた。俺もなんだかホッとしてしまう。
「えーと、じゃあさっそくためしてみよっかなぁ……」
「ああ」
顔を赤らめて視線をそらしたアーベルに、俺も急に恥ずかしくなってしまい、間を持たせるために、いそいそと容器のフタを開けた。
(少し薄荷の香りがするな)
薄緑色のクリームを、人さし指でタップリすくい、手の甲に塗りつけてみた。すると途端に塗布した箇所がじくじくと痛み出す。
「いっ……たあ、イタタタ、な、コレすっげ、しみる……」
急激な痛みに堪えきれず、自然に涙がボロボロとこぼれ落ちた。俺はうめくのも辛くて、前のめりに体を折り曲げたまま椅子から転げ落ちてしまった。
朦朧とする意識の中で、アーベルの慌てた声が聞こえたけど、何を言ってるのかよく分からない。
(そういや店で洗い物してたとき、包丁で手をちょっと深めに切っちゃったんだ……あんまり痛くなかったけど、なかなか血が止まんなかったっけ……)
いつの間にか、アーベルが俺を抱きかかえ、なにか言葉を発する前に店を飛び出し、あっという間に馬車に押しこまれた。俺は痛みに震えながらも、背中に寄り添うあたたかい感触に、グッタリと身を任せて目を閉じた。
それから……意識が飛んでしまった。
子どもの頃、冬の寒い夜は母親によく手をさすってもらった。
母親は、いつも体の弱い弟につきっきりで、あまり構ってもらった記憶がないけど、これだけは鮮明に覚えている。
「あっ……つ……」
「もう少しで楽になるから、こらえてくれ……」
こめかみに柔らかい物が押し付けられる感触に、薄っすらと目を開いた。
「気がついたか」
「アーベルさん? ここは……」
涙の膜の向こう側に、アーベルの心配そうな顔があった。
視線を落とすと、両手は膝の上に乗せられた洗面器の、熱すぎずぬるすぎない湯に浸されていた。そして俺の赤く腫れた手を、ひとまわり大きな手がゆっくりと撫でていた。
少しずつ薄らいでいく痛みに、だんだんと思考がクリアになっていく。そしてようやく、自分がどこか立派な部屋にいて、椅子に座るアーベルに、背中からすっぽり抱き込まれていることに気づいた。
「わっ、どうしてこんな……は、はなして」
「こら、急に動くと危ない。薬を洗い落とすまで大人しくしてろ」
有無を言わさぬ態度に、俺はあきらめて強張る体から力を抜いた。ぬるま湯の中の手はふにゃふにゃにふやけて、だんだんむず痒くなってきた。
「……痛みはどうだ」
「うん、もう平気」
湯の中でアーベルの手をそっと外し、洗面器から両手を恐る恐る取り出した。指先から水を滴らせる両手は、すぐにアーベルの手で真っ白な柔らかいタオルで包まれた。
「血が、出ている……」
「あ、うん。この間ちょっとヘマして切っちゃったんだ」
アーベルはまるで自分が痛むように、眉をギュッと寄せた。俺はそれに気づかない振りをして、黙って拭かれるまま両手を差し出す。
服の袖が視界に入り、俺はようやく自分が見慣れない服を着ていることに気づいた。やたら肌触りが良くて柔らかい、寝巻のような前ボタンの上下を身に纏っている。
(い、いつの間に着替えたんだ?)
なんでも俺が意識を失っている間に、お医者さんを呼んで診察してもらったらしい。しきりに『誓って、診察中に部屋には入ってない』と繰り返すアーベルに、何が問題なのかよく理解できなかった。
知らない内に、医者に体を診られていたことには驚いたけど、それ以上にアーベルの心配性の方が気になった。
「……勝手に悪いが、君の店に連絡して仕事はしばらく休みにしてもらった」
「はあ!?」
「手のあかぎれも酷い状態だが、それ以上に君の体はだいぶ衰弱しているそうだ。医師の見立てでは、少なくとも十日は安静する必要があるらしい」
俺は呆けたまま、タオルに包まれた自分の両手を見下ろす。
(えっ、なに、手だけじゃないの?)
ようやくタオルを外された両手は、両脇から伸びたアーベルの両手によって、今度は濡れた布で慎重に包まれた。少ししみるのは、おそらく布に薬が浸してあるせいだろう。その上から手際よく包帯を巻かれると、次に後ろからギュッと抱きしめられた。
「も、もう終わっただろ……離せよ」
「……もう少しだけ、このまま」
肩に埋められた銀色の頭が震えてるから、どうしても突き放せない。
「アーベルさん、こ、困るよ」
「悪い……」
ようやく緩んだ腕にホッとするも、今度は膝の上から離してもらえない。よくみると両足は、靴も靴下も履いてない素足のままだ。
「あの、俺の靴は……」
「後で用意させるから、しばらくここで横になるといい」
アーベルさんは俺を一瞬抱き上げると、傍らの長椅子に下ろしてくれた。そしてテキパキと毛布を掛けられてしまう。急な病人扱いに、すっかり面食らうと同時に気分が滅入ってくる。
「……ゴメン、いろいろ迷惑掛けちゃて」
「いや、もとはと言えば私のせいだから、気にしなくていい」
たしかにアーベルのくれた薬が引き金だが、あかぎれは元から酷かったから、そこまで気にする事ないのに。
「ところで……ここ、どこ?」
「私の部屋だ」
「えっ、アーベルさんの屋敷なんだ」
「いや、バルテレミー城の西棟にある私の部屋だ」
どうやら俺は、現在お城の中にいるらしい。
「ちょっ、大丈夫なのかよ!? 一般市民は門の中に入れないはずだろ!」
「一般市民でも、城の関係者の付き添いがあれば入っても問題ない」
「そ、そっか……じゃあ、手当もしてもらったことだし、俺そろそろ帰るよ」
俺は長椅子から降りようとして、ふと靴が無い事を思い出した。
「えーと、俺の靴どこ? あと出口はどっちか教えてもらえる? 俺、帰って明日の支度をしないと……」
そこまで言いかけて、明日からしばらく仕事が休みになった事を思い出した。包帯を巻かれた両手を見下ろす。
(たしかに、これじゃあ水仕事は無理だな。給仕も包帯だらけの手だと、接客させてくれないだろうし……弱ったな)
何か、別の仕事を見つけないと。俺は顔を上げて、アーベルさんを見つめる。
「あのさ、食堂の仕事が休みの間、なにか簡単な仕事とかしたいんだけど……労働局の相談窓口だっけ? あれって、俺みたいな国外からの移民者も利用できたりするの?」
「……簡単な仕事、か」
アーベルは俺の座る長椅子の前に跪いた。視線が同じ高さになって、その真剣な視線にドキリとする。
「ならば……うちの屋敷に来ないか」
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
121
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる