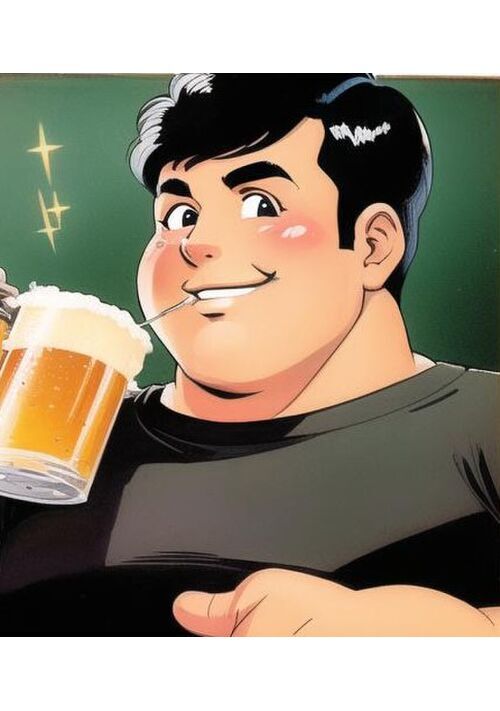6 / 9
特別じゃない贈り物
特別じゃないデート
しおりを挟む
なだらかな丘へと続く道の両側は、清々しい緑の芝が広がり、ふんわり漂う綿雲が浮かぶ青空と鮮やかなコントラストを描いていた。
ピクニック日和とは、まさにこんな日を指すのだろう。俺は雲の影を目で追いかけながら、スキップしてしまいそうな足取りで、アーベルと一緒に『西の砦』と呼ばれる遺跡へと続く一本道を歩いていた。
「わあ、すっげ! だんだん見えてきた!」
遺跡の一部が丘のてっぺんから頭を出すと、自然と足取りが軽くなる。
「俺、先に行ってる! アーベルさんは、ゆっくり来ていいよ」
「おい、あわてて転ぶなよ」
「大丈夫、大丈夫」
アーベルの笑いを含んだ忠告が追いかけてきたけど、そよ風の中を突っ切るとたまらなく気持ちよくて、走り出した足は止まりそうになかった。
やがて崩れた石垣がぽっかりと浮かぶ、数百年前に建てられた要塞の跡地までたどり着くと、勢いづいた駆け足がようやく落ち着きを取り戻した。
跡地と呼ばれるだけあって、建物の原型はとどめておらず、青く茂った芝を縁取るように、崩れた石壁が残っているばかりだ。風化が進んでいる上、苔に包まれているせいか、遠くから見ると緑の丘の一部となりつつあった。きっと子供の頃に見たら、うってつけの遊び場と思ったことだろう。
「アーベルさん、ここすごいね。秘密基地とか作るのにサイコーじゃん!」
追いついたアーベルが、一瞬キョトンとし、次の瞬間吹き出した。
「なんでそこで笑うんだよー」
「そんなこと言うのは君くらいだ」
「そうかな? 食料とか持ち込んでさ、夜通し作戦会議とかやったら楽しそうじゃん」
「夜は冷えるし、風邪でも引いたらどうする。野営するならば、それなりの準備をしなくては」
「野営って、軍隊じゃあるまいし、寝袋でもありゃ足りるだろ。まっ、一晩中起きてるだろうから、そんなもん必要無さそうだけどな」
「まさか本気で夜を明かすつもりか」
「それもいいかもな」
「明日も仕事だろう。どうするつもりだ」
「ここから通えばいいだろ。さいわい食べ物もタップリあるしな」
アーベルが持つ大きなバスケットには、彼の屋敷のお抱えシェフ特製ランチが、食べきれないほど詰まっているはずだ。
「……夜冷えてきたら、どうするつもりだ」
「アーベルさんのマントがあるじゃん」
「私もここに泊まれというのか?」
「秘密基地に隊員ひとりじゃ、かっこうつかないだろ。隊長も必要だしな、アーベル隊長」
「それならば隊長は君だ。セディウス・ゾルガー隊長」
心地よい風が、アーベルの銀色に輝く前髪を揺らす。フワリと微笑んだ顔が優しげで、俺の胸は不覚にもトクッと小さな音を立てた。
さいきんアーベルと話していると、胸が苦しいような、つまったような、それでいてくすぐったいような、おかしな気分になって困る。
「さーてと、腹減ったな。飯にしようぜ。あ、あの場所がいいんじゃね?」
多少わざとらしくても、無理やり話題を変える俺は、けっこう意気地なしだ。こんな場所に二人きりでやってきて、しかもデートだって分かっていて、それなのに相手を意識した途端つい話をそらしてしまう。
昼飯は予想以上に素晴らしかった。かなりの量があったけど、青空の下で食べる解放感もあいまって、ペロリと平らげてしまった。
「あー、うまかった!」
携帯用のポットに入れてきたお茶を飲み干すと、心地よい満腹感を覚えながら、敷物の上にゴロリと仰向けに寝転んだ。薄雲がやわらかいブランケットのように、ふんわりと全身を覆うように流れていく。
そよ風が草花ゆらして、さやかな音色を奏でながら耳元を通り過ぎていく。もう少しで眠りに落ちそうになった時、薄い布が体を包みこむ感触に気づいた。
薄目を開くと、アーベルのマントが肩までかけられていた。頬がじわりと熱くなって、思わず飛び起きてしまった。そして驚いた様子のアーベルに向かって、ぶっきらぼうにマントを突き返す。
「アーベルも少しは休めよ。昨日は夜勤だったんだろ」
「休んでいる。こうして君とのんびりしてるだけで疲れは取れる」
「いいから、少しは寝ろよ」
渋るアーベルを無理やり敷物の上に押し倒すと、首元までマントをかけてやる。すると当惑気味だった男の口元が、わずかにほころんだ。
「では、君も一緒に寝るといい」
「お、俺はいいよ」
「このところ君は、毎日遅くまで仕事をしてた。私が寝る必要があると言うのならば、君も同じだ」
力強い腕に引っ張られ、俺の体はいとも簡単に仰向けに転がった。すぐ隣のアーベルの肩と肩がぶつかって心臓が跳ねる。
「いいって言ったのに……」
「ときには休むことも必要だろう、セディウス・ゾルガー隊長」
「……セディだよ」
半身を起こして、隣で目を丸くしているアーベルの顔をのぞきこむ。
「セディウス・ゾルガーじゃ、いちいち長いだろ。セディ、でいいよ」
「……セディ……」
「ん、それでいーよ……」
空を背にした俺のシルエットが、アーベルの体に重なる。薄く形の良い唇が、何か言いたげに開き、銀色の長いまつげが、透明な水色の瞳に濃い影を落とした次の瞬間……ポツリ、と白いなだらかな頬に水滴が落ちた。
(ん? 雨……?)
ポツ、ポツと空から落ちてくる雨粒に、おだやかな空気は一掃されてしまう。俺たちがあわてて荷物をまとめている間にも、雨足はどんどん激しさを増していった。
「うわっ、冷たっ!」
「こっちだ、これを被るといい」
サッと頭からマントを被され、腕を取られて引っ張られる。どこへ行くかと思ったら、砦の風化しかかった壁の一角まで連れてこられた。ちょうど崩れた建物の角にあたる場所で、打ち付けてくる雨からある程度は濡れるのを防いでくれる。
アーベルはマントを頭上まで引っ張り上げた状態で、折りたたんだ敷物を足元に広げてくれた。壁を背にして並んで座ると、ちょうど小さなテントの中にいるみたいだ。
「寒くないか」
「平気だよ。アーベルさんもだいぶ濡れちゃったね」
「私は野営で慣れているから大丈夫だ。それよりも、君がずぶ濡れだ……」
長い指が、俺の濡れた頬をぬぐうように撫でる。顎をすくい上げられると、目の前には同じように雨に濡れた端正な顔が、吐息がかかりそうなほど間近にあった。
灰色に濡れそぼった前髪からは、水滴がポタポタと、大理石のような白い頬を伝って零れ落ちていく。薄い唇には血の気が無いが、向けられた瞳は先ほどの青空のように温かい。実際アーベルの腕の中は、俺をすっぽりと温かく包んでくれる。
「俺も一緒にマントを持つよ。アーベルさんひとりで、腕上げっぱなしじゃ疲れちゃうだろ」
「……ハルトでいい」
「え?」
「私の呼び名だ。ベルンハルトだが、親しい者の間ではハルトと呼ばれている」
「で、でも、急にはちょっと……」
「セディ」
「いや、だから」
「セディ……」
「わ、わかった、うん。ハルト、だな! そうだよな、これでお互い様だもんな。あ、そうそう、俺もマント持つんだったな。こっち側を持てばいいか?」
頭上のマントに手を伸ばすと、指先がアーベル、もといハルトの腕に触れた。濡れた服越しに硬い筋肉が感じられ、そのたくましさに俺は思わず手を引っ込めてしまった。
(な、なんだか、俺とぜんぜん違う……やっぱ鍛え方が違うのかな)
しかし引いた手は、すぐさま長い指に絡め取られてしまう。冷たい唇が指先に触れ、息をのんだ俺の耳元で掠れた声が響いた。
「君が好きだ……セディ」
細められた青い瞳が、暴力的なほど色っぽくて、俺は一瞬固まってしまう。握られた手から伝わる微かな震えに、緊張しているのは俺だけじゃないことが伝わってきた。
アーベルは小さく息を吐くと、わずかに目を伏せた。
「……突然、悪かった」
「へっ?」
反応が遅れたせいだろうか。握られていた手は、そっと振りほどかれてしまった。
マントが取りはらわれると、いつの間にか雨が上がっていて、雲間から差し込む光がやけにまぶしく感じた。
ホッとして青空を見上げていると、隣にいたハルトが荷物を手に立ち上がった。
「もう帰ろう」
「え? ちょ、ちょっと待てよ……」
ハルトは背を向けると、さっさと丘を下りはじめてしまった。俺も急いで立ち上がって、後を追いかける。
「おい、待てってば!」
「雨が上がったとはいえ、君はずぶ濡れだ。早めに帰宅して熱いシャワーを浴びないと、明日からの仕事に差し障る。西門近くにきたら馬車を手配するから、体が冷えきってしまう前に寮へ戻るといい……私はこのまま詰所に戻って仕事をする」
「はあっ!? 仕事に戻るって、なんで? 今日は非番だろ?」
足を止めようとしないハルトの前に駆け足で回りこみ、行く手を阻むとようやく足を止めた。
酷い顔色をした男前の顔が、渋面を浮かべて正面に立ちふさがる俺を見つめる。俺はやれやれと、大きく肩で息を吐いた。
「あんた、今すっごく肝心なところで逃げ出そうとしてんだろ」
目の前の顔が、スッと表情を失くした。
「……悪かった」
小さな謝罪に、そうじゃないと腹が立つ。なんでいつもこうなんだ。
「悪かったって、なんであやまるんだよ。俺、うれしかったのにっ……なんで、そうやって壁を作っちまうんだよ?」
「セディ……」
「俺の気持ちも返事も聞きたくないのかよ。そんで一方的に、あれこれ優しくされると、こっちだって調子狂うんだよ!」
彼の心の扉は厳重に鍵が掛けられて、なかなか中に入れてくれない。それがくやしくって、ほぼ八つ当たりだと分かっているのに、目の前にある奴の胸を数度叩いてしまう。そして濡れたシャツを掴み上げると、崩れそうな足をふんばって睨み上げた。
「人をこんな気持ちにさせといて、いまさら放り出すんじゃねーよっ……そもそも」
長い指が俺の口をふさいだ。
(えっ……)
意表を突かれ、涙が引っ込んでしまう。その次の瞬間、指越しにハルトの口が重なった。
濡れた前髪が額をくすぐり、見開いた瞼に焼き付いたのは、彼の伏せられた長いまつ毛だった。
ゆっくりと放される体と、名残惜しそうに唇に残された指先がもどかしい。ハルトの顔は真っ赤だった。
「もう、本当に君は……これ以上、私を好きにさせてどうするつもりだ」
乾きかけた前髪をかき上げながら、きまり悪そうに顔を逸らす。
「とてもじゃないが、これから仕事なんてできそうにない」
「……戻らなくていいだろ。そのために、わざわざ一日休み取ったんだし。だからこうやって、俺と一緒にデートしてんだろ?」
「だが一日では無理だ。とても足りない。一緒にいればいるほど、今日の終わりを迎えるのが辛くて、どうにかなってしまいそうだ」
「アーベルさん……」
目の前の男が、つらそうに顔を歪めて項垂れる。そんな顔、させるつもりじゃなかったのに。
「このままでは、君の仕事や生活の邪魔になる。君に迷惑を掛けてしまうと思うと」
「アーベルさんってば! 迷惑なんて、そんなの恋愛なら当たり前じゃないですか」
俺は苦笑を漏らした。彼の誠実で真面目なところは好きだし、長所だと思うけど、行き過ぎると時としてあだとなる。
「好きになる気持ちって、そんなに仕事や生活の邪魔ですか?」
「セディウス・ゾルガー……」
「そりゃ相手のことを考えて、仕事に手がつかなくなったり、一人だった頃の生活から変わっちゃう事もいろいろあると思います。でも、それってそんなにダメなことですか?」
気持ちが先だって、いろいろ変わってしまうことは、必ずしも悪いことではない。どうすれば分かってもらえるだろう。
「とにかく不自由な中にも、良い事だってたくさんあると思うんだ。少なくとも俺は、アーベルさんとこうやって一緒に出掛けてられて楽しいし、うれしいし、幸せだよ?」
「……呼び方、もとに戻ってる」
「は?」
「アーベルさんって」
「あ、ああ……いや、まだ慣れてなくって。それを言うなら、アー……ハルトだって、さっき俺のことフルネームで呼んだだろ?」
「なるほど、お互いまだ慣れてないのだな……これから少しずつ慣れていけばいいのか」
「そうだよ、もっと時間掛けてさ……だからもう少しだけ、ピクニック続けようよ。芝ももう乾いたから、さっきみたいに並んで寝そべってさ。のんびりくつろごう?」
「そうだな、それはいい考えに思えるな」
俺たちは、どちらからともなく手を繋ぐと、再び丘のてっぺんを目指してゆっくりと歩き出きだす。
小さな喧嘩やすれ違いは、これから先もたくさんあるだろう。でもその度に少しずつでいいから、お互いの心を近づけていけたら……きっと幸せだと思うんだ。
(おわり)
ピクニック日和とは、まさにこんな日を指すのだろう。俺は雲の影を目で追いかけながら、スキップしてしまいそうな足取りで、アーベルと一緒に『西の砦』と呼ばれる遺跡へと続く一本道を歩いていた。
「わあ、すっげ! だんだん見えてきた!」
遺跡の一部が丘のてっぺんから頭を出すと、自然と足取りが軽くなる。
「俺、先に行ってる! アーベルさんは、ゆっくり来ていいよ」
「おい、あわてて転ぶなよ」
「大丈夫、大丈夫」
アーベルの笑いを含んだ忠告が追いかけてきたけど、そよ風の中を突っ切るとたまらなく気持ちよくて、走り出した足は止まりそうになかった。
やがて崩れた石垣がぽっかりと浮かぶ、数百年前に建てられた要塞の跡地までたどり着くと、勢いづいた駆け足がようやく落ち着きを取り戻した。
跡地と呼ばれるだけあって、建物の原型はとどめておらず、青く茂った芝を縁取るように、崩れた石壁が残っているばかりだ。風化が進んでいる上、苔に包まれているせいか、遠くから見ると緑の丘の一部となりつつあった。きっと子供の頃に見たら、うってつけの遊び場と思ったことだろう。
「アーベルさん、ここすごいね。秘密基地とか作るのにサイコーじゃん!」
追いついたアーベルが、一瞬キョトンとし、次の瞬間吹き出した。
「なんでそこで笑うんだよー」
「そんなこと言うのは君くらいだ」
「そうかな? 食料とか持ち込んでさ、夜通し作戦会議とかやったら楽しそうじゃん」
「夜は冷えるし、風邪でも引いたらどうする。野営するならば、それなりの準備をしなくては」
「野営って、軍隊じゃあるまいし、寝袋でもありゃ足りるだろ。まっ、一晩中起きてるだろうから、そんなもん必要無さそうだけどな」
「まさか本気で夜を明かすつもりか」
「それもいいかもな」
「明日も仕事だろう。どうするつもりだ」
「ここから通えばいいだろ。さいわい食べ物もタップリあるしな」
アーベルが持つ大きなバスケットには、彼の屋敷のお抱えシェフ特製ランチが、食べきれないほど詰まっているはずだ。
「……夜冷えてきたら、どうするつもりだ」
「アーベルさんのマントがあるじゃん」
「私もここに泊まれというのか?」
「秘密基地に隊員ひとりじゃ、かっこうつかないだろ。隊長も必要だしな、アーベル隊長」
「それならば隊長は君だ。セディウス・ゾルガー隊長」
心地よい風が、アーベルの銀色に輝く前髪を揺らす。フワリと微笑んだ顔が優しげで、俺の胸は不覚にもトクッと小さな音を立てた。
さいきんアーベルと話していると、胸が苦しいような、つまったような、それでいてくすぐったいような、おかしな気分になって困る。
「さーてと、腹減ったな。飯にしようぜ。あ、あの場所がいいんじゃね?」
多少わざとらしくても、無理やり話題を変える俺は、けっこう意気地なしだ。こんな場所に二人きりでやってきて、しかもデートだって分かっていて、それなのに相手を意識した途端つい話をそらしてしまう。
昼飯は予想以上に素晴らしかった。かなりの量があったけど、青空の下で食べる解放感もあいまって、ペロリと平らげてしまった。
「あー、うまかった!」
携帯用のポットに入れてきたお茶を飲み干すと、心地よい満腹感を覚えながら、敷物の上にゴロリと仰向けに寝転んだ。薄雲がやわらかいブランケットのように、ふんわりと全身を覆うように流れていく。
そよ風が草花ゆらして、さやかな音色を奏でながら耳元を通り過ぎていく。もう少しで眠りに落ちそうになった時、薄い布が体を包みこむ感触に気づいた。
薄目を開くと、アーベルのマントが肩までかけられていた。頬がじわりと熱くなって、思わず飛び起きてしまった。そして驚いた様子のアーベルに向かって、ぶっきらぼうにマントを突き返す。
「アーベルも少しは休めよ。昨日は夜勤だったんだろ」
「休んでいる。こうして君とのんびりしてるだけで疲れは取れる」
「いいから、少しは寝ろよ」
渋るアーベルを無理やり敷物の上に押し倒すと、首元までマントをかけてやる。すると当惑気味だった男の口元が、わずかにほころんだ。
「では、君も一緒に寝るといい」
「お、俺はいいよ」
「このところ君は、毎日遅くまで仕事をしてた。私が寝る必要があると言うのならば、君も同じだ」
力強い腕に引っ張られ、俺の体はいとも簡単に仰向けに転がった。すぐ隣のアーベルの肩と肩がぶつかって心臓が跳ねる。
「いいって言ったのに……」
「ときには休むことも必要だろう、セディウス・ゾルガー隊長」
「……セディだよ」
半身を起こして、隣で目を丸くしているアーベルの顔をのぞきこむ。
「セディウス・ゾルガーじゃ、いちいち長いだろ。セディ、でいいよ」
「……セディ……」
「ん、それでいーよ……」
空を背にした俺のシルエットが、アーベルの体に重なる。薄く形の良い唇が、何か言いたげに開き、銀色の長いまつげが、透明な水色の瞳に濃い影を落とした次の瞬間……ポツリ、と白いなだらかな頬に水滴が落ちた。
(ん? 雨……?)
ポツ、ポツと空から落ちてくる雨粒に、おだやかな空気は一掃されてしまう。俺たちがあわてて荷物をまとめている間にも、雨足はどんどん激しさを増していった。
「うわっ、冷たっ!」
「こっちだ、これを被るといい」
サッと頭からマントを被され、腕を取られて引っ張られる。どこへ行くかと思ったら、砦の風化しかかった壁の一角まで連れてこられた。ちょうど崩れた建物の角にあたる場所で、打ち付けてくる雨からある程度は濡れるのを防いでくれる。
アーベルはマントを頭上まで引っ張り上げた状態で、折りたたんだ敷物を足元に広げてくれた。壁を背にして並んで座ると、ちょうど小さなテントの中にいるみたいだ。
「寒くないか」
「平気だよ。アーベルさんもだいぶ濡れちゃったね」
「私は野営で慣れているから大丈夫だ。それよりも、君がずぶ濡れだ……」
長い指が、俺の濡れた頬をぬぐうように撫でる。顎をすくい上げられると、目の前には同じように雨に濡れた端正な顔が、吐息がかかりそうなほど間近にあった。
灰色に濡れそぼった前髪からは、水滴がポタポタと、大理石のような白い頬を伝って零れ落ちていく。薄い唇には血の気が無いが、向けられた瞳は先ほどの青空のように温かい。実際アーベルの腕の中は、俺をすっぽりと温かく包んでくれる。
「俺も一緒にマントを持つよ。アーベルさんひとりで、腕上げっぱなしじゃ疲れちゃうだろ」
「……ハルトでいい」
「え?」
「私の呼び名だ。ベルンハルトだが、親しい者の間ではハルトと呼ばれている」
「で、でも、急にはちょっと……」
「セディ」
「いや、だから」
「セディ……」
「わ、わかった、うん。ハルト、だな! そうだよな、これでお互い様だもんな。あ、そうそう、俺もマント持つんだったな。こっち側を持てばいいか?」
頭上のマントに手を伸ばすと、指先がアーベル、もといハルトの腕に触れた。濡れた服越しに硬い筋肉が感じられ、そのたくましさに俺は思わず手を引っ込めてしまった。
(な、なんだか、俺とぜんぜん違う……やっぱ鍛え方が違うのかな)
しかし引いた手は、すぐさま長い指に絡め取られてしまう。冷たい唇が指先に触れ、息をのんだ俺の耳元で掠れた声が響いた。
「君が好きだ……セディ」
細められた青い瞳が、暴力的なほど色っぽくて、俺は一瞬固まってしまう。握られた手から伝わる微かな震えに、緊張しているのは俺だけじゃないことが伝わってきた。
アーベルは小さく息を吐くと、わずかに目を伏せた。
「……突然、悪かった」
「へっ?」
反応が遅れたせいだろうか。握られていた手は、そっと振りほどかれてしまった。
マントが取りはらわれると、いつの間にか雨が上がっていて、雲間から差し込む光がやけにまぶしく感じた。
ホッとして青空を見上げていると、隣にいたハルトが荷物を手に立ち上がった。
「もう帰ろう」
「え? ちょ、ちょっと待てよ……」
ハルトは背を向けると、さっさと丘を下りはじめてしまった。俺も急いで立ち上がって、後を追いかける。
「おい、待てってば!」
「雨が上がったとはいえ、君はずぶ濡れだ。早めに帰宅して熱いシャワーを浴びないと、明日からの仕事に差し障る。西門近くにきたら馬車を手配するから、体が冷えきってしまう前に寮へ戻るといい……私はこのまま詰所に戻って仕事をする」
「はあっ!? 仕事に戻るって、なんで? 今日は非番だろ?」
足を止めようとしないハルトの前に駆け足で回りこみ、行く手を阻むとようやく足を止めた。
酷い顔色をした男前の顔が、渋面を浮かべて正面に立ちふさがる俺を見つめる。俺はやれやれと、大きく肩で息を吐いた。
「あんた、今すっごく肝心なところで逃げ出そうとしてんだろ」
目の前の顔が、スッと表情を失くした。
「……悪かった」
小さな謝罪に、そうじゃないと腹が立つ。なんでいつもこうなんだ。
「悪かったって、なんであやまるんだよ。俺、うれしかったのにっ……なんで、そうやって壁を作っちまうんだよ?」
「セディ……」
「俺の気持ちも返事も聞きたくないのかよ。そんで一方的に、あれこれ優しくされると、こっちだって調子狂うんだよ!」
彼の心の扉は厳重に鍵が掛けられて、なかなか中に入れてくれない。それがくやしくって、ほぼ八つ当たりだと分かっているのに、目の前にある奴の胸を数度叩いてしまう。そして濡れたシャツを掴み上げると、崩れそうな足をふんばって睨み上げた。
「人をこんな気持ちにさせといて、いまさら放り出すんじゃねーよっ……そもそも」
長い指が俺の口をふさいだ。
(えっ……)
意表を突かれ、涙が引っ込んでしまう。その次の瞬間、指越しにハルトの口が重なった。
濡れた前髪が額をくすぐり、見開いた瞼に焼き付いたのは、彼の伏せられた長いまつ毛だった。
ゆっくりと放される体と、名残惜しそうに唇に残された指先がもどかしい。ハルトの顔は真っ赤だった。
「もう、本当に君は……これ以上、私を好きにさせてどうするつもりだ」
乾きかけた前髪をかき上げながら、きまり悪そうに顔を逸らす。
「とてもじゃないが、これから仕事なんてできそうにない」
「……戻らなくていいだろ。そのために、わざわざ一日休み取ったんだし。だからこうやって、俺と一緒にデートしてんだろ?」
「だが一日では無理だ。とても足りない。一緒にいればいるほど、今日の終わりを迎えるのが辛くて、どうにかなってしまいそうだ」
「アーベルさん……」
目の前の男が、つらそうに顔を歪めて項垂れる。そんな顔、させるつもりじゃなかったのに。
「このままでは、君の仕事や生活の邪魔になる。君に迷惑を掛けてしまうと思うと」
「アーベルさんってば! 迷惑なんて、そんなの恋愛なら当たり前じゃないですか」
俺は苦笑を漏らした。彼の誠実で真面目なところは好きだし、長所だと思うけど、行き過ぎると時としてあだとなる。
「好きになる気持ちって、そんなに仕事や生活の邪魔ですか?」
「セディウス・ゾルガー……」
「そりゃ相手のことを考えて、仕事に手がつかなくなったり、一人だった頃の生活から変わっちゃう事もいろいろあると思います。でも、それってそんなにダメなことですか?」
気持ちが先だって、いろいろ変わってしまうことは、必ずしも悪いことではない。どうすれば分かってもらえるだろう。
「とにかく不自由な中にも、良い事だってたくさんあると思うんだ。少なくとも俺は、アーベルさんとこうやって一緒に出掛けてられて楽しいし、うれしいし、幸せだよ?」
「……呼び方、もとに戻ってる」
「は?」
「アーベルさんって」
「あ、ああ……いや、まだ慣れてなくって。それを言うなら、アー……ハルトだって、さっき俺のことフルネームで呼んだだろ?」
「なるほど、お互いまだ慣れてないのだな……これから少しずつ慣れていけばいいのか」
「そうだよ、もっと時間掛けてさ……だからもう少しだけ、ピクニック続けようよ。芝ももう乾いたから、さっきみたいに並んで寝そべってさ。のんびりくつろごう?」
「そうだな、それはいい考えに思えるな」
俺たちは、どちらからともなく手を繋ぐと、再び丘のてっぺんを目指してゆっくりと歩き出きだす。
小さな喧嘩やすれ違いは、これから先もたくさんあるだろう。でもその度に少しずつでいいから、お互いの心を近づけていけたら……きっと幸せだと思うんだ。
(おわり)
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
121
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる