16 / 33
第二話 幸福の招き猫
7
しおりを挟む
見るからに年季の入った、白い車。
「祖父の趣味です。『スカイライン ハコスカ』と呼ばれるものらしいですが、僕も車には疎くて」
眼鏡ほだか先生が運転する車は、国道134号線へ入る。横須賀と大磯を結ぶこの路線は、湘南の海が見える国道線としてかなり有名だ。デートドライブの定番ルートされており、道なりにはお洒落なショップが数多く並んでいる。またサーフィンスポットとしても有名で、夏になればサーファーたちが波を求めてこの海外線へと訪れる。実際、砂浜にはサーフボードを持った男女が並んで歩いている。沈みゆく夕陽の向こうに、江ノ島が見えてくる。
ちょうど、信号が赤となり車がゆっくりと停車したあたりで。ほだか先生は、静かに口を開いた。
「結衣くんの言った通りです。ある時から、ボクには昴くんに付き纏う黒い影が見えていました。ただ今回昴くんに付き纏っているものは、結衣くんのときとは違い、悪霊と呼ばれるものではありません。ただただ昴くんの隣を並んで、彼の髪ばかりを見つめていただけなんです」
ほだか先生はそこまで言ったあたりで、途端に語るのをやめてしまう。誰とまでは、遂には言及しなかった。わたしも、誰とは聞かなかった。薄々とは、分かってしまうから。
──海に落ちて亡くなりました、だとさ。遺書とかは見つかってないけど、自殺したんじゃないかって話だよ。
その後は、言葉一つ挟まない。窓の向こうから、今流行りの韓流ミュージック音が流れてくる。見ると、若い男女が乗っている真っ赤なオープンカーが隣に並んでいた。楽しそうなデートドライブ。ハンドルを乗る彼のことが大好きなのだろうか、幸せそうな彼女の横顔。本来ならわたしもそうあってもいい状況なのに、今はそんな気分にもなれなかった。
駐車場に車を止めた後、わたしはほだか先生に連れられるがまま海岸線を沿って歩いた。そうして、江ノ島弁天橋近くの砂浜にて。
「昴くん、やはりここにいましたか」
スーツ姿の三觜が、革靴のまま砂浜に立ち、日の沈みゆく海をぼんやりと眺めていた。ほだか先生は、ゆったりとした歩調でその隣へと並ぶ。
「覚えていますか、昴くん。昔、君が自転車の後ろに乗せてくれて、よくこの場所へ連れてきてくれた」
「……」
「昴くん、言ってましたよね。海を見ていたら、人間の悩みなんてちっぽけに思える。辛いことがあったら、ここに来たらいいと……当時の僕は、昴くんのあの言葉に、すごく救われたんですよ」
そういえば以前、ほだか先生はこんなことを言っていた。小学生の頃の話だ。体が弱く部屋に閉じこもりがちだったほだか先生のもとに、よく三觜が遊びに来てくれた。当時の三觜は明るく、クラスの人気者。そんな彼がわざわざ自宅まで足を運んでくれたことが凄く嬉しかった、と。
「だから、なんだってんだよ」
ずっと黙っていた三觜は、冷ややかな瞳をほだか先生へと向けて、言った。
「あんなもん、ただの見栄張りでやっただけだ。お前に構ってやれば、みんなが俺のことを褒めてくれる。『優しいね』『偉いね』って、誰かにそう言われるのが楽しかっただけだ」
「それでも、善意であることに変わりはありません。それは、僕が救われたことにしてもそうです。昴くんは、正しいことをしたんです」
「……だから、やめろよそういうのッ! ほだか! 俺は昔から、お前のそういうキザな態度が大ッ嫌いなんだよ!」
三觜の怒号が轟いた。眉間にしわを寄せ、ほだか先生の胸ぐらへ掴みかかる。
「騙されたフリをしていたのは、同情のつもりだったんだろ? そうやって、心の中では俺のことを嘲笑っていたんだろ? なあ、ほだか! 本当のこと言えよッ!」
「ちょっと、やめ──」
「大丈夫ですよ、結衣くん。下がっていてください」
ほだか先生は、二人の間へ割って入ろうとするわたしへやんわり断りを入れる。睨みを利かせる三觜へと向き直った。以前、三觜は敵意ある眼差しをほだか先生へ。だがそのうちにも、そんなことをしたって無駄だと悟ったのだろう。どのような感情をぶつけたところで、ほだか先生は決して動じず、全てを受け入れる。そんなことくらい、三觜自身が一番よく理解しているだろう。
「むかつくな、ほんと」
「だったら、怒りをぶつけてもらっても結構です。僕はそのつもりで、ここへ来ましたから」
「そんなことは、別にいいんだよ。そうじゃねえ。はっきり言えよ、ほだか」
「はい」
「……由美は」
「……」
「……あいつは、もう死んでるんだな?」
その場一体へ、一瞬にして、緊張の糸が張り詰める。しばしの静寂。一秒、二秒……そして十秒が過ぎる。ほだか先生は──
「残念ですが」
言った、次の瞬間。三觜はほだか先生の胸ぐらから手を離した。唇を震わせる。
「本当は、俺だって分かってんだよ……」
怒りのやり場を失ったせいなのか、三觜の拳は小刻みに震えていた。
「どんなに頑張っても、由美はもう帰っては来ない。俺はただ、あいつらに言いように利用されているだけ……由美が、もうこの世にいないことも、薄々と気付いてたんだ。ただ、それでも、由美の死を認めてしまえば、全てがなかったことになる気がして……怖かったんだよ」
度し難い罪を犯した罪人のような顔をして三觜は、ぼそぼそと、由美さんへ降りかかった不幸を語り始めた。
由美さんの様子がおかしくなり始めたのは、今から一年前の春頃だった。一人前の美容師となるために頑張っていた由美さんが、突然「幸福の会」に入ると言い出した。これまで美容師として頑張ってきた由美さんを知っていた三觜は、はじめそれが悪い冗談に聞こえて仕方なかったという。
「『幸福の会』については、ちらっと噂に聞いたことがあるから知っていた。それがよくある『ネズミ講』だってこともな。もちろん、由美を説得しようとした。だけどな、あいつは頑なに認めようとしないんだよ……もはや洗脳だ、あれは」
由美さんは「幸福の会」とめぐり合ったことを、運が良かったと言ったらしい。夢を叶えるために頑張っている仲間たちと出会えた、そう嬉しそうに。
そしてなにかに取り憑かれたように、「お金が必要だ」と言い出した。夢を追うことには、自由に使える時間が必要だ。時間を作るには、働かなくても入ってくるお金が必要だ。という結論に至った由美さんは、美容師をやる傍ら「幸福の会」の商品をあらゆる人へ紹介した。最初は友達や親戚、親、三觜へ。そのうち店のスタッフへ、遂には店のお客さまにまで手を伸ばし始めた。
「みんな、由美から離れていったよ。せっかく頑張って掴んだ指名客も、いなくなってしまった。そのときだよ。俺が、あいつを本気で怒ったのは……確かに美容師は厳しい世界かもしれないけど、でも働いているときの由美はいつもキラキラしてた。だから、支えてやろうって決めてたのに……あいつは、せっかく築き上げてきた努力を、自分の手で台無しにしたんだ」
次の日、由美さんは三觜の前から姿を消した。連絡一切つかず、彼女の働いていた美容室へ尋ねてみたが「解雇した」とのことだった。
友人に聞いても、絶縁状態。八方塞りとなった三觜は、「幸福の会」へ連絡を取らざるをえなかった。そうして知らされた事実──前々から資金繰りに滞っていた由美さんには、莫大な借金があった。
誰かがその借金を補填する必要がある……三觜が「幸福の会」で働き始めたのは、その頃からだった。それが半年と数ヶ月前の話、そして今だ。
「二兎追う者は一兎も得ず。結局あいつは、全てを投げ出して、消えちまった……ああ、ほんとバカみてぇ。なにが夢だ。いつまでもそんなガキみたいなこと言ってるから、いいように利用されるんだ。普通に生きることの、なにがいけないっていうんだよ……普通に働いて、恋愛して、普通に結婚して、子供が産まれて……いいじゃねえか、それで」
「昴くん……」
「ほだか。お前も、昔からそうだったよな。自分は体が弱いけど、いつか美容師になるんだって、いつもここで言ってたよな」
皮肉めいた笑みを浮かべた三觜は、次第に闇沼のように黒ずんでいく夜の海を見渡しながら言った。
「はっきり言ってやるよ。俺は、あのときからお前のことを見下してたよ。なにやらしても満足にこなせないお前なんかには、絶対無理だってさ。だからな、そもそもが勘違いだ。俺は、お前の思っているような友達じゃねえ。今だってそうだ。俺は、お前を騙して金を毟りとった。夢を叶えたお前から、夢を奪おうとしたんだ。結局、俺も由美を騙した奴らと同じ……最低最悪の屑野郎だ」
それら自らの罪を告白した三觜は、途端に吹っ切れた表情を見せる。次にスーツの懐へ手を伸ばし小瓶を取り出す。中には、小粒の錠剤が瓶一杯に詰まっていた。
「許してくれなんて今更言うつもりもねぇ。ただ、けじめくらいはつけてやるさ」
……けじめ?
「三觜さん。あなたまさか……」
三觜は罪晴れた笑みを作り、力任せに瓶の蓋をこじ開けた。悪寒がした。仮にも、あれら錠剤全てが劇薬だったとしたら──睡眠薬や向精神薬などの過剰摂取は、人体に壊滅的な影響を齎す。確か、オーバードースと呼ばれる症状だ。最悪の場合、死に至る。
「三觜さん、やめてッ!」
三觜が瓶に口をつける。もう間に合わない──そんな最悪な未来を想像してしまったとき。
「やめなさいッ!」
耳をつんざく、怒声。初めて聞いたほだか先生の叫び声が、けたたましく砂浜に轟いた。わたしは、息を飲む。三觜の手が、ぴたりと止まる。
ほだか先生は、重々しいため息を吐いた。
「昴くん、命を粗末にするのはやめてください。そんなことをしたら、いよいよ由美さんに会えなくなります」
「……どういう、意味だ」
「ですから、由美さんはまだこの世にいます。それも、昴くんのずっと側に」
「今更そんな嘘をついたって、俺は──」
「嘘でも冗談でもありません」
断言したほだか先生は、それは精悍な顔付きで、真摯な眼差しを三觜へと向けている。その堂々した姿が、嘘偽りはないと体現しているみたく。
「信じるも信じないも……昴くん、あなた次第です。ですが僕ならば、昴くんと由美さんと引き合わせることができる」
「……またそれかよ、ほだか。まさかあれか、よくガキの頃に言ってた『幽霊が見える』って、そういうやつかよ」
「否定はしません」
三觜は黙った。畳み掛けるように、ほだか先生は言った。
「どうせ投げ出す命ならば、最後に騙されたと思って、僕のことを信じてみてはくれませんか?」
以前、三觜は黙ったままだ。その手に握られた薬瓶も、離そうとはしない。ただその表情からは、先程までの緊迫感がいくらか失われているように思われた。
ザァー……ザァー……耳打つ潮騒が、この場に於ける唯一の救いと感じられる、薄紫色の空の下──
「俺は……」
決断は、三觜に委ねられた。
言われた通り、わたしは準備を進めていく。彼の首回りに三つ折りの麻布を巻く。その上からカットクロスを纏わせ、髪の毛が入らないように、締まり過ぎて首が苦しくないよう、慎重な手つきでマジックテープを閉じた。はじめてのことで緊張したが、なんとか大丈夫のようだ。
「ありがとうございます、結衣くん」
ほだか先生はシザーケースを腰に巻きながら、セット面に座る彼の髪へスプレイヤーを吹きかける。丁寧なコームさばきにて、髪全体に水を馴染ませていく。
鏡の前に座る三觜は、ぐっすりと眠ったままだ。
あの後について──三觜は結局なにも告げず、そのまま帰っていった。ほだか先生も引き止めることはしなかった。その理由は分からないが、ほだか先生のことだから三觜がそんなバカなことをしないと信じていたのかもしれない。
そして案の定、本日の夕方頃だった。三觜が「カクリヨ」へ訪れた。「身なりくらい整えて死にたいからな」などという、素直じゃない彼らしい言い訳を引っ提げて。でも、わたしは分かっている。三觜は、由美さんに会えるというほだか先生の言葉を信じたんだ。
その後、席についた三觜がウトウトし始めて、そのうちぐっすりと眠ってしまった。
ほだか先生は、たすき紐で肩を縛りながら、
「日頃から、慢性的な寝不足だったのでしょう。それこそここ最近は、あまり眠っていなかったのかもしれませんね」
そうなのかもしれない。確かに、三觜の目の下には深いクマが浮かび上がっている。
また、ほだか先生のブレンドしたハーブティーには精神を鎮静化させるリラックス効能があるという。店内に漂っているバニラのお香にしても、同様の効能があるのだと本日はじめて知った。普段は意識していなかったけど、それらは全てお客さまの気持ちを穏やかにさせるものだったのだろう。美容室は癒しの空間。いつか聞いたその言葉を、わたしは心深いところで理解した。
「結衣くん、心の準備はよろしいですか?」
いつぞやの小槌を手にしたほだか先生へ、わたしは力強く頷き返してみせる。今この場にいることは、わたしが選択したことだ。
──関わった身として、最後まで見届けます。
そう言ったわたしに、後悔はしてない。例え、これからどんなものを見たにせよ。
「では、はじめます」
リーン、リーン、リーン、リーン……耳心地の良い鈴の音が、静謐とした室内を木霊する。これがどういったものかは知らない。でも以前、わたしはこの音が鳴った直後にも黒い影を見た。だったら今回も、そのようになるのだろうか──と。刹那。ぞわぞわっ……全身に寒気が走る。皮膚に直接冷気が刺さっているような感覚、直後だった。鏡に映る、眠る三觜の頭に、ぼんやりとした白いモヤのようなものが浮かび上がっていく。そうして、見てしまう。それは。
この世のものとは到底考えつかない、青白い手だった。
「これから、昴くんの髪を切ります。だから由美さん……あなたが、どのように昴くんの髪を切っていたのかを、僕に教えていただけませんか?」
爽やかなほだか先生の声が、その手に語りかけられる。また目だけでわたしへ合図を送ってくる。わたしはその手とほだか先生の顔を交互に見て、ゆっくりと頷いた。
そして、ほだか先生のカットは始まる──かちんっ、かちんっと、リズミカルなハサミの開閉音を鳴らして、三觜の襟足髪を鮮やかに切り落としていく。ほだか先生はときおり「なるほど」と独り言のように呟く。多分だけど、ほだか先生には由美さんの声が聞こえていたのかもしれない。もしくは、その思いが。
「結衣くん、申し訳ありません。少しだけで構いませんので、昴くんの頭を支えてはくれませんか?」
一瞬だけ、迷わされる。仮にも三觜の頭を支えるとなると、その手に触れてしまうことになるのだけれど。
「……はい」
恐怖を捨て去りきったわけではないが──彼女の手に、そっと自身の手を重ね合わせてみた。そのときだ。脳内へ、誰かの感情が流れ込んできた、そんな気がした。瞼を閉じて、神経を研ぎ澄ましてみる。声を聞いた。
──だから言ったじゃない。わたしがいないと、昴はこうなっちゃうんだから。
それは、由美さんの声なのだろうか。
──やっぱり、わたしが付いていてあげないとダメね……それなのに……ごめんね、昴。
まるで、本当にその場にいるかのような感覚。ただ、由美さんはもうこの世のものではない。わたしは、その事実を既に知っている。
そのうち、由美さんの感情、声は、夏の蜃気楼みたく、わたしの心から完全に失われる。ゆっくりと、瞼を開けてみる。三觜の目尻からツーと流れ落ちる、ひと筋の涙を見る。わびしい感情に駆られる。鏡に映り込んでいたその手は、もうどこにもなかった。
「地縛霊と呼ばれるものです」
ほだか先生はハサミを動かしながら、静かに語り出した。
「自身が亡くなったことに気付いていない魂が、生前と同じ行動を繰り返すことがあります。由美さんの場合は、伸びきった昴くんの髪を切ってあげたかったと。そんな思いが、きっと彼女をこの地へ縛りつけていたのでしょうね」
「では、由美さんは……自身が亡くなったことに、気付いてなかった?」
「ええ。悲しい話ですが、そういうことになります」
本当に、悲しい話だった。自分が亡くなったことに気付かず、ずっと三觜さんの側に寄り添い続けた由美さん。由美さんが見えていないはずなのに、未だ由美さんと付き合っているみたく振る舞っていた三觜。お互いがお互いを思っているはずなのに、二人が交わる機会は訪れない。
でも、もしも、夢の中だけでなら──
「二人が、ちゃんと再開できてたらいいんですけど……」
ほだか先生はひと呼吸置いて、小さく頷いた。
「ご安心ください。つい先ほど、由美さんはその思いを遂げて、安らかな眠りにつかれました。きっと、大丈夫です」
「祖父の趣味です。『スカイライン ハコスカ』と呼ばれるものらしいですが、僕も車には疎くて」
眼鏡ほだか先生が運転する車は、国道134号線へ入る。横須賀と大磯を結ぶこの路線は、湘南の海が見える国道線としてかなり有名だ。デートドライブの定番ルートされており、道なりにはお洒落なショップが数多く並んでいる。またサーフィンスポットとしても有名で、夏になればサーファーたちが波を求めてこの海外線へと訪れる。実際、砂浜にはサーフボードを持った男女が並んで歩いている。沈みゆく夕陽の向こうに、江ノ島が見えてくる。
ちょうど、信号が赤となり車がゆっくりと停車したあたりで。ほだか先生は、静かに口を開いた。
「結衣くんの言った通りです。ある時から、ボクには昴くんに付き纏う黒い影が見えていました。ただ今回昴くんに付き纏っているものは、結衣くんのときとは違い、悪霊と呼ばれるものではありません。ただただ昴くんの隣を並んで、彼の髪ばかりを見つめていただけなんです」
ほだか先生はそこまで言ったあたりで、途端に語るのをやめてしまう。誰とまでは、遂には言及しなかった。わたしも、誰とは聞かなかった。薄々とは、分かってしまうから。
──海に落ちて亡くなりました、だとさ。遺書とかは見つかってないけど、自殺したんじゃないかって話だよ。
その後は、言葉一つ挟まない。窓の向こうから、今流行りの韓流ミュージック音が流れてくる。見ると、若い男女が乗っている真っ赤なオープンカーが隣に並んでいた。楽しそうなデートドライブ。ハンドルを乗る彼のことが大好きなのだろうか、幸せそうな彼女の横顔。本来ならわたしもそうあってもいい状況なのに、今はそんな気分にもなれなかった。
駐車場に車を止めた後、わたしはほだか先生に連れられるがまま海岸線を沿って歩いた。そうして、江ノ島弁天橋近くの砂浜にて。
「昴くん、やはりここにいましたか」
スーツ姿の三觜が、革靴のまま砂浜に立ち、日の沈みゆく海をぼんやりと眺めていた。ほだか先生は、ゆったりとした歩調でその隣へと並ぶ。
「覚えていますか、昴くん。昔、君が自転車の後ろに乗せてくれて、よくこの場所へ連れてきてくれた」
「……」
「昴くん、言ってましたよね。海を見ていたら、人間の悩みなんてちっぽけに思える。辛いことがあったら、ここに来たらいいと……当時の僕は、昴くんのあの言葉に、すごく救われたんですよ」
そういえば以前、ほだか先生はこんなことを言っていた。小学生の頃の話だ。体が弱く部屋に閉じこもりがちだったほだか先生のもとに、よく三觜が遊びに来てくれた。当時の三觜は明るく、クラスの人気者。そんな彼がわざわざ自宅まで足を運んでくれたことが凄く嬉しかった、と。
「だから、なんだってんだよ」
ずっと黙っていた三觜は、冷ややかな瞳をほだか先生へと向けて、言った。
「あんなもん、ただの見栄張りでやっただけだ。お前に構ってやれば、みんなが俺のことを褒めてくれる。『優しいね』『偉いね』って、誰かにそう言われるのが楽しかっただけだ」
「それでも、善意であることに変わりはありません。それは、僕が救われたことにしてもそうです。昴くんは、正しいことをしたんです」
「……だから、やめろよそういうのッ! ほだか! 俺は昔から、お前のそういうキザな態度が大ッ嫌いなんだよ!」
三觜の怒号が轟いた。眉間にしわを寄せ、ほだか先生の胸ぐらへ掴みかかる。
「騙されたフリをしていたのは、同情のつもりだったんだろ? そうやって、心の中では俺のことを嘲笑っていたんだろ? なあ、ほだか! 本当のこと言えよッ!」
「ちょっと、やめ──」
「大丈夫ですよ、結衣くん。下がっていてください」
ほだか先生は、二人の間へ割って入ろうとするわたしへやんわり断りを入れる。睨みを利かせる三觜へと向き直った。以前、三觜は敵意ある眼差しをほだか先生へ。だがそのうちにも、そんなことをしたって無駄だと悟ったのだろう。どのような感情をぶつけたところで、ほだか先生は決して動じず、全てを受け入れる。そんなことくらい、三觜自身が一番よく理解しているだろう。
「むかつくな、ほんと」
「だったら、怒りをぶつけてもらっても結構です。僕はそのつもりで、ここへ来ましたから」
「そんなことは、別にいいんだよ。そうじゃねえ。はっきり言えよ、ほだか」
「はい」
「……由美は」
「……」
「……あいつは、もう死んでるんだな?」
その場一体へ、一瞬にして、緊張の糸が張り詰める。しばしの静寂。一秒、二秒……そして十秒が過ぎる。ほだか先生は──
「残念ですが」
言った、次の瞬間。三觜はほだか先生の胸ぐらから手を離した。唇を震わせる。
「本当は、俺だって分かってんだよ……」
怒りのやり場を失ったせいなのか、三觜の拳は小刻みに震えていた。
「どんなに頑張っても、由美はもう帰っては来ない。俺はただ、あいつらに言いように利用されているだけ……由美が、もうこの世にいないことも、薄々と気付いてたんだ。ただ、それでも、由美の死を認めてしまえば、全てがなかったことになる気がして……怖かったんだよ」
度し難い罪を犯した罪人のような顔をして三觜は、ぼそぼそと、由美さんへ降りかかった不幸を語り始めた。
由美さんの様子がおかしくなり始めたのは、今から一年前の春頃だった。一人前の美容師となるために頑張っていた由美さんが、突然「幸福の会」に入ると言い出した。これまで美容師として頑張ってきた由美さんを知っていた三觜は、はじめそれが悪い冗談に聞こえて仕方なかったという。
「『幸福の会』については、ちらっと噂に聞いたことがあるから知っていた。それがよくある『ネズミ講』だってこともな。もちろん、由美を説得しようとした。だけどな、あいつは頑なに認めようとしないんだよ……もはや洗脳だ、あれは」
由美さんは「幸福の会」とめぐり合ったことを、運が良かったと言ったらしい。夢を叶えるために頑張っている仲間たちと出会えた、そう嬉しそうに。
そしてなにかに取り憑かれたように、「お金が必要だ」と言い出した。夢を追うことには、自由に使える時間が必要だ。時間を作るには、働かなくても入ってくるお金が必要だ。という結論に至った由美さんは、美容師をやる傍ら「幸福の会」の商品をあらゆる人へ紹介した。最初は友達や親戚、親、三觜へ。そのうち店のスタッフへ、遂には店のお客さまにまで手を伸ばし始めた。
「みんな、由美から離れていったよ。せっかく頑張って掴んだ指名客も、いなくなってしまった。そのときだよ。俺が、あいつを本気で怒ったのは……確かに美容師は厳しい世界かもしれないけど、でも働いているときの由美はいつもキラキラしてた。だから、支えてやろうって決めてたのに……あいつは、せっかく築き上げてきた努力を、自分の手で台無しにしたんだ」
次の日、由美さんは三觜の前から姿を消した。連絡一切つかず、彼女の働いていた美容室へ尋ねてみたが「解雇した」とのことだった。
友人に聞いても、絶縁状態。八方塞りとなった三觜は、「幸福の会」へ連絡を取らざるをえなかった。そうして知らされた事実──前々から資金繰りに滞っていた由美さんには、莫大な借金があった。
誰かがその借金を補填する必要がある……三觜が「幸福の会」で働き始めたのは、その頃からだった。それが半年と数ヶ月前の話、そして今だ。
「二兎追う者は一兎も得ず。結局あいつは、全てを投げ出して、消えちまった……ああ、ほんとバカみてぇ。なにが夢だ。いつまでもそんなガキみたいなこと言ってるから、いいように利用されるんだ。普通に生きることの、なにがいけないっていうんだよ……普通に働いて、恋愛して、普通に結婚して、子供が産まれて……いいじゃねえか、それで」
「昴くん……」
「ほだか。お前も、昔からそうだったよな。自分は体が弱いけど、いつか美容師になるんだって、いつもここで言ってたよな」
皮肉めいた笑みを浮かべた三觜は、次第に闇沼のように黒ずんでいく夜の海を見渡しながら言った。
「はっきり言ってやるよ。俺は、あのときからお前のことを見下してたよ。なにやらしても満足にこなせないお前なんかには、絶対無理だってさ。だからな、そもそもが勘違いだ。俺は、お前の思っているような友達じゃねえ。今だってそうだ。俺は、お前を騙して金を毟りとった。夢を叶えたお前から、夢を奪おうとしたんだ。結局、俺も由美を騙した奴らと同じ……最低最悪の屑野郎だ」
それら自らの罪を告白した三觜は、途端に吹っ切れた表情を見せる。次にスーツの懐へ手を伸ばし小瓶を取り出す。中には、小粒の錠剤が瓶一杯に詰まっていた。
「許してくれなんて今更言うつもりもねぇ。ただ、けじめくらいはつけてやるさ」
……けじめ?
「三觜さん。あなたまさか……」
三觜は罪晴れた笑みを作り、力任せに瓶の蓋をこじ開けた。悪寒がした。仮にも、あれら錠剤全てが劇薬だったとしたら──睡眠薬や向精神薬などの過剰摂取は、人体に壊滅的な影響を齎す。確か、オーバードースと呼ばれる症状だ。最悪の場合、死に至る。
「三觜さん、やめてッ!」
三觜が瓶に口をつける。もう間に合わない──そんな最悪な未来を想像してしまったとき。
「やめなさいッ!」
耳をつんざく、怒声。初めて聞いたほだか先生の叫び声が、けたたましく砂浜に轟いた。わたしは、息を飲む。三觜の手が、ぴたりと止まる。
ほだか先生は、重々しいため息を吐いた。
「昴くん、命を粗末にするのはやめてください。そんなことをしたら、いよいよ由美さんに会えなくなります」
「……どういう、意味だ」
「ですから、由美さんはまだこの世にいます。それも、昴くんのずっと側に」
「今更そんな嘘をついたって、俺は──」
「嘘でも冗談でもありません」
断言したほだか先生は、それは精悍な顔付きで、真摯な眼差しを三觜へと向けている。その堂々した姿が、嘘偽りはないと体現しているみたく。
「信じるも信じないも……昴くん、あなた次第です。ですが僕ならば、昴くんと由美さんと引き合わせることができる」
「……またそれかよ、ほだか。まさかあれか、よくガキの頃に言ってた『幽霊が見える』って、そういうやつかよ」
「否定はしません」
三觜は黙った。畳み掛けるように、ほだか先生は言った。
「どうせ投げ出す命ならば、最後に騙されたと思って、僕のことを信じてみてはくれませんか?」
以前、三觜は黙ったままだ。その手に握られた薬瓶も、離そうとはしない。ただその表情からは、先程までの緊迫感がいくらか失われているように思われた。
ザァー……ザァー……耳打つ潮騒が、この場に於ける唯一の救いと感じられる、薄紫色の空の下──
「俺は……」
決断は、三觜に委ねられた。
言われた通り、わたしは準備を進めていく。彼の首回りに三つ折りの麻布を巻く。その上からカットクロスを纏わせ、髪の毛が入らないように、締まり過ぎて首が苦しくないよう、慎重な手つきでマジックテープを閉じた。はじめてのことで緊張したが、なんとか大丈夫のようだ。
「ありがとうございます、結衣くん」
ほだか先生はシザーケースを腰に巻きながら、セット面に座る彼の髪へスプレイヤーを吹きかける。丁寧なコームさばきにて、髪全体に水を馴染ませていく。
鏡の前に座る三觜は、ぐっすりと眠ったままだ。
あの後について──三觜は結局なにも告げず、そのまま帰っていった。ほだか先生も引き止めることはしなかった。その理由は分からないが、ほだか先生のことだから三觜がそんなバカなことをしないと信じていたのかもしれない。
そして案の定、本日の夕方頃だった。三觜が「カクリヨ」へ訪れた。「身なりくらい整えて死にたいからな」などという、素直じゃない彼らしい言い訳を引っ提げて。でも、わたしは分かっている。三觜は、由美さんに会えるというほだか先生の言葉を信じたんだ。
その後、席についた三觜がウトウトし始めて、そのうちぐっすりと眠ってしまった。
ほだか先生は、たすき紐で肩を縛りながら、
「日頃から、慢性的な寝不足だったのでしょう。それこそここ最近は、あまり眠っていなかったのかもしれませんね」
そうなのかもしれない。確かに、三觜の目の下には深いクマが浮かび上がっている。
また、ほだか先生のブレンドしたハーブティーには精神を鎮静化させるリラックス効能があるという。店内に漂っているバニラのお香にしても、同様の効能があるのだと本日はじめて知った。普段は意識していなかったけど、それらは全てお客さまの気持ちを穏やかにさせるものだったのだろう。美容室は癒しの空間。いつか聞いたその言葉を、わたしは心深いところで理解した。
「結衣くん、心の準備はよろしいですか?」
いつぞやの小槌を手にしたほだか先生へ、わたしは力強く頷き返してみせる。今この場にいることは、わたしが選択したことだ。
──関わった身として、最後まで見届けます。
そう言ったわたしに、後悔はしてない。例え、これからどんなものを見たにせよ。
「では、はじめます」
リーン、リーン、リーン、リーン……耳心地の良い鈴の音が、静謐とした室内を木霊する。これがどういったものかは知らない。でも以前、わたしはこの音が鳴った直後にも黒い影を見た。だったら今回も、そのようになるのだろうか──と。刹那。ぞわぞわっ……全身に寒気が走る。皮膚に直接冷気が刺さっているような感覚、直後だった。鏡に映る、眠る三觜の頭に、ぼんやりとした白いモヤのようなものが浮かび上がっていく。そうして、見てしまう。それは。
この世のものとは到底考えつかない、青白い手だった。
「これから、昴くんの髪を切ります。だから由美さん……あなたが、どのように昴くんの髪を切っていたのかを、僕に教えていただけませんか?」
爽やかなほだか先生の声が、その手に語りかけられる。また目だけでわたしへ合図を送ってくる。わたしはその手とほだか先生の顔を交互に見て、ゆっくりと頷いた。
そして、ほだか先生のカットは始まる──かちんっ、かちんっと、リズミカルなハサミの開閉音を鳴らして、三觜の襟足髪を鮮やかに切り落としていく。ほだか先生はときおり「なるほど」と独り言のように呟く。多分だけど、ほだか先生には由美さんの声が聞こえていたのかもしれない。もしくは、その思いが。
「結衣くん、申し訳ありません。少しだけで構いませんので、昴くんの頭を支えてはくれませんか?」
一瞬だけ、迷わされる。仮にも三觜の頭を支えるとなると、その手に触れてしまうことになるのだけれど。
「……はい」
恐怖を捨て去りきったわけではないが──彼女の手に、そっと自身の手を重ね合わせてみた。そのときだ。脳内へ、誰かの感情が流れ込んできた、そんな気がした。瞼を閉じて、神経を研ぎ澄ましてみる。声を聞いた。
──だから言ったじゃない。わたしがいないと、昴はこうなっちゃうんだから。
それは、由美さんの声なのだろうか。
──やっぱり、わたしが付いていてあげないとダメね……それなのに……ごめんね、昴。
まるで、本当にその場にいるかのような感覚。ただ、由美さんはもうこの世のものではない。わたしは、その事実を既に知っている。
そのうち、由美さんの感情、声は、夏の蜃気楼みたく、わたしの心から完全に失われる。ゆっくりと、瞼を開けてみる。三觜の目尻からツーと流れ落ちる、ひと筋の涙を見る。わびしい感情に駆られる。鏡に映り込んでいたその手は、もうどこにもなかった。
「地縛霊と呼ばれるものです」
ほだか先生はハサミを動かしながら、静かに語り出した。
「自身が亡くなったことに気付いていない魂が、生前と同じ行動を繰り返すことがあります。由美さんの場合は、伸びきった昴くんの髪を切ってあげたかったと。そんな思いが、きっと彼女をこの地へ縛りつけていたのでしょうね」
「では、由美さんは……自身が亡くなったことに、気付いてなかった?」
「ええ。悲しい話ですが、そういうことになります」
本当に、悲しい話だった。自分が亡くなったことに気付かず、ずっと三觜さんの側に寄り添い続けた由美さん。由美さんが見えていないはずなのに、未だ由美さんと付き合っているみたく振る舞っていた三觜。お互いがお互いを思っているはずなのに、二人が交わる機会は訪れない。
でも、もしも、夢の中だけでなら──
「二人が、ちゃんと再開できてたらいいんですけど……」
ほだか先生はひと呼吸置いて、小さく頷いた。
「ご安心ください。つい先ほど、由美さんはその思いを遂げて、安らかな眠りにつかれました。きっと、大丈夫です」
0
あなたにおすすめの小説

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...
MisakiNonagase
青春
39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。
ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。
さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?
そのほかに外伝も綴りました。
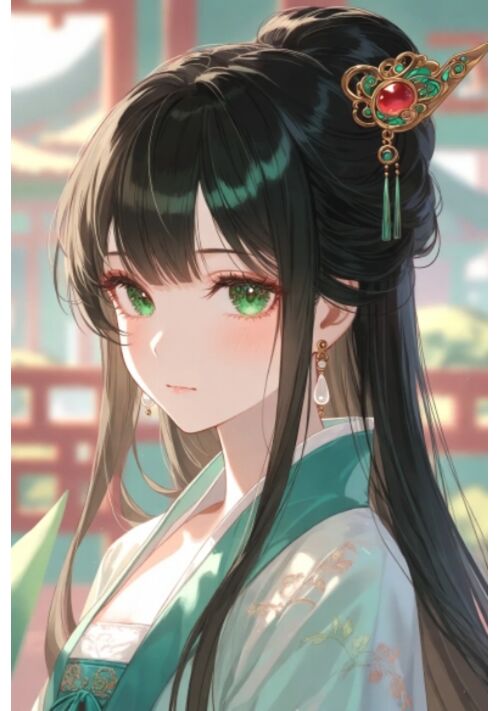
完結‼️翡翠の歌姫は 後宮で声を隠す〜特殊な眼を持つ歌姫が、2人の皇子と出会い、陰謀に巻き込まれながら王家の隠した真実に迫る
雪城 冴
キャラ文芸
1/23本編完結‼️
【中華サスペンス】
皇帝が隠した禁忌の秘密。
それを“思い出してはいけない少女”がいた――
【あらすじ】
特殊な眼を持つ少女・翠蓮(スイレン)は、不吉を呼ぶとして忌み嫌われ、育ての父を村人に殺されてしまう。
居場所を失った彼女は、宮廷直属の音楽団の選抜試験を受けることに。
しかし、早速差別の洗礼を受けてしまう。
そんな翠蓮を助けたのは、危険な香りをまとう皇子と、天女のように美しいもう一人の皇子だった。
それをきっかけに翠蓮は皇位争いに巻き込まれ、選抜試験も敵の妨害を受けてしまう。
彼女は無事合格できるのか。
◆二章◆
仲間と出会い、心を新たにするも次なる試練が待ち受ける。
それは、ライバル歌姫との二重唱と、メンバーからの嫌がらせだった。
なんとか迎えた本番。翠蓮は招かれた地方貴族から、忌み嫌われる眼の秘密に触れる。
◆三章◆
翠蓮の歌声と真心が貴妃の目にとまる。しかし後宮で"寵愛を受けている"と噂になり、皇后に目をつけられた。
皇后の息子から揺さぶりをかけられ、もう一人の皇子とは距離が急接近。
しかし、後宮特有の嫌がらせの中で翠蓮は、自分の存在が皇子に迷惑をかけていると知る。
わずかに芽生えていた恋心とも尊敬とも付かない気持ちは、押さえつけるしかなかった。
◆最終章◆
後宮で命を狙われ、生死をさまよう翠蓮は、忘れていた記憶を取り戻す。
かつて王家が封じた“力”とは?
翠蓮の正体とは?
身分違いの恋の行方は?
声を隠すか歌うのか。
運命に選ばれた少女が、最後に下す決断とは――
※架空の中華風ファンタジーです
※アルファポリス様で先行公開しており、書き溜まったらなろう、カクヨム様に移しています
※表紙絵はAI生成

烏の王と宵の花嫁
水川サキ
キャラ文芸
吸血鬼の末裔として生まれた華族の娘、月夜は家族から虐げられ孤独に生きていた。
唯一の慰めは、年に一度届く〈からす〉からの手紙。
その送り主は太陽の化身と称される上級華族、縁樹だった。
ある日、姉の縁談相手を誤って傷つけた月夜は、父に遊郭へ売られそうになり屋敷を脱出するが、陽の下で倒れてしまう。
死を覚悟した瞬間〈からす〉の正体である縁樹が現れ、互いの思惑から契約結婚を結ぶことになる。
※初出2024年7月

子持ち愛妻家の極悪上司にアタックしてもいいですか?天国の奥様には申し訳ないですが
霧内杳/眼鏡のさきっぽ
恋愛
胸がきゅんと、甘い音を立てる。
相手は、妻子持ちだというのに。
入社して配属一日目。
直属の上司で教育係だって紹介された人は、酷く人相の悪い人でした。
中高大と女子校育ちで男性慣れしてない私にとって、それだけでも恐怖なのに。
彼はちかよんなオーラバリバリで、仕事の質問すらする隙がない。
それでもどうにか仕事をこなしていたがとうとう、大きなミスを犯してしまう。
「俺が、悪いのか」
人のせいにするのかと叱責されるのかと思った。
けれど。
「俺の顔と、理由があって避け気味なせいだよな、すまん」
あやまってくれた彼に、胸がきゅんと甘い音を立てる。
相手は、妻子持ちなのに。
星谷桐子
22歳
システム開発会社営業事務
中高大女子校育ちで、ちょっぴり男性が苦手
自分の非はちゃんと認める子
頑張り屋さん
×
京塚大介
32歳
システム開発会社営業事務 主任
ツンツンあたまで目つき悪い
態度もでかくて人に恐怖を与えがち
5歳の娘にデレデレな愛妻家
いまでも亡くなった妻を愛している
私は京塚主任を、好きになってもいいのかな……?

あまりさんののっぴきならない事情
菱沼あゆ
キャラ文芸
強引に見合い結婚させられそうになって家出し、憧れのカフェでバイトを始めた、あまり。
充実した日々を送っていた彼女の前に、驚くような美形の客、犬塚海里《いぬづか かいり》が現れた。
「何故、こんなところに居る? 南条あまり」
「……嫌な人と結婚させられそうになって、家を出たからです」
「それ、俺だろ」
そーですね……。
カフェ店員となったお嬢様、あまりと常連客となった元見合い相手、海里の日常。

苦手な冷徹専務が義兄になったかと思ったら極あま顔で迫ってくるんですが、なんででしょう?~偽家族恋愛~
霧内杳/眼鏡のさきっぽ
恋愛
「こちら、再婚相手の息子の仁さん」
母に紹介され、なにかの間違いだと思った。
だってそこにいたのは、私が敵視している専務だったから。
それだけでもかなりな不安案件なのに。
私の住んでいるマンションに下着泥が出た話題から、さらに。
「そうだ、仁のマンションに引っ越せばいい」
なーんて義父になる人が言い出して。
結局、反対できないまま専務と同居する羽目に。
前途多難な同居生活。
相変わらず専務はなに考えているかわからない。
……かと思えば。
「兄妹ならするだろ、これくらい」
当たり前のように落とされる、額へのキス。
いったい、どうなってんのー!?
三ツ森涼夏
24歳
大手菓子メーカー『おろち製菓』営業戦略部勤務
背が低く、振り返ったら忘れられるくらい、特徴のない顔がコンプレックス。
小1の時に両親が離婚して以来、母親を支えてきた頑張り屋さん。
たまにその頑張りが空回りすることも?
恋愛、苦手というより、嫌い。
淋しい、をちゃんと言えずにきた人。
×
八雲仁
30歳
大手菓子メーカー『おろち製菓』専務
背が高く、眼鏡のイケメン。
ただし、いつも無表情。
集中すると周りが見えなくなる。
そのことで周囲には誤解を与えがちだが、弁明する気はない。
小さい頃に母親が他界し、それ以来、ひとりで淋しさを抱えてきた人。
ふたりはちゃんと義兄妹になれるのか、それとも……!?
*****
千里専務のその後→『絶対零度の、ハーフ御曹司の愛ブルーの瞳をゲーヲタの私に溶かせとか言っています?……』
*****
表紙画像 湯弐様 pixiv ID3989101

あやかし帝都の婚姻譚 〜浄癒の花嫁が祓魔の軍人に溺愛されるまで〜
鳴猫ツミキ
キャラ文芸
【完結】【第一章までで一区切り】時は大正。天羽家に生まれた桜子は、特異な体質から、家族に虐げられた生活を送っていた。すると女学院から帰ったある日、見合いをするよう命じられる。相手は冷酷だと評判の帝国陸軍あやかし対策部隊の四峰礼人だった。※和風シンデレラ風のお話です。恋愛要素が多いですが、あやかし要素が主体です。第9回キャラ文芸大賞に応募しているので、応援して頂けましたら嬉しいです。【第一章で一区切りで単体で読めますので、そこまででもご覧頂けると嬉しいです】。

後宮の手かざし皇后〜盲目のお飾り皇后が持つ波動の力〜
二位関りをん
キャラ文芸
龍の国の若き皇帝・浩明に5大名家の娘である美華が皇后として嫁いできた。しかし美華は病により目が見えなくなっていた。
そんな美華を冷たくあしらう浩明。婚儀の夜、美華の目の前で彼女付きの女官が心臓発作に倒れてしまう。
その時。美華は慌てること無く駆け寄り、女官に手をかざすと女官は元気になる。
どうも美華には不思議な力があるようで…?
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















