36 / 52
番外編
ヘリオドール・アガットの献身と受難─4─(完)
しおりを挟む
────
星々の煌めきの中を星の位置を頼りに飛び続け、空が白み始める頃、トーリボルの城壁の突起で一度羽を休めながら、ヘリオドールは支部の場所を探す。
(──なんて顔してるんだよ、馬鹿)
自分が飛び立った二階の窓の側に、フェンティセーザの姿が見えた。猛禽類の、良すぎる視力のせいで、目の下の隈まで見えてしまう。
(寝とけよな、ほんと)
ヘリオドールが化けた鳥の姿を見つけたのか、慌ててフェンティセーザが窓を開けた。そこに向かって、あともう少し、と、翼を羽ばたかせてヘリオドールが飛び立つ。
「──ただいま、一日遅くなった」
窓枠にに降り立つとすぐに術を解く。
夜の寒さは昼の暑さよりだいぶマシだったが、それでも夜通しの移動はかなり疲労が溜まる。
外套の重みが、ずしりと響いた。
「──ヘリオ!」
気が付いた時には、ヘリオドールの身体は、窓枠からそのまま倒れ込み、フェンティセーザの腕の中にあった。
「ヘリオ、しっかりしろ、ヘリオ…」
「『準備と移動で一ヶ月待て』って、伝言」
頬をぺちぺちと叩かれてはいるが、溜まった疲労と無事に着いた安堵から、身体が鉛の様に重たくなる。
あと──温かい。
飛ぶ間、冷たい空気から守ってくれたこの外套が温かいんだと思う事にする。
温かくて、眠い。
「ちゃんと、手紙ととげたから、すこしねせて…」
目を閉じると、急速に意識が落ちていく。
(…おまえ、も、ねなよ…)
自分の髪を掻き上げる手が、やけに優しいなと思いながら、ヘリオドールは意識を手放した。
─────
余程疲れていたのだろうか──ヘリオドールが目を覚ましたのは、その日の深夜だった。
外套を脱がされ、眼鏡や身体を締め付けるものを外された状態なのは理解できるものの、フェンティセーザに背中から抱き込まれていて流石に驚く。
あり得ない。
『学府』ではありとあらゆる手を使って妹を護ってたあの超火力のシスコンが?
自分と?同衾??
「…目が覚めたか?」
「…うん。まだ動きたくないけど」
慣れない事をしたせいで全身が怠くて重い。
明日は多分、全身筋肉痛かもしれない。
──動きたくないのは、決して背中に感じる温もりが心地いいからだけじゃない。怠くて重いせいだ。
喉の渇きを伝えると、枕元に水差しが準備されていた。なんとか起き上がって、一杯飲む。もう一杯注いでフェンティセーザに勧めると同じ様に飲み干した。
向かい合って座り直すと
「通信機器を、設置した直後に、倒れたと、連絡が入って、心配した」
「…ごめん、向こうの暑さが頭に入ってなかった」
「…私もだ…」
「お前暑さ寒さには強いもんな」
羨ましいよ、と力無く呟くと、髪を撫でられる。
「…帰って、来ないかと思った」
「ちゃんと戻るって言っただろ」
「……」
フェンティセーザが初めて見せた不安定な姿を、ヘリオドールは見なかった事にして胸の中に倒れ込む様に身を預ける。
「…一応な、『学府』からの指示でアーマラット支部所属だけど、そこは人足りてるからトーリボルに出向って形になった」
「…そうか」
いつもの口調がなりを潜めているのは、どうも不思議なものだ。
「…何があったか知らないけどさ、もう少し寝ようぜ」
「……ああ」
「零したけりゃ聞くよ?起きてる間は」
「……」
薄目を開けると、少し乱れた銀色の薄幕が視界を埋める。流石に寝る時は解いて寝るのかとぼんやり思いながら、疲労からか少し痺れが残る重い腕をなんとか動かして整えてやると、相手の身体が少し強張ったのが感じ取れた。
心音に耳を傾ける。
「……ちょ、ティス、お前、心臓うるさすぎ」
ふふ、くすっ、とヘリオドールが笑いを零す。
「せっかく心音聴きながら寝よって、思ったのに、早鐘じゃあ」
これじゃあ、まるで。
「…お前が、アーマラットの外套を、着てる姿を見て」
ぽつり、ぽつりとフェンティセーザが呟く様に、言葉を捻り出す。
「向こうで、本当に、何かあったのでは、ないかと」
「……そんな心配されるほど、私は誰かさんの番になった覚えはないんだけどな」
フェンティセーザもヘリオドールも、お互い、研究室を持たない研究員だった頃を知っている──立場の無い研究員がどんな目に合うのかも。
同族が、同族を。
立場が上の者が、下の者を。
淺ましくも喰らうのだ。
一度だけ、ヘリオドールは喰らわれる所を見られた事がある。
今はもう思い出しても犬に噛まれた程度の事でしかないのは、当時からのヘリオドール本人の諦観と達観もあるが、見られた翌日に、見た本人から「レポートを手伝って欲しい」と強制的に巻き込まれたせいだ。
ヘリオドールの得意とする分野は、どうやらフェンティセーザの専門外で──どうしてもレポートの完成度を高める為には必要だったのだ。
あの時、双子は、研究員達の雑魚寝部屋の片隅に、迷宮探索時に使われる、一時休憩用の安全地帯の結界を張って、そこでレポートを作っていた。
結局仕上げまで付き合わされた上、連名による提出もあって、ヘリオドールは自身の研究室まで手にしてしまった。
出した助け舟に対しては重すぎる対価を以って、泥水を啜る様な闇の中から助けられてしまったのだ。
今でもあの双子が自分と同じ目に遭わなくて良かったと、ヘリオドールは心から思う。
「あれは、夜通し翔ぶから寒くない様にって貸してくれた防寒着だよ」
「……分かってる」
「脱がせて、楽にしてくれたの、お前だろ?」
「……ああ」
「何かされた跡でもあった?」
「……無かった」
「…検分したのかよ」
「……」
「夜は、ギムリさんとマネラさんの所に泊まった。向こうの支部長さんと研究員も一緒だった」
ほっ、と安堵の溜息が漏れる。
「──これで、眠れる?」
隈の残る目の下を指でそっと撫ぜてやると
「……ああ」
と息を漏らす様な答えが返って来た。
やっと、眠れる、と。
目の下の隈を撫ぜる手を取り、手首と、掌に口付けを落とすと、そのまま倒れる様に眠りについてしまった。
(──言葉にしなきゃ、伝わらないんだよ、ティス)
囲い込んで、囲んで、逃げられない様に心を縛って、手中に収めたつもりになってるくせに──何故そんな行動に出るのかという、一番肝心な事をこの男は言わない。
分かってるだろう、伝わっているだろうと思っているのか、それとも──
言葉にするだけの勇気が無いのか。
どちらにしろ、言葉にして伝えてくれない限り、応えるつもりはない。
それにいずれ血を残す為に、彼も古代種エルフの女性を──見つけたら、娶るだろう。だから自分は隣に立つ『友』のままで充分だ。
心の軋みに蓋をして、ヘリオドールもさっさと横になる。
(なんでここまでしても、決定的な一言を口にしてくれないのかな、この強情っぱり)
たった一言、言えばいいのに。
そしたら面倒くさくなんてないのにさ。
────
翌日昼前。
「…おはよ…」
ヘリオドールは筋肉痛で軋む身体を無理矢理起こして朝から湯を貰い、支部の表側に顔を出す。
トーリボルの良い所は、何故かは知らないが、だいたいの大きな施設に、清掃の時間以外は一日中入られる湯殿が完備されている事だ。
どういった構造かはしっかり調べてみないと分からないが、温水すらわざわざ焚いて準備する必要もない。
確かヒノモトの迷宮攻略拠点には、地熱と水源の関係で温泉が多数あるというが、それに似た様なものだろうか?
──風呂は良い。身体が温まるし疲れも取れる。
「おはよう、ヘリオドール。お久しぶりね」
「お久しぶり、アレンティーナ。それと…」
「かつてのパーティーメンバーよ」
そこにいたのは、久々に顔を見る双子の妹、アレンティーナと、白髪混じりの真っ直ぐな黒髪が印象的な中年の美しい女戦士、少し顔に皺があるハーフフットの男だった。
「初めまして。私はヘリオドール・アガット。魔術師です」
「初めまして、私はトゥーリーン。君主だ」
「オイラはハロド。忍者だよ」
聞けば、今街の外れに拠点を建築中との事で、出来るまでの間は『学府』の施設を拠点としてるとの事だった。
正直なところ、ダンジョンマスターがまだ復帰してないので潜った所で意味はないのだが。
「フェンティスの『友達』だって?」
「……巻き込まれて連んでるだけですよ」
トゥーリーンの質問に、ちょっと考えてヘリオドールが答える。
『アーマラットの呪いの迷宮』についてのレポートの共同執筆者で、時々無茶振りに巻き込まれては付き合わされるだけの──他者から見れば、その程度の関係だろう。互いにしか見せない顔など、周囲には、言葉に出さなければ『無い』事になる。
「巻き込まれて連んでるだけだとしてもさぁ、今も側に居ていられる時点で相当だと思うけどなぁ」
「ハロドもそう思うよね?」
「…聴こえてるよ?」
ハロドとアレンティーナの密やかなふりをしたやり取りに、流石にヘリオドールがツッコミを入れる。
「向こうは何も言わないからね、こちらからは客観的にどう見えているかしか説明できないと思うんだけど」
「言わなきゃダメなの?」
「関係性を確定させたければ、だよ。少なくとも私はね」
なあなあなのも勝手に判断されるのも嫌いなんだ、とヘリオドールが付け加える。
「…面倒くさいのね」
「…口約束であっても、契約ってのは面倒臭いものなんだよ、アレンティー」
ヘリオドールの返事に、三人が三人、きょとんとした顔で、見合わせ──「なーんだ」と言う顔で三様にため息を漏らす。
「?何か?」
「ヘリオドール、居るか?」
同時に、奥からフェンティセーザが顔を出した。
「居るよ」
「午後から冒険者ギルドの方に行く。一緒に来てもらえるか?」
「いいよ。何時ごろ?」
「昼食の後でいい」
「了解。昼飯どうする?」
「あるもので済ませる」
「あるものって何があるのさ」
甘やかさなど欠片も無い、まるで学友の様なやりとりに、残る三人は呆気に取られる。
(え?………兄さん……?)
(昨日の朝からずっと部屋に籠ってたよね?)
(それでまだ付き合ってすらいないのかい?)
ヘリオドールが調理場の食糧のストックを確認に席を立ち──
「あるものって、何?」
真正面からじっと見据えられたフェンティセーザが、つい、と目を逸らす。
あ、これは食べるつもりもなく抜く気だな?
「まさか『エルフの焼き菓子』とか言わないよな?
他のみんなにまでアレ食わせる気?」
まさかね?
非常時ですらないのに、欠片ぽりぽりさせる気?
「「「はんたーーーい!!!」」」
流石にそれには、アレンティーナ、トゥーリーン、ハロドの三人も声を上げる。
「カパタト様の所の炊き出しでももう少し品数あるわよ!」
「何でせっかく街にいるのにクッキー一枚なんだい?肉食いに行くよ!」
「食べ歩きしたい!買い食いしたい!街ブラブラしに行くんだーーーーい!」
三種三様にフェンティセーザを引っ掴んで外に連れ出すのを、更にその背中をヘリオドールが押して追い出す。
「行ってきなよ、向こうで合流な」
そして、ぱたんとわざと軽く音を立てる。
そこから先は素早く戸締りを終えると、台所に立って牛乳を沸かし始めた。
予想した通り、食糧のストックはさみしいもので、とてもじゃないけど四人分の腹を満足させる程ではなかった。
支部住まい達が夜はどうしているのか全然分からないけれど、昼から出るなら何か日持ちする食糧を買って帰ってきた方がいいかもしれない。
何も食べる気は起きないし、せっかく材料も買ってきたので、マネラのレシピを見ながら、一度シチュードティーを作って飲もう。美味しく出来たら、その時は──振舞ってやるのもいいかもしれない。
──なんかちょっと、心なしか一抹の不安を覚えながらも、ヘリオドール・アガットの日常はやっと始まったかの様に思えた。
───幕間「冒険者ギルドにて・3」へ続く。
星々の煌めきの中を星の位置を頼りに飛び続け、空が白み始める頃、トーリボルの城壁の突起で一度羽を休めながら、ヘリオドールは支部の場所を探す。
(──なんて顔してるんだよ、馬鹿)
自分が飛び立った二階の窓の側に、フェンティセーザの姿が見えた。猛禽類の、良すぎる視力のせいで、目の下の隈まで見えてしまう。
(寝とけよな、ほんと)
ヘリオドールが化けた鳥の姿を見つけたのか、慌ててフェンティセーザが窓を開けた。そこに向かって、あともう少し、と、翼を羽ばたかせてヘリオドールが飛び立つ。
「──ただいま、一日遅くなった」
窓枠にに降り立つとすぐに術を解く。
夜の寒さは昼の暑さよりだいぶマシだったが、それでも夜通しの移動はかなり疲労が溜まる。
外套の重みが、ずしりと響いた。
「──ヘリオ!」
気が付いた時には、ヘリオドールの身体は、窓枠からそのまま倒れ込み、フェンティセーザの腕の中にあった。
「ヘリオ、しっかりしろ、ヘリオ…」
「『準備と移動で一ヶ月待て』って、伝言」
頬をぺちぺちと叩かれてはいるが、溜まった疲労と無事に着いた安堵から、身体が鉛の様に重たくなる。
あと──温かい。
飛ぶ間、冷たい空気から守ってくれたこの外套が温かいんだと思う事にする。
温かくて、眠い。
「ちゃんと、手紙ととげたから、すこしねせて…」
目を閉じると、急速に意識が落ちていく。
(…おまえ、も、ねなよ…)
自分の髪を掻き上げる手が、やけに優しいなと思いながら、ヘリオドールは意識を手放した。
─────
余程疲れていたのだろうか──ヘリオドールが目を覚ましたのは、その日の深夜だった。
外套を脱がされ、眼鏡や身体を締め付けるものを外された状態なのは理解できるものの、フェンティセーザに背中から抱き込まれていて流石に驚く。
あり得ない。
『学府』ではありとあらゆる手を使って妹を護ってたあの超火力のシスコンが?
自分と?同衾??
「…目が覚めたか?」
「…うん。まだ動きたくないけど」
慣れない事をしたせいで全身が怠くて重い。
明日は多分、全身筋肉痛かもしれない。
──動きたくないのは、決して背中に感じる温もりが心地いいからだけじゃない。怠くて重いせいだ。
喉の渇きを伝えると、枕元に水差しが準備されていた。なんとか起き上がって、一杯飲む。もう一杯注いでフェンティセーザに勧めると同じ様に飲み干した。
向かい合って座り直すと
「通信機器を、設置した直後に、倒れたと、連絡が入って、心配した」
「…ごめん、向こうの暑さが頭に入ってなかった」
「…私もだ…」
「お前暑さ寒さには強いもんな」
羨ましいよ、と力無く呟くと、髪を撫でられる。
「…帰って、来ないかと思った」
「ちゃんと戻るって言っただろ」
「……」
フェンティセーザが初めて見せた不安定な姿を、ヘリオドールは見なかった事にして胸の中に倒れ込む様に身を預ける。
「…一応な、『学府』からの指示でアーマラット支部所属だけど、そこは人足りてるからトーリボルに出向って形になった」
「…そうか」
いつもの口調がなりを潜めているのは、どうも不思議なものだ。
「…何があったか知らないけどさ、もう少し寝ようぜ」
「……ああ」
「零したけりゃ聞くよ?起きてる間は」
「……」
薄目を開けると、少し乱れた銀色の薄幕が視界を埋める。流石に寝る時は解いて寝るのかとぼんやり思いながら、疲労からか少し痺れが残る重い腕をなんとか動かして整えてやると、相手の身体が少し強張ったのが感じ取れた。
心音に耳を傾ける。
「……ちょ、ティス、お前、心臓うるさすぎ」
ふふ、くすっ、とヘリオドールが笑いを零す。
「せっかく心音聴きながら寝よって、思ったのに、早鐘じゃあ」
これじゃあ、まるで。
「…お前が、アーマラットの外套を、着てる姿を見て」
ぽつり、ぽつりとフェンティセーザが呟く様に、言葉を捻り出す。
「向こうで、本当に、何かあったのでは、ないかと」
「……そんな心配されるほど、私は誰かさんの番になった覚えはないんだけどな」
フェンティセーザもヘリオドールも、お互い、研究室を持たない研究員だった頃を知っている──立場の無い研究員がどんな目に合うのかも。
同族が、同族を。
立場が上の者が、下の者を。
淺ましくも喰らうのだ。
一度だけ、ヘリオドールは喰らわれる所を見られた事がある。
今はもう思い出しても犬に噛まれた程度の事でしかないのは、当時からのヘリオドール本人の諦観と達観もあるが、見られた翌日に、見た本人から「レポートを手伝って欲しい」と強制的に巻き込まれたせいだ。
ヘリオドールの得意とする分野は、どうやらフェンティセーザの専門外で──どうしてもレポートの完成度を高める為には必要だったのだ。
あの時、双子は、研究員達の雑魚寝部屋の片隅に、迷宮探索時に使われる、一時休憩用の安全地帯の結界を張って、そこでレポートを作っていた。
結局仕上げまで付き合わされた上、連名による提出もあって、ヘリオドールは自身の研究室まで手にしてしまった。
出した助け舟に対しては重すぎる対価を以って、泥水を啜る様な闇の中から助けられてしまったのだ。
今でもあの双子が自分と同じ目に遭わなくて良かったと、ヘリオドールは心から思う。
「あれは、夜通し翔ぶから寒くない様にって貸してくれた防寒着だよ」
「……分かってる」
「脱がせて、楽にしてくれたの、お前だろ?」
「……ああ」
「何かされた跡でもあった?」
「……無かった」
「…検分したのかよ」
「……」
「夜は、ギムリさんとマネラさんの所に泊まった。向こうの支部長さんと研究員も一緒だった」
ほっ、と安堵の溜息が漏れる。
「──これで、眠れる?」
隈の残る目の下を指でそっと撫ぜてやると
「……ああ」
と息を漏らす様な答えが返って来た。
やっと、眠れる、と。
目の下の隈を撫ぜる手を取り、手首と、掌に口付けを落とすと、そのまま倒れる様に眠りについてしまった。
(──言葉にしなきゃ、伝わらないんだよ、ティス)
囲い込んで、囲んで、逃げられない様に心を縛って、手中に収めたつもりになってるくせに──何故そんな行動に出るのかという、一番肝心な事をこの男は言わない。
分かってるだろう、伝わっているだろうと思っているのか、それとも──
言葉にするだけの勇気が無いのか。
どちらにしろ、言葉にして伝えてくれない限り、応えるつもりはない。
それにいずれ血を残す為に、彼も古代種エルフの女性を──見つけたら、娶るだろう。だから自分は隣に立つ『友』のままで充分だ。
心の軋みに蓋をして、ヘリオドールもさっさと横になる。
(なんでここまでしても、決定的な一言を口にしてくれないのかな、この強情っぱり)
たった一言、言えばいいのに。
そしたら面倒くさくなんてないのにさ。
────
翌日昼前。
「…おはよ…」
ヘリオドールは筋肉痛で軋む身体を無理矢理起こして朝から湯を貰い、支部の表側に顔を出す。
トーリボルの良い所は、何故かは知らないが、だいたいの大きな施設に、清掃の時間以外は一日中入られる湯殿が完備されている事だ。
どういった構造かはしっかり調べてみないと分からないが、温水すらわざわざ焚いて準備する必要もない。
確かヒノモトの迷宮攻略拠点には、地熱と水源の関係で温泉が多数あるというが、それに似た様なものだろうか?
──風呂は良い。身体が温まるし疲れも取れる。
「おはよう、ヘリオドール。お久しぶりね」
「お久しぶり、アレンティーナ。それと…」
「かつてのパーティーメンバーよ」
そこにいたのは、久々に顔を見る双子の妹、アレンティーナと、白髪混じりの真っ直ぐな黒髪が印象的な中年の美しい女戦士、少し顔に皺があるハーフフットの男だった。
「初めまして。私はヘリオドール・アガット。魔術師です」
「初めまして、私はトゥーリーン。君主だ」
「オイラはハロド。忍者だよ」
聞けば、今街の外れに拠点を建築中との事で、出来るまでの間は『学府』の施設を拠点としてるとの事だった。
正直なところ、ダンジョンマスターがまだ復帰してないので潜った所で意味はないのだが。
「フェンティスの『友達』だって?」
「……巻き込まれて連んでるだけですよ」
トゥーリーンの質問に、ちょっと考えてヘリオドールが答える。
『アーマラットの呪いの迷宮』についてのレポートの共同執筆者で、時々無茶振りに巻き込まれては付き合わされるだけの──他者から見れば、その程度の関係だろう。互いにしか見せない顔など、周囲には、言葉に出さなければ『無い』事になる。
「巻き込まれて連んでるだけだとしてもさぁ、今も側に居ていられる時点で相当だと思うけどなぁ」
「ハロドもそう思うよね?」
「…聴こえてるよ?」
ハロドとアレンティーナの密やかなふりをしたやり取りに、流石にヘリオドールがツッコミを入れる。
「向こうは何も言わないからね、こちらからは客観的にどう見えているかしか説明できないと思うんだけど」
「言わなきゃダメなの?」
「関係性を確定させたければ、だよ。少なくとも私はね」
なあなあなのも勝手に判断されるのも嫌いなんだ、とヘリオドールが付け加える。
「…面倒くさいのね」
「…口約束であっても、契約ってのは面倒臭いものなんだよ、アレンティー」
ヘリオドールの返事に、三人が三人、きょとんとした顔で、見合わせ──「なーんだ」と言う顔で三様にため息を漏らす。
「?何か?」
「ヘリオドール、居るか?」
同時に、奥からフェンティセーザが顔を出した。
「居るよ」
「午後から冒険者ギルドの方に行く。一緒に来てもらえるか?」
「いいよ。何時ごろ?」
「昼食の後でいい」
「了解。昼飯どうする?」
「あるもので済ませる」
「あるものって何があるのさ」
甘やかさなど欠片も無い、まるで学友の様なやりとりに、残る三人は呆気に取られる。
(え?………兄さん……?)
(昨日の朝からずっと部屋に籠ってたよね?)
(それでまだ付き合ってすらいないのかい?)
ヘリオドールが調理場の食糧のストックを確認に席を立ち──
「あるものって、何?」
真正面からじっと見据えられたフェンティセーザが、つい、と目を逸らす。
あ、これは食べるつもりもなく抜く気だな?
「まさか『エルフの焼き菓子』とか言わないよな?
他のみんなにまでアレ食わせる気?」
まさかね?
非常時ですらないのに、欠片ぽりぽりさせる気?
「「「はんたーーーい!!!」」」
流石にそれには、アレンティーナ、トゥーリーン、ハロドの三人も声を上げる。
「カパタト様の所の炊き出しでももう少し品数あるわよ!」
「何でせっかく街にいるのにクッキー一枚なんだい?肉食いに行くよ!」
「食べ歩きしたい!買い食いしたい!街ブラブラしに行くんだーーーーい!」
三種三様にフェンティセーザを引っ掴んで外に連れ出すのを、更にその背中をヘリオドールが押して追い出す。
「行ってきなよ、向こうで合流な」
そして、ぱたんとわざと軽く音を立てる。
そこから先は素早く戸締りを終えると、台所に立って牛乳を沸かし始めた。
予想した通り、食糧のストックはさみしいもので、とてもじゃないけど四人分の腹を満足させる程ではなかった。
支部住まい達が夜はどうしているのか全然分からないけれど、昼から出るなら何か日持ちする食糧を買って帰ってきた方がいいかもしれない。
何も食べる気は起きないし、せっかく材料も買ってきたので、マネラのレシピを見ながら、一度シチュードティーを作って飲もう。美味しく出来たら、その時は──振舞ってやるのもいいかもしれない。
──なんかちょっと、心なしか一抹の不安を覚えながらも、ヘリオドール・アガットの日常はやっと始まったかの様に思えた。
───幕間「冒険者ギルドにて・3」へ続く。
0
あなたにおすすめの小説

敵に貞操を奪われて癒しの力を失うはずだった聖女ですが、なぜか前より漲っています
藤谷 要
恋愛
サルサン国の聖女たちは、隣国に征服される際に自国の王の命で殺されそうになった。ところが、侵略軍将帥のマトルヘル侯爵に助けられた。それから聖女たちは侵略国に仕えるようになったが、一か月後に筆頭聖女だったルミネラは命の恩人の侯爵へ嫁ぐように国王から命じられる。
結婚披露宴では、陛下に側妃として嫁いだ旧サルサン国王女が出席していたが、彼女は侯爵に腕を絡めて「陛下の手がつかなかったら一年後に妻にしてほしい」と頼んでいた。しかも、侯爵はその手を振り払いもしない。
聖女は愛のない交わりで神の加護を失うとされているので、当然白い結婚だと思っていたが、初夜に侯爵のメイアスから体の関係を迫られる。彼は命の恩人だったので、ルミネラはそのまま彼を受け入れた。
侯爵がかつての恋人に似ていたとはいえ、侯爵と孤児だった彼は全く別人。愛のない交わりだったので、当然力を失うと思っていたが、なぜか以前よりも力が漲っていた。
※全11話 2万字程度の話です。

第3皇子は妃よりも騎士団長の妹の私を溺愛している 【完結】
日下奈緒
恋愛
王家に仕える騎士の妹・リリアーナは、冷徹と噂される第3皇子アシュレイに密かに想いを寄せていた。戦の前夜、命を懸けた一戦を前に、彼のもとを訪ね純潔を捧げる。勝利の凱旋後も、皇子は毎夜彼女を呼び続け、やがてリリアーナは身籠る。正妃に拒まれていた皇子は離縁を決意し、すべてを捨ててリリアーナを正式な妃として迎える——これは、禁じられた愛が真実の絆へと変わる、激甘ロマンス。

王様の恥かきっ娘
青の雀
恋愛
恥かきっ子とは、親が年老いてから子供ができること。
本当は、元気でおめでたいことだけど、照れ隠しで、その年齢まで夫婦の営みがあったことを物語り世間様に向けての恥をいう。
孫と同い年の王女殿下が生まれたことで巻き起こる騒動を書きます
物語は、卒業記念パーティで婚約者から婚約破棄されたところから始まります
これもショートショートで書く予定です。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

敗戦国の姫は、敵国将軍に掠奪される
clayclay
恋愛
架空の国アルバ国は、ブリタニア国に侵略され、国は壊滅状態となる。
状況を打破するため、アルバ国王は娘のソフィアに、ブリタニア国使者への「接待」を命じたが……。
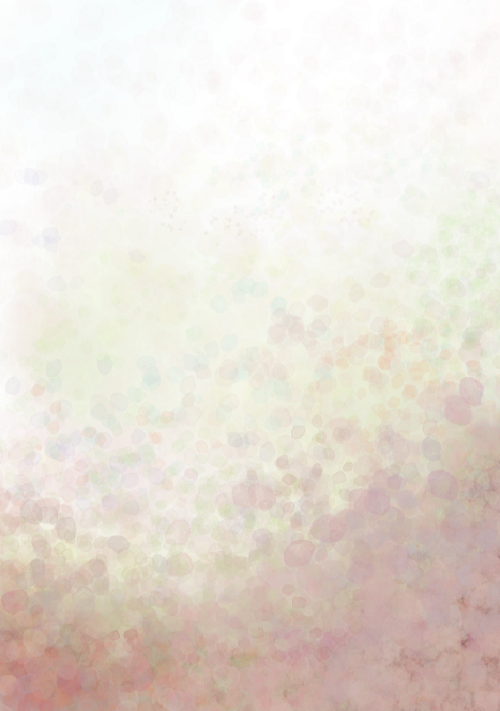
「今とっても幸せですの。ごめんあそばせ♡」 捨てられ者同士、溺れちゃうほど愛し合ってますのでお構いなく!
若松だんご
恋愛
「キサマとはやっていけない。婚約破棄だ。俺が愛してるのは、このマリアルナだ!」
婚約者である王子が開いたパーティ会場で。妹、マリアルナを伴って現れた王子。てっきり結婚の日取りなどを発表するのかと思っていたリューリアは、突然の婚約破棄、妹への婚約変更に驚き戸惑う。
「姉から妹への婚約変更。外聞も悪い。お前も噂に晒されて辛かろう。修道院で余生を過ごせ」
リューリアを慰めたり、憤慨することもない父。マリアルナが王子妃になることを手放しで喜んだ母。
二人は、これまでのリューリアの人生を振り回しただけでなく、これからの未来も勝手に決めて命じる。
四つ違いの妹。母によく似たかわいらしい妹が生まれ、母は姉であ、リューリアの育児を放棄した。
そんなリューリアを不憫に思ったのか、ただの厄介払いだったのか。田舎で暮らしていた祖母の元に預けられて育った。
両親から離れたことは寂しかったけれど、祖母は大切にしてくれたし、祖母の家のお隣、幼なじみのシオンと仲良く遊んで、それなりに楽しい幼少期だったのだけど。
「第二王子と結婚せよ」
十年前、またも家族の都合に振り回され、故郷となった町を離れ、祖母ともシオンとも別れ、未来の王子妃として厳しい教育を受けることになった。
好きになれそうにない相手だったけれど、未来の夫となる王子のために、王子に代わって政務をこなしていた。王子が遊び呆けていても、「男の人はそういうものだ」と文句すら言わせてもらえなかった。
そして、20歳のこの日。またも周囲の都合によって振り回され、周囲の都合によって未来まで決定されてしまった。
冗談じゃないわ。どれだけ人を振り回したら気が済むのよ、この人たち。
腹が立つけれど、どうしたらいいのかわからずに、従う道しか選べなかったリューリア。
せめて。せめて修道女として生きるなら、故郷で生きたい。
自分を大事にしてくれた祖母もいない、思い出だけが残る町。けど、そこで幼なじみのシオンに再会する。
シオンは、結婚していたけれど、奥さんが「真実の愛を見つけた」とかで、行方をくらましていて、最近ようやく離婚が成立したのだという。
真実の愛って、そんなゴロゴロ転がってるものなのかしら。そして、誰かを不幸に、悲しませないと得られないものなのかしら。
というか。真実もニセモノも、愛に真贋なんてあるのかしら。
捨てられた者同士。傷ついたもの同士。
いっしょにいて、いっしょに楽しんで。昔を思い出して。
傷を舐めあってるんじゃない。今を楽しみ、愛を、想いを育んでいるの。だって、わたしも彼も、幼い頃から相手が好きだったってこと、思い出したんだもの。
だから。
わたしたちの見つけた「真実の愛(笑)」、邪魔をしないでくださいな♡

イケメンエリートは愛妻の下僕になりたがる(イケメンエリートシリーズ第四弾)
便葉
恋愛
国内有数の豪華複合オフィスビルの27階にある
IT関連会社“EARTHonCIRCLE”略して“EOC”
謎多き噂の飛び交う外資系一流企業
日本内外のイケメンエリートが
集まる男のみの会社
そのイケメンエリート軍団のキャップ的存在
唯一の既婚者、中山トオルの意外なお話
中山加恋(20歳)
二十歳でトオルの妻になる
何不自由ない新婚生活だが若さゆえ好奇心旺盛
中山トオル(32歳)
17歳の加恋に一目ぼれ
加恋の二十歳の誕生日に強引に結婚する
加恋を愛し過ぎるあまりたまに壊れる
会社では群を抜くほどの超エリートが、
愛してやまない加恋ちゃんに
振り回されたり落ち込まされたり…
そんなイケメンエリートの
ちょっと切なくて笑えるお話

JKメイドはご主人様のオモチャ 命令ひとつで脱がされて、触られて、好きにされて――
のぞみ
恋愛
「今日から、お前は俺のメイドだ。ベッドの上でもな」
高校二年生の蒼井ひなたは、借金に追われた家族の代わりに、ある大富豪の家で住み込みメイドとして働くことに。
そこは、まるでおとぎ話に出てきそうな大きな洋館。
でも、そこで待っていたのは、同じ高校に通うちょっと有名な男の子――完璧だけど性格が超ドSな御曹司、天城 蓮だった。
昼間は生徒会長、夜は…ご主人様?
しかも、彼の命令はちょっと普通じゃない。
「掃除だけじゃダメだろ? ご主人様の癒しも、メイドの大事な仕事だろ?」
手を握られるたび、耳元で囁かれるたび、心臓がバクバクする。
なのに、ひなたの体はどんどん反応してしまって…。
怒ったり照れたりしながらも、次第に蓮に惹かれていくひなた。
だけど、彼にはまだ知られていない秘密があって――
「…ほんとは、ずっと前から、私…」
ただのメイドなんかじゃ終わりたくない。
恋と欲望が交差する、ちょっぴり危険な主従ラブストーリー。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















