51 / 52
集結の章 挿話─風─
reconciliation/atonement
しおりを挟む
システムの異変をいち早く感じ取ったのは、フールの回復の補佐に当たっているハイプリエステスだった。
『……?』
『入れておあげよ』
何者かの侵入を解析しようとしたハイプリエステスを、止める声がする。
ハイプリエステスが声がする方に意識を向けると、そこには、銀髪の小柄な女性が立っていた。
『やあ、久しぶりだな』
『久しぶりだね。ちっとも変わらないよ、アンタは』
遅れて姿を現した、褐色の肌の男に、銀髪の女は笑いかけた。
『そりゃあ変わらんさ。システムだからな』
そりゃそうだ、と笑い飛ばして、
『向こうは空けてていいのかい?』
『今、暫定的だが直通しているからな。移動の手間もそう掛からん』
様子を見たら直ぐ帰る、と、柔らかく男は笑う。
『あの、──』
『ああ、ハイプリエステス。
マジシャンでいいよ、アタシの事は』
いくつもの呼び名のある銀髪の女性を、どう呼ぼうかという逡巡に、女が返す。
システム01:Magitian。
そう呼べと告げた女に
『…本当に、システムになってしまったのだな』
『あの時は、別れも告げずに済まないねぇ、ドミニク』
ここからは遠く西──『学府』の地下に眠る地下迷宮のメインシステムに、マジシャンは苦笑を返す。
彼のシステムの名を正式に呼べる者は、彼一人のみ。他の者が呼べば、如何なる者でも瞬く間に呪いに蝕まれる。
それほど彼は──どれほどの時が経とうとも、まだ、誰も何も赦してはいないのだ。
『来てくれたついでだ。うちの子を診てくれないかね』
『お前らしいな。客を使うか』
『アタシじゃ手に負えなくてねぇ』
全方向に無限の広がりを見せる空間の中、3つのシステムの足元には、壊れ掛けていたシステムが、淡々と組み上げ直されていた。
冴えない壮年の男の姿に、まだ若干のノイズが入る。
その胸部から腹部に掛けて、とても小さな立方体が色を揃えて積み上げられていっている。
『己も紐解けばああなるのか?』
『アレはアタシが造った子だからねぇ。それより昔から在るシステムは、流石に全て紐解いた事はないよ』
女はかつて──まだ『学府』が今の形となる前、『地下迷宮』を作り出すシステムを紐解く者だった。何故なら──この『地下迷宮』を造り出す為だ。
『基幹システム、00:Foolだよ』
この世界にもあるタロットから名前を取った22のシステムが、この『地下迷宮』のシステムだ。
一つの基幹システムが、残り21のシステムを自在に掛け合わせて操作する事で、攻略する者達への最高難易度を叩き出す──まるで「人間」の様な動きをするシステム構築だ。
そこまでして、この迷宮が護っているものは、この世界のバランスを崩すほどの、凶悪で強力な遺物の数々──その中には、自らの意志を持つアイテムも少なくない。
その全てを、この女が、まだ『学府』が今の形となる前に発掘した。
『ほとんど直っている様に見えるが?』
『記録と記憶を手離さないせいで、パフォーマンスがガタ落ちなんだよ』
修復途中のシステムの周りを、チカチカと丸い光が走り回る。
『アレは?』
『the Fool Ⅱ。あの子の修復の為だけに生成されたシステムさね』
基幹システムの許可の上で生成された修復システムは、ヒトとしての姿形を持たない。持たせた所で意味も無いので、その分修復能力にリソースを回したのだ。おかげでFool Ⅱの生成から、確かに基幹システムの修復速度は予定よりも上がった。
しかし──長年、人間から改変させられ続けた事によるダメージはほとんど回復出来ていない。
『記録と記憶を消せば済むだろう』
『それをお前さんが言うのかい?』
基幹システムは思考だけではなく、感情も、意識も、何もかもを『人間』に近づけた。
それ故の弊害を、その基幹システム自身が手離さないのだ。
『主は』
『そのままのこの子を、慈しみ続けているよ』
マジシャンは、システムの中からずっと見て来た。
人の身でありながら、五度もやり直してまで、基幹システムが壊れない未来を望み──しかし、叶わなかった。
十余年も掛けて、救け出して、逃げて、変わり果てた我が子を連れて戻ってきた。
あまりもの我が子の姿に、マジシャンも一度は強制リセットを掛けようとしたのだ──まさか即座に阻止されるとは思っていなかったけれども。
阻止されて初めて、マジシャンは、主になった若造の中に、深い想いがあるのを知ったのだ。でなければ、出逢って最初の言葉なぞ憶えている訳がない。
『アタシの話なんぞ、ちぃっとも聞いてくれやしない。話を聞いてやってくれないかい?』
『…了解した。聞くだけ聞いてきてやろう』
────
すぐ辿り着くだろうと読んでいた、基幹システムまでの距離はそこそこあった。
『誰だい?』
すぐさま、システムの周りを飛び回っていた丸い光が、入ってきたシステムの周囲をチカチカと飛び回り始める。
『お初にお目にかかる』
自分のデータを読んでいるのだろう、と踏んで、『ドミ・ンクシャド』はその場に留まり、光が飛び回るに任せた。
──何も言わなくとも、直接この飛び回る光は、自分を『読み取る』だろう。
『上でお前達の母親から、話を聞いてきてくれと言われてな』
『マジかよあンのクソババァ』
創造主に対して何という口の利き方だ、と思うが、彼女の悪癖というか与えられた能力──『祝福』を考えると、否定はできない。
なんだかんだで彼女に結構な借りのある『ドミ・ンクシャド』ですら『あの厄ネタ』と思わずにはいられない時もあるのだ。
『彼とは、話せるか?』
『本人にその気があるなら』
組み上げている最中だから、身体は動かせない。
しかし、会話程度なら出来る、と、光の明滅が告げてくる。
Fool Ⅱは、目の前の別のシステムは手を出して来ないと疑わない。その気になれば介入し、改変できてしまうほど側にいるのに、だ。
『お前は、疑わないのだな』
『悪意は此処には入ってこれねぇ。どんな『システム』だって標準装備じゃねえのかよ』
『そんなシステムなぞ無かった頃の古物だよ、己はな』
この『試練場』に搭載されている、複数のサブシステムによる大掛かりな地下迷宮システムは、地下迷宮システムが悪意によるプログラム改竄からの自動迎撃機能が備わって無かった事が判明したが故の構成だ。
ソレを詳らかにしたのは──詳らかにしたからこそ、このシステムを組み上げられた──紛れもなく、ここのシステムと成り果てた『試練場』システムの構築者。
その功績を以て『学府』初代学長となった
メイディ・ワーダナットそのひとだ。
ふぅん、と丸い光は唸るように声を洩らすと、ふい、とまた基幹システムの方に飛び戻る。
それを是と受け止め、『ドミ・ンクシャド』は修復中の男の側に寄った。
かつての面影など微塵もない、冴えない壮年の男の髪に、そっと、優しく触れ、撫でる。
そこから、大量の情報が、二人の間を行き交う。
流石に情報の奔流を感じ取ったのか、眠る様に目を閉じていた男が、こじ開けるように瞼を上げた。
「……」
「……」
二人──二基の間に言葉は無かった。
大量の情報が行き交う速さは、発した声が相手の耳に届くよりも速い。その中から、『ドミ・ンクシャド』は、修復中のシステムにとってのいくつもの枷を見つけ出す。
(ああ、この枷どもが、この子の邪魔をするのか)
枷が無くなれば、この基幹システムは、きっとかつての性能を取り戻していくのだろう。
しかし──その枷を外すのは、このシステム自身にしか出来ない事だ。
たった一言、ソレを口にするだけでいいのに
そうしないと、始まらないのに
きっとまだ、このシステムは、主とシステムとの関係性を滅茶苦茶にされた後、その一言を口にできないでいる。
システムの精神は、肉体を持ったが故に、人と同じく、肉体に左右される様になってしまった──それこそ、ほぼ壊れた自分に、主がずっと寄り添い続けてきた事実すらも、霞んでしまうほどに。
『……怖いか?』
システムに刻まれた記録は、見るに耐え難いものだった。余程──期間が短かった自分の主の方が、まだマシに思える位には。
常人なら、壊れるであろう。
壊れ果てずに済んだのは、この男が『システム』だったから、というのもあっただろう。
(──構築者は、どうやら甘く考えている様だが)
五度の繰り返しによる蓄積は、作り直したとしても消せようもない瑕疵を、システムに刻んでしまっている。何度リセットを掛けたとしても残るであろうソレを知れば、最悪彼女の性格だ、自暴自棄になって何もかもを放り出すだろう。
(彼の者に、賭けるか)
『……怖かろうな』
ならば、その傷を抱えながらも強く、この場に在り続けるしかない。
ぽそり、と、『ドミ・ンクシャド』の口から、音が漏れた。
『だがそれでも、呼んでやれ。
己らシステムにとって『主』と呼べる存在が在る事が最上である様に──』
どちらの立場も経験したからこそ解る、重みを添えて。
『『主』と呼ばれる事こそが、地下迷宮を治める者の最上の喜びでもあるのだから、な』
───よんで、いいの、かな
はくはくと、フールが口を動かす。
口の動きの何倍もの情報が、『ドミ・ンクシャド』に流れ込む。
それはまるで、混乱と狂気が入り混じった混沌だった。
『呼ばねば、片付かんぞ』
胸部から腹部に掛けて、色を揃えて積み上げられていく無数の立方体──データの断片に手を突っ込んで一混ぜしてやれば混沌になるのだろうな、と思いながら、この哀れで愛おしいシステムが一歩を踏み出す縁となる様、祈りを込めて。
『お前の主は充分に、答えを示し続けているのだろう?』
それは痛いほど、フール自身が理解していた。
この姿で救い出されてから今までずっと、寄り添い、手を差し伸べられ続けているのも。
そこに何の打算もないことも。
長年を掛けて、肌が触れればそこから膨大な情報をやりとりできる様に作り替えられたのは、自分が「たった一言」を言えないでいたからだ。
どうなろうとも、どうあろうとも、自分が『主』と呼んでいた男は、自分を選んでいるのは明白だった。
ただ。
あの悪夢を、五度、繰り返された。
五度も、繰り返された。
それはきっと、彼が──かつての自分の姿を何処かで求めていたからではなかろうか。何も改変されない、無事な姿の自分を救い出したかったからではないだろうか。
そう思ったら、この大きくて重たい身体が憎い。変わり果ててしまったこの器が、彼がずっと寄り添ってくれたこの器が憎くて憎くて仕方がない。
側に居たい、隣に立ちたい。誰にも彼のひとの隣を開け渡したくなどない。
それなのにこの姿で──否、例え元の姿を取り戻したとしても、彼の傍に立ちたくない。
……立つ資格なぞ──
もう一度、瞼を閉じようとしたフールの脳内に小さく警鐘が鳴る。
「……!」
『え!?あ、ちょ』
同時に、フールが動いた。
いきなりの事に声を上げたFool Ⅱの頭上を、まだ組み上げ途中だったデータの欠片が舞う。
ほんの一瞬で、フールの姿が消えた。
同時に、激しく警報がその場に響く。
『なんだよもう!』
『──No.02からFool Ⅱへ。マスター・エルドナス、応戦』
『はァ?!』
『──どうやら『連れ』と何かあった様だな。己が止めよう』
いきなりの最上級緊急事態に、白い光が後ろにひっくり返って見せる様な動きを取る。
それに背を向け
『──機会があれば、また来よう』
一言残して、『ドミ・ンクシャド』はその場を離れた。
────
その頃。
「……この様な所まで、遥々と。
まだこの迷宮は正式に稼働していないのだが」
「知ってるよ」
『試練場』システムから『異常』の知らせが入ってすぐ、『アルター』は<転移>で最下層への入口に飛び、異変の元へ辿り着いた。
この迷宮の主である『アルター』であっても「迷宮の最下層へは<転移>で直に侵入できない」という不文律は如何ともしようがない。
最下層、地下十階の、最奥の玄室──『試練場』のシステムルームに一番近い部屋の真ん中に、男は居た。
兜を脇に抱えた、白銀の金属鎧の男のマントには、見慣れた懐かしい紋が刺繍されている。
ヒカリゴケの明かりでは足りないと判断し、『アルター』は懐から一枚の巻物を広げると、記された術式が発動し、玄室が魔力の灯りに満たされる。
神に祈りを捧げて起こす奇跡を封じた<明り>の巻物だ。
照らし出す時間はそこまで長くはないが、短くもないといったところか。
「……私は」
「知ってるよ。エル・ダーナス。
『学府』探索棟所属、古代種エルフとの縁組による保護の元、同じ探索棟のフェンティセーザ・スリスファーゼ及びヘリオドール・アガットに師事」
これだけでも充分に特異なのだけどね、と鎧の男は続けた。
「──メイディ・ワーダナットの宝物庫の発見者、だろう?」
男から敵意は感じられない。
が、首の後ろがひたすらチリチリする。
「オレは…そうだね」
そう、男は真正面から『アルター』に向き直る。
「あの二人の縁者なら、ちゃんと名乗ろうか」
向き直って初めて、装備の仰々しさが目の当たりとなった。
兜を被っても邪魔にならない様に短く揃えられた黒髪に、ヒノモトの民を彷彿とさせる、凛々しくもやや幼い顔立ち。
兜にも、鎧にも、両の小手にも、美しい彫刻と共に、奇跡の明かりを受けて煌めく大きな透明の石があしらわれている。ちらりと見えた剣の柄にも、同じ煌めきが見てとれた。
「オレはサトヤマシゲル。
登録名には長いからね、『シゲル』で登録しているよ。
名前から察してるかもだけど『異世界転生者』で、今はとりあえず『学府』迷宮探索棟所属の戦士さ。
異世界転生者が何のことだか分からなかったら、知ってる人に聞いてよ」
とん、と小気味良い音が響いた。
「二つ名は『<汚辱>の金剛騎士』」
続いた言葉は、『アルター』のすぐ近くから聞こえた。
────
ガギン、と重い音を立てて、シゲルの剣が姿無き盾に阻まれて跳ね返った。とん、と床を蹴ってシゲルが距離を取る。
「…すごいや、コレを防ぐなんて」
『アルター』が自分の直感に従って、小さな音がした瞬間に魔力を増幅させ、分厚い殻を作り上げたのだ。
「……いや、貴方が手加減してくれたからだ」
静かに『アルター』が返す。
「殺気も何も無い。『堕ちたる者』である貴方ほどの実力があれば、私なぞまだ何度でも斬り付けられるはず。なのに見える攻撃がたった一度だけ。これが手加減でなくて何と言う」
「ほとんどの術者は訳も分からずコレで終わるんだけどね」
シゲルはたった一撃で終わる、と軽く言ってのけるが、魔術師でも見える程度の速さの攻撃をたった一度だけいうのは相当な手加減だ、と『アルター』は分析する。
確かに、魔術師の肉体戦闘能力を考えればこれで終わる者も多いだろう。
が、『アルター』は、その目で間近で、最強の強者達の闘いぶりを飽くほどに見てきているのだ。
身体はともかく、攻撃を見切れる程度には目は鍛え上げられていた。
「貴方の名前は初めて聞くが、その二つ名は知っている」
「へぇ?」
「『学府』で師達に師事する前に、双子の少年たちに連れられて入った書庫で、その二つ名を見た」
『アルター』──エル・ダーナスと呼ばれた男は、その書庫が、世の中から秘匿された知識を収め置く『奥書庫』と呼ばれる禁足地だとは知らない。
その書庫に入るには、年齢はともかく、外観が瓜二つの双子──『学府』の下に眠る『ドミ・ンクシャドの呪いの穴』の主こと『双子王』を伴わないとならない事も、そして一度入れたからと言って、また入れるとは限らない事もだ。
そこで触れた知識は、青く若かりし彼を変えるには──夢物語を確信に変え、長く果てのない探索に駆り出すには充分だった。
『ドミ・ンクシャドの呪いの穴』の真相。
『北の古城』一帯に起こった、成り行きと経緯。
そうして、一枚の紙片に走り書きで記された『ワーダナットの地下宝物庫』の存在。
「それで、こんな辺鄙なところまで自分の迷宮を放ってまで態々やってきたのはどう言う理由でかね?
『呪いの穴』のダンジョンマスター殿」
「そんなの簡単だよ」
真っ直ぐに見据えて問うてきた『アルター』に、人の良い笑みを浮かべてシゲルが答える。
その目は、笑っていなかった。
「──お前を殺してこの迷宮の制御権を得て、メイディが集めた宝の全てを破壊する」
「言っている意味も理由も理解できないが、これは『学府』の宝だ。死ぬのも荒らされるのも御免被る」
驚くほどに冷静に『アルター』は答え、呪文を唱えた。
────
先に動いたのは『アルター』だった。
小さく呪文を唱えると、玄室全体に火の手が周り、シゲルに襲いかかる。
「……」
『アルター』は、やはりか、といった顔で、炎が収まった所に盾を構えて立つ戦士を見やる。
男──シゲルが装備するのは、『迷宮固有』の『金剛騎士の武具』。
美しい彫刻と、あしらわれた大きな金剛石が特徴の、白銀色の武具だ。
紐解いた真相から、相手が纏っているのは、一連の出来事の後に、若きドワーフの鍛治士によって造られたレプリカでしかない──が、防御力もさることながら、足の具足以外には聖霊の加護が掛けられていて、無限に奇跡や呪文の効果を具現できる。
それらを上回る一撃で削り切れなければ回復されて、そこから一撃でも撃ち込まれたら終わりだ。
方や盾に身を隠して何とか難を逃れたシゲルは『アルター』の想像以上の強さに闘争心が抑えきれなくなってきていた。
(すごい……すごい!
今の呪文ただの<火花>だった、それがドラゴンのブレス並とか…!)
嵌めていた指輪の力を解放して、炎に削り取られた体力や火傷を一気に回復させる。替わりにぐずぐずと、力を解放した指輪が砂になった。
レプリカに込められた聖霊の加護は、本物には程遠い。
武防具の力を解放させたとしても、呪文による攻撃は、あの殻の様な盾のせいで届かない。初級の呪文でこの火力を叩き出すと言うのなら護りの力も追いつかない。
もう一度、呪文を喰らって相打ち狙いで一撃を入れるしかないが、あの殻を破って尚届く一撃を叩き込めなければ終わりだ。
──しかし、『アルター』は動かない。
煌々と照らされる中、一目で分かる。
魔術師の顔は、青ざめていた。
「……私は、戦えないんだ」
声を震わせて、それでも、真っ直ぐに、魔術師は戦士を見据える。
「それでも、私はここを護らねばならん」
後ろにはシステムルームがある。
そこではフールが、今も修復中だ。
彼を起動する訳には、いかない。
この玄室の護り手たる二人の王は、それぞれが、この迷宮の構築者によって据えられた『宝物庫』に居る。喚べばすぐに来るだろうが、戦闘慣れしてないせいで自分の攻撃に巻き込むのは避けたい。
などというのは甘い考えか。
それでも、自分がこの場で斃れるなどという事は、二度とあってはならない。
システムを守り抜く為なら、何でもやる。
命を賭けるところまでできただから、今度は──生き延びる、ところまで。
『試練場』を再起動させた時のフールとは違い、この男の攻撃なら、魔力の盾や殻で攻撃を受け、いなすことも出来るし──
直ぐには詰みはしない。否、詰みにはさせない。
この場を守り抜く。
この迷宮の要であるフールを護り抜く。
「──加減は効かない」
『アルター』の、声の震えが、消えた。
その一言が、二撃目の合図だった。
(──どこから、来させる)
一言、呪文を唱えるだけでいい。
それだけの隙を稼げるだけの盾をどこにどう作るか。
全身を覆う様に殻を作るのは簡単だが、殻が持つ防御力以上の一撃を撃ち込まれたら危ない。
相手は最初から自分を殺そうとしているのだ。
だとしたら───
────
目の前の魔術師の覚悟の決まった響きと同時に、シゲルは盾を捨てて床を蹴った。
(──全力で、叩く!)
相手の動きは魔術師のものだ。魔力の盾で受け、止められても避ける事はできまい。
呪文を唱える前に、どれだけ気を逸らさせ、防御をガラ空きにさせるか。
力勝負なら、負けない。
相手もダンジョンマスターだ。殺す気でいかないと、自分が死ぬ。
────
ひとつ、ふたつ、みっつ、よっつ。
魔力の盾が、いとも容易く音を立てて消えて行く。
いつつ、むっつ。
(──ここだ!!!)
(──今だ!!!)
『アルター』に向けられた渾身の一撃を
『アルター』が創り出した魔力の盾が、はじく。
が、相殺できなかった威力で『アルター』が跳ね飛ばされて床に叩きつけられる。
「……っ……」
したたかに打ちつけた全身が痛い。
が、我を失ったフールを抱き止めた時程ではない。
(まだだ、まだだ……!)
本来なら、弾くのではなく受け流して、そのまま相手の懐に入り呪文を使うつもりだった。
見誤っていたというなら、相手の実力を──規格外であったリ・ボーをよく知るが故に、『アルター』が知識として知る中でも最古の『堕ちたる者』をまだ軽く見ていた、それだけだ。
「はは、すごいや、まだ動けてるなんて」
三撃目からもしやと思ってはいたが、七撃目のカウンターで攻撃を誘導されていた事を悟ったシゲルは、その瞬間、そのまま圧し斬るのではなく、敢えて『アルター』を弾き飛ばした。
そのまま圧し斬っていれば、この男は多少の傷を負ったとしても呪文を唱えていただろう。攻撃呪文か、弱体化か──どちらにせよ、威力はろくでもない災厄に決まっている。
初手の一撃を見抜き、恐れを抑え込んで、次の手から攻撃を誘導して誘い込む。
物理攻撃で敵わないのなんて最初っから分かっているのに、それでもただただ足掻くのではなく、意図を持って動こうとしている。
こんな魔術師は、初めてだ。
それだけ、この男が護るモノは、計り知れない価値があるのだろう。
「だけど、終わり。立たせない」
距離を一気に詰め、シゲルは剣を振るった。
────
その切先が届く事は無かった。
「……っ」
邪魔が入ったことに、シゲルが舌打ちする。
「『マスター』、ぶじ?」
二人のダンジョンマスターの間に、一本の杖を手に、痩躯の男が立ち塞がっていた。
杖の先の金色に輝く丸玉が、『アルター』に迫っていた切先を押さえて込んでいる。
「………!」
しかし、痩躯の男の姿は、まともとは言えなかった。
全身にジリジリと酷いノイズが走り、胸部には穴が貫通している。
修復中の所から無理やり飛び出して来たのだ。
移動用の器の具現化が追いついていない。
「なんで、なんでロクに実体化もしてないくせに…!」
杖と扱う腕だけを実体化させて押さえ込まれて歯軋りするシゲルに
「ここは、おいらのばしょ」
実体を徐々に纏いつつ、痩躯の男が返す。
「すきかってなんか、させるか!」
杖の先端を上手く操り、シゲルの剣先を跳ね飛ばす
「‼︎」
そしてそのまま、杖の先端が喉元を狙う。
──が、それが届く事はなかった。
「済まないが」
更なる声の乱入に、フールが、『アルター』が、そしてシゲルが、声の方に視線を向ける。
「そこまでだ。
──時間切れだ、『マスター』」
フールの杖と、シゲルの間に割り込む様に、先ほどまでシステムルームに居た褐色の肌の男が立ちはだかる。その手の── シゲルが捨てた盾が、フールの杖の先を止めていた。
「シャド…」
「そろそろ還らないと、向こうが、な」
分かった、と渋々シゲルが一歩下がる。
合わせてフールも、杖を下ろした。
「──この様な顔合わせで済まない、『試練場』のマスター。私は『ドミ・ンクシャド』。
単刀直入に聞く。
ここにメイディ・ワーダナットの『絵姿』はあるか?」
「ある」
『ドミ・ンクシャド』──『学府』の下に眠る最初期かつ最高難易度の地下迷宮の名前を口に出せるのは『呪いの穴』を創り出した本人しかいない。彼以外の者が一度口にすれば、瞬く間に呪いに蝕まれる。
──彼は、今でも、彼を裏切り、彼の唯一を傷つけた者たちを、赦してなどいないのだ。
かつて奥書庫で読んだ本の表記そのものの姿の男に、『アルター』は即答で返した。
「ただ、額縁の裏に一言『最後の一葉』と記されていて、いかなる手段を持ってしても処分できなかった」
この世界の各所に散る『学府』の徒にとって、初代学長メイディ・ワーダナットの絵姿の抹消は、最重要案件だ。例えそれがデッサン程度の物であろうと、はたまた本の裏表紙に貼られた紙片であろうと、状況が許す限り、見つけ次第焼却処分の命令が下されている。
「『最後の一葉』か。分かった。こちらでも調べてみよう。
そのまま厳重保管を願う」
「──御意」
『アルター』の返事を皮切りに、二人の姿が徐々に薄れていく。完全に消える直前、振り向いたシゲルと『アルター』の視線がかち合った。
────
極度の緊張が解けてへたり込んだ『アルター』の側に、そっとフールも腰を下ろした。
「フール…」
「?」
まだ、実体化が伴わないその胸に、『アルター』がそっと手を這わせる。
「私を……また『主』と、呼んで、くれるのか…?」
『アルター』は、自分がやった五度の巻き戻しでフールに消えない瑕疵を刻んだ事を悔いていた。
間違っていたのではないかと、ずっと自問し続けていた。
自分にとってフールは、唯一無二の存在だ。
それは今でも変わらない。
しかし、自分がフールにとっての唯一無二になるための契約まではしていなかった。
この『試練場』は、『学府』初代学長自らが創り出したモノだ。
情報をほとんど残す事なく、存在すらも匂わせる程度に留めていたその思惑を慮り、『アルター』が『地下宝物庫』の存在を秘していたのは、『王都』の介入を防ぎ、無事に『学府』に引き渡す為だ。
『学府』へ引き渡し、『地下宝物庫』の探索が出来るほどに体制を整えられれば、この迷宮の中身ごと、存在が『学府』に帰属する。
そうなった場合、特定の『主』は邪魔でしかない。
──複数の『地下迷宮』の探索・研究結果から、ダンジョンマスターの在り方が地下迷宮の在り方を左右する事が判明している以上、『アルター』は余計な癖を付けない為に『保全』を選んだのだ。
「うん。呼んでいい?」
「……私は、お前を……五度も……」
フールの胸に置いた手の甲に、額を寄せる。
「あの苦しみに、晒したのだぞ……」
────
攫われたフールを最初に取り戻した時、『アルター』──エルドナスの頭に過ったのは
「これでは、フールが壊れてしまう」
だった。
『学府』は、その地下にある『呪いの穴』の影響で、夜な夜な享楽と狂乱の坩堝と化す。
研究室という堅固な結界は所属する者たち全てには行き渡らないし、坩堝の時間になれば研究室の外にいる者は多かれ少なかれ影響を受ける。
若きエル・ダーナス自身はそういった面からは、幸運にも望まれなかったのもあって難を逃れてきたが、坩堝に呑まれ、徐々に壊れていく『学府』の徒を何人も見てきた。
老いも若きも──性別も種族を問わず、壊れていくのだが、男よりも女、それも若ければ若いほど、壊れるのは早かった。
それを見知ってたが故に、最初は過去に飛んだ。
二度、三度と繰り返すうち、もっと早く駆けつければもしかしたら間に合うのではないかと、結局五回過去に飛んだ。
でも、駄目だった。間に合わなかった。
フールに負わせ、蓄積された瑕疵を目の当たりにし、全ての感情が自分に向いた。
フールを壊して自分自身も欠片も残さず消し炭にする為に、思いつく限り最大火力の呪文を唱えた──
しかし、それも叶わなかった。
その威力は、フールが囚われていた『闇地下迷宮』を、かつての王都ごと破壊したに過ぎなかった。
瓦礫の中で、二人が居た所だけが、護られた様に無事だった。
それから後は、記憶がない。
気がついたら、遠く離れた北の国との国境付近にある辺境の村、アドロス村で匿われていた。
己を取り戻すまで、どれだけ掛かったろうか。
人間に化けた『不死なりし王』と『魔のモノ達の王』に見張られる様に隠されて、匿われて、改めてフールと向かい合った時、エルドナスの胸に去来したのは
『ああ、この姿なら、共に生きても彼が自らを壊さずに済むのではなかろうか』
──胸に宿った希望の光が示した事へのあまりもの嫌悪感に、ぴくりとも動かないフールの細った足に縋って哭いた──
────
「うん。でもマスターは、ずっとそばにいてくれた」
最後の五回目、エルドナスが自分ごと全てを焼き尽くそうと呪文を唱えた時、フールは持てる力全てを使って結界を張った。
『地下宝物庫』に続く扉を見つけ──しかしそこには『試練場』の主は探索者として入れないという事実に直面した時の、エルドナスの姿をフールは今でも鮮明に憶えている。
彼が流す血の涙を、もう見たくなかった。
壁に立てる爪に滲む血を、もう見たくなかった。
ただ一度きりの慟哭を、二度とさせてなるものかと思った。
それなのに、変わり果てた自分を抱きしめる主に、血の涙を流させ慟哭させてしまった。
──何とかして彼だけは護らないと。
ただそれだけだった。
自分は壊れていい。
完全に破壊されたら、システムが次の自分を構築し始めるはずだ──生きていればまた、主は元の場所に立てる。そうして再構築された自分と、またやっていけばいい。
きっと、主ならやっていける。
そう思っていたはずだった。
爪先に点る熱さに、己を取り戻した。
熱源に意識をやると、主が自分の足に縋って哭いていた。
そこから、部屋に灯りを灯す様に、自分という意識が、意志が、再起動していく。
それが真の地獄の始まりなのは、思考のどこかでうっすら理解していたはずなのに。
それでも──主が選んだのは再構築された自分ではなくて、今の自分だ、という喜びが、嬉しさが、再起動の強制停止の邪魔をした。
「おいらはメインオペレーションシステムだよ。
マスターとの意思疎通にはぜったいひつようだから、こわれたら、さいこうちくされるようになってる」
それは、フールがエルドナスに──『アルター』に伝えるに伝えられなかった真実だった。
それがずっと、フールに「たった一言」を言わせられなくしていた。
「さいこうちくされたおいらとやっていくみちもあったのに、おいらをえらんでくれたんだもん」
今までずっと。
『試練場』の再稼働をした時も。
Fool Ⅱがそっと伝えてくれた、再稼働時の強制リセットの一部始終が、フールの意識に、記憶に、記録に今も温かく、優しく灯る。
きゅ、と、フールの手が、『アルター』の服を掴む。
「おいらに、ダナのこと、マスターって、呼ばせてほしい。それに」
口をはくはく、とさせて、フールが勇気を振り絞った。
「…いまの、おいらのからだなら、けいやくも、できるよ…?」
自分にとっての「唯一無二」になって欲しい──システムからのお誘いを理解した『アルター』の顔が、耳が、真っ赤になっていく。
「わわ、私は……その、な」
今にも泡を噴きそうな慌てぶりの後、『アルター』が言葉を絞り出す。
「あの……その、やりかたを、しらない……から、うまく、できるかは……」
「それは、おいらがこうしてって、いうから……」
そこで、二人の会話が止まった。
盛大に照れ合い、言葉を失う二人の身体がふわりと浮かぶ。
見る者が見れば、首根っこを掴むようにして、全身に古代文字の羅列が刻まれた人型を取る魔力の塊が見えただろう。
その人型がそのまま二人を連れて、玄室の奥にある魔法陣からその場を離れる。
ひょいのひょいの、と移動した先は、領主の城の三階の、よりにもよって領主の居室だ。
魔力の塊は二人をご丁寧にもベッドの上に座らせ置くと、跡形もなく霧散した。
「……あー……」
たまたま、そこで書類を取りに来たついでに一部始終を見ていたリヴォワールドが、ベッドの上で照れ合う二人に声を掛ける。
「二階の湯殿に一番近い客間、すぐ使えるけど」
────
その日、大慌てで街を駆けずり回る『アルター』の姿を目撃されて以降、翌日から三日間、毎日街のどこかで見掛けられていた『アルター』と『フールトゥ』の姿を見た者はいなかった。
『……?』
『入れておあげよ』
何者かの侵入を解析しようとしたハイプリエステスを、止める声がする。
ハイプリエステスが声がする方に意識を向けると、そこには、銀髪の小柄な女性が立っていた。
『やあ、久しぶりだな』
『久しぶりだね。ちっとも変わらないよ、アンタは』
遅れて姿を現した、褐色の肌の男に、銀髪の女は笑いかけた。
『そりゃあ変わらんさ。システムだからな』
そりゃそうだ、と笑い飛ばして、
『向こうは空けてていいのかい?』
『今、暫定的だが直通しているからな。移動の手間もそう掛からん』
様子を見たら直ぐ帰る、と、柔らかく男は笑う。
『あの、──』
『ああ、ハイプリエステス。
マジシャンでいいよ、アタシの事は』
いくつもの呼び名のある銀髪の女性を、どう呼ぼうかという逡巡に、女が返す。
システム01:Magitian。
そう呼べと告げた女に
『…本当に、システムになってしまったのだな』
『あの時は、別れも告げずに済まないねぇ、ドミニク』
ここからは遠く西──『学府』の地下に眠る地下迷宮のメインシステムに、マジシャンは苦笑を返す。
彼のシステムの名を正式に呼べる者は、彼一人のみ。他の者が呼べば、如何なる者でも瞬く間に呪いに蝕まれる。
それほど彼は──どれほどの時が経とうとも、まだ、誰も何も赦してはいないのだ。
『来てくれたついでだ。うちの子を診てくれないかね』
『お前らしいな。客を使うか』
『アタシじゃ手に負えなくてねぇ』
全方向に無限の広がりを見せる空間の中、3つのシステムの足元には、壊れ掛けていたシステムが、淡々と組み上げ直されていた。
冴えない壮年の男の姿に、まだ若干のノイズが入る。
その胸部から腹部に掛けて、とても小さな立方体が色を揃えて積み上げられていっている。
『己も紐解けばああなるのか?』
『アレはアタシが造った子だからねぇ。それより昔から在るシステムは、流石に全て紐解いた事はないよ』
女はかつて──まだ『学府』が今の形となる前、『地下迷宮』を作り出すシステムを紐解く者だった。何故なら──この『地下迷宮』を造り出す為だ。
『基幹システム、00:Foolだよ』
この世界にもあるタロットから名前を取った22のシステムが、この『地下迷宮』のシステムだ。
一つの基幹システムが、残り21のシステムを自在に掛け合わせて操作する事で、攻略する者達への最高難易度を叩き出す──まるで「人間」の様な動きをするシステム構築だ。
そこまでして、この迷宮が護っているものは、この世界のバランスを崩すほどの、凶悪で強力な遺物の数々──その中には、自らの意志を持つアイテムも少なくない。
その全てを、この女が、まだ『学府』が今の形となる前に発掘した。
『ほとんど直っている様に見えるが?』
『記録と記憶を手離さないせいで、パフォーマンスがガタ落ちなんだよ』
修復途中のシステムの周りを、チカチカと丸い光が走り回る。
『アレは?』
『the Fool Ⅱ。あの子の修復の為だけに生成されたシステムさね』
基幹システムの許可の上で生成された修復システムは、ヒトとしての姿形を持たない。持たせた所で意味も無いので、その分修復能力にリソースを回したのだ。おかげでFool Ⅱの生成から、確かに基幹システムの修復速度は予定よりも上がった。
しかし──長年、人間から改変させられ続けた事によるダメージはほとんど回復出来ていない。
『記録と記憶を消せば済むだろう』
『それをお前さんが言うのかい?』
基幹システムは思考だけではなく、感情も、意識も、何もかもを『人間』に近づけた。
それ故の弊害を、その基幹システム自身が手離さないのだ。
『主は』
『そのままのこの子を、慈しみ続けているよ』
マジシャンは、システムの中からずっと見て来た。
人の身でありながら、五度もやり直してまで、基幹システムが壊れない未来を望み──しかし、叶わなかった。
十余年も掛けて、救け出して、逃げて、変わり果てた我が子を連れて戻ってきた。
あまりもの我が子の姿に、マジシャンも一度は強制リセットを掛けようとしたのだ──まさか即座に阻止されるとは思っていなかったけれども。
阻止されて初めて、マジシャンは、主になった若造の中に、深い想いがあるのを知ったのだ。でなければ、出逢って最初の言葉なぞ憶えている訳がない。
『アタシの話なんぞ、ちぃっとも聞いてくれやしない。話を聞いてやってくれないかい?』
『…了解した。聞くだけ聞いてきてやろう』
────
すぐ辿り着くだろうと読んでいた、基幹システムまでの距離はそこそこあった。
『誰だい?』
すぐさま、システムの周りを飛び回っていた丸い光が、入ってきたシステムの周囲をチカチカと飛び回り始める。
『お初にお目にかかる』
自分のデータを読んでいるのだろう、と踏んで、『ドミ・ンクシャド』はその場に留まり、光が飛び回るに任せた。
──何も言わなくとも、直接この飛び回る光は、自分を『読み取る』だろう。
『上でお前達の母親から、話を聞いてきてくれと言われてな』
『マジかよあンのクソババァ』
創造主に対して何という口の利き方だ、と思うが、彼女の悪癖というか与えられた能力──『祝福』を考えると、否定はできない。
なんだかんだで彼女に結構な借りのある『ドミ・ンクシャド』ですら『あの厄ネタ』と思わずにはいられない時もあるのだ。
『彼とは、話せるか?』
『本人にその気があるなら』
組み上げている最中だから、身体は動かせない。
しかし、会話程度なら出来る、と、光の明滅が告げてくる。
Fool Ⅱは、目の前の別のシステムは手を出して来ないと疑わない。その気になれば介入し、改変できてしまうほど側にいるのに、だ。
『お前は、疑わないのだな』
『悪意は此処には入ってこれねぇ。どんな『システム』だって標準装備じゃねえのかよ』
『そんなシステムなぞ無かった頃の古物だよ、己はな』
この『試練場』に搭載されている、複数のサブシステムによる大掛かりな地下迷宮システムは、地下迷宮システムが悪意によるプログラム改竄からの自動迎撃機能が備わって無かった事が判明したが故の構成だ。
ソレを詳らかにしたのは──詳らかにしたからこそ、このシステムを組み上げられた──紛れもなく、ここのシステムと成り果てた『試練場』システムの構築者。
その功績を以て『学府』初代学長となった
メイディ・ワーダナットそのひとだ。
ふぅん、と丸い光は唸るように声を洩らすと、ふい、とまた基幹システムの方に飛び戻る。
それを是と受け止め、『ドミ・ンクシャド』は修復中の男の側に寄った。
かつての面影など微塵もない、冴えない壮年の男の髪に、そっと、優しく触れ、撫でる。
そこから、大量の情報が、二人の間を行き交う。
流石に情報の奔流を感じ取ったのか、眠る様に目を閉じていた男が、こじ開けるように瞼を上げた。
「……」
「……」
二人──二基の間に言葉は無かった。
大量の情報が行き交う速さは、発した声が相手の耳に届くよりも速い。その中から、『ドミ・ンクシャド』は、修復中のシステムにとってのいくつもの枷を見つけ出す。
(ああ、この枷どもが、この子の邪魔をするのか)
枷が無くなれば、この基幹システムは、きっとかつての性能を取り戻していくのだろう。
しかし──その枷を外すのは、このシステム自身にしか出来ない事だ。
たった一言、ソレを口にするだけでいいのに
そうしないと、始まらないのに
きっとまだ、このシステムは、主とシステムとの関係性を滅茶苦茶にされた後、その一言を口にできないでいる。
システムの精神は、肉体を持ったが故に、人と同じく、肉体に左右される様になってしまった──それこそ、ほぼ壊れた自分に、主がずっと寄り添い続けてきた事実すらも、霞んでしまうほどに。
『……怖いか?』
システムに刻まれた記録は、見るに耐え難いものだった。余程──期間が短かった自分の主の方が、まだマシに思える位には。
常人なら、壊れるであろう。
壊れ果てずに済んだのは、この男が『システム』だったから、というのもあっただろう。
(──構築者は、どうやら甘く考えている様だが)
五度の繰り返しによる蓄積は、作り直したとしても消せようもない瑕疵を、システムに刻んでしまっている。何度リセットを掛けたとしても残るであろうソレを知れば、最悪彼女の性格だ、自暴自棄になって何もかもを放り出すだろう。
(彼の者に、賭けるか)
『……怖かろうな』
ならば、その傷を抱えながらも強く、この場に在り続けるしかない。
ぽそり、と、『ドミ・ンクシャド』の口から、音が漏れた。
『だがそれでも、呼んでやれ。
己らシステムにとって『主』と呼べる存在が在る事が最上である様に──』
どちらの立場も経験したからこそ解る、重みを添えて。
『『主』と呼ばれる事こそが、地下迷宮を治める者の最上の喜びでもあるのだから、な』
───よんで、いいの、かな
はくはくと、フールが口を動かす。
口の動きの何倍もの情報が、『ドミ・ンクシャド』に流れ込む。
それはまるで、混乱と狂気が入り混じった混沌だった。
『呼ばねば、片付かんぞ』
胸部から腹部に掛けて、色を揃えて積み上げられていく無数の立方体──データの断片に手を突っ込んで一混ぜしてやれば混沌になるのだろうな、と思いながら、この哀れで愛おしいシステムが一歩を踏み出す縁となる様、祈りを込めて。
『お前の主は充分に、答えを示し続けているのだろう?』
それは痛いほど、フール自身が理解していた。
この姿で救い出されてから今までずっと、寄り添い、手を差し伸べられ続けているのも。
そこに何の打算もないことも。
長年を掛けて、肌が触れればそこから膨大な情報をやりとりできる様に作り替えられたのは、自分が「たった一言」を言えないでいたからだ。
どうなろうとも、どうあろうとも、自分が『主』と呼んでいた男は、自分を選んでいるのは明白だった。
ただ。
あの悪夢を、五度、繰り返された。
五度も、繰り返された。
それはきっと、彼が──かつての自分の姿を何処かで求めていたからではなかろうか。何も改変されない、無事な姿の自分を救い出したかったからではないだろうか。
そう思ったら、この大きくて重たい身体が憎い。変わり果ててしまったこの器が、彼がずっと寄り添ってくれたこの器が憎くて憎くて仕方がない。
側に居たい、隣に立ちたい。誰にも彼のひとの隣を開け渡したくなどない。
それなのにこの姿で──否、例え元の姿を取り戻したとしても、彼の傍に立ちたくない。
……立つ資格なぞ──
もう一度、瞼を閉じようとしたフールの脳内に小さく警鐘が鳴る。
「……!」
『え!?あ、ちょ』
同時に、フールが動いた。
いきなりの事に声を上げたFool Ⅱの頭上を、まだ組み上げ途中だったデータの欠片が舞う。
ほんの一瞬で、フールの姿が消えた。
同時に、激しく警報がその場に響く。
『なんだよもう!』
『──No.02からFool Ⅱへ。マスター・エルドナス、応戦』
『はァ?!』
『──どうやら『連れ』と何かあった様だな。己が止めよう』
いきなりの最上級緊急事態に、白い光が後ろにひっくり返って見せる様な動きを取る。
それに背を向け
『──機会があれば、また来よう』
一言残して、『ドミ・ンクシャド』はその場を離れた。
────
その頃。
「……この様な所まで、遥々と。
まだこの迷宮は正式に稼働していないのだが」
「知ってるよ」
『試練場』システムから『異常』の知らせが入ってすぐ、『アルター』は<転移>で最下層への入口に飛び、異変の元へ辿り着いた。
この迷宮の主である『アルター』であっても「迷宮の最下層へは<転移>で直に侵入できない」という不文律は如何ともしようがない。
最下層、地下十階の、最奥の玄室──『試練場』のシステムルームに一番近い部屋の真ん中に、男は居た。
兜を脇に抱えた、白銀の金属鎧の男のマントには、見慣れた懐かしい紋が刺繍されている。
ヒカリゴケの明かりでは足りないと判断し、『アルター』は懐から一枚の巻物を広げると、記された術式が発動し、玄室が魔力の灯りに満たされる。
神に祈りを捧げて起こす奇跡を封じた<明り>の巻物だ。
照らし出す時間はそこまで長くはないが、短くもないといったところか。
「……私は」
「知ってるよ。エル・ダーナス。
『学府』探索棟所属、古代種エルフとの縁組による保護の元、同じ探索棟のフェンティセーザ・スリスファーゼ及びヘリオドール・アガットに師事」
これだけでも充分に特異なのだけどね、と鎧の男は続けた。
「──メイディ・ワーダナットの宝物庫の発見者、だろう?」
男から敵意は感じられない。
が、首の後ろがひたすらチリチリする。
「オレは…そうだね」
そう、男は真正面から『アルター』に向き直る。
「あの二人の縁者なら、ちゃんと名乗ろうか」
向き直って初めて、装備の仰々しさが目の当たりとなった。
兜を被っても邪魔にならない様に短く揃えられた黒髪に、ヒノモトの民を彷彿とさせる、凛々しくもやや幼い顔立ち。
兜にも、鎧にも、両の小手にも、美しい彫刻と共に、奇跡の明かりを受けて煌めく大きな透明の石があしらわれている。ちらりと見えた剣の柄にも、同じ煌めきが見てとれた。
「オレはサトヤマシゲル。
登録名には長いからね、『シゲル』で登録しているよ。
名前から察してるかもだけど『異世界転生者』で、今はとりあえず『学府』迷宮探索棟所属の戦士さ。
異世界転生者が何のことだか分からなかったら、知ってる人に聞いてよ」
とん、と小気味良い音が響いた。
「二つ名は『<汚辱>の金剛騎士』」
続いた言葉は、『アルター』のすぐ近くから聞こえた。
────
ガギン、と重い音を立てて、シゲルの剣が姿無き盾に阻まれて跳ね返った。とん、と床を蹴ってシゲルが距離を取る。
「…すごいや、コレを防ぐなんて」
『アルター』が自分の直感に従って、小さな音がした瞬間に魔力を増幅させ、分厚い殻を作り上げたのだ。
「……いや、貴方が手加減してくれたからだ」
静かに『アルター』が返す。
「殺気も何も無い。『堕ちたる者』である貴方ほどの実力があれば、私なぞまだ何度でも斬り付けられるはず。なのに見える攻撃がたった一度だけ。これが手加減でなくて何と言う」
「ほとんどの術者は訳も分からずコレで終わるんだけどね」
シゲルはたった一撃で終わる、と軽く言ってのけるが、魔術師でも見える程度の速さの攻撃をたった一度だけいうのは相当な手加減だ、と『アルター』は分析する。
確かに、魔術師の肉体戦闘能力を考えればこれで終わる者も多いだろう。
が、『アルター』は、その目で間近で、最強の強者達の闘いぶりを飽くほどに見てきているのだ。
身体はともかく、攻撃を見切れる程度には目は鍛え上げられていた。
「貴方の名前は初めて聞くが、その二つ名は知っている」
「へぇ?」
「『学府』で師達に師事する前に、双子の少年たちに連れられて入った書庫で、その二つ名を見た」
『アルター』──エル・ダーナスと呼ばれた男は、その書庫が、世の中から秘匿された知識を収め置く『奥書庫』と呼ばれる禁足地だとは知らない。
その書庫に入るには、年齢はともかく、外観が瓜二つの双子──『学府』の下に眠る『ドミ・ンクシャドの呪いの穴』の主こと『双子王』を伴わないとならない事も、そして一度入れたからと言って、また入れるとは限らない事もだ。
そこで触れた知識は、青く若かりし彼を変えるには──夢物語を確信に変え、長く果てのない探索に駆り出すには充分だった。
『ドミ・ンクシャドの呪いの穴』の真相。
『北の古城』一帯に起こった、成り行きと経緯。
そうして、一枚の紙片に走り書きで記された『ワーダナットの地下宝物庫』の存在。
「それで、こんな辺鄙なところまで自分の迷宮を放ってまで態々やってきたのはどう言う理由でかね?
『呪いの穴』のダンジョンマスター殿」
「そんなの簡単だよ」
真っ直ぐに見据えて問うてきた『アルター』に、人の良い笑みを浮かべてシゲルが答える。
その目は、笑っていなかった。
「──お前を殺してこの迷宮の制御権を得て、メイディが集めた宝の全てを破壊する」
「言っている意味も理由も理解できないが、これは『学府』の宝だ。死ぬのも荒らされるのも御免被る」
驚くほどに冷静に『アルター』は答え、呪文を唱えた。
────
先に動いたのは『アルター』だった。
小さく呪文を唱えると、玄室全体に火の手が周り、シゲルに襲いかかる。
「……」
『アルター』は、やはりか、といった顔で、炎が収まった所に盾を構えて立つ戦士を見やる。
男──シゲルが装備するのは、『迷宮固有』の『金剛騎士の武具』。
美しい彫刻と、あしらわれた大きな金剛石が特徴の、白銀色の武具だ。
紐解いた真相から、相手が纏っているのは、一連の出来事の後に、若きドワーフの鍛治士によって造られたレプリカでしかない──が、防御力もさることながら、足の具足以外には聖霊の加護が掛けられていて、無限に奇跡や呪文の効果を具現できる。
それらを上回る一撃で削り切れなければ回復されて、そこから一撃でも撃ち込まれたら終わりだ。
方や盾に身を隠して何とか難を逃れたシゲルは『アルター』の想像以上の強さに闘争心が抑えきれなくなってきていた。
(すごい……すごい!
今の呪文ただの<火花>だった、それがドラゴンのブレス並とか…!)
嵌めていた指輪の力を解放して、炎に削り取られた体力や火傷を一気に回復させる。替わりにぐずぐずと、力を解放した指輪が砂になった。
レプリカに込められた聖霊の加護は、本物には程遠い。
武防具の力を解放させたとしても、呪文による攻撃は、あの殻の様な盾のせいで届かない。初級の呪文でこの火力を叩き出すと言うのなら護りの力も追いつかない。
もう一度、呪文を喰らって相打ち狙いで一撃を入れるしかないが、あの殻を破って尚届く一撃を叩き込めなければ終わりだ。
──しかし、『アルター』は動かない。
煌々と照らされる中、一目で分かる。
魔術師の顔は、青ざめていた。
「……私は、戦えないんだ」
声を震わせて、それでも、真っ直ぐに、魔術師は戦士を見据える。
「それでも、私はここを護らねばならん」
後ろにはシステムルームがある。
そこではフールが、今も修復中だ。
彼を起動する訳には、いかない。
この玄室の護り手たる二人の王は、それぞれが、この迷宮の構築者によって据えられた『宝物庫』に居る。喚べばすぐに来るだろうが、戦闘慣れしてないせいで自分の攻撃に巻き込むのは避けたい。
などというのは甘い考えか。
それでも、自分がこの場で斃れるなどという事は、二度とあってはならない。
システムを守り抜く為なら、何でもやる。
命を賭けるところまでできただから、今度は──生き延びる、ところまで。
『試練場』を再起動させた時のフールとは違い、この男の攻撃なら、魔力の盾や殻で攻撃を受け、いなすことも出来るし──
直ぐには詰みはしない。否、詰みにはさせない。
この場を守り抜く。
この迷宮の要であるフールを護り抜く。
「──加減は効かない」
『アルター』の、声の震えが、消えた。
その一言が、二撃目の合図だった。
(──どこから、来させる)
一言、呪文を唱えるだけでいい。
それだけの隙を稼げるだけの盾をどこにどう作るか。
全身を覆う様に殻を作るのは簡単だが、殻が持つ防御力以上の一撃を撃ち込まれたら危ない。
相手は最初から自分を殺そうとしているのだ。
だとしたら───
────
目の前の魔術師の覚悟の決まった響きと同時に、シゲルは盾を捨てて床を蹴った。
(──全力で、叩く!)
相手の動きは魔術師のものだ。魔力の盾で受け、止められても避ける事はできまい。
呪文を唱える前に、どれだけ気を逸らさせ、防御をガラ空きにさせるか。
力勝負なら、負けない。
相手もダンジョンマスターだ。殺す気でいかないと、自分が死ぬ。
────
ひとつ、ふたつ、みっつ、よっつ。
魔力の盾が、いとも容易く音を立てて消えて行く。
いつつ、むっつ。
(──ここだ!!!)
(──今だ!!!)
『アルター』に向けられた渾身の一撃を
『アルター』が創り出した魔力の盾が、はじく。
が、相殺できなかった威力で『アルター』が跳ね飛ばされて床に叩きつけられる。
「……っ……」
したたかに打ちつけた全身が痛い。
が、我を失ったフールを抱き止めた時程ではない。
(まだだ、まだだ……!)
本来なら、弾くのではなく受け流して、そのまま相手の懐に入り呪文を使うつもりだった。
見誤っていたというなら、相手の実力を──規格外であったリ・ボーをよく知るが故に、『アルター』が知識として知る中でも最古の『堕ちたる者』をまだ軽く見ていた、それだけだ。
「はは、すごいや、まだ動けてるなんて」
三撃目からもしやと思ってはいたが、七撃目のカウンターで攻撃を誘導されていた事を悟ったシゲルは、その瞬間、そのまま圧し斬るのではなく、敢えて『アルター』を弾き飛ばした。
そのまま圧し斬っていれば、この男は多少の傷を負ったとしても呪文を唱えていただろう。攻撃呪文か、弱体化か──どちらにせよ、威力はろくでもない災厄に決まっている。
初手の一撃を見抜き、恐れを抑え込んで、次の手から攻撃を誘導して誘い込む。
物理攻撃で敵わないのなんて最初っから分かっているのに、それでもただただ足掻くのではなく、意図を持って動こうとしている。
こんな魔術師は、初めてだ。
それだけ、この男が護るモノは、計り知れない価値があるのだろう。
「だけど、終わり。立たせない」
距離を一気に詰め、シゲルは剣を振るった。
────
その切先が届く事は無かった。
「……っ」
邪魔が入ったことに、シゲルが舌打ちする。
「『マスター』、ぶじ?」
二人のダンジョンマスターの間に、一本の杖を手に、痩躯の男が立ち塞がっていた。
杖の先の金色に輝く丸玉が、『アルター』に迫っていた切先を押さえて込んでいる。
「………!」
しかし、痩躯の男の姿は、まともとは言えなかった。
全身にジリジリと酷いノイズが走り、胸部には穴が貫通している。
修復中の所から無理やり飛び出して来たのだ。
移動用の器の具現化が追いついていない。
「なんで、なんでロクに実体化もしてないくせに…!」
杖と扱う腕だけを実体化させて押さえ込まれて歯軋りするシゲルに
「ここは、おいらのばしょ」
実体を徐々に纏いつつ、痩躯の男が返す。
「すきかってなんか、させるか!」
杖の先端を上手く操り、シゲルの剣先を跳ね飛ばす
「‼︎」
そしてそのまま、杖の先端が喉元を狙う。
──が、それが届く事はなかった。
「済まないが」
更なる声の乱入に、フールが、『アルター』が、そしてシゲルが、声の方に視線を向ける。
「そこまでだ。
──時間切れだ、『マスター』」
フールの杖と、シゲルの間に割り込む様に、先ほどまでシステムルームに居た褐色の肌の男が立ちはだかる。その手の── シゲルが捨てた盾が、フールの杖の先を止めていた。
「シャド…」
「そろそろ還らないと、向こうが、な」
分かった、と渋々シゲルが一歩下がる。
合わせてフールも、杖を下ろした。
「──この様な顔合わせで済まない、『試練場』のマスター。私は『ドミ・ンクシャド』。
単刀直入に聞く。
ここにメイディ・ワーダナットの『絵姿』はあるか?」
「ある」
『ドミ・ンクシャド』──『学府』の下に眠る最初期かつ最高難易度の地下迷宮の名前を口に出せるのは『呪いの穴』を創り出した本人しかいない。彼以外の者が一度口にすれば、瞬く間に呪いに蝕まれる。
──彼は、今でも、彼を裏切り、彼の唯一を傷つけた者たちを、赦してなどいないのだ。
かつて奥書庫で読んだ本の表記そのものの姿の男に、『アルター』は即答で返した。
「ただ、額縁の裏に一言『最後の一葉』と記されていて、いかなる手段を持ってしても処分できなかった」
この世界の各所に散る『学府』の徒にとって、初代学長メイディ・ワーダナットの絵姿の抹消は、最重要案件だ。例えそれがデッサン程度の物であろうと、はたまた本の裏表紙に貼られた紙片であろうと、状況が許す限り、見つけ次第焼却処分の命令が下されている。
「『最後の一葉』か。分かった。こちらでも調べてみよう。
そのまま厳重保管を願う」
「──御意」
『アルター』の返事を皮切りに、二人の姿が徐々に薄れていく。完全に消える直前、振り向いたシゲルと『アルター』の視線がかち合った。
────
極度の緊張が解けてへたり込んだ『アルター』の側に、そっとフールも腰を下ろした。
「フール…」
「?」
まだ、実体化が伴わないその胸に、『アルター』がそっと手を這わせる。
「私を……また『主』と、呼んで、くれるのか…?」
『アルター』は、自分がやった五度の巻き戻しでフールに消えない瑕疵を刻んだ事を悔いていた。
間違っていたのではないかと、ずっと自問し続けていた。
自分にとってフールは、唯一無二の存在だ。
それは今でも変わらない。
しかし、自分がフールにとっての唯一無二になるための契約まではしていなかった。
この『試練場』は、『学府』初代学長自らが創り出したモノだ。
情報をほとんど残す事なく、存在すらも匂わせる程度に留めていたその思惑を慮り、『アルター』が『地下宝物庫』の存在を秘していたのは、『王都』の介入を防ぎ、無事に『学府』に引き渡す為だ。
『学府』へ引き渡し、『地下宝物庫』の探索が出来るほどに体制を整えられれば、この迷宮の中身ごと、存在が『学府』に帰属する。
そうなった場合、特定の『主』は邪魔でしかない。
──複数の『地下迷宮』の探索・研究結果から、ダンジョンマスターの在り方が地下迷宮の在り方を左右する事が判明している以上、『アルター』は余計な癖を付けない為に『保全』を選んだのだ。
「うん。呼んでいい?」
「……私は、お前を……五度も……」
フールの胸に置いた手の甲に、額を寄せる。
「あの苦しみに、晒したのだぞ……」
────
攫われたフールを最初に取り戻した時、『アルター』──エルドナスの頭に過ったのは
「これでは、フールが壊れてしまう」
だった。
『学府』は、その地下にある『呪いの穴』の影響で、夜な夜な享楽と狂乱の坩堝と化す。
研究室という堅固な結界は所属する者たち全てには行き渡らないし、坩堝の時間になれば研究室の外にいる者は多かれ少なかれ影響を受ける。
若きエル・ダーナス自身はそういった面からは、幸運にも望まれなかったのもあって難を逃れてきたが、坩堝に呑まれ、徐々に壊れていく『学府』の徒を何人も見てきた。
老いも若きも──性別も種族を問わず、壊れていくのだが、男よりも女、それも若ければ若いほど、壊れるのは早かった。
それを見知ってたが故に、最初は過去に飛んだ。
二度、三度と繰り返すうち、もっと早く駆けつければもしかしたら間に合うのではないかと、結局五回過去に飛んだ。
でも、駄目だった。間に合わなかった。
フールに負わせ、蓄積された瑕疵を目の当たりにし、全ての感情が自分に向いた。
フールを壊して自分自身も欠片も残さず消し炭にする為に、思いつく限り最大火力の呪文を唱えた──
しかし、それも叶わなかった。
その威力は、フールが囚われていた『闇地下迷宮』を、かつての王都ごと破壊したに過ぎなかった。
瓦礫の中で、二人が居た所だけが、護られた様に無事だった。
それから後は、記憶がない。
気がついたら、遠く離れた北の国との国境付近にある辺境の村、アドロス村で匿われていた。
己を取り戻すまで、どれだけ掛かったろうか。
人間に化けた『不死なりし王』と『魔のモノ達の王』に見張られる様に隠されて、匿われて、改めてフールと向かい合った時、エルドナスの胸に去来したのは
『ああ、この姿なら、共に生きても彼が自らを壊さずに済むのではなかろうか』
──胸に宿った希望の光が示した事へのあまりもの嫌悪感に、ぴくりとも動かないフールの細った足に縋って哭いた──
────
「うん。でもマスターは、ずっとそばにいてくれた」
最後の五回目、エルドナスが自分ごと全てを焼き尽くそうと呪文を唱えた時、フールは持てる力全てを使って結界を張った。
『地下宝物庫』に続く扉を見つけ──しかしそこには『試練場』の主は探索者として入れないという事実に直面した時の、エルドナスの姿をフールは今でも鮮明に憶えている。
彼が流す血の涙を、もう見たくなかった。
壁に立てる爪に滲む血を、もう見たくなかった。
ただ一度きりの慟哭を、二度とさせてなるものかと思った。
それなのに、変わり果てた自分を抱きしめる主に、血の涙を流させ慟哭させてしまった。
──何とかして彼だけは護らないと。
ただそれだけだった。
自分は壊れていい。
完全に破壊されたら、システムが次の自分を構築し始めるはずだ──生きていればまた、主は元の場所に立てる。そうして再構築された自分と、またやっていけばいい。
きっと、主ならやっていける。
そう思っていたはずだった。
爪先に点る熱さに、己を取り戻した。
熱源に意識をやると、主が自分の足に縋って哭いていた。
そこから、部屋に灯りを灯す様に、自分という意識が、意志が、再起動していく。
それが真の地獄の始まりなのは、思考のどこかでうっすら理解していたはずなのに。
それでも──主が選んだのは再構築された自分ではなくて、今の自分だ、という喜びが、嬉しさが、再起動の強制停止の邪魔をした。
「おいらはメインオペレーションシステムだよ。
マスターとの意思疎通にはぜったいひつようだから、こわれたら、さいこうちくされるようになってる」
それは、フールがエルドナスに──『アルター』に伝えるに伝えられなかった真実だった。
それがずっと、フールに「たった一言」を言わせられなくしていた。
「さいこうちくされたおいらとやっていくみちもあったのに、おいらをえらんでくれたんだもん」
今までずっと。
『試練場』の再稼働をした時も。
Fool Ⅱがそっと伝えてくれた、再稼働時の強制リセットの一部始終が、フールの意識に、記憶に、記録に今も温かく、優しく灯る。
きゅ、と、フールの手が、『アルター』の服を掴む。
「おいらに、ダナのこと、マスターって、呼ばせてほしい。それに」
口をはくはく、とさせて、フールが勇気を振り絞った。
「…いまの、おいらのからだなら、けいやくも、できるよ…?」
自分にとっての「唯一無二」になって欲しい──システムからのお誘いを理解した『アルター』の顔が、耳が、真っ赤になっていく。
「わわ、私は……その、な」
今にも泡を噴きそうな慌てぶりの後、『アルター』が言葉を絞り出す。
「あの……その、やりかたを、しらない……から、うまく、できるかは……」
「それは、おいらがこうしてって、いうから……」
そこで、二人の会話が止まった。
盛大に照れ合い、言葉を失う二人の身体がふわりと浮かぶ。
見る者が見れば、首根っこを掴むようにして、全身に古代文字の羅列が刻まれた人型を取る魔力の塊が見えただろう。
その人型がそのまま二人を連れて、玄室の奥にある魔法陣からその場を離れる。
ひょいのひょいの、と移動した先は、領主の城の三階の、よりにもよって領主の居室だ。
魔力の塊は二人をご丁寧にもベッドの上に座らせ置くと、跡形もなく霧散した。
「……あー……」
たまたま、そこで書類を取りに来たついでに一部始終を見ていたリヴォワールドが、ベッドの上で照れ合う二人に声を掛ける。
「二階の湯殿に一番近い客間、すぐ使えるけど」
────
その日、大慌てで街を駆けずり回る『アルター』の姿を目撃されて以降、翌日から三日間、毎日街のどこかで見掛けられていた『アルター』と『フールトゥ』の姿を見た者はいなかった。
0
あなたにおすすめの小説

敵に貞操を奪われて癒しの力を失うはずだった聖女ですが、なぜか前より漲っています
藤谷 要
恋愛
サルサン国の聖女たちは、隣国に征服される際に自国の王の命で殺されそうになった。ところが、侵略軍将帥のマトルヘル侯爵に助けられた。それから聖女たちは侵略国に仕えるようになったが、一か月後に筆頭聖女だったルミネラは命の恩人の侯爵へ嫁ぐように国王から命じられる。
結婚披露宴では、陛下に側妃として嫁いだ旧サルサン国王女が出席していたが、彼女は侯爵に腕を絡めて「陛下の手がつかなかったら一年後に妻にしてほしい」と頼んでいた。しかも、侯爵はその手を振り払いもしない。
聖女は愛のない交わりで神の加護を失うとされているので、当然白い結婚だと思っていたが、初夜に侯爵のメイアスから体の関係を迫られる。彼は命の恩人だったので、ルミネラはそのまま彼を受け入れた。
侯爵がかつての恋人に似ていたとはいえ、侯爵と孤児だった彼は全く別人。愛のない交わりだったので、当然力を失うと思っていたが、なぜか以前よりも力が漲っていた。
※全11話 2万字程度の話です。

第3皇子は妃よりも騎士団長の妹の私を溺愛している 【完結】
日下奈緒
恋愛
王家に仕える騎士の妹・リリアーナは、冷徹と噂される第3皇子アシュレイに密かに想いを寄せていた。戦の前夜、命を懸けた一戦を前に、彼のもとを訪ね純潔を捧げる。勝利の凱旋後も、皇子は毎夜彼女を呼び続け、やがてリリアーナは身籠る。正妃に拒まれていた皇子は離縁を決意し、すべてを捨ててリリアーナを正式な妃として迎える——これは、禁じられた愛が真実の絆へと変わる、激甘ロマンス。

王様の恥かきっ娘
青の雀
恋愛
恥かきっ子とは、親が年老いてから子供ができること。
本当は、元気でおめでたいことだけど、照れ隠しで、その年齢まで夫婦の営みがあったことを物語り世間様に向けての恥をいう。
孫と同い年の王女殿下が生まれたことで巻き起こる騒動を書きます
物語は、卒業記念パーティで婚約者から婚約破棄されたところから始まります
これもショートショートで書く予定です。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

敗戦国の姫は、敵国将軍に掠奪される
clayclay
恋愛
架空の国アルバ国は、ブリタニア国に侵略され、国は壊滅状態となる。
状況を打破するため、アルバ国王は娘のソフィアに、ブリタニア国使者への「接待」を命じたが……。
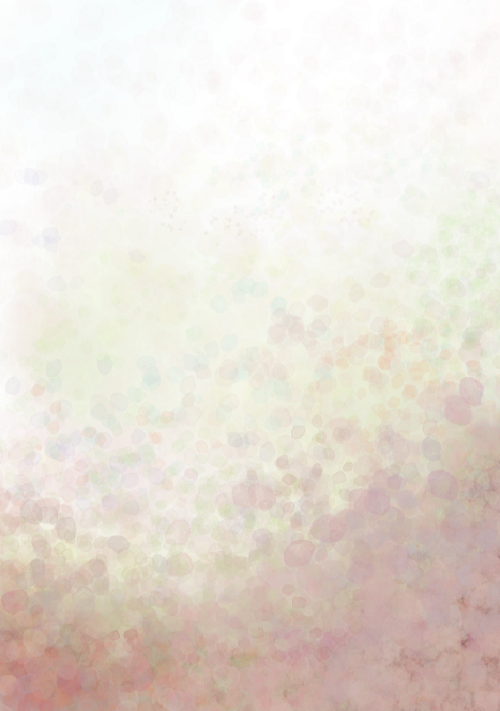
「今とっても幸せですの。ごめんあそばせ♡」 捨てられ者同士、溺れちゃうほど愛し合ってますのでお構いなく!
若松だんご
恋愛
「キサマとはやっていけない。婚約破棄だ。俺が愛してるのは、このマリアルナだ!」
婚約者である王子が開いたパーティ会場で。妹、マリアルナを伴って現れた王子。てっきり結婚の日取りなどを発表するのかと思っていたリューリアは、突然の婚約破棄、妹への婚約変更に驚き戸惑う。
「姉から妹への婚約変更。外聞も悪い。お前も噂に晒されて辛かろう。修道院で余生を過ごせ」
リューリアを慰めたり、憤慨することもない父。マリアルナが王子妃になることを手放しで喜んだ母。
二人は、これまでのリューリアの人生を振り回しただけでなく、これからの未来も勝手に決めて命じる。
四つ違いの妹。母によく似たかわいらしい妹が生まれ、母は姉であ、リューリアの育児を放棄した。
そんなリューリアを不憫に思ったのか、ただの厄介払いだったのか。田舎で暮らしていた祖母の元に預けられて育った。
両親から離れたことは寂しかったけれど、祖母は大切にしてくれたし、祖母の家のお隣、幼なじみのシオンと仲良く遊んで、それなりに楽しい幼少期だったのだけど。
「第二王子と結婚せよ」
十年前、またも家族の都合に振り回され、故郷となった町を離れ、祖母ともシオンとも別れ、未来の王子妃として厳しい教育を受けることになった。
好きになれそうにない相手だったけれど、未来の夫となる王子のために、王子に代わって政務をこなしていた。王子が遊び呆けていても、「男の人はそういうものだ」と文句すら言わせてもらえなかった。
そして、20歳のこの日。またも周囲の都合によって振り回され、周囲の都合によって未来まで決定されてしまった。
冗談じゃないわ。どれだけ人を振り回したら気が済むのよ、この人たち。
腹が立つけれど、どうしたらいいのかわからずに、従う道しか選べなかったリューリア。
せめて。せめて修道女として生きるなら、故郷で生きたい。
自分を大事にしてくれた祖母もいない、思い出だけが残る町。けど、そこで幼なじみのシオンに再会する。
シオンは、結婚していたけれど、奥さんが「真実の愛を見つけた」とかで、行方をくらましていて、最近ようやく離婚が成立したのだという。
真実の愛って、そんなゴロゴロ転がってるものなのかしら。そして、誰かを不幸に、悲しませないと得られないものなのかしら。
というか。真実もニセモノも、愛に真贋なんてあるのかしら。
捨てられた者同士。傷ついたもの同士。
いっしょにいて、いっしょに楽しんで。昔を思い出して。
傷を舐めあってるんじゃない。今を楽しみ、愛を、想いを育んでいるの。だって、わたしも彼も、幼い頃から相手が好きだったってこと、思い出したんだもの。
だから。
わたしたちの見つけた「真実の愛(笑)」、邪魔をしないでくださいな♡

イケメンエリートは愛妻の下僕になりたがる(イケメンエリートシリーズ第四弾)
便葉
恋愛
国内有数の豪華複合オフィスビルの27階にある
IT関連会社“EARTHonCIRCLE”略して“EOC”
謎多き噂の飛び交う外資系一流企業
日本内外のイケメンエリートが
集まる男のみの会社
そのイケメンエリート軍団のキャップ的存在
唯一の既婚者、中山トオルの意外なお話
中山加恋(20歳)
二十歳でトオルの妻になる
何不自由ない新婚生活だが若さゆえ好奇心旺盛
中山トオル(32歳)
17歳の加恋に一目ぼれ
加恋の二十歳の誕生日に強引に結婚する
加恋を愛し過ぎるあまりたまに壊れる
会社では群を抜くほどの超エリートが、
愛してやまない加恋ちゃんに
振り回されたり落ち込まされたり…
そんなイケメンエリートの
ちょっと切なくて笑えるお話

JKメイドはご主人様のオモチャ 命令ひとつで脱がされて、触られて、好きにされて――
のぞみ
恋愛
「今日から、お前は俺のメイドだ。ベッドの上でもな」
高校二年生の蒼井ひなたは、借金に追われた家族の代わりに、ある大富豪の家で住み込みメイドとして働くことに。
そこは、まるでおとぎ話に出てきそうな大きな洋館。
でも、そこで待っていたのは、同じ高校に通うちょっと有名な男の子――完璧だけど性格が超ドSな御曹司、天城 蓮だった。
昼間は生徒会長、夜は…ご主人様?
しかも、彼の命令はちょっと普通じゃない。
「掃除だけじゃダメだろ? ご主人様の癒しも、メイドの大事な仕事だろ?」
手を握られるたび、耳元で囁かれるたび、心臓がバクバクする。
なのに、ひなたの体はどんどん反応してしまって…。
怒ったり照れたりしながらも、次第に蓮に惹かれていくひなた。
だけど、彼にはまだ知られていない秘密があって――
「…ほんとは、ずっと前から、私…」
ただのメイドなんかじゃ終わりたくない。
恋と欲望が交差する、ちょっぴり危険な主従ラブストーリー。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















