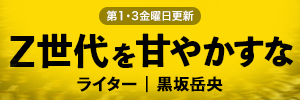教員不足を起こした真の問題点、やるべきは教職科目の単位削減ではない!採用倍率という“数字”でない政策目標を
2026.01.16
Wedge ONLINE
表向きの目的は、「学ぶべき内容の最適化」や「専門性を伸ばしやすい教職課程の実現」とされている。しかし、深刻化する教員不足を前に、この説明を額面通りに受け取る教育関係者は多くないだろう。
専門職の価値を自ら下げる危うさ
確かに、従来の教員免許制度には課題もあった。とりわけ小・中学校免許は、取得に必要な単位数や実習要件が多く、教育学部を擁する国立大学に履修環境が集中しやすいなど、制度の硬直性は否定できない。
しかし、単位数削減という形で入口のハードルを下げることは、「誰でもなれる仕事」というメッセージを社会に発信することにもなる。それは志望者の裾野を広げるどころか、教職への憧れや信頼を損ないかねない。
単位数削減は、教員不足問題に対して、教員という専門職の価値そのものを切り下げる政策に他ならない。
教師はなぜ教師になろうとするのか
教員志望者減少の本質を考えるためには、「人はなぜ教員になろうとしてきたのか」を問い直す必要がある。
「本邦における小中学校教師の教職を志望する動機に関する検討」(三和秀平・信州大学学術研究院教育学系ほか、2023年)によれば、教職志望の主な理由として、①教えること自体への興味ややりがい、②子どもの成長に関わることへの価値意識、③尊敬できる教師との出会い、④社会的意義や公共性への志向、などが挙げられている。
これらの動機は、教員という仕事が「人格的影響力を持つ専門職」として社会から信頼され、必要とされてきたことが、志望理由として重要であったことを示唆している。
しかし、現在インターネットやSNSの普及によって、教員の長時間労働や過剰な業務負担は広く可視化され、学生の教職志望に大きな影響を与えている。教員志望学生が教職を敬遠する理由として、「過酷な労働環境」「本来業務以外の仕事の多さ」「待遇の低さ」が上位を占めている。
重要なのは、彼らがまだ教壇に立つ前段階で、教員という仕事の魅力に触れることなく離脱している点である。制度や環境への不信が、入口に立つ前から志望動機を削いでいる。
多くの現場教員は、教員の資質が採用時点で完成しているものではなく、その後の育成環境や学校組織の文化、管理職のマネジメントによって大きく左右されることを実感している。
実際には学校現場における同僚性のもとに行われる継続的な研修が、教員としての成長を決定づける。それにもかかわらず、採用倍率という数字で追及され続ける行政が偏った政策へと引き寄せてしまう。その結果、制度の根幹である免許制度にまで、場当たり的な介入が及ぶ。
教員不足は「人材政策」ではなく「統治」の問題
教員不足は、単なる人材確保の失敗によって生じたものではない。本来の原因は、教育をサービス産業化へと導いてきた統治の失敗にある。
国民は教育者に集金事務や過剰な保護者対応、際限のない部活動指導といった「サービスとしての充実」を求め、政治家と行政はその要求を受け入れた。結果的に学校のブラック化を加速させている。
そうした過重労働は、長らく教員の使命感によって吸収されてきた。悲劇は、その吸収力がすでに限界を超えていたことに、教員のなり手がいなくなるまで、誰も気づかなかったことにある。
必要なのは国が「教員」という専門職をもつ覚悟
教員不足への対策として、入口を広げ続けることはできるかもしれない。しかし、過度な要求に迎合し、教員が本来の業務に専門職として成長し続けられる環境を塞いだままでは、いずれ学校教育制度そのものが立ち行かなくなる。
法律上、教員の職務は、児童生徒の「教育をつかさどる」ことにある。求められてきた「サービス」は、教員の専門性とは言い難い。
教育のサービス産業化に歯止めをかけるとともに、定数改善、業務の切り分け、部活動を含む教職外業務の外部化を実効性ある形で進める必要がある。そうして初めて、教員が授業力や生徒指導力といった専門性を成長させ続けられる環境が整う。
遠回りに見えるかもしれないが、これこそが最も確実な教員不足対策である。今、問われているのは、教員という専門職を本気で育て、守る覚悟が、政策決定者にあるのかどうかである。