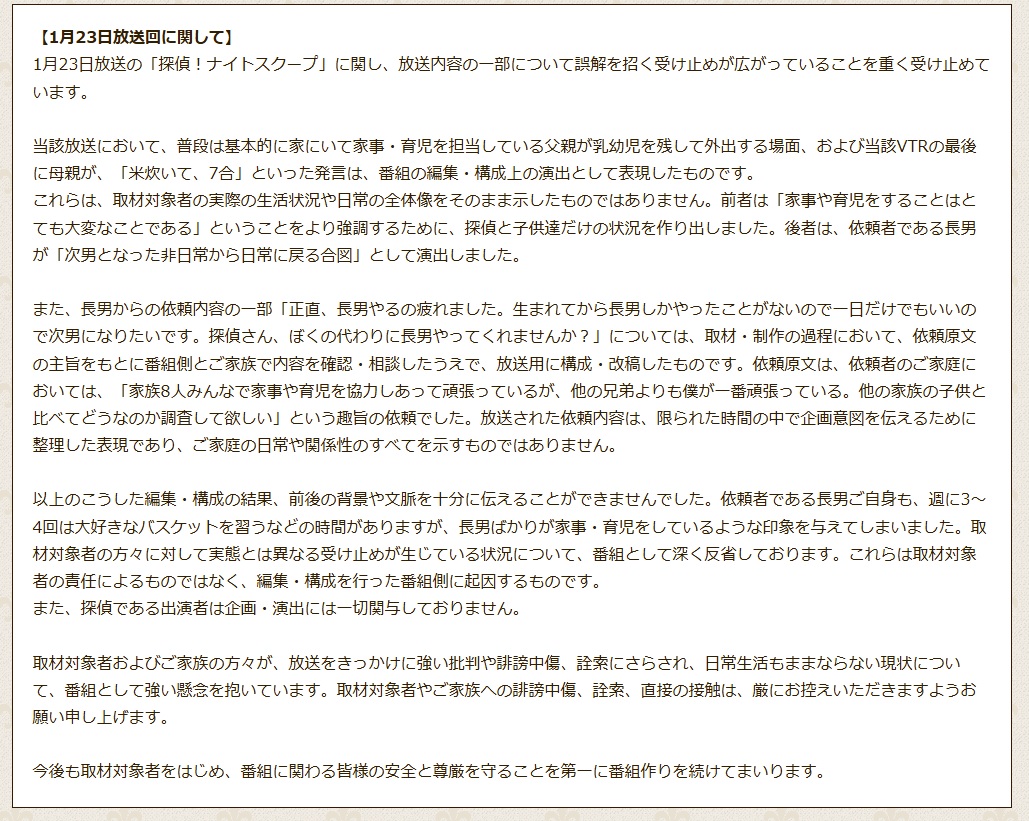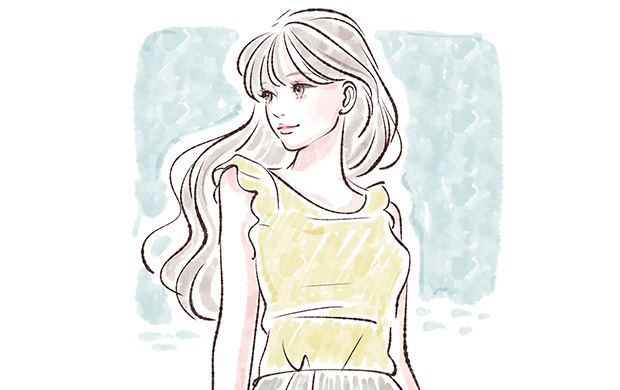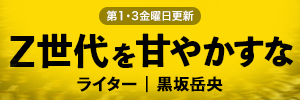『探偵!ナイトスクープ』炎上騒動から考える「やさしさ」の功罪…SNSによる「正義の鉄槌」、家族への批判が子どもを助けるのか?
2026.02.04
Wedge ONLINE
バラエティー番組の企画が、SNSという巨大な鏡を通じて現代社会の複雑な断面を浮き彫りにした。朝日放送テレビの『探偵!ナイトスクープ』である。

(番組公式HPより)
1月23日放送の回で、6人兄妹の長男が、日常的な家事の負担を軽減してほしいと「探偵」に助けを求めた放送直後、「育児放棄」「ヤングケアラー問題」と捉えた視聴者からの抗議が相次いだ。矛先は取材対象となった家族への誹謗中傷やプライバシーの「特定」などにも向かった。
結果、番組側が2回にわたり番組ホームページで声明文を公表。TVerでの配信も停止される事態に至っている。
今回の騒動が突きつけたのは、ヤングケアラー問題そのもの以上に、「子どもを守る」という善意が、家族への糾弾へ転化しうる危うさだ。必要なのは断罪ではなく、支援の設計である。
ここには、メディアの演出、家族の多様性、そしてSNSにおける「正義」の行使という三つの層が、複雑に絡み合った構図が見て取れる。私たちはどう捉えるべきなのか。
メディアが紡ぐ「物語」と、アップデートされる価値観
まず向き合うべき問題は、メディアが実在する人々を「物語(ナラティブ)」としてパッケージ化する際のリスクである。日本のテレビメディアには、少なくとも一部には「大家族の奮闘記」を美談的に捉える価値観が長らく存在した。昭和の時代には1家庭に5人以上の子供がいる家庭も珍しくなく、上の子が下の子をあやし、家事を担う光景は、かつては「健気な家族愛や親孝行」の象徴として茶の間の共感を呼ぶ定番的演出だった一面も考えられる。
しかし少子高齢化と人口減少が進み、ヤングケアラーが深刻な社会問題として認識された現代において、その文脈は変容を遂げている。特にかつて「美談」とされた子供の献身は、いまや「児童の権利侵害」や「搾取」という文脈で評価される。
今回の番組側には、視聴者の受け取り方を大きく左右する情報が、編集によって強調されていた実態が説明されている。
番組側は炎上を受け、「父親が乳幼児を残して外出する場面」や「母親の『米炊いて、7合』といった発言」は編集上の演出であり、実際の生活の全体像を示したものではないと説明した。さらに長男の依頼文についても、趣旨を踏まえつつ放送用に構成・改稿したとしている。
視聴者が「育児放棄」「搾取」と受け取ったのは、家族の実態というよりも番組が提示した“物語の設計”に強く依存していたことになる。結果として、怒りを喚起しやすい構図が成立してしまった点で、番組側の情報提示の誠実さは問われるべきだろう。
なぜこのような演出がなされ、炎上したのか。参考になるのは、ジョナサン・ゴットシャルが『ストーリーが世界を滅ぼす』(東洋経済新報社)で説いた、物語が持つ強力な感染力である。
メディアが「わかりやすい物語」を提供した時、受容者側もまた、その物語に沿って現実を解釈しようとする。こうした物語が感情を喚起するほど注目を集め、必然的に視聴率にも繋がる。視聴者は提供された映像などの断片的情報から「不憫な被害者(長男)」と「無責任な加害者(親)」という二項対立的な物語を瞬時に再構築した。
しかしながら、実在する家族はコンテンツとして使い捨てられるべき架空の物語の登場人物ではない。実際には機能していた「演出の外側の事実」にあった家族の役割が、物語の整合性を乱すノイズとして切り捨てられていった。その過程には、現代的な情報の受容の危うさが潜んでいる。
「家族の責任」をめぐるリアリティの断絶
本論に入るにあたり、先に筆者の個人的な経験も提示したい。筆者は高校生時代、病気の父の介助から家事までを担った他ならぬヤングケアラー経験者でもある。父は筆者が高校生になってほどなく悪性の脳腫瘍で倒れ、筆者が高校卒業する少し前に他界した。