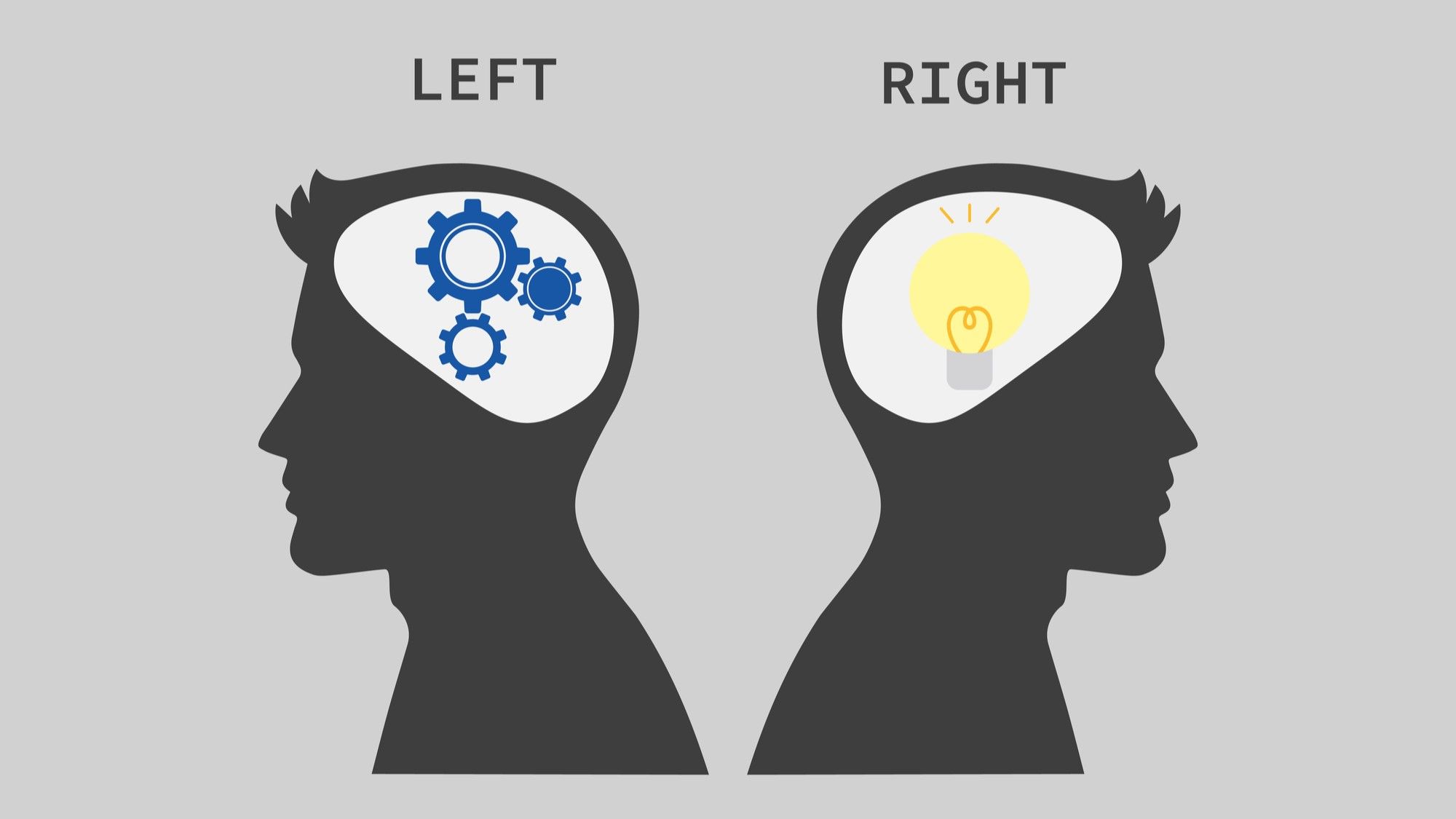
「書店減少」嘆くのにネットで本買う日本人の矛盾
2023.11.02
東洋経済オンライン

書店は、いろんな意味で新しい発見をさせてくれる、ワクワクできる空間だ。それが今、減少の一途をたどっている(画像:Hirotama/PIXTA)
「お金の本質を突く本で、これほど読みやすい本はない」
「勉強しようと思った本で、最後泣いちゃうなんて思ってなかった」
経済の教養が学べる小説『きみのお金は誰のため――ボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」』には、発売直後から多くの感想の声が寄せられている。本書は発売前から2万部の重版が決まった話題作だ。
著者の田内学氏は元ゴールドマン・サックスのトレーダー。資本主義の最前線で16年間戦ってきた田内氏はこう語る。
「みんながどんなにがんばっても、全員がお金持ちになることはできません。でも、みんなでがんばれば、全員が幸せになれる社会をつくることはできる。大切なのは、お金を増やすことではなく、そのお金をどこに流してどんな社会を作るかなんです」
今回は、小説内でも取り上げられている「未来への投票としての消費」という考え方を解説してもらう。
書店には「新しい発見」があふれている
30年前、「待ち合わせ」という言葉には、緊張感があった。

『きみのお金は誰のため: ボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」』(東洋経済新報社)今回は記事の内容を鑑みて、書影をクリックしてもAmazonのサイトにはジャンプしません。
「明日の待ち合わせは、正午にBIGMAN前だからね」
気になっている女の子と約束をして、意気揚々と電話を切るのだが、内心は穏やかではない。本当に来てくれるのか不安になる。
まだ携帯電話が普及していなかった時代だ。黒電話の受話器を置いた瞬間から、会うまでは連絡をとることができなかった。
そのため、待ち合わせ場所はわかりやすい場所じゃないといけない。そして、時間厳守だ。時間どおりに行かないと、会えないおそれがある。それに、怒って帰ったのか、これからやって来るのか、すっぽかされたのか確認する手段がない。
BIGMANというのは、大阪の阪急梅田駅のそばにある大型スクリーンの名称。東京でいうところの、渋谷ハチ公前や新宿アルタ前のような待ち合わせのメッカである。
BIGMANで待ち合わせるときは、遅くとも30分前には到着していた。そして、待ち合わせ時刻の5分前まで、隣の紀伊國屋書店梅田店で時間をつぶすのが習慣だった。
学生だった僕は、書店に入るとまず『週刊少年ジャンプ』を手に取り『スラムダンク』や『ドラゴンボール』の最新話をチェックする。もしくは、新刊コーナーで話題の本を手に取ってみたりする。『磯野家の謎』や松本人志の『遺書』を買って読んだのも、この書店での出会いがあったからだ。当時は書店が情報収集の場だった。
相手との関係に慣れてくると、待ち合わせ場所はBIGMAN前から書店の中へと変わった。それはまた、新たな発見の機会でもあった。相手がどんな本に興味を持っているのか、どんな趣味なのかがわかる。
書店は多くの意味で新しい発見の場であり、ワクワクする空間だった。
急激に減る書店は「世の中に街に不要」なのか
30年が経った現在、そのワクワクする空間が徐々に減っている。僕が働いていた赤坂・六本木エリアではこの数年で、わかっているだけで5つの書店が閉店した。

文教堂赤坂店の張り紙(撮影:筆者)
昨年、文教堂赤坂店が閉店した際の入り口の張り紙は大きな反響を呼んだ。
「書店という業態は世の中に街に必要とされなくなっているのだろうか?」
書店員さんのこの訴えには、心から「そんなことは決してないです」と答えたかった。その書店の空間やそこに流れる時間を僕は愛していた。同じように感じる人たちはきっと多いだろう。しかし、事実として全国の書店は減少している。





























