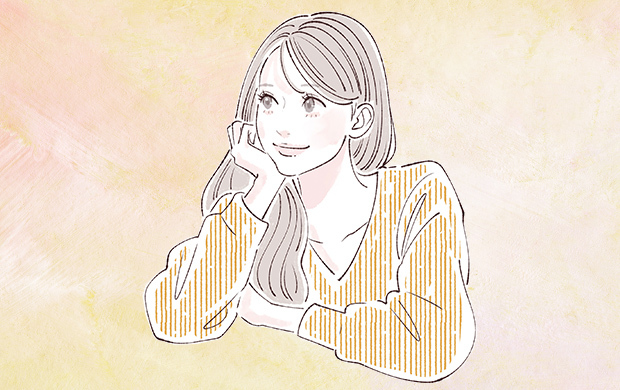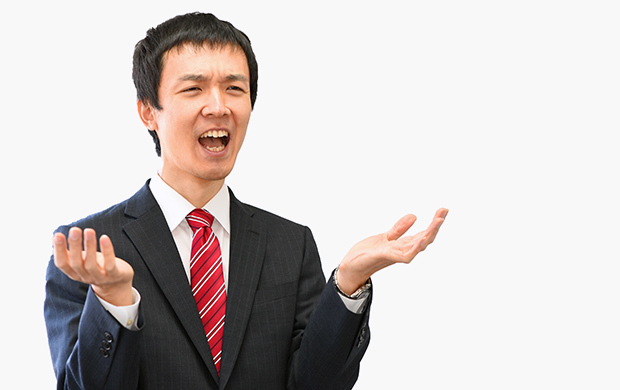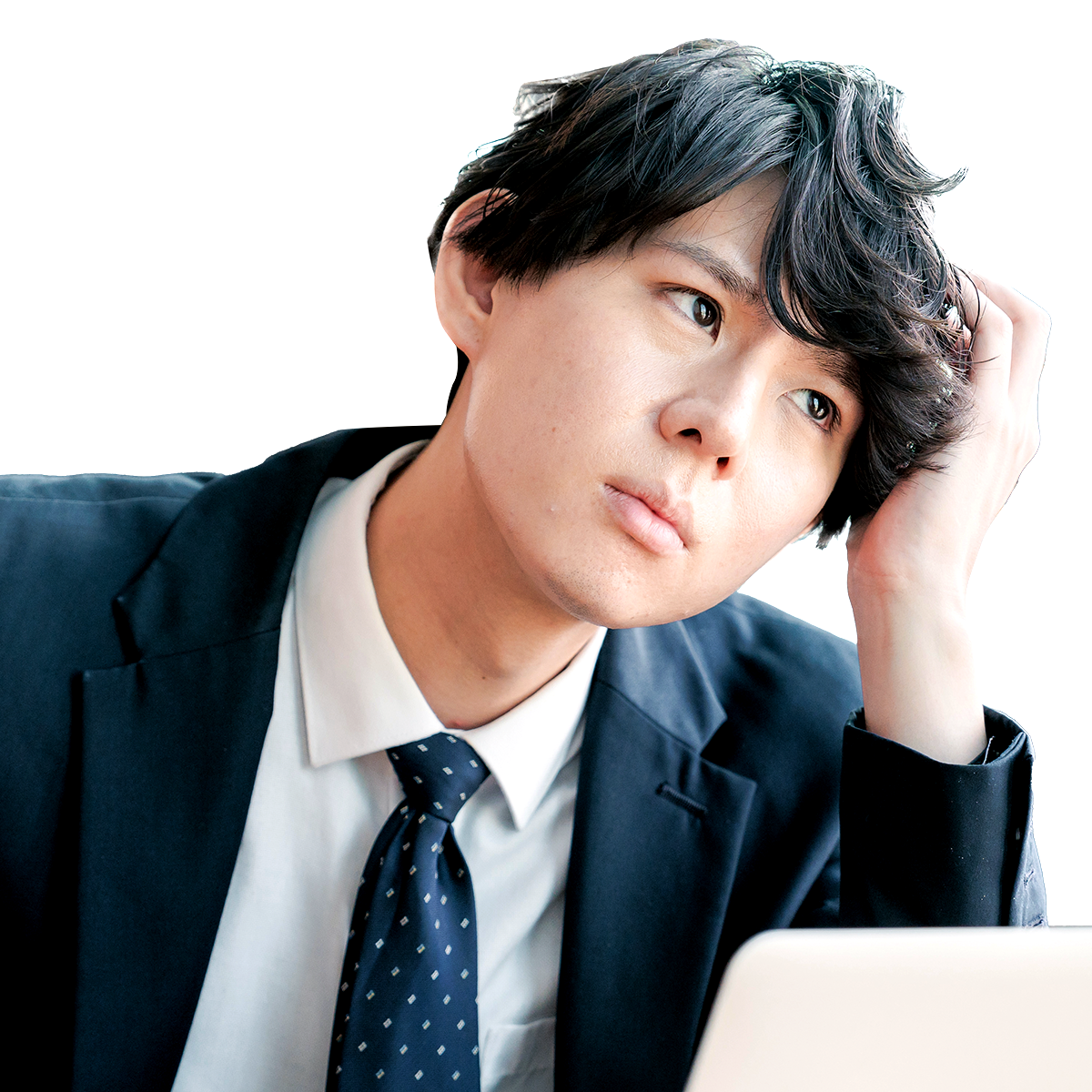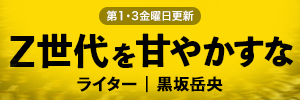絶望の「みずほFG」再び旧3行でトップ分け合い、システム障害でも社外取締役が全員留任
2022.01.31
ビジネスジャーナル

みずほフィナンシャルグループ(FG)は相次いだシステム障害の責任をとって3首脳が一斉に退陣。新しい社長、会長が1月17日に正式に決まった。結果は、旧3行がトップを分け合う、旧態依然とした内向きのトップ人事である。みずほFGの再出発は期待薄だ。
21年11月26日、金融庁は8度のシステム障害を起こしたみずほ銀行と持ち株会社みずほFGに、業務改善命令を出した。「短期間に複数のシステム障害を発生させ、個人・法人の顧客に重大な影響を及ぼした」と経営陣の責任を厳しく追及した。これを受け、みずほFGの坂井辰史社長(旧日本興業銀行出身、62)とみずほ銀の藤原弘治頭取(旧第一勧業銀行出身、60)が22年4月1日付で辞任予定。みずほFGの佐藤康博会長(旧興銀出身、69)も同日付で会長職を退き、6月の株主総会で取締役を退任することになった。
10年におよんだ旧興銀の支配は終焉するはずだったが、坂井社長の後任も興銀出身の木原正裕執行役(56)が昇格。4月から2月1日に2カ月前倒しされた。佐藤会長の後任は旧第一勧銀出身の今井誠司副社長(59)に落ち着いた。今井副社長の就任は4月1日付だ。木原・新社長の弟は岸田文雄首相の懐刀といわれている木原誠二官房副長官であることから、政界からも注目される人事となった。指名委員会委員長の甲斐中辰夫弁護士は1月17日の記者会見で「弟が政治家ということは考えていない。金融庁は政治家を利用した空中戦は最も嫌う」と述べた。
みずほのトップ人事で想定外だったのは木原・新社長の就任が2カ月前倒しされたことだけだ。
ガバナンスの脆弱性
業務改善命令を出した金融庁が最終的に問うたのは、システム障害の背景にあるガバナンス(企業統治)の脆弱性だ。金融庁は業務改善命令で「取締役会が坂井社長ら執行部門に対して適切な指示を与える態勢になっていなかった」と指摘した。みずほFGの取締役会の構成は、計13人のうち社外取締役が6人を占めている。今回の処分は、社外取締役の責任を問う過去に例のない内容となった。
2013年に明らかになった反社会的勢力への融資問題を機に、大手行のなかで最も早く「指名委員会等設置会社」に移行した。坂井社長の選任も社外取締役だけで構成する指名委員会が主導した。当時の、みずほの最大の課題は、他のメガバンクと比較してコスト高の構造だった。コスト削減に力を発揮するとの判断が、坂井社長が選出される決め手になったとされる。坂井氏は18年の就任以来、構造改革に邁進。19年度からの5カ年計画で、人員や国内拠点の削減を進めた結果、17年9月中間期に76.4%だった経費率は21年9月中間期には60.2%まで低下。ライバルの三井住友フィナンシャルグループを下回った。
副作用も生じた。システム関連の人員削減を進めた結果、勘定系システム「MINORI」で一連のシステム障害が頻発した。21年6月に第三者委員会が公表した報告書によると、「MINORI」の開発や運用に関わった人員はシステム稼働前の約1100人からおよそ500人(21年3月末)に半減した。
金融庁は、取締役会について「システムリスクに直結する怖れのある人員の削減計画や業務量の状況について十分な審議を行っていない」と指摘した。「社外取締役は執行部の説明を追認するばかりでチェック機能が不十分だった。社外取締役が多数で構成するリスク委員会や監査委員会が機能していなかった」ことを問題点として挙げた。
真の意味で「独立した」社外取締役で構成されていない
みずほのガバナンスの形態は指名委員会等設置会社である。取締役会の権限は強く、執行部門の監督が主な責務となる。6人の社外取締役は小林いずみが取締役会議長に就いているのをはじめ、甲斐中氏が指名委員会、山本正巳氏が報酬委員会、月岡隆氏が監査委員会の各委員長を務めている。