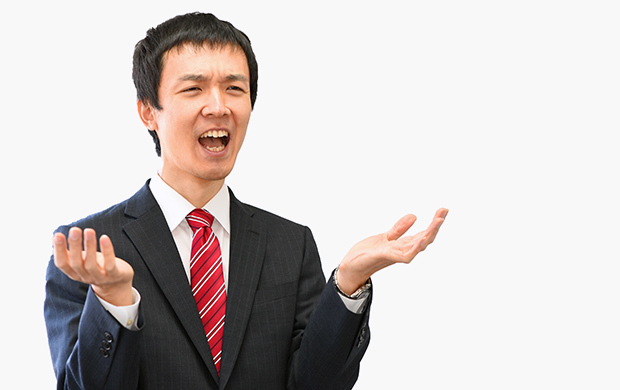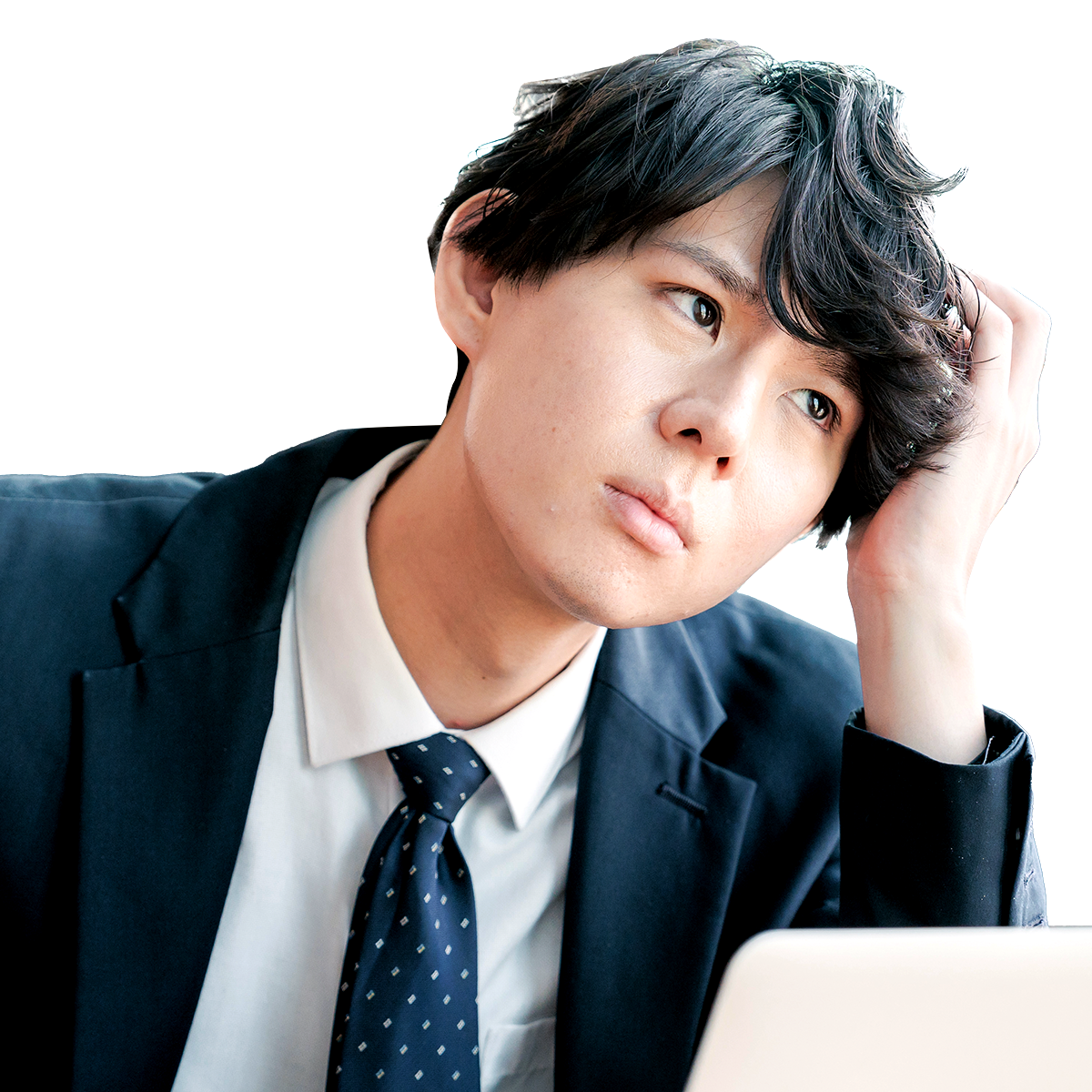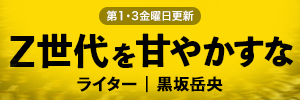いきなり!ステーキ社内報が炎上「教育で経営改善&社員に温かい経営」の時代錯誤
2022.02.07
ビジネスジャーナル
ただ、このような状況が『教育で改善できる』と信じているところが一瀬社長らしいというか、優しいところであり、令和の現実を直視できていないところかもしれません。チェーン内に不良従業員がいる。それが会社と敵対することを楽しんでいる。そのような場合でも古い会社は、彼らをなんとかして更生させようとする。その教育的指導自体がSNSで反撃されるような時代に、一瀬社長のウェットな経営手法はマッチしていないように感じられます。
令和の時代ならば、クレームを減らし全体のサービスクォリティを上げていくために店舗を閉鎖し、その店舗の従業員を切り捨てるという手法を優先する経営者は少なくありません。私は、いきなり!ステーキの経営はネットでいわれるようなブラックではなく、従業員に優しすぎ、従業員の可能性を信じすぎている『温かくてダメな経営』であるように感じます」
高いホスピタリティを社員に求めるという発想の弊害
また、外食業界関係者はいう。
「基本的に、いきなり!ステーキをはじめとする低価格とボリューム、商品提供の速さをウリにする外食チェーンの店舗では、最低限の人員と効率良いオペレーションを徹底しているため、店員は余裕がないなかで目の前の注文をさばくのに精いっぱいの状態で、お世辞にも高いとはいえない給料や時給でキツイ労働を強いられている。
顧客単価が高い高級フレンチ店ならまだしも、そうした外食チェーンの現場の人間からしてみれば、“作業ではダメ”“自己改革しろ”“クレーム受けたら処分する”と言われたところで、反感を抱くだけでしょう。経営層であれば、社員が積極的・自発的にカスタマーロイヤリティを向上させようと動く仕組みづくり、個々の社員にそうした余裕を持たせるオペレーションづくりを、まず第一に考えるべき。
そもそも高いコストパフォーマンスをウリに顧客を集める低価格の外食チェーンで、過度に高いホスピタリティやサービスを社員に求めるという発想は、いわゆるブラック企業化につながりかねず、労働環境の悪化や社員離脱を招く懸念もある」(1月28日付当サイト記事より)
「何ら咎められるものではない」
今回の社内報、法律的には問題ないのだろうか。山岸純法律事務所代表の山岸純弁護士は次のように解説する。
「この社内報の社長の『あいさつ欄』、一瀬邦夫社長ご本人が書いているとしたら、大変僭越ながら、相当の文章力をお持ちの方と感じます。文章にも、“熱い”“冷静”などの温度感があるわけですが、私はこの文章を拝読し、経営理念、目標といった大きいところから始まって、目先の『ではどうすればよいか』という各論に至る“流れ”がとても良く構成されていると思います(僭越でスミマセン)。
お客様を大切にする“お客様商売”の方々の基本の発想であり、何ら咎められるものではないでしょう。
もっとも、クレームがあった従業員について『厳重な処分をします』とのことですが、従業員に適用される就業規則には『懲戒処分』の項目があり、『こういう場合にはこういう懲戒処分となる』ことが明確に規定されています。
しかし、『お客様からクレームがあった場合、減給処分とする』などとストレートには規定されておらず、おそらく、
・素行不良
・著しく協調性に欠ける
・会社の名誉を傷つけた
などとされているでしょうから、『お客様からのクレーム』が、上記のような項目に該当しない限り、『厳重な処分』をすることはできません。単に 『お客様からのクレーム』があったことだけをもって懲戒処分をしようものなら、不当な懲戒処分として撤回を求められたり、損害賠償の対象となることもあります。
一瀬社長が使用した文言自体は、従業員に“発破をかける”という性質の社内報ですから許容範囲であるとしても、実際に 『厳重な処分』を行うと、上記のような問題が発生します」(1月28日付当サイト記事より)
いずれにしても、一瀬社長の“社員にやさしい経営”は、なかなか世間には理解されないようだ。
(文=編集部、協力=鈴木貴博/百年コンサルティング代表取締役)