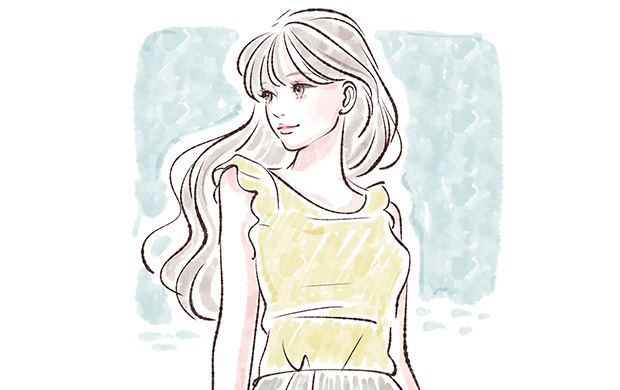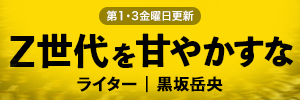不動産業界の“聖域”が崩壊するか…西松建設「脱デベ」開発、建設費高騰の特効薬か
2026.02.13
ビジネスジャーナル
不動産ジャーナリストの秋田智樹氏は次のように分析する。
「現在は建築費高騰により、利回り前提が崩れている案件が多い。総事業費の1割圧縮は、IRR(内部収益率)を数ポイント改善するインパクトがある。自己開発型は理論的には合理性が高い選択肢だ」
ゼネコンを縛ってきた「固定価格」の重圧
なぜ、ゼネコンはこれまで“請負”に徹してきたのか。その背景には、日本の建設業界特有の商慣習がある。
多くの案件は固定価格契約(いわゆる一式請負)で発注される。資材費の高騰や人件費上昇があっても、契約後のコスト増はゼネコン側が吸収する構図が長らく続いてきた。いわば「不平等条約」ともいえる慣習だ。
「価格転嫁が難しい体質が、ゼネコンの収益力を慢性的に圧迫してきた。自己開発型は、その構造からの脱却でもある」(秋田氏)
事業主が自社であれば、資材価格の変動に応じた設計見直しや工期調整を自ら判断できる。他人の都合で赤字を掘るリスクを、経営の裁量でコントロール可能になる。
これは単なるコスト削減策ではなく、「リスク配分の再設計」といえる。
ホテルオークラとの直接連携が生む合理性
もっとも、建設会社が事業主になる場合、最大の弱点は「運営ノウハウ」にある。特にホテル事業は、ブランド力、集客力、サービス品質が収益を左右する。
西松建設はこの点を踏まえ、早期段階からホテルオークラと連携。運営はオークラが担うスキームを採用した。施工のプロと運営のプロが、ディベロッパーという“伝言ゲーム”を介さず直接対話する体制である。
ホテル経営にも精通する秋田氏は次のように評価する。
「設計段階から運営者が入ることで、動線設計やバックヤード効率、客室仕様の最適化が可能になる。開業後のオペレーションコストを抑える設計は、長期収益性を大きく左右する」
これは、単なる“中抜き”ではない。施工と運営の垂直統合による合理化であり、収益構造そのものを磨き込む試みだ。
広がるゼネコン主導モデルと、その副作用
この動きは西松建設に限らない。大林組や清水建設などスーパーゼネコンも、自社投資型の不動産開発を強化している。安定収益源の確保という観点からも、アセット保有は魅力的だ。
だが、劇薬には副作用がある。
(1)財務リスクの増大
土地取得費や建設費を自社の貸借対照表(B/S)に計上するため、財務負担は重い。市況悪化時には減損リスクも発生する。
(2)市況変動リスク
ホテルや商業施設は景気敏感業種である。インバウンド需要の減退や金利上昇局面では収益が揺らぐ。
(3)企画力の空白
ディベロッパーは本来、リスク分散や資金調達、テナント誘致の専門家だ。彼らを排除することで、別の専門性を失う可能性もある。
秋田氏はこう警鐘を鳴らす。
「ゼネコンが開発を内製化する動きは合理的だが、全案件で成功するわけではない。アセット運用能力やリスクヘッジ戦略が伴わなければ、景気後退局面で財務を圧迫する」
問われるディベロッパーの存在意義
西松建設の挑戦は、一企業の戦略にとどまらない。「とりあえずディベロッパーに任せる」という従来構造の必然性が問われている。
今後、ディベロッパーは単なる“中間業者”では生き残れない。高度な企画力、金融スキーム構築力、リスク分散設計など、明確な付加価値を提示できなければ淘汰は避けられない。
一方、ゼネコンも「請負業者」から「事業プロデューサー」へと脱皮を迫られる。財務戦略、運営パートナー選定、出口戦略まで視野に入れた経営力が不可欠だ。
建設費高騰という逆風は、日本の不動産開発に構造改革を迫っている。西松建設の“ディベロッパー抜き”開発は、その象徴だ。
それが特効薬となるのか、禁じ手となるのか。答えは、ゼネコンが「工事会社」の殻を破り、真の事業主体へと進化できるかどうかにかかっている。
(文=BUSINESS JOURNAL編集部、協力=秋田智樹/不動産ジャーナリスト)