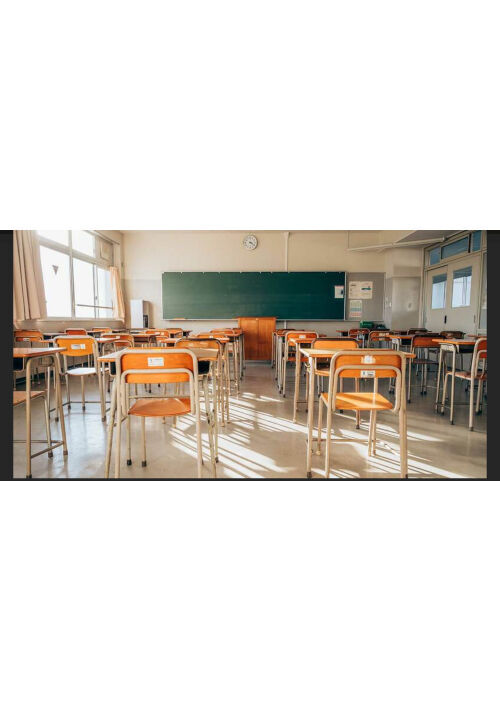4 / 13
【第4話】 巫女の同級生
しおりを挟む
僕の嫌な勘はよく当たる。
何とか掴まれた手を振り切ろうとしたが、昨日と同じでびくともしない。何かに掴まれるものではもないかと辺りを見回して、手水の横に置いた紙袋が目に入った。果物は全て食べられてしまったが、あの中にはまだ洋菓子が入っている。
「タツミ!お菓子が!虫に食べられちゃうって!」
「えー、大丈夫だよ。後で取りに来ればいいじゃん」
「いいわけあるか!暑さで溶けるぞ!」
「チョコは溶けても美味しいよ?」
「もったいないだろうが!
食べ物を大事にしないなら、もう持ってこないぞ!?」
「やだー!!」
ぱっとタツミが僕の手を離した。今だ。
尻もちをつきそうになりながら半回転して走り出すと、手水まで行って紙袋を掴んで龍の背後へ行く。すぐに戻ってくると思っていたタツミは一瞬ポカンとして、僕がニヤリと笑ったのを見てようやく騙されたことに気付いた。
すぐさま、ものすごい勢いでこちらに走り出した。
やっぱり、タツミは僕より足が速い。
力でもスピードでも敵わない以上、神社から逃げようとしても追いつかれるだろう。けれど僕とタツミの遊びの勝敗は、7:3で僕の方が上だ。
タツミは手水の前まで来ると、角に手をかけて遠心力で曲がるとする。再び僕の腕を掴もうと視線を下げた彼女は、すぐに僕の右手が握りこぶしを作って手水の水面に浮かんでいることに気付く。
次の瞬間、タツミの顔に水がかかった。
「ぎゃぶっ!?」
「はは!引っかかったな!」
「え?え?え?」
予測できなかったのも無理はない。
僕の右手はほとんど動かず、依然として水上にある。僕はただ、握りこぶしを引き締めただけだ。
多くの人が子供の頃に風呂場でよく遊んだ手遊びの水鉄砲、ところがタツミは訳が分からずきょとんとしている。
そう、これがタツミの弱点だ。彼女はあまりにもモノを知らない。
「な、何それ!?」
「水鉄砲だよ、ほら」
もう一度水を飛ばすと、タツミはキラキラと目を輝かせた。何故なら、彼女は常に遊びに飢えている。
タツミが僕を真似て手水に手を突っ込む。あまりの勢いで水が跳ねて、大きな水音が響く。
「あっ、待ってタツミ…」
このままだと、恐らくタツミはただただ力任せに水をかけてくるのではないだろうか。そうしたら、水鉄砲どこの勢いではない。僕は頭から水を被ることになる。
それは、困る。
「待たないよーっだ!」
「いやさすがに服を汚すわけには…」
困り果てたところで、もうタツミを止める手段も避ける場所もない。諦めて目をつむって衝撃に耐える。
そのとき、どこからか女神のような声がした。
「ちょっと、そこで何してるの!?
…あれ、一角くん?」
「…紅葉?どうしてここに」
箒を手に現れた紅葉はセーラー服ではなくタツミと同じ巫女服で、髪をハーフアップにしてサイドを編みこんでいた。
学校で机を合わせて教科書を見せてもらった時、ちらりと見えた彼女のノートには綺麗な文字が連なっていたから、手先が器用なのは想像通りだったけれど。
学校では手取り足取り優しく僕を指導してくれた彼女は、今やまるで不審者を見るように眉間に皺をよせていた。
「…一角くんこそ、何でここに?」
「僕は友達と遊んでて、あれ?」
そういいながらタツミを見たら、既にその姿かたちもなかった。
あいつ、僕を置いて逃げやがった。
恐らく同じ巫女に見つかったらサボっているのを怒られるから、僕を囮にしたのだろう。あまりに早く清々しい逃げ足の速さだ。
何とも、怒られるのが嫌いなタツミらしい。
「うちの神社の手水で、何をしていたの?」
「ごめんなさい」
「…何してたのって聞いてるんだけど」
「……」
「まぁいいや、丁度いいから掃除手伝ってよ」
聞けば紅葉は放課後に時々この神社で手伝いをしていて、丁度掃き掃除をしようとしていたらしい。言われてみれば、境内は落ち葉だらけだ。
お詫びに掃き掃除を手伝いながら、僕はこの神社では貴重な「働く人」をつい目で追ってしまう。
何年か前に一度大人の神職の人に会ったこともあるけど、白衣に紋が入った紫色の袴を着たその人は、階段でグリコをして遊ぶ僕らを穏やかな笑みで眺めるだけだった。
おばさん達以外の大人に会うなんて滅多になかったし、その神職の人は目元の泣きぼくろが特徴的だったからよく覚えている。
彼女は僕らが敷地内で走り回ることも声を上げることも、黙認してくれた。
だが、紅葉は違う。
「信じられない、神社で遊んでいた何て」
「ご、ごめんって」
「それに神域の近くで」
「それはその…あの場所が神域って知らなかったんだ」
「神社は村民みんなのものなの。今回は許すけど、次は親御さんにも連絡するからね」
「…はい」
紅葉は、ヒステリック気味に何度も僕を叱った。おばさんと同族の根に持つタイプだ、うっかり通報されたりしなくて良かった。前に見つかった時は、運が良かったのだろう。
紅葉がそこまで怒る理由は、すぐに明らかになった。彼女は葉っぱを一か所に集めながら、参道を横切るたびに一礼をしていた。信心深い紅葉には染み付いた作法を、僕とタツミは一度もしたことがない。
「偉いね、ちゃんとお辞儀するんだ」
「あのねぇ。
ここは神様の土地なんだから、穢れた人間は礼儀を持って敬わなきゃいけないの」
「僕、汚くないよ!」
「そういう意味じゃない!」
柿を手掴みで食べていたタツミならともかく。
あいつは時々頭が濡れた野犬みたいな匂いがするけど、僕は毎日お風呂に入っているし箸やフォークで食事をする。
でもどうやらそういうことではないらしく、紅葉は呆れたような顔をする。
おかしいな、清楚で頭脳明晰なクラスのマドンナはどこに行ったんだ。
「そうやって穢れがついたり信仰が薄まったりしたら、神様の力が弱まっちゃうんだからね」
「神様の力が、弱まる?神様なのに?」
「…村を守る力が弱まるってこと。
村の畑に降る雨や川の水に村民の健康、龍神様はそれらを司る神様なんだよ」
確かに、この神社は龍神様を祭っている。
村の名前は龍神村で学校の名前は龍神中学校、その由来はこの龍神神社にある。
おばさんの家にある神棚には、この神社で貰ったお神札もこの神社で貰ったものだ。この村ができたとき、つまり100年以上前から存在する龍神神社はそれだけ村や村民にとって特別な信仰対象なのだろう。
転校してきたからといって、龍神様の地域にいる限りその例外にはならないと紅葉は言う。
「それも知らなかったの?…はぁ、一角くんはもう少し真面目な子だと思ってたよ」
「もうわかったよ!ごめんって!」
その文言は、昨夜散々聞いた。
とはいえ地面には僕とタツミが格闘した後が残り、手水の周りにも水が散っている。
明らかに僕に非がある以上、白い目で見られても謝罪することしかできない。整えられた前髪の影が瞳にかかって、紅葉からは不気味さまで感じる。
だがこの期に及んで、僕はさらに後ろめたいことがある。
謝りながら、僕は彼女にバレない様に静かに手水に近づいていた。
石造りの手水の傍には僕が持ってきた紙袋が置いてあって、中には食べ残したお菓子が入っている。
飲食禁止の神社でこれ以上怒られないよう、距離を十分に詰めてから駆け寄って回収をはかる。そのまま自転車のカゴに入れようと引き寄せ胸に抱えると、背後に気配を感じた。
袋を身体で隠しながら振り向くと、箒をバットみたいに肩にかけた紅葉がいた。
表情こそ優しかったけれど、明らかに疑っているのが声のトーンでわかった。
「何それ?」
「あ…いや…」
「見せて」
手を差し出されたら、観念するしかない。
頭を下げて包みを頭上に差し出すように渡したら、紅葉は中を覗き込んで片眉を上げた。
僕は意味もなく正座して、罪を言い渡される罪人のような気持ちで紅葉の言葉を待った。
「お菓子?神社は飲食禁止なんだけど?」
「いや…僕が食べるためじゃなくて」
「あぁ、お供え?」
「え?」
「渡しに来たんでしょ?」
「…うん?」
「神饌はお米とか野菜が多いんだけど、気持ちが大事だからね。
これは受け取っておくね」
「うん…?」
どうやら、紅葉は大量の菓子を見て龍神様への供え物だと勘違いしたらしい。
本当はタツミに渡すつもりだったけど、それを行ったら怒られそうだったので、とにかく頷く。
残り物だけれど、神社のお供え物にしていいのかなとは思いつつ。
紅葉は神袋を持って、神社の横にある社務所に入っていった。正月は巫女さんがお守りや護符なんかを売ったりする場所らしいのだが、参拝客の少ない神社では普段は閉まっていて、開いているのを見るのは初めてだ。
扉が閉まる前に、紅葉が手を伸ばした。箒を戻すように言っているのだろう。
「もうすぐ日が沈むから、帰っていいよ」
「うん、わかった」
「そうだ、来週はお祭りがあるんだよ。ぜひ来てね」
「へぇ、そうなんだ」
紅葉が社務所の閉じられた窓を指さした。
窓には、一枚のお祭りのポスターが貼られている。
毎年秋ごろにお祭りがあるのは知っていたけれど、村には夏休みにしか来ないので行ったことはない。
今年はタツミと参加してみようかとも思ったけど、その日は社務所が開く数少ない日だし巫女さんは忙しいだろう。紅葉もタツミも忙しいはずだ。
僕くらいしか遊ぶ人がいないタツミはともかく、面倒見がよく美人な紅葉と一緒にお祭りを回りたいクラスメートは多いだろうに。
そういえば、タツミはいつも僕と神域で遊び惚けているし狛犬によじ登ってお菓子を食べたりもするけど、ちゃんと巫女としてやっていけているのだろうか。
普通に考えればサボッているのだろうけれど、意外と仕事の時間は真面目にしていたりするのだろうか。
紅葉に箒を渡しながら、僕は好奇心から僕が知らないタツミのことを知りたくなった。
「そういえば、紅葉はタツミと知り合いなの?」
「タツミ?誰?」
「誰って、この神社の巫女さんだよ。
名前はわからないけど、よく遊んでいるんだ」
フルネームを言おうとして、僕はタツミの名前に心当たりがなかった。
気づいたときには僕はタツミをタツミと呼んでいたし、タツミは僕をいっくんと呼んでいた。
自己紹介なんてしたこともないと思ったところで、もしかしてタツミが僕を一角ではなく「いっくん」と呼ぶようにタツミもニックーネームなのかもしれないと閃いた。
「このくらいの背丈で、紅葉くらいの髪に、年も同じ…あとは」
「うーん?」
性格は粗野で乱暴だけどタツミは大人しくしていれば紅葉以上の美人だし、話したら印象には残っているはずなのだが。紅葉には、思い当たる人物がいないようだ。
詳しく説明しようとしたけど、それ以上の情報が出てこなかった。どこに住んでいて本名は何というのか、親はどんな人なのか、僕が勝手に想像していただけで何一つわからない。
そう、僕はタツミのことを何も知らない。
「ほとんどの巫女さんは私より年上なんだよ。特に赤袴の人はね」
「じゃあ…信じたくないけど、あいつは僕より年上なのかな」
神社で働く人はみんな袴を履いていて、その色で階級や仕事がわかる。
タツミと紅葉のような巫女は、祭事の時以外は伝統的な装束である赤袴を着用しているらしい。ちなみに神職の人は階級に合わせて浅葱色や紫色の袴を履いており、冠婚葬祭で色を変えることはあっても巫女と同色になることはない。
なので、消去法でタツミが年上の巫女である可能性が浮上する。散々子供扱いしていたタツミが年上なのは、何とも言えない気持ちだ。
というか、年上ならもっとしっかりして欲しい。
「一角くん、それどうしたの」
「それ?」
箒を受け取った紅葉は、僕の質問には答えず心配そうに眉を下げた。
視線を辿ると、僕の左腕にはっきりとした袴と同じ色の手形が残っていた。思い当たるのは、少し前に引っ張られた記憶だ。
犯人は一人しかいない、タツミだ。
「あぁ、タツミに掴まれたときにね。あいつ、力強いんだよな」
「…女の子なんだよね?」
「さすがに男だったらわかるよ…女、だよな?」
いや、昨日ハグをしたときに男にはない感触を感じたからわかる。
それに、もしナニがついていたら肩車したときなんかにやっぱりわかるはずだ。大体、男が巫女になれるのだろうか。
どれも比較対象がいないので、断言できないのが悔しい。
「私の力じゃそうならないと思うけど、冷やしておくといいよ」
「そうするよ、ありがとう」
「それと、今日働いているのは私だけだよ」
「え?そうなの?」
「うん、お祭りに向けて軽く掃除をしようと思って。
ほら、落ち葉が積もってたでしょ?
恥ずかしい話、しばらく掃除されてなかったんだよ」
「それってつまり……どういうこと?」
「ねぇ、その子本当にこの神社の巫女なの?」
巫女じゃなかったら、何だって言うんだ。
巫女服を着たくて借りていたにしても買ったにしても、タツミがただのコスプレ少女になってしまう。
でも、タツミならただ可愛い服を着たくて着ていても不思議じゃない。あとは、紅葉が知らないだけで…。
戸締りがあるからと言われて話は中断してしまい、僕の心にはモヤモヤしたものが残ったままだった。
紅葉が身体を退けた間に見えた社務所の奥には誰もおらず、冷え切っていた。紅葉が真実を偽る理由もメリットもないし、話は真実なのだろう。
自転車に乗る前に神域に続く階段を振り返ったけど、タツミは姿を現さなかった。
「でも、今日も遊べなかったからまた怒るんだろうな」
小動物みたいに頬を膨らませて、地団太を踏みながら。
明日は、もっと柿を持っていこう。
そう硬く決意した僕だったが、それから数日間僕が神社に訪れることはなかった。
何とか掴まれた手を振り切ろうとしたが、昨日と同じでびくともしない。何かに掴まれるものではもないかと辺りを見回して、手水の横に置いた紙袋が目に入った。果物は全て食べられてしまったが、あの中にはまだ洋菓子が入っている。
「タツミ!お菓子が!虫に食べられちゃうって!」
「えー、大丈夫だよ。後で取りに来ればいいじゃん」
「いいわけあるか!暑さで溶けるぞ!」
「チョコは溶けても美味しいよ?」
「もったいないだろうが!
食べ物を大事にしないなら、もう持ってこないぞ!?」
「やだー!!」
ぱっとタツミが僕の手を離した。今だ。
尻もちをつきそうになりながら半回転して走り出すと、手水まで行って紙袋を掴んで龍の背後へ行く。すぐに戻ってくると思っていたタツミは一瞬ポカンとして、僕がニヤリと笑ったのを見てようやく騙されたことに気付いた。
すぐさま、ものすごい勢いでこちらに走り出した。
やっぱり、タツミは僕より足が速い。
力でもスピードでも敵わない以上、神社から逃げようとしても追いつかれるだろう。けれど僕とタツミの遊びの勝敗は、7:3で僕の方が上だ。
タツミは手水の前まで来ると、角に手をかけて遠心力で曲がるとする。再び僕の腕を掴もうと視線を下げた彼女は、すぐに僕の右手が握りこぶしを作って手水の水面に浮かんでいることに気付く。
次の瞬間、タツミの顔に水がかかった。
「ぎゃぶっ!?」
「はは!引っかかったな!」
「え?え?え?」
予測できなかったのも無理はない。
僕の右手はほとんど動かず、依然として水上にある。僕はただ、握りこぶしを引き締めただけだ。
多くの人が子供の頃に風呂場でよく遊んだ手遊びの水鉄砲、ところがタツミは訳が分からずきょとんとしている。
そう、これがタツミの弱点だ。彼女はあまりにもモノを知らない。
「な、何それ!?」
「水鉄砲だよ、ほら」
もう一度水を飛ばすと、タツミはキラキラと目を輝かせた。何故なら、彼女は常に遊びに飢えている。
タツミが僕を真似て手水に手を突っ込む。あまりの勢いで水が跳ねて、大きな水音が響く。
「あっ、待ってタツミ…」
このままだと、恐らくタツミはただただ力任せに水をかけてくるのではないだろうか。そうしたら、水鉄砲どこの勢いではない。僕は頭から水を被ることになる。
それは、困る。
「待たないよーっだ!」
「いやさすがに服を汚すわけには…」
困り果てたところで、もうタツミを止める手段も避ける場所もない。諦めて目をつむって衝撃に耐える。
そのとき、どこからか女神のような声がした。
「ちょっと、そこで何してるの!?
…あれ、一角くん?」
「…紅葉?どうしてここに」
箒を手に現れた紅葉はセーラー服ではなくタツミと同じ巫女服で、髪をハーフアップにしてサイドを編みこんでいた。
学校で机を合わせて教科書を見せてもらった時、ちらりと見えた彼女のノートには綺麗な文字が連なっていたから、手先が器用なのは想像通りだったけれど。
学校では手取り足取り優しく僕を指導してくれた彼女は、今やまるで不審者を見るように眉間に皺をよせていた。
「…一角くんこそ、何でここに?」
「僕は友達と遊んでて、あれ?」
そういいながらタツミを見たら、既にその姿かたちもなかった。
あいつ、僕を置いて逃げやがった。
恐らく同じ巫女に見つかったらサボっているのを怒られるから、僕を囮にしたのだろう。あまりに早く清々しい逃げ足の速さだ。
何とも、怒られるのが嫌いなタツミらしい。
「うちの神社の手水で、何をしていたの?」
「ごめんなさい」
「…何してたのって聞いてるんだけど」
「……」
「まぁいいや、丁度いいから掃除手伝ってよ」
聞けば紅葉は放課後に時々この神社で手伝いをしていて、丁度掃き掃除をしようとしていたらしい。言われてみれば、境内は落ち葉だらけだ。
お詫びに掃き掃除を手伝いながら、僕はこの神社では貴重な「働く人」をつい目で追ってしまう。
何年か前に一度大人の神職の人に会ったこともあるけど、白衣に紋が入った紫色の袴を着たその人は、階段でグリコをして遊ぶ僕らを穏やかな笑みで眺めるだけだった。
おばさん達以外の大人に会うなんて滅多になかったし、その神職の人は目元の泣きぼくろが特徴的だったからよく覚えている。
彼女は僕らが敷地内で走り回ることも声を上げることも、黙認してくれた。
だが、紅葉は違う。
「信じられない、神社で遊んでいた何て」
「ご、ごめんって」
「それに神域の近くで」
「それはその…あの場所が神域って知らなかったんだ」
「神社は村民みんなのものなの。今回は許すけど、次は親御さんにも連絡するからね」
「…はい」
紅葉は、ヒステリック気味に何度も僕を叱った。おばさんと同族の根に持つタイプだ、うっかり通報されたりしなくて良かった。前に見つかった時は、運が良かったのだろう。
紅葉がそこまで怒る理由は、すぐに明らかになった。彼女は葉っぱを一か所に集めながら、参道を横切るたびに一礼をしていた。信心深い紅葉には染み付いた作法を、僕とタツミは一度もしたことがない。
「偉いね、ちゃんとお辞儀するんだ」
「あのねぇ。
ここは神様の土地なんだから、穢れた人間は礼儀を持って敬わなきゃいけないの」
「僕、汚くないよ!」
「そういう意味じゃない!」
柿を手掴みで食べていたタツミならともかく。
あいつは時々頭が濡れた野犬みたいな匂いがするけど、僕は毎日お風呂に入っているし箸やフォークで食事をする。
でもどうやらそういうことではないらしく、紅葉は呆れたような顔をする。
おかしいな、清楚で頭脳明晰なクラスのマドンナはどこに行ったんだ。
「そうやって穢れがついたり信仰が薄まったりしたら、神様の力が弱まっちゃうんだからね」
「神様の力が、弱まる?神様なのに?」
「…村を守る力が弱まるってこと。
村の畑に降る雨や川の水に村民の健康、龍神様はそれらを司る神様なんだよ」
確かに、この神社は龍神様を祭っている。
村の名前は龍神村で学校の名前は龍神中学校、その由来はこの龍神神社にある。
おばさんの家にある神棚には、この神社で貰ったお神札もこの神社で貰ったものだ。この村ができたとき、つまり100年以上前から存在する龍神神社はそれだけ村や村民にとって特別な信仰対象なのだろう。
転校してきたからといって、龍神様の地域にいる限りその例外にはならないと紅葉は言う。
「それも知らなかったの?…はぁ、一角くんはもう少し真面目な子だと思ってたよ」
「もうわかったよ!ごめんって!」
その文言は、昨夜散々聞いた。
とはいえ地面には僕とタツミが格闘した後が残り、手水の周りにも水が散っている。
明らかに僕に非がある以上、白い目で見られても謝罪することしかできない。整えられた前髪の影が瞳にかかって、紅葉からは不気味さまで感じる。
だがこの期に及んで、僕はさらに後ろめたいことがある。
謝りながら、僕は彼女にバレない様に静かに手水に近づいていた。
石造りの手水の傍には僕が持ってきた紙袋が置いてあって、中には食べ残したお菓子が入っている。
飲食禁止の神社でこれ以上怒られないよう、距離を十分に詰めてから駆け寄って回収をはかる。そのまま自転車のカゴに入れようと引き寄せ胸に抱えると、背後に気配を感じた。
袋を身体で隠しながら振り向くと、箒をバットみたいに肩にかけた紅葉がいた。
表情こそ優しかったけれど、明らかに疑っているのが声のトーンでわかった。
「何それ?」
「あ…いや…」
「見せて」
手を差し出されたら、観念するしかない。
頭を下げて包みを頭上に差し出すように渡したら、紅葉は中を覗き込んで片眉を上げた。
僕は意味もなく正座して、罪を言い渡される罪人のような気持ちで紅葉の言葉を待った。
「お菓子?神社は飲食禁止なんだけど?」
「いや…僕が食べるためじゃなくて」
「あぁ、お供え?」
「え?」
「渡しに来たんでしょ?」
「…うん?」
「神饌はお米とか野菜が多いんだけど、気持ちが大事だからね。
これは受け取っておくね」
「うん…?」
どうやら、紅葉は大量の菓子を見て龍神様への供え物だと勘違いしたらしい。
本当はタツミに渡すつもりだったけど、それを行ったら怒られそうだったので、とにかく頷く。
残り物だけれど、神社のお供え物にしていいのかなとは思いつつ。
紅葉は神袋を持って、神社の横にある社務所に入っていった。正月は巫女さんがお守りや護符なんかを売ったりする場所らしいのだが、参拝客の少ない神社では普段は閉まっていて、開いているのを見るのは初めてだ。
扉が閉まる前に、紅葉が手を伸ばした。箒を戻すように言っているのだろう。
「もうすぐ日が沈むから、帰っていいよ」
「うん、わかった」
「そうだ、来週はお祭りがあるんだよ。ぜひ来てね」
「へぇ、そうなんだ」
紅葉が社務所の閉じられた窓を指さした。
窓には、一枚のお祭りのポスターが貼られている。
毎年秋ごろにお祭りがあるのは知っていたけれど、村には夏休みにしか来ないので行ったことはない。
今年はタツミと参加してみようかとも思ったけど、その日は社務所が開く数少ない日だし巫女さんは忙しいだろう。紅葉もタツミも忙しいはずだ。
僕くらいしか遊ぶ人がいないタツミはともかく、面倒見がよく美人な紅葉と一緒にお祭りを回りたいクラスメートは多いだろうに。
そういえば、タツミはいつも僕と神域で遊び惚けているし狛犬によじ登ってお菓子を食べたりもするけど、ちゃんと巫女としてやっていけているのだろうか。
普通に考えればサボッているのだろうけれど、意外と仕事の時間は真面目にしていたりするのだろうか。
紅葉に箒を渡しながら、僕は好奇心から僕が知らないタツミのことを知りたくなった。
「そういえば、紅葉はタツミと知り合いなの?」
「タツミ?誰?」
「誰って、この神社の巫女さんだよ。
名前はわからないけど、よく遊んでいるんだ」
フルネームを言おうとして、僕はタツミの名前に心当たりがなかった。
気づいたときには僕はタツミをタツミと呼んでいたし、タツミは僕をいっくんと呼んでいた。
自己紹介なんてしたこともないと思ったところで、もしかしてタツミが僕を一角ではなく「いっくん」と呼ぶようにタツミもニックーネームなのかもしれないと閃いた。
「このくらいの背丈で、紅葉くらいの髪に、年も同じ…あとは」
「うーん?」
性格は粗野で乱暴だけどタツミは大人しくしていれば紅葉以上の美人だし、話したら印象には残っているはずなのだが。紅葉には、思い当たる人物がいないようだ。
詳しく説明しようとしたけど、それ以上の情報が出てこなかった。どこに住んでいて本名は何というのか、親はどんな人なのか、僕が勝手に想像していただけで何一つわからない。
そう、僕はタツミのことを何も知らない。
「ほとんどの巫女さんは私より年上なんだよ。特に赤袴の人はね」
「じゃあ…信じたくないけど、あいつは僕より年上なのかな」
神社で働く人はみんな袴を履いていて、その色で階級や仕事がわかる。
タツミと紅葉のような巫女は、祭事の時以外は伝統的な装束である赤袴を着用しているらしい。ちなみに神職の人は階級に合わせて浅葱色や紫色の袴を履いており、冠婚葬祭で色を変えることはあっても巫女と同色になることはない。
なので、消去法でタツミが年上の巫女である可能性が浮上する。散々子供扱いしていたタツミが年上なのは、何とも言えない気持ちだ。
というか、年上ならもっとしっかりして欲しい。
「一角くん、それどうしたの」
「それ?」
箒を受け取った紅葉は、僕の質問には答えず心配そうに眉を下げた。
視線を辿ると、僕の左腕にはっきりとした袴と同じ色の手形が残っていた。思い当たるのは、少し前に引っ張られた記憶だ。
犯人は一人しかいない、タツミだ。
「あぁ、タツミに掴まれたときにね。あいつ、力強いんだよな」
「…女の子なんだよね?」
「さすがに男だったらわかるよ…女、だよな?」
いや、昨日ハグをしたときに男にはない感触を感じたからわかる。
それに、もしナニがついていたら肩車したときなんかにやっぱりわかるはずだ。大体、男が巫女になれるのだろうか。
どれも比較対象がいないので、断言できないのが悔しい。
「私の力じゃそうならないと思うけど、冷やしておくといいよ」
「そうするよ、ありがとう」
「それと、今日働いているのは私だけだよ」
「え?そうなの?」
「うん、お祭りに向けて軽く掃除をしようと思って。
ほら、落ち葉が積もってたでしょ?
恥ずかしい話、しばらく掃除されてなかったんだよ」
「それってつまり……どういうこと?」
「ねぇ、その子本当にこの神社の巫女なの?」
巫女じゃなかったら、何だって言うんだ。
巫女服を着たくて借りていたにしても買ったにしても、タツミがただのコスプレ少女になってしまう。
でも、タツミならただ可愛い服を着たくて着ていても不思議じゃない。あとは、紅葉が知らないだけで…。
戸締りがあるからと言われて話は中断してしまい、僕の心にはモヤモヤしたものが残ったままだった。
紅葉が身体を退けた間に見えた社務所の奥には誰もおらず、冷え切っていた。紅葉が真実を偽る理由もメリットもないし、話は真実なのだろう。
自転車に乗る前に神域に続く階段を振り返ったけど、タツミは姿を現さなかった。
「でも、今日も遊べなかったからまた怒るんだろうな」
小動物みたいに頬を膨らませて、地団太を踏みながら。
明日は、もっと柿を持っていこう。
そう硬く決意した僕だったが、それから数日間僕が神社に訪れることはなかった。
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
1
1 / 4
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる