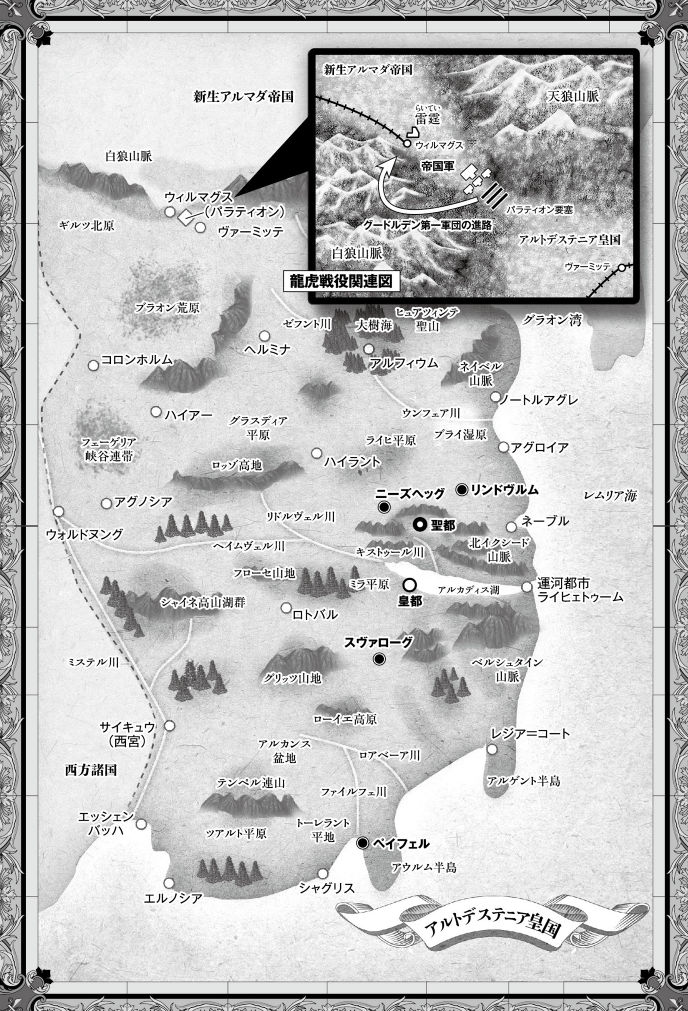49 / 526
4巻
4-1
しおりを挟むそれは愚かしくも心の浮き立つような時代だった。
何もかもが目まぐるしく入れ替わり、誰もが明日へ明日へと突き進んだ。
今の平穏な時代しか知らない者たちから見れば、野蛮で獰猛で、救いのない時代だったように思えるかもしれないが、当時の自分たちはそんなことを露ほども考えず、その日その日の変化に適応しようと躍起になっていたものだ。
人が成長するように、国が栄え滅びるように、時代もまた成長し、栄え、滅ぶ。
いつか自分たちのこの文明も、第一次文明のように滅びるだろう。
人によっては、それについて幾らでも言いたいことがあるだろうが、滅びもまた必要なことなのだと私は思う。
この文明を苗床にして、新たな文明が花開く。それは親から子へと続く生命の連鎖のように、この世界の中で生きる文明にとって自然なことだとは思えないだろうか。
――――統一暦三三二年黒の第五月 皇国星天軍元帥 イドリアス・ガラハ・アーデン
第一章 皇都にて
明るい光の中で、彼は優しく微笑んでいた。
少女の総てを受け容れるように、少女の背負う重荷を受け容れるように。
他の誰にも出来ない、彼だけの笑顔。
この国で生まれ、この国で育ち、それ故に、少女とその重い役割を知る者には決して浮かべることが出来ない彼の表情に、彼女は惹かれた。
知らぬ故に少女自身を見詰め、理解出来ぬが故に少女自身を理解しようとする彼の姿に心打たれた。
役目を果たし、彼の内なる世界で揺蕩う彼女を呼び起こした声。
久しく聞いていなかった名前。
姉以外の誰もが口にしなかった彼女の名を、彼は呼んでくれた。
あの声を聞き、自分は自分なのだと思えた。
抱き上げられ、自分は此処にいてもいいのだと思えた。
リリシア、と。あの人に呼んでもらえるのなら、他に何もいらない。
巫女姫の肩書きさえ、彼の隣に侍るための道具に過ぎないのだから――
皇都イクシード。
当代皇王とその支持貴族によって戦火に晒された皇国最大の都市は、新たな皇国の主である一人の青年の出現によって再びその栄華を取り戻そうとしていた。
都市外へと疎開していた住民たちが我が家へと帰り、鎧戸を固く閉じていた商店は次々と店を開く。学校や公園には子どもたちのはしゃぐ声が蘇り、路面列車や乗合馬車、乗合魔動車には明るい表情の住民たちの姿があった。
住民や商店を相手にする卸業者の隊商もまた皇都へと舞い戻り、市場は多くの人々で賑わっている。呼び込みや値段交渉の声は幾重にも重なり、とある屋台の商店主は、懐かしささえ感じるその喧騒に目尻を濡らした。
そんな彼の屋台に、真昼間から酒を楽しむ二人の男がいた。
「皇太子殿下は北に向かわれたそうだのう……」
「んだ。帝国のグロ――何とかというお姫さまが軍隊を引き連れて攻めてきたらしい」
「おうおう、おっかねぇなぁ。そういや、うちの婿の実家が確か北の方での、向こうの旦那が今年は雪が早いとか言っておったわ」
「んだら、皇太子さまのお帰りも早いかもしれんな」
「だと良いのう。お城には巫女姫さましかおらんで、さぞ寂しかろう」
「大層めんこい子じゃったに、皇太子さまもさぞかし向こうで心配しとるじゃろ」
「そりゃそうだ」
呵々と笑い、祝の酒を酌み交わす二人。彼らは今朝方皇都に荷物を届けに来た商会の人間だった。
大分老いを重ねた彼らにしてみれば、皇太子も巫女姫も孫と言っていい程の年齢だ。皇太子に対する忠誠心も巫女姫に対する崇敬の念もあるが、まず彼らに対して抱くのは若い雛鳥に向ける愛情だった。見ていて思わず微笑んでしまうようなそれだ。
出来るならば、雛たちには健やかに過ごして貰いたいと思う。
この皇都を襲った未曾有の惨禍に終止符を打ち、今また外からの脅威に立ち向かっている皇太子。
その皇太子を支える宿命を負い、ただ一人広大な皇城に残された巫女姫。
人々は、彼ら自身が思っているよりも彼らのことを想っていた。
幸せな夢だった。
今は遠く北の大地にいるあの人が、自分の隣にいる夢。
だからだろう、目が覚めたときに酷く虚しい気持ちになったのは。
隣に誰もおらず、目を開けてもただ窓掛けが朝日に揺れるばかり。
その向こうに見える清々しいまでの青空さえ、憎く思えた。
「起きよう……」
上半身を起こし、ともすれば沈み込む思考を晴らそうと、少し強く頭を振る。
さらさらとした薄絹の夜着が肌に擦れた。身体を締め付ける下着は安眠に良くない、と神殿付きの女官に教えられて以来、就寝時には下着を着けなくなった。それから大分経つから、鋭敏な素肌を夜着が擦るのも慣れた感触だ。
肩からずり落ちた夜着を整えることもせず、彼女は寝台の上に座り込む。
透けるように白い肌と艶やかな翡翠の髪、そして身に纏う衣は薄い夜着だけという非現実的なまでに扇情的な姿は、間違いなく世の男どもが夢想してやまない理想の女の姿だった。それが今年十四になったばかりの少女が具現化しているとは、彼らとて想像出来ないだろう。
だが、少女自身がそうあろうとしている訳ではない。
彼女は、自分が心の底から想うたった一人の男のためにこの姿を手に入れた。彼女にとって最も大切なのはその男であり、自身の容姿など所詮副次的なものだった。
以前から美しく在りたいという気持ちはある。
しかしその願いは人から『美しくあるべき』と教えられたからこそで、彼女が自ら見付けた願望ではなかった。
彼女が本当の意味で自分の容姿に気を配るようになったのは、やはりあの青年に心惹かれてからだろう。
雪のような素肌に布の跡がつかないようにと夜着を選び、それこそ件の青年以外の異性に見せることはないであろう身体の隅々にまで目を配る日々。神殿にいた頃から付いてくれている女官など、少女のそんな姿に「あらあら」と嬉しそうに笑みを浮かべたほどだ。
元々の資質もあったのだろうが、今の少女は絵画に残しても誰一人異論を唱えることが出来ないほど美しくなった。
未成熟であるが故に滲み出る艶。
熟れきった者にも、成熟の途上にある者にもない独特の艶気は、密かに後宮の職員たちの間で噂になっていた。
「あんなにも可憐な巫女姫さまを娶られる摂政殿下は大陸一の果報者」
そう後宮の者たちが評するのも無理はない。
少なくとも今の少女は、皇都近くの離宮にいるもう一人の女性――美しく在ることこそが存在意義の『蕾の姫』に匹敵するだけの麗姿を持っているのだから。
「レクティファール様は、今何をしていらっしゃるのでしょう」
そんな彼女だが、浮かぶ表情は憂いを多分に秘めたものだった。
こんこんと部屋に響いた軽い音に振り返る最中も、その憂いが消えることはない。
そして、どうぞ、と音の主を招き入れる声もまた、何処と無く沈んでいた。
「失礼します、猊下」
音も立てずに扉を開け、一つお辞儀をした女官。重厚そうな扉だが、閉める音もなかった。
「メチェリ、おはよう」
「おはようございます、お目覚めでしたか」
メチェリと呼ばれた女官は、隙のない所作で少女――リリシアの座る寝台へと歩み寄る。
深い紫の髪を頭頂部で一纏めにし、端整な顔立ちの彼女であるが、何よりも一番人の目を引くのはその鋭い眼だろう。まるで抜き身の刃のようと評されるその眼は、今は主人であるリリシアをじっと見詰めていた。
「いい夢を見ていたのだけど、やっぱり夢は夢だった。起きたら少し寂しくなってしまったの」
「良い夢ほど現実との落差に虚しさを覚えるものです。――おそらく、これから幾度も同じ経験をなさるでしょう」
「ええ、きっとそうでしょうね」
リリシアはうっすらと笑んだ。
確かに笑っていながら、しかし感情を窺うことのできない空虚と言う他ないその顔に、メチェリは眉をぴくりと跳ね上げた。
「猊下……」
呼んではみたものの、続ける言葉が無いメチェリ。
彼女は後宮を守る皇族最後の盾――『機甲乙女騎士団』の一員として多くの妃を見てきたが、これほど若い第一妃候補は初めてだった。それどころか、皇太子と正式に婚儀を行っていない妃〝候補〟を迎えたことも初めての経験で、リリシアとどのように接するべきか悩む部分も未だに多い。
メチェリの懊悩を悟ったか、リリシアは小さく微笑んで言った。
「沐浴の準備をお願い」
「はい」
両手を揃え、頭を垂れるメチェリ。
近衛軍侍女大尉としてリリシア付き侍女頭を任されて以来、彼女はずっと悩み続けていた。
この少女の笑顔が、どうしても泣き顔に見えたから。
沐浴を済ませたリリシアは、朝食までの時間を中庭にある大聖堂で過ごしていた。
後宮の中心にある中庭は広く、そこに点在する庭園では多くの樹木草花が皇妃たちの目を楽しませている。
石造りの遺跡庭園もあれば、イズモ様式の枯山水もあり、さらには南国の気候を再現した温室もある。中庭の中央近くの湖には多くの野鳥が訪れ、さらには庭園で放し飼いにされている鳥たちも季節相応の姿を見せてくれた。
しかし、そんな優美な印象とは裏腹に、後宮とはただ皇王とその妃が暮らすだけの施設ではない。皇王と皇族を守る最後の砦だ。その証拠に、この後宮で働く二〇〇〇人の侍女女官は総て、近衛軍の軍人、『機甲乙女騎士団』の団員だった。
洗濯物を洗う侍女、後宮内を掃除する女官、庭師たちでさえも『機甲乙女騎士団』の一員。
彼女たちはいずれも男を知らず、騎士団の名の通り〝乙女〟としてこの後宮で働き続けている。
そして、近衛軍部隊で最も平均年齢が低い。その所以は男を知り、その名を〝乙女〟から〝女〟へと変えた女性はこの騎士団から別部隊へと異動になるからだ。
近衛軍は個人の恋愛に口を出さないが、結婚せずとも〝女〟になれば『機甲乙女騎士団』に所属することは出来なくなる。それは後宮にいるべき男が皇王と、女皇の配偶者のみで、彼らの手が付いた場合を考慮してのことだった。
女皇の配偶者の手が付いた場合、それは問題にはならない。生まれてくる子どもには皇族としての資格は当然無く、ただの私生児に過ぎない。
だが、皇王の手が付いた場合はどうなるか。
これは言うまでもなく、皇族名簿に記載される立場となる。無論、母親の意向によっては名簿に記載されること無く生涯を閉じることもあるだろう、だが、母親である団員が皇妃となれば子どもは準皇族となり、有力な貴族に養子として出される場合も考えられる。
そんなとき、父親が皇王でないと発覚したらどうなるか。
これまでも皇王の手が付き皇妃や側妃となった団員は存在した。それらの産んだ子どもたちは貴族や有力な名家の養子となっており、万が一父親が別に存在するとなれば、間違いなく皇王家の権威は大きく傷付くことになる。
いや、実はこれまでの歴史でそのような事例が一度だけ存在した。
当時は『機甲乙女騎士団』が存在せず、近衛軍の女性のみの部隊が後宮の警護役だった。
ときの皇王はその中の一人を見初め、召し上げた。
皇王の手が付いた時点では、確かにその団員は男を知らず、近衛軍を統括する皇王府もまた、皇王の意向に沿って彼女の皇妃入りを認めたのだ。
彼女はやがて皇王の子どもを身篭り、出産。
しかし、その後の検査にてとんでもない事態が発生したのだ。
皇妃の産んだ子が、皇王の子ではないと発覚したのだ。
皇国の象徴たるべき皇妃の一人が、あろうことか他の男と姦通していた――皇王府も政府も、他の皇族も大いに揺れた。
議会は荒れ、流れた噂によって国民も動揺した。
何よりも、皇王自身が心に多大な衝撃を受け、床に伏せてしまった。
皇妃は後宮から離宮へと移され、蟄居。後に病死。
皇妃の元上司である近衛軍総司令官は責任を取って辞任し、その数日後、自宅で自刃。皇妃の実家も夜逃げ同然に国を出奔し、この事件は皇国史上最悪の不祥事となってしまった。
だが、皇王府と近衛軍の捜査によって明かされた真実は、大して珍しくも無いことだった。
皇妃となった女性には、幼馴染の許嫁がいたのだ。
幼少の頃に結婚の約束を交わしており、それは両家も承知の上。
ある家具職人の弟子になっていた男が社会的に自立したら、正式に夫婦となる予定であった。
しかし、近衛軍に属していた女は皇王に見初められ、流されるままその愛を受けてしまった。
それだけであればただ手が付いただけ、女が身を引けば大きな問題にはならなかったはずだ。だが、女の実家が欲を出してしまった。皇王から娘の皇妃入りを求められた際、それを受けてしまったのだ。
女は悲しみを押し殺し、家のため後宮へと上った。
だが、悲しみは癒えることなく、彼女は独り立ちし、一人前の家具職人となっていた幼馴染に家具を頼みたいと願った。そして、当時は皇王の許可さえあれば一部の部外者も立ち入ることが出来た後宮内へと彼を招き入れた。
元近衛軍の女には、後宮内の警備の穴を突くことなど難しいことではなかった。
彼女は幼馴染と、後宮内で密通した。
幾度も、幾度も、新しい家具を作りたいと、少し家具に手を入れたいと言い、男を招いた。
おそらく、彼女と幼馴染の密通に気付いていた近衛軍の軍人もいただろう。
だが、彼女の境遇に同情した元同僚たちは、その密通を上司に報告することも、止めることもしなかった。
そして、あの後宮史上最悪の事件が起きた。
事件後、すぐに近衛軍は『機甲乙女騎士団』を設立。所属団員の厳正な選抜と厳格な服務規程を定め、このような事件が二度と発生しないよう現在の後宮の形へと制度を切り替えた。
例外なく、一切の部外者の立ち入りを禁止。
皇妃たちには専属の護衛隊を付け、いかなる状況下であっても傍を離れることがない警備体制を作り上げた。これは皇妃自身が望んでも覆らない。
実際、リリシアが就寝している隣の部屋には、常時一個分隊の護衛が待機しており、彼女の行動を監視し続けていた。
今このとき、リリシアが礼拝を行っている最中も、護衛隊は大聖堂の中に散らばり己の職務を果たしていたのだ。
「侍女大尉殿、本日の予定のことなのですが……」
礼拝堂の入口近くに立ち、礼拝のため祭壇の前で跪くリリシアの姿を視界の端に捉えていたメチェリの下に一人の部下が駆け寄ってきた。メチェリと同じく侍女服姿だが、襟元の階級章は准尉のものだった。
「どうした、何か予定に変更か?」
「は、実は――」
メチェリの耳に口を寄せ、囁く准尉。
その言葉を聞いたメチェリの目は大きく見開かれ、表情は強張った。
「まさか、パールフェル妃殿下が……」
「どうなさいますか? 司令部からは猊下の意向を是とせよとの命令が届いておりますが……」
准尉の問いに、メチェリは疲れたように頭を振った。
「ならば、猊下に直接伺うしかあるまい。――今上陛下の第一妃、パールフェル殿下がお会いしたいと仰っていると」
◇ ◇ ◇
リリシアの答えは是だった。
今上皇王は公的に未だ皇王である。
ならばその妃は後宮を退いても皇王第一妃であり、未だ正式な皇妃ではないリリシアにその誘いを断ることは出来ない。
ただ、パールフェルの誘いよりも前に決められていた予定に関しては、これを優先することにした。
予定とは今回の騒乱で傷付いた国民の慰撫であり、都市外に建設された難民避難施設の慰問を行ったり、神殿の運営する病院などに足を運んで入院患者を見舞うことだった。
これをパールフェル側に打診すると、すぐに承諾するとの返事がきた。
本人もリリシアと同じく、国民のために少しでも行動したいと願っている。
すでに国民からの敬意を受けるには汚れ過ぎているパールフェルだが、リリシアに毅然とした態度を示すことで、第一妃の在り方を教えたのかもしれない。国民の象徴である皇妃としての役割は未だ果たす積もりでいるらしい。
パールフェル自身は今回の騒動で罪を犯してはいないが、実家グリマルディ侯爵家が事実上の取り潰しとなった現在、皇妃としての実権など何一つ持ってはいないのだ。
それでも皇妃としての毅然とした在り方を忘れないパールフェルに、リリシアは密かに憧憬の念を抱いた。
自分があのように振る舞える日はいつになるだろうか。そんなことを考えた。
難民の避難施設に着いたリリシアはまず、一緒に運んできた支援物資の配布から始めた。
これは皇王府が用意したものだったが、リリシアが運び、そして配布することで、国民の意識に「リリシア〝皇妃〟は自分たちの味方」という印象を植え付けようとしていた。
民を騙すようだとリリシアは思ったが、それで幸せを得る民が過半を占めるならやるべきだとも思った。
総てを救うほどの力はない。
なら、救えるだけの人々は救うべきだ。リリシアはそう決断した。
そういう意味では、レクティファールよりもリリシアの方が余程政治的判断を的確に行えるのかもしれない。
政治は民のためにある。
リリシアの趣味嗜好や矜持のためにあるのではないのだ。
「おお……お妃さま……」
「皇太子さまといい、此度の皇族様方は慈悲深い方ばかりじゃ……」
今朝焼いたばかりのパンを配り歩くリリシアの手を握り締め、涙さえ流す老夫婦。
夫は車椅子に乗ったまま幾度もむせび、妻は歩くための杖を地面に放り出してリリシアの前に膝を付いていた。
「お二人とも、これまで大きな苦労を掛けました。以後、皆様の安寧はわたしと、摂政殿下が保障いたします」
「リリシア様……ありがとうございます……!」
「皇太子さまの御武運、この老骨たちにも祈らせて下さい……」
「ありがとうございます。殿下はきっと、皆様のお心を剣鎧として勝ちましょう」
優しく微笑むリリシア。
老夫婦だけではない、周囲の人々さえ彼女の言葉に声を詰まらせた。
今上皇王によって大きな傷を受けた人々。
彼らは皇王家に対して不信感を抱きながらも、同時に皇王家を信じたいという願望を抱いていた。
二〇〇〇年の間に人々の間に芽生えた皇王家への崇敬の念は、一度の裏切りで消えるものではない。
裏切られても、それでも信じたいと願う人々の心を、リリシアは感じた。
「皆様――」
だから、彼女はもう一度自分たちを信じて欲しいと言うつもりだった。
しかし、その言葉は突然の怒声に掻き消された。
「この裏切り者!」
一人の若い女性が、真っ赤に血走った目でリリシアを睨みつけながら叫び、人垣を割って現れた。
リリシアの周囲にいた人々は口々に女性の不敬を詰ったが、当のリリシアがそれを制した。
「――」
「反論しないの? やっぱり裏切り者なのね! あんたたちは!」
女性はぱさついた赤茶色の髪を振り乱し、リリシアの襟元を掴んだ。
護衛のメチェリ以下数名が侍女服の中に隠し持っていた短剣を抜こうとしたが、リリシアの咎めるような眼差しによって動きを止める。
「遅すぎるのよ! あんたたちがあと三日早ければ、あの子は死なずに済んだのに! あの人は殺されずに済んだのに!」
「――――」
唾を飛ばし、今にもリリシアの喉笛に喰らいつきそうなほど、女性の眼は狂気と悲しみに満ちていた。
リリシアは反論もせず、黙って罵声を受け止める。
「知ってる!? あの子は優しくて賢くて、いつも私の作るご飯を美味しいって食べてくれたのよ! あの人はぶっきらぼうだけど真面目で、他の兵士さんたちにも頼りにされていたのよ!」
女性は、皇都守備を担当していた皇国軍兵士の妻だった。
彼女の夫は支持貴族軍が皇都を占拠したあとも傭兵たちの無法を取り締まっていた、住人たちの信頼も篤い実直な兵士だった。いつか助けが来ると信じ、同僚たちと街を守り続けていた。
だが、そんな兵士は当然傭兵たちに恨まれる。
職務中幾度も暴行を受け、怪我をしない日はなかった。
それでも彼は心配する妻に大丈夫だと告げ、毎日の仕事に向かった。
そして、レクティファールによる皇都奪還の三日前。
彼は自宅への帰路、傭兵たちに尾行された。
家族を人質に取って彼に立場を知らしめてやろうという傭兵たちの、唾棄すべき策だった。
彼が自宅に辿り着いたとき、扉が開いたことを確認した傭兵たちは一斉に彼の家に踏み込んだ。
多勢に無勢。そう言う他ない。
彼は何人もの傭兵たちに取り押さえられ、家族を人質に取られた。
抵抗は、そこで止んだ。
彼は家族の安全を求めたが、傭兵たちがそれを飲むはずはない。
このとき皇都を支配していたのは彼ら支持貴族軍であり、近衛さえ彼らには手出し出来なかった。
傭兵たちは下卑た笑い声を上げながら、彼の前で妻を陵辱した。
やめてくれと叫ぶ彼の言葉にも、やめてという妻の悲鳴にも、泣き叫ぶ子どもの声にも耳を貸さず、傭兵たちは幾度も妻の身を穢した。
自分たちこそが支配者であると誇示するため、都市外を包囲する始原貴族軍の威圧から一時的にせよ逃れるため、彼らは己の欲望を晴らした。
そんな悲劇が二時間ほど続いただろうか。
子どもを押さえ付けていた傭兵が油断した隙に、子どもが拘束から抜け出した。
子どもは助けを呼ぼうと家の外に飛び出し――
「私の目の前で、傭兵に斬り殺されたわ!」
事件の発覚を恐れたのか、それとも急変した事態に動揺しただけなのか。
傭兵たちは子どもを斬り殺し、それに怒りの声を上げた父親の首を落とした。
「あの人の首は、床に押さえ付けられていた私の目の前まで転がってきたわ! そして彼の首は私の目を見て、動かなくなった!」
それから三日間、彼女は延々と傭兵たちの慰み者にされた。
家族の思い出の詰まった家に監禁され、そこで昼夜を問わず嬲られた。
心が何度も砕けそうになった。
そのたび、傭兵たちへの怒りで持ち堪えた。
いつか復讐してやると思い、必死で耐えた。
「あんたたちが来たのは、あの人の首が腐り始めた頃……!」
突如騒がしくなった皇都。
慌てた傭兵たちはこの三日間一度も衣服を身に着けることが出来なかった彼女を放り出し、逃げるように家を飛び出した。
その直後、傭兵たちの悲鳴が聞こえた。みっともない声だった。
命乞いの声も聞こえた。
しかし、彼女の心は晴れない。
この手で殺してやると思い、陵辱された姿のまま夫の剣を持ち出した。
そして玄関の扉を開けた彼女は、これまで散々自分を穢した傭兵たちの死体と対面した。
一人だけ生き残った傭兵は既に拘束されており、彼女の夫とは違う軍装の兵士たちに連行されるところだった。
彼女は奇声を上げ、その傭兵に斬りかかった。
「でも、殺せなかった!」
彼女はすぐに一人の女性兵士に取り押さえられ、剣を取り上げられた。
殺す、殺すと叫び続ける彼女に対して傭兵たちを屠った兵士たちは沈痛な表情を浮かべ、魔法によって彼女の意識を刈り取った。
次に目覚めたとき、彼女は皇都の病院だった。
家族を失った悲しみと、復讐を果たせなかった虚しさ以外、何も残っていなかった。
10
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

娼館で元夫と再会しました
無味無臭(不定期更新)
恋愛
公爵家に嫁いですぐ、寡黙な夫と厳格な義父母との関係に悩みホームシックにもなった私は、ついに耐えきれず離縁状を机に置いて嫁ぎ先から逃げ出した。
しかし実家に帰っても、そこに私の居場所はない。
連れ戻されてしまうと危惧した私は、自らの体を売って生計を立てることにした。
「シーク様…」
どうして貴方がここに?
元夫と娼館で再会してしまうなんて、なんという不運なの!

私が死んで満足ですか?
マチバリ
恋愛
王太子に婚約破棄を告げられた伯爵令嬢ロロナが死んだ。
ある者は面倒な婚約破棄の手続きをせずに済んだと安堵し、ある者はずっと欲しかった物が手に入ると喜んだ。
全てが上手くおさまると思っていた彼らだったが、ロロナの死が与えた影響はあまりに大きかった。
書籍化にともない本編を引き下げいたしました

魔王を倒した手柄を横取りされたけど、俺を処刑するのは無理じゃないかな
七辻ゆゆ
ファンタジー
「では罪人よ。おまえはあくまで自分が勇者であり、魔王を倒したと言うのだな?」
「そうそう」
茶番にも飽きてきた。処刑できるというのなら、ぜひやってみてほしい。
無理だと思うけど。

もう無理して私に笑いかけなくてもいいですよ?
冬馬亮
恋愛
公爵令嬢のエリーゼは、遅れて出席した夜会で、婚約者のオズワルドがエリーゼへの不満を口にするのを偶然耳にする。
オズワルドを愛していたエリーゼはひどくショックを受けるが、悩んだ末に婚約解消を決意する。
だが、喜んで受け入れると思っていたオズワルドが、なぜか婚約解消を拒否。関係の再構築を提案する。
その後、プレゼント攻撃や突撃訪問の日々が始まるが、オズワルドは別の令嬢をそばに置くようになり・・・
「彼女は友人の妹で、なんとも思ってない。オレが好きなのはエリーゼだ」
「私みたいな女に無理して笑いかけるのも限界だって夜会で愚痴をこぼしてたじゃないですか。よかったですね、これでもう、無理して私に笑いかけなくてよくなりましたよ」

本物の夫は愛人に夢中なので、影武者とだけ愛し合います
こじまき
恋愛
幼い頃から許嫁だった王太子ヴァレリアンと結婚した公爵令嬢ディアーヌ。しかしヴァレリアンは身分の低い男爵令嬢に夢中で、初夜をすっぽかしてしまう。代わりに寝室にいたのは、彼そっくりの影武者…生まれたときに存在を消された双子の弟ルイだった。
※「小説家になろう」にも投稿しています

魔王を倒した勇者を迫害した人間様方の末路はなかなか悲惨なようです。
カモミール
ファンタジー
勇者ロキは長い冒険の末魔王を討伐する。
だが、人間の王エスカダルはそんな英雄であるロキをなぜか認めず、
ロキに身の覚えのない罪をなすりつけて投獄してしまう。
国民たちもその罪を信じ勇者を迫害した。
そして、処刑場される間際、勇者は驚きの発言をするのだった。

王子を身籠りました
青の雀
恋愛
婚約者である王太子から、毒を盛って殺そうとした冤罪をかけられ収監されるが、その時すでに王太子の子供を身籠っていたセレンティー。
王太子に黙って、出産するも子供の容姿が王家特有の金髪金眼だった。
再び、王太子が毒を盛られ、死にかけた時、我が子と対面するが…というお話。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる
本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。
このユーザをミュートしますか?
※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。
※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。
※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。