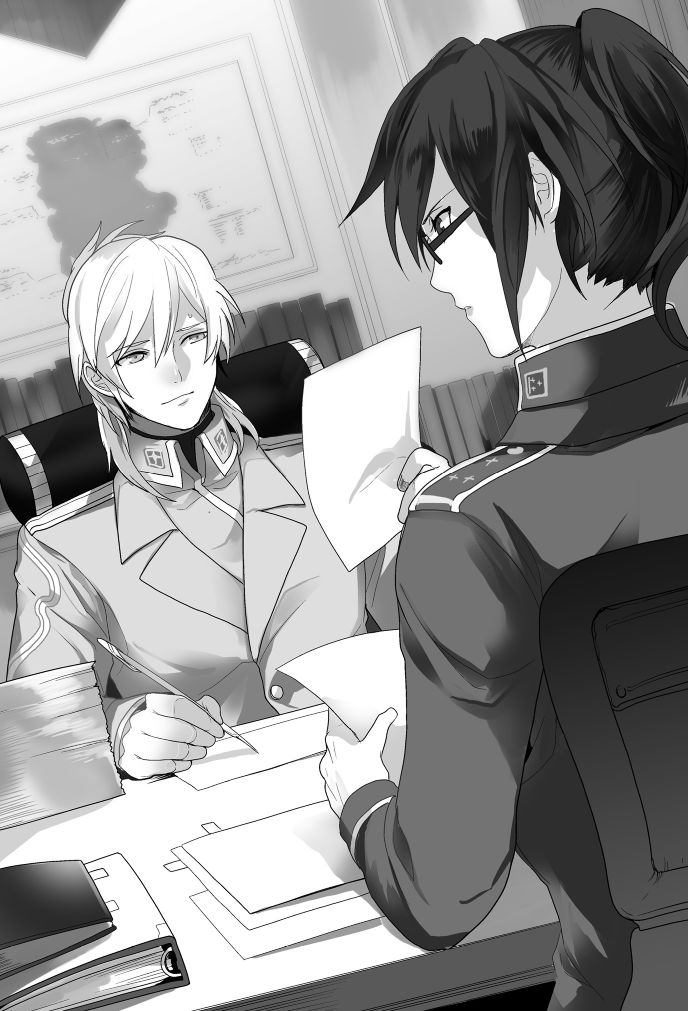50 / 526
4巻
4-2
しおりを挟む
「だから私はずっとあんたたちを追い続けた!」
慰問の予定は、慰問先以外に知らされていない。
警備上の問題だが、それは女性にとって不都合以外の何物でも無かった。
リリシアが現れたと聞いてその場に向かっても、既にリリシアの姿はなく。そんなことを何度も繰り返した。
そして今日、ようやくリリシアの慰問の情報を掴み、想いを遂げるためにここへ現れた。
「これは、あんたたち皇族が招いたこと! 自分たちさえ律することが出来なかったあんたたちが人を支配しようとしたからこんなことになった!」
女性が懐から短剣を取り出す。
きらりと輝く白刃に、リリシアの蒼褪めた顔が映った。
「猊下をお守りせよ!」
メチェリたちが慌ててリリシアから女性を引き剥がそうとする。
しかし、女性の動きの方が僅かに速い。
「報いなのよ! これはッ!!」
女性は短剣を逆手に構える。
そこに至り、リリシアは女性の真意に気付いた。
彼女は――
「――ッ! だめぇええええええええええええええッ!!」
「民の血に塗れ、地獄に堕ちろッ!!」
自分の喉に、短剣を突き刺した。
「ああ……あああ……」
真っ青な顔で女を見るリリシア。
その目の前で、女は咳き込んだ。
「ごぶっ……」
噴き出す鮮血。
女性は血の泡を吐きながら、リリシアの目を睨み続ける。
崩れ落ちそうになる女性の身体をリリシアが支えようとするが、彼女の力では支えきれなかった。共に地面に倒れ込んでしまう。
リリシアはメチェリたちが治癒魔法の術式を編んでいることに気付いたが、もう間に合わないと悟る。既に、女性の目から生気は抜け落ちていた。
ただ、その唇だけが震えるように音を紡いでいる。
リリシアは意を決し、女性の口元に耳を寄せた。
「ちの……あかが、あんたら……には……おにあい……」
「――!」
リリシアの頬を伝った血が、口に入り、錆のような味を感じさせる。
他の誰にも聞こえなかったその言葉が、嘲笑を浮かべたまま息絶えた女性の遺言だった。
◇ ◇ ◇
予定を取りやめようというメチェリたちの言葉に、返り血を浴びたままのリリシアは力無く首を横に振った。
ここで退いては、きっと彼女の言う通りになってしまう。そう感じたのだ。
リリシアは急ぎ後宮に戻って着替え、次の予定へと向かう。
その足取りは重く、メチェリたちは護衛以外にも心を砕かねばならなかった。
それでも何とか予定を消化し、ついにパールフェルとの面会に漕ぎ着けた。
だが、その頃にはもう、リリシアの目にあの女性と会うまで確かにあった眩しい輝きはない。
まるで生きる屍のような空虚な瞳で、パールフェルの待つ離宮へと向かうこととなった。
リリシアがパールフェルに抱いた最初の印象は、『儚い』。
パールフェルがリリシアに抱いた最初の印象は、『脆い』。
お互いに疲れ切った表情で、二人は離宮の庭園にて対面した。
「こうして顔を合わせるのは二度目ですね、猊下」
「はい、先日は碌にお話しする時間もありませんでしたから……」
パールフェルは喪服である黒衣を纏い、面紗の向こうからリリシアを見詰めてきた。
その瞳に在るのは、ただ諦念と疲労のみ。
他の多くの皇妃が実家へと帰参する中、ただ一人帰る場所もなくレクティファールが用意した離宮へと下がることしか出来なかった彼女にとって、これまでの総てがただ疲れるだけのことだったのだろう。
この国で彼女の味方は殆どいない。
いや、総てが敵と言っても過言ではないはずだ。
此度の騒乱の原因は、間違いなく彼女の夫にあるのだから。
「今日は、猊下にお伝えしたいことがあってお招きいたしました。ご多忙の中、ご足労頂き感謝いたします」
深々と頭を下げるパールフェル。
イズモの血を色濃く受け継いでいるらしい黒髪が、面紗の向こうに見えた。
「こちらこそ、ご挨拶に伺おうと思っていながら、此度の遅参、お許し下さい」
リリシアも謝罪の言葉と共に頭を下げる。
立場としてはリリシアの方が上であるが、パールフェルは皇妃であり、リリシアにとって義母のようなものだ。礼を失する態度は取れない。
パールフェルはリリシアの言葉に苦笑し、テーブルの上に置かれたお茶を勧めた。
「亡き陛下がよくわたくしに送ってくださった茶葉です。向こう見ずなところもあった陛下ですが、わたくしたち妃にはお優しい方でした」
「――頂きます」
そっとお茶を口に運ぶリリシア。
香りも良く、口に含んだお茶から広がる味わいも深く、芳醇だった。
恐らくリリシアが知らない種類の茶葉だが、一口で彼女の心を掴んだ。
「イズモ産の落葉茶と申します。お気に召されましたか?」
「はい……とても……」
パールフェルはリリシアの答えに微笑み、自分も一口お茶を含んだ。
しばし懐かしげに磁碗の中を見詰め、庭園へと目を移した。
「お話ししたいことというのは、陛下のことです」
「はい」
リリシアは居住まいを正した。
いつか来ると思っていた話題だが、やはり感情が波立つ。
先程の女性の姿が、幾度も心にちらついた。
「世では陛下は裏切り者、愚皇と呼ばれているようですね」
「はい……」
答えながら、俯くリリシア。
民にとって全く正当な評だが、目の前の女性にとってはまた別だ。
「お気になさらず、猊下が気に病む必要はありません」
パールフェルは諦めきった表情で、リリシアを慰める。しかし、その目に映る悲しみは大きく、隠しきれていない。
「陛下のなしたことを思えば、わたくしたちが犯した罪を思えば、確かに正しい言葉です。民たちに何と言って詫びればいいのか、正直考えつきません」
パールフェルが表に立てば、民たちの怒りは再燃する。
レクティファールはそれを恐れ、騒動の罪をグリマルディ侯と当代皇王に被せることで事態の沈静化を図った。
だからこそ、パールフェルは民に石もて追われること無く、この離宮で静かに暮らしていられる。
「ですが、摂政殿下にだけは陛下のお心を知って頂きたいのです。されど、わたくしが殿下の下に参じれば、下衆の勘繰りをする者も現れましょう。殿下の評判に傷を付けることにもなりかねません」
「だから、殿下が北にいる間に、わたしをお呼びに……?」
「ええ」
パールフェルはレクティファールが北に向かっている間に、総ての決着を付けるつもりだった。
これからの皇国の舵取りを少しでも容易にするため、そして、亡き夫の願いを叶えるために。
「陛下は――あの方はこの国を心から愛しておられました」
リリシアは黙り込み、パールフェルの言葉をひたすら受け止める。
「北の帝国、西の連合国、どちらも我が国にとって大いなる脅威。東のイズモとて、〈天照〉を擁し油断ならない相手です」
パールフェルは静かに続けた。
「ですが、先代陛下はそれらの国々と友誼を結ぶことに執心され、我が夫はそんな父親の姿勢を批判し続けていました。そんな弱腰では相手に付け入られると」
それは、確かに先代皇王の外交姿勢の一側面だった。
事実、帝国は先代皇王の外交姿勢で勢い付き、こうして大規模な軍を差し向けてきたのだ。
「だから、あの方は自分がこの国を守るのだと」
父が頼りないのなら、自分がこの国を守る。今上皇王はそう決意した。
現れたはずの〝白〟を害したという噂も、そこに原因があるのだろう。
皇太子たる〝白〟の教育は当代の皇王が担当する。
ならば、当然当代皇王の政治姿勢が〝白〟に色濃く継承されることになるだろう。
つまり、父の薫陶を受けた〝白〟が皇王となれば、この国はこれまでと変わらず他国に対して弱腰で居続ける。
だから彼は、〝白〟を廃して自らが立った。それが事実では無いとしても、人々はそう思った。
「今から思えば、先代陛下のお考えも理解出来ます。ですが、当時の夫にも、わたくしにもそれは理解出来なかった。先代陛下は国を滅ぼしてしまう、本気でそう思っておりました」
守りたい。
そう願い、今上皇王は権力を求めた。
誰にも虐げられることのない、絶対的な権力を。
「――陛下はその想いを、貴族たちに利用されたのかも知れません」
先代皇王の御代、非主流派であった今上皇王の支持貴族。
彼らは権力を手に入れるため、今上皇王を誑かした。
「貴族たちは言葉巧みに陛下を陥れました。言っても信じては貰えないでしょうが、多くの忠臣を遠ざけたのは陛下の意志ではなく、彼らの思惑だったのです。彼らの忠誠心は見事なれど、今は陛下の想いの妨げになる、と」
今上皇王は彼ら忠臣を疎みはした。
だが、その皇国への愛情に疑いなど持たなかった。
だから、いつか分かり合えると思い続けていた。
今上皇王にとって、彼らが敵となる理由など、ありはしなかったのだ。
「結果として、陛下は多くの忠臣を遠ざけ、自分の成すべきことに協力的な者たちを権力の座に就けました」
この処遇は、一時的なものとなるはずだった。
今上皇王の願いを忠臣たちが理解することが出来れば、すぐにでも中央に呼び戻すつもりだった。
「ですが、事態は最悪な方向へと動き始めました」
それは、連合の侵攻と、始原貴族の皇王に対する裏切り。
「陛下は、このとき壊れてしまわれたのかもしれません」
疎み、それでも信じていた始原貴族の裏切り。
だが、その始原貴族もまた、今上皇王に裏切られたと思っていた。
彼らの行き違いは、致命的な齟齬となって皇国に未曾有の惨禍をもたらす。
「陛下は何としても連合の侵攻を阻止しようと軍を集めました。しかし、その策も失敗だったのでしょう。このとき陛下が胸襟を開いて始原貴族たちと話し合っていれば事態は好転していたかもしれません。ですが、始原貴族を信じられなくなっていた陛下は、自らを支持する貴族たちに軍を集めさせ、それを連合にぶつけた」
結果は、惨敗。
さらに今上皇王の思惑を超え、始原貴族たちも軍を発する動きを見せ始めた。
「始原貴族たちの裏切り、陛下はそれを嘆いておられました。そして幾度も敗退を重ねる自らの軍、既に陛下のお心は限界でした」
やがて連合が皇都を包囲したとき、今上皇王は命を落とした。
それから始まったのは、まさに悲劇としか言いようの無い出来事だった。
「陛下がお隠れあそばされたとき、わたくしは『やはり』と思っておりました。ですが、陛下がどのようにして命を落としたのか、未だ真実は分かりません。自ら命を絶ったのか、貴族の謀反によって弑されたのか、或いはそれ以外の何かが起きたのか」
パールフェルはリリシアに向き直り、再び頭を垂れた。
「陛下の罪は消えません。ですが、陛下の願いだけは殿下にお伝え頂きたいのです。あの方は間違いなくこの国を愛し、守りたかった。その想いだけは、殿下に受け継いで頂きたいのです」
皇太子たる〝白〟の教育は当代皇王の役目。
ならば、レクティファールに歴代皇王の想いを繋げるのは今上皇王であってほしいとパールフェルは思った。
「どうか、殿下にお伝え下さい。この国の皇王は、ただ一人の例外もなく皇国を愛していたと」
「―――」
リリシアは瞑目する。
頷くことは出来る。
だが、それは民の想いを踏み躙ることにはならないだろうか。
今上皇王の想いを肯定することは、民たちの苦しみを肯定することにはならないだろうか。
「どうか、お願いします」
パールフェルは震える声で懇願する。
彼女にとって、これが妻として夫に出来る最後のことだった。
それは、リリシアにも理解出来た。
「――分かりました」
「あ、ありがとうございます……!」
そして、ここで自分に出来ることは、ここで頷いた罪を背負うこと。
あの女性の血を纏い、生き続けること。
「我が名に誓って、陛下の想い、殿下にお伝えいたします」
あの方のため、罪を背負い続けること。
「きっと、レクティファール殿下も理解してくださるでしょう」
民たちの怨嗟を受けながら、微笑み続けること。
第二章 戦いの兆し
「摂政付参謀」
そうリーデが声を掛けられたのは、司令室にもっとも近い士官用食堂でのことだった。
遅い昼食、早目の夕食、どちらとも言えるような時間帯に食堂に訪れたにも拘わらず、そこは随分と盛況であった。この戦役で何度目かの限定休戦。要塞内は設備の補修や負傷者の後送のために戦闘中とは別種の忙しさがある。
「こっちだ」
リーデが視線を巡らせると、奥まった一席で手を振る男の姿があった。
砲兵参謀。陸軍砲兵科大佐の階級章と兵科章を着用した吸血族の男だ。
「――何か御用ですか?」
自分の食事の載った角盆を抱え、リーデは砲兵参謀の下に近付く。
そこには、砲兵参謀の他に何人かいた。いずれも金色の参謀飾緒を着けた主任参謀たちである。
「一緒にどうかと思ってな。――殿下のご様子も聞いておきたい」
砲兵参謀は声を落として答え、立場上、リーデはその求めに応じることを選択するしかなかった。
摂政付参謀は、摂政と他の軍人の間を取り持つことも役目の一つである。
「機兵参謀殿も、おられたのですか」
「――たまには、な」
リーデは主任参謀たちの中に、機兵参謀の姿があることに少しだけ驚いた。
これまでの印象からすれば、こういった場で同僚と同じ席に座り、食事をとるなんて想像できない。
「どういった心境の変化かは分からないが、機兵参謀の方から声を掛けてきたんだ。前まではどれだけ誘っても、袖にされてたんだがなぁ」
騎兵参謀が蒸し芋を頬張りながら、感慨深げに呟く。人間種の中年男性で、この集まりの中では最先任であった。
「殿下に色々教えてもらったのです」
機兵参謀の言葉に、リーデの眉がぴくりと動く。不快ではないが、理解できない。
「色々、ね」
龍族女性の航空参謀が面白そうに目を細め、貝練麺を突き匙に刺したまま喉を鳴らした。
「せいぜい手篭めにされないよう気を付けなさい。メリエラ様は嫉妬深そうよ」
同じ龍族として思うところがあるのか、航空参謀の言葉は何とも不穏な響きを帯びていた。
彼女自身は紅龍公の一族に属するが、龍族の基本的気質に関してはどの一族でもさほど違いはない。
「――そういうことではない」
機兵参謀は同僚の言葉を否定すると、無言で自分の焼飯を口に放り込む。その様子を黙って見ていた他の参謀たちは、無言でリーデに席を勧めた。
「失礼します」
勧められた席に座り、リーデは湯気を立てる牛乳粥に匙を入れた。食事が充実しているのは皇国軍の特徴の一つとして挙げられている。他国への研修旅行に出る機会のある参謀たちは、その評価の正しさを自身の経験から理解している。
前線で温かい食事をとることができる軍隊が、果たしてどれだけ存在しているのか。
熱感知を防ぐために遮熱布で覆った炊事所が、皇国軍の前線には点在しているのだ。対して帝国軍は、凍り付いた缶詰を人肌で溶かして食べるようなことも珍しくない。
「それで、殿下のことなのだが」
砲兵参謀の言葉に、リーデは顔を上げる。彼女の上司たちが揃って自分に目を向けている光景は、さながら査問会のようだと彼女は思った。
「ご様子はどうだ」
「特に変化はありません。いつもと同じように過ごしておられます」
戦闘後に行われた身体検査を終え、執務室に戻ってきたレクティファールは、戦いに赴く前とさしたる違いはなかった。
すでに一度実戦に出ているからなのか、〈皇剣〉の持つ力なのか、リーデにはその理由は分からない。ただ、レクティファールがあの戦闘の前後で大きな変化を見せていないということだけが、彼女にとっての事実であった。
「あの子たちは――」
機兵参謀が口を開くと、周囲の視線はそちらに集中した。リーデもまた、同じように機兵参謀に目を向ける。
「殿下に、それ以外の総てにさえも感謝するという感情もまだ理解できていない。だから、私が代わって感謝していたと、伝えて貰えないだろうか」
リーデは、機兵参謀の表情を見、そこに微かな羞恥を見出した。
何故だろうと考え、あの戦闘前のできごとが原因なのだと理解した。
「参謀ご自身がお伝えください。殿下は参謀の望みを叶えたのでしょうが、それは殿下ご自身の願いでもあったからです。人に感謝することは、決して恥じることではありません」
「そうだぞ機兵参謀。殿下が君の同胞を救ったのは事実、それを嬉しいと思うのなら、そう伝えればいい」
騎兵参謀が肉団子を頬張りながらリーデに追従する。
面白そうだから、というだけではないだろう。参謀たちの間には、機兵参謀というある種の幼さを残した同僚を見守る仲間意識があった。
「そうね。誰だってお礼を言われれば嬉しい。言った方も相手が喜べば嬉しいし、いいこと尽くめでしょう」
航空参謀が笑みを浮かべ、騎兵参謀に同調する。
「それで、摂政付参謀。殿下のこれからの予定は?」
砲兵参謀がリーデに問う。
リーデは、レクティファールの予定を脳裏に浮かべ、その内容を答えた。
「今日はこれから皇都より持ち込まれた書類の決裁などを行うそうです。小官はその間、レクティファール様にお渡しする資料の整理を」
「では、今日はずっと執務室におられるのだな」
騎兵参謀の表情はひどく明るい。航空参謀も同じような表情を浮かべ、機兵参謀だけがいつもの無表情であった。
「――――」
機兵参謀は何も言わない。
ただ、何度もリーデの顔を窺い、食事の手がその都度止まった。
「機兵参謀殿」
リーデはその姿に呆れてしまった。
理路整然と思考を制御し、失敗もなく、ただ妥当な結果のみを得られるはずの機人族が何故――と思った。
「お手隙なら、我軍の自動人形部隊に関する資料を頂けませんか。可能なら直接殿下にご説明頂ければ……」
ただ、参謀として正しいことを選ぶなら、こう口にするべきだと思った。
自動人形部隊は軍の中にあってある種特異な位置にある。リーデもそれなりに知識はあるが、実際にそれらの部隊の運用方法を研究している本職の機兵参謀が説明した方が良いだろう。
「――分かった。では、一七〇〇に伺う」
「了解しました。殿下にお伝えいたします」
リーデは何故か、精神的な疲労を感じ、溜息を吐いた。
レクティファールは食事から戻ったリーデに微かな違和感を覚えた。
小さく会釈する態度や所作そのものに変わりはない。だが、レクティファールをじっと見詰めるようなその視線がこれまでとは僅かに違っているように思える。
そう、敢えて言葉にするならば、これまでの視線が監視で、今の視線は何かを試すような、摂政としてのレクティファールではなく、レクティファールという個人を見ているかのような視線だった。
だが、その直感を口にして説明することは出来ないし、仮に説明出来たとしてそれが問題であるかと問われれば、否である。
そのリーデ・アーデンという参謀からしてみれば、レクティファールという男は常に監視対象であって考試対象でもあった。当然、レクティファールの一挙手一投足に注目してそれを然るべき相手に報告する必要があるだろう。
それに、自分勝手に戦場に飛び出した男を見る目としては、まだ優しさがあるのではないだろうか。
徹底して冷たい視線を向けられるのだろうと思っていたレクティファールにとって、むしろ幸運だったと言って良い。しかし、幸運だから何かをするということもない。
「――仕事をしても?」
「どうぞ」
ただそれだけの言葉を交わして、レクティファールは執務机に積まれた書類の決裁を始める。
「参謀、ここから北方総軍司令部に書簡を届けるとしたら、どれくらい掛かる?」
「飛竜を使って最短で一日というところでしょうか」
「ふむ」
レクティファールは手元の書類に花押を書き入れながら、思案するように唸る。
近衛軍から派遣されてきた秘書役の下士官たちが忙しなくレクティファールの周囲を動き回り、決裁待ちの書類を持ってきたかと思えば、決裁の終わった別の書類を抱えて執務室を出ていく。
普段であればメリエラが顔を出すこともあるが、戦闘で傷を負ったこともあり、今日は一日ウィリィアと共に静養している。
「何かございましたか」
「うん、まあ、そんな所で」
レクティファールはひらひらと一枚の紙を揺らし、リーデの興味を引き付けた。
「北方総軍からの援軍編成の行程表です。これによると、やはり万単位の援軍編成には時間がかかるようで」
師団規模の援軍となれば、移動一つとってもそれなりの準備を要する。それは送り出す側も、受け容れる側も同じだ。
特に、北方総軍は帝国軍の別働隊を警戒して国境全体に神経を尖らせている。
いくら山脈によって守られた国境とはいえ、ものごとに絶対はない。
ゼレーヴェ川、ギルツ北原、ノルティアス川の上流。北方国境の要衝といえばその辺りだが、皇国と北東部で国境を接しているヴィストーレ半島国家群は、先の内乱の際に帝国側に利する行動を見せていた前科がある。
いまでこそ皇国側に擦り寄る態度を見せているが、いつ手のひらを返すか分かったものではないのだ。
「〈トゥーム〉の海軍陸戦師団にも動員を掛けて、ようやく総ての拠点に兵力を手当てしているのが現状です。〈カティーナ〉にも予備兵力を置かなくてはなりませんし、ギルツの国境線だって警戒態勢を維持しなくてはなりません」
皇国陸軍でもっとも大きな兵力を持つ北方総軍であるが、その数は担当区域に比して十分とは言い切れない。
ただそれは、東西南北中央と、総てを見ても同じことなのだ。
慰問の予定は、慰問先以外に知らされていない。
警備上の問題だが、それは女性にとって不都合以外の何物でも無かった。
リリシアが現れたと聞いてその場に向かっても、既にリリシアの姿はなく。そんなことを何度も繰り返した。
そして今日、ようやくリリシアの慰問の情報を掴み、想いを遂げるためにここへ現れた。
「これは、あんたたち皇族が招いたこと! 自分たちさえ律することが出来なかったあんたたちが人を支配しようとしたからこんなことになった!」
女性が懐から短剣を取り出す。
きらりと輝く白刃に、リリシアの蒼褪めた顔が映った。
「猊下をお守りせよ!」
メチェリたちが慌ててリリシアから女性を引き剥がそうとする。
しかし、女性の動きの方が僅かに速い。
「報いなのよ! これはッ!!」
女性は短剣を逆手に構える。
そこに至り、リリシアは女性の真意に気付いた。
彼女は――
「――ッ! だめぇええええええええええええええッ!!」
「民の血に塗れ、地獄に堕ちろッ!!」
自分の喉に、短剣を突き刺した。
「ああ……あああ……」
真っ青な顔で女を見るリリシア。
その目の前で、女は咳き込んだ。
「ごぶっ……」
噴き出す鮮血。
女性は血の泡を吐きながら、リリシアの目を睨み続ける。
崩れ落ちそうになる女性の身体をリリシアが支えようとするが、彼女の力では支えきれなかった。共に地面に倒れ込んでしまう。
リリシアはメチェリたちが治癒魔法の術式を編んでいることに気付いたが、もう間に合わないと悟る。既に、女性の目から生気は抜け落ちていた。
ただ、その唇だけが震えるように音を紡いでいる。
リリシアは意を決し、女性の口元に耳を寄せた。
「ちの……あかが、あんたら……には……おにあい……」
「――!」
リリシアの頬を伝った血が、口に入り、錆のような味を感じさせる。
他の誰にも聞こえなかったその言葉が、嘲笑を浮かべたまま息絶えた女性の遺言だった。
◇ ◇ ◇
予定を取りやめようというメチェリたちの言葉に、返り血を浴びたままのリリシアは力無く首を横に振った。
ここで退いては、きっと彼女の言う通りになってしまう。そう感じたのだ。
リリシアは急ぎ後宮に戻って着替え、次の予定へと向かう。
その足取りは重く、メチェリたちは護衛以外にも心を砕かねばならなかった。
それでも何とか予定を消化し、ついにパールフェルとの面会に漕ぎ着けた。
だが、その頃にはもう、リリシアの目にあの女性と会うまで確かにあった眩しい輝きはない。
まるで生きる屍のような空虚な瞳で、パールフェルの待つ離宮へと向かうこととなった。
リリシアがパールフェルに抱いた最初の印象は、『儚い』。
パールフェルがリリシアに抱いた最初の印象は、『脆い』。
お互いに疲れ切った表情で、二人は離宮の庭園にて対面した。
「こうして顔を合わせるのは二度目ですね、猊下」
「はい、先日は碌にお話しする時間もありませんでしたから……」
パールフェルは喪服である黒衣を纏い、面紗の向こうからリリシアを見詰めてきた。
その瞳に在るのは、ただ諦念と疲労のみ。
他の多くの皇妃が実家へと帰参する中、ただ一人帰る場所もなくレクティファールが用意した離宮へと下がることしか出来なかった彼女にとって、これまでの総てがただ疲れるだけのことだったのだろう。
この国で彼女の味方は殆どいない。
いや、総てが敵と言っても過言ではないはずだ。
此度の騒乱の原因は、間違いなく彼女の夫にあるのだから。
「今日は、猊下にお伝えしたいことがあってお招きいたしました。ご多忙の中、ご足労頂き感謝いたします」
深々と頭を下げるパールフェル。
イズモの血を色濃く受け継いでいるらしい黒髪が、面紗の向こうに見えた。
「こちらこそ、ご挨拶に伺おうと思っていながら、此度の遅参、お許し下さい」
リリシアも謝罪の言葉と共に頭を下げる。
立場としてはリリシアの方が上であるが、パールフェルは皇妃であり、リリシアにとって義母のようなものだ。礼を失する態度は取れない。
パールフェルはリリシアの言葉に苦笑し、テーブルの上に置かれたお茶を勧めた。
「亡き陛下がよくわたくしに送ってくださった茶葉です。向こう見ずなところもあった陛下ですが、わたくしたち妃にはお優しい方でした」
「――頂きます」
そっとお茶を口に運ぶリリシア。
香りも良く、口に含んだお茶から広がる味わいも深く、芳醇だった。
恐らくリリシアが知らない種類の茶葉だが、一口で彼女の心を掴んだ。
「イズモ産の落葉茶と申します。お気に召されましたか?」
「はい……とても……」
パールフェルはリリシアの答えに微笑み、自分も一口お茶を含んだ。
しばし懐かしげに磁碗の中を見詰め、庭園へと目を移した。
「お話ししたいことというのは、陛下のことです」
「はい」
リリシアは居住まいを正した。
いつか来ると思っていた話題だが、やはり感情が波立つ。
先程の女性の姿が、幾度も心にちらついた。
「世では陛下は裏切り者、愚皇と呼ばれているようですね」
「はい……」
答えながら、俯くリリシア。
民にとって全く正当な評だが、目の前の女性にとってはまた別だ。
「お気になさらず、猊下が気に病む必要はありません」
パールフェルは諦めきった表情で、リリシアを慰める。しかし、その目に映る悲しみは大きく、隠しきれていない。
「陛下のなしたことを思えば、わたくしたちが犯した罪を思えば、確かに正しい言葉です。民たちに何と言って詫びればいいのか、正直考えつきません」
パールフェルが表に立てば、民たちの怒りは再燃する。
レクティファールはそれを恐れ、騒動の罪をグリマルディ侯と当代皇王に被せることで事態の沈静化を図った。
だからこそ、パールフェルは民に石もて追われること無く、この離宮で静かに暮らしていられる。
「ですが、摂政殿下にだけは陛下のお心を知って頂きたいのです。されど、わたくしが殿下の下に参じれば、下衆の勘繰りをする者も現れましょう。殿下の評判に傷を付けることにもなりかねません」
「だから、殿下が北にいる間に、わたしをお呼びに……?」
「ええ」
パールフェルはレクティファールが北に向かっている間に、総ての決着を付けるつもりだった。
これからの皇国の舵取りを少しでも容易にするため、そして、亡き夫の願いを叶えるために。
「陛下は――あの方はこの国を心から愛しておられました」
リリシアは黙り込み、パールフェルの言葉をひたすら受け止める。
「北の帝国、西の連合国、どちらも我が国にとって大いなる脅威。東のイズモとて、〈天照〉を擁し油断ならない相手です」
パールフェルは静かに続けた。
「ですが、先代陛下はそれらの国々と友誼を結ぶことに執心され、我が夫はそんな父親の姿勢を批判し続けていました。そんな弱腰では相手に付け入られると」
それは、確かに先代皇王の外交姿勢の一側面だった。
事実、帝国は先代皇王の外交姿勢で勢い付き、こうして大規模な軍を差し向けてきたのだ。
「だから、あの方は自分がこの国を守るのだと」
父が頼りないのなら、自分がこの国を守る。今上皇王はそう決意した。
現れたはずの〝白〟を害したという噂も、そこに原因があるのだろう。
皇太子たる〝白〟の教育は当代の皇王が担当する。
ならば、当然当代皇王の政治姿勢が〝白〟に色濃く継承されることになるだろう。
つまり、父の薫陶を受けた〝白〟が皇王となれば、この国はこれまでと変わらず他国に対して弱腰で居続ける。
だから彼は、〝白〟を廃して自らが立った。それが事実では無いとしても、人々はそう思った。
「今から思えば、先代陛下のお考えも理解出来ます。ですが、当時の夫にも、わたくしにもそれは理解出来なかった。先代陛下は国を滅ぼしてしまう、本気でそう思っておりました」
守りたい。
そう願い、今上皇王は権力を求めた。
誰にも虐げられることのない、絶対的な権力を。
「――陛下はその想いを、貴族たちに利用されたのかも知れません」
先代皇王の御代、非主流派であった今上皇王の支持貴族。
彼らは権力を手に入れるため、今上皇王を誑かした。
「貴族たちは言葉巧みに陛下を陥れました。言っても信じては貰えないでしょうが、多くの忠臣を遠ざけたのは陛下の意志ではなく、彼らの思惑だったのです。彼らの忠誠心は見事なれど、今は陛下の想いの妨げになる、と」
今上皇王は彼ら忠臣を疎みはした。
だが、その皇国への愛情に疑いなど持たなかった。
だから、いつか分かり合えると思い続けていた。
今上皇王にとって、彼らが敵となる理由など、ありはしなかったのだ。
「結果として、陛下は多くの忠臣を遠ざけ、自分の成すべきことに協力的な者たちを権力の座に就けました」
この処遇は、一時的なものとなるはずだった。
今上皇王の願いを忠臣たちが理解することが出来れば、すぐにでも中央に呼び戻すつもりだった。
「ですが、事態は最悪な方向へと動き始めました」
それは、連合の侵攻と、始原貴族の皇王に対する裏切り。
「陛下は、このとき壊れてしまわれたのかもしれません」
疎み、それでも信じていた始原貴族の裏切り。
だが、その始原貴族もまた、今上皇王に裏切られたと思っていた。
彼らの行き違いは、致命的な齟齬となって皇国に未曾有の惨禍をもたらす。
「陛下は何としても連合の侵攻を阻止しようと軍を集めました。しかし、その策も失敗だったのでしょう。このとき陛下が胸襟を開いて始原貴族たちと話し合っていれば事態は好転していたかもしれません。ですが、始原貴族を信じられなくなっていた陛下は、自らを支持する貴族たちに軍を集めさせ、それを連合にぶつけた」
結果は、惨敗。
さらに今上皇王の思惑を超え、始原貴族たちも軍を発する動きを見せ始めた。
「始原貴族たちの裏切り、陛下はそれを嘆いておられました。そして幾度も敗退を重ねる自らの軍、既に陛下のお心は限界でした」
やがて連合が皇都を包囲したとき、今上皇王は命を落とした。
それから始まったのは、まさに悲劇としか言いようの無い出来事だった。
「陛下がお隠れあそばされたとき、わたくしは『やはり』と思っておりました。ですが、陛下がどのようにして命を落としたのか、未だ真実は分かりません。自ら命を絶ったのか、貴族の謀反によって弑されたのか、或いはそれ以外の何かが起きたのか」
パールフェルはリリシアに向き直り、再び頭を垂れた。
「陛下の罪は消えません。ですが、陛下の願いだけは殿下にお伝え頂きたいのです。あの方は間違いなくこの国を愛し、守りたかった。その想いだけは、殿下に受け継いで頂きたいのです」
皇太子たる〝白〟の教育は当代皇王の役目。
ならば、レクティファールに歴代皇王の想いを繋げるのは今上皇王であってほしいとパールフェルは思った。
「どうか、殿下にお伝え下さい。この国の皇王は、ただ一人の例外もなく皇国を愛していたと」
「―――」
リリシアは瞑目する。
頷くことは出来る。
だが、それは民の想いを踏み躙ることにはならないだろうか。
今上皇王の想いを肯定することは、民たちの苦しみを肯定することにはならないだろうか。
「どうか、お願いします」
パールフェルは震える声で懇願する。
彼女にとって、これが妻として夫に出来る最後のことだった。
それは、リリシアにも理解出来た。
「――分かりました」
「あ、ありがとうございます……!」
そして、ここで自分に出来ることは、ここで頷いた罪を背負うこと。
あの女性の血を纏い、生き続けること。
「我が名に誓って、陛下の想い、殿下にお伝えいたします」
あの方のため、罪を背負い続けること。
「きっと、レクティファール殿下も理解してくださるでしょう」
民たちの怨嗟を受けながら、微笑み続けること。
第二章 戦いの兆し
「摂政付参謀」
そうリーデが声を掛けられたのは、司令室にもっとも近い士官用食堂でのことだった。
遅い昼食、早目の夕食、どちらとも言えるような時間帯に食堂に訪れたにも拘わらず、そこは随分と盛況であった。この戦役で何度目かの限定休戦。要塞内は設備の補修や負傷者の後送のために戦闘中とは別種の忙しさがある。
「こっちだ」
リーデが視線を巡らせると、奥まった一席で手を振る男の姿があった。
砲兵参謀。陸軍砲兵科大佐の階級章と兵科章を着用した吸血族の男だ。
「――何か御用ですか?」
自分の食事の載った角盆を抱え、リーデは砲兵参謀の下に近付く。
そこには、砲兵参謀の他に何人かいた。いずれも金色の参謀飾緒を着けた主任参謀たちである。
「一緒にどうかと思ってな。――殿下のご様子も聞いておきたい」
砲兵参謀は声を落として答え、立場上、リーデはその求めに応じることを選択するしかなかった。
摂政付参謀は、摂政と他の軍人の間を取り持つことも役目の一つである。
「機兵参謀殿も、おられたのですか」
「――たまには、な」
リーデは主任参謀たちの中に、機兵参謀の姿があることに少しだけ驚いた。
これまでの印象からすれば、こういった場で同僚と同じ席に座り、食事をとるなんて想像できない。
「どういった心境の変化かは分からないが、機兵参謀の方から声を掛けてきたんだ。前まではどれだけ誘っても、袖にされてたんだがなぁ」
騎兵参謀が蒸し芋を頬張りながら、感慨深げに呟く。人間種の中年男性で、この集まりの中では最先任であった。
「殿下に色々教えてもらったのです」
機兵参謀の言葉に、リーデの眉がぴくりと動く。不快ではないが、理解できない。
「色々、ね」
龍族女性の航空参謀が面白そうに目を細め、貝練麺を突き匙に刺したまま喉を鳴らした。
「せいぜい手篭めにされないよう気を付けなさい。メリエラ様は嫉妬深そうよ」
同じ龍族として思うところがあるのか、航空参謀の言葉は何とも不穏な響きを帯びていた。
彼女自身は紅龍公の一族に属するが、龍族の基本的気質に関してはどの一族でもさほど違いはない。
「――そういうことではない」
機兵参謀は同僚の言葉を否定すると、無言で自分の焼飯を口に放り込む。その様子を黙って見ていた他の参謀たちは、無言でリーデに席を勧めた。
「失礼します」
勧められた席に座り、リーデは湯気を立てる牛乳粥に匙を入れた。食事が充実しているのは皇国軍の特徴の一つとして挙げられている。他国への研修旅行に出る機会のある参謀たちは、その評価の正しさを自身の経験から理解している。
前線で温かい食事をとることができる軍隊が、果たしてどれだけ存在しているのか。
熱感知を防ぐために遮熱布で覆った炊事所が、皇国軍の前線には点在しているのだ。対して帝国軍は、凍り付いた缶詰を人肌で溶かして食べるようなことも珍しくない。
「それで、殿下のことなのだが」
砲兵参謀の言葉に、リーデは顔を上げる。彼女の上司たちが揃って自分に目を向けている光景は、さながら査問会のようだと彼女は思った。
「ご様子はどうだ」
「特に変化はありません。いつもと同じように過ごしておられます」
戦闘後に行われた身体検査を終え、執務室に戻ってきたレクティファールは、戦いに赴く前とさしたる違いはなかった。
すでに一度実戦に出ているからなのか、〈皇剣〉の持つ力なのか、リーデにはその理由は分からない。ただ、レクティファールがあの戦闘の前後で大きな変化を見せていないということだけが、彼女にとっての事実であった。
「あの子たちは――」
機兵参謀が口を開くと、周囲の視線はそちらに集中した。リーデもまた、同じように機兵参謀に目を向ける。
「殿下に、それ以外の総てにさえも感謝するという感情もまだ理解できていない。だから、私が代わって感謝していたと、伝えて貰えないだろうか」
リーデは、機兵参謀の表情を見、そこに微かな羞恥を見出した。
何故だろうと考え、あの戦闘前のできごとが原因なのだと理解した。
「参謀ご自身がお伝えください。殿下は参謀の望みを叶えたのでしょうが、それは殿下ご自身の願いでもあったからです。人に感謝することは、決して恥じることではありません」
「そうだぞ機兵参謀。殿下が君の同胞を救ったのは事実、それを嬉しいと思うのなら、そう伝えればいい」
騎兵参謀が肉団子を頬張りながらリーデに追従する。
面白そうだから、というだけではないだろう。参謀たちの間には、機兵参謀というある種の幼さを残した同僚を見守る仲間意識があった。
「そうね。誰だってお礼を言われれば嬉しい。言った方も相手が喜べば嬉しいし、いいこと尽くめでしょう」
航空参謀が笑みを浮かべ、騎兵参謀に同調する。
「それで、摂政付参謀。殿下のこれからの予定は?」
砲兵参謀がリーデに問う。
リーデは、レクティファールの予定を脳裏に浮かべ、その内容を答えた。
「今日はこれから皇都より持ち込まれた書類の決裁などを行うそうです。小官はその間、レクティファール様にお渡しする資料の整理を」
「では、今日はずっと執務室におられるのだな」
騎兵参謀の表情はひどく明るい。航空参謀も同じような表情を浮かべ、機兵参謀だけがいつもの無表情であった。
「――――」
機兵参謀は何も言わない。
ただ、何度もリーデの顔を窺い、食事の手がその都度止まった。
「機兵参謀殿」
リーデはその姿に呆れてしまった。
理路整然と思考を制御し、失敗もなく、ただ妥当な結果のみを得られるはずの機人族が何故――と思った。
「お手隙なら、我軍の自動人形部隊に関する資料を頂けませんか。可能なら直接殿下にご説明頂ければ……」
ただ、参謀として正しいことを選ぶなら、こう口にするべきだと思った。
自動人形部隊は軍の中にあってある種特異な位置にある。リーデもそれなりに知識はあるが、実際にそれらの部隊の運用方法を研究している本職の機兵参謀が説明した方が良いだろう。
「――分かった。では、一七〇〇に伺う」
「了解しました。殿下にお伝えいたします」
リーデは何故か、精神的な疲労を感じ、溜息を吐いた。
レクティファールは食事から戻ったリーデに微かな違和感を覚えた。
小さく会釈する態度や所作そのものに変わりはない。だが、レクティファールをじっと見詰めるようなその視線がこれまでとは僅かに違っているように思える。
そう、敢えて言葉にするならば、これまでの視線が監視で、今の視線は何かを試すような、摂政としてのレクティファールではなく、レクティファールという個人を見ているかのような視線だった。
だが、その直感を口にして説明することは出来ないし、仮に説明出来たとしてそれが問題であるかと問われれば、否である。
そのリーデ・アーデンという参謀からしてみれば、レクティファールという男は常に監視対象であって考試対象でもあった。当然、レクティファールの一挙手一投足に注目してそれを然るべき相手に報告する必要があるだろう。
それに、自分勝手に戦場に飛び出した男を見る目としては、まだ優しさがあるのではないだろうか。
徹底して冷たい視線を向けられるのだろうと思っていたレクティファールにとって、むしろ幸運だったと言って良い。しかし、幸運だから何かをするということもない。
「――仕事をしても?」
「どうぞ」
ただそれだけの言葉を交わして、レクティファールは執務机に積まれた書類の決裁を始める。
「参謀、ここから北方総軍司令部に書簡を届けるとしたら、どれくらい掛かる?」
「飛竜を使って最短で一日というところでしょうか」
「ふむ」
レクティファールは手元の書類に花押を書き入れながら、思案するように唸る。
近衛軍から派遣されてきた秘書役の下士官たちが忙しなくレクティファールの周囲を動き回り、決裁待ちの書類を持ってきたかと思えば、決裁の終わった別の書類を抱えて執務室を出ていく。
普段であればメリエラが顔を出すこともあるが、戦闘で傷を負ったこともあり、今日は一日ウィリィアと共に静養している。
「何かございましたか」
「うん、まあ、そんな所で」
レクティファールはひらひらと一枚の紙を揺らし、リーデの興味を引き付けた。
「北方総軍からの援軍編成の行程表です。これによると、やはり万単位の援軍編成には時間がかかるようで」
師団規模の援軍となれば、移動一つとってもそれなりの準備を要する。それは送り出す側も、受け容れる側も同じだ。
特に、北方総軍は帝国軍の別働隊を警戒して国境全体に神経を尖らせている。
いくら山脈によって守られた国境とはいえ、ものごとに絶対はない。
ゼレーヴェ川、ギルツ北原、ノルティアス川の上流。北方国境の要衝といえばその辺りだが、皇国と北東部で国境を接しているヴィストーレ半島国家群は、先の内乱の際に帝国側に利する行動を見せていた前科がある。
いまでこそ皇国側に擦り寄る態度を見せているが、いつ手のひらを返すか分かったものではないのだ。
「〈トゥーム〉の海軍陸戦師団にも動員を掛けて、ようやく総ての拠点に兵力を手当てしているのが現状です。〈カティーナ〉にも予備兵力を置かなくてはなりませんし、ギルツの国境線だって警戒態勢を維持しなくてはなりません」
皇国陸軍でもっとも大きな兵力を持つ北方総軍であるが、その数は担当区域に比して十分とは言い切れない。
ただそれは、東西南北中央と、総てを見ても同じことなのだ。
10
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

娼館で元夫と再会しました
無味無臭(不定期更新)
恋愛
公爵家に嫁いですぐ、寡黙な夫と厳格な義父母との関係に悩みホームシックにもなった私は、ついに耐えきれず離縁状を机に置いて嫁ぎ先から逃げ出した。
しかし実家に帰っても、そこに私の居場所はない。
連れ戻されてしまうと危惧した私は、自らの体を売って生計を立てることにした。
「シーク様…」
どうして貴方がここに?
元夫と娼館で再会してしまうなんて、なんという不運なの!

私が死んで満足ですか?
マチバリ
恋愛
王太子に婚約破棄を告げられた伯爵令嬢ロロナが死んだ。
ある者は面倒な婚約破棄の手続きをせずに済んだと安堵し、ある者はずっと欲しかった物が手に入ると喜んだ。
全てが上手くおさまると思っていた彼らだったが、ロロナの死が与えた影響はあまりに大きかった。
書籍化にともない本編を引き下げいたしました

魔王を倒した手柄を横取りされたけど、俺を処刑するのは無理じゃないかな
七辻ゆゆ
ファンタジー
「では罪人よ。おまえはあくまで自分が勇者であり、魔王を倒したと言うのだな?」
「そうそう」
茶番にも飽きてきた。処刑できるというのなら、ぜひやってみてほしい。
無理だと思うけど。

もう無理して私に笑いかけなくてもいいですよ?
冬馬亮
恋愛
公爵令嬢のエリーゼは、遅れて出席した夜会で、婚約者のオズワルドがエリーゼへの不満を口にするのを偶然耳にする。
オズワルドを愛していたエリーゼはひどくショックを受けるが、悩んだ末に婚約解消を決意する。
だが、喜んで受け入れると思っていたオズワルドが、なぜか婚約解消を拒否。関係の再構築を提案する。
その後、プレゼント攻撃や突撃訪問の日々が始まるが、オズワルドは別の令嬢をそばに置くようになり・・・
「彼女は友人の妹で、なんとも思ってない。オレが好きなのはエリーゼだ」
「私みたいな女に無理して笑いかけるのも限界だって夜会で愚痴をこぼしてたじゃないですか。よかったですね、これでもう、無理して私に笑いかけなくてよくなりましたよ」

本物の夫は愛人に夢中なので、影武者とだけ愛し合います
こじまき
恋愛
幼い頃から許嫁だった王太子ヴァレリアンと結婚した公爵令嬢ディアーヌ。しかしヴァレリアンは身分の低い男爵令嬢に夢中で、初夜をすっぽかしてしまう。代わりに寝室にいたのは、彼そっくりの影武者…生まれたときに存在を消された双子の弟ルイだった。
※「小説家になろう」にも投稿しています

魔王を倒した勇者を迫害した人間様方の末路はなかなか悲惨なようです。
カモミール
ファンタジー
勇者ロキは長い冒険の末魔王を討伐する。
だが、人間の王エスカダルはそんな英雄であるロキをなぜか認めず、
ロキに身の覚えのない罪をなすりつけて投獄してしまう。
国民たちもその罪を信じ勇者を迫害した。
そして、処刑場される間際、勇者は驚きの発言をするのだった。

王子を身籠りました
青の雀
恋愛
婚約者である王太子から、毒を盛って殺そうとした冤罪をかけられ収監されるが、その時すでに王太子の子供を身籠っていたセレンティー。
王太子に黙って、出産するも子供の容姿が王家特有の金髪金眼だった。
再び、王太子が毒を盛られ、死にかけた時、我が子と対面するが…というお話。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる
本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。
このユーザをミュートしますか?
※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。
※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。
※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。