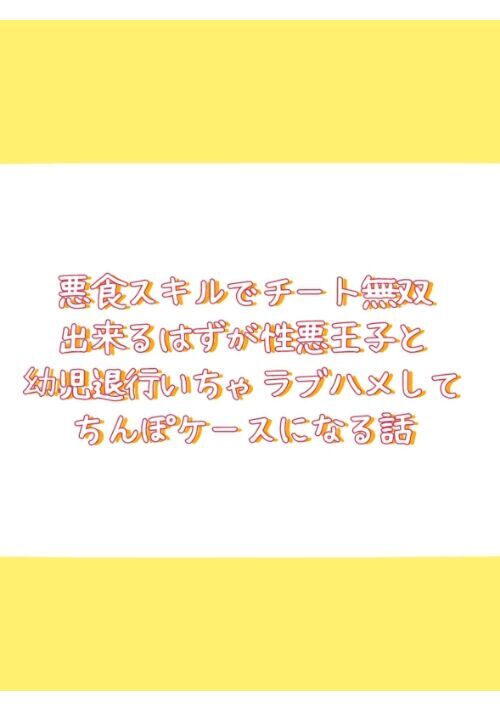42 / 100
松の木の下で 2
しおりを挟む眩しい陽の光を感じて、僕は目を覚ました。
十分に体を休めることが出来たからなのか、爽やかな気分で起き上がることが出来た。
すっかり元気が戻ったように感じると、一刻も早く外に出て陽の光を全身に感じたくなり、布団を片付けてから洗面所へと向かった。
久しぶりに見る自分の顔には、無精髭が生えていた。
少し頬がこけたようにも思えたが、鏡の中に映る自分の瞳は以前よりも力があるように感じた。
「僕は、変われるかもしれないな」
僕は鏡の中の刈谷昌景に向かってそう言うと、少し笑ってくれたように思えた。
それから軒下に向かうと、逞しい背中をした男が座っているのが見えた。
「おはよう、昌景。
体の調子はどうだ?」
僕が声をかける前に、紅天狗はそう言いながら振り返った。
「あっ…おはよう。もう大丈夫だよ、ありがとう。
普通に歩けてるし、お腹も空いてるぐらいだから」
「そうか。良かった。
なら、飯にするか。
いい天気だしな」
と、紅天狗は言った。
久しぶりに見る空は青く澄んでいた。
きらきらとした陽の光が降り注ぐと、紅葉が明るく輝いて喜びの色を発しながら僕を迎えてくれたように思った。
しばらく離れていてからこそ分かった。
この場所が、本当に好きだ。この場所は優しくて、とても居心地がいい。
今日起きてくると分かっていたのか、紅天狗は僕の分も用意してくれていた。久しぶりに食べる食事は本当に美味しくて、残さず食べれたことに自分でも驚いた。
紅天狗はそんな僕を満足そうな顔で見ていたが、不意に口を開いた。
「今宵は満月だ。
美しい月を見ながら、一緒に飲まないか?」
断る理由はなかった。
ここでは都会のようなギラギラした明かりはないから、宝石を散りばめたような星空が見える。
以前、紅天狗と一緒に酒を飲みながら見た夜空は、夢のような美しさだった。はめ殺しの窓から見える夜空は限られているし遠く感じるから、もう一度夜風を感じながら見てみたい。
それに、もしかしたら兄も見ているかもしれない。
また会うことが出来るのならば、僕は兄の隣で酒を飲める男になっていたい。そう流れ星に願い、一日一日を生きていこう。
二つ返事で答えると、紅天狗は嬉しそうに笑った。
「月が昇れば、迎えに来る。
中で、待ってろ。
夜風が冷たいからな、暖かくしろよ」
と、紅天狗は言った。
「ここで、飲むんだよね?」
と、僕は聞いた。
ここではない場所で飲むような口ぶりだった。
軒下は深く垂れ込めるような紅葉のお陰で寒くはない。冷たい風で体を冷やさないように守られていると感じるほどだった。
「いや、ここじゃない。
前に話したの覚えてないか?」
紅天狗はそう言ったが、僕は思い出せなかった。
「なら、より楽しみにしてろ。
今宵は、カラスも来るからな。
あっ…そうだ。短刀も忘れんなよ」
紅天狗は澄み渡る青空を見ながら言った。
紅天狗の後ろ姿が見えなくなってから僕も立ち上がった。
部屋に戻ると鞄を開け、クチャクチャになっていたパーカーを手に取った。それから食料を詰め込んだ鞄を開け、駅の構内で買った酒の肴になりそうな物を選んだ。
紅天狗がそれを食べるかどうかは分からない。一緒に食べてはいるが、紅天狗の好物も苦手な物も分からなかった。
いつもニコニコしながら話を聞いてくれるから僕の話がほとんどで、紅天狗がどんな道を歩んできたのかも知らなかった。
僕は手に取った物を畳の上に置き、ため息をつきながら部屋を見渡した。床の間が目に入ると、僕は静かに桔梗と松の枝葉に近づいて行き、ぼんやりと眺めていた。
はめ殺しの窓から夜空の光が差し込んでくると、白の羽織を着た紅天狗が姿を現した。月が昇ると1人で出歩く事が出来ないので、夜に歩くのは久しぶりだった。
高く聳える木々の隙間から夜空の光が差し込み、僕の足元を照らしてくれた。何処に向かっているのか分からなかったが、落葉を踏む音がカサカサと響いた。
いくら舞い落ちても、次の日には鮮やかな紅葉が咲き誇っている。
枯れ木になることも色褪せることもなく、この山は美しい。
不思議な山だ。
袴の人が言ったように、それは全て紅天狗の力によるものなのだろう。草木も落葉も全て、男の心に従っているのだろう。
男が吹く笛の音によるものなのか、それとも男が大切に想っているからなのか…僕には分からない。
もしかしたら…両方なのかもしれない。
笛の音で心と体が癒されていき、僕を大切に思ってくれている男の言葉の威力の両方を僕は感じたのだから。
ふと顔を上げ、目の前を歩く紅天狗の後ろ姿を眺めた。
すると夜のせいなのか灰色の翼が少し濃くなったような気がした。
「紅天狗…」
「あ?なんだ?
気分でも悪くなったか?」
振り返った紅天狗は心配そうな顔をしていた。
「いや…その…」
その表情を見た僕は声をかけたことを後悔した。
「なんだよ?言えよ」
「翼の色が少し変わったな…と思って。
灰色っていうより…黒くなりつつあるような。
天狗の翼も…冬羽のように生え変わるのかな?」
僕はそう言い終わらないうちに、男は天狗であり鳥ではないのだから何を言ってるのだろうと思った。
すると、男の瞳は少し険しくなった。
「そうか。
昌景も、分かるか。急がねばならないな。
白から灰色に化わり、全てを燃やし尽くす黒になる前に」
と、紅天狗は言った。
「え?どういう事?」
「冬じゃない。
蔓延る醜悪さが、俺の翼の色を化えるんだ。
この続きは着いてからにしよう」
紅天狗は素っ気なく言うと、また前を向いて歩き始めた。
やがて鬱蒼とした老杉に囲まれた数百段もある長い階段が見えてきた。この階段は何度も見ている。いつも額に汗を滲ませながら上っている階段だ。
「異界に行くの?」
と、僕は言った。
いつもとは違う道だったから、今の今まで気付かなかった。
「いや、行かん。
この先で、飲むんだ」
紅天狗は下駄を鳴らしながら軽快に上って行った。
僕は額に汗を滲ませながら階段を上りきった。
汗を拭ってから顔を上げると、聳え立つ黒い大きな影によって美しい夜空は見ることが出来ず、辺りは不気味なほどに暗かった。
「よく…見えないね…」
僕がそう言うと、紅天狗は右手を掲げた。
「ならば、輝かせてみせよう」
紅天狗の言葉を待っていたかのように視界を塞いでいた立派な松の枝が大きく動き、夜空に浮かぶ大きな光が差し込んだ。
幹が輝きを放つかのように白く色づき、それを合図に光り輝く世界が広がっていった。
「あぁ…綺麗だ」
紅天狗は目を細めた。
その美しさに触れようとするかのように右手を伸ばすと、夜空がさらなる煌めきを放った。
麗しい満月が夜空に浮かび、美しい星が輝いている。
これほど綺麗な夜空は見たことがない。
満月は煌々と輝いているのに、宝石のように散りばめられた星の輝きもかげることはない。
眩い満月の光は星の光を遮ってしまうはずなのに、何らかの力が働いているのか星も輝きを失わなかった。月が煌々と輝くほどに、星も美しく輝いた。
不思議でたまらないのに、僕はその美しさに魅せられ見つめることしか出来なかった。神々しさすらも感じたからだろう。
その力は、全てを支配している。
僕達人間など、小さな小さな点に過ぎないのだ。
「ほら、ここにも月があるぞ」
松の木の裏手から紅天狗の声が響いた。
男は木橋の上に立っていた。
透き通った池の水面にも麗しい満月が浮かび、星の輝きが映し出された金色の池の上に男は立っていた。木橋も輝きに溶け込み、僕達も煌めきとなって星空に漂っているように感じた。
しゃがみ込んで星に手を伸ばすと、届かぬ輝きが揺らめきながらでも手の中にあるような幻を見ることができた。
水面は美しい波紋を描いた。
満月が揺れ、星は華麗に水の中を泳ぎ、せせらぎの癒しの音が響き渡った。
しゃがみ込んだまま紅天狗を見上げると、僕は満月の光に照らされた男の力を見た。
僕の目に映る男は、優雅さと烈しさを兼ね備えた特別な存在だった。
銀色の瞳の輝きは、空に浮かぶ満月そのものだ。夜風に吹かれて髪は烈しい炎のように揺れ動き、強靭な肉体からは全てを圧倒するような力を発していた。
陽の光の下で見るよりも満月の光の下の方が、紅天狗の美しさと恐ろしさがより烈しく目に焼きついたのだった。
「座るか、昌景」
紅天狗はそう言うと、僕を色々と準備された松の木の下に案内してくれた。
紅天狗は刀を地面に置き、美しい星を眺めながら大きな幹に寄りかかった。
「元気になってくれて良かった。
俺も、嬉しいよ。
ありがとな。
ほら、昌景」
紅天狗は微笑みを浮かべながら、僕に飲み物を差し出してくれた。それは酒器ではなく湯呑みだった。
吸い込まれそうな深い黒の光沢に星を散りばめたような斑紋が美しい。空を手にしたかのように感じるほどの荘厳さだった。
「なんだよ?やけに驚いた顔してるな」
「日本酒が出てくるものだとばかり思ってたから」
僕がそう言うと、紅天狗は笑った。
「そんな無理はさせんさ。
そんな体で酒なんか飲んだら、また寝込むことになるぞ」
と、紅天狗は言った。
一口飲むと、まろやかな甘みが舌の上に広がっていった。
華やかさを感じる香りで心も満たされると、足に触れる草がさらに柔らかく感じ、ここまで歩いてきた疲れが取れていった。
僕達は異界について語ることはなかった。紅葉にコスモスのこと、滝や鴉のこと、共に見てきた美しい数々について語り合った。
穏やかな気持ちで明るい話をするうちに、日が暮れてから感じ始めた怠さもなくなっていった。
お茶を全部飲み干してから湯呑みを草の上に置くと、指に松の枝葉が触れた。ソレを拾い上げると、部屋に飾ってある桔梗と松の枝葉を思い出した。河童の領域に行ってから数日経つのに、桔梗は美しく咲き続けている。否、美しさは増すばかりであった。
あの日から、僕の全てが変わったのだ。
「この松の木に、紅天狗を見たんだ」
突拍子もなく僕が切り出したからなのか、湯呑みを口に運ぼうとしていた紅天狗の手が止まった。
「そうか。どんな風にだ?」
と、紅天狗は言った。
僕が話し始めると紅天狗は黙ったまま聞いてくれたので、僕は桔梗と松の枝葉のことも付け加えた。
「おかしいよね。一緒の花瓶に挿すなんてさ。
繊細な桔梗は嫌がるかもしれないのに、どうしても一緒にしたくなったんだよ。
そしたら枝葉の色が、白く変わったんだ。
不思議だよね?」
僕はそう言ったが、紅天狗は何も言わなかった。
冷たい夜風が吹いて、何処かで鴉が鳴いた。心を抉るような悲しい鳴き声に聞こえた。
紅天狗をチラリと見ると、男は夜空を見つめていた。男の瞳には美しい星が映っていた。
「どうしたの?」
「桔梗は…何か言ってたか?」
と、紅天狗は言った。
花は喋るはずもないので、紅天狗が何を言っているのか一瞬よく分からなかった。
僕は目を丸くしながら、紅天狗を見た。
すると男は心を落ち着かせるかのように赤い髪をかき上げてから、切なげな表情で僕を見つめてきた。
「教えてくれよ、昌景」
「どうだったかな…?
えっと…あの…あっ!嬉しそうにユラユラと揺れていたよ!
そう…そうだ!それから松の枝葉に寄り添っていったんだ!自分から望んで身を委ねるかのように」
僕が大きな声で言うと、紅天狗は柔らかい表情になった。
そして少し恥ずかしそうに笑うと、また美しい星を見つめた。
「星が綺麗だな」
男はそう言うと、柔らかい草の上に置いていた刀に触れた。
「ありがとな、昌景。
本当に、ありがとな」
紅天狗は刀の柄を握りしめてから、僕を見つめた。
満月の光が男に注がれると、銀色の瞳が煌めきを放った。息を呑むような麗しさだった。
だが、その瞳は徐々に燃え上がるような烈しさを帯びていった。
「お前の言葉は正しい。
この松の木は、俺そのものだ」
「え?どういう事?」
「漂うニオイが濃くなり、門を引っ掻く爪の音がするたびに、山の神様がお選びになった妖怪を惨殺する…と俺は言った。
だが厳密に言うと、今は、そうじゃない。
ある時から、ニオイは届かなくなった。
俺が、ソレを望んだからだ。
この松の木と俺の翼が、ニオイの全てを背負う。醜悪なニオイが蓄積されていくにつれ…色を化える」
紅天狗は静かに笑い、幹の鼓動を感じるかのように瞳を閉じた。
「けれど、それでは愉しめない。
また「タダ」で与えてしまうことになる。
漂ってくるニオイを嗅げなくされた代わりに、一部の妖怪の頭には、松の木の色が変わっていくさまを見ることが出来るようにされた。
それで頻繁に行かなくていいようになり、探す為の時間が出来た。
けれど頭に命じられて「早くしろ」とばかりに爪を立てにくる妖怪がいるから、異界中に響き渡らないようにソイツらを殺しに行っている。
白から灰色に、そして黒くなり果てた時…俺は、俺を、終わらせるんだ。
俺は、昔の俺に、戻るだけだ」
「昔の…紅天狗?」
と、僕は言った。
「知りたいか?」
紅天狗の瞳が妖しく光った。その光は、僕にその覚悟があるのかを問うていた。
「は……い。
いえ…僕は…僕は知りたい」
「ならカラスが来るまで、昔話の続きでもするか」
紅天狗は刀から手を離し、大きく伸びをしてから幹にもたれかかった。
「はい。お願いします」
僕は背筋を伸ばしてから言うと、紅天狗の真似をするかのように幹にもたれかかった。
見上げた満月は、少し赤みを帯びたような気がした。
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
2
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる