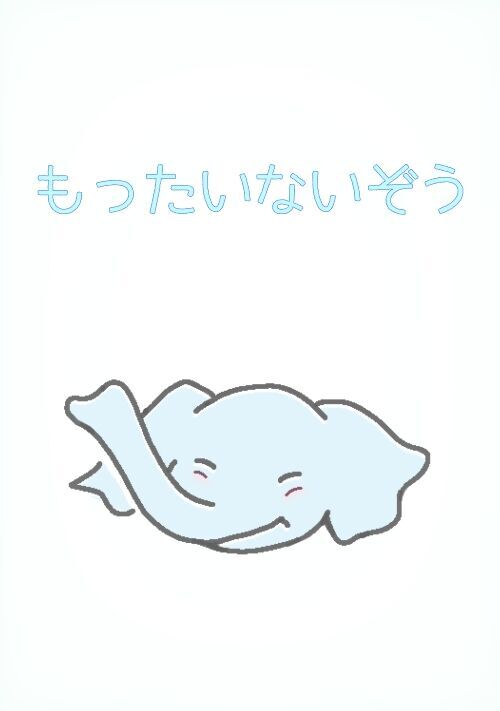1 / 3
草原の狼
しおりを挟む――その人はいつもどこか遠くを見ていた。
北方の草原にある騎馬民族の国、叶狗璃留。その蒼天の下、夏の青々とした草地に白い馬がいた。
「こらこら、そっちじゃない。ソリル!」
その背に跨がるのはまだ幼さの残る少女だ。長い髪は艶やか、色素の薄いその瞳は日を受けて金のように輝いている。ぐっと強引に手綱を引いて、調教の終わっていない荒馬を操ろうとしていた。
「リャンホア、まだお前には無理だよ」
「そんなことないわ、兄様。ソリルは父様から貰った私の馬よ。私が調教してみせる」
リャンホアと呼ばれた少女に声をかけたのは、叶狗璃留を束ねる八氏族のひとつ斗武南氏の王子バヤルだ。食いつかれるように妹姫に言い返されて、バヤルは肩をすくめる。
「では、剣の稽古はナシだ」
「そんな! 今すぐ下ります。それでいいでしょ、兄様」
リャンホアは慌てて馬から下りた。そんな妹の姿に、バヤルは思わず苦笑した。
「調子のいいやつだ」
「うふふ、それより約束忘れないでね。兄様から一本取ったら、その琥珀の指輪をくれるって」
「ああ、叶狗璃留の男は約束を違えぬ」
「やったぁ!」
リャンホアはいそいそと馬を繋ぐと、稽古用の剣を手にする。そしてそのままバヤルに振り下ろした。
「兄様、覚悟!」
「甘い。そんな大振りでは胴体がガラ空きだ」
だが未熟なリャンホアの太刀筋はすぐさま弾かれた。その後何度もリャンホアは剣を振ったが、ただの一度もバヤルに敵うことはなかった。
「はぁ……はぁ……。悔しい……」
息を切らして草の上に大の字に転がるリャンホアの横に、バヤルも座る。
「まだまだ、だな」
「いつかきっと、兄様から一本取ってみせるから。約束よ……」
「ああ、待っているよ」
バヤルはそう言って、負けん気の強い妹の頭を優しく撫でた。
……しかし、その約束は果たされることは無かった。その夜、兄バヤルは何者かに殺害されたからだ。
「嘘よ! バヤル兄様が死ぬわけない!」
「姫様!」
信じられない知らせに、叫びながら取り乱したリャンホアを、侍女のアリマが必死で押さえる。
「嘘よ……」
かすれ、震えた彼女の声が真っ暗な草原の空に溶けていった。
***
それは暗殺かもしれない、と噂された。武勇を尊ぶ騎馬民族の国、叶狗璃留の氏族長の子息たちの中でも、一際に勇壮として知られたバヤル。その彼が背中から短剣でひと突きにされたのだ。
「これは、まさか『旺』の手の……」
「こら、滅多なことを言うんじゃない」
軽率に口にした者に叱責の声が飛ぶ。旺はこの草原から南一帯を支配する帝国の名だ。叶狗璃留は旺との長きに渡る争いの末に、今は属国となっている。
「バヤルの天幕からは宝物である白銀の狼の毛皮が盗まれていた。ただの盗賊かもしれないのだぞ」
「だが刺さっていた短剣の柄の文様は旺のものだ」
人々に不安と動揺が広がり、様々な憶測が飛び交う中で葬儀は行われた。
「……」
リャンホアは青ざめた顔で、悲嘆にくれ慟哭の声を上げる母に寄り添っていた。バヤルの死は彼女にとって身が震えるほど悲しいはずなのに、なぜか涙が出なかった。リャンホアの顔はこわばり、胸にぽっかりと穴の開くような気持ちで、絶えることのない弔問の列を眺めていた。
「お呼びですか。父様」
数日に渡る葬儀を終えた後、リャンホアは父の呼び出しでその天幕を訪れた。
「そこに座りなさい」
重く、低い声で父はリャンホアに命じた。期待の跡取り息子を喪った父の顔はやつれ、目の下に深い隈が刻まれている。父の側にリャンホアが座ると、目の前に一枚の紙が差し出された。
「……これは旺の文字? 読めません、お父様」
「『蓮花』と読む。お前の新しい名だ」
「……え?」
父の唐突な言葉にリャンホアは思わず聞き返した。そんな彼女に向かって父は言葉を続ける。
「八氏族の合議により、お前の旺への輿入れが決まった」
「輿……入れ……」
「そうだ。お前も知っているだろう。バヤルは旺との融和派の若手筆頭だったが、あやつの死によってそれが揺らいでいる。バヤルの死に反発した者が、一部の過激派に転じたとも聞く」
そう、今は亡き兄バヤルは旺の文化を積極的に取り入れ、この叶狗璃留の繁栄に繋げようとしていた。以前から、物珍しい異国の話をリャンホアにもいくつも話していくれていた。
「そんな、それでは……」
バヤルの志が潰えてしまう、とリャンホアが息を飲むと、父は床に手をついて娘に向かって頭を下げた。
「すまぬ! 斗武南氏の族長として、旺との和平を揺るがす為にはいかぬ……。リャンホア、お前に思うところはあるだろうが、この話を飲んでくれ!」
それは見たこともない父の姿だった。いつも厳めしい顔をした無口な父が、自分に頼み事をするなんて。それだけのことが起こっているのだ、と彼女は感じた。
「……顔を上げてください父様」
「リャンホア」
「蓮花、ですよね」
「……」
旺の手の者がバヤルを殺した、という誰かの声が頭をかすめる。だけれど……いや、だからこそ。自分は旺へと向かうべきなのかもしれない。
「父様。この話、お受けします。……私は旺に嫁ぎます」
リャンホア――いや蓮花は静かに、そしてきっぱりと父に答えた。
***
それからバヤルの喪が明けるまで、蓮花は旺語の読み書きを徹底的に学んだ。慌ただしく花嫁仕度が次々と行われていく。そうしているうちに旺からの迎えの日がやってきた。
「姫様、外へ! お迎えがやって参りました」
その日、晴れ着に身を包んだ蓮花はアリマの声に、珊瑚や瑪瑙の玉飾りを揺らしながら顔を上げ、天幕の外に出た。真昼の日差しに一瞬目がくらみ……そして薄目を開けると、そこには赤い輿と馬の部隊、そして荷馬車の一団がゆっくりとこちらに向かってくるのが見える。
「兄様……とうとうこの日がやって参りました」
蓮花は呟き、紐をかけて首から吊した指輪をそっと撫でた。大きな琥珀のその指輪は兄バヤルの形見。これを見て、よくバヤルは蓮花の瞳のようだと言っていた。
「私は行きます」
蓮花はそのままその一団に向かって進み始めた。
「旺の皇子、顕王一同、蓮花翁主をお迎えに参上いたしました」
「ご苦労」
蓮花の父が先触れに頷き、目の前に降ろされた輿に向かって声をかけた。
「旺の皇帝が五の皇子、顕王殿。斗武南氏の族長シドゥルグと申す。この度は我が娘、蓮花の親迎の為、遙々と当地までお越しいただき、誠に……」
「あぁ、良い良い。そういうのは」
蓮花の父が口上を述べ終わらないうちにばさりと輿の被いをまくって、中から背の高い青年が出てきた。
「花嫁を迎えに来た。どこだ」
そう言ってぐるりと辺りを見渡す。どうやらこの青年が蓮花の夫となる旺の皇子らしい。すっと切れ長の目が印象的な、見惚れるほどの美丈夫だ。しかし……。
「あの……私です」
蓮花は戸惑ったが、おずおずと手を挙げた。
「お前か。ふむ……」
旺の皇子はじっと蓮花を見た。
「俺は旺の五皇子劉帆だ」
「わ、私は蓮花……です」
「へぇ、叶狗璃留の女は初めて見たが、なかなか可愛いじゃないか。良かった、熊みたいのじゃあなくて」
「熊……?」
「はははは! 冗談だ」
この無礼で軽薄な男に自分は嫁ぐというのか。蓮花は信じられないようなものを見る目で劉帆と名乗った皇子を見た。
「さぁ、我々は一休みといこう。シドゥルグ殿、案内を頼む」
劉帆はぷいと横を向くと、スタスタと目の前から去って行った。蓮花は身の内に言いようのない苛立ちがこみ上げてくるのを堪えていた。
皇子の一団は一晩、集落に留まり、翌朝に蓮花を輿に乗せて旺の帝都まで向かうという。
「リャンホア……蓮花」
「母様?」
蓮花がもやもやしながら劉帆の背を見つめていると、母が声をかけてきた。
「これを持って行きなさい」
「これは……大事な金毛の狼の毛皮じゃないの」
母が差し出したのはバヤルの天幕から失われた白銀の狼と番の狼の毛皮であった。
「いつでも、この草原の風を感じられるように……。どんな嫁ぎ先でも苦労はあるものです。旦那様によくお仕えしなさい」
「はい……」
蓮花は母から手渡された毛皮を受け取った。すると母は涙を浮かべて蓮花をぎゅっと抱きしめるのだった。
「――姉様!」
「元気でね、みんな。父様と母様の言うことをよく聞いて、立派な大人になりなさい」
翌日、離れがたいとまとわりつくまだ幼い弟妹たちにそう言い聞かせる。
「……よろしくお願いいたします。顕王様」
「劉帆でかまわん。よし、出せ!」
「はっ!」
こうして蓮花は故郷、叶狗璃留の地を後にした。
***
叶狗璃留と旺との和平の架け橋と期待され、蓮花を乗せた輿は草原を進む。故郷から供をするのは侍女のアリマと愛馬のソリルだけだ。
「ふう……」
まさか自分の夫になる男が、あんな人物だとは思わなかった。蓮花は嘆息して、輿の覆いをそっとめくった。すでに蓮花のいた天幕は遠くなっている。
「姫様……」
そんな蓮花の様子を、侍女のアリマは心配そうに見つめている。蓮花より少し年上の彼女はまるで姉のように寄り添ってきた。主の身に降って湧いた今までの出来事は、アリマにとっても我が事のように悩ましいものであった。
「あの……私、昨晩夢を見たのです」
気まずい沈黙の中、アリマは指先をいじりながらぽつりと漏らした。
「夢……? ああ……」
その言葉に蓮花は外から視線を外し、アリマを見た。アリマが夢の話をするのはこれが初めてではない。彼女の祖母は一族の巫者であり、その話を聞いて育った為か、はたまた血筋の所為か、たまにこのような話をするのだ。
「夢で私は鳳凰が降り立つのを見ました。姫様は皇后となって、旺も叶狗璃留も共に栄え世は太平となるのです」
「馬鹿なことを……私が輿入れするのは第五皇子なのよ? ありえないわ」
「だとしても、吉兆です。きっといいことがありますよ」
「ならいいけどね……」
だが相手はあの皇子だ。蓮花は隣を進む劉帆の輿を睨み付けた。
たとえ旺に嫁いだとしても、蓮花はバヤルのことを忘れたりなどしない。もしも本当にバヤルを殺したのが旺の人間であったのなら……蓮花は拳をぎゅっと握りしめた。
――その時、輿がガクンと揺れた。
「何!?」
蓮花が慌てて外を見ると、焦った様子の衛兵がこちらに駆け寄って来た。
「中にお入りください! 盗賊に襲われております!」
「……分かったわ」
蓮花はそう口にしつつ、言葉とは裏腹に立ち上がった。
「姫様、ちょっと!」
「大丈夫!」
口元に手をやると、蓮花は指笛を吹いた。
「ソリル、おいで!」
すると手綱を握っていた人間の手を振り払い、白馬ソリルがこちらに走ってくる。蓮花は輿から身を乗り出すと、ひらりとその背に跨がった。
確かに武装した男たちが、隊列の先頭でやりあっているのが見える。
蓮花はソリルの手綱を引き、前方へと駆けた。
「叶狗璃留の者のいる隊列を襲うとは、身の程知らず。後悔をさせてあげましょう!」
そのまま馬上で弓を構える。キリキリと弦を引き絞り矢が放たれると、それは見事に盗賊の首に突き刺さった。
「……ぎゃっ」
突然の援軍に幾人かが振り返った。そして、それが護衛しているはずの皇子の花嫁と知ると彼らは目を疑った。
「ほら、よそ見は命取りよ!」
蓮花は人馬一体となってさらに弓を放つ。次々と盗賊たちが倒れ、その度に金の耳環が揺れる。兄バヤルを喪ってから、蓮花はずっと騎射も剣術もかかさず鍛錬してきた。
「さぁ! かかってきなさい」
蓮花は勇ましく、ならず者たちを挑発した。絹と簪で着飾った若い女の声に、頭に血が上った愚か者が突進する。蓮花からしてみればいい的である。彼らは鋭い矢の一閃に射貫かれ、討たれていった。
「すごい……」
年若い衛兵はそれを見て息を飲む。まるで荒ぶる狼のようである、と。疾く、鋭く相手の喉笛を噛み切るような、容赦のない動き。
「――危ない!」
ギィン、と彼の目の前で刃が弾かれ、火花が散った。
「戦いの最中よ!」
今度は弓の射程から外れて近接した蓮花は、剣を引き抜いて盗賊に斬りかかった。
衛兵は見惚れていた自分に気付き、慌てて己の剣を握り直す。
「……大丈夫?」
「は、はい! 申し訳ございません。あ……血が……」
蓮花の顔と胸元に血がついている。蓮花は無表情のまま、ぐいっと顔の血を拭って答えた。
「……私の血じゃないわ」
「はぁ……」
蓮花はそのまま、剣を振って血しぶきをふるい落とすと、辺りを見わたした。
「あらかた倒したようね。先に進みましょう」
一切取り乱すことすらなく、白馬を引いて輿に戻っていく蓮花の姿を見て、衛兵はぶるり、と身を震わせた。
「あぁ、洗って落ちますでしょうか。こんなに汚して!」
「ごめんなさい」
輿の中で蓮花はアリマの小言を聞いていた。ちらりと隣の皇子の輿を見たが、被いの中は窺い知れない。この騒ぎに彼は輿の中で震えていただけなのだろうか。
蓮花はまたため息をつく。そんな重苦しい思いを抱えながら、隊列は草原を進んでいった。
***
草原を抜けると、道には木々が増えていった。聞いたことの無い鳥の声を聞きながら、蓮花は輿の中で膝を抱えていた。
叶狗璃留の姫として、後ろを振り返るような真似はしてはいけない。そう思うのに、土地の匂いが変わっていくうちに不安が増していく。だけど、そんなことは口にできない。それが侍女のアリマだとしても。きっと彼女だって同じ気持ちだろうから。
そんな風に悶々と考えに捕らわれていると、ぴたりと輿が止まった。
「……どうしたの?」
「街についたそうです。今日はここに宿をとってあるとか」
「ああ、そう……」
蓮花は思い詰めていたせいか、街に入ったのも気づいていなかったようだ。
泊まるのはこの街一番の大きな宿。蓮花たちが通された部屋は新しく、手入れの行き届いた部屋だった。
「うーん」
蓮花は乗り物の中で縮こまった体を、両手をあげて伸ばす。輿に揺られてゆくこの度は、彼女にとって窮屈なものだった。迎えがこなければ、狩りや街見物をしながらゆっくり旺に向かうのに、と思うが花嫁を迎えに行くのが旺の風習らしい。
「しきたりが多くてややこしいわ」
だが、慣れるしかない。これから蓮花が生きる世界はそういうものなのだから。そう思いながら蓮花は窓の下に目を落とす。宿の外にたむろっているのは、付き添いの官吏たちだ。まだ日は高いがまもなく暮れたら、酒場にでも繰り出そうとでもいうのだろうか。
「いいな……」
蓮花はちらりと荷物の整理をしているアリマを見た。
「ねぇ、アリマ。ちょっとお願いがあるんだけど」
「はい……?」
「私、お風呂に入りたくなっちゃったなぁ」
「もうですか? あぁ、でも疲れましたものね」
アリマは一瞬ぽかんとしたものの、納得したみたいだ。蓮花はひっそりと心の中でほくそ笑む。
「そうなの。だから下でお湯を貰ってきてくれないかしら」
「かしこまりました」
アリマが出て行く。お湯を沸かして風呂の仕度をするまでにしばらくかかるだろう。これで蓮花は一人だ。扉が閉まるのを見て、そーっと荷物の中からアリマの服を取りだした。そして、そそくさとそれに着替えると、扉を開ける。左右を確認して、誰も居ないと確かめると、蓮花は宿の裏口から街に出て行った。
「ふふん、私だって何か買い食いでもしちゃお」
大通りは人でごった返している。仕事を終えた人、買い物の人、旅人と様々だ。
「そうねぇ」
はじめての街は何がどこにあるか分からない。蓮花は勘を頼りに通りを歩いた。するとやがて賑やかな市場に辿り着く。
「うちの麺は絶品だよ」
「銀細工が色々あるよ。見事な細工だ、見ていって!」
様々な呼び声に、蓮花はわくわくして店先を冷やかしていく。
「そこの奥さん! そろそろ店じまいだ、安くしておくよ」
中にはそろそろ市場が閉まるのを見越して、そんな風に手を叩いている者もいた。きっと帰りの荷物が重いのが嫌なのだろう。買い物上手な奥方は、その声に早足で店に向かっていく。その様子をくすくす笑いながら見ていた蓮花にも、声が掛かる。
「お嬢さん、飴はいかが。美味しいよ。お代は試して気に入ったらでいいよ」
「いただくわ」
蓮花は渡された飴をひとつ口にする。優しい甘さの中にほんのりと独特の香りがある。
「おいしい。おじさん、一袋ちょうだい」
旅路のお供に丁度良いと思い、蓮花はひとつそれを買い求めた。
「こんなのもあるよ」
飴屋のおやじが蓮花に見せたのは飴細工だった。飴でかわいらしい人形が形作られている。
「まぁ、すごい。どうやってやるの」
「飴が熱いうちに吹いたり、ひねったり。まぁ素人では無理だね」
「へぇ、じゃあこれもひとつ」
蓮花はどこかとぼけた顔をしているひよこの飴を買った。この顔つきでアリマのことを思い出したのだ。今頃、宿を抜け出した蓮花に気づいてへそを曲げているだろうから、土産に丁度良い。
「そろそろ帰ろうか」
ころころと口の中で飴を転がしながら、蓮花が大通りに戻ろうとすると、ぐっと急に服をひっぱられた。
「……おかあちゃん」
「えっ!?」
見れば小さな男の子が、蓮花の服を掴んで立っていた。
「おかあちゃんがいない……」
「どうしたの、迷子?」
蓮花が声をかけると、男の子は涙を浮かべ、しくしく泣き出した。その声はどんどん大きくなる。
「えっ、あっ。どうしようかしら……」
とにかくこの子の母を探さなくては。しかしこんなに泣いたままでは話も聞けない。
「そうだ。ぼうや、いいものがあるのよ」
蓮花は手にしていたひよこの飴を男の子に差し出した。男の子はじっとそれを見つめると、にこっと笑って受け取った。蓮花はほっとして、ようやく辺りを見渡した。
「さぁ。お母さんを探しましょ、ぼうやお名前は?」
「小雲」
「そう、良い子ね。小雲! 小雲くんのお母さんは居ませんか!」
蓮花は大声で、小雲の手を引いて通りを歩いたが足を止める人はいない。
「もういいよ。おかあちゃんはぼくをおいていっちゃったんだ」
小雲が歩き疲れて泣きべそをかきながらしゃがみこんだ。
「こら! そんなはずないでしょう」
「でも……」
小雲の目にまた大粒の涙が浮かんだ。その時だった。
「小雲!」
その声に蓮花が振り返ると、青ざめた顔の女性が駆け寄ってきた。
「ぼうやのお母さんですか?」
「ええ! ああ……人さらいにでもあったのかと……」
女性は小雲をぎゅっと抱きしめた。そして何度も何度も蓮花に頭を下げて去っていった。
「良かった……」
アリマへのお土産は無くなってしまったけれど。と、蓮花はほっと胸をなで下ろした。が、次の瞬間、はっとした。
「ここ……どこ……?」
闇雲に通りを捜索したせいで、元来た道が分からなくなっていた。
「えーっと、こっちだったかしら」
見たような道を探しながら、蓮花は宿に帰ろうとした。だが、行けども行けどもあの大通りに辿り着かない。そのうちにだんだん日が暮れてきた。
「どうしよう……」
ぽつりぽつりと通りの灯籠が点り出す。
いつの間にか蓮花はやけに人通りの多い通りに入り込んでいた。
「あらぁ、ご無沙汰ね」
「お兄さん、寄ってらして」
白粉をした女達が通りで、男達に声をかけている。
「おや、君はどこの妓楼の妓だい?」
すれ違った男にそんな風に声をかけられて、蓮花はここが色街なのを理解した。こんなところを嫁入り前の身でふらふらする訳にはいかない。さすがの蓮花もそう思って、来た道を引き返そうとした時だった。
「おいおい、やめておくれ」
聞き覚えのある声にピタリと足が止まる。今の声は……劉帆の声だ。蓮花は声のした窓を下からそっとのぞき込む。すると、昼間に宿の周りでたむろっていた官吏たちが服の襟をくつろげて、酒を飲んでいるのが見えた。そこには妓女たちが侍って甲高い笑い声をあげている。
「つれない方ですこと」
「ははは、もっと美人をつれてこい!」
「ひどぉい」
そして、その真ん中で赤ら顔で冗談を飛ばしているのは劉帆だった。
「な、なにあれ……」
蓮花は頭の芯がカッとするのを感じた。あの男は花嫁を迎えに来た道中で女遊びをしているというのか。心底怒りを覚えた蓮花は足早にその場を去った。
すると、道一本隔てたところに元来た大通りがあり、蓮花はようやく宿に戻ることができた。
「なぜ勝手に一人で外をうろうろするのですか! 姫様に何かあったら族長になんと申せばいいのですか!」
「ごめんなさい……」
宿の部屋に入ってアリマのお説教を聞きながら、蓮花のはらわたはまだ煮えくり返っていた。おかげで、その翌日の旅路の輿の中は重たい空気が流れることになった。
***
「姫様、姫様!」
長い道のりを、ゆらゆらとした振動に揺られて、うとうととしていた蓮花。彼女はアリマの大声に目を覚ました。
「見てください、あれ! ほら!」
興奮気味のアリマに急かされて外を見ると、そこには巨大な城壁があった。高く堅牢な石造りの立派なものだ。
もちろん叶狗璃留にだって街はある。蓮花のいた集落の近郊にも、遊牧や交易で得たものを農作物や様々な道具に交換する場があって、何度か行ったこともある。それらには異民族の攻撃や盗人などから身を守る為の柵や壁があった。
けれど……これはそんな、蓮花やアリマの知っている街の壁とはまったく規模の違ったものだった。
「これが旺の帝都……」
蓮花は被いを捲りあげて上を見上げた。城壁のてっぺんには見張り台。赤に黄で縁どられた旺の旗が上っている。この壁はどこまで伸びているのだろう。
入り口の門は分厚い木に鉄の枠を嵌めて出来ていて、何人もの門兵が出入りする者を厳重に見張っていた。
「皆の者、道を空けよ! 皇子殿下のご一行がお通りだ」
兵が人々を蹴散らすようにして通り道を空ける。そこをゆっくりと前に進む五皇子・劉帆の一団。人々は沿道に居並び、頭を下げつつその輿に注目した。
「おい、あれだろ……ほら、北の夷狄の」
「そう、蛮族の姫を妃に」
小さな声でそう囁かれる中、列は進む。例の花嫁がどのようなご面相なのか、被いの掛かった輿から見られなかったが、その後に続く荷馬車を見て人々はぎょっとした。
「え……あれって羊か?」
「山羊もいるぞ」
「後宮に家畜を連れていくのか……?」
それは蓮花が叶狗璃留から連れてきたものだった。彼女からすればこれらは当然のこと。むしろ羊や山羊がいなくてどうやって暮らすというのか、と言って荷馬車に乗せてきたのだ。
「んめぇーっ、めぇーー」
やんごとなき皇族の隊列にのどかな鳴き声を響かせながら、列は去って行く。民たちは唖然としながらそれを見送った。
「第五皇子、顕王殿下。斗武南蓮花翁主のおなりでございます!」
広く豪奢な宮殿の広間に進み出た、劉帆と蓮花は玉座の前に跪いた。
「皇帝陛下、拝謁いたします。万歳、万歳万々歳。皇后陛下、千歳、千歳千々歳」
劉帆の声に、蓮花は慌てて挨拶を続け、更に深く頭を下げた。
「面を上げよ」
柔らかく、落ち着いた声が聞こえてきた。顔を上げると、そこには目元が少し劉帆に似ている五十過ぎくらいの男性と、丸顔の優しげな顔立ちの女性――皇帝と皇后がそこにいた。
「ありがとうございます陛下。……第五皇子顕王、ここに叶狗璃留の姫を迎え、帯同いたしました。いやぁ、遠かったです。大層疲れました。途中で恐ろしい盗賊も出まして」
劉帆はへらへらと軽薄な笑みを浮かべながら、皇帝に報告をする。蓮花は輿から出てこなかったくせに、と思った。
「うむ、ご苦労。蓮花翁主、遙かなところからよくぞ参った。これよりこの旺の後宮がそなたの家だ。今日のところはゆるりと旅の疲れを癒やすがよい」
「……っは! かしこまりました」
蓮花はドギマギしながら皇帝の声に応えた。
なんとか拝謁を終えて退出した蓮花の姿を見届けると、誰も彼もが噂した。
「――聞いたか? あの五皇子の花嫁」
「旅路で盗賊をやり込めたらしい」
「家畜をつれて後宮に入ったって」
「所詮は叶狗璃留の野蛮人よ」
ひそひそと、後宮のどこもかしこもが蓮花の話で持ちきりとなった……。
***
――数日後、蓮花と劉帆の婚儀が執り行われた。真っ赤な婚礼衣裳はずしりと重く、さらに重たい冠が蓮花の頭上に載せられる。その姿で劉帆と並び立ち、祖霊を祀る廟をお参りし、広間に移動し皇帝、皇后への挨拶を済ませた。
「これで二人は晴れて夫婦となった。千代に仲睦まじく、手を取り合っていくように」
「まぁ、可憐なお妃さまだこと。きっと良いご縁となりましょう」
二人それぞれに、ありがたい言葉を頂き、豪勢な宴が開かれた。そのどれもが物珍しい珍味ばかりであったが、蓮花の胸中は複雑なまま、曖昧に微笑んでいた。
とうとうこのぼんくら皇子と夫婦となってしまった。果たして自分はこれからどうしていったらいいのだろうかと考え巡らせながら。
慌ただしい一日が終わり、蓮花はアリマに手伝ってもらいながら、肩のこる衣裳を脱ぎ、身を清めて寝間着に着替えた。
「……」
ところが劉帆の姿が見当たらない。一体どうしたのだろうか。
しばらく待ってみたものの、一向に現れない。着替えの前には居たような気がしたのだけれど、と蓮花が不思議に思っていると、アリマが困り顔でやってきた。
「姫さ……あっ、嫡福晋でしたね」
この婚礼で蓮花の呼び名は斗武南蓮花翁主から斗武南嫡福晋になったはずである。が、心底面倒くさいと蓮花は思った。
「いいわよ、蓮花で」
「……蓮花様、あっあのですね」
「なに?」
「その……殿下は今夜はいらっしゃらないそうで」
「は!?」
蓮花は思わず声がひっくり返ってしまった。
「だって今夜は……」
――初夜だ。夫婦となって初めての夜。
「遅くなるので、先に休んで欲しいと側近の方から」
「……そう。分かったからアリマも休みなさいね」
そう彼女には優しい言葉を投げかけながら、蓮花の内心は煮えくり返っていた。
アリマがぱたりと部屋の扉を閉じた後、蓮花は寝台に突っ伏した。
「……なにそれっ!」
悔しい。別にこの日を心待ちにしていた訳でもないが、それなりに覚悟を決めて待っていたのに。蓮花は奥歯がぎりぎり言うほど噛みしめて声を漏らした。
「寝るかぁ」
そんな自分が恥ずかしくて、ひとしきり足をバタバタさせた後、蓮花は諦めたように呟いて布団に潜り込んだ。
今日は、祝いの酒で忙しなかったのかもしれない。そう思い直した蓮花だったが、また翌日も劉帆は寝所に現れなかった。
「――もう!」
蓮花は寝間着のままで皇宮の庭に飛び出した。その一角には蓮花が用意させた厩舎がある。
「ソリル」
そっと声をかけると、愛馬はつぶらな瞳で蓮花を見た。
「ちょっと付き合ってちょうだい」
ソリルを厩舎から引き出し、鞍をかけて乗る。そのまま庭をぐるぐると歩きながら、蓮花はぶつぶつと呟いていた。
「あの人なんなのかしら……え……? 私たち結婚したのよね……?」
「ぶるるるるっ」
「そうよね……あんまりよね……」
そんな風に気を紛らわせて、この日はようやく眠りについた蓮花だった。
しかし、ソリルに語りかけながら徘徊する蓮花の姿を見た門の見張り番は、のちに夜中に幽鬼を見たと仲間に話した。
婚儀は三日かけて行われる。今日が最後。最後ならば……蓮花はそう考えた。だが……。
「今日も来ない……!?」
「は、はい……」
アリマが身を小さくしながらそれを告げると、蓮花は拳を握り、肩を震わせた。
「そう……そうなの……分かったわ」
「蓮花様……あの……」
「いいのよ、アリマはなんにも悪くない。気にすることはないのよ」
もう、どうでも良くなった。アリマを帰し、蓮花は一人になると項垂れた。この扱いは何だというのか。お飾りの妻だとしてもあんまりな仕打ちではないか。
「もう、いい」
蓮花が今後ずっとこんな日が続くかと思うと胸が潰れそうになった。まるで籠の鳥。いや、さえずることもないのならば鳥よりひどい。
ひとりぼっちの寝台の上で膝を抱える。ふと目をやった視線の先には、先日持ち込んだ花嫁道具の箪笥があった。
「そうだ……」
蓮花は吸い込まれるようにその箪笥の前に向かう。精巧な彫り物をした艶やかな箪笥。めでたい桃と橙の枝と花、そして実があしらってある。
蓮花はその橙と桃の実をぐっと指で同時に押し込んだ。
――ガコンッ。
何かが外れる音がした。すると枝のあったところが小さな扉のように開く。その先にあったのは、弓だ。
「……後宮に入る時に武器は全部取り上げられたけど、これだけは手放せない」
もう何年も蓮花とともにあった短弓。馬上での扱いに長けたそれは騎馬民族ならばおもちゃの代わりにして育つ。
「夫がどうであれ、私にはやることがあるもの」
矢をつがえて引き絞る。力強い弦の感触。蓮花は自分の頭が冴え渡っていくのを感じた。
「兄様を殺した仇を探す……」
犯人は白銀の狼の毛皮を持って行った。あれだけの見事な品だ。きっと誰かに捧げるなり売るなりするつもりだったのだろう。それを見つけられたら、犯人に辿り着く。
「旺の人間……許さない」
バヤルの命を奪った旺のものと思われる短剣。蓮花の手に力がこもった。
「殺してやる」
低くそう呟いた――その時だった。
「旺が憎いか?」
突然背後からした声に、蓮花は驚き振り向いた。
「……劉帆」
しまった、聞かれた。蓮花は唇を噛んだ。
「なんのことでしょう」
「なんのこと、とそんな物騒な格好で言われても」
劉帆は例のごとくニヤニヤとして、笑いながら答えた。そしてなお続けた。
「なぁ……お前は旺が憎いのか?」
こんな状況で、酔っているのだろうか、と蓮花は思った。だとしてもこれはまずい。
蓮花は劉帆をじっと見た。この男が兄を殺した可能性……も否定できない。そしてそうでなくても、こうなったら黙らせるほかない。蓮花は矢を劉帆に向け、睨み付けた。
「ええ。私の兄様を殺した旺が憎い」
「……兄? シドゥルグ殿の息子は殺されていたのか?」
「聞いてないの? 兄様の背には旺の短剣が刺さっていて、天幕からは宝物の狼の毛皮が盗まれていたのよ」
「そうか……」
劉帆は怯えるどころか、そう言うと黙り込んだ。それが、どこか悲しそうに見えて、蓮花は動揺した。
「なぁ、蓮花。俺と手を組もう」
「――何!?」
唐突な申し出に、蓮花は思わず大声を出してしまった。
手を組む? 私と劉帆が? 一体何のために? 疑問が頭を駆け巡り、蓮花の背中に嫌な汗が浮かぶ。
「……俺も旺が、この朝廷が憎い。だから手を組もう」
「なぜ? あなた旺の人でしょ」
「だからさ。きっとこの帝国の歪みが、蓮花……お前の兄を殺したのだと思う。俺は国を変えたいのだ」
劉帆はしっかりとした口調で、まっすぐに蓮花を見つめて、そう言い放った。その姿にあの暗愚な振る舞いの影はない。
「……ちゃんと話してくれる?」
蓮花が構えていた弓を降ろすと、劉帆は側の椅子に座り、話し始めた。
「ああ。聞いてくれ」
――それは三年前。長いこと病で伏せっていた皇太子が急死したことから、その皇太子位が空位となった。それから宮中での跡目争いが静かに激化しているのだという。
「俺は第五皇子だし、今は亡き母の身分も低いから後ろ盾も弱い。だから争いに興味は無かったんだがな……」
劉帆はそう言って頬を掻く。
「ならば、何故?」
蓮花が問いかけると、劉帆はぽつりぽつりと話しはじめた。
「俺は、太子が没する前に呼ばれたんだ……」
皇太子だった趙貞彰は俊秀で、人格も慈愛に満ち将来も期待されていた。しかし元来病弱で、次第に起き上がれることが少なくなった。
いよいよ、と周りが覚悟を決めた頃。劉帆は貞彰に呼ばれたのだった。
『劉帆。私はね、悔しい。せっかく恵まれた生まれで、この国の栄えに携われる立場にあるというのに……もうこの世を離れなくてはならない』
『そんな……殿下』
『私はね、知っているよ。皇兄たちに遠慮してお前はわざと出来の悪い風に振る舞っているが、本当は聡い。二皇子や四皇子は駄目だ……彼らには大義がない。臣民の為に事をなすということを分かっていない。そんな者が玉座につけばこの国はどうなるか……。頼む、劉帆。私の志を継ぐのはそなただ』
痩せて骨張った手からは意外なほどの力で、彼は劉帆の手を握って訴えた。
『……殿下のお心、しかと受け止めました』
劉帆はただただ絞り出すようにして、そう答えた。
跡目争いに興味が無かったのは確かだ。勝ち目の少ない自分が戦っても、苦労が増えるばかり。それよりも後々、皇族として与えられた領土でそこそこの統治をして、悠々自適に暮らした方がいい。そんな風に考えていた。だが、死を前にしての皇太子の願いを前に、劉帆はそれを無碍にすることは出来なかった。
なぜなら皇后、そしてその息子の皇太子には大恩がある。
彼女は劉帆の母、夏妃とは姉妹のように仲良く、夏妃が冤罪をかけられた時もそれを助けてくれた恩人であった。それが無ければ母子共々命が無かったかもしれなかったのだ……。太子の母である董姚皇后は下の皇子を赤ん坊の頃に亡くしている。それもあって皇太子が病に倒れた悲しみから、塞ぎ込むようになった。
こうして劉帆は決意した。いつか自分が皇太子となり、この帝国の皇帝になると。
「……という訳だ」
「じゃあ、今までのは馬鹿のふりをしていたってこと?」
「そういうことになるな」
蓮花はじーっと琥珀色の目で劉帆を見つめた。劉帆は落ち着き払った様子で、嘘を言っているようには見えない。だが、蓮花にはなぜそんな話を自分にするのか分からない。
「どうして私にそんなことを言うの?」
「……盗賊に襲われた時の動きを見ていた。まるで草原の狼のようだった。迷い無く敵を葬り、躊躇いなく人を守る。なかなか出来るものではない」
「それで……」
「ああ。皇太子の喪の明けた折のこの婚儀には、乗り気では無かったが……あの時、もしかしたらこれは好機なのかもしれぬと思ったのだ」
「……」
蓮花はどう答えていいか分からなかった。自分の役目は旺と叶狗璃留の和平であって、権力が欲しい訳ではない。そんな迷いが劉帆にも伝わったのだろう。彼は更にたたみかけた。
「お前の兄の仇はこの後宮におるやもしれんぞ」
「……後宮に?」
「ああ。宝物の毛皮を盗られたと言ったな。それだけのものならばここに持ち込まれる可能性は高い。それを辿れば……」
「ああ……」
「それに俺が皇太子となって政に携わるようになれば、叶狗璃留との関係も盤石なものになるだろう」
そうか、自分はとんだ見込み違いをしていたようだ。蓮花は心の中で呟いた。
おもしろい。ただの籠の鳥になるよりずっといい。それこそ、バヤルの思いを蓮花が引き継ぐことになるのではないか。そんな風に考えて、蓮花はまっすぐに劉帆に向き直った。
「旺の第五皇子、顕王……劉帆。分かったわ。手を組みましょう」
――こうして蓮花は劉帆と共に、この宮廷の皇子たちを制し、次期皇太子の位をめぐる争いに身を投じることとなった。
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
33
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる