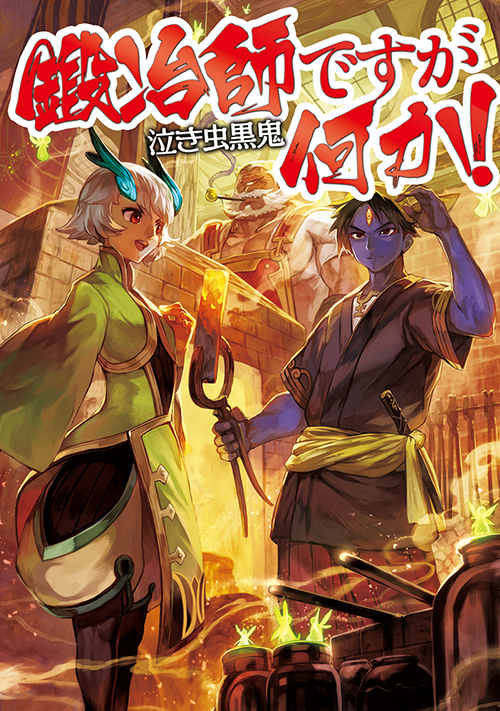36 / 206
第2部開戦
5(モンゴルの進軍2 どこでアルタイを越えたか?前編)
しおりを挟む
(今回はグーグルマップをお供にしていただければと想います。
一応下手な地図を添付しましたので、それでも分かります。(あくまで概略を示したもので、相互の距離・縮尺などはいい加減なものに過ぎません。)
今回は、地図とにらめっこしているのが好きという、作者の好みが色濃く反映した話です。
しかし異国の歴史の面白みというのは、こういうところも、あわせ楽しんでこそとも想いますので。
以上前書きでした。)
ところで、それではどこら辺でアルタイを越えたかを知りたいというのが人情というものです。
ここで手がかりとなるのが元史の「鎭海伝」が伝えるところの「(チンギスは鎭海に)命じるに、阿魯歓において屯田し、鎭海城を立て、之を戍守せよ。」です。(注1)
チンギスに呼ばれて西方に赴いた長春が上述の地近くを過ぎたこともあって、チンギスの軍もやはりここを通ったと推定されています。(注2)
それでは、この鎭海城ってどこだろうとなりますが、これを日本とモンゴルの共同調査隊が発見しています。(注3)
それによると鎭海城はモンゴルのゴビ・アルタイ県のシャルガ近くのハルザン・シレグ遺跡であるとされています。
ゴビ・アルタイ県は、現モンゴル国の南西隅にあります。
つまりハンガイ山脈に沿って西へと進んで来たモンゴル軍は、南西方向へと道を転じたのです。
(自作地図では、南麓側を進軍しておる如くに見えますが、実際は北麓・南麓に別れて進んだと想います。
また分かりやすくするために、進軍路は夏営しないという条件で示しています。)
グーグルマップでシャルガを探すと、Shargaがそれに当たると分かります。「sharga モンゴル」で検索できます。
この後チンギスが通ったと分かるのは天山北麓のビシュバリクであり、これは中国の新疆ウイグル自治区のジムサルの北約10キロにあるとされます。
グーグルマップで「吉木薩爾鎮」で検索すれば出ます。
それで、このジムサルと先のシャルガを結べば、おおよそのルートを知り得ます。
グーグルマップは出発地で右クリックをすると「距離の測定」という項目が出ます。それを選択後、到着地を左クリックすると、二点間が結ばれます。ついでに距離も表示されます。
ただここで一つの問題が明らかとなります。このルートだと、イルティシュ川の源流部どころか、更に南東のウルングゥ川の源流部あたりに出そうです。
実際のところは、手許にある世界地図帳と見比べますと、この源流部より更に外れて、その南東側に出るのではとさえ想われます。
ただこのことは、そこに水や草がないことにはなりません。
このアルタイの西側斜面からは多くの川が流れ出ており(それが合流してウルングゥ川やイルティシュ川となる)、やはり同一方向の斜面ゆえに、ここに同程度の雨量は期待できます。
(大陸だと、逆斜面(例えば南斜面と北斜面)では雨量が全く異なるということは、しばしばあります。)
ここの山肌を流れる細流がウルングゥ川に合流するのか、砂中に尻無し川として消えるのか、はっきりしません。
他方で、ビシュバリクに向かうのを第一に考えるならば、このルートの方が明らかに距離が近く、納得できるところではあります。
ウルングゥ川はアルタイ山脈を発し、西北西に流れ、ウルングゥ湖に注ぎ入る河です。
(グーグルマップ上では、ウルングゥ川の名は表示されず、ウルングゥ湖は乌伦古湖もしくは烏倫古湖で表示。)
実際秘史の五巻158節ではチンギスとオン・カンはナイマンのブイルク・カンを追う時、アルタイを越えて、このウルングゥ川を下り追い、キシル・バシ湖で追いついたとあります。キシル・バシ湖はトルコ語『キジル・バシュ(赤頭)』のモンゴルなまりとみなされています。今のウルングゥ湖の古名です。(注4)
これより、このアルタイ越えのルートが以前より使われており、またウルングゥ川に至るものであることが確認できます。
(厳密に言えば、ビシュバリクに向かうルートからはそれて、ある程度の移動が必要なのかもしれませんが。)
ブイルク・カンがウルングゥ川を下ったのは、軍勢を率いておったからでしょう。
つまり、多くの軍馬の水を確保しつつ、逃走を図ったのです。
他方、例えば、少数の長春一行は、アルタイを越えて、ある川(訳者はこれをUrunga川とみなしています)の岸に至り、そこは水と草を豊かであるとするも、数日滞在するだけで、川を下るのではなく、川を渡ってビシュバリクの方に進んでいます。(注2)
それゆえ、考えられるのは、
1.そもそも史料の伝えるイルティシュ川で夏営したというのが間違いで、ウルングゥ川で夏営した。
2.ウルングゥ川からイルティッシュ河上流部まで大きく広がり夏営した。
多くの軍馬・家畜をたずさえることを考えれば、2は充分にありえることです。
西征に足の遅い羊や山羊を連れて行ったか否かというのは、史料上確認できることではありません。
ただ、膨大な軍兵であること、及び長距離に及ぶ(当然、その分、長期間に及ぶ)ことから、現地調達でまかなうのは不可能と想われ、引き連れたは間違いないと想われます。
イルティッシュ川の目印はザイサン湖(ウルングゥ(乌伦古)湖の西北西約270キロにある)です。アルタイ山脈に発し、やはり西北西に流れザイサン湖に入り、これより流れ出ます。
(グーグルマップではイルチェイシュ・リカと表示されますが、川が長大すぎて、この語で検索してもうまく表示されません。)
基本、夏に動かないのは次の冬を乗り越えるためです。
「馬肥ゆる秋」という如く、それまでに充分に太らせないと強烈な寒波による厳寒・強風・豪雪(枯れ草を食べられなくなる)で大量死してしまいます。
なぜアザラシがそろいもそろって丸々と太っておるのかを想えば、厳寒の地の動物というのが基本太っておる必要があるは、明らかでしょう。
やせておったら死ぬのです。
また夏というのは、暑さに加え、家畜の乳量が最も多い時期に当たります。
そのゆえに家畜は他の季節に比べ水を必要とします。
この家畜の乳こそが、この時期の将兵の食糧のほとんどとなるのであるから、ないがしろにできようはずもない。
また家畜の肉というのは、これを殺さなければ得らません。
それゆえ、可能な限り乳製品で食糧をまかなうのが基本です。
アルタイを初夏に渡った部隊は、イルティッシュ川の方まで広がり、長期夏営し、
楚材の如く盛夏に渡った部隊はウルングゥ川で小休止したとみなせば良いでしょう。
そして、秋になるのを待って進軍を再開したということだけは間違いないところです。
(以下後編につづきます。)
注1:『元史』(明・宋濂等)中華書局 北京 1976年
注2:岩村忍訳『長春眞人西遊記』筑摩書房 1948年
注3 村岡 倫「コラム2 長春真人の旅とチンカイ城」(白石典之編『チンギス・カンとその時代』勉誠出版 2015年 七七~八五貢)
注4:参照した秘史の訳書については、参考文献に記しております。
一応下手な地図を添付しましたので、それでも分かります。(あくまで概略を示したもので、相互の距離・縮尺などはいい加減なものに過ぎません。)
今回は、地図とにらめっこしているのが好きという、作者の好みが色濃く反映した話です。
しかし異国の歴史の面白みというのは、こういうところも、あわせ楽しんでこそとも想いますので。
以上前書きでした。)
ところで、それではどこら辺でアルタイを越えたかを知りたいというのが人情というものです。
ここで手がかりとなるのが元史の「鎭海伝」が伝えるところの「(チンギスは鎭海に)命じるに、阿魯歓において屯田し、鎭海城を立て、之を戍守せよ。」です。(注1)
チンギスに呼ばれて西方に赴いた長春が上述の地近くを過ぎたこともあって、チンギスの軍もやはりここを通ったと推定されています。(注2)
それでは、この鎭海城ってどこだろうとなりますが、これを日本とモンゴルの共同調査隊が発見しています。(注3)
それによると鎭海城はモンゴルのゴビ・アルタイ県のシャルガ近くのハルザン・シレグ遺跡であるとされています。
ゴビ・アルタイ県は、現モンゴル国の南西隅にあります。
つまりハンガイ山脈に沿って西へと進んで来たモンゴル軍は、南西方向へと道を転じたのです。
(自作地図では、南麓側を進軍しておる如くに見えますが、実際は北麓・南麓に別れて進んだと想います。
また分かりやすくするために、進軍路は夏営しないという条件で示しています。)
グーグルマップでシャルガを探すと、Shargaがそれに当たると分かります。「sharga モンゴル」で検索できます。
この後チンギスが通ったと分かるのは天山北麓のビシュバリクであり、これは中国の新疆ウイグル自治区のジムサルの北約10キロにあるとされます。
グーグルマップで「吉木薩爾鎮」で検索すれば出ます。
それで、このジムサルと先のシャルガを結べば、おおよそのルートを知り得ます。
グーグルマップは出発地で右クリックをすると「距離の測定」という項目が出ます。それを選択後、到着地を左クリックすると、二点間が結ばれます。ついでに距離も表示されます。
ただここで一つの問題が明らかとなります。このルートだと、イルティシュ川の源流部どころか、更に南東のウルングゥ川の源流部あたりに出そうです。
実際のところは、手許にある世界地図帳と見比べますと、この源流部より更に外れて、その南東側に出るのではとさえ想われます。
ただこのことは、そこに水や草がないことにはなりません。
このアルタイの西側斜面からは多くの川が流れ出ており(それが合流してウルングゥ川やイルティシュ川となる)、やはり同一方向の斜面ゆえに、ここに同程度の雨量は期待できます。
(大陸だと、逆斜面(例えば南斜面と北斜面)では雨量が全く異なるということは、しばしばあります。)
ここの山肌を流れる細流がウルングゥ川に合流するのか、砂中に尻無し川として消えるのか、はっきりしません。
他方で、ビシュバリクに向かうのを第一に考えるならば、このルートの方が明らかに距離が近く、納得できるところではあります。
ウルングゥ川はアルタイ山脈を発し、西北西に流れ、ウルングゥ湖に注ぎ入る河です。
(グーグルマップ上では、ウルングゥ川の名は表示されず、ウルングゥ湖は乌伦古湖もしくは烏倫古湖で表示。)
実際秘史の五巻158節ではチンギスとオン・カンはナイマンのブイルク・カンを追う時、アルタイを越えて、このウルングゥ川を下り追い、キシル・バシ湖で追いついたとあります。キシル・バシ湖はトルコ語『キジル・バシュ(赤頭)』のモンゴルなまりとみなされています。今のウルングゥ湖の古名です。(注4)
これより、このアルタイ越えのルートが以前より使われており、またウルングゥ川に至るものであることが確認できます。
(厳密に言えば、ビシュバリクに向かうルートからはそれて、ある程度の移動が必要なのかもしれませんが。)
ブイルク・カンがウルングゥ川を下ったのは、軍勢を率いておったからでしょう。
つまり、多くの軍馬の水を確保しつつ、逃走を図ったのです。
他方、例えば、少数の長春一行は、アルタイを越えて、ある川(訳者はこれをUrunga川とみなしています)の岸に至り、そこは水と草を豊かであるとするも、数日滞在するだけで、川を下るのではなく、川を渡ってビシュバリクの方に進んでいます。(注2)
それゆえ、考えられるのは、
1.そもそも史料の伝えるイルティシュ川で夏営したというのが間違いで、ウルングゥ川で夏営した。
2.ウルングゥ川からイルティッシュ河上流部まで大きく広がり夏営した。
多くの軍馬・家畜をたずさえることを考えれば、2は充分にありえることです。
西征に足の遅い羊や山羊を連れて行ったか否かというのは、史料上確認できることではありません。
ただ、膨大な軍兵であること、及び長距離に及ぶ(当然、その分、長期間に及ぶ)ことから、現地調達でまかなうのは不可能と想われ、引き連れたは間違いないと想われます。
イルティッシュ川の目印はザイサン湖(ウルングゥ(乌伦古)湖の西北西約270キロにある)です。アルタイ山脈に発し、やはり西北西に流れザイサン湖に入り、これより流れ出ます。
(グーグルマップではイルチェイシュ・リカと表示されますが、川が長大すぎて、この語で検索してもうまく表示されません。)
基本、夏に動かないのは次の冬を乗り越えるためです。
「馬肥ゆる秋」という如く、それまでに充分に太らせないと強烈な寒波による厳寒・強風・豪雪(枯れ草を食べられなくなる)で大量死してしまいます。
なぜアザラシがそろいもそろって丸々と太っておるのかを想えば、厳寒の地の動物というのが基本太っておる必要があるは、明らかでしょう。
やせておったら死ぬのです。
また夏というのは、暑さに加え、家畜の乳量が最も多い時期に当たります。
そのゆえに家畜は他の季節に比べ水を必要とします。
この家畜の乳こそが、この時期の将兵の食糧のほとんどとなるのであるから、ないがしろにできようはずもない。
また家畜の肉というのは、これを殺さなければ得らません。
それゆえ、可能な限り乳製品で食糧をまかなうのが基本です。
アルタイを初夏に渡った部隊は、イルティッシュ川の方まで広がり、長期夏営し、
楚材の如く盛夏に渡った部隊はウルングゥ川で小休止したとみなせば良いでしょう。
そして、秋になるのを待って進軍を再開したということだけは間違いないところです。
(以下後編につづきます。)
注1:『元史』(明・宋濂等)中華書局 北京 1976年
注2:岩村忍訳『長春眞人西遊記』筑摩書房 1948年
注3 村岡 倫「コラム2 長春真人の旅とチンカイ城」(白石典之編『チンギス・カンとその時代』勉誠出版 2015年 七七~八五貢)
注4:参照した秘史の訳書については、参考文献に記しております。
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
10
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる