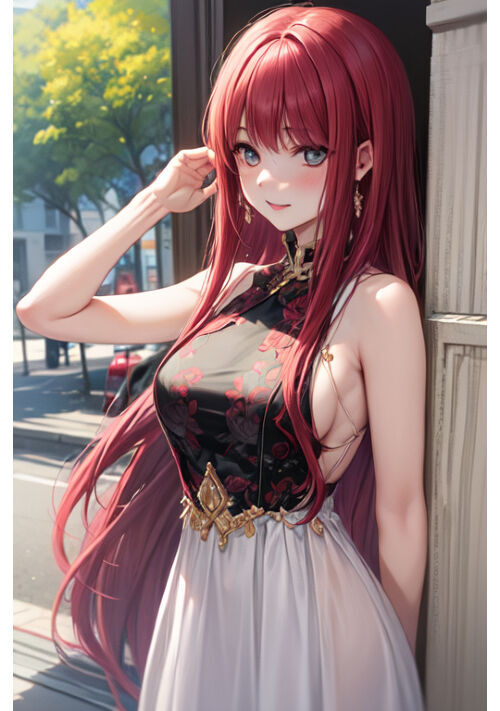3 / 16
1巻
1-3
しおりを挟む
* * * *
「――――」
立っていた。
じっと、礼拝堂の中で私は立ち尽くしていた。
美しくも何処か儚い偶像を前に、私は懐古していた。
「礼拝は済みましたか、ミレア」
カツカツ、と石造りの床に響く足音。
今生と変わらぬ過去の名前に私は反応を見せ、声のした方へと顔を向ける。
そこには黒と白が基調となった修道服の女性がいた。そして私は声を上げる。
「シスターメリッサ」
彼女の名はメリッサ。
この礼拝堂を管理する修道女である。気品溢れるメリッサのその立ち姿は、何処かのご令嬢を思わせるようなものであった。
「礼拝は、今し方終えたところです」
「そうですか」
淡白なやり取りをし、メリッサはそのまま歩みを止める事なく、私のすぐ側まで歩み寄る。
「主は全てを御覧になられています……と、誰もが言いますが、それは果たして本当なのでしょうか」
視線は設えられた偶像に向けたまま、メリッサが唐突にそう、ひとりごちた。
「知悉しておられるならば、どうして戦争が終わらないのです。どうして貧富の差はなくならないのです。どうして、こうも辛い世界が生まれるのですか」
神に仕える者だからこそ、疑いたくはない。けれど、全知全能の神ならば、何故この現状を救ってはくれないのだろうか。どうして、この凄惨な現実を見過ごしているのか。そう疑問に思わざるを得なかったのだろう。
「主から与えられた試練であると、誰もがかく語ります……ですが、それは本当に試練なのでしょうか。耐え難い苦痛を味わい、苦しんで悲しんで痛んで泣いて。そうせざるを得ない状況が真に試練であると?」
悲哀に塗れた声音で彼女は言う。
詰め込めるだけ詰め込んだ感情の奔流が、言葉と共に流れ出ていた。
「貴女は……どう思いますか。ミレア」
「私が、ですか」
「ええ。貴女がどう思っているのか。それを私に聞かせては貰えませんか」
シスターでこそないが、私も礼拝をする身。
形だけではあるけれど、信仰する神を貶める事は言いたくない。でも、
「……縋るべきではないでしょう」
「それは主に、ですか?」
「はい」
私は、救われた人間だ。
死の狭間から救い出された人間。
だけど、私を救ってくれたのは神でも、血の繋がった家族でもない。
「救いたいと望むのなら、この腐った世界を変えたいならば……私達自身が救える存在になるべきだと考えます。自分の手で救うしかないと思っています」
少なくとも私は、神様ではなく一人の女性に救われた。飢えに苦しむ孤児を救おうとするシスターメリッサによって、私という人間は救われたのだ。
「それでは、貴女自身が神にでもなると?」
「……いえ。そんな大それた事は出来る筈がありません。でも、シスターメリッサに救われた私だからこそ……今度は私が誰かを救いたい」
神も権力者も。
誰も手を差し伸べないならば、私が代わりにすればいい。
私が代わりに、彼らの光になればいい。
「私を含め、誰もが手を伸ばしているんです。助けてくれと。救ってくれと。だから私は、その手を取れる光となりたい」
一人ではどうにも出来ず、他人の手すら取る余裕がない。かつての私がそうだったように。その気持ちが痛いほど分かる私だからこそ、光になりたかった。
きっとこの時この瞬間こそが、私が『聖女』を目指すに至るキッカケであったのだ。
孤児として生き、シスターメリッサに救われ、こうして人間らしく生きる事が出来ている。
誰かに救われた私だからこそ、光となるべきであった。そしてその『光』である限り、私は救おう。
誰も彼もを救ってみせよう。それはただの自己満足でしかないのだとしても。
僅かに笑い、私は偶像を仰いだ。
神様のような全知全能には、どう頑張ってもなれないだろう。けれど、そんな私でも出来る事はある筈だ。
痛みを、辛さを、悲しさを、苦しさを。
その全てを知る私だからこそ、誰よりも弱者の気持ちが分かる。救って欲しいと手を伸ばす者の気持ちが。これは傲慢だ。傲慢だけど、それでも。
私が救おう。
私が助けよう。
私が守ろう。
私が手を取ろう。
何故なら私が、
――『光』でありたいと願ったから。
小さく、儚く、薄く、暗く。
私の存在を『光』として表すならば、きっとそんな言葉が羅列された事だろう。
まだ曙光すら射していない夜更け。
そんな中途半端な時間に目を覚まし、夢の世界を後にした私は、上体を起こして数時間前のバンハードとのやり取りを思い返していた。彼は私を終始奇異の視線で見つめ続けた。その光景が脳裏にありありと映し出される。
言葉にこそされなかったが、私の考えや感情が理解の埒外であると、目が口ほどにものを言っていた。
人は、己が理解出来ない事柄に直面した際、何よりも優先してその『異常』を理解しようと試みる。『異常』である事に答えを求めたがる。己の価値観に基づいた答えを出そうとして、けれど答えは出てこなくて。
だから、きっと彼は憤ったのだと思う。
「共感は、求めてないんだよね」
この生き方。この思考。この価値観。
共感する事は素晴らしい。理解し、言葉を尽くして語り合う。誰もが誰もを尊重して思いやる。それは何よりも称揚されるべき行為だ。
けれど、私は共感を必要としていなかった。
他人がどう言おうとも最早この考えは変わらない。
そこにどれだけの自己犠牲が付き纏ったとしても、私の場合はそれがどうしたで終わってしまう。
それこそが、バンハードにとっての『異常』。
「……でも、まあ、もう無理に共感してもらう必要はないと思うけど」
何故なら、もう私は『聖女』ではないから。
私を理解しようとする人間など、バンハードのような、私の体の壊れ加減を知る医者ぐらいである。実家の近くで細々と救済活動を続けるだけの今後は、そんな人物との接点は片手で事足りる程度だろう。
それこそ、『聖女』なんていう肩書きがない限り、滅多な事では接点は生まれない筈だ。
「結局、『聖女』として何を救うのが正しかったのかは分からず終いだったけど、それでもきっと意味はあったよね」
否定の声も肯定の声も聞こえてこない。
だけど、私は自分自身の中に存在するこの満足感さえあれば十分だった。それだけあれば、意味があったのだと思う事が出来た。
「最後はこうして倒れて、迷惑をかけちゃった。でも、私なりに出来る事は……した。案の定、限界がやって来たけど、それでも」
口酸っぱく己に出来る事をしろと言い続けてくれた、一人のシスターの姿を想起する。
「貴女の教えを私は守れていましたか……シスターメリッサ」
この時代において、誰も知らない邂逅。誰も知らない思い出。誰も知らない、教え。
そして私の根幹たるシスターメリッサだけが知る誓い。『光』であろうと、『救う』と決めたあの日の誓い。それらが今日までの私を突き動かす動力源でもあった。
そして、私の思考を横切る一瞬の懐古。
一つの映像が私の頭の中を侵食する。過去と現在が交錯し、やって来る思い出に一人酔い痴れた。
『――――光ですか』
それは夢の続き。
儚い夢の世界にて懐かしんだ記憶の続き。
『貴女は、自分自身が苦しむ人々を救う「光」となれる、と?』
そう問いかけるシスターメリッサに対し、私はかぶりを振る。
『なれる、ではありません。私は……ならなければいけないのです』
『……その言葉だけでは、まるで義務のように聞こえてしまいますね』
『はい。きっとこれは私にとって命題であり、天命であり、成さねばならない義務なのでしょう』
『天国』という救いは、残念ながら何処にも存在しない。死ねば極楽。そんな救いも持ち得ない人々は、一体何に縋って生きれば良いのだろうか。
救って欲しいと必死に手を伸ばす彼らに、誰が手を差し伸べるのだろうか。
……私のこの考えは夢物語だろう。
腹を抱えて大笑されて然るべき夢物語だろう。
しかし彼女だけは、シスターメリッサだけは、
『……そう、ですか』
決してこの想いを笑わない。
『貴女が真にそうしたいと思っているのならば、それが正しいのでしょう。それが、貴女にしか出来ない事なのでしょう』
――私には出来ませんでしたが、貴女なら。
消え入りそうな声で付け加えられたその言葉は、いやに耳に残った。
『……どうか、貴女の行く道に救いがあらん事を』
殊更ゆっくりと。
まるで祈りを捧げるように、シスターメリッサが言う。
『その想いを抱く間は、どうか多くの人々の「光」となってあげてください、ミレア』
莞爾と笑う彼女は、本当に綺麗だった。
きっと私という人間は、シスターメリッサという人間に何処までも憧れていたのだ。憧れて、そんな彼女に近づき、彼女のようになりたいと願って。
だから――『聖女』として生きてきたのだろう。
「眩しいなあ……ほんと」
永遠に憧れの人。
私にとっての救いであり、目標であり、縋っていた『光』は、私の中で今も尚、まばゆく輝いていた。
そんな事を考えていたからか、眠気はすっかり吹き飛んでしまった。二度寝は……出来ないかな、と苦笑いを浮かべ、私は窓越しに広がる夜闇の景色をじっと眺める事にした。
5話
「ねえ、レイン。最後に一つだけ、我儘を言ってもいいかな」
それから、二時間ほど後。
朝焼けが夜闇にじんわりと染み渡り始めた頃、私の部屋を訪ねて来たレインの声をドア越しに聞き取り、彼を部屋に通すや否や、私はそんな事を口にしていた。
不要なトラブルは避けたいと、正論を口にするだろうレインに対し、あえて、私は『我儘』という言葉を使う。
そして、見る見るうちに、レインの表情は顰めっ面へと変貌を遂げていく。
「……内容によります」
「寄りたい場所があるの。私はきっと、王都には当分来れなくなるだろうから、最後に一度だけ」
「……その場所は」
「勿論、いつもの場所だよ」
そう言うと、やはりかと言わんばかりに、レインは眉間に皺を寄せた。
私が口にするいつもの場所とは、王都において唯一の掃き溜めの地――スラム街。
せめて『聖女』くらいはと、手を差し伸べ続けた場所であった。
「……ミレアお嬢様は、もう『聖女』ではないんですよ」
レインのその言葉は、きっと本意ではない。ずっと『聖女』足らんとしてきた人間に対して、お前は違うのだと、彼は言いたくなかったのだ。でも、それくらいしか私を止められる言葉はないと判断したのだろう。
『聖女』というものに私が固執していたと、誰よりも知るレインだからこそ、あえてその言葉を選んだ筈だ。
だけど、
「うん。分かってる。そんな事は分かってる。でもね、約束した事くらいは、守らないと」
彼の葛藤を理解して尚、私はそれに応じる事だけは出来なかった。
「……そう口にされるのは、また、救いたいから、ですか」
――『聖女』だから。
今の私からは、その前提は既に取っ払われてしまっている。だから、『聖女』らしくあろうとする必要はないじゃないか。
レインの歪められた表情は、そう言いたげであった。
勿論その通りだ。
しかしこれは、私が私の為に、好きで『救おう』としているだけ。好きで『光』足らんとしてるだけ。好きで、いつか交わした約束を守ろうとしているだけ。
だから、『聖女』だ、『聖女』でないといった前提なんてものは、これに関係ないんだよと胸中で言葉を重ねながら、続ける。
「私はね、昔はずっとよく思ってたんだ。生きていたって苦しいだけじゃんって。苦しい思いをして、悲しい思いをして、辛い思いをして。そうやってたっぷり苦しんでまで、あえて生きる理由って本当にあるのかなって」
前世、間違っても人に誇れるような生まれでなかった私は、日々そんな考えを抱きながら生きていた。勿論『救い』なんて言葉は、当時の私の頭の辞書には存在すらしていなかった。
「でもある時、その考えは間違いだったって気付かされたんだ。ある人に、教えてもらったんだ。この世に、生きる必要のない人間は一人としていないんだって。そう、手を差し伸べられて。私自身が『救われて』、初めて気づく事が出来た」
だからね、と私は言葉を続ける。
「自己満足でしかないけど、私は救いたいんだ。『聖女』であろうと、なかろうと」
その救いとは、手を差し伸ばし続ける事。
「だって――――私も、救われた側の人間だから」
少しでも、あの人の想いが多くの人達に伝わりますように。
そんな私の言葉を耳にしたレインの表情は、相変わらず、悲痛に歪んでいた。
考え直してくださいと言っても、私が微塵も受け取る気はないと分かっていたのだろう。
言葉を投げ掛けたところで無為に終わるだけ。その後続いた小さな溜息は、きっとそんな意味合いを持ったものだったんだと思う。
「ごめんね、レイン」
謝罪を一つ。
決して、私がこれからする行動が間違っているとは思わない。
でも、レインにこんな顔をさせている原因は、紛う事なく私にある。
だから、私は謝る。
謝るくらいなら、少しは自分の言う事を聞いてくれ。そう言わんばかりに見詰めてくるレインに対して、私は苦笑いを浮かべて視線を逸らす事しか出来なかった。
視線を逸らした先には窓があって。
空から射し込む朝焼けの光が、私の表情を窓に映している。その顔は、何処か悲しそうで、何処か迷っているようにも見て取れてしまって。
「……ひっどい顔」
それは本当に、酷い顔だった。
そんな表情を浮かべる人間が一体誰を救えるのだと、自分自身を責め立ててやりたいくらいに、私らしくない顔であった。
* * * *
「……何も言わずに、此処から引き返せ」
まず感じたのは鼻腔をくすぐる腐臭。その原因だろうゴミの山が、あちこちにある。
真っ当な人間であれば、三日として耐えられないであろう環境が、そこには当たり前のように広がっていた。まともな感性を持つ者であれば、近付きすらしないであろう場所。
それが――――スラム街。
ボロ切れのようにも見える薄汚れた黒のパーカーコートを着込んだ男は、若干俯いた状態で私に言葉を投げ掛けて来た。
――――……早く此処から消えてくれ。
ぞんざいに吐き捨てられた筈なのに、どうしてだろう。私の耳にはそれが切実な訴えにしか聞こえなかった。
だけど、
「や。ライナ。久しぶり」
私はあえて、その訴えを黙殺した。
そして相貌にいつも通りの笑顔を貼り付けて、公園にでも遊びに行くように、そう言って彼の下へ歩み寄る。
彼の名は、ライナ。
スラム街の住人の一人で、それでもって、私の知り合いの一人でもあった。
「……なんで此処に来た」
「ごめんね、最近は体調が悪くて外に出られなかったんだ。それと、今日はあんまり時間がなくてさ。急いでるから、早速で悪いけどいつものように案内してもらえない?」
「――なんで、此処に来たんだっておれは聞いてんだろうがッ‼」
会話になっていなかった。
……ううん、それは私の思い違いだ。
私に、会話をする気がなかった。こうなった原因は、ただそれだけの事。だから、彼はこうして怒りに任せて叫び散らしていた。
「あんた、自分の立場ってもんが分かんねえのかよ。これまであんたがスラム街に来ても大事にならなかったのは、あんたが『聖女』の肩書きを持っていたからだ。流石の荒くれ共も、手を出せば間違いなく殺されると分かっていたから、表立っては何もしてこなかった……今はその保障がないんだぞ」
『偽聖女』の件は、既にスラム街にまで届いていたらしい。
けれど、私からすれば、そんなものは伝わっていようがいまいが関係なかった。
たとえなんであろうと、私のやりたいようにやる。ただそれだけの事なんだから。
「うん。それは勿論知ってる。でも、だから何? 特にスラム街には生きたいって必死に願っている弱者が多くいる。それを私は知ってる。だったら、なんであれ、私は手を差し伸べるだけ。それはこれまでも、これから先も変わらない。たとえ何があろうと、それだけは変わらない。だから、ね? 今更過ぎる問い掛けは、よしてよライナ」
私は常に、至極真っ当な事を言っているつもりだ。己が真に正しいと断じられる言葉を並べ立てているだけ。
なのに決まって、何故か賛同だけは得られない。
私が救いたいから、救う。
ただそれだけの筈なのに。
「だけど、こうした救済を『聖女』らしさの証として当て嵌めていたって気持ちは勿論、私の中にもあったと思う。なにせ、私が憧れていた『聖女』ってものは、そういうものだから。でも、私のこの『救いたい』と願う想いは何処までも真実だよ」
だから、『聖女』であろうとなかろうと。
そこに危険が付き纏う事になろうと関係がないよと、ライナに向けて私は諭した。
なのに、
「……あんたの考えてる事が、どうやってもおれには分からねえ」
返ってきたのは、掠れた声で紡がれた葛藤滲む言葉であった。次いで、拒絶の瞳が向けられる。
そしてそれは、説得の放棄でもあった。
やがて、彼は私に背を向けて歩き出す。
「……おれはただ、帰るだけ。後をつけるなら勝手にしろ」
――――引き返せ。
開口一番のライナのその言葉は、間違いなく私に対する配慮であり、気遣いであり、懇願であった筈だ。理由は一つ、何が起こるか分からないから。そしてその考えを覆す気は彼にはない。
しかし、押し掛けてきた私も自分の意見を覆す気は更々ない。
これは、そんな中で出したライナなりの妥協なのだろう。勝手について来るなら止めはしない。
それが、口下手な彼の精一杯の譲歩だった。
「やっぱり優しいね、ライナは」
もう、五年近く前だろうか。
私が初めてスラム街に踏み込み、誰かを救うのだとお節介を焼こうとした初めての人は、何処までも心配性で、相変わらず優しかった。
そうして私は、奥へ奥へと淀みない歩調で向かっていくライナの背中を、レインと共に追いかける。
辛うじて建物と呼べるほどに傷み、亀裂が無数に点在するひしゃげた家の中。
薄汚れたベッドの上にて横たわり、苦しそうに肩で息をする少女の下へと、私達は辿り着いた。
私は『聖魔法』という一風変わった魔法を扱えるが、それは同時に治癒の魔法に精通している事も意味する。
この世界において、治療とは高価なものである。
治癒の魔法を扱える人間はごく僅かな為、魔法一つかけるだけで膨大な金銭を稼ぐ事も出来る。
勿論、貧しい人々には手が届かない。その結果、外傷が原因の合併症などで命を落とす、もしくはさらなる重体に陥ってしまう事例が特に多かった。
それを憂えた私は、治癒の魔法が得意なのを利用して、スラム街や他の場所で、施療院の真似を定期的に行っていたのだ。
しかし、それ以上の事は出来ていないのが実情だった。
「私に力があれば、教会でも何処かにぶっ立てて、みんなを保護出来たのにね」
かつて、それを現実にしてみせた人物の事が頭をよぎり、そんな言葉が口を衝いて出てしまった。
明らかに病気を患い苦しんでいる少女を前に、私は悔恨を口にする。
いくら己が『聖女』と呼ばれていたとはいえ、所詮は偶像程度の扱い。
加えて、婚約者であった王太子から私は特に嫌われており、何かをしたいと言えば、間違いなく反発が起こると分かっていた為、施療院の真似より目立った行動は起こせていなかった。
仕方がないとはいえ、本来スラム街とは人が住めるような場所ではない。
子供であるなら尚更だ。
「……あんたなら、本当にやりかねないな」
「うん。だって、やりたいもん」
病気を患う少女の下まで案内をしてくれたライナは、壁にもたれながら呆れてみせる。
困っている人を助けたい。
だから、スラム街に詳しいライナに、その為の案内役を頼みたい。
五年前、出会った頃の彼にそう頼んだ。私が治癒の魔法を使えるとライナも知っており、こうして病気を患ってしまった人達の下へ私を案内してくれる。
「――――」
立っていた。
じっと、礼拝堂の中で私は立ち尽くしていた。
美しくも何処か儚い偶像を前に、私は懐古していた。
「礼拝は済みましたか、ミレア」
カツカツ、と石造りの床に響く足音。
今生と変わらぬ過去の名前に私は反応を見せ、声のした方へと顔を向ける。
そこには黒と白が基調となった修道服の女性がいた。そして私は声を上げる。
「シスターメリッサ」
彼女の名はメリッサ。
この礼拝堂を管理する修道女である。気品溢れるメリッサのその立ち姿は、何処かのご令嬢を思わせるようなものであった。
「礼拝は、今し方終えたところです」
「そうですか」
淡白なやり取りをし、メリッサはそのまま歩みを止める事なく、私のすぐ側まで歩み寄る。
「主は全てを御覧になられています……と、誰もが言いますが、それは果たして本当なのでしょうか」
視線は設えられた偶像に向けたまま、メリッサが唐突にそう、ひとりごちた。
「知悉しておられるならば、どうして戦争が終わらないのです。どうして貧富の差はなくならないのです。どうして、こうも辛い世界が生まれるのですか」
神に仕える者だからこそ、疑いたくはない。けれど、全知全能の神ならば、何故この現状を救ってはくれないのだろうか。どうして、この凄惨な現実を見過ごしているのか。そう疑問に思わざるを得なかったのだろう。
「主から与えられた試練であると、誰もがかく語ります……ですが、それは本当に試練なのでしょうか。耐え難い苦痛を味わい、苦しんで悲しんで痛んで泣いて。そうせざるを得ない状況が真に試練であると?」
悲哀に塗れた声音で彼女は言う。
詰め込めるだけ詰め込んだ感情の奔流が、言葉と共に流れ出ていた。
「貴女は……どう思いますか。ミレア」
「私が、ですか」
「ええ。貴女がどう思っているのか。それを私に聞かせては貰えませんか」
シスターでこそないが、私も礼拝をする身。
形だけではあるけれど、信仰する神を貶める事は言いたくない。でも、
「……縋るべきではないでしょう」
「それは主に、ですか?」
「はい」
私は、救われた人間だ。
死の狭間から救い出された人間。
だけど、私を救ってくれたのは神でも、血の繋がった家族でもない。
「救いたいと望むのなら、この腐った世界を変えたいならば……私達自身が救える存在になるべきだと考えます。自分の手で救うしかないと思っています」
少なくとも私は、神様ではなく一人の女性に救われた。飢えに苦しむ孤児を救おうとするシスターメリッサによって、私という人間は救われたのだ。
「それでは、貴女自身が神にでもなると?」
「……いえ。そんな大それた事は出来る筈がありません。でも、シスターメリッサに救われた私だからこそ……今度は私が誰かを救いたい」
神も権力者も。
誰も手を差し伸べないならば、私が代わりにすればいい。
私が代わりに、彼らの光になればいい。
「私を含め、誰もが手を伸ばしているんです。助けてくれと。救ってくれと。だから私は、その手を取れる光となりたい」
一人ではどうにも出来ず、他人の手すら取る余裕がない。かつての私がそうだったように。その気持ちが痛いほど分かる私だからこそ、光になりたかった。
きっとこの時この瞬間こそが、私が『聖女』を目指すに至るキッカケであったのだ。
孤児として生き、シスターメリッサに救われ、こうして人間らしく生きる事が出来ている。
誰かに救われた私だからこそ、光となるべきであった。そしてその『光』である限り、私は救おう。
誰も彼もを救ってみせよう。それはただの自己満足でしかないのだとしても。
僅かに笑い、私は偶像を仰いだ。
神様のような全知全能には、どう頑張ってもなれないだろう。けれど、そんな私でも出来る事はある筈だ。
痛みを、辛さを、悲しさを、苦しさを。
その全てを知る私だからこそ、誰よりも弱者の気持ちが分かる。救って欲しいと手を伸ばす者の気持ちが。これは傲慢だ。傲慢だけど、それでも。
私が救おう。
私が助けよう。
私が守ろう。
私が手を取ろう。
何故なら私が、
――『光』でありたいと願ったから。
小さく、儚く、薄く、暗く。
私の存在を『光』として表すならば、きっとそんな言葉が羅列された事だろう。
まだ曙光すら射していない夜更け。
そんな中途半端な時間に目を覚まし、夢の世界を後にした私は、上体を起こして数時間前のバンハードとのやり取りを思い返していた。彼は私を終始奇異の視線で見つめ続けた。その光景が脳裏にありありと映し出される。
言葉にこそされなかったが、私の考えや感情が理解の埒外であると、目が口ほどにものを言っていた。
人は、己が理解出来ない事柄に直面した際、何よりも優先してその『異常』を理解しようと試みる。『異常』である事に答えを求めたがる。己の価値観に基づいた答えを出そうとして、けれど答えは出てこなくて。
だから、きっと彼は憤ったのだと思う。
「共感は、求めてないんだよね」
この生き方。この思考。この価値観。
共感する事は素晴らしい。理解し、言葉を尽くして語り合う。誰もが誰もを尊重して思いやる。それは何よりも称揚されるべき行為だ。
けれど、私は共感を必要としていなかった。
他人がどう言おうとも最早この考えは変わらない。
そこにどれだけの自己犠牲が付き纏ったとしても、私の場合はそれがどうしたで終わってしまう。
それこそが、バンハードにとっての『異常』。
「……でも、まあ、もう無理に共感してもらう必要はないと思うけど」
何故なら、もう私は『聖女』ではないから。
私を理解しようとする人間など、バンハードのような、私の体の壊れ加減を知る医者ぐらいである。実家の近くで細々と救済活動を続けるだけの今後は、そんな人物との接点は片手で事足りる程度だろう。
それこそ、『聖女』なんていう肩書きがない限り、滅多な事では接点は生まれない筈だ。
「結局、『聖女』として何を救うのが正しかったのかは分からず終いだったけど、それでもきっと意味はあったよね」
否定の声も肯定の声も聞こえてこない。
だけど、私は自分自身の中に存在するこの満足感さえあれば十分だった。それだけあれば、意味があったのだと思う事が出来た。
「最後はこうして倒れて、迷惑をかけちゃった。でも、私なりに出来る事は……した。案の定、限界がやって来たけど、それでも」
口酸っぱく己に出来る事をしろと言い続けてくれた、一人のシスターの姿を想起する。
「貴女の教えを私は守れていましたか……シスターメリッサ」
この時代において、誰も知らない邂逅。誰も知らない思い出。誰も知らない、教え。
そして私の根幹たるシスターメリッサだけが知る誓い。『光』であろうと、『救う』と決めたあの日の誓い。それらが今日までの私を突き動かす動力源でもあった。
そして、私の思考を横切る一瞬の懐古。
一つの映像が私の頭の中を侵食する。過去と現在が交錯し、やって来る思い出に一人酔い痴れた。
『――――光ですか』
それは夢の続き。
儚い夢の世界にて懐かしんだ記憶の続き。
『貴女は、自分自身が苦しむ人々を救う「光」となれる、と?』
そう問いかけるシスターメリッサに対し、私はかぶりを振る。
『なれる、ではありません。私は……ならなければいけないのです』
『……その言葉だけでは、まるで義務のように聞こえてしまいますね』
『はい。きっとこれは私にとって命題であり、天命であり、成さねばならない義務なのでしょう』
『天国』という救いは、残念ながら何処にも存在しない。死ねば極楽。そんな救いも持ち得ない人々は、一体何に縋って生きれば良いのだろうか。
救って欲しいと必死に手を伸ばす彼らに、誰が手を差し伸べるのだろうか。
……私のこの考えは夢物語だろう。
腹を抱えて大笑されて然るべき夢物語だろう。
しかし彼女だけは、シスターメリッサだけは、
『……そう、ですか』
決してこの想いを笑わない。
『貴女が真にそうしたいと思っているのならば、それが正しいのでしょう。それが、貴女にしか出来ない事なのでしょう』
――私には出来ませんでしたが、貴女なら。
消え入りそうな声で付け加えられたその言葉は、いやに耳に残った。
『……どうか、貴女の行く道に救いがあらん事を』
殊更ゆっくりと。
まるで祈りを捧げるように、シスターメリッサが言う。
『その想いを抱く間は、どうか多くの人々の「光」となってあげてください、ミレア』
莞爾と笑う彼女は、本当に綺麗だった。
きっと私という人間は、シスターメリッサという人間に何処までも憧れていたのだ。憧れて、そんな彼女に近づき、彼女のようになりたいと願って。
だから――『聖女』として生きてきたのだろう。
「眩しいなあ……ほんと」
永遠に憧れの人。
私にとっての救いであり、目標であり、縋っていた『光』は、私の中で今も尚、まばゆく輝いていた。
そんな事を考えていたからか、眠気はすっかり吹き飛んでしまった。二度寝は……出来ないかな、と苦笑いを浮かべ、私は窓越しに広がる夜闇の景色をじっと眺める事にした。
5話
「ねえ、レイン。最後に一つだけ、我儘を言ってもいいかな」
それから、二時間ほど後。
朝焼けが夜闇にじんわりと染み渡り始めた頃、私の部屋を訪ねて来たレインの声をドア越しに聞き取り、彼を部屋に通すや否や、私はそんな事を口にしていた。
不要なトラブルは避けたいと、正論を口にするだろうレインに対し、あえて、私は『我儘』という言葉を使う。
そして、見る見るうちに、レインの表情は顰めっ面へと変貌を遂げていく。
「……内容によります」
「寄りたい場所があるの。私はきっと、王都には当分来れなくなるだろうから、最後に一度だけ」
「……その場所は」
「勿論、いつもの場所だよ」
そう言うと、やはりかと言わんばかりに、レインは眉間に皺を寄せた。
私が口にするいつもの場所とは、王都において唯一の掃き溜めの地――スラム街。
せめて『聖女』くらいはと、手を差し伸べ続けた場所であった。
「……ミレアお嬢様は、もう『聖女』ではないんですよ」
レインのその言葉は、きっと本意ではない。ずっと『聖女』足らんとしてきた人間に対して、お前は違うのだと、彼は言いたくなかったのだ。でも、それくらいしか私を止められる言葉はないと判断したのだろう。
『聖女』というものに私が固執していたと、誰よりも知るレインだからこそ、あえてその言葉を選んだ筈だ。
だけど、
「うん。分かってる。そんな事は分かってる。でもね、約束した事くらいは、守らないと」
彼の葛藤を理解して尚、私はそれに応じる事だけは出来なかった。
「……そう口にされるのは、また、救いたいから、ですか」
――『聖女』だから。
今の私からは、その前提は既に取っ払われてしまっている。だから、『聖女』らしくあろうとする必要はないじゃないか。
レインの歪められた表情は、そう言いたげであった。
勿論その通りだ。
しかしこれは、私が私の為に、好きで『救おう』としているだけ。好きで『光』足らんとしてるだけ。好きで、いつか交わした約束を守ろうとしているだけ。
だから、『聖女』だ、『聖女』でないといった前提なんてものは、これに関係ないんだよと胸中で言葉を重ねながら、続ける。
「私はね、昔はずっとよく思ってたんだ。生きていたって苦しいだけじゃんって。苦しい思いをして、悲しい思いをして、辛い思いをして。そうやってたっぷり苦しんでまで、あえて生きる理由って本当にあるのかなって」
前世、間違っても人に誇れるような生まれでなかった私は、日々そんな考えを抱きながら生きていた。勿論『救い』なんて言葉は、当時の私の頭の辞書には存在すらしていなかった。
「でもある時、その考えは間違いだったって気付かされたんだ。ある人に、教えてもらったんだ。この世に、生きる必要のない人間は一人としていないんだって。そう、手を差し伸べられて。私自身が『救われて』、初めて気づく事が出来た」
だからね、と私は言葉を続ける。
「自己満足でしかないけど、私は救いたいんだ。『聖女』であろうと、なかろうと」
その救いとは、手を差し伸ばし続ける事。
「だって――――私も、救われた側の人間だから」
少しでも、あの人の想いが多くの人達に伝わりますように。
そんな私の言葉を耳にしたレインの表情は、相変わらず、悲痛に歪んでいた。
考え直してくださいと言っても、私が微塵も受け取る気はないと分かっていたのだろう。
言葉を投げ掛けたところで無為に終わるだけ。その後続いた小さな溜息は、きっとそんな意味合いを持ったものだったんだと思う。
「ごめんね、レイン」
謝罪を一つ。
決して、私がこれからする行動が間違っているとは思わない。
でも、レインにこんな顔をさせている原因は、紛う事なく私にある。
だから、私は謝る。
謝るくらいなら、少しは自分の言う事を聞いてくれ。そう言わんばかりに見詰めてくるレインに対して、私は苦笑いを浮かべて視線を逸らす事しか出来なかった。
視線を逸らした先には窓があって。
空から射し込む朝焼けの光が、私の表情を窓に映している。その顔は、何処か悲しそうで、何処か迷っているようにも見て取れてしまって。
「……ひっどい顔」
それは本当に、酷い顔だった。
そんな表情を浮かべる人間が一体誰を救えるのだと、自分自身を責め立ててやりたいくらいに、私らしくない顔であった。
* * * *
「……何も言わずに、此処から引き返せ」
まず感じたのは鼻腔をくすぐる腐臭。その原因だろうゴミの山が、あちこちにある。
真っ当な人間であれば、三日として耐えられないであろう環境が、そこには当たり前のように広がっていた。まともな感性を持つ者であれば、近付きすらしないであろう場所。
それが――――スラム街。
ボロ切れのようにも見える薄汚れた黒のパーカーコートを着込んだ男は、若干俯いた状態で私に言葉を投げ掛けて来た。
――――……早く此処から消えてくれ。
ぞんざいに吐き捨てられた筈なのに、どうしてだろう。私の耳にはそれが切実な訴えにしか聞こえなかった。
だけど、
「や。ライナ。久しぶり」
私はあえて、その訴えを黙殺した。
そして相貌にいつも通りの笑顔を貼り付けて、公園にでも遊びに行くように、そう言って彼の下へ歩み寄る。
彼の名は、ライナ。
スラム街の住人の一人で、それでもって、私の知り合いの一人でもあった。
「……なんで此処に来た」
「ごめんね、最近は体調が悪くて外に出られなかったんだ。それと、今日はあんまり時間がなくてさ。急いでるから、早速で悪いけどいつものように案内してもらえない?」
「――なんで、此処に来たんだっておれは聞いてんだろうがッ‼」
会話になっていなかった。
……ううん、それは私の思い違いだ。
私に、会話をする気がなかった。こうなった原因は、ただそれだけの事。だから、彼はこうして怒りに任せて叫び散らしていた。
「あんた、自分の立場ってもんが分かんねえのかよ。これまであんたがスラム街に来ても大事にならなかったのは、あんたが『聖女』の肩書きを持っていたからだ。流石の荒くれ共も、手を出せば間違いなく殺されると分かっていたから、表立っては何もしてこなかった……今はその保障がないんだぞ」
『偽聖女』の件は、既にスラム街にまで届いていたらしい。
けれど、私からすれば、そんなものは伝わっていようがいまいが関係なかった。
たとえなんであろうと、私のやりたいようにやる。ただそれだけの事なんだから。
「うん。それは勿論知ってる。でも、だから何? 特にスラム街には生きたいって必死に願っている弱者が多くいる。それを私は知ってる。だったら、なんであれ、私は手を差し伸べるだけ。それはこれまでも、これから先も変わらない。たとえ何があろうと、それだけは変わらない。だから、ね? 今更過ぎる問い掛けは、よしてよライナ」
私は常に、至極真っ当な事を言っているつもりだ。己が真に正しいと断じられる言葉を並べ立てているだけ。
なのに決まって、何故か賛同だけは得られない。
私が救いたいから、救う。
ただそれだけの筈なのに。
「だけど、こうした救済を『聖女』らしさの証として当て嵌めていたって気持ちは勿論、私の中にもあったと思う。なにせ、私が憧れていた『聖女』ってものは、そういうものだから。でも、私のこの『救いたい』と願う想いは何処までも真実だよ」
だから、『聖女』であろうとなかろうと。
そこに危険が付き纏う事になろうと関係がないよと、ライナに向けて私は諭した。
なのに、
「……あんたの考えてる事が、どうやってもおれには分からねえ」
返ってきたのは、掠れた声で紡がれた葛藤滲む言葉であった。次いで、拒絶の瞳が向けられる。
そしてそれは、説得の放棄でもあった。
やがて、彼は私に背を向けて歩き出す。
「……おれはただ、帰るだけ。後をつけるなら勝手にしろ」
――――引き返せ。
開口一番のライナのその言葉は、間違いなく私に対する配慮であり、気遣いであり、懇願であった筈だ。理由は一つ、何が起こるか分からないから。そしてその考えを覆す気は彼にはない。
しかし、押し掛けてきた私も自分の意見を覆す気は更々ない。
これは、そんな中で出したライナなりの妥協なのだろう。勝手について来るなら止めはしない。
それが、口下手な彼の精一杯の譲歩だった。
「やっぱり優しいね、ライナは」
もう、五年近く前だろうか。
私が初めてスラム街に踏み込み、誰かを救うのだとお節介を焼こうとした初めての人は、何処までも心配性で、相変わらず優しかった。
そうして私は、奥へ奥へと淀みない歩調で向かっていくライナの背中を、レインと共に追いかける。
辛うじて建物と呼べるほどに傷み、亀裂が無数に点在するひしゃげた家の中。
薄汚れたベッドの上にて横たわり、苦しそうに肩で息をする少女の下へと、私達は辿り着いた。
私は『聖魔法』という一風変わった魔法を扱えるが、それは同時に治癒の魔法に精通している事も意味する。
この世界において、治療とは高価なものである。
治癒の魔法を扱える人間はごく僅かな為、魔法一つかけるだけで膨大な金銭を稼ぐ事も出来る。
勿論、貧しい人々には手が届かない。その結果、外傷が原因の合併症などで命を落とす、もしくはさらなる重体に陥ってしまう事例が特に多かった。
それを憂えた私は、治癒の魔法が得意なのを利用して、スラム街や他の場所で、施療院の真似を定期的に行っていたのだ。
しかし、それ以上の事は出来ていないのが実情だった。
「私に力があれば、教会でも何処かにぶっ立てて、みんなを保護出来たのにね」
かつて、それを現実にしてみせた人物の事が頭をよぎり、そんな言葉が口を衝いて出てしまった。
明らかに病気を患い苦しんでいる少女を前に、私は悔恨を口にする。
いくら己が『聖女』と呼ばれていたとはいえ、所詮は偶像程度の扱い。
加えて、婚約者であった王太子から私は特に嫌われており、何かをしたいと言えば、間違いなく反発が起こると分かっていた為、施療院の真似より目立った行動は起こせていなかった。
仕方がないとはいえ、本来スラム街とは人が住めるような場所ではない。
子供であるなら尚更だ。
「……あんたなら、本当にやりかねないな」
「うん。だって、やりたいもん」
病気を患う少女の下まで案内をしてくれたライナは、壁にもたれながら呆れてみせる。
困っている人を助けたい。
だから、スラム街に詳しいライナに、その為の案内役を頼みたい。
五年前、出会った頃の彼にそう頼んだ。私が治癒の魔法を使えるとライナも知っており、こうして病気を患ってしまった人達の下へ私を案内してくれる。
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
6,016
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる
本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。
このユーザをミュートしますか?
※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。
※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。
※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。