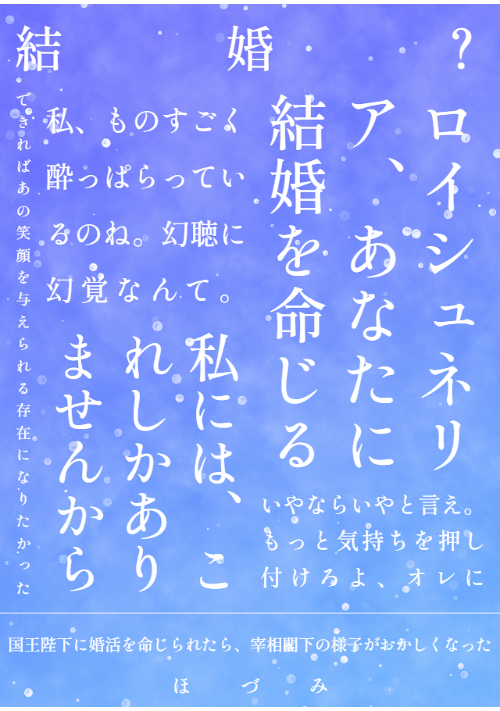36 / 49
36、理解できない
しおりを挟む* * *
夕暮れが迫り、部屋の中には闇が忍び寄っている。
ユリウスは館の主の顔を、正面から見据えていた。執務室で机に向かうゼルガーダンは苦虫を噛み潰したような顔でユリウスを睨んでいた。
話がある、と訪ねてみたら、案外あっさりと通された。だが、通しておきながら一刻も早く追い返したいという雰囲気である。
話というのが気になるが、このいけ好かない青二才の顔など一秒だって長く見ていたくないというのが本音だろう。
「それで、話というのは何だ?」
型にはまった挨拶代わりの話をするのも煩わしいらしい。余裕のなさをユリウスは内心嘲っていた。
「あなたはそれほど私が怖かったのか? ゼルガーダン卿」
開口一番、無礼極まる発言に、ゼルガーダンは目を吊り上げた。
「なんだと?」
「私はしばらくの間、ある人をさがしていた。見つかりそうで見つからないということが多々あって、しかしそれは魔人というものが気紛れで嘘つきでだらしないからだと思っていた。そこに噛んでいる者がいるとは、考えもしなかったよ」
ゼルガーダンはユリウスを睨みつけたまま黙り込んでいる。
ザシャにもう一度調べ直させた結果、エデルの居所をつかむのにあれほど苦労した原因は、ゼルガーダンだったとわかった。
積極的に工作していたのではなく、それとなく、息のかかった者にやらせていたのだが、そのせいでゼルガーダンの気配に気がつかなかった。
ゼルガーダンは自分が直接関わることは避け、エデルの扱いには口を挟まず、ただ、ユリウスの手が届きそうで届かないようにさせていたのだ。
ユリウスがエデル・フォルハイン辺境伯をさがしていることを、ゼルガーダンがいつ気づいたのかはわからない。けれどユリウスはエデルの売買に関係した者を次々に葬っていたので、調べればそれを知るのはさほど難しくはない。
嫌がらせのつもりだったのだろう。
妙なのは、ゼルガーダンがエデルを引き取ろうとしなかったことだ。ユリウスを苦しめたいのならエデルを自分の元に連れてきて、いたぶるなり殺すなりすればよかったのだ。
だが、ゼルガーダンはそうしなかった。いつも、指示しているのかしていないのかわからない程度の距離で他の者を操っていた。
「私が怖かったのだろう? 私のものに手を出して、仕返しをされることをあなたは恐れたのだ」
だから自分が絡んでいる痕跡を消していた。
ゼルガーダンは失いたくないものがたくさんある。一方、ユリウスはエデルのためならば捨て身になってどこへでも飛び込める。
ゼルガーダンはユリウスを憎んでいたが、同時にユリウスが自分の首を取りに来ることに怯えていた。回りくどいやり方がそれを証明している。
――あまりにも、小物だ。
だが彼が臆病だったおかげで、エデルは生かさず殺さずといった判断がなされ、ようやくユリウスが見つけるに至ったのだ。
「そんな妄想を言うためにわざわざ私のところまで来たと?」
ゼルガーダンはあくまでしらを切り通すつもりらしい。ユリウスは笑みを深めた。
「ご安心を、ゼルガーダン卿。私は怒ってなどいない。大切なものは手に入った。あなたを『許して』やろう」
挑発に返ってきたのは、怒りのこもった沈黙だった。殺意がぎらついているものの、実際ここでそれをぶつけるつもりはないようだ。向こうとしても、ここで収拾のつかない喧嘩を始めるのは益がないのだろう。
「ゼルガーダン卿。私はあなたとは違う。あなたはその持ち物の大半を継いだだけだ。私は自分で築いた。いつ手放しても構わないからあなたの気持ちはわからないな。ましてや……」
ユリウスは首を傾げて言い放った。
「世話になった叔父をこっそり殺してでも、自分の地位を盤石なものにしようとする気持ちは、理解できない」
耳に痛いくらいの静寂が落ちた。
ゼルガーダンは血走った目を見開き、ユリウスではなくあらぬ方を見つめている。
本人からの説明を待つほど暇でもないユリウスは、自分が得た情報を話し始めた。
「あなたがツァイテールを保護した理由はそれだ。ツァイテールはあなたと会う前に別の魔人と組んで、気づかれないようひっそりと魔人を死に追いやる方法を考えていた。それに必要だったのが、人間の奴隷だ」
ゼルガーダンの眉がぴくりと動いて反応する。
「人間の体の内側に特殊な紋をつけ、主人である魔人に移すような仕組みをつくる。これで魔人は体を壊すわけだ。一見するとよくわからない病気にかかったとしか思えない。紋を運んだ人間は魔人ではないから同じような症状は見せないし、人間が運んできたとは思わないだろう」
その仕組みに思い至ったきっかけは、エデルの記憶の中にあるツァイテールの言葉にあった。
――魔人のやつらが、伝染病にかかることは、ないのか。
これは魔族と人間の戦争中に、痺れをきらしたツァイテールが言ったことだった。
ツァイテールは伝染病や病といったものに少々詳しかった。といっても特に専門家だったというのではなく、彼は伝染病の研究に熱心に出資していたのだ。
己が病に怯えていたという理由や、大衆の人気取りが目的でもあったが、そのお陰で実際彼は評判が上がった時期があった。
出資しているのだから研究者から説明を聞く機会があり、一時期流行った伝染病はネズミなどの小動物が媒介しているとツァイテールは知ったのだ。
巧妙な呪術を紋に組み込み、魔人にだけ効果がある病のようなものを作り出した。それを運んだ人間に影響はないので、経路はわかりにくい。
ゼルガーダンがユリウスに奴隷はいらないかと聞いてきたのもこれが理由だ。エデルは強力な淫紋がついており、他の効果は付与できないので使えなかったのである。
他にもツァイテールから奴隷を買った魔人がいたから紋を調べてみたら、やはり呪いが付与されていた。こういった、こそこそとした回りくどいやり方を魔人は好まなかったので、今まで試した者はいなかっただろう。ツァイテールの入れ知恵に違いない。
ゼルガーダンは同じ一族である叔父のハルファースから期待されて地位を受け継いだ。世襲は魔人社会ではさほど一般的でもないが、古い家であればよくあることだ。
ハルファースは現役を引退しており、ただでさえ弱っていた。だからゼルガーダンが焦る必要などなかったはずなのだが、やはり叔父が怖かったのだろう。圧倒的な彼の存在と、未だ消えることのない影響力が。
「理解できない」
ユリウスは笑みを消さずに、繰り返した。
叔父を殺そうとしたことを訝っているのではない。
「消したいのなら、そんないやらしい、まだるっこしいことはせず、直接行って手を下せばいいじゃないか」
魔人達が暮らすのは弱肉強食の世界であるから、親も師も子供も、脅威であれば殺す。そうやってのしあがっていくのは当たり前だ。
だが、ゼルガーダンは潜在的な能力はかなりなものだがお上品に育ったためか、やや臆病で慎重派なのだろう。
みっともないことこの上ない、とユリウスは蔑んだ。
「……それで?」
ゼルガーダンも青ざめたまま、やっと口の端を上げた。
ハルファースはもう長くないという事実が、彼を慰めているのだろう。ひと月ほど前、かなり容態は悪いと聞いているはずだ。
「誰にでも過ちはある。ゼルガーダン卿。あなたは自分の叔父にしたことを――方法を、悔やむべきだろうな。魔人であるなら。今度は正々堂々立ち向かうがいい。別に、闇討ちでもいいが。他種族を使うなんて魔族の恥だ」
ゼルガーダンの耳には若造の侮蔑の言葉はほとんど入っていないらしかった。ある部分が引っかかったらしい。
「今度?」
「ああ、今度だ。ハルファース卿はすっかり回復されたのだからな。お身内が元気になられて何よりだ」
ゼルガーダンは机の端を握ったまま、しばらく絶句していた。
「……嘘を吐かすな」
驚愕の表情があまりに可笑しくて、ユリウスは小さく笑い声をもらした。
「嘘ではない。治したのはうちの者だ。うちには医者のようなことができる者がいて、ハルファース卿のもとへ連れて行かせてもらった。かなり重い症状だったが、回復したよ。さすがハルファース卿はお強い方で、ほとんど数日で良くなられた。歩けるどころか、もう走れるのではないかな? あの方が走られるのかどうかは知らないが」
原因である紋を消すと、あっさりと復活した。ハルファース卿は起き上がれるようになると、お気に入りの奴隷と涼しい顔で散歩をしていた。面やつれもしておらず、寝込んでいたなど嘘のようだ。
額に脂汗を浮かべているゼルガーダンに近づいて、ユリウスは顔を近づけると言った。
「安心されるがいい。ハルファース卿には告げ口はしていない。ただうちの者が優秀で心得があったため、治療に効果があったのだろう、と説明しておいた」
「何が目的だ」
歯を食いしばり、ゼルガーダンは言葉を押し出した。ユリウスとハルファースはこれまで何の関係も持っていなかった。ユリウスがハルファースを助け、真相をハルファースに告げないとすれば、ゼルガーダンに何か取り引きを持ちかけるためとしか考えられないのだ。
「ツァイテールとは手を切ってもらう。今この瞬間から。その方があなたにとってもいいだろう? もしいつかハルファース卿の病のことで怪しまれても、ツァイテールが勝手にやったと、罪をなすりつければいい」
ツァイテールの後ろ盾はゼルガーダンだけだ。それを切り離せばツァイテールは孤立無援となる。
「それだけか」
ユリウスは、ふう、と小さくため息をついた。
「二度とつまらない真似はしないでいただこう。私はあなたと縄張り争いをするつもりはない。権力の拡大なんて興味がないんだ。あなたが手を出さなければ、こちらもあなたに手は出さない。だから、もう関わらないでもらいたい」
これ以上鬱陶しい展開になるのはうんざりだ。これで言いたいことは言ったので、口を閉じた。
ゼルガーダンは猜疑心のこもった眼差しをユリウスに向けている。
今ここで自分の首を取るつもりではないのだろうか。そう疑っているのかもしれない。
ユリウスはゼルガーダンの工作のせいでエデルを保護するのがかなり遅れた。仕返しをするのが当然だと思うのだろう。
「心配されなくても、私はこのまま帰る。ゼルガーダン卿、私があなたを殺さないのは……」
調査の結果、様々な事実が判明した後。話を聞いたエデルが、ユリウスの襟をつかんでそっと引き寄せ、耳打ちをしたのを思い出す。
――ユリウス。ゼルガーダン卿を殺さなくていい。その男は……。
「殺す価値もないからだ」
あくどい笑みを浮かべるユリウスに大して、ゼルガーダンは唖然としている。
――わざわざ殺す価値もないよ。そんな小物は放っておけ。今までのことより、これからが大切じゃないか。そうだろう?
そう。用が済んだらこんな男は忘れるに限るのだ。
何より、眼中にないという意思表示が、いたくゼルガーダンの自尊心を傷つけるだろう。それだけで多少の溜飲は下がる。
許して、殺さず、忘れてしまう。これがこの男にとって最大の屈辱となるのだ。
こうして脅して立場をわからせておけば、ゼルガーダンはエデルの願いも無視できないはずだった。
簡単に別れの挨拶を述べると、硬直しているゼルガーダンに笑いかけ、ユリウスは颯爽と部屋を後にした。
応援ありがとうございます!
5
お気に入りに追加
173
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる