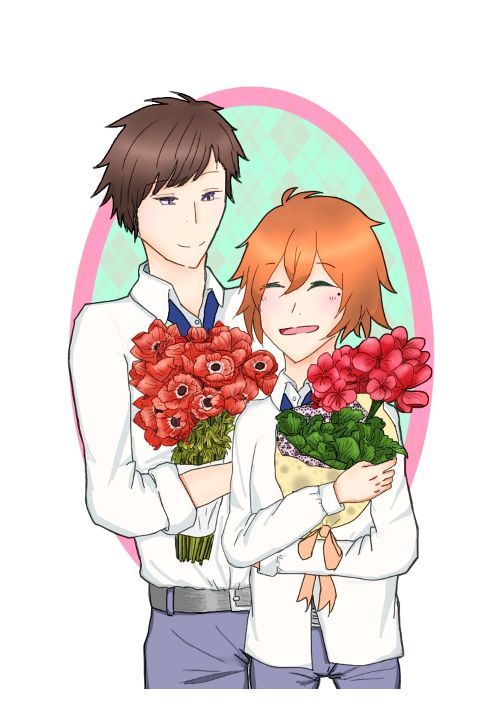87 / 95
前篇:夢の通ひ路
第四十一話 其の三
しおりを挟む
思わず声に出てしまい、身体が強張った。宮を起こしてしまったかも……
少しだけ視線を上げてみれば、やはり宮の目は開いていた。それも、うっすらではなく、しっかりと。今目覚めたという顔ではない。
「また、難しいお顔をしていますね」
「……起こしてしまい、申し訳ありません」
「謝ることはありませんよ。実は少し前から、姫を見つめていました。姫は、全くお気づきになりませんでしたが」
薄暗闇の中、にっこりといつも通りきれいに笑って答えた宮に、気まずさが募る。
おそらく私は、百面相をしていたに違いない。夢中であれこれと考える様子を、宮は何も言わずにずっと観察していたということだ。
……恥ずかしすぎる。無意識に、他の独り言なんて言ってなければいいけれど。
「大丈夫ですよ、姫は何も言っていません」
安心してください、と言わんばかりのフォローだが、考えていることをここまで正確に読まれているのもどうかと思うのだ。そんなに私は分かりやすい顔をしていたのだろうか。否定できないことが悲しい。
三の君の夢に泣き、こめかみを濡らした涙は既に乾いてはいたが、跡が残っていたのだろう。それに気が付いた宮は、少しだけ目を細めた。私を案じている視線だった。
「また恐ろしい夢でも見たのですか」
「……恐ろしいというよりも、悲しいものでした」
「そうでしたか」
それはどんな夢だったのか、と宮は問わなかった。ただ、私の腰の辺りに置いてあった腕に少しだけ力がこもった。
二人とも目が冴えてしまい、すぐには寝付けそうにもない。虫の鳴き声だけが聞こえる静まり返った夜半は、まるでそこだけ切り取られた空間のようだった。ああ、今がいいかもしれないと、ふと思った。
宮には、早めに話しておかなくてはいけない。昼間の小梅との会話を思い出し、私は静かに口を開いた。
「宮様。宮様にお伝えしておかなくてはならぬことがあります」
「何でしょうか」
「私が宮様とこうして一緒にいられる時間は、おそらくさほど多くは残されておりません。私は先日、宮様にこの頃は夢見が悪いと申し上げましたが、それはこの先の私の消失と関係しております」
「姫? ……どういうことでしょうか」
宮は思わずといったように身体を起こした。私も同じように起き、宮をまっすぐに見つめた。
向かい合った彼の瞳は、とても不安げだった。いつもの余裕や自信はそこにはない。ただ、私の次の言葉を待っている。
「宮様と結婚する少し前から、私はよく、ある夢を見るようになりました。この頃はその回数もずっと増え、これまでは夜のみだったものが、昼間にも見たり、同じ夜に二度、三度と見たり…… 睡魔の強さを感じて抗えず眠ることもあれば、突然意識を失うように眠ってしまうこともございます。自分では、どうすることもできません」
「あなたはずっと悪夢を見ていると…… そういうことなのですか?」
「悪夢、ではありませんわ。悪夢とは似て非なるものです。私がこのことを宮様に隠さずお伝えしたのは、この先、宮様の前でもそのような姿を見せてしまうことがあるだろうと思ったからです。けれど、それは病や物の怪のせいではございません。ですから、どうか見苦しい場面を見て驚いたとしても大事にはせず、父母には伏せていただきたくお願い申し上げます」
「それは……分かりました。あなたがそう言うのならば」
自分でもよく分かっている。小梅に対しても、宮に対しても、余りにも一方的な言い分だと。でも、こう話す以外にどう伝えればいいのか、私には分からなかった。
色々と言いたいこと、聞きたいこともあるはずなのに、宮は全てを呑み込んで頷いた。何を言っているのか、もっと詳しく話せないのかと言われても仕方のない内容でも、一言も不満は言わない。それらをぶつけたところで、私が答えに困ること、そしてどれほど問われても話すつもりがないことを分かっているからだろう。
宮は、とても心の強い人なのだと思う。いつかの私のように不安を吐露することもない。けれど、彼に負担をかけていることは事実だ。どうしたら、それを少しでも取り除くことができるのか。
宮の手をそっと取り、両手で握りしめた。今の私にできることといったら、それくらいしかなかった。優しく握り返してくれた温もりに、心がじわりとする。
「ありがとうございます。このことは、宮様の他、女房の小梅にも申し伝えております。もしも何かお困りの際は、小梅をお呼びください」
「……ええ」
「先の続きですが…… 夢は、以前の人格である三の君の記憶のようなのです」
宮が少しだけ目を見開いた。
記憶が戻れば私は消失する――宮にはそう伝えているのだから、当然だ。
「夢を見る時間が増えれば増えるほど、私の存在も徐々に薄れてきております。自分のことですから、分かるのです。この先、私が消える時はそう遠くありません。すべての記憶を夢として見たあとには、きっと私はいないのでしょう」
これは、嘘ではなく直感だった。
薄々分かってはいた。このまま、三の君の記憶の夢を永遠に見るわけではないことを。おそらく、夢の終わりが近々くるはずだ。それが私が現代へ戻れる唯一のタイミングのような気がしている。
見る夢が時系列通りではないと言っても、ここ最近のものに限ればだが、話の流れは繋がっている。それも、何気ない日々を見ているのではなく、三の君の心に大きな動きがあった時だけを見ているのだ。繰り返し見ている夢を除けば、確かに夢は現在へ近づいている。おそらく、あと数回程度で三の君が病へ倒れる場面へつながるはず。
あくまでただの勘で、これといって理由があるわけではない。けれど、先ほどまで考えていたことも、後押ししていた。間違いなくその時はすぐそこまで来ている。言葉ではうまく言い表せないけれど、もうすぐなのだと五感が訴えているような――そんな感覚といえばいいのか。
天狗は、私と三の君が話せる機会があるとしたら、ただの一度きりだと言った。だけど、これまで一度も彼女と相見えてはいない。おそらく、私達の魂があるべき場所へ帰る時が、その機会だ。もうそれしか考えられない。
空間の歪みに消え去る方が先か、三の君と会う方が先か。
あとはただ、運命に従うだけだ。
目覚めた時から、もうずっと、暗闇の中を手探りで進んでいるような気持ちが消えなかった。
宮や小梅、雛菊、様変わりしてしまった三の君である私を気にかけてくれた父母、邸の者達……沢山の人と優しさに囲まれていても、私は一人だった。
平安といういるはずではない時代、場所で、天狗の助言を頼りに今日まで来た。でも、それももうすぐ終わる。
三の君の記憶の断片、私達二人の因果関係――、一つずつが確かに繋がっている。すべてが結ばれ一本の糸になったときは、宮に別れを告げるときだ。
「貴女を繋ぎとめる術が、私にあればよかった」
宮の言葉だった。
一言そう言い、ぎこちなく微笑んだ宮は、「分かりました」と続けた。
「初めから、貴女はすべてを話してくれていました。こうなることを承知した上での結婚です。ですから、私は何も言えませんし、言いません。ただ、貴女と、貴女がその時を迎える瞬間まで夫婦として共に過ごすだけです」
私も、宮のように笑えただろうか。
随分と固く感じられた頬を動かそうとはしたけれど、上手くいっているかも分からない。宮と一緒にいる時は笑顔でいたいと願っても、涙をこらえるのが精一杯だ。私はこんなにも涙もろくなかったはずなのに、気が付けば宮の前ではいつだって目を潤ませてしまう。
「私も、一つだけ貴女に嘘をついていました」
「嘘?」
「褥を共にしないのは、貴女の心身を案じているからなのだとお話ししましたね。ですが、あれは私のためでもあったのですよ」
言葉の意味が分からない。首をかしげた私に、宮は苦笑いを浮かべている。
「貴女に触れてしまえば、歯止めが効かなくなる。ずっと貴女を私の傍に置いておきたい、その為ならばどのような手段でも選ばない――いつか自分がそのようになるのが分かるのです。姫の記憶が戻らなければ、貴女はずっと存在していられるのでしょう。であれば、姫の記憶などいらぬと」
「それは……」
「ええ、貴女がそれを望まぬことは分かっています。とても傲慢な考えですね。私も自分にこのような一面があったことに驚いています」
「……宮様」
「ですが、貴女の望まぬことはしたくない。我を通して、貴女を傷つけるたくなどありません。せめて貴女の前でだけは、こうして強がらせて下さい」
何か言おうとして、結局何も言えず口ごもった私を、宮はただ、もう一度抱きしめた。どこにも行かないでと、そう言われているような気がした。
彼の腕の中があまりにも優しいから、また涙をこぼしてしまいそうになる。私はこの先、どれほどこの人に我慢をさせ、辛い思いをさせるのか。
「私は、今日一日を、奇跡と思い過ごしています。姫が今日も私の腕に中にいてくれた、と。それで……それだけでいいのです。他には何も望みません」
こらえきれず溢れた涙が、宮の衣に吸い込まれて小さな染みを作った。
夫婦であれば当然の毎日を、私が相手であるが故にこの人に「奇跡」と言わせてしまっていることが、とても悲しかった。これがこの時代に生きる他の女性であれば、ここまで背負わせることもなかったのに。新婚という、なんの曇りも憂いもない幸せを感じる時間だったはずなのに。
「契らずとも、貴女は確かに私の妻です。それだけは忘れないでいてほしい」
「はい……」
「私達は夫婦ですよ」
「は、い……」
「どうして泣くのです? 私は、幸せです」
「私も、幸せです……」
こんな人にはきっともう出会えない。私をここまで理解して、想ってくれる人なんて。
この人の傍にいられるのは、あとどれくらいなのだろう。
宮とこうして過ごす時間を幸せだと感じるほど、先に待ち受けているものが別れしかないのだと突きつけられているようで胸が痛む。
いつの日か、宮を想い涙した今日のことでさえ、思い出の一部として静かに受け止める日がくるのだろうか。それとも、現代へ戻るとすべて忘れてしまうのか。
いずれにしろ、そんな先のことは今は考えられなかった。
その時が来たら、宮一人をこの時代に残し自分だけが現代へ還る――本当に? そんなことができる?
ここまで私のことを想い、大切にしてくれているこの人を、一人にできるの? 私は、こうなることまでを考えなくてはいけなかったのではないの?
あの日の決断は、あれでよかったのか。
そう思い始める直前に、宮の声が私の思考を遮断した。
「私なら大丈夫です。だって貴女はかぐや姫ですから。出逢った時から、天へ還る運命だったのでしょう。一日でも長く、貴女が私の元にいてくれるようにと月に願わねばなりませんね」
冗談めかして彼が笑う。だから、もう泣かないで、と。
「触れたくても触れられぬ、ずっと貴女は、私のかぐや姫のまま」
ごめんなさい、と口には出せなかった。全て理解し、今が幸せだからと笑ってくれた宮に、それだけは言ってはいけないような気がした。言ったところで楽になるのは私だけだ。懺悔のような謝罪は喉の奥に押し込めて、私は微笑んだ。それしかできることがなかった。
「いつか、その時までは共にいましょう」
口づけて、宮はまた、私を一層強く抱きしめた。
私を包む香りに、違う思いで胸が締め付けられて、瞼を下ろすとまた一筋涙が流れていく。
ただ、この人だけは幸せに、私が去った後も幸せでいてほしい。
彼は私の時間を積み重ねて残したいと言ってくれたけど、私が還るときは、私のことをすべて消し去ってほしい。悲しみも苦しみも、何一つ残さずに。
その分、全てを私が引き受けるから。淋しさも、苦しさも、全部。
だから、どうか。
ただ、この人だけは。
そう願った夜だった。
少しだけ視線を上げてみれば、やはり宮の目は開いていた。それも、うっすらではなく、しっかりと。今目覚めたという顔ではない。
「また、難しいお顔をしていますね」
「……起こしてしまい、申し訳ありません」
「謝ることはありませんよ。実は少し前から、姫を見つめていました。姫は、全くお気づきになりませんでしたが」
薄暗闇の中、にっこりといつも通りきれいに笑って答えた宮に、気まずさが募る。
おそらく私は、百面相をしていたに違いない。夢中であれこれと考える様子を、宮は何も言わずにずっと観察していたということだ。
……恥ずかしすぎる。無意識に、他の独り言なんて言ってなければいいけれど。
「大丈夫ですよ、姫は何も言っていません」
安心してください、と言わんばかりのフォローだが、考えていることをここまで正確に読まれているのもどうかと思うのだ。そんなに私は分かりやすい顔をしていたのだろうか。否定できないことが悲しい。
三の君の夢に泣き、こめかみを濡らした涙は既に乾いてはいたが、跡が残っていたのだろう。それに気が付いた宮は、少しだけ目を細めた。私を案じている視線だった。
「また恐ろしい夢でも見たのですか」
「……恐ろしいというよりも、悲しいものでした」
「そうでしたか」
それはどんな夢だったのか、と宮は問わなかった。ただ、私の腰の辺りに置いてあった腕に少しだけ力がこもった。
二人とも目が冴えてしまい、すぐには寝付けそうにもない。虫の鳴き声だけが聞こえる静まり返った夜半は、まるでそこだけ切り取られた空間のようだった。ああ、今がいいかもしれないと、ふと思った。
宮には、早めに話しておかなくてはいけない。昼間の小梅との会話を思い出し、私は静かに口を開いた。
「宮様。宮様にお伝えしておかなくてはならぬことがあります」
「何でしょうか」
「私が宮様とこうして一緒にいられる時間は、おそらくさほど多くは残されておりません。私は先日、宮様にこの頃は夢見が悪いと申し上げましたが、それはこの先の私の消失と関係しております」
「姫? ……どういうことでしょうか」
宮は思わずといったように身体を起こした。私も同じように起き、宮をまっすぐに見つめた。
向かい合った彼の瞳は、とても不安げだった。いつもの余裕や自信はそこにはない。ただ、私の次の言葉を待っている。
「宮様と結婚する少し前から、私はよく、ある夢を見るようになりました。この頃はその回数もずっと増え、これまでは夜のみだったものが、昼間にも見たり、同じ夜に二度、三度と見たり…… 睡魔の強さを感じて抗えず眠ることもあれば、突然意識を失うように眠ってしまうこともございます。自分では、どうすることもできません」
「あなたはずっと悪夢を見ていると…… そういうことなのですか?」
「悪夢、ではありませんわ。悪夢とは似て非なるものです。私がこのことを宮様に隠さずお伝えしたのは、この先、宮様の前でもそのような姿を見せてしまうことがあるだろうと思ったからです。けれど、それは病や物の怪のせいではございません。ですから、どうか見苦しい場面を見て驚いたとしても大事にはせず、父母には伏せていただきたくお願い申し上げます」
「それは……分かりました。あなたがそう言うのならば」
自分でもよく分かっている。小梅に対しても、宮に対しても、余りにも一方的な言い分だと。でも、こう話す以外にどう伝えればいいのか、私には分からなかった。
色々と言いたいこと、聞きたいこともあるはずなのに、宮は全てを呑み込んで頷いた。何を言っているのか、もっと詳しく話せないのかと言われても仕方のない内容でも、一言も不満は言わない。それらをぶつけたところで、私が答えに困ること、そしてどれほど問われても話すつもりがないことを分かっているからだろう。
宮は、とても心の強い人なのだと思う。いつかの私のように不安を吐露することもない。けれど、彼に負担をかけていることは事実だ。どうしたら、それを少しでも取り除くことができるのか。
宮の手をそっと取り、両手で握りしめた。今の私にできることといったら、それくらいしかなかった。優しく握り返してくれた温もりに、心がじわりとする。
「ありがとうございます。このことは、宮様の他、女房の小梅にも申し伝えております。もしも何かお困りの際は、小梅をお呼びください」
「……ええ」
「先の続きですが…… 夢は、以前の人格である三の君の記憶のようなのです」
宮が少しだけ目を見開いた。
記憶が戻れば私は消失する――宮にはそう伝えているのだから、当然だ。
「夢を見る時間が増えれば増えるほど、私の存在も徐々に薄れてきております。自分のことですから、分かるのです。この先、私が消える時はそう遠くありません。すべての記憶を夢として見たあとには、きっと私はいないのでしょう」
これは、嘘ではなく直感だった。
薄々分かってはいた。このまま、三の君の記憶の夢を永遠に見るわけではないことを。おそらく、夢の終わりが近々くるはずだ。それが私が現代へ戻れる唯一のタイミングのような気がしている。
見る夢が時系列通りではないと言っても、ここ最近のものに限ればだが、話の流れは繋がっている。それも、何気ない日々を見ているのではなく、三の君の心に大きな動きがあった時だけを見ているのだ。繰り返し見ている夢を除けば、確かに夢は現在へ近づいている。おそらく、あと数回程度で三の君が病へ倒れる場面へつながるはず。
あくまでただの勘で、これといって理由があるわけではない。けれど、先ほどまで考えていたことも、後押ししていた。間違いなくその時はすぐそこまで来ている。言葉ではうまく言い表せないけれど、もうすぐなのだと五感が訴えているような――そんな感覚といえばいいのか。
天狗は、私と三の君が話せる機会があるとしたら、ただの一度きりだと言った。だけど、これまで一度も彼女と相見えてはいない。おそらく、私達の魂があるべき場所へ帰る時が、その機会だ。もうそれしか考えられない。
空間の歪みに消え去る方が先か、三の君と会う方が先か。
あとはただ、運命に従うだけだ。
目覚めた時から、もうずっと、暗闇の中を手探りで進んでいるような気持ちが消えなかった。
宮や小梅、雛菊、様変わりしてしまった三の君である私を気にかけてくれた父母、邸の者達……沢山の人と優しさに囲まれていても、私は一人だった。
平安といういるはずではない時代、場所で、天狗の助言を頼りに今日まで来た。でも、それももうすぐ終わる。
三の君の記憶の断片、私達二人の因果関係――、一つずつが確かに繋がっている。すべてが結ばれ一本の糸になったときは、宮に別れを告げるときだ。
「貴女を繋ぎとめる術が、私にあればよかった」
宮の言葉だった。
一言そう言い、ぎこちなく微笑んだ宮は、「分かりました」と続けた。
「初めから、貴女はすべてを話してくれていました。こうなることを承知した上での結婚です。ですから、私は何も言えませんし、言いません。ただ、貴女と、貴女がその時を迎える瞬間まで夫婦として共に過ごすだけです」
私も、宮のように笑えただろうか。
随分と固く感じられた頬を動かそうとはしたけれど、上手くいっているかも分からない。宮と一緒にいる時は笑顔でいたいと願っても、涙をこらえるのが精一杯だ。私はこんなにも涙もろくなかったはずなのに、気が付けば宮の前ではいつだって目を潤ませてしまう。
「私も、一つだけ貴女に嘘をついていました」
「嘘?」
「褥を共にしないのは、貴女の心身を案じているからなのだとお話ししましたね。ですが、あれは私のためでもあったのですよ」
言葉の意味が分からない。首をかしげた私に、宮は苦笑いを浮かべている。
「貴女に触れてしまえば、歯止めが効かなくなる。ずっと貴女を私の傍に置いておきたい、その為ならばどのような手段でも選ばない――いつか自分がそのようになるのが分かるのです。姫の記憶が戻らなければ、貴女はずっと存在していられるのでしょう。であれば、姫の記憶などいらぬと」
「それは……」
「ええ、貴女がそれを望まぬことは分かっています。とても傲慢な考えですね。私も自分にこのような一面があったことに驚いています」
「……宮様」
「ですが、貴女の望まぬことはしたくない。我を通して、貴女を傷つけるたくなどありません。せめて貴女の前でだけは、こうして強がらせて下さい」
何か言おうとして、結局何も言えず口ごもった私を、宮はただ、もう一度抱きしめた。どこにも行かないでと、そう言われているような気がした。
彼の腕の中があまりにも優しいから、また涙をこぼしてしまいそうになる。私はこの先、どれほどこの人に我慢をさせ、辛い思いをさせるのか。
「私は、今日一日を、奇跡と思い過ごしています。姫が今日も私の腕に中にいてくれた、と。それで……それだけでいいのです。他には何も望みません」
こらえきれず溢れた涙が、宮の衣に吸い込まれて小さな染みを作った。
夫婦であれば当然の毎日を、私が相手であるが故にこの人に「奇跡」と言わせてしまっていることが、とても悲しかった。これがこの時代に生きる他の女性であれば、ここまで背負わせることもなかったのに。新婚という、なんの曇りも憂いもない幸せを感じる時間だったはずなのに。
「契らずとも、貴女は確かに私の妻です。それだけは忘れないでいてほしい」
「はい……」
「私達は夫婦ですよ」
「は、い……」
「どうして泣くのです? 私は、幸せです」
「私も、幸せです……」
こんな人にはきっともう出会えない。私をここまで理解して、想ってくれる人なんて。
この人の傍にいられるのは、あとどれくらいなのだろう。
宮とこうして過ごす時間を幸せだと感じるほど、先に待ち受けているものが別れしかないのだと突きつけられているようで胸が痛む。
いつの日か、宮を想い涙した今日のことでさえ、思い出の一部として静かに受け止める日がくるのだろうか。それとも、現代へ戻るとすべて忘れてしまうのか。
いずれにしろ、そんな先のことは今は考えられなかった。
その時が来たら、宮一人をこの時代に残し自分だけが現代へ還る――本当に? そんなことができる?
ここまで私のことを想い、大切にしてくれているこの人を、一人にできるの? 私は、こうなることまでを考えなくてはいけなかったのではないの?
あの日の決断は、あれでよかったのか。
そう思い始める直前に、宮の声が私の思考を遮断した。
「私なら大丈夫です。だって貴女はかぐや姫ですから。出逢った時から、天へ還る運命だったのでしょう。一日でも長く、貴女が私の元にいてくれるようにと月に願わねばなりませんね」
冗談めかして彼が笑う。だから、もう泣かないで、と。
「触れたくても触れられぬ、ずっと貴女は、私のかぐや姫のまま」
ごめんなさい、と口には出せなかった。全て理解し、今が幸せだからと笑ってくれた宮に、それだけは言ってはいけないような気がした。言ったところで楽になるのは私だけだ。懺悔のような謝罪は喉の奥に押し込めて、私は微笑んだ。それしかできることがなかった。
「いつか、その時までは共にいましょう」
口づけて、宮はまた、私を一層強く抱きしめた。
私を包む香りに、違う思いで胸が締め付けられて、瞼を下ろすとまた一筋涙が流れていく。
ただ、この人だけは幸せに、私が去った後も幸せでいてほしい。
彼は私の時間を積み重ねて残したいと言ってくれたけど、私が還るときは、私のことをすべて消し去ってほしい。悲しみも苦しみも、何一つ残さずに。
その分、全てを私が引き受けるから。淋しさも、苦しさも、全部。
だから、どうか。
ただ、この人だけは。
そう願った夜だった。
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
68
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる