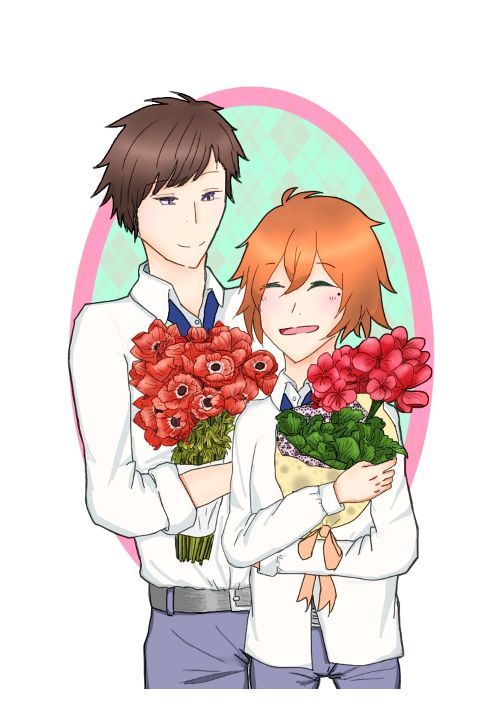89 / 95
前篇:夢の通ひ路
第四十二話 其の二
しおりを挟む
◆◆◆
新月が好きだ、と思う。
白い月光が隠れた暗闇は、私の涙も醜い心も、お兄様への想いも、全て隠してくれるような気がするから。
虫の鳴き声も聞こえない、静かな夜だった。澄んだ冬の冷たい空気が心地よくて、ただぼんやりと佇んでいた。不思議なことに、手足の指先は氷のように冷えているのに、寒さは感じない。
「姫様、お身体を冷やしてはいけませんわ」
小梅が、「わたくしが目を離しますと、姫様はすぐにご無理をなさる」と、小言を言いながら格子を下ろしていく。夜風に当たっていた私のことを彼女は随分と怒っているようだったが、無理もない。私はここ数日間、病のせいで熱にうなされ、ろくに起き上がることもできずにいたのだから。
「すぐに白湯をお持ちいたします」
言葉通り、本当にすぐに白湯を持ってきた小梅は私にそれを差し出した。大人しく受け取り、一口すすると、口の中にじわりと温かさが広がっていく。けれど、一向に身体が温まるような気はしなかった。
「病が悪化したらどうなさるおつもりだったのです」
「大丈夫よ」
「姫様のおっしゃることは信用できませんわ」
「随分なことね」
苦笑いをするしかない。小梅のいうことは最もで、私の「大丈夫」には何ら信ぴょう性がなかった。病に侵され、日々脂汗を浮かべながら呼吸を荒げても、私は苦しいとは一言も言わなかった。むしろ、「大丈夫」と口癖のように言っているのだ。しかし小梅からしたら、全く正反対に受け取っているのだろう。
たとえ素直に辛苦を吐き出したところで、私の身体が回復しなければ、余計に小梅の心に負荷をかけるだけ。何の意味もないではないか。嘆きや弱音は胸に留め、口にしようとは一切思わなかった。いずれにしろ、小梅は私を心配してしまう性質なのだから。
「さあ姫様、お休みになってください」
「分かったわ、小梅の小言は長いものね。大人しく言う通りにするわ」
「まあ、姫様ったら!」
小梅がわざと大げさに反応する。私はくすくすと小さく笑いながら伏せて衾を掛けた。
指先はまだ固く冷えたまま、まるで自分のものではないように白い。それを取り、両手で温めるように握りしめた小梅の顔が一瞬だけ歪んだ。まるで、死人のような冷たさだと思ったのだろう。
「これほどになるまで外に出られるなどっ……」
「ほんの一時よ。元々冷えていたんだわ」
気にしないでと微笑んだが、小梅の表情は和らぐことはなかった。私の手は、どれほど彼女がさすっても、少しも温もりは戻ってこない。
多分、きっと、そう。私はもうすぐ、この生を終えるのだろう。かろうじて生きながらえているだけで、死人と大差はない。
現世にしがみ付きたいなどとは露ほどにも思わない。むしろ、できることなら早くお兄様の元へ行きたいと願っている。生きていてよかったと思えたことなど、この数年で数えるほどしかなかった。
何のために自分は存在しているのか。いつもその答えを求め続けて、結局見つからずに今日を迎え――ようやく、それも終わりになるのだと、どこか安堵している自分がいる。私はもう、全てを終わりにしたかった。
「姫様……」
「どうしたの」
言いにくそうに何度か唇を震わせ、やがて意を決したと言わんばかりに小梅は言った。
彼女のその表情を見ているだけで、何を言うのかは聞かなくても分かっていた。これまでに、同じ進言を幾度となく聞いてきたからだ。
「差し出がましいことと十分承知の上で申し上げます。……どうか、有明中将様と、今一度お会いになって下さい」
「必要ないわ」
もう二度と会わない。そう決めたのだから。
「せめて、こちらだけでもお目通しいただけませんか」
小梅の出した文は、お兄様からの文使いから預かったものだろう。
私の答えはいつも同じ、首を横に振るだけだ。固く結ばれたその文を開くことはない。
お兄様へ離別を申し出てから、随分と時間が経っていた。
あれから、お兄様には一度もお会いしていない。ただの一度も。
日を空けず届くお兄様の文も、全て捨てた。燃してしまったものもある。読めばあの日のことをなかったことにしてしまいたくなると分かっていた。だから、お兄様の全てを私の生活から消して生きてきた。
小梅はもちろんのこと、お父様やお母様までもが私を諫めようとなさったけれど、その言葉を聞く気にはなれなかった。どれほどの覚悟でお兄様にあれほどひどいことを申し上げたか――それを何事もなかったように白紙に戻せと言うのは無理な話だった。
一向に首を縦に振らぬ私に呆れ、諦め、やがて、誰もその話には触れなくなった。ただ一人、あの場に同席していた小梅だけは、未だにこうしてお兄様の名を私の前で呼ぶが、その数も随分と少なくはなっている。
私はもう、あのような身を切る思いはしたくない。あの日の、お兄様の悲し気な声が、今でも耳に張り付いて離れない。夢にまで見るほどなのに。どうして、もう一度ただの妹に戻れるだろうか。
距離を置いてお兄様への恋を忘れることができたのならば、まだよかった。それができないから、未だにお兄様に会おうとは思えないのだ。
お兄様の好きな香の香り、花の色、恋の歌まで、全部……なぜ、この胸は一つ残らず大事にしまい込み、捨てることができないのだろう。
不調という形で変化が現れたのは、身体の方だった。
お兄様を遠ざけたあの日以来、私の身体は弱っていく一方だった。そんな中でかかった流行病で床についたことをきっかけに、起き上がることもままならず、そうしている間に、気が付けば四季は次々と移ろっていった。春夏秋冬の美しさを愛でる余裕はなく、この目には何もかもが色を失い、褪せて見えた。
お父様、お母様が私をお諫めにならなくなったのは、この病のせいもあるのだろう。日ごと弱る娘の姿を目の当たりにし、私を気遣う言葉以外は口にできなくなったのだ。それほどまでに、私の姿は様変わりしていった。髪の艶は消え、肌は青白く、身体の芯から冷えている。ただ、死を待ち、息をしているだけの存在に違いなかった。
小梅が震えながらさすり続ける私の手は、自分でも驚くほど痩せ細っていた。そういえば、まともに食事を摂ったのはいつだっただろう。
「ねぇ、小梅……これから私が話すことは、私の独り言よ。だからあなたは、何も聞いていない。そういうことにしてちょうだい」
「姫様……?」
「私は、お兄様が、私のことを憎み嫌って下さればいいと思っているの」
「中将様が、姫様を憎むなどあるはずがございませんわ! あれ以来、お見舞いの文も絶えず届き、姫様がお会いにならぬだけで、こちらへもいらっしゃっているのですよ? 姫様が、ただ一言許すと、そうおっしゃって下されば――」
「独り言に返事をしてはだめよ。……優しい思い出というものは、残された人たちを苦しめる。だから私は、お兄様にそういうものを残したくないの」
私は、よく知っている。亡くなられた一番上のお兄様が、私にとってそうだった。
思い出すだけで心が温まるような――そんな記憶は、ともすれば、故人への強い未練へと変わる。そしていつまでも、そこに囚われてしまう。私はお兄様が居たからこうして今、息をしているけれど、あのまま、底なし沼のような悲しみへ引きずられてもおかしくはなかった。
お兄様は、私とは違う。私よりも強く、私よりも生に対して執着がある。
だから、たとえ私が死すとも私のようにはならないのだろう。けれど、心に深い傷を負うことには変わりはない。それがせめて浅くなればいいと願う。
「あんなひどいことを言った妹のことなど知らぬ」と私を忌み嫌うことで、お兄様の悲しみが薄れてしまえばいい。一番上のお兄様を喪ったあの悲しみを、もう一度お兄様に与えてはいけない。
私は最期まで、お兄様にとって悪い妹でありたい。お兄様の苦しみが、それで少しでも減るのならば。
それが、花を差し出し、私を悲しみの淵から救い出してくれたお兄様に最後にできる、私の唯一のことだった。
本当は――本当は、お兄様に謝ろうと何度も思い直した。そしてその度に、これまでのことを無駄にするのかと自分に言い聞かせてきた。
だけれど、伏せる時間が増え、いよいよ死が現実的なものとして迫ってきたときに、あれほどまで葛藤していたことが信じられないほどに迷いは消え去った。どのみち私は永くは生きられないのならば、今のままが一番良いと思ったのだ。
「そのようなやり方は間違っておりますわ、姫様。先ほども申し上げましたが、中将様はどのような姫様でも大切に思っておいでです。このままでは、行き違いがあったままだと、ずっと後悔されるに違いありませんわ。姫様は、そのような形で中将様を苦しめてもいいとおっしゃるのですか?」
小梅の指摘したことを、勿論考えなかったわけではない。むしろ、お兄様の性格を知っているからこそ、その可能性が高いことだって分かっていた。
でも、私はやはり歪んでいる。お兄様を苦しめたくないと願う一方で、お兄様の心に「後悔」という形で強く遺るのならば、それもまたいいのではないか、と。矛盾していることなど、とうに知っている。自分がおかしいことも。
恋や愛などでは決してない特別。ただの残像のようなもの。けれど、お兄様の中に他の女達とは違うものとして在り続けられる。ならば、それもまた「特別」だ。この歪み切った想いを、誰に理解してもらおうとも思わない。
「どうしたってお兄様は、私を喪えば苦しむわ」
「姫様……」
「けれど小梅、あなたはどうか最期まで私の傍にいてちょうだい……お兄様のように、あなたも遠ざけてしまえばよかったのだけれど、どうしてもできなかった。私の我儘よ、あなただけにはここにいて欲しい」
「何を当たり前のことをっ……わたくしの主は姫様だけですわ」
「ええ。私にも、もう小梅しかいないわ」
薄い涙の膜が、小梅の瞳を覆っていた。こんな醜い心を持った私のために、彼女は泣いてくれる。それがどんなに有難いことか。死を願おうとも、病の身で心細い日がなかったわけではない。冷たい私の手を握るこの温かさに、何度助けられ、温もりを分けてもらっただろうか。
「長い独り言を言ってしまったわ。もう休むわね」
静かに手を解き、小梅に背を向けた。小梅は何も言わず、嗚咽を呑み込むような音だけが聴こえた。それ以上彼女といると、私まで涙をこぼしてしまいそうだった。とうに枯れたはずだったのに。
喉に石がいくつも詰まったような重い苦しさが込み上げてくる。
小梅を、大切な彼女を、私のことに巻き込んでしまったことだけは申し訳なく、心残りだった。
私が生きている間は、小梅は私のことで手一杯だ、とても恋をするような暇はない。けれど、その先ならば――どうか私のような恋はせず、幸せに笑っていてほしい。
自分はそれを見ることができないのだということが、ひどく淋しかった。
◆◆◆
新月が好きだ、と思う。
白い月光が隠れた暗闇は、私の涙も醜い心も、お兄様への想いも、全て隠してくれるような気がするから。
虫の鳴き声も聞こえない、静かな夜だった。澄んだ冬の冷たい空気が心地よくて、ただぼんやりと佇んでいた。不思議なことに、手足の指先は氷のように冷えているのに、寒さは感じない。
「姫様、お身体を冷やしてはいけませんわ」
小梅が、「わたくしが目を離しますと、姫様はすぐにご無理をなさる」と、小言を言いながら格子を下ろしていく。夜風に当たっていた私のことを彼女は随分と怒っているようだったが、無理もない。私はここ数日間、病のせいで熱にうなされ、ろくに起き上がることもできずにいたのだから。
「すぐに白湯をお持ちいたします」
言葉通り、本当にすぐに白湯を持ってきた小梅は私にそれを差し出した。大人しく受け取り、一口すすると、口の中にじわりと温かさが広がっていく。けれど、一向に身体が温まるような気はしなかった。
「病が悪化したらどうなさるおつもりだったのです」
「大丈夫よ」
「姫様のおっしゃることは信用できませんわ」
「随分なことね」
苦笑いをするしかない。小梅のいうことは最もで、私の「大丈夫」には何ら信ぴょう性がなかった。病に侵され、日々脂汗を浮かべながら呼吸を荒げても、私は苦しいとは一言も言わなかった。むしろ、「大丈夫」と口癖のように言っているのだ。しかし小梅からしたら、全く正反対に受け取っているのだろう。
たとえ素直に辛苦を吐き出したところで、私の身体が回復しなければ、余計に小梅の心に負荷をかけるだけ。何の意味もないではないか。嘆きや弱音は胸に留め、口にしようとは一切思わなかった。いずれにしろ、小梅は私を心配してしまう性質なのだから。
「さあ姫様、お休みになってください」
「分かったわ、小梅の小言は長いものね。大人しく言う通りにするわ」
「まあ、姫様ったら!」
小梅がわざと大げさに反応する。私はくすくすと小さく笑いながら伏せて衾を掛けた。
指先はまだ固く冷えたまま、まるで自分のものではないように白い。それを取り、両手で温めるように握りしめた小梅の顔が一瞬だけ歪んだ。まるで、死人のような冷たさだと思ったのだろう。
「これほどになるまで外に出られるなどっ……」
「ほんの一時よ。元々冷えていたんだわ」
気にしないでと微笑んだが、小梅の表情は和らぐことはなかった。私の手は、どれほど彼女がさすっても、少しも温もりは戻ってこない。
多分、きっと、そう。私はもうすぐ、この生を終えるのだろう。かろうじて生きながらえているだけで、死人と大差はない。
現世にしがみ付きたいなどとは露ほどにも思わない。むしろ、できることなら早くお兄様の元へ行きたいと願っている。生きていてよかったと思えたことなど、この数年で数えるほどしかなかった。
何のために自分は存在しているのか。いつもその答えを求め続けて、結局見つからずに今日を迎え――ようやく、それも終わりになるのだと、どこか安堵している自分がいる。私はもう、全てを終わりにしたかった。
「姫様……」
「どうしたの」
言いにくそうに何度か唇を震わせ、やがて意を決したと言わんばかりに小梅は言った。
彼女のその表情を見ているだけで、何を言うのかは聞かなくても分かっていた。これまでに、同じ進言を幾度となく聞いてきたからだ。
「差し出がましいことと十分承知の上で申し上げます。……どうか、有明中将様と、今一度お会いになって下さい」
「必要ないわ」
もう二度と会わない。そう決めたのだから。
「せめて、こちらだけでもお目通しいただけませんか」
小梅の出した文は、お兄様からの文使いから預かったものだろう。
私の答えはいつも同じ、首を横に振るだけだ。固く結ばれたその文を開くことはない。
お兄様へ離別を申し出てから、随分と時間が経っていた。
あれから、お兄様には一度もお会いしていない。ただの一度も。
日を空けず届くお兄様の文も、全て捨てた。燃してしまったものもある。読めばあの日のことをなかったことにしてしまいたくなると分かっていた。だから、お兄様の全てを私の生活から消して生きてきた。
小梅はもちろんのこと、お父様やお母様までもが私を諫めようとなさったけれど、その言葉を聞く気にはなれなかった。どれほどの覚悟でお兄様にあれほどひどいことを申し上げたか――それを何事もなかったように白紙に戻せと言うのは無理な話だった。
一向に首を縦に振らぬ私に呆れ、諦め、やがて、誰もその話には触れなくなった。ただ一人、あの場に同席していた小梅だけは、未だにこうしてお兄様の名を私の前で呼ぶが、その数も随分と少なくはなっている。
私はもう、あのような身を切る思いはしたくない。あの日の、お兄様の悲し気な声が、今でも耳に張り付いて離れない。夢にまで見るほどなのに。どうして、もう一度ただの妹に戻れるだろうか。
距離を置いてお兄様への恋を忘れることができたのならば、まだよかった。それができないから、未だにお兄様に会おうとは思えないのだ。
お兄様の好きな香の香り、花の色、恋の歌まで、全部……なぜ、この胸は一つ残らず大事にしまい込み、捨てることができないのだろう。
不調という形で変化が現れたのは、身体の方だった。
お兄様を遠ざけたあの日以来、私の身体は弱っていく一方だった。そんな中でかかった流行病で床についたことをきっかけに、起き上がることもままならず、そうしている間に、気が付けば四季は次々と移ろっていった。春夏秋冬の美しさを愛でる余裕はなく、この目には何もかもが色を失い、褪せて見えた。
お父様、お母様が私をお諫めにならなくなったのは、この病のせいもあるのだろう。日ごと弱る娘の姿を目の当たりにし、私を気遣う言葉以外は口にできなくなったのだ。それほどまでに、私の姿は様変わりしていった。髪の艶は消え、肌は青白く、身体の芯から冷えている。ただ、死を待ち、息をしているだけの存在に違いなかった。
小梅が震えながらさすり続ける私の手は、自分でも驚くほど痩せ細っていた。そういえば、まともに食事を摂ったのはいつだっただろう。
「ねぇ、小梅……これから私が話すことは、私の独り言よ。だからあなたは、何も聞いていない。そういうことにしてちょうだい」
「姫様……?」
「私は、お兄様が、私のことを憎み嫌って下さればいいと思っているの」
「中将様が、姫様を憎むなどあるはずがございませんわ! あれ以来、お見舞いの文も絶えず届き、姫様がお会いにならぬだけで、こちらへもいらっしゃっているのですよ? 姫様が、ただ一言許すと、そうおっしゃって下されば――」
「独り言に返事をしてはだめよ。……優しい思い出というものは、残された人たちを苦しめる。だから私は、お兄様にそういうものを残したくないの」
私は、よく知っている。亡くなられた一番上のお兄様が、私にとってそうだった。
思い出すだけで心が温まるような――そんな記憶は、ともすれば、故人への強い未練へと変わる。そしていつまでも、そこに囚われてしまう。私はお兄様が居たからこうして今、息をしているけれど、あのまま、底なし沼のような悲しみへ引きずられてもおかしくはなかった。
お兄様は、私とは違う。私よりも強く、私よりも生に対して執着がある。
だから、たとえ私が死すとも私のようにはならないのだろう。けれど、心に深い傷を負うことには変わりはない。それがせめて浅くなればいいと願う。
「あんなひどいことを言った妹のことなど知らぬ」と私を忌み嫌うことで、お兄様の悲しみが薄れてしまえばいい。一番上のお兄様を喪ったあの悲しみを、もう一度お兄様に与えてはいけない。
私は最期まで、お兄様にとって悪い妹でありたい。お兄様の苦しみが、それで少しでも減るのならば。
それが、花を差し出し、私を悲しみの淵から救い出してくれたお兄様に最後にできる、私の唯一のことだった。
本当は――本当は、お兄様に謝ろうと何度も思い直した。そしてその度に、これまでのことを無駄にするのかと自分に言い聞かせてきた。
だけれど、伏せる時間が増え、いよいよ死が現実的なものとして迫ってきたときに、あれほどまで葛藤していたことが信じられないほどに迷いは消え去った。どのみち私は永くは生きられないのならば、今のままが一番良いと思ったのだ。
「そのようなやり方は間違っておりますわ、姫様。先ほども申し上げましたが、中将様はどのような姫様でも大切に思っておいでです。このままでは、行き違いがあったままだと、ずっと後悔されるに違いありませんわ。姫様は、そのような形で中将様を苦しめてもいいとおっしゃるのですか?」
小梅の指摘したことを、勿論考えなかったわけではない。むしろ、お兄様の性格を知っているからこそ、その可能性が高いことだって分かっていた。
でも、私はやはり歪んでいる。お兄様を苦しめたくないと願う一方で、お兄様の心に「後悔」という形で強く遺るのならば、それもまたいいのではないか、と。矛盾していることなど、とうに知っている。自分がおかしいことも。
恋や愛などでは決してない特別。ただの残像のようなもの。けれど、お兄様の中に他の女達とは違うものとして在り続けられる。ならば、それもまた「特別」だ。この歪み切った想いを、誰に理解してもらおうとも思わない。
「どうしたってお兄様は、私を喪えば苦しむわ」
「姫様……」
「けれど小梅、あなたはどうか最期まで私の傍にいてちょうだい……お兄様のように、あなたも遠ざけてしまえばよかったのだけれど、どうしてもできなかった。私の我儘よ、あなただけにはここにいて欲しい」
「何を当たり前のことをっ……わたくしの主は姫様だけですわ」
「ええ。私にも、もう小梅しかいないわ」
薄い涙の膜が、小梅の瞳を覆っていた。こんな醜い心を持った私のために、彼女は泣いてくれる。それがどんなに有難いことか。死を願おうとも、病の身で心細い日がなかったわけではない。冷たい私の手を握るこの温かさに、何度助けられ、温もりを分けてもらっただろうか。
「長い独り言を言ってしまったわ。もう休むわね」
静かに手を解き、小梅に背を向けた。小梅は何も言わず、嗚咽を呑み込むような音だけが聴こえた。それ以上彼女といると、私まで涙をこぼしてしまいそうだった。とうに枯れたはずだったのに。
喉に石がいくつも詰まったような重い苦しさが込み上げてくる。
小梅を、大切な彼女を、私のことに巻き込んでしまったことだけは申し訳なく、心残りだった。
私が生きている間は、小梅は私のことで手一杯だ、とても恋をするような暇はない。けれど、その先ならば――どうか私のような恋はせず、幸せに笑っていてほしい。
自分はそれを見ることができないのだということが、ひどく淋しかった。
◆◆◆
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
68
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる