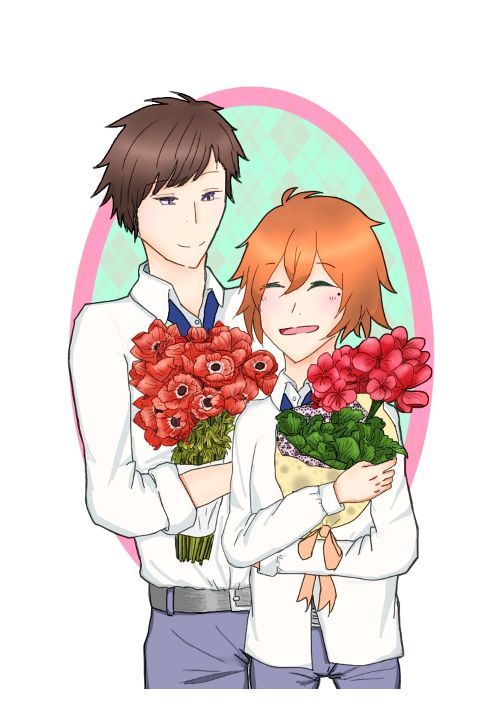90 / 95
前篇:夢の通ひ路
第四十二話 其の三
しおりを挟む
「ああ、姫様…… よかった、お気付きになられましたか」
安堵と心配が入り交じった声だった。
ぼんやりとしていた輪郭が徐々に鮮明になり、人影に目をやれば小梅が声と同じような表情でこちらを見つめていた。少し遅れて自分の状況を理解する。私は、小梅と話している最中に、また眠ってしまったのだ。それも、意識を突然失うという、小梅を最も驚かせ不安にさせる最悪の形で。
身体を起こすと、彼女が掛けてくれたらしい衾がずり落ちた。床の上でそのまま眠っていたせいか、背中が痛むが、気にしている場合でもない。
「心配をかけてごめんなさい。私は大丈夫よ」
少しだけ掠れてしまったが、私の第一声に小梅は心底ほっとしたようだった。
この昏睡のことを彼女に何も伝えずにいたままだったならば、今頃は大事になっていただろうと思うと冷や汗ものである。小梅のことだから、大騒ぎをして、まずは父母に知らせに走ったに違いない。下手をしたら、目覚めると同時に加持祈祷の煙の中ということもありえなくはなかったのだ。昨日のうちにしっかりと話しておいてよかったと、私の方が胸を撫で下ろしていた。
「姫様、本当にお加減はよろしいのでございますか?」
「ええ、ただ眠っていただけだもの。驚かせてしまってごめんなさい。私はどれほど眠っていたのかしら」
「半刻ほどでございますわ」
「半刻!?」
「え、ええ。それほどの時であったと思いますが……」
雛菊をはじめとした女房達がまだ戻ってきていないところを見ると、それほど長い時間ではないとは思っていたが、想定よりも随分と短い。
しかし、この状況に鑑みれば、早く目が覚めてよかったという一言に尽きる。今回ばかりは短時間で夢から解放されたことに感謝するばかりだ。小梅の心的負担が軽いにこしたことはない。私の目覚めが遅ければ遅いほど、彼女の心配は積み重なっていくのだから。
「確かに姫様は、静かに寝息を立てていらっしゃいましたわ。けれどわたくしは、本当にお目覚めになるのかと気が気ではなく…… 姫様は大事にするなとおっしゃいましたからそのようにいたしましたけれど、殿様や東の方様にお伝えしなくてもよいものか、やはり薬師を呼ぶべきか呼ぶまいか、とりあえず衾をお掛けしたものの、このような床の上に姫様がお伏せになられたままというのもどうかと……」
やはり小梅は相当に私のことで気をもんだらしい。
張りつめていた糸が、ぷつりと切れたのだろう。次から次へと吐露されるのは、彼女のこの数十分間の大きな不安だ。
小梅を疑うわけでは決してないが、あれ以上眠っていたなら、小梅は耐えきれずに父母に知らせたかもしれない、と思うほどには、延々と喋り続けている。とにかく小梅は、こと三の君に対しては心配性な面がある。これまでの夢の通り、三の君の生に対して投げやりな部分を見てきた彼女がそうなるのは、いたしかたないことと言えるが。
「小梅、落ち着いてちょうだい。昨日も話した通り、私は眠っていただけよ。どこも悪くないから大丈夫なの」
「そうおっしゃられましても…… 姫様、本当の本当に、御身のどこにもご不調はないのでございますね?」
念を押すように、ずい、と身体を前にのめり出して聞いてきた小梅に、私は苦笑いを浮かべて頷いた。
目の前でいきなり倒れたのだ。いくら、そういう時があるのだと話していたとしても、やはりにわかには信じられないのだろう。小梅は未だに疑うような眼差しでこちらを伺っている。心配しないで、と付け足そうとしたが、言ったところでされるのは目に見えているのでやめておいた。
「ところで姫様、先ほどのお話の続きなのですが……」
「私が眠る前のことね?」
「はい。片端のみお伝えし、誤解を招いてはいけませんから…… よろしいでしょうか」
「ええ、もちろんよ」
倒れた手前、なかなか話を戻せずにいたのだが、小梅からきっかけをくれるなんて好都合だ。私が眠ってしまったせいで、二人きりでいられる時間は随分と限られているはず。早く彼女の本意を知りたかった。
一体、どうして「私の記憶が戻ることが怖い」と彼女が言ったのか。
二、三度ゆっくりと呼吸をした後、小梅は悲し気な顔で語りだした。
「姫様、姫様は覚えていらっしゃらないかもしれませんが…… あの日を境に、姫様はお変わりになりました。死期が近いのだと何もかも諦め、聞き入れず、病に倒れても薬一つお飲みにならなかった。わたくしは……、わたくしは、そのようなお姿を見るのが、ずっと辛うございました……」
「小梅……」
「姫様はどれほど苦しんでおられても、苦しいとは一言もおっしゃいませんでしたわ。ただ、いつも淋しげに微笑んでおられるだけ…… だけれど、わたくしはほんの少しでもいい、姫様のお力になりたかったのです。辛いなら辛い、苦しいなら苦しいと、おっしゃっていただきたかったのです」
小梅の瞳が、みるみるうちに涙に覆われていく。それが頬、顎をつたい、ぽたぽたと落ちた。顔を背け、扇で隠したものの、彼女が嗚咽を我慢しているのは気配で分かった。
「もう永くないのだと、そのようなお言葉をわたくしがどんな思いで聞いていたか……」
三の君はきっと知らなかったのだろう。小梅もまた、三の君と同じように苦しんでいたことを。
大切な人が目の前で弱っていく様を見るのは、誰だって耐え難い。この優しく真面目な女房は、主の力になれないのだと自分を責めて、あの日々を過ごしていたのだ。三の君を大切に思えば思うほど、自責の念も強く押し寄せてきたはずだ。それはいつしか後悔となり、どれほど彼女を苦しめてきたのか、察するに余りある。
まさに今、三の君と小梅の会話を、私は見てきたばかりだ。あの過去を知っているからこそ、今の小梅の言葉を信じられるし、今度こそ嘘偽りではないといえる。だって、小梅はこうして涙しながらも、精一杯の自分を私に見せてくれているのだから。
彼女の声はかすかに涙に震えていた。
「一番お傍にいるのに、何もできぬ無力な我が身を、何度嘆いたことでしょう。わたくしは、姫様に何もして差し上げられなかった…… 有明中将様とのことも、姫様があのようにお考えだったとは存じ上げず、わたくしがもっと姫様に寄り添うことができていたのならば、お二人のご関係も何か違っていたのではないかと――」
「いいえ! いいえ、小梅。私が望んでしてきたことなのだもの、あなたのせいではないわ」
最後まで小梅の言葉を待たずに、思わず遮った。それは違う。三の君がここにいたならば、私のように迷わず否定しただろう。
三の君と兄の離別はどうしたって避けることはできなかった。三の君が兄への恋心を捨てられない以上、遅かれ早かれ、ああいう形になっていたはずだ。そして、彼女はその秘めた恋を誰にも触れられたくないと望んでいた。それがたとえ小梅相手だったとしても、兄への思慕を語ることは決してしなかっただろう。
現に三の君は、毎日一緒に過ごしている小梅にも、そして兄本人にも、その胸の内を悟られることはなかった。視線の動き、話す声音、立ち居振る舞いの全てに細心の注意を払い、いつも通りの自分を演じながら、よほど上手く欺き隠してきたに違いない。姫という立場上、常に人の目がある中でそれを完璧にやり遂げるのは、随分と負担が大きかっただろうと思う。少しの綻びもあってはならないのだから、途方もないことだ。私などでは絶対に真似できない。
結果的に、その積み重ねは三の君の逃げ道を更に塞ぎ、兄と疎遠になるという決断にいたった。彼女に残された選択肢はそれだけだったのだから、小梅が自分のせいなのだと思うのは、やはり間違っている。
それに、三の君は小梅に感謝をしていたのだ。
「私はお兄様を遠ざけることはできても、あなたまではそうしなかった。私の最期をあなたに見せるということがどれほどあなたにとって辛いことかを知っていても、そうできなかった。それは……私があなたにだけは傍にいてほしいと思っていたからよ」
「姫、様……」
「小梅の存在が、私の救いだったんだわ」
私が言っているのか、それとも三の君が言っているのか。意識せず発した自分の言葉が、すとん、と胸に落ちた。ああ、きっと、そうだ。
三の君が自分の恋を小梅に話さなかったのは、単純に知られたくないというだけではない。小梅との関係が変わることを恐れたのだろう。彼女は、大切な乳兄弟を、姉のような傍付女房を、失いたくなかった。
同調も同情もせず、何も知らない小梅と年頃の女性らしく、無邪気に笑い合える時間を救いにしていた。その時間だけは、全て忘れられたはずだから。
「小梅は、何もできなかっただなんて言ったけれど、私はあなたに幾度となく助けられていたわ」
「しかし、わたくしは……」
「お兄様とのことを伏せていたのは、私のためを思ってのことだったのね」
「……さようでございます」
頷いたときに、また大きな雫が落ちた。小梅は今度は隠すこともせず、はらはらと涙を流しながら続けた。
「姫様が病に倒れて後、お目覚めになり、記憶を失ったとおっしゃられたとき……なんと大変なことかと血の気の引く思いがすると同時に、わたくしは、どこか安堵しておりました。全てをお忘れになったのであれば、姫様はもう苦しまなくてもよいのではないかと思ったのです」
「私の病が重くなりだしたのはあの日以降だった。だから、あの日のことを話せなかったのね?」
「はい。順調に、見違えるほど回復をされていた姫様が、何かを思い出され、そのためにまたも床に伏せられたら、と、そう思うと……何も申し上げられませんでした。畏れながら、姫様はどこかで死を願っているように見えましたわ。けれどわたくしは、どんな姫様であっても、姫様に生きていてほしかったのです」
「……小梅」
「中将様とて姫様との離別は元より望んでいらっしゃらなかった、あの日のことをご自分からは決してお伝えにならないと分かっておりました。事実、見舞いという形でこちらにお見えになったときに、何もお話しにはなりませんでしたから。であれば、わたくしさえ口をつぐめば、あの過去はなかったものにできるのだと、そう思ってしまったのです」
「……確かにそうね、お兄様は私と以前のように話せて嬉しいとおっしゃっていたわ。あなたの言う通り、お兄様からあの日のことを口にすることはこの先もないでしょう」
兄と初めて会った日のことを思い出しているうちに、小梅はもう一度伏せた。一瞬で頭の中が疑問符で埋め尽くされる。
この流れでなぜ突然、土下座をする??
しかも、なんとも重いような――ああ、そうだ。時代劇の「切腹いたします!」的な切々とした空気、あれと同じものが漂っている気がする。
私の勘があながち間違っていなかったらしいと知るのは、小梅の意を決した一言を聞いてからだった。
「申し訳ございません、姫様……! 言い訳は一切いたしません。どのような理由であれ、わたくしは姫様を偽っておりました。どのような処分も甘んじてお受けいたします」
「やめてちょうだい! 全く、あなたったら真面目が過ぎるんだわ……」
妙な既視感があるのは、雛菊が私に仕え始めたころ、同じようなことをしたからだ。しかも、髪が櫛に絡まっただけという、なんともちっぽけな理由。小梅といい、雛菊といい、大げさすぎるのだ。たったこれだけのことで処分だなんて冗談じゃない。
小梅の身体をぐいと引っ張って無理やり起こし、私は苦笑いをしながら言った。
「私のために良かれと思いそうしたことを、どうして私が咎められるでしょう。それでもあなたが納得できずに処分が必要だというのならば、この先も私の傍にいてちょうだい。それが処分よ。私はあなたがいないと困ると何度も言っているわ」
「そのような…… 罰になりませんわ、姫様」
「そもそも罰など必要ないの! いいわね、この話はこれでお終いよ」
聞きたかった話は聞けたし、これ以上はいいだろう。
深い意図があるわけでもなく、小梅はただ、三の君を思って口を閉ざしただけだった。ここまで腹を割って話してくれたのだから、疑いようもない。
“あの日”が小梅にとってひどいトラウマのようになっていることには驚いたけれど、いかにも彼女らしい。今、こうして話したことで、小梅は少しでも楽になっただろうか。抱えていたものが軽くなったのであればいいけれど……
ちらりと小梅の横顔を見ると、どこかすっきりとしたような、晴れやかな表情に見えた。私に隠していることがあるという後ろめたさが消えたのかもしれない。
「さて、と。そろそろ皆が戻ってくるかもしれないわね。小梅、今のうちにお化粧を整えていらっしゃい」
あれほど大粒の涙を流していた小梅の顔は、涙の跡と化粧が混ざり、ぐちゃぐちゃの状態だった。間違いなく、お化粧直しの時間が彼女には必要だ。
目が腫れなければいいと思うが、そこは小梅のことだ。何か聞かれても適当な理由をつけてはぐらかすだろうから心配はしていない。
「ああ、さようでございますわね…… 申し訳ありません、姫様。では少々、お傍を離れます」
「ゆっくりでいいわ」
「姫様……、あの」
「どうしたの?」
小梅は、少しだけ赤くなった目元を緩ませて微笑んだ。
「もしかしたら、姫様はおかしなことだと思われるかもしれません。けれど……、姫様の記憶が失われましたこと、皆は物の怪の仕業と恐れましたが、わたくしはそうは思いませんでしたの。もしかしたら、これは、御仏が姫様の苦しみを全て消し去って下さったのではないか、と」
……その逆転の発想は全くなかった。
なるほど小梅の立場から見たら、物の怪ではなく御仏と、そういったポジティブ思考もあるのか。
思えば小梅だけは確かに私のことを一切怖がらずにいてくれたのだ。もちろん三の君を妹のように思っていることもあるだろうが、まさか、そんなふうに思っていただなんて。
「今でも、わたくしはそう信じています。あれほど死期が近いとおっしゃっていた姫様が、今はこうしてお健やかになられ、宮様とお幸せでいらっしゃいますもの」
「……そうね。そう考える方が素敵だわ」
心からの言葉に、私は曖昧に頷くことしかできなかった。
確かに宮と結ばれたことは幸せで、その言葉以外では表しようがない。でもそれは、いつか儚く消えてしまうものだ。
本来であれば今はもう生きているはずのないだろう三の君がいることで、未来が変わってしまった。私達がもう一度入れ替わった時、狂った時の流れはどうなるのだろう。
事情を知らぬ小梅が言ったことなのだ、突き詰めることもないけれど、御仏のお導きだなどと、そんな尊いものではない。私自身、どうしてここにいるのかもまだ分かっていないのに……
考え出したらキリがない諸々を頭の隅に追いやり、私は小梅をお化粧直しへ向かわせた。
次は、兄か。一度、腹を割って話さなくてはいけない。
小梅のように簡単にはいかないだろうと思うと、ため息が漏れた。兄が何を考えているのか、全く分からない。ただ、三の君に記憶を取り戻してほしくないことだけははっきりしているけれど……兄の腹を割らせる難易度の高さに頭痛がしそう。もう一度、大きなため息をついた。
ともあれ、とりあえず、会う約束を取り付けなくてはいけない。
書き出しをどうしようかと迷いながら、数時間前まで使用していた紙を取りだしたところで、足音が聞こえてきた。おそらく雛菊達が戻ってきたのだろう。雨音に混じり、何やら楽し気な話声が聞こえてくる。小梅が珍しい菓子で気を引いたと言っていたから、話題はそのことだろうか。
あの様子では、集中して手紙を書くことなど到底無理だろう。やはり、女房達が下がる明朝にでも筆を取った方がいい。
そう決めて、私はもう一度、紙を箱に戻したのだった。
安堵と心配が入り交じった声だった。
ぼんやりとしていた輪郭が徐々に鮮明になり、人影に目をやれば小梅が声と同じような表情でこちらを見つめていた。少し遅れて自分の状況を理解する。私は、小梅と話している最中に、また眠ってしまったのだ。それも、意識を突然失うという、小梅を最も驚かせ不安にさせる最悪の形で。
身体を起こすと、彼女が掛けてくれたらしい衾がずり落ちた。床の上でそのまま眠っていたせいか、背中が痛むが、気にしている場合でもない。
「心配をかけてごめんなさい。私は大丈夫よ」
少しだけ掠れてしまったが、私の第一声に小梅は心底ほっとしたようだった。
この昏睡のことを彼女に何も伝えずにいたままだったならば、今頃は大事になっていただろうと思うと冷や汗ものである。小梅のことだから、大騒ぎをして、まずは父母に知らせに走ったに違いない。下手をしたら、目覚めると同時に加持祈祷の煙の中ということもありえなくはなかったのだ。昨日のうちにしっかりと話しておいてよかったと、私の方が胸を撫で下ろしていた。
「姫様、本当にお加減はよろしいのでございますか?」
「ええ、ただ眠っていただけだもの。驚かせてしまってごめんなさい。私はどれほど眠っていたのかしら」
「半刻ほどでございますわ」
「半刻!?」
「え、ええ。それほどの時であったと思いますが……」
雛菊をはじめとした女房達がまだ戻ってきていないところを見ると、それほど長い時間ではないとは思っていたが、想定よりも随分と短い。
しかし、この状況に鑑みれば、早く目が覚めてよかったという一言に尽きる。今回ばかりは短時間で夢から解放されたことに感謝するばかりだ。小梅の心的負担が軽いにこしたことはない。私の目覚めが遅ければ遅いほど、彼女の心配は積み重なっていくのだから。
「確かに姫様は、静かに寝息を立てていらっしゃいましたわ。けれどわたくしは、本当にお目覚めになるのかと気が気ではなく…… 姫様は大事にするなとおっしゃいましたからそのようにいたしましたけれど、殿様や東の方様にお伝えしなくてもよいものか、やはり薬師を呼ぶべきか呼ぶまいか、とりあえず衾をお掛けしたものの、このような床の上に姫様がお伏せになられたままというのもどうかと……」
やはり小梅は相当に私のことで気をもんだらしい。
張りつめていた糸が、ぷつりと切れたのだろう。次から次へと吐露されるのは、彼女のこの数十分間の大きな不安だ。
小梅を疑うわけでは決してないが、あれ以上眠っていたなら、小梅は耐えきれずに父母に知らせたかもしれない、と思うほどには、延々と喋り続けている。とにかく小梅は、こと三の君に対しては心配性な面がある。これまでの夢の通り、三の君の生に対して投げやりな部分を見てきた彼女がそうなるのは、いたしかたないことと言えるが。
「小梅、落ち着いてちょうだい。昨日も話した通り、私は眠っていただけよ。どこも悪くないから大丈夫なの」
「そうおっしゃられましても…… 姫様、本当の本当に、御身のどこにもご不調はないのでございますね?」
念を押すように、ずい、と身体を前にのめり出して聞いてきた小梅に、私は苦笑いを浮かべて頷いた。
目の前でいきなり倒れたのだ。いくら、そういう時があるのだと話していたとしても、やはりにわかには信じられないのだろう。小梅は未だに疑うような眼差しでこちらを伺っている。心配しないで、と付け足そうとしたが、言ったところでされるのは目に見えているのでやめておいた。
「ところで姫様、先ほどのお話の続きなのですが……」
「私が眠る前のことね?」
「はい。片端のみお伝えし、誤解を招いてはいけませんから…… よろしいでしょうか」
「ええ、もちろんよ」
倒れた手前、なかなか話を戻せずにいたのだが、小梅からきっかけをくれるなんて好都合だ。私が眠ってしまったせいで、二人きりでいられる時間は随分と限られているはず。早く彼女の本意を知りたかった。
一体、どうして「私の記憶が戻ることが怖い」と彼女が言ったのか。
二、三度ゆっくりと呼吸をした後、小梅は悲し気な顔で語りだした。
「姫様、姫様は覚えていらっしゃらないかもしれませんが…… あの日を境に、姫様はお変わりになりました。死期が近いのだと何もかも諦め、聞き入れず、病に倒れても薬一つお飲みにならなかった。わたくしは……、わたくしは、そのようなお姿を見るのが、ずっと辛うございました……」
「小梅……」
「姫様はどれほど苦しんでおられても、苦しいとは一言もおっしゃいませんでしたわ。ただ、いつも淋しげに微笑んでおられるだけ…… だけれど、わたくしはほんの少しでもいい、姫様のお力になりたかったのです。辛いなら辛い、苦しいなら苦しいと、おっしゃっていただきたかったのです」
小梅の瞳が、みるみるうちに涙に覆われていく。それが頬、顎をつたい、ぽたぽたと落ちた。顔を背け、扇で隠したものの、彼女が嗚咽を我慢しているのは気配で分かった。
「もう永くないのだと、そのようなお言葉をわたくしがどんな思いで聞いていたか……」
三の君はきっと知らなかったのだろう。小梅もまた、三の君と同じように苦しんでいたことを。
大切な人が目の前で弱っていく様を見るのは、誰だって耐え難い。この優しく真面目な女房は、主の力になれないのだと自分を責めて、あの日々を過ごしていたのだ。三の君を大切に思えば思うほど、自責の念も強く押し寄せてきたはずだ。それはいつしか後悔となり、どれほど彼女を苦しめてきたのか、察するに余りある。
まさに今、三の君と小梅の会話を、私は見てきたばかりだ。あの過去を知っているからこそ、今の小梅の言葉を信じられるし、今度こそ嘘偽りではないといえる。だって、小梅はこうして涙しながらも、精一杯の自分を私に見せてくれているのだから。
彼女の声はかすかに涙に震えていた。
「一番お傍にいるのに、何もできぬ無力な我が身を、何度嘆いたことでしょう。わたくしは、姫様に何もして差し上げられなかった…… 有明中将様とのことも、姫様があのようにお考えだったとは存じ上げず、わたくしがもっと姫様に寄り添うことができていたのならば、お二人のご関係も何か違っていたのではないかと――」
「いいえ! いいえ、小梅。私が望んでしてきたことなのだもの、あなたのせいではないわ」
最後まで小梅の言葉を待たずに、思わず遮った。それは違う。三の君がここにいたならば、私のように迷わず否定しただろう。
三の君と兄の離別はどうしたって避けることはできなかった。三の君が兄への恋心を捨てられない以上、遅かれ早かれ、ああいう形になっていたはずだ。そして、彼女はその秘めた恋を誰にも触れられたくないと望んでいた。それがたとえ小梅相手だったとしても、兄への思慕を語ることは決してしなかっただろう。
現に三の君は、毎日一緒に過ごしている小梅にも、そして兄本人にも、その胸の内を悟られることはなかった。視線の動き、話す声音、立ち居振る舞いの全てに細心の注意を払い、いつも通りの自分を演じながら、よほど上手く欺き隠してきたに違いない。姫という立場上、常に人の目がある中でそれを完璧にやり遂げるのは、随分と負担が大きかっただろうと思う。少しの綻びもあってはならないのだから、途方もないことだ。私などでは絶対に真似できない。
結果的に、その積み重ねは三の君の逃げ道を更に塞ぎ、兄と疎遠になるという決断にいたった。彼女に残された選択肢はそれだけだったのだから、小梅が自分のせいなのだと思うのは、やはり間違っている。
それに、三の君は小梅に感謝をしていたのだ。
「私はお兄様を遠ざけることはできても、あなたまではそうしなかった。私の最期をあなたに見せるということがどれほどあなたにとって辛いことかを知っていても、そうできなかった。それは……私があなたにだけは傍にいてほしいと思っていたからよ」
「姫、様……」
「小梅の存在が、私の救いだったんだわ」
私が言っているのか、それとも三の君が言っているのか。意識せず発した自分の言葉が、すとん、と胸に落ちた。ああ、きっと、そうだ。
三の君が自分の恋を小梅に話さなかったのは、単純に知られたくないというだけではない。小梅との関係が変わることを恐れたのだろう。彼女は、大切な乳兄弟を、姉のような傍付女房を、失いたくなかった。
同調も同情もせず、何も知らない小梅と年頃の女性らしく、無邪気に笑い合える時間を救いにしていた。その時間だけは、全て忘れられたはずだから。
「小梅は、何もできなかっただなんて言ったけれど、私はあなたに幾度となく助けられていたわ」
「しかし、わたくしは……」
「お兄様とのことを伏せていたのは、私のためを思ってのことだったのね」
「……さようでございます」
頷いたときに、また大きな雫が落ちた。小梅は今度は隠すこともせず、はらはらと涙を流しながら続けた。
「姫様が病に倒れて後、お目覚めになり、記憶を失ったとおっしゃられたとき……なんと大変なことかと血の気の引く思いがすると同時に、わたくしは、どこか安堵しておりました。全てをお忘れになったのであれば、姫様はもう苦しまなくてもよいのではないかと思ったのです」
「私の病が重くなりだしたのはあの日以降だった。だから、あの日のことを話せなかったのね?」
「はい。順調に、見違えるほど回復をされていた姫様が、何かを思い出され、そのためにまたも床に伏せられたら、と、そう思うと……何も申し上げられませんでした。畏れながら、姫様はどこかで死を願っているように見えましたわ。けれどわたくしは、どんな姫様であっても、姫様に生きていてほしかったのです」
「……小梅」
「中将様とて姫様との離別は元より望んでいらっしゃらなかった、あの日のことをご自分からは決してお伝えにならないと分かっておりました。事実、見舞いという形でこちらにお見えになったときに、何もお話しにはなりませんでしたから。であれば、わたくしさえ口をつぐめば、あの過去はなかったものにできるのだと、そう思ってしまったのです」
「……確かにそうね、お兄様は私と以前のように話せて嬉しいとおっしゃっていたわ。あなたの言う通り、お兄様からあの日のことを口にすることはこの先もないでしょう」
兄と初めて会った日のことを思い出しているうちに、小梅はもう一度伏せた。一瞬で頭の中が疑問符で埋め尽くされる。
この流れでなぜ突然、土下座をする??
しかも、なんとも重いような――ああ、そうだ。時代劇の「切腹いたします!」的な切々とした空気、あれと同じものが漂っている気がする。
私の勘があながち間違っていなかったらしいと知るのは、小梅の意を決した一言を聞いてからだった。
「申し訳ございません、姫様……! 言い訳は一切いたしません。どのような理由であれ、わたくしは姫様を偽っておりました。どのような処分も甘んじてお受けいたします」
「やめてちょうだい! 全く、あなたったら真面目が過ぎるんだわ……」
妙な既視感があるのは、雛菊が私に仕え始めたころ、同じようなことをしたからだ。しかも、髪が櫛に絡まっただけという、なんともちっぽけな理由。小梅といい、雛菊といい、大げさすぎるのだ。たったこれだけのことで処分だなんて冗談じゃない。
小梅の身体をぐいと引っ張って無理やり起こし、私は苦笑いをしながら言った。
「私のために良かれと思いそうしたことを、どうして私が咎められるでしょう。それでもあなたが納得できずに処分が必要だというのならば、この先も私の傍にいてちょうだい。それが処分よ。私はあなたがいないと困ると何度も言っているわ」
「そのような…… 罰になりませんわ、姫様」
「そもそも罰など必要ないの! いいわね、この話はこれでお終いよ」
聞きたかった話は聞けたし、これ以上はいいだろう。
深い意図があるわけでもなく、小梅はただ、三の君を思って口を閉ざしただけだった。ここまで腹を割って話してくれたのだから、疑いようもない。
“あの日”が小梅にとってひどいトラウマのようになっていることには驚いたけれど、いかにも彼女らしい。今、こうして話したことで、小梅は少しでも楽になっただろうか。抱えていたものが軽くなったのであればいいけれど……
ちらりと小梅の横顔を見ると、どこかすっきりとしたような、晴れやかな表情に見えた。私に隠していることがあるという後ろめたさが消えたのかもしれない。
「さて、と。そろそろ皆が戻ってくるかもしれないわね。小梅、今のうちにお化粧を整えていらっしゃい」
あれほど大粒の涙を流していた小梅の顔は、涙の跡と化粧が混ざり、ぐちゃぐちゃの状態だった。間違いなく、お化粧直しの時間が彼女には必要だ。
目が腫れなければいいと思うが、そこは小梅のことだ。何か聞かれても適当な理由をつけてはぐらかすだろうから心配はしていない。
「ああ、さようでございますわね…… 申し訳ありません、姫様。では少々、お傍を離れます」
「ゆっくりでいいわ」
「姫様……、あの」
「どうしたの?」
小梅は、少しだけ赤くなった目元を緩ませて微笑んだ。
「もしかしたら、姫様はおかしなことだと思われるかもしれません。けれど……、姫様の記憶が失われましたこと、皆は物の怪の仕業と恐れましたが、わたくしはそうは思いませんでしたの。もしかしたら、これは、御仏が姫様の苦しみを全て消し去って下さったのではないか、と」
……その逆転の発想は全くなかった。
なるほど小梅の立場から見たら、物の怪ではなく御仏と、そういったポジティブ思考もあるのか。
思えば小梅だけは確かに私のことを一切怖がらずにいてくれたのだ。もちろん三の君を妹のように思っていることもあるだろうが、まさか、そんなふうに思っていただなんて。
「今でも、わたくしはそう信じています。あれほど死期が近いとおっしゃっていた姫様が、今はこうしてお健やかになられ、宮様とお幸せでいらっしゃいますもの」
「……そうね。そう考える方が素敵だわ」
心からの言葉に、私は曖昧に頷くことしかできなかった。
確かに宮と結ばれたことは幸せで、その言葉以外では表しようがない。でもそれは、いつか儚く消えてしまうものだ。
本来であれば今はもう生きているはずのないだろう三の君がいることで、未来が変わってしまった。私達がもう一度入れ替わった時、狂った時の流れはどうなるのだろう。
事情を知らぬ小梅が言ったことなのだ、突き詰めることもないけれど、御仏のお導きだなどと、そんな尊いものではない。私自身、どうしてここにいるのかもまだ分かっていないのに……
考え出したらキリがない諸々を頭の隅に追いやり、私は小梅をお化粧直しへ向かわせた。
次は、兄か。一度、腹を割って話さなくてはいけない。
小梅のように簡単にはいかないだろうと思うと、ため息が漏れた。兄が何を考えているのか、全く分からない。ただ、三の君に記憶を取り戻してほしくないことだけははっきりしているけれど……兄の腹を割らせる難易度の高さに頭痛がしそう。もう一度、大きなため息をついた。
ともあれ、とりあえず、会う約束を取り付けなくてはいけない。
書き出しをどうしようかと迷いながら、数時間前まで使用していた紙を取りだしたところで、足音が聞こえてきた。おそらく雛菊達が戻ってきたのだろう。雨音に混じり、何やら楽し気な話声が聞こえてくる。小梅が珍しい菓子で気を引いたと言っていたから、話題はそのことだろうか。
あの様子では、集中して手紙を書くことなど到底無理だろう。やはり、女房達が下がる明朝にでも筆を取った方がいい。
そう決めて、私はもう一度、紙を箱に戻したのだった。
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
68
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる