聖水拝受 小説一覧
1
件
1
私は4歳の頃、友達の家に昼間預けられていた。涼心がとても忙しく、ご飯を作ることもできず、親戚からの紹介もあり、近所の友達の家に出入りするようになった。そこにはやや大柄な怖くて優しいママと細身で痩せ型のパパも住んでいた。ママは昼間仕事に出るが、いつも赤いハイヒールを履いていた。私はなぜかそのハイヒールに自身を投影させる事が多く、いつしか友人のママに慕情を越えた、憧憬、服従心、被支配感、被征服感を覚え始めた。そのうちではなぜか、みなパンツ一丁で生活していた。ママも白いパンティで過ごしていて、豊かな胸をいつもされしていた。私は台所に向かって調理しているママの脚、お尻と腰に特に興味を持ち、じっと見つめる事が多かった。ある日、私がママの赤いハイビーヒールを手にして遊んでいるのを見つかってしまい、ひどく叱られた。
泣きながら謝って、なぜハイヒールを手に持ていたか、問われ、この赤いハイヒールは僕自身だと感じていると告げてしまった。その時ママは何かを理解したように頷き、ママが台所で調理をしている間、私はママのお尻に顔を埋めていることが多くなった。なんだか逃げ場所できた気がしてとても安心な気がしていた。でもママのお尻にまともに敷かれると息ができないし、すごい匂いがして、驚いた。
私が顔を背けるとちゃんと現実を受け止めなければいけないと諭された。そこの臭いも含めてすべてを覚えて、これから生きていかなければいけないとも言われた。
友達のママのお尻の臭いも慣れてくると親しみを覚え、新しい友達ができた気がした。
入浴は友達と三人で、洗髪と体洗いまでしてもらっていた。
友達にママが背を向ける体勢になると私は口にママから小水を注がれた。
全然飲めなかったが、いつかきっと飲み干して、ママに褒めてもらいたいと思った。
小学生になってから、遂に友達のママの小水を全部飲むことができた。
それができるようになったら、パンティ越しじゃなく、素尻のまま顔にしゃがまれるようになり、ママのアヌスをしゃぶるようになった。
味はしなかったが、匂いはいつまで経っても臭いままで、結構きつかった。
慣れたら食べさせてあげるとママから言われたが、それが叶ったのは中学生に上がってからだった。
文字数 9,762
最終更新日 2025.09.14
登録日 2025.09.14
1
件












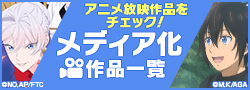
.png)
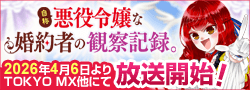

_修正_250×90_anatanoai_cimoaaward2026.png)

















