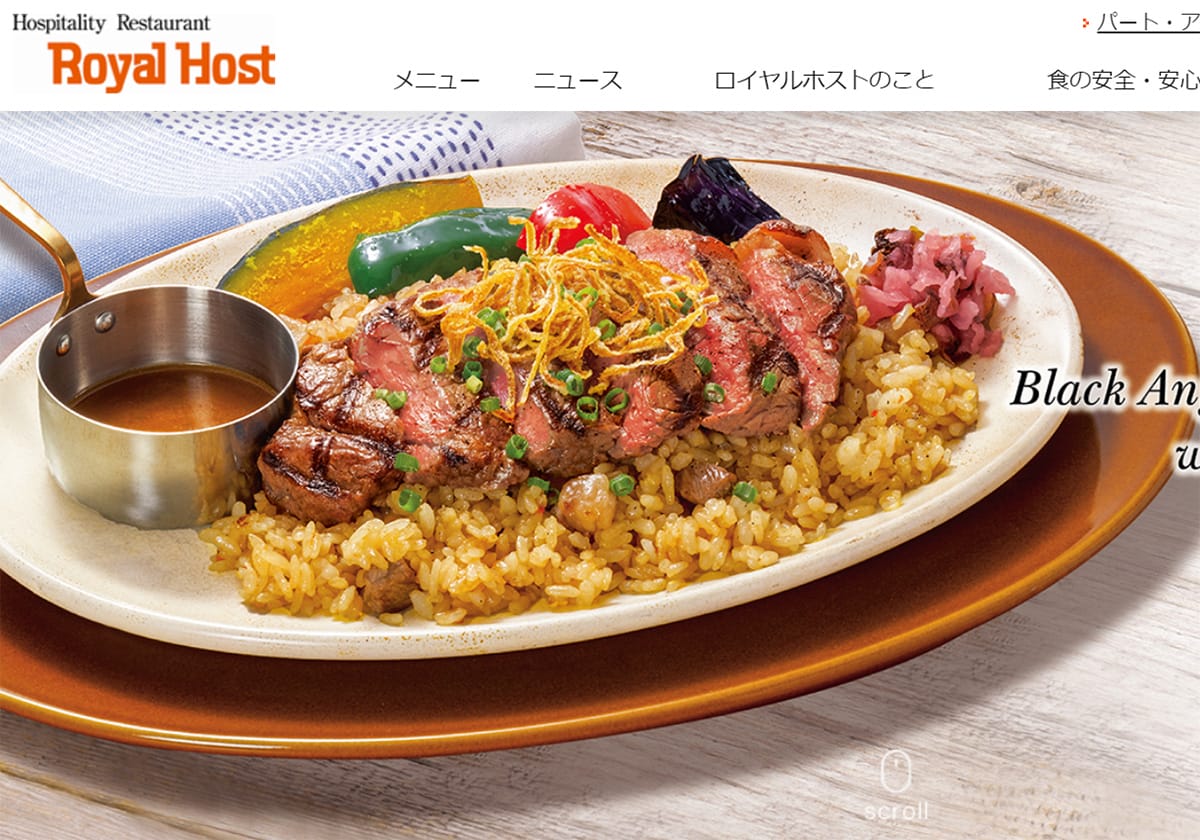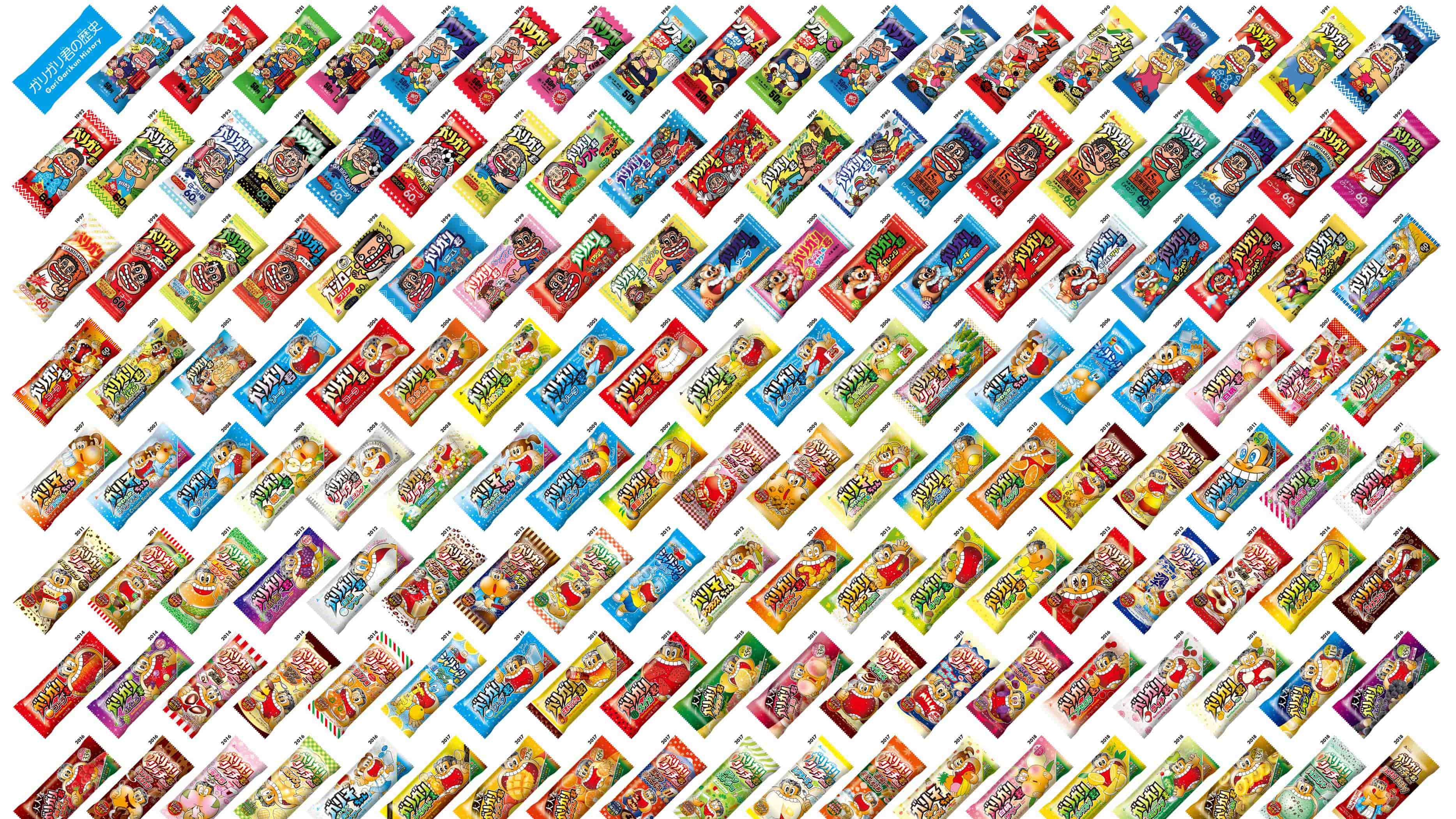アップルの低迷→復活の歴史に見えてくる本質
2020.09.03
東洋経済オンライン

GAFAの最古参企業にはかつて大きな危機がありました(写真:2020年 ロイター/Mike Segar)
今は一流の企業でも、大きな危機に直面し、それを乗り越えてきた過去がある。日米20社の「危機の乗り越え方」事例を分析した新著『20社のV字回復でわかる「危機の乗り越え方」図鑑』を上梓した杉浦泰氏が全3回で3社のケースを読み解きます。
第3回は「アップル」編。GAFA(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン)の一角として世界的なシェアを誇るアップルも、過去には巨額赤字の計上と存続の危機にさらされ、カリスマ経営者スティーブ・ジョブズ氏もまた日本の各種メディアから、「みじめ」と評されていた時期がありました。
何がアップルを存続の危機にまで追いやったのか、そしてそのV字回復から学ぶべき教訓とは? 危機突破の本質を探ります(本稿は杉浦泰著『20社のV字回復でわかる「危機の乗り越え方」図鑑』の一部を抜粋・再編集したものです。参考文献は本書に掲載)。
アップルはGAFAの最古参企業
2010年代に世界を席巻したビジネスのトレンドは、「GAFA」でした。このグーグル、アップル、フェイスブック、アマゾンのうち、創業年という点で見た場合に、1社、仲間外れがあります。さて、どの企業でしょう?
それはアップルです。グーグル、フェイスブック、アマゾンはインターネットが普及した1990年代以降に創業されたのに対し、アップルの創業は1976年。GAFAの中では古参企業に当たります。
今でこそアップルは優良企業として世界に名をはせていますが、1990年代は危機の真っただ中にありました。慢性的な低収益に悩まされ、「アップルは復活できない」とささやかれていたのです。
1990年代以降のインターネット業界で有望企業が続々誕生したように、企業の歴史をひもとき比較していると、ある特定の時期、ある特定の業種で、同時多発的に有望企業が誕生することがあります。本稿で取り上げるアップルもまた、1970年代におけるコンピューター業界における起業の波の中で誕生した企業でした。
コンピューター業界でベンチャー企業が同時多発的に出現した最初のきっかけは、1970年代における半導体産業の進歩です。1971年にインテルは、それまで巨大な筐体の中で動作していたコンピューターを「マイクロプロセッサ」という1つのチップで動作させました。このイノベーションによって、コンピューターは一般の人々の身近な存在へと変貌し、「パソコン」という巨大市場が生まれることとなったのです。この巨大市場の創世記に過敏に反応したのが、 マイクロソフト(1975年創業)のビル・ゲイツ氏、アップルのスティーブ・ジョブズ氏といった起業家でした。
アップルは1976年の創業後、パソコン市場の拡大によって急成長を遂げます。1980年には株式公開を行って設立わずか4年で会社は軌道に乗ることとなり、その経営者であるジョブズ氏にも注目が集まりました。その後も、アップルは一貫してパソコンの開発に邁進し、1984年に「マッキントッシュ」を世に送り出しています。
ところが1981年、コンピューター業界の巨人IBMがパソコンに参入して「IBM-PC」を発表すると、アップルと正面衝突することとなりました。アップルのパソコンはグラフィックが強いという趣味的要素の高いものであったのに対し、IBMのパソコンはビジネス用途で使うことに主眼を置いたため、IBMは一気にシェアを拡大していきました。
加えて、IBM-PCには、業界の競争ルールを変えてしまう力がありました。それは、OS(基本ソフト)にはマイクロソフト、マイクロプロセッサにはインテルの製品が採用されたことです。この結果、パソコン市場の中心はIBMやアップルのようなパソコンメーカーではなく、OSやマイクロプロセッサを供給する裏方企業――マイクロソフトとインテルなどに移ることとなりました。