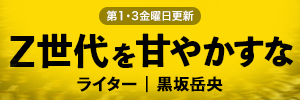核融合バブル到来か…米国は1社あたり4200億円投資、日本は「FAST」構想で挑む
2025.11.07
ビジネスジャーナル
さらに、コスト競争力も問われる。仮に商用炉1基の建設費が数千億円に下がったとしても、再生可能エネルギーや小型モジュール炉(SMR)と競合できる価格水準にはまだ遠い。ゆえに、2030年代は「実証期」から「商業モデル確立期」への過渡期となる見通し」
「ポスト再エネ」時代の覇権争い
国際的には、米国・英国・中国・日本・韓国・フランスが核融合競争の中心だ。中国では政府主導で「人工太陽」計画を推進し、安徽省で稼働したEAST実験炉は100秒以上の連続核融合反応を達成。韓国も2030年代に民間主導の核融合炉建設を計画している。
つまり、再エネをめぐる競争が一段落し、次なる覇権争いの舞台が「核融合」へと移りつつある。ただし、エネルギー政策は政治・外交・安全保障が密接に絡む領域だ。たとえば、ウクライナ戦争以降、エネルギー自立=安全保障という認識が世界的に共有された。
この流れのなかで、核融合技術の国産化は「次世代の防衛インフラ」としての意味も帯びつつある。
結論から言えば、技術力では日本は世界トップクラスにある。京都大学・名古屋大学・原子力機構などが半世紀にわたり蓄積してきた研究成果は、欧米の民間ベンチャーが模倣する対象になっている。実際、ITER(国際熱核融合実験炉)プロジェクトの主要部材や制御システムは日本企業が手掛けている。
しかし、最大の弱点は「スケールアップ資金」と「人材流動性」だ。米国ではNASAやグーグル出身のエンジニアがスタートアップに合流するが、日本では大学と企業の人材の壁が依然として厚い。経産省が進める「人材リスキリング支援」や「大学発スタートアップ育成枠」が、このギャップを埋める鍵になるだろう。
核融合が実用化すれば、エネルギーコストが劇的に低下し、国際経済の構造が根底から変わる。石油、天然ガス、ウランといったエネルギー資源の地政学的価値が相対的に下がり、「資源国」と「非資源国」の関係は逆転する。
それは同時に、「エネルギーが無限に近い社会」という、人類史上初の資本主義再設計を意味する。
その未来を見据えて、米国は巨額の国家投資を行い、日本は「技術で勝負する」戦略を描く。バブルと冷静の狭間で揺れ動く核融合産業は、いままさに「産業革命以来最大の転換点」を迎えている。
(文=BUSINESS JOURNAL編集部)?