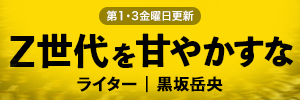CES 2026が示したフィジカルAI時代の到来と、かつてのロボット王国・日本の現在地
2026.01.16
ビジネスジャーナル
中国:政府主導で進む「価格破壊」と社会実装
一方、中国勢はまったく異なるアプローチで存在感を示した。彼らの武器は、国家主導による量産体制と圧倒的なコスト競争力だ。
●Zeroth「M1」:高齢者見守りを量産する発想
スタートアップZeroth(ゼロス)が展示した小型ヒューマノイド「M1」は、高齢者見守りや教育用途を想定したモデルだ。視覚・言語・動作を統合するVLA(Vision-Language-Action)により、日常会話を通じてユーザーの行動パターンを学習する。
注目すべきはその価格帯だ。量産を前提とし、40万円前後という現実的な水準が示された。
●Roborockが突破した「日本住宅最大の壁」
さらに象徴的だったのが、Roborock(ロボロック)の「Saros Rover」である。日本の住宅事情における最大の障壁――階段を、伸縮する脚と車輪を組み合わせた「脚輪型」構造で克服した。
生活空間の課題を、力業で解決する設計思想。これもまた、大量の試作と実証を短期間で回せる中国の開発体制があってこそ可能なアプローチだ。
スペック比較で見る「現在地」
CES 2026を通じて見えた中韓日3カ国の立ち位置は、以下のように整理できる。
韓国:米テック企業とのAI連合を軸に、ロボットを「プラットフォーム化」する戦略
中国:政府主導で量産と低価格化を進め、市場シェアの獲得を最優先
日本:特定現場向けの高信頼ロボットと、部品・デバイス供給に特化
ITジャーナリスト・小平貴裕氏は、こう警鐘を鳴らす。
「日本は、スマホ時代の部品メーカーと同じ立場に立たされつつあります。完成品とOSを握らなければ、いずれ価格決定権を失う」
影の薄い日本勢、それでも残る“強み”
日本勢がまったく何もしていないわけではない。クボタの自動農機、医療・物流向けの特化型ロボットなど、現場で確実に価値を生む技術は着実に進化している。
また、減速機、精密センサー、モーターといった基幹部品では、今なお世界トップシェアを誇る分野も多い。
だが、CES 2026が突きつけたのは、「それだけでは勝てない」という現実だ。ロボットの価値を決める主戦場は、もはや機械精度ではなく、AIと資本力、そして量産体制へと移行している。
かつてASIMOは、世界に「日本=ロボット大国」というイメージを植え付けた。しかし、CES 2026が示したのは、精緻なハードウェアだけでは勝てない時代の到来である。
AIという“脳”を誰が握るのか。その身体を、誰がどれだけの数、社会に送り込めるのか。この2点で後れを取れば、日本は再び「高性能部品を供給する下請け国家」に甘んじる可能性が高い。フィジカルAIは、次の10年の産業地図を塗り替える。その分岐点に、日本は立たされている。
(文=BUSINESS JOURNAL編集部)