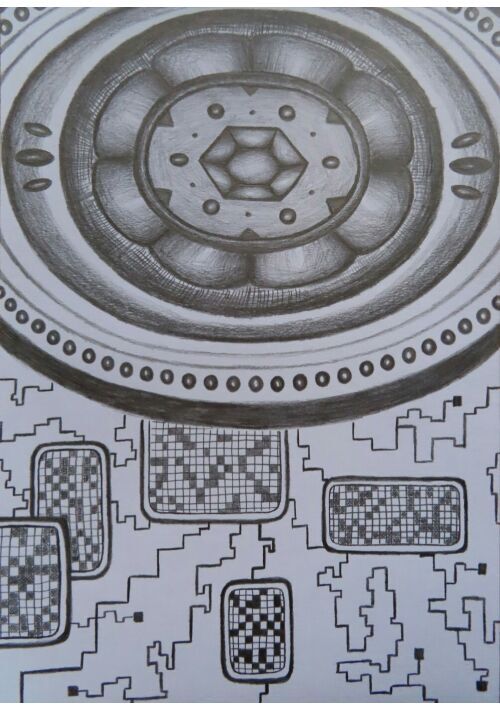22 / 26
本編
21
しおりを挟む◇◇ ソフィ ◇◇
その日の午後、わたしがお茶を取りに行く前に、ルイーズがそれを運んで来た。
そして、彼女を従えていたのは、豪華なドレスを纏い、美しく着飾ったクリスティナで、
わたしは嫌な予感に気分も落ちた。
「私もお茶をご一緒させて頂いてもよろしいかしら、魔王様。
久しぶりにソフィとも話したいの、私たち、《姉妹》ですもの」
クリスティナは上機嫌だった。
だが、わたしは彼女が上機嫌であればある程、嫌な予感がし、
エクレールがその申し出を断ってくれるのを願った。
だが、エクレールはすんなりと「構わぬ」と許してしまった。
エクレールはいつも通り、長ソファに座っている。
向かいの席に、恭しくクリスティナが腰かけた。
わたしは例に寄って、エクレールから「おまえは私の隣だ」と言われ、
不承不承そこへ腰を下ろした。
ルイーズが給仕をしてくれたが、わたしの紅茶を置く時、彼女が嘲る様な笑みを見せたので、
わたしの悪い予感は更に大きなものとなった。
暫くは、クリスティナは無難な話題を振り、お茶を楽しんでいた。
天気の良い日が続き、気持ちがよろしいですわね…とかだ。
相変わらず、エクレールに魅力たっぷりの笑みを向け、猫撫で声で媚びる彼女に、
わたしはうんざりし、気配を消してケーキを食べていた。
ふと、それが途切れたかと思うと、クリスティナは、今度はわたしに視線を向け、
話し掛けて来た。
「ねぇ、ソフィ、あなた覚えている?
私たち、幼い頃、家族でよくピクニックに行っていたわよね?」
「ええ、覚えています」
「森林の近くに行った事もあったわね?」
「ええ…」
森林?
何故、急にこんな話を?
わたしが問う様に見ると、クリスティナは猫が獲物を狙う時の様な目をしていて、ゾクリとした。
まさか、彼女は気付いたのだろうか…
わたしのこの推測は当たっていた。
「魔王様がソフィに一目惚れをされたのは、きっと、その時ね?」
わたしは答え様が無く、茫然としていた。
代わりに、エクレールがそれに答えた。
「おまえは独りで居た、家族とはぐれたのであれば、送ってやれば良かったな、
無事に帰れたか?ソフィ」
エクレールの視線を避ける様に、わたしは俯き、紅茶のカップに手を伸ばした。
「わたしは、覚えていませんので…」
カップを持つ手が震えてしまう。
これでは変に思われてしまうだろうと、わたしはカップから手を放し、膝の上で握った。
クリスティナは当然、許さなかった。
彼女は、わたしを糾弾しようと狙っていたのだから___
「森林と言えば、私には思い出がありますの。
あれは、7歳の頃ですわ、あの頃の私は、金色の髪に青い瞳で、
周囲からは天使の様だと言われていましたのよ、そうよね、ソフィ?」
「ええ…」
「それに引き換え、あなたは、癖のある赤毛で、いつもモップみたいに爆発していたわよね!」
「ええ…」
わたしは膝の上の手をギュっと握る。
クリスティナがここまで言えば、流石にエクレールにも分かるだろう…
それを願っていた筈なのに、顔を上げる事はとても出来なかった。
「ある時、森林から出て来た男の方に、声を掛けられた事がありますの。
その方は、丁度、魔王様の様に黒尽くめで背が高く、立派な体躯をなさっていましたわ。
子供ながらに怯えてしまい、つい、あなたの名を騙ってしまったのだけど、許してね、ソフィ。
その方は私に赤い李の様な果実を下さったの。
後であなたに奪われてしまったけど、覚えている?ソフィ」
奪ったなんて!
わたしは上目で睨んだが、クリスティナは意地悪く笑っただけだった。
「魔王様を見ていると、不思議と、あの日の事が思い出されますの…何故かしら?」
クリスティナは優雅な仕草でカップを持ち、紅茶を飲んだ。
奇妙な静けさがあった。
痺れを切らしたのは、クリスティナだった。
「魔王様とソフィの出会いを詳しくお聞きしたいですわ」
エクレールはそれには答えずに、結論を述べた。
「私が出会った娘は、ソフィではなく、おまえだと言いたいのだな?」
「まぁ!それでは、やはり、あの時の方は魔王様でしたのね!?
ああ!私、あなたを一目見た時から、そうでは無いかと思っていましたの!
私には感じますもの!魔王様が私の《運命の相手》だと___!」
わたしは驚きに息を飲んだ。
クリスティナは王妃だ、不貞など、あってはならない事だ。
それこそ、反逆罪か何かで断罪されるだろう。
わたしはギョッとして、ルイーズを見たが、ルイーズは少しの動揺も見せず、
当然の様な顔をし立っていた。
ルイーズも知っていたんだわ!何故、諫めなかったのかしら!
「ソフィ!あなた、全部知っていて、魔王様に言わずにいたのね!
魔王様が自分に夢中になっているのを見て、嘲笑っていたのでしょう?
何て意地の悪い女なのかしら!あなたは小さい頃からそうよ!
私の物を何でも欲しがって、奪っていくんだわ!
でも、彼は渡さないわよ!彼の運命の相手は私だもの!あなたじゃないのよ、ソフィ!」
クリスティナの深い青色の目が爛々と輝いている。
他人を糾弾する時程、悦に入る時は無いのか、彼女は生き生きとしていた。
わたしは何も言えなかった。
この時まで、本当の事を話さなかったわたしを、エクレールは信じないだろう…
それに、クリスティナの嘘を正した処で、
彼女がエクレールの《運命の相手》という事は変わらないのだから。
後は二人で好きにすれば良い、どうなろうと知った事ではないわ___
わたしは何もかも放り出したい気分になっていた。
「成程、そういう事か、だが、私の《運命の相手》がおまえだというのは早計だぞ、王妃」
エクレールの言葉に、クリスティナは目を見開き、わたしも顔を上げ彼を見ていた。
この後に及んで、まだ認めないのかと、その頑固さに驚いたが、そうでは無かった。
「魔王様、あなたの《運命の相手》は、間違いなく、私ですわ!」
クリスティナは声を荒げ主張した。
彼女のその青色の目は、恐ろしい程に目力を発揮していたが、
それを受けるエクレールの方は、無表情だった。
「私が出会ったのは、おまえで間違いないだろう、王妃」
エクレールが言った事で、クリスティナの顔に笑みが戻った。
わたしは奥歯を噛み、膝の上の手を握り締めた。
「私は美しい娘に一目で心を奪われ、美しい宝石を見た時の様に、手に入れたくなった。
名を聞くと、その者は『ソフィ』と名乗った」
「それは、先にも申しましたが、知らない者に声を掛けられ、恐ろしかったからですわ!」
「その様な場面で妹の名を騙るとはな、妹が恐ろしい目に遭うとは考えなかったのか?」
「ええ…それは…子供でしたので…」
クリスティナはもごもごと言葉を濁した。
エクレールは「まぁ、良い」と続けた。
「私は幾つかの呪いを掛けた実を、その者に渡した。
だが、実を食べたのは、『ソフィ』という名の別の娘だった…」
「その実は、ソフィが私から奪ったのですわ!」
「そう責めるな、恐ろしいと感じた、知らぬ者から渡された物を、
別の者に奪われたのなら、寧ろ良かったではないか。
それに相手は小さな妹だ、許してやれ、王妃」
クリスティナは愕然とし、口を開けていた。
これまで優遇されて当然だった彼女には、余程ショックだった様だ。
エクレールは全く気にする事無く、続けた。
「《呪い》により、私は自分の指輪を通し、その娘の事を少しばかり知る事が出来た。
居場所や、成長具合、生きているかどうか位だがな。
だが、その時から、私は彼女を見守り、彼女を想い続けてきた。
そして、出会い、想像を超えてくる彼女に恋をし、愛に変わった___」
わたしは「はっ」とし、エクレールを見た。
彼の黒い目は、いつの間にか赤色に変わり、
薄い笑みを浮かべ、わたしを見ていて、わたしは無意識にゴクリと唾を飲んだ。
「違うわ!ソフィじゃない!あなたが一目で心を奪われたのは私よ!!」
クリスティナが叫ぶ。
エクレールは顔だけをそちらに向け、あっさりと言った。
「それは認めると言っただろう、尤も、子供の頃のおまえの外見にだがな。
大人のおまえには、心惹かれるものは無かったぞ、王妃」
「な、なんですって!?私のこの美貌が、見えませんの!?」
「フン、思い上がるな、おまえ程度ならば、珍しくもない。
それに、おまえのその性格や喋り方は、37番目、68番目、120番目…の、
元妻に似ている、思い出すのも不愉快だ」
「120番目!??」
エクレールの結婚歴を知らないクリスティナは目を丸くし、口をあんぐりと開けた。
「私、これで失礼致しますわ!」と、クリスティナが投げ付ける様に言い放ち、席を立った。
エクレールに引き止めて欲しいのか、引き止められるのを待っているのか…
クリスティナは暫くその場で睨み付けていたが、エクレールに「どうした、行かぬのか」と問われ、
顔を真っ赤にし、鬼の形相で肩を怒らせ、ルイーズを引き連れて出て行った。
エクレールはクリスティナを一度も引き止めようとはしなかったし、興味も示さなかった。
その事に安堵するも、わたしは彼に謝る必要があった。
「あなたが出会ったのが、姉だという事を、黙っていて申し訳ありませんでした。
クリスティナは既に結婚していましたし、王妃でしたから…」
「私は面倒の芽という訳だな、だが、それで良かった。
あの者と私とでは、結果は見えている。
『お互いに知り合う必要がある』という、おまえの助言は正しかったな、ソフィ」
エクレールがニヤリと笑う。
エクレールに未練は無い様で、わたしは安堵した。
「だが、《運命の相手》がまやかしというのは、間違いだ。
私が出会った者はまやかしだったが、そこから、不思議にも、おまえに繋がった。
《運命》というのは、得てしてそういうものではないのか?
私の《運命の相手》は、おまえだ、ソフィ」
わたしの頬を、その大きな手が優しく撫でる。
赤い目は、今は優しさに満ちている…
だけど、わたしは、応えられなかった。
わたしがスッと顔を反らすと、エクレールも向きを戻し、紅茶を飲んだ。
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
232
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる