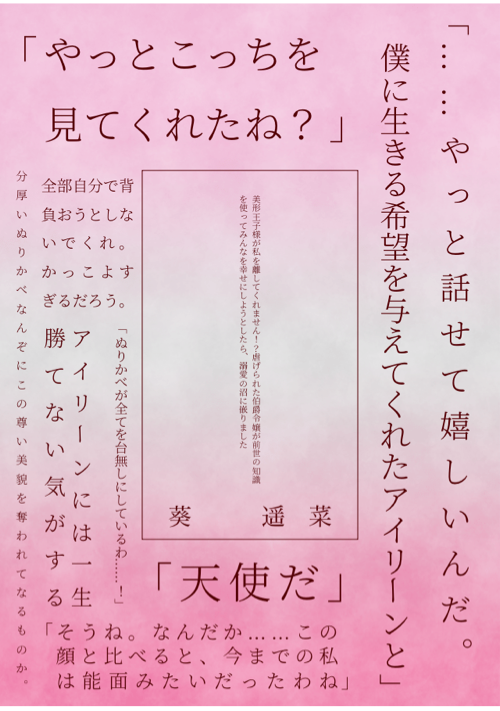11 / 14
第二章
第11夜
しおりを挟む
「…お茶、入れます。どこにありますか」
「えっとね、ここはお店だから…台所はここには無いんだ。場所を移動しよう、ええと」
魔法使いはシャーサの先ほどの剣幕を思い出し、立ち上がろうとした腰を沈める。
「…移動を手伝ってくれるかい?」
「はい」
シャーサに支えられながら、魔法使いは店の奥へと歩く。
形が異なる扉が付いた、長い廊下の突き当たり。
その壁にそのまま足を踏み出す魔法使いにシャーサの足が止まりかける。
「え、」
「大丈夫」
ぶつかる、と思ったその足が、壁を通り抜けた。
布を潜り抜けたような感触に混乱しながら、シャーサは目をつむって魔法使いと共に壁を通り抜けた。
室内の暖かさを感じる空気に、無意識に止めていた息をはっと吐いて、目を開ける。
そこは、人の暮らしを感じるリビングが広がっていた。
木目の床に、丸い絨毯。ローテーブルの前には、シャーサが見たこともないような布張りの大きな長椅子。
白く綺麗な漆喰らしき壁。どういう原理なのか、天井から下げられたランタンには揺らめかない火が灯っている。
振り返ると、シャーサが潜り抜けてきた壁にはレースカーテンが掛かっていて、先程の廊下と店が透けて見えた。
「…すごい…」
「ここが、ボクのお家」
呆けたように感嘆を漏らすシャーサに、魔法使いはいたずらっぽく笑う。
「お店からお家の中が見られるの、ちょっと恥ずかしいからね」
だからと言って、こんな見たことも聞いたこともない技術で遮るものだろうか、とシャーサは面食らいながら頷く。
布張りの長椅子まで連れていき、座らせると、魔法使いは思い出したように靴を脱いだ。
「そうだ、室内は土足厳禁なんだ。スリッパスリッパ…」
ふらふらと椅子に掴まって立ちあがる魔法使いを慌てて制して、レースカーテンの脇の棚からスリッパを取ってくる。
「ああ、ありがとう。…ひとりで暮らしているものだから、怪我をしてても普通に動くことが癖になってしまっているんだ。その、なかなか慣れなくてごめんね」
申し訳なさそうな魔法使いの前にスリッパを置き、自分もそれを履いてから、少し迷ってシャーサは魔法使いの隣に座った。
「いえ…痛くないんですか」
「…うーん…多分痛いと思うんだけど、ちょっと今は麻痺してるから元気、かな」
「そうですか」
「そうなんだ」
そこで途切れる会話に、魔法使いは「そうだ」と手を叩く。
「そう、それで、お茶だったね。あっちが台所なんだ。どれを使っても大丈夫だから、好きに使って」
「はい」
明らかに高そうな茶葉や茶器に緊張しつつ、お茶の用意を済ませてリビングへ戻ると、魔法使いはいつの間にか服装が室内着のそれに変わっていた。
ありがとうとカップを受け取り、香りを楽しむ魔法使いの隣に、シャーサは腰を下ろす。
カップの水面に顔を寄せれば、花のような芳醇な香りに自然と口角が上がった。
普段とは違う気の抜けたシャーサの表情に、魔法使いも頬を緩める。
「…ふしぎな気持ちだ」
「不思議な気持ち、ですか?」
「君が、ボクの隣に座ってる」
「…だけ、ですよ?」
「うん。だって、初めてだもの、嬉しいさ」
「うれしい」
「うん」
うれしい、ともう一度言って、そろそろと紅茶を飲む魔法使いを、シャーサは見つめる。
ああ、そうだ。自分は、この言葉が聞きたかったのだ。
何か大それたことをしなくても、お茶を淹れて、隣に座って、話をして、それが嬉しいのだと。
しかし、シャーサは、はっと頭を振る。
この心地良さに慣れては、抜け出せなくなるような気がしたからだ。
まだ、夢に沈みきらない今のうちに、自分から出ないと、帰れなくなりそうだった。
「それで、そうだ。答えを、求める気に、なったのかな」
「え」
ドキリとして、シャーサはカップを握る手に力を込めた。
「それとも、出た答えを、この場所に、求めにきたのかな」
こちらを真っすぐに見ながら首を傾げる魔法使いの目線に、射貫かれたように動けなくなる。
「それとも、」
魔法使いはことりとカップを置いて笑った。
「ボクに、攫われてくれるのかな」
シャーサはその言葉に、目を見開く。
「さらわれ…?」
魔法使いは、何かおかしいことを言っただろうか、というふうに不思議そうな表情をしている。
実際、魔法使いのその言葉は、『普段よりも思考力が落ちたから』出てしまった言葉であった。
だから、その時の魔法使いは、みるみる顔を赤くするシャーサを見て、「どうしてそんなに照れることがあるのだろうか」と疑問にしか感じなかった。
「だ、誰が、誰を」
「ボクが、君を」
「なんで、ですか」
「なんでって…君と一緒にいたいもの。君のこと、好きだから」
「だから、君がいいなら、ボクに攫われてくれたらいいなって」と笑う魔法使いに、シャーサは落としそうになるカップを思わず机に置いた。
「…私は、前も言いましたが、婚約している方が、います。…それに、あなたのこと、本当に好きなのか、まだ、分からない。自信が、なくて…」
「うん」
「…多分、あなたに優しくされて、舞い上がってしまったんです」
ちょうどこんなふうに、と思いながら、シャーサは置いたカップの中で揺蕩う水面を見た。
そこには、この幸せな場所には不釣り合いな、陰気な女…自分の姿が写っている。
「あなたは私を幸せにできるかもしれないけれど、私は、同じだけあなたを幸せにできる自信はない」
「…ふむ…」
「それに、私は、あなたを神様みたいに思ってしまう気がするんです」
「神さま?」
「…なんというか、依存、してしまうかもしれない。それは、嫌です」
シャーサは自分のことを重い女であると、自覚していた。
だからこそ、自分が自立できないままでいることも、分かっている。
それは、シャーサに「自分で選ぶこと」を教えた魔法使いも察しているだろうことだ。
魔法使いは少し考えるそぶりを見せてから、答える。
「ボクが君を幸せにするために、これから沢山頑張っていくとして。…君はもうボクの幸せなのだから、難しい事は特に考えなくて良いと思うんだ」
現にいま、ボクは幸せだからね、と魔法使いはカップの中身を揺らす。
「あと、今思い出したのだけど、ボクは君のかみさまになりたいんだった。だから大丈夫」
「?」
予想していなかった言葉に、シャーサは目を丸くする。
どういうことですか、と聞こうとする言葉は、魔法使いの嬉しそうな声に遮られた。
「そうだ。ボク、君を舞い上がらせたいのだけど、優しくってどんな感じかな?」
「どんなって…」
「好きになってほしいんだ」
今日、何回目か分からない告白に、シャーサはウッと言葉を詰まらせる。
「もしかして、今はボクのこと、好きではないかもしれないんだろう?だから、この気持ちは本物だって心から信じられるくらいに…君に、ボクのこと好きになってほしい」
「い、いや、もう、わたしに構わないでください。わたしの、気持ち、が」
シャーサはとうとう、手の甲で顔を隠した。
「揺らいで、しまうから」
シャーサの言葉に、魔法使いは溢れるように笑う。
「ボクは、君自身にもっともっと揺らいでほしいので、君に構うのをやめません」
シャーサは眉を寄せる。
流されてしまっていいんだろうか。全部ほっぽりだして、この魔法使いに身を預けてしまっても、いいんだろうか。
少しの間、目を伏せてから、シャーサは深呼吸をする。
「…あの、一度、帰ってもいい、ですか」
手を下ろして、自分のスカートを握り、シャーサは決意の眼差しを魔法使いに向けた。
「きちんと、自分で、あなたの元を選びたい」
攫われたから、なんて、この人に責任を全部押しつけて逃げるのは、卑怯なことのように思えた。
たとえ母親から否定されても、どういう結果になっても、こんなにも自分のことを望んでくれる相手の隣にいることは、きっと間違いではない。
魔法使いは瞬きをして、「…うん」と小さく頷く。
珍しく歯切れの悪い魔法使いの様子に、シャーサは不安になる。
「なにか、思うところが、ありますか」
「その、少し、心配で」
魔法使いは真剣な表情でつぶやいた。
「…焦れて、迎えに行ってしまうかも」
その言葉に、胸の奥がくすぐったくなって、シャーサは笑う。
「じょ、冗談では無いんだよ…!」
魔法使いの慌てた様子がおかしくて、余計に笑いを誘われた。
「あなたが来てくれるのは、嬉しいのですが、どうか、待っていてください」
「う、は、はい…」
珍しくころころと年相応に笑うシャーサの声が、部屋に響いた。
そうして、小さなお茶会が終わり、シャーサは改めて店の扉の前に立った。
これを抜ければ、またあの家に帰るのだと思うと、憂鬱だった。
けれど、その先に彼との生活が待っていることを思えば、いつもより怖くはない。
扉に手をかけて、見送りに立つ魔法使いに頭を下げる。
「じゃあ、失礼します」
「うん。…行ってらっしゃい」
小さく手を振る魔法使いに、シャーサは微笑んだ。
「いってきます」
「えっとね、ここはお店だから…台所はここには無いんだ。場所を移動しよう、ええと」
魔法使いはシャーサの先ほどの剣幕を思い出し、立ち上がろうとした腰を沈める。
「…移動を手伝ってくれるかい?」
「はい」
シャーサに支えられながら、魔法使いは店の奥へと歩く。
形が異なる扉が付いた、長い廊下の突き当たり。
その壁にそのまま足を踏み出す魔法使いにシャーサの足が止まりかける。
「え、」
「大丈夫」
ぶつかる、と思ったその足が、壁を通り抜けた。
布を潜り抜けたような感触に混乱しながら、シャーサは目をつむって魔法使いと共に壁を通り抜けた。
室内の暖かさを感じる空気に、無意識に止めていた息をはっと吐いて、目を開ける。
そこは、人の暮らしを感じるリビングが広がっていた。
木目の床に、丸い絨毯。ローテーブルの前には、シャーサが見たこともないような布張りの大きな長椅子。
白く綺麗な漆喰らしき壁。どういう原理なのか、天井から下げられたランタンには揺らめかない火が灯っている。
振り返ると、シャーサが潜り抜けてきた壁にはレースカーテンが掛かっていて、先程の廊下と店が透けて見えた。
「…すごい…」
「ここが、ボクのお家」
呆けたように感嘆を漏らすシャーサに、魔法使いはいたずらっぽく笑う。
「お店からお家の中が見られるの、ちょっと恥ずかしいからね」
だからと言って、こんな見たことも聞いたこともない技術で遮るものだろうか、とシャーサは面食らいながら頷く。
布張りの長椅子まで連れていき、座らせると、魔法使いは思い出したように靴を脱いだ。
「そうだ、室内は土足厳禁なんだ。スリッパスリッパ…」
ふらふらと椅子に掴まって立ちあがる魔法使いを慌てて制して、レースカーテンの脇の棚からスリッパを取ってくる。
「ああ、ありがとう。…ひとりで暮らしているものだから、怪我をしてても普通に動くことが癖になってしまっているんだ。その、なかなか慣れなくてごめんね」
申し訳なさそうな魔法使いの前にスリッパを置き、自分もそれを履いてから、少し迷ってシャーサは魔法使いの隣に座った。
「いえ…痛くないんですか」
「…うーん…多分痛いと思うんだけど、ちょっと今は麻痺してるから元気、かな」
「そうですか」
「そうなんだ」
そこで途切れる会話に、魔法使いは「そうだ」と手を叩く。
「そう、それで、お茶だったね。あっちが台所なんだ。どれを使っても大丈夫だから、好きに使って」
「はい」
明らかに高そうな茶葉や茶器に緊張しつつ、お茶の用意を済ませてリビングへ戻ると、魔法使いはいつの間にか服装が室内着のそれに変わっていた。
ありがとうとカップを受け取り、香りを楽しむ魔法使いの隣に、シャーサは腰を下ろす。
カップの水面に顔を寄せれば、花のような芳醇な香りに自然と口角が上がった。
普段とは違う気の抜けたシャーサの表情に、魔法使いも頬を緩める。
「…ふしぎな気持ちだ」
「不思議な気持ち、ですか?」
「君が、ボクの隣に座ってる」
「…だけ、ですよ?」
「うん。だって、初めてだもの、嬉しいさ」
「うれしい」
「うん」
うれしい、ともう一度言って、そろそろと紅茶を飲む魔法使いを、シャーサは見つめる。
ああ、そうだ。自分は、この言葉が聞きたかったのだ。
何か大それたことをしなくても、お茶を淹れて、隣に座って、話をして、それが嬉しいのだと。
しかし、シャーサは、はっと頭を振る。
この心地良さに慣れては、抜け出せなくなるような気がしたからだ。
まだ、夢に沈みきらない今のうちに、自分から出ないと、帰れなくなりそうだった。
「それで、そうだ。答えを、求める気に、なったのかな」
「え」
ドキリとして、シャーサはカップを握る手に力を込めた。
「それとも、出た答えを、この場所に、求めにきたのかな」
こちらを真っすぐに見ながら首を傾げる魔法使いの目線に、射貫かれたように動けなくなる。
「それとも、」
魔法使いはことりとカップを置いて笑った。
「ボクに、攫われてくれるのかな」
シャーサはその言葉に、目を見開く。
「さらわれ…?」
魔法使いは、何かおかしいことを言っただろうか、というふうに不思議そうな表情をしている。
実際、魔法使いのその言葉は、『普段よりも思考力が落ちたから』出てしまった言葉であった。
だから、その時の魔法使いは、みるみる顔を赤くするシャーサを見て、「どうしてそんなに照れることがあるのだろうか」と疑問にしか感じなかった。
「だ、誰が、誰を」
「ボクが、君を」
「なんで、ですか」
「なんでって…君と一緒にいたいもの。君のこと、好きだから」
「だから、君がいいなら、ボクに攫われてくれたらいいなって」と笑う魔法使いに、シャーサは落としそうになるカップを思わず机に置いた。
「…私は、前も言いましたが、婚約している方が、います。…それに、あなたのこと、本当に好きなのか、まだ、分からない。自信が、なくて…」
「うん」
「…多分、あなたに優しくされて、舞い上がってしまったんです」
ちょうどこんなふうに、と思いながら、シャーサは置いたカップの中で揺蕩う水面を見た。
そこには、この幸せな場所には不釣り合いな、陰気な女…自分の姿が写っている。
「あなたは私を幸せにできるかもしれないけれど、私は、同じだけあなたを幸せにできる自信はない」
「…ふむ…」
「それに、私は、あなたを神様みたいに思ってしまう気がするんです」
「神さま?」
「…なんというか、依存、してしまうかもしれない。それは、嫌です」
シャーサは自分のことを重い女であると、自覚していた。
だからこそ、自分が自立できないままでいることも、分かっている。
それは、シャーサに「自分で選ぶこと」を教えた魔法使いも察しているだろうことだ。
魔法使いは少し考えるそぶりを見せてから、答える。
「ボクが君を幸せにするために、これから沢山頑張っていくとして。…君はもうボクの幸せなのだから、難しい事は特に考えなくて良いと思うんだ」
現にいま、ボクは幸せだからね、と魔法使いはカップの中身を揺らす。
「あと、今思い出したのだけど、ボクは君のかみさまになりたいんだった。だから大丈夫」
「?」
予想していなかった言葉に、シャーサは目を丸くする。
どういうことですか、と聞こうとする言葉は、魔法使いの嬉しそうな声に遮られた。
「そうだ。ボク、君を舞い上がらせたいのだけど、優しくってどんな感じかな?」
「どんなって…」
「好きになってほしいんだ」
今日、何回目か分からない告白に、シャーサはウッと言葉を詰まらせる。
「もしかして、今はボクのこと、好きではないかもしれないんだろう?だから、この気持ちは本物だって心から信じられるくらいに…君に、ボクのこと好きになってほしい」
「い、いや、もう、わたしに構わないでください。わたしの、気持ち、が」
シャーサはとうとう、手の甲で顔を隠した。
「揺らいで、しまうから」
シャーサの言葉に、魔法使いは溢れるように笑う。
「ボクは、君自身にもっともっと揺らいでほしいので、君に構うのをやめません」
シャーサは眉を寄せる。
流されてしまっていいんだろうか。全部ほっぽりだして、この魔法使いに身を預けてしまっても、いいんだろうか。
少しの間、目を伏せてから、シャーサは深呼吸をする。
「…あの、一度、帰ってもいい、ですか」
手を下ろして、自分のスカートを握り、シャーサは決意の眼差しを魔法使いに向けた。
「きちんと、自分で、あなたの元を選びたい」
攫われたから、なんて、この人に責任を全部押しつけて逃げるのは、卑怯なことのように思えた。
たとえ母親から否定されても、どういう結果になっても、こんなにも自分のことを望んでくれる相手の隣にいることは、きっと間違いではない。
魔法使いは瞬きをして、「…うん」と小さく頷く。
珍しく歯切れの悪い魔法使いの様子に、シャーサは不安になる。
「なにか、思うところが、ありますか」
「その、少し、心配で」
魔法使いは真剣な表情でつぶやいた。
「…焦れて、迎えに行ってしまうかも」
その言葉に、胸の奥がくすぐったくなって、シャーサは笑う。
「じょ、冗談では無いんだよ…!」
魔法使いの慌てた様子がおかしくて、余計に笑いを誘われた。
「あなたが来てくれるのは、嬉しいのですが、どうか、待っていてください」
「う、は、はい…」
珍しくころころと年相応に笑うシャーサの声が、部屋に響いた。
そうして、小さなお茶会が終わり、シャーサは改めて店の扉の前に立った。
これを抜ければ、またあの家に帰るのだと思うと、憂鬱だった。
けれど、その先に彼との生活が待っていることを思えば、いつもより怖くはない。
扉に手をかけて、見送りに立つ魔法使いに頭を下げる。
「じゃあ、失礼します」
「うん。…行ってらっしゃい」
小さく手を振る魔法使いに、シャーサは微笑んだ。
「いってきます」
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
17
1 / 4
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる